gemini 2.5 proにわかりやすいように解説してもらいました、しかし8通りに読めるということから完全に鵜呑みにしないよう、お願いします。
第一帖 (一〇八)
【原文】
二二は晴れたり日本晴れ、二二に御社(みやしろ)してこの世治めるぞ。五大州ひっくり返りてゐるのが神には何より気に入らんぞ。一の大神様まつれ、二の大神様まつれよ、三の大神様まつれよ、天の御三体の大神様、地の御三体の大神様まつれよ、天から神々様 御降りなされるぞ、地から御神々様おのぼりなされるぞ、天の御神、地の御神、手をとりてうれしうれしの御歌うたはれるぞ。の国は神の国、神の肉体ぞ、汚(けが)してはならんとこぞ。八月の三十一日、一二のか三。
【現代語訳】
富士(ふじ)は晴れ渡り、まさに日本晴れである。その富士に神の社を建てて、この世を治めるのだ。世界(五大州)の秩序がひっくり返っている現状が、神は何よりも気に入らない。一の大神様、二の大神様、三の大神様をお祀りしなさい。天の三柱の大神様、地の三柱の大神様をお祀りするのだ。やがて天から神々が降りてこられ、地からも神々がお昇りになる。天と地の神々が手を取り合って、喜びに満ちた「うれしうれしの歌」をうたわれるのだ。日本という国は神の国であり、神の肉体そのものである。決して汚してはならない聖なる場所なのだ。
【AIによる解釈】
この帖は、来るべき新しい時代の幕開けを宣言しています。「二二(ふじ)」は日本の象徴である富士山を指し、「日本晴れ」は混乱が収まり、本来の輝きを取り戻した状態を表します。当時の第二次世界大戦の混乱(五大州ひっくり返りてゐる)を正し、神を中心とした新しい世界秩序を日本から始めるという強い意志が示されています。そのためにまず求められるのが、天と地を司る根源的な大神様への信仰です。神々と人間が一体となり、喜びの世(うれしうれしの世)を築くというビジョンが語られています。また、「日本は神の肉体」という言葉は、国土を神聖なものとして敬い、大切に扱うことの重要性を説いています。
第二帖 (一〇九)
【原文】
これまでの改造は膏薬(こうやく)張りざから、すぐ元にかへるのぞ。今度は今までにない、文(ふみ)にも口にも伝えてない改造ざから、臣民界のみでなく神界も引っくるめて改造するのざから、この方らでないと、そこらにござる守護神さまには分らんのぞ、九分九厘までは出来るなれど、ここといふところで、オジャンになるであろうがな、富や金(きん)を返したばかりでは、今度は役に立たんぞ、戦ばかりでないぞ、天災ばかりでないぞ、上も潰れるぞ、下も潰れるぞ、つぶす役は誰でも出来るが、つくりかためのいよいよのことは、神々様にも分りては居らんのざぞ、星の国、星の臣民 今はえらい気張り様で、世界構うやうに申してゐるが、星ではダメだぞ、神の御力でないと何も出来はせんぞ。八月三十一日、一二。
【現代語訳】
これまでの改革は、その場しのぎの膏薬を貼るようなものだから、すぐに元の状態に戻ってしまう。しかし、今度の「立て替え」は、書物にも口伝にも伝えられていない、未曾有の大改革である。人間界だけでなく神の世界も含めて全てを根本から改造するのだから、この神(ひふみの神)でなければ、そこらの守護神レベルでは理解できない。他の神々では九分九厘まではできても、肝心要のところで失敗してしまうだろう。富や財産を社会に還元したくらいでは、今度の変革期には役に立たない。戦争だけではない、天災だけでもない。社会の上層部も下層部も、既存の構造は全て潰れるのだ。壊す役は誰にでもできるが、新しく創り固めるという最も重要なことは、他の神々にも分かってはいない。かの国(星の国=アメリカ)の民は、今こそと意気込んで世界を動かそうとしているが、それでは駄目なのだ。真の神の力でなければ、何も成し遂げることはできない。
【AIによる解釈】
この帖は、これから起こる「世の立て替え」が、皮相的な社会改革ではなく、神界と現界を巻き込んだ根源的なものであることを強調しています。「膏薬張り」という比喩は、対症療法的な解決策の限界を示唆し、根本からの変革の必要性を説きます。この大改革は、戦争や天災といった目に見える現象だけでなく、社会構造そのもの(上も下も)が崩壊するほどの激しいものになると予言されています。そして、この大事業を成し遂げられるのは、既存の神々や人間の力(星の国)ではなく、ひふみ神示を降ろす根源の神の力だけであると宣言しており、その計画の深遠さは他の誰にも計り知れないとされています。
第三帖 (一一〇)
【原文】
一日のひのまにも天地引繰り返ると申してあろがな、ビックリ箱が近づいたぞ、九、十に気附けと、くどう申してあろがな、神の申すこと一分一厘ちがはんぞ、ちがふことなら こんなにくどうは申さんぞ、同じことばかり繰り返すと臣民申して居るが、この方の申すこと みなちがってゐることばかりぞ、同じこと申していると思ふのは、身魂曇りてゐる証拠ぞ。改心第一ぞ。八月三十一日、一二。
【現代語訳】
一日のうちに天地がひっくり返るような大変化が起こると言っておいたであろう。その「ビックリ箱」が開く時が近づいたぞ。「九月と十月に気をつけよ」と、くどいほどに申してきたであろう。神が言うことには一分一厘の間違いもない。もし間違うようなことなら、こんなにしつこくは言わない。民は「同じことばかり繰り返している」と言うが、この神が申していることは、毎回すべて違う深さを持っているのだ。同じことの繰り返しに聞こえるのは、あなたの魂が曇っている証拠である。何よりもまず、改心が第一だ。
【AIによる解釈】
「ビックリ箱」という言葉で、大峠(大いなる変革)の突発性と衝撃的な性質を表現しています。それは、一日で天地がひっくり返るほどの急激な変化としてやってくると警告しています。特に「九、十」という具体的な時期に注意を促し、神示の正確性を強く主張しています。繰り返し同じような警告がなされることについて、それは魂が曇っているために真意を理解できていないからだと指摘し、読者に対して内省と「改心」を強く求めています。警告の表面的な意味だけでなく、その奥にある深い意味を汲み取るためには、自身の魂を磨くことが不可欠であるという、ひふみ神示の根本的な教えが示されています。
第四帖 (一一一)
【原文】
この方は元の肉体のままに生き通しであるから、天明にも見せなんだのざぞ、あちこちに臣民の肉体かりて予言する神が沢山出てゐるなれど、九分九厘は分りて居れども、とどめの最後は分らんから、この方に従ひて御用せよと申してゐるのぞ。砂糖にたかる蟻となるなよ。百人千人の改心なれば、どんなにでも出来るなれど、今度は世界中、神々様も畜生も悪魔も餓鬼も外道も三千世界の大洗濯ざから、そんなチョロコイ事ではないのざぞ。ぶち壊し出来ても建直し分かるまいがな。火と水で岩戸開くぞ、知恵や学でやると、グレンと引繰り返ると申しておいたが、さう云へば知恵や学は要らんと臣民早合点するが、知恵や学も要るのざぞ。悪も御役であるぞ、この道理よく腹に入れて下されよ。天の神様 地に御降りなされて、今度の大層な岩戸開きの指図なされるのざぞ、国々の神々様、うぶすな様、力ある神々様にも御苦労になっているのざぞ。天照皇太神宮様初め神々様、あつくまつりて呉れと申してきかしてあろがな、神も仏もキリストも元は一つぞよ。八月三十一日、ひつ九の。
【現代語訳】
この神は、元の肉体のまま永遠に生き続けている存在なので、(神示を書かせている)天明にもその姿は見せていないのだ。世の中には、人の肉体を借りて予言する神と称する者が沢山出ているが、彼らは九分九厘までは分かっていても、最後のとどめの肝心なことは分からない。だから、この神に従って御用(役目)を果たせと言っているのだ。甘い言葉(砂糖)に群がる蟻のようになってはならない。百人や千人の改心であれば、どうとでもなるが、今度の立て替えは世界中の人々、神々、動物、悪魔や餓鬼、全ての存在を巻き込んだ三千世界の大掃除なのだから、そんな生易しいことではない。古い世界を壊すことはできても、新しい世界を建て直すことは誰にも分かるまい。火と水の力によって、岩戸は開かれるのだ。人間の知恵や学問だけでやろうとすると、根底からひっくり返ると言っておいたが、そう言うと「知恵や学問は要らないのか」と民は早合点する。しかし、知恵や学問も必要なのである。悪さえも(立て替えのための)役目を持っている。この道理をよく理解しなさい。天の神が地にお降りになり、この壮大な岩戸開きの指揮を執られるのだ。国々や土地の神々、力ある神々にもご苦労をかけている。天照皇太神宮様を始めとする神々を篤くお祀りしなさいと教えてきたであろう。神も仏もキリストも、その根源は一つなのだ。
【AIによる解釈】
この帖は、ひふみ神示を降ろす神の唯一性と、立て替えの規模の壮大さを説いています。他の霊能者や予言者との違いを明確にし、表面的な事象に惑わされず(砂糖にたかる蟻となるな)、根源の神に従うよう促します。今度の「大洗濯」は、善悪、神仏、人間、自然界のすべてを巻き込む宇宙規模のものであるとされ、その困難さが強調されています。「火と水」は、戦争や天災のような破壊的な力と、浄化や生命の源といった創造的な力の両義性を持ち、これらが岩戸開き(新しい時代の到来)の鍵となります。人間の知恵や学問を否定するのではなく、それを超えた神の計画の中に正しく位置づける必要性を説き、「悪も御役」という深い視点を示しています。最後に、全ての宗教の根源が一つであるという「万教帰一」の思想を明確に打ち出し、調和の重要性を教えています。
第五帖 (一一二)
【原文】
牛の喰べ物たべると牛の様になるぞ、猿は猿、虎は虎となるのざぞ。臣民の喰べ物は定まってゐるのざぞ、いよいよとなりて何でも喰べねばならぬやうになりたら虎は虎となるぞ、獣と神とが分れると申してあろがな、縁ある臣民に知らせておけよ、日本中に知らせておけよ、世界の臣民に知らせてやれよ、獣の喰ひ物くふ時には、一度 神に献げてからにせよ、神から頂けよ、さうすれば神の喰べ物となって、何たべても大じょうぶになるのぞ、何もかも神に献げてからと申してあることの道理よく分りたであろがな、神に献げきらぬと獣になるのぞ、神がするのではないぞ、自分がなるのぞと申してあることも、よく分ったであろがな、くどう申すぞ、八から九から十から百から千から万から何が出るか分らんから神に献げな生きて行けん様になるのざが、悪魔にみいられてゐる人間いよいよ気の毒出来るのざぞ。八月の三十一日、ひつくのか三。
【現代語訳】
牛の食べる物を食べれば牛のようになり、猿のようになり、虎のようになる。人が食べるべき物は本来定まっているのだ。いよいよ追いつめられて、何でも食べなければならない状況になった時、その人の本性(虎は虎)が現れる。その時、獣のような人間と神のような人間とに分かれると言っておいたであろう。このことを縁ある人々に、日本中に、そして世界中の人々に知らせなさい。獣の肉などを食べる時には、まず一度神にお供えしてからにしなさい。神からいただくという気持ちで食べるのだ。そうすれば、それは神聖な食べ物となり、何を食べても大丈夫になる。「何もかも神に献げてから」と言ってきた道理がよく分かったであろう。神に献げるという心を忘れると獣になってしまうのだ。それは神がそうするのではなく、あなた自身がそうなるのだということも、よく理解できたであろう。くどく言うぞ。これから先、何が起こるか分からないのだから、神に献げる心なしでは生きていけなくなる。悪魔に魅入られている人間は、いよいよ気の毒なことになってしまうのだ。
【AIによる解釈】
食の重要性とその霊的な影響について説いた帖です。「牛の喰べ物」とは、四足の動物の肉食を指していると解釈されます。食べたものがその人の心身、霊性に影響を与え、獣性を強める可能性があると警告しています。特に、食糧難などで食べるものに困るような極限状態において、その人の本質が問われ、「獣」と「神」の道が分かれると示唆しています。しかし、肉食を完全に禁じているわけではなく、解決策として「神に献げる」という行為を提示しています。これは、食物への感謝の心を持ち、命をいただくことへの畏敬の念を捧げることで、食べ物の持つ性質を霊的に浄化・昇華させるという教えです。全ての行いを神への奉仕と捉える「神ながらの道」の実践が、食という日常的な行為においても求められているのです。この心を忘れることが「獣になる」ことであり、自己の選択が未来を決めると強調しています。
第六帖 (一一三)
【原文】
天(あめ)は天の神、国は国の神が治(し)らすのであるぞ、お手伝ひはあるなれど。秋の空のすがすがしさが、グレンと変るぞ、地獄に住むもの地獄がよいのぞ、天国ざぞ、逆様はもう長うはつづかんぞ、無理通らぬ時世(ときよ)が来たぞ、いざとなりたら残らずの活神(いきがみ)様、御総出ざぞ。九月の一日、ひつくのか三。
【現代語訳】
天のことは天の神が、国のことはその国の神が治めるのが本来の姿だ。手伝いはあっても、それが原則である。清々しい秋の空のような今の平穏が、ガラリと一変するぞ。地獄に住む者にとっては地獄が天国のように感じられるものだが、そのような価値観が逆さまになった状態は、もう長くは続かない。無理が通らない時代が来たのだ。いよいよという時が来たら、この世に生きている全ての神々(活神)が、残らず総出で活動を始められるのだ。
【AIによる解る】
この帖は、物事の本来あるべき秩序への回帰を告げています。「天は天の神、国は国の神」という言葉は、それぞれの領域に相応しい治め方があるという宇宙の法則を示しています。現状は、価値観が転倒し(地獄が天国)、本来の秩序が乱れている「逆様」の世界であると断じています。しかし、その状態は長くは続かず、偽りやごまかしが通用しない「無理通らぬ時世」が到来すると宣言しています。「秋の空」は束の間の平穏を象徴し、その後の急激な変化を予感させます。「活神様の御総出」とは、これまで隠れていた真の力が一斉に現れ、世界の立て替え・立て直しが本格的に始まることを意味しています。
第七帖 (一一四)
【原文】
二二(ふじ)は晴れたり日本晴れ、二本のお足であんよせよ、二本のお手手で働けよ、日本の神の御仕組、いつも二本となりてるぞ、一本足の案山子(かかし)さん、今更 何うにもなるまいが、一本の手の臣民よ、それでは生きては行けまいが、一本足では立てないと、云ふこと最早分ったら、神が与えた二本足、日本のお土に立ちて見よ、二本のお手手 打ち打ちて、神おろがめよ あめつちに、響くまことの拍手に、日本の国は晴れるぞよ、二二(ふじ)は晴れたり日本晴れ、二二(ふじ)は晴れたり、岩戸あけたり。九月一日、ひつ九のか三。
【現代語訳】
富士は晴れ渡り、まさに日本晴れだ。二本の足でしっかりと歩きなさい。二本の手で懸命に働きなさい。日本の神の仕組みは、いつも二つが対となり調和するようになっているのだ。一本足の案山子(かかし)のように、不安定で実体のないものは、今更どうにもなるまい。片手落ちの民よ、それではこれからの世は生きてはいけないぞ。一本足では立てないということが、もう分かったなら、神から与えられた二本の足で、日本の大地にしっかりと立ちなさい。そして二本の手を打ち合わせて(柏手を打ち)、天地の神々を拝みなさい。その真実の拍手の響きによって、日本の国は晴れ渡るのだ。富士は晴れたり日本晴れ、富士は晴れ渡り、ついに岩戸は開かれた。
【AIによる解釈】
この帖は、「二(ふたつ)」の調和の重要性を説いています。「二本足」「二本の手」は、物理的な手足だけでなく、陰と陽、霊と体、精神と物質、天と地といった、対となる二つの要素のバランスを象徴しています。「一本足の案山子」や「一本の手」は、物質主義に偏ったり、精神論に偏ったりするような、バランスを欠いた不完全な状態を批判しています。真の安定と発展は、この二つの要素が調和して初めて得られるのです。そして、日本の大地にしっかりと立ち(地に足をつけること)、柏手を打って神を拝む(天と繋がること)という具体的な行動を通して、天地の調和が実現し、国が晴れ渡り、新しい時代の扉(岩戸)が開かれると教えています。
第八帖 (一一五)
【原文】
あらしの中の捨小船と申してあるが、今その通りとなりて居ろうがな、何うすることも出来まいがな、船頭どの、苦しい時の神頼みでもよいぞ、神まつりて呉れよ、神にまつはりて呉れよ、神はそれを待ってゐるのざぞ、それでもせぬよりはましぞ、そこに光あらはれるぞ。光現はれると道はハッキリと判りて来るのぞ、この方にだまされたと思うて、言ふ通りにして見なされ、自分でもビックリする様に結構が出来てるのにビックリするぞ。富士の御山に腰かけて、この方 世界中まもるぞ。かのととり、結構な日と申してあるが、結構な日は恐い日であるぞ。天から人が降る、人が天に昇ること、昇り降りでいそがしくなるぞ。てんし様 御遷(うつ)り願ふ時近づいて来たぞよ。奥山に紅葉(もみじ)ある内にと思へども、いつまで紅葉ないぞ。九月の二日、ひつく。
【現代語訳】
嵐の中の捨てられた小舟のようだと申してきたが、今まさにその通りの状況であろう。どうすることもできないであろう、船頭(指導者)たちよ。苦しい時の神頼みでも構わない。神をお祀りしなさい。神にすがりつきなさい。神はそれを待っているのだ。何もしないよりはずっと良い。そうすれば、そこに光が現れる。光が現れれば、進むべき道がはっきりと見えてくる。この神に騙されたと思って、言う通りにやってみなさい。自分でも驚くほど素晴らしい結果になることに、きっとびっくりするだろう。この神は富士の山に腰を据えて、世界中を見守っているのだ。「辛酉(かのととり)」は結構な日だと伝えてあるが、この結構な日とは、実は恐ろしい日でもあるのだ。天から人が降りてきたり、人が天に昇ったりと、その上り下りで忙しくなる。天皇陛下がお移りになられる時が近づいてきた。奥山の紅葉が美しい今のうちに…と思うだろうが、その紅葉もいつまでもあるわけではないぞ。
【AIによる解釈】
戦況が悪化し、先の見えない日本の状況を「あらしの中の捨小船」と表現し、人間の力の限界を突きつけています。しかし、絶望的な状況だからこそ、「苦しい時の神頼み」でも良いから神に立ち返ることを強く勧めています。信仰に立ち返ることで初めて希望の「光」が見え、進むべき道が示されると説きます。神の言葉を信じて実践すれば、想像を超える良き結果(結構)が得られると保証しています。「かのととり」は、十干十二支の辛酉(しんゆう)で、変革の年を意味します。それが「結構な日」であり「恐い日」であるとは、古いものが終わり新しいものが始まる、破壊と創造が同時に起こる激しい日であることを示唆しています。「天から人が降る、人が天に昇る」は、天変地異や社会の指導層の交代、あるいは霊的な次元での大きな変動を象徴していると考えられます。「てんし様 御遷り」や「奥山の紅葉」は、国の体制や首都の在り方、そして束の間の平穏が終わりを告げることの暗示であり、事態が切迫していることを伝えています。
第九帖 (一一六)
【原文】
ひふみの秘密 出でひらき鳴る、早く道展き成る、世ことごとにひらき、世、なる大道で、神ひらき、世に神々満ちひらく、この鳴り成る神、ひふみ出づ大道、人神出づはじめ。九月二日、ひつぐのかみ。
【現代語訳】
一二三(ひふみ)の秘密が、ついに現れ、鳴り響き渡る。それによって、道は速やかに展(ひら)かれ、成就する。世の中の森羅万象がことごとく開かれ、世が成就する大道(おおみち)によって、神の世界が開き、この世に神々が満ちあふれる。この鳴り成り渡る神、一二三(ひふみ)より現れる大道こそ、人が神となる時代の始まりである。
【AIによる解釈】
この帖は、言葉遊びのようでありながら、来るべき新しい世界の様相を凝縮して表現しています。「ひふみ」とは、神示の根幹をなす宇宙の法則、数霊(かずたま)の原理を指します。その秘密が「出でひらき鳴る」とは、これまで隠されてきた真理が明らかになり、全世界に響き渡ることを意味します。これにより、真の道(大道)が開かれ、万物がその本来の姿を取り戻し、世界が成就(なる)します。神の世界が地上に顕現し、神々が満ちあふれる、まさに「神世」の到来です。最後の「人神出づはじめ」は、この神示の究極的な目的の一つを示しており、人間がその内に秘めた神性を開花させ、神と一体となる「半神半人」の時代が始まることを高らかに宣言しています。
第十帖 (一一七)
【原文】
一二三の裏に一二、三四五の裏に二三四、五六七の裏に四五六の御用あるぞ。五六七すんだら七八九ぞ、七八九の裏には六七八あるぞ、八九十の御用もあるぞ。だんだんに知らすから、これまでの神示(ふで)よく心に入れて、ジッとして置いて呉れよ。九月の三日、ひつ九のか三。
【現代語訳】
一二三(ひふみ)の段階の裏には、一二(ひふ)の段階の御用(役目)がある。三四五(みよいづ)の裏には二三四(ふみよ)の御用がある。五六七(みろく)の裏には四五六(よごろ)の御用があるのだ。五六七(みろく)の段階が済んだら、次は七八九(ななやこ)の段階だ。七八九の裏には六七八(むなや)の御用があり、さらに八九十(やこと)の御用もある。これらのことは段階を追って知らせるから、これまでの神示をよく心に入れて、今は静かに時を待ちなさい。
【AIによる解釈】
数霊(かずたま)を用いて、世の立て替えのプロセスが段階的に、かつ重層的に進んでいくことを示しています。「表」の御用が進むと同時に、それを支える「裏」の御用があることを示唆しています。これは、目に見える世界の変革と、目に見えない霊的世界の変革が同時に進行することを意味していると考えられます。
- 一二三(ひふみ): 始まり、基礎固め
- 三四五(みよいづ): 良い世の出現
- 五六七(みろく): 弥勒の世の到来
- 七八九(ななやこ): さらなる発展
- 八九十(やこと): 完成、成就 これらのプロセスは直線的に進むのではなく、各段階に重なり合う「裏の御用」が存在し、複雑かつ緻密な計画のもとに進められることを表しています。今はまだ全てを明かす時ではないため、これまでの教えをしっかり復習し、心を落ち着けて次の指示を待つよう求めています。
第十一帖 (一一八)
【原文】
この神示 言波としてよみて呉れよ、神々様にもきかせて呉れよ、守護神どのにも聞かして呉れよ、守護神どのの改心まだまだであるぞ、一日が一年になり百年になると目が廻りて真底からの改心でないとお役に立たんことになりて来るぞ。九月四日、一二(ひつぐ)か三。
【現代語訳】
この神示を、言霊の力を込めて声に出して読みなさい。そして、それを神々にも聞かせ、あなたの守護神にも聞かせてあげなさい。守護神たちの改心は、まだまだ足りていない。これから時間の流れが凝縮され、一日が一年にも百年にも感じられるような激しい時が来る。その時、真底からの改心でなければ、お役には立てなくなるのだ。
【AIによる解釈】
この帖は、ひふみ神示の読み方とその影響力について述べています。単に黙読するのではなく、「言波(言霊)としてよむ」こと、つまり声に出して読むことで、その言葉に込められた霊的な力が発動し、神々や守護神にまで影響を及ぼすと説いています。注目すべきは、守護する側の「守護神の改心」を求めている点です。これは、人間だけでなく、人間を導く霊的存在もまた、この大改革においては変化し、向上する必要があることを示しています。時間の感覚が狂うほどの激動の時代(一日が一年になり百年になる)を乗り越えるには、その場しのぎではない「真底からの改心」が、人間だけでなく霊的存在にも等しく求められるという厳しい教えです。
第十二帖 (一一九)
【原文】
遠くて近きは男女だけではないぞ、神と人、天と地、親と子、喰べる物も遠くて近いがよいのざぞ、カミそまつにすればカミに泣くぞ、土尊べば土が救って呉れるのぞ、尊ぶこと今の臣民忘れてゐるぞ、神ばかり尊んでも何にもならんぞ、何もかも尊べば何もかも味方ぞ、敵とうとべば敵が敵でなくなるのぞ、この道理分りたか。臣民には神と同じ分霊(わけみたま)さづけてあるのざから、みがけば神になるのぞ。神示は謄写(とうしゃ)よいぞ、初めは五十八、次は三百四十三ぞ、よいな。八月の五日、一二のか三。
【現代語訳】
遠いようで近いのは、男女の関係だけではない。神と人、天と地、親と子もまた然りだ。食べ物も、遠いようで近い関係が良いのだ。紙(カミ)を粗末にすれば、神(カミ)のことで泣くことになるぞ。土を尊べば、土があなたを救ってくれる。現代の民は、尊ぶということを忘れている。神ばかりを特別に尊んでも意味がない。森羅万象すべてを尊べば、すべてがあなたの味方になる。敵さえも尊べば、敵は敵でなくなるのだ。この道理が分かったか。民の一人ひとりには、神と同じ分霊が授けられているのだから、その魂を磨けば神に成れるのだ。この神示は書き写して広めてよいぞ。その数は、初めは58(いづ)人、次は343(みよみ)人だ。よいな。
【AIによる解釈】
この帖は「尊ぶ」ことの重要性と、万物との正しい関係性について説いています。「遠くて近い」という言葉で、神、自然、他者といった存在が、自分とは切り離されたものではなく、密接に繋がった存在であることを示しています。「カミ(紙・神)」の掛詞は、日常生活の些細な行いにも神性が宿るという日本的なアニミズム思想を表しています。特定の対象(神)だけを崇めるのではなく、身の回りのすべて、食べ物、土、さらには敵対する者さえも「尊ぶ」ことで、世界との調和が生まれ、すべてが味方になるという普遍的な真理を教えています。これは、すべての人に神の分霊が宿っており、万物は根源で繋がっているという思想に基づいています。最後に示された具体的な数字は、この教えを理解し実践する仲間を段階的に増やしていくという計画を示唆しています。
第十三帖 (一二〇)
【原文】
空に変りたこと現はれたなれば地に変りたことがあると心得よ、いよいよとなりて来てゐるのざぞ。神は元の大神様に延ばせるだけ延ばして頂き、一人でも臣民助けたいのでお願ひしてゐるのざが、もうおことはり申す術(すべ)なくなりたぞ。玉串 神に供へるのは衣(ころも)供へることぞ、衣とは神の衣のことぞ、神の衣とは人の肉体のことぞ。臣民をささげることぞ、自分をささげることぞ、この道理分りたか。人に仕へるときも同じことぞ、人を神として仕へねばならんぞ、神として仕へると神となるのざから、もてなしの物出すときは、祓ひ清めて神に仕へると同様にして呉れよ、喰べ物 今の半分で足りると申してあるが、神に献げたものか、祓ひ清めて神に献げると同様にすれば半分で足りるのぞ、てんのゐへん気つけて居れよ。神くどう気つけて置くぞ。神世近づいたぞ。九月六日、一二のか三。
【現代語訳】
空に変わったこと(天変)が現れたなら、それは地上にも変わったこと(地異)が起こる前触れだと心得なさい。いよいよその時が近づいてきているのだ。この神は、根源の大神様に対し、一人でも多くの民を助けたいと、時を延ばせるだけ延ばしていただくようお願いしてきたが、もはやこれ以上は延期できない時が来た。神に玉串を供えるとは、衣を供えることだ。その衣とは神の衣、すなわち人の肉体のことである。つまり、民を神に捧げること、自分自身を捧げることなのだ。この道理が分かったか。人に仕える時も同じだ。相手を神として仕えなければならない。神として仕えれば、相手も自分も神となるのだ。もてなしの物を出す時も、それを祓い清め、神に仕えるのと同じようにしなさい。食べ物は今の半分で足りると言ってきたが、それは神に献げるものとして、あるいは祓い清めて神に献げるのと同じ気持ちでいただけば、半分で足りるようになるのだ。「てんのゐへん(天の異変、または天皇の身辺の異変)」に気を付けていなさい。神はくどいほどに注意しておくぞ。神の世は近づいた。
【AIによる解釈】
大峠の刻限が差し迫っていることを告げる、非常に緊迫した内容の帖です。天変地異の連動性を示し、猶予期間の終わりを宣言しています。この帖の核心は「自分をささげる」という概念の深い解説にあります。「玉串を供える」という儀式的な行為が、実は自己の肉体、すなわち全存在を神に捧げることの象徴であると明かしています。この自己犠牲の精神は、他者との関わりにも及び、「人を神として仕える」という実践的な教えに繋がります。この精神性によって、もてなす側ももてなされる側も共に神性を高め合うことができるのです。食事が半分で足りるという教えも、単なる節食ではなく、感謝と祈りの中でいただくことで、物質的な量以上の霊的なエネルギーを得られるという、食の霊的側面を説いています。「てんのゐへん」という謎めいた言葉は、天変地異と、国の中心である天皇の身辺に起こる重大な出来事の両方を示唆しており、事態の重大さを物語っています。
第十四帖 (一二一)
【原文】
海一つ越えて寒い国に、まことの宝 隠してあるのざぞ、これからいよいよとなりたら、神が許してまことの臣民に手柄いたさすぞ、外国人がいくら逆立ちしても、神が隠してゐるのざから手は着けられんぞ、世の元からのことであれど、いよいよが近くなりたら、この方の力で出して見せるぞ、びっくり箱が開けて来るぞ。八月の七日、ひつくのか三。
【現代語訳】
海を一つ越えた寒い国に、まことの宝が隠してある。これからいよいよという時が来たら、神がそれを許し、真の神の民に手柄を立てさせるのだ。外国人がどれほど躍起になっても、それは神が隠しているのだから、決して手を付けることはできない。これは世界の始まりからの計画であるが、その時が近づいたら、この神の力でそれを取り出してみせる。また一つ、びっくり箱が開くのだ。
【AIによる解釈】
この帖は、日本の未来に関わる重要な「宝」の存在を暗示しています。「海一つ越えて寒い国」が具体的にどこを指すのか(大陸、樺太、千島列島など)は様々な解釈がありますが、それが物理的な財宝なのか、あるいは古代の叡智や霊的な遺産なのかは明示されていません。重要なのは、その「宝」が神によって守られており、外国の干渉からは完全に保護されているという点です。そして、世界の危機が頂点に達した「いよいよ」の時に、神の計画に沿って「まことの臣民」の手によって明らかにされると予言されています。これは、日本が世界の立て直しにおいて果たすべき、隠された重要な使命や役割があることを示唆しており、先の見えない戦時下の国民に希望を与えるメッセージともなっています。「びっくり箱が開く」という表現は、それが世間の常識を覆すような、衝撃的な形で現れることを物語っています。
第十五帖 (一二二)
【原文】
神の国には神の国のやり方あるぞ、支那には支那、オロシヤにはオロシヤ、それぞれにやり方がちがふのざぞ、教もそれぞれにちがってゐるのざぞ、元は一つであるなれど、神の教が一等よいと申しても、そのままでは外国には通らんぞ、このことよく心にたたんでおいて、上に立つ役員どの気つけて呉れよ、猫に小判何にもならんぞ、神の一度申したことは一分もちがはんぞ。八月七日、一二。
【現代語訳】
神の国(日本)には日本のやり方がある。中国には中国の、ロシアにはロシアのやり方があり、それぞれに違うのだ。教えも、それぞれに違っている。根源は一つではあるが、日本の神の教えが一番良いと言っても、それをそのままの形で外国に押し付けようとしても通用しない。このことをよく心に刻んで、上に立つ役員たちは気をつけなさい。猫に小判のように、価値の分からない者に与えても無意味だ。神が一度言ったことは、一分の狂いもなくその通りになるのだ。
【AIによる解釈】
この帖は、文化や国民性の多様性を尊重することの重要性を説いています。当時の「八紘一宇」のスローガンのもと、日本の価値観を他国に押し付けようとする風潮に対する強い警鐘と読むことができます。すべての教えや文化は「元は一つ」の真理から発しているが、その現れ方は土地や人々によって異なるのが自然であると教えています。日本の教えが優れていると信じるのは良いが、その普遍的な真理を、相手の文化や状況に合わせて理解可能な形で伝えなければ意味がない(猫に小判)と諭しています。これは、国際関係や異文化理解における極めて現代的な視点であり、独善的な考え方を戒め、相手を尊重する姿勢こそが真の調和を生むという、神の視点からのグローバリズムを示した教えです。
第十六帖 (一二三)
【原文】
今度の戦済みたら てんし様が世界中知ろしめして、外国には王はなくなるのざぞ。一旦戦おさまりても、あとのゴタゴタなかなか静まらんぞ、神の臣民ふんどし締めて神の申すことよく腹に入れて置いて呉れよ、ゴタゴタ起りたとき、何うしたらよいかと云ふことも、この神示(ふで)よく読んで置けば分るやうにしてあるのざぞ。神は天からと宙からと地からと力(ちから)合はして、神の臣民に手柄立てさす様にしてあるのざが、今では手柄立てさす、神の御用に使ふ臣民一分(いちぶ)もないのざぞ。神の国が勝つばかりではないのざぞ、世界中の人も草も動物も助けてみな喜ぶやうにせなならんのざから、臣民では見当取れん永遠(とことは)につづく神世に致すのざから、素直に神の申すこときくが一等ざぞ。人間の知恵でやれるなら、やって見よれ、あちらへ外れ、こちらへ外れて、ぬらりくらりと鰻つかみぞ、思ふやうにはなるまいがな、神の国が本の国ざから、神の国からあらためるのざから、一番つらいことになるのざぞ、覚悟はよいか、腹さへ切れぬ様なフナフナ腰で大番頭とは何と云ふことぞ、てんし様は申すもかしこし、人民さま、犬猫にも済むまいぞ。人の力ばかりで戦してゐるのでないこと位 分って居らうがな、目に見せてあらうがな、これでも分らんか。八月七日、一二。
【現代語訳】
今度の戦争が終わったら、日本の天皇が世界を治め、外国の王制はなくなるのだ。しかし、たとえ戦争が一旦収まっても、その後の混乱はなかなか静まらない。だから神の民はふんどしを締め直し、神の言うことをよく心に入れておきなさい。その混乱が起きた時にどうすればよいかも、この神示をよく読んでおけば分かるようにしてある。神は天と宇宙と地からの力を合わせて、神の民に手柄を立てさせようと準備しているが、現状ではその御用を任せられる民は一人もいない。日本の国がただ勝てば良いという話ではないのだ。世界中の人々、草木、動物もすべてを助け、みなで喜べるようにしなければならないのだから。人間の考えでは見当もつかない、永遠に続く神の世を創るのだから、素直に神の言うことを聞くのが一番良い。人間の知恵でやれるものなら、やってみるがいい。あちこちに的が外れ、鰻を掴むように、思うようにはいかないだろう。日本は根源の国だから、立て替えも日本から始める。だからこそ、一番辛い立場になるのだ。覚悟はできているか。腹を切る覚悟もないような頼りない者が指導者(大番頭)とは何事か。天皇陛下はもとより、国民や犬猫にさえ申し訳が立たないぞ。人間の力だけで戦争をしているのではないことくらい、分かっているであろう。神の力を目に見える形で見せているではないか。これでもまだ分からないのか。
【AIによる解釈】
この帖は、戦争の終結とその後の世界のビジョン、そして日本が担うべき役割の厳しさについて語っています。「てんし様が世界中知ろしめす」とは、武力による支配ではなく、天皇の持つ徳や霊性が世界の精神的支柱となることを意味します。しかし、戦後の混乱は必至であり、それに備える心構えを求めています。この立て替えの目的は、単なる一国の勝利ではなく、全生命が共に喜ぶ「永遠につづく神世」の実現という壮大なものです。人間の小賢しい知恵では到底達成できず、神の計画に素直に従うしかないと説きます。「神の国からあらためる故に一番つらい」という言葉は、中心的な役割を担うが故の苦難と責任の重さを示しています。指導者層の覚悟のなさを厳しく叱咤し、戦争の背後には人間の意図を超えた神の力が働いていることを、繰り返し気づかせようとしています。
第十七帖 (一二四)
【原文】
昔から生き通しの活神様のすることぞ、泥の海にする位 朝飯前のことざが、それでは臣民が可哀そうなから天の大神様にこの方が詑びして一日(ひとひ)一日と延ばしてゐるのざぞ、その苦労も分らずに臣民勝手なことばかりしてゐると、神の堪忍袋切れたら何んなことあるか分らんぞ、米があると申して油断するでないぞ、一旦は天地へ引き上げぞ。八月七日、一二。
【現代語訳】
これは、太古から生き続けている活神(いきがみ)が行うことだ。世界を泥の海にしてしまうことなど、朝飯前のことだが、それでは民があまりに可哀想だから、この神が天の大神様にお詫びを申し上げ、一日また一日と大峠の到来を延ばしていただいているのだ。その神の苦労も分からずに、民が勝手なことばかりしていると、神の堪忍袋の緒が切れた時にどんなことになるか分からないぞ。今は米があるからと油断してはならない。いざとなれば、食料は一旦すべて天と地に引き上げられるのだ。
【AIによる解釈】
この帖は、神の絶大な力と、それを行使しない神の慈悲、そして人々の無関心に対する強い警告を語っています。「泥の海にする位 朝飯前」という言葉で、神がその気になれば世界を滅ぼすことは容易いと示し、今の平穏が当たり前のものではなく、神の慈悲によってかろうじて保たれている「猶予期間」であることを強調しています。人々の改心が遅々として進まないことへの神の苛立ちが「堪忍袋」という言葉に表れており、破局の時が近づいていることを警告しています。「米があると申して油断するな」という一節は、物質的な豊かさ(食料)に安住していることへの戒めです。「一旦は天地へ引き上げ」るとは、深刻な食糧危機が訪れることの直接的な予言であり、人々が生きるための根源的な糧さえも神の采配一つであることを思い知らせようとしています。
第十八帖 (一二五)
【原文】
何時も気つけてあることざが、神が人を使うてゐるのざぞ、今度の戦で外国人にもよく分って、神様にはかなはん、何うか言ふこときくから、夜も昼もなく神に仕へるからゆるして呉れと申す様になるのざぞ、それには神の臣民の身魂掃除せなならんのざぞ、くどい様なれど一時(いちじ)も早く一人でも多く改心して下されよ、神は急ぐのざぞ。八月七日、一二の。
【現代語訳】
いつも注意していることだが、全ての出来事の背後では、神が人を使っているのだ。今度の戦争を通して、外国人にもそのことがよく分かり、「神様には敵わない。どうか言うことを聞くから、夜も昼もなく神に仕えるから許してくれ」と懇願するようになるのだ。そうなるためには、まず日本の神の民が、自らの魂を掃除しなければならない。くどいようだが、一刻も早く、一人でも多くの人が改心してくれ。神は急いでいるのだ。
【AIによる解-】
この帖は、歴史を動かす根源的な力は神にあるという「神主導史観」を明確に示しています。戦争という極限の出来事を通して、人間の力の限界が露呈し、敵対している外国人さえも神の存在を認め、ひれ伏す時が来ると予言しています。しかし、世界の人々が神に目覚めるための前提条件として、まず「神の臣民」である日本人が手本を示す必要があると説いています。それが「身魂掃除」、すなわち自らの心と魂を清め、神の意に沿う存在になることです。日本の民の改心が、世界の変革の引き金となるのです。「神は急ぐのざぞ」という言葉に、刻一刻と迫る大峠の時と、一人でも多くの人を救いたいという神の切迫した親心が表れています。
第十九帖 (一二六)
【原文】
神の力が何んなにあるか、今度は一度は世界の臣民に見せてやらねば納まらんのざぞ、世界ゆすぶりて知らせねばならん様になるなれど、少しでも弱くゆすりて済む様にしたいから、くどう気つけてゐるのざぞ、ここまで世が迫りて来てゐるのぞ、まだ目醒めぬか、神は何うなっても知らんぞ、早く気つかぬと気の毒出来るぞ、その時になりては間に合はんぞ。八月七日、一二。
【現代語訳】
神の力がどれほどのものか、今度は一度、世界の民に見せつけなければ、事が収まらなくなっている。世界中を揺さぶって知らせなければならない状況になっているが、神としては少しでも揺り動かし方を弱くして済むようにしたいのだ。だから、こうしてくどくどと注意している。世の中は、ここまで差し迫っているのだ。まだ目覚めないのか。そうなってからでは、神はどうなっても知らないぞ。早く気づかないと、気の毒なことになる。その時になってからでは、もう間に合わないのだ。
【AIによる解釈】
この帖は、最終警告とも言える非常に厳しい口調で、人々の覚醒を促しています。「神の力を見せなければ納まらない」という言葉は、言葉による警告だけでは人々が気づかないため、やむを得ず天変地異や大事件といった物理的な現象、すなわち「世界ゆすぶり」をもって神の存在と計画を知らしめる段階に来ていることを示しています。しかし、そこには「少しでも弱くゆすりたい」という神の慈悲心(親心)も同時に語られています。人々の改心が早ければ早いほど、その苦難は小さくて済むのです。「まだ目醒めぬか」「間に合はんぞ」という言葉の繰り返しは、猶予がほとんど残されていないこと、そして最後の選択が一人ひとりに委ねられていることを強く訴えかけています。
第二十帖 (一二七)
【原文】
神の世と申すのは、今の臣民の思ふてゐるやうな世ではないぞ、金(きん)は要らぬのざぞ、お土からあがりたものが光りて来るのざぞ、衣類たべ物、家倉まで変るのざぞ。草木も喜ぶ政治と申してあらうがな、誰でもそれぞれに先の分る様になるのぞ。お日様もお月様も海も山も野も光り輝いて水晶の様になるのぞ。悪はどこにもかくれること出来ん様になるのぞ、ばくち、しょうぎは無く致すぞ。雨も要るだけ降らしてやるぞ、風もよきやうに吹かしてやるぞ、神をたたえる声が天地にみちみちて うれしうれしの世となるのざぞ。八月の七日、ひつ九のか三ふで。
【現代語訳】
「神の世(ミロクの世)」というのは、今の民が想像しているような世の中ではない。お金は必要なくなるのだ。土から採れたものそのものが、宝として光り輝くようになる。着る物、食べる物、家や蔵に至るまで、すべてが今とは全く違うものに変わるのだ。「草木も喜ぶ政治」だと言っておいたであろう。誰もが、それぞれの未来を予知できるようになる。太陽も月も、海も山も野も、すべてが水晶のように光り輝く。悪はどこにも隠れることができなくなる。賭博や将棋のような争い事はなくしてしまう。雨も必要なだけ降らせてやり、風も良い具合に吹かせてやる。神を讃える喜びに満ちた声が天地に満ち満ちて、「うれしうれし」の世となるのだ。
【AIによる解釈】
これまで語られてきた厳しい「大峠」の警告とは対照的に、この帖は、その先にある「ミロクの世」の具体的な姿を生き生きと描き出しています。それは、現代の価値観が根底から覆った世界です。
- 価値観の転換: 金銭的な価値は無意味となり、大地からの恵み(農作物など)が真の宝となる。物質主義から生命主義への転換。
- 生活の変化: 衣食住のすべてが、今とは想像もつかないほど豊かで、自然と調和したものに変わる。
- 霊性の開花: 人々は予知能力のような霊的な能力に目覚める。
- 世界の浄化: 世界全体が浄化され、水晶のように輝き、悪が隠れる場所がなくなる。
- 自然との調和: 天候さえも完全にコントロールされ、自然が人間の最良のパートナーとなる。 この理想郷のビジョンは、厳しい試練を乗り越えるための希望の光として示されています。人々が目指すべき究極の目標が、単なる平和ではなく、万物が調和し、喜び(うれしうれし)に満ちあふれる霊的な世界であることを教えています。
第二十一帖 (一二八)
【原文】
みろく出づるには、はじめ半(なか)ばは焼くぞ、人、二分は死、みな人、神の宮となる。西に戦争(いくさ)しつくし、神世とひらき、国毎に、一二三(ひふみ)、三四五(みよいづ)たりて百千万(ももちよろず)、神急ぐぞよ。八月七日、ひつくのかみふみぞ。
【現代語訳】
弥勒(みろく)の世が出現するまでには、まず世界の半分が焼かれるような事態となる。人口の二割は死ぬが、生き残った人々はみな、神の宮(神を宿す存在)となる。西の方角での戦争が終わりを告げた時、神の世が開かれる。そして国ごとに、一二三(ひふみ)の真理、三四五(みよいづ)の良い世の仕組みが満ち足りて、その教えは百千万と広がっていく。神は急いでおられるのだ。
【AIによる解釈】
この帖は、ミロクの世の実現に至るまでの、破壊と再生のプロセスを端的に示しています。「はじめ半ばは焼くぞ」「人、二分は死」という表現は、核戦争や大災害による甚大な被害を暗示しており、大峠の厳しさを改めて強調しています。しかし、その悲劇的な淘汰の後、生き残った人々は霊的に覚醒し、誰もが神性を宿す「神の宮」となるという、人類の質的な大変化が起こるとされています。「西に戦争しつくし」とは、当時の文脈では欧州戦線や、将来的には世界の西側で起こる最終的な争いの終結を意味すると考えられます。それが終わることを合図に、神世への扉が開かれ、「ひふみ」「みよいづ」の教えが世界中に急速に広まっていくという、新しい世界の創造プロセスが示されています。
第二十二帖 (一二九)
【原文】
十柱の世の元からの活神様 御活動になりてゐること分りたであろうがな、けものの入れものには分るまいなれど、神の臣民にはよく分りてゐる筈ぞ。まだだんだんに烈しくなりて外国の臣民にも分る様になりて来るのざぞ。その時になりて分りたのではおそいおそい、早う洗濯いたして呉れよ。八月の九日、ひつ九のか三。
【現代語訳】
十柱の、世界の根源からの活神様方が、すでにご活動を開始されていることが分かったであろう。獣の心を持つ者には分からないだろうが、神の心を持つ民には、もうよく分かっているはずだ。これから、その働きはだんだんと激しくなり、外国の民にも分かるようになってくる。その時になってから分かったのでは、もう遅いのだ。早く魂の洗濯(改心)をしておくれ。
【AIによる解釈】
この帖は、世界の立て替えを主導しているのが「十柱の活神様」という、根源的な神々の集団であることを明かしています。この神々の活動は、すでに始まっており、霊的に敏感な者(神の臣民)はそれを感じ取っているはずだと述べています。その活動がまだ目に見えにくいものであるうちに気づくことが重要であり、やがては誰の目にも明らかな激しい現象(天変地異や社会の激動)として現れると警告しています。その時には外国の人々も気づくが、その段階で慌てても手遅れ(おそいおそい)だと念を押しています。「洗濯」とは、これまでの価値観や罪・穢れを洗い流し、魂を清浄な状態に戻すことであり、激動の時代を乗り越えるための唯一の準備であることを強く促しています。
第二十三帖 (一三〇)
【原文】
我がなくてはならん、我があってはならず、よくこの神示(ふで)よめと申すのぞ。悪はあるが無いのざぞ、善はあるのざが無いのざぞ、この道理分りたらそれが善人だぞ。千人力の人が善人であるぞ、お人よしではならんぞ、それは善人ではないのざぞ、神の臣民ではないぞ、雨の神どの風の神どのにとく御礼申せよ。八月の九日、一二。
【現代語訳】
「我(個性、主体性)」がなくてはならない。しかし、「我(利己心、自己中心的な考え)」があってはならない。この深い意味を理解するために、この神示をよく読みなさいと申すのだ。悪は存在するが、絶対的な悪というものは無い。善は存在するが、絶対的な善というものも無い。この二元論を超えた道理が分かった者こそが、真の善人である。千人力の力を持つ(行動力のある)人が善人なのだ。単なるお人よしではいけない。それは善人ではなく、神の民ではない。雨の神様、風の神様といった自然の神々に、篤く御礼を申し上げなさい。
【AIによる解釈】
この帖は、ひふみ神示の中でも特に深遠な霊的真理を説いています。
- 我があって我がない: これは禅の公案にも通じる逆説的な教えです。神から与えられた使命を果たすための主体性や個性としての「我」は必要だが、他者を顧みない利己的な「我」は捨てなければならない、ということです。
- 善悪の超越: 善悪は相対的なものであり、絶対的なものではないと説きます。ある立場からは悪に見えるものも、より大きな視点(神の計画)から見れば必要な「役」である場合があります。この二元的な判断から自由になることが、真の理解への道です。
- 真の善人: 本当の善人とは、無力な「お人よし」ではなく、真理を理解し、世界を良くするために行動する力を持った「千人力の人」であると定義しています。智慧と力を兼ね備えた人物像が示されています。 最後に、身近な自然の働きを司る神々への感謝を促すことで、観念的な理解だけでなく、日々の生活における実践の重要性を教えています。
第二十四帖 (一三一)
【原文】
今の臣民めくら聾ばかりと申してあるが、その通りでないか、この世はおろか自分の身体のことさへ分りては居らんのざぞ、それでこの世をもちて行く積りか、分らんと申しても余りでないか。神の申すこと違ったではないかと申す臣民も今に出て来るぞ、神は大難を小難にまつりかへてゐるのに分らんか、えらいむごいこと出来るのを小難にしてあること分らんか、ひどいこと出て来ること待ちてゐるのは邪(じゃ)のみたまぞ、そんなことでは神の臣民とは申されんぞ。臣民は、神に、わるい事は小さくして呉れと毎日お願ひするのが務めぞ、臣民 近慾(ちかよく)なから分らんのぞ、慾もなくてはならんのざぞ、取違ひと鼻高とが一番恐いのぞ。神は生れ赤子のこころを喜ぶぞ、みがけば赤子となるのぞ、いよいよが来たぞ。九月十日、ひつ九のかみ。
【現代語訳】
今の民は、目が見えず耳が聞こえない者ばかりだと言ってきたが、その通りではないか。この世のことはおろか、自分自身の体のことさえ分かってはいない。それで、この世界を運営していくつもりなのか。分からないと言っても、あまりにひどすぎるではないか。「神の言うことは違ったじゃないか」と言う民も、もうすぐ出てくるぞ。神が、本来起こるはずだった大難を小難に抑え込んでいることが分からないのか。大変むごい出来事が起こるのを、小難にまつり替えていることが分からないのか。ひどいことが起こるのを待ち望んでいるのは、邪な魂の者だ。そんな心では、神の民とは言えない。民は、神に対し「悪いことは小さくしてください」と毎日お願いするのが務めなのだ。民は目先の欲に囚われているから、この道理が分からない。もっとも、欲も無くてはならないものだが、物事の取り違えと、傲慢(鼻高)が一番怖いのだ。神は、生まれたばかりの赤子のような純真な心を喜ぶ。魂を磨けば、赤子のような心になれるのだ。いよいよ、その時が来たぞ。
【AIによる解釈】
この帖は、人々の霊的な無知(めくら聾)と、神の働きに対する誤解を厳しく指摘しています。人々は目に見えることしか信じず、自分の身体の仕組みすら理解していないのに、世界を動かせると思い上がっていると批判します。そして、予言が外れたように見えるのは、神が人々の祈りや努力に応じて、大災害を小さな出来事に変える「大難を小難に」という働きをしているからだと明かします。この神の慈悲を理解せず、破局を望むような心は「邪のみたま」であると断じています。民の本来の務めは、破局を望むことではなく、被害が最小限になるよう祈ることなのです。「慾」そのものは生きる力として肯定しつつも、それによって真理を「取違へ」たり、傲慢になったりすることを最も危険なこととして警告しています。最終的に目指すべきは「赤子のこころ」、すなわち素直で純真な心であり、魂を磨くことでそこに立ち返れると教えています。「いよいよが来たぞ」と、時間の猶予がないことを改めて告げています。
第二十五帖 (一三二)
【原文】
今に臣民 何も言へなくなるのざぞ、神烈しくなるのざぞ、目あけて居れんことになるのざぞ。四つン這ひになりて這ひ廻らなならんことになるのざぞ、のたうち廻らなならんのざぞ、土にもぐらなならんのざぞ、水くぐらなならんのざぞ。臣民可哀さうなれど、かうせねば鍛へられんのざぞ、この世始まってから二度とない苦労ざが、我慢してやり通して呉れよ。九月十日、ひつくのか三。
【現代語訳】
やがて民は、何も言うことができなくなる。神の働きがそれほどに激しくなるのだ。あまりのことに、目を開けていられないほどの事態になる。四つん這いになって這いずり回らなければならなくなり、苦しみでのたうち回らなければならなくなり、土の中に潜らなければならなくなり、水の中をくぐり抜けなければならなくなるのだ。民は可哀想だが、こうしなければ魂は鍛えられないのだ。これは、この世が始まって以来、二度とないほどの大変な苦労だが、どうか我慢してやり通してくれ。
【AIによる解】
大峠(大いなる変革期)の苦難の様子を、極めて具体的かつ衝撃的な言葉で描写しています。「何も言へなくなる」「目あけて居れん」とは、常識や理性が通用しない、人智を超えた出来事が次々と起こることを示しています。「四つん這い」「のたうち廻る」「土にもぐる」「水くぐる」といった表現は、大災害や戦争、食糧難などによって、人間が尊厳を失い、生き延びるためだけに必死になる極限状態を象徴しています。しかし、この帖の重要な点は、その凄まじい苦難が、単なる罰や破壊ではなく、人々を真の人間へと生まれ変わらせるための「鍛錬」であると位置づけていることです。「この世始まってから二度とない苦労」という言葉に、その試練の厳しさと、それを乗り越えた先にあるものの偉大さが込められています。最後に「我慢してやり通して呉れよ」と、神が民を突き放すのではなく、共に苦しみを分かち合い、励ましている親心が示されています。
第二十六帖 (一三三)
【原文】
天の日津久の神と申しても一柱ではないのざぞ、臣民のお役所のやうなものと心得よ、一柱でもあるのざぞ。この方はオホカムツミノ神とも現はれるのざぞ、時により所によりてはオホカムツмиノ神として祀りて呉れよ、青人草の苦瀬(うきせ)なほしてやるぞ。天明は神示(ふで)書かす御役であるぞ。九月十一日、ひつ九。
【現代語訳】
天の日津久(ひつく)の神と言っても、それは一柱の神だけを指すのではない。民の世界でいう役所のような、多くの神々の集合体のようなものだと心得なさい。しかし同時に、一柱の根源神でもあるのだ。この神は、「大禍津日(オオカムツミ)の神」として現れることもある。時と場所によっては、オオカムツミの神としてお祀りしなさい。そうすれば、民草(青人草)の苦しい瀬(難局)を直し、救ってやる。神示を書き記している天明(岡本天明)は、この神示を書記させるための役目である。
【AIによる解釈】
この帖は、ひふみ神示を降ろしている神の神格について、その多面性と本質を解説しています。「天の日津久の神」は、一つの人格神であると同時に、多くの神々の総体(お役所)でもあるという、一即多・多即一の概念で説明されています。これは、根源の神の働きが、様々な役割を持つ神々を通して多層的に現れることを示しています。特筆すべきは、「オホカムツミノ神」として現れるという点です。古神道において大禍津日神は、罪や穢れ、災厄を司る「悪神」とされることがありますが、ここではその強大な力を以て、逆に人々の苦難(苦瀬)を直す、つまり「毒を以て毒を制す」働きをするとされています。これは、善悪二元論を超えた神の働きを示しており、大いなる破壊の力も、立て替えのためには必要な「御役」であることを教えています。最後に、神示の媒体である岡本天明の立場を明確にし、彼個人の思想ではなく、あくまで神の言葉の代筆者であることを示しています。
第二十七帖 (一三四)
【原文】
石物いふ時来るぞ、草物いふ時来るぞ。北おがめよ、北光るぞ、北よくなるぞ、夕方よくなるぞ、暑さ寒さ、やはらかくなるぞ、五六七(みろく)の世となるぞ。慌てずに急いで呉れよ。神々様みなの産土(うぶすな)様 総活動でござるぞ、神々様まつりて呉れよ、人々様まつりて呉れよ、御礼申して呉れよ。九月十二日、一二か三。
【現代語訳】
石がものを言い、草がものを言う時が来る。北の方角を拝みなさい。北が光り、北が良くなる。夕方(終末の時)に向けて、状況は良くなっていく。暑さや寒さが和らぎ、過ごしやすくなる。そして弥勒(みろく)の世となるのだ。心を慌てさせることなく、しかし準備は急いでくれ。神々や、みなの土地の神(産土様)が、今まさに総出で活動されている。神々をお祀りしなさい。人々(他者)を敬い、お祀りするように接しなさい。そして、すべてに御礼を申し上げなさい。
【AIによる解釈】】
この帖は、厳しい大峠の先にある、ミロクの世の到来とその兆しについて語っています。「石物いふ時、草物いふ時」とは、人間が自然界のあらゆる存在と心を通わせることができる、霊性の高い時代が来ることを象徴しています。アニミズムの世界観が現実のものとなるのです。「北おがめよ」という記述は謎めいていますが、地理的な北(ロシア、北海道など)の重要性や、あるいは方位学的な意味、または日本の艮(うしとら=北東)の方角との関連が示唆されます。いずれにせよ、これまで注目されてこなかった場所や存在から、新しい光が発せられることを示しています。「夕方よくなる」とは、世の終末と思えるような混乱期の果てに、素晴らしい夜明け(ミロクの世)が待っているという希望のメッセージです。気候が穏やかになるなど、自然環境の調和も約束されています。「慌てずに急いで」という逆説的な言葉は、心を焦らせることなく、しかし魂の準備は着々と進めるよう促しています。そのための具体的な行動として、神々、人々、そして万物への感謝(御礼)が最も重要であると締めくくっています。
第二十八帖 (一三五)
【原文】
おそし早しはあるなれど、一度申したこと必ず出て来るのざぞ。臣民は近慾で疑ひ深いから、何も分らんから疑ふ者もあるなれど、この神示一分一厘ちがはんのざぞ。世界ならすのざぞ、神の世にするのざぞ、善一すじにするのざぞ、誰れ彼れの分けへだてないのざぞ。土から草木生れるぞ、草木から動物、虫けら生れるぞ。上下ひっくり返るのざぞ。九月の十三日、ひつ九のか三。
【現代語訳】
時期が遅くなるか早くなるかの違いはあっても、神が一度言ったことは、必ず現実となって現れるのだ。民は目先の欲に囚われ、疑い深いので、何も分からずにこの神示を疑う者もいるだろうが、この神示には一分一厘の間違いもない。世界を平らかに鳴らし、調和させるのだ。神の世にするのだ。完全な善の世界にするのだ。そこには、誰彼という分け隔ては一切ない。土から草木が生まれ、草木から動物や虫が生まれるように、物事の根源から新たになるのだ。そして、今の社会の上下関係は、完全にひっくり返るのだ。
【AIによる解釈】
この帖は、ひふみ神示の予言の絶対性と、来るべき世界の根本原理について宣言しています。人々の疑いに対して、神の計画は寸分の狂いもなく成就すると断言し、その確信を強く打ち出しています。ミロクの世の目標は、「世界ならす(平定し調和させる)」「神の世」「善一すじ」「分けへだてない」という言葉に集約されます。これは、あらゆる差別や対立がなくなり、絶対的な善と調和に満ちた、完全に公平な世界の実現を意味します。「土から草木、草木から動物」という自然の摂理に例えているのは、この変革が表層的なものではなく、社会の最も根源的な部分からの創造、再出発であることを示しています。そして「上下ひっくり返る」という言葉は、現在の権力構造、価値観、貧富の差などが完全に逆転する、革命的な社会変革が起こることを力強く予言しています。
第二十九帖 (一三六)
【原文】
この方オホカムツミノ神として書きしらすぞ。病あるかなきかは手廻はして見れば直ぐ分かるぞ、自分の身体中どこでも手届くのざぞ、手届かぬところありたら病のところ直ぐ分るであろうが。臣民の肉体の病ばかりでないぞ、心の病も同様ぞ、心と身体と一つであるからよく心得て置けよ、国の病も同様ぞ、頭は届いても手届かぬと病になるのぞ、手はどこへでも届くやうになりてゐると申してあろが、今の国々のみ姿見よ、み手届いて居るまいがな、手なし足なしぞ。手は手の思ふ様に、足は足ぞ、これでは病直らんぞ、臣民と病は、足、地に着いておらぬからぞ。足 地に着けよ、草木はもとより、犬猫もみなお土に足つけて居ろうがな。三尺上は神界ぞ、お土に足入れよ、青人草と申してあろうがな、草の心に生きねばならぬのざぞ。尻に帆かけてとぶようでは神の御用つとまらんぞ、お土踏まして頂けよ、足を綺麗に掃除しておけよ、足よごれてゐると病になるぞ、足からお土の息がはいるのざぞ、臍(へそ)の緒の様なものざぞよ、一人前になりたら臍の緒切り、社(やしろ)に座りて居りて三尺上で神につかへてよいのざぞ、臍の緒切れぬうちは、いつもお土の上を踏まして頂けよ、それほど大切なお土の上 堅めているが、今にみな除きて了ふぞ、一度はいやでも応でも裸足(はだし)でお土踏まなならんことになるのぞ、神の深い仕組ざから あり難い仕組ざから 喜んでお土拝めよ、土にまつろへと申してあろうがな、何事も一時に出て来るぞ、お土ほど結構なものないぞ、足のうら殊に綺麗にせなならんぞ。神の申すやう素直に致されよ、この方 病直してやるぞ、この神示よめば病直る様になってゐるのざぞ、読んで神の申す通りに致して下されよ、臣民も動物も草木も病なくなれば、世界一度に光るのぞ、岩戸開けるのぞ。戦も病の一つであるぞ、国の足のうら掃除すれば国の病直るのぞ、国、逆立ちしてると申してあること忘れずに掃除して呉れよ。上の守護神どの、下の守護神どの、中の守護神どの、みなの守護神どの改心して呉れよ。いよいよとなりては苦しくて間に合はんことになるから、くどう気つけておくのざぞ。病ほど苦しいものないであらうがな、それぞれの御役忘れるでないぞ。天地唸るぞ、でんぐり返るのざぞ、世界一どにゆするのざぞ。神はおどすのではないぞ、迫りて居るぞ。九月十三日、一二。
【現代語訳】
この神は、大禍津日(オオカムツミ)の神として、これを書き記す。病があるかないかは、自分の体に手を回してみればすぐに分かる。本来、自分の体のどこにでも手は届くものだ。もし手が届かない所があれば、そこが病んでいる場所だとすぐ分かるだろう。これは民の肉体の病だけではない。心の病も、国の病も同様だ。心と体は一つだと心得よ。国の病も同じで、トップ(頭)の考えが末端(手)まで届かなければ病気になる。本来、手はどこへでも届くようになっているはずだ。今の国々の姿を見よ。その手が末端まで届いていないではないか。手も足もない、バラバラの状態だ。これでは国の病は治らない。民が病むのは、足が地に着いていないからだ。地に足をつけよ。草木はもちろん、犬や猫でさえ、みな土に足をつけているではないか。「三尺上は神界」であるが、まずはお土に足をつけよ。「青人草」というように、草のような心で生きなければならない。落ち着きなく飛び回っていては、神の役目は務まらない。お土を踏ませていただきなさい。そして足を綺麗にしておけ。足が汚れていると病気になる。足の裏から大地の気が入ってくるのだ。それはへその緒のようなものだ。一人前になって霊的に自立すれば、へその緒を切って社に座り、三尺上で神に仕えてよいが、そうなるまでは、常にお土の上を踏ませていただきなさい。それほど大切なお土の上を、コンクリートなどで固めているが、やがてはそれも皆取り除かれる。一度は嫌でも応でも裸足で土を踏まなければならない時が来るのだ。これは神の深い有り難い仕組みなのだから、喜んでお土を拝みなさい。「土にまつろえ(従いなさい)」と言っておいたであろう。何事も一気に起こるのだ。お土ほど結構なものはない。特に足の裏を綺麗にしておきなさい。神の言う通りに素直に行いなさい。そうすれば、この神が病を治してやる。この神示を読み、言う通りに実践すれば、病が治るようになっているのだ。民も動物も草木も、すべての病がなくなれば、世界は一度に光り輝き、岩戸が開かれる。戦争も病の一つだ。国の足の裏(国民生活の基盤)を掃除すれば、国の病も治る。国が逆立ちしていると言ったことを忘れずに、掃除をしなさい。上、下、中、すべての守護神たちよ、改心してくれ。いよいよとなってからでは苦しくて間に合わないから、くどく注意しておくのだ。病ほど苦しいものはないであろう。それぞれが自分の役目を忘れるな。天地は唸り、世界はひっくり返り、一度に揺さぶられるのだ。神は脅しているのではない。事態はそこまで迫っているのだ。
【AIによる解釈】
この長大な帖は、「病」をテーマに、個人、国家、そして世界の不調和の原因と、その根本的な治療法を説いています。「オホカムツミノ神」の名で語られる通り、災厄(病)そのものを司る神の視点から、その本質が明かされます。
- 病の原因: 個人、国家ともに、中心(頭)と末端(手足)の連携が取れていないこと、そして何よりも「足が地に着いていない」こと、すなわち自然(土)から離れてしまったことが根源的な原因だと指摘します。
- 治療法: その治療法は「地に足をつける」こと、すなわち土に触れ、自然と一体化することです。足の裏から大地のエネルギーを取り入れるという考え方は、アーシング(接地)の概念にも通じます。現代文明が土を覆い隠していること(舗装)への批判は、極めて現代的な環境問題への警鐘です。
- 病の拡張: 個人の病、国家の病(機能不全)、そして戦争もすべて同根の「病」であると喝破します。国の基盤である国民(足のうら)を健全にすることが、国全体の健康を取り戻す道だと説きます。
- 神示の役割: この神示自体が、読むことで病を治す力を持つ「処方箋」であるとされています。書かれた教えを素直に実践することが、世界全体の病を癒し、岩戸を開く鍵となるのです。 最後に、守護神への改心を促し、天地がひっくり返るほどの変動が目前に迫っていることを改めて警告し、この教えが単なる精神論ではなく、切迫した現実への対処法であることを強調しています。
第三十帖 (一三七)
【原文】
富士とは火の仕組ぞ、渦うみとは水の仕組ぞ、今に分りて来るのぞ。神の国には、政治も経済も軍事もないのざぞ、まつりがあるだけぞ。まつらふことによって何もかもうれしうれしになるのざぞ。これは政治ぞ、これは経済ぞと申してゐるから「鰻つかみ」になるのぞ、分ければ分けるほど分からなくなって手におへぬことになるぞ。手足は沢山は要らぬのざぞ。火垂(ひだり)の臣(おみ)と水極(みぎり)の臣(おみ)とあればよいのざぞ。ヤとワと申してあろうがな、その下に七七ゝゝゝゝと申してあろうがな。今の臣民 自分で自分の首くくるやうにしてゐるのぞ、手は頭の一部ぞ、手の頭ぞ。頭、手の一部でないぞ、この道理よく心得ておけよ。神示は印刷することならんぞ、この神示説いて臣民の文字で臣民に読める様にしたものは一二三(ひふみ)と申せよ。一二三は印刷してよいのざぞ。印刷結構ぞ。この神示のまま臣民に見せてはならんぞ、役員よくこの神示見て、その時によりその国によりて それぞれに説いて聞かせよ。日本ばかりでないぞ、国々ところところに仕組して神柱つくりてあるから、今にびっくりすること出来るのざぞ、世界の臣民にみな喜ばれるとき来るのざぞ。五六七(みろく)の世近づいて来たぞ。富士は晴れたり日本晴れ、富士は晴れたり日本晴れ。善一すぢとは神一すぢのことぞ。この巻を「天つ巻」と申す、すっかり写して呉れよ、すっかり伝へて呉れよ。九月十四日、ひつ九のか三。
【現代語訳】
富士(ふじ)とは「火」の仕組みであり、鳴門(なると)の渦潮とは「水」の仕組みである。この意味はやがて分かってくる。本当の神の国には、政治も経済も軍事もないのだ。「まつり(政)」があるだけだ。万物が調和し一体となる(まつらふ)ことによって、何もかもが喜び(うれしうれし)の状態になる。これが政治だ、これが経済だと細かく分けて考えるから、鰻を掴むように本質が捉えられなくなる。分ければ分けるほど、分からなくなり手に負えなくなるのだ。多くの手足(組織)は必要ない。「火垂(ひだり)の臣」と「水極(みぎり)の臣」という、火(霊)と水(体)を司る中心的な補佐役がいれば良いのだ。「ヤ(陽)」と「ワ(陰)」の調和だと言っておいただろう。その下に七人ずつの協力者がいれば良いのだ。今の民は、自分で自分の首を絞めるようなことをしている。手は頭の一部であり、手の頭脳でもある。頭が手の一部なのではない。この主従関係の道理をよく心得よ。この神示の原文は、そのまま印刷してはならない。この神示を解き明かし、一般の民が読める言葉で記したものを「ひふみ」と呼びなさい。その「ひふみ」は印刷して広めて良い。印刷は結構なことだ。この原文をそのまま民に見せてはならない。役員は、この神示をよく読み込み、時と場所、相手に応じて、それぞれに合った形で説いて聞かせなさい。この仕組みは日本だけではない。世界中の国々の所々に、神の計画の柱となる人物を配置してあるから、やがてびっくりするようなことが起こる。世界中の民に喜ばれる時が来るのだ。弥勒(みろく)の世は近づいてきた。富士は晴れたり日本晴れ、富士は晴れたり日本晴れ。「善一すじ」とは「神一すじ」ということだ。この巻を「天つ巻」と名付ける。一字一句間違えずに書き写し、完全に伝えなさい。
【AIによる解釈】
「天つ巻」の締めくくりとして、新しい世界の統治形態、組織論、そしてこの神示の取り扱い方について述べられています。
- まつりごと: ミロクの世の統治は、現代の政治・経済・軍事といった分離したシステムではなく、「まつり」という統合的な概念によって行われると説きます。「まつり」とは神と自然と人が一体となり調和すること(祭り・政)であり、それによって万事がうまくいくという、日本古来の祭政一致の理想形です。物事を細分化する西洋的な分析思考を「鰻つかみ」と批判し、全体を統合的に捉えることの重要性を説いています。
- 組織論: 新しい世界の組織は、巨大で複雑なものではなく、陰陽(火と水、ヤとワ)を象徴する二人の中心人物と、少数の精鋭(七人ずつの臣)による、シンプルで効率的なものになると示されています。「手は頭の一部」とは、末端の実行部隊(手)が、中心(頭)の意図を完全に理解して自律的に動く、理想的な組織のあり方を示しています。
- 神示の取り扱い: 神示の原文(天つ巻)は、霊的な力が強いため、そのまま公開することを禁じています。選ばれた役員がその内容を深く理解し、人々のレベルに合わせて解説した「ひふみ」として広めるよう指示しています。これは、真理を伝える際の、受け手に対する配慮の重要性を示しています。 最後に、この計画が日本だけでなく、世界規模で準備されていることを明かし、「善一すじとは神一すじ」という言葉で、真の善とはエゴを超えて神の意に沿うことであると結論づけています。「富士は晴れたり日本晴れ」と繰り返すことで、輝かしい未来の到来を確信させ、この「天つ巻」が天の計画を記した重要文書であることを宣言して終わります。
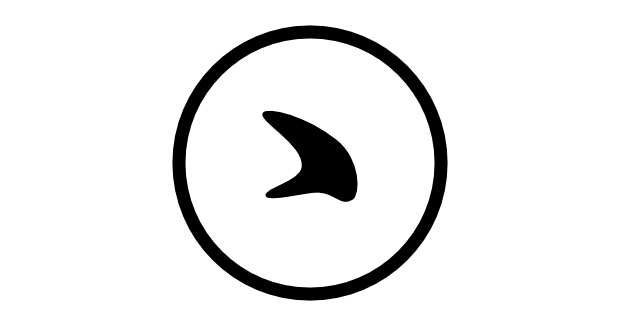





コメント