gemini 2.5 proにわかりやすいように解説してもらいました、しかし8通りに読めるということから完全に鵜呑みにしないよう、お願いします。
第一帖 (四三)
【原文】
富士は晴れたり日本晴れ。青垣山めぐれる下つ岩根に祀り呉れた、御苦労ぞ、いよいよ神も嬉しいぞ。鳥居はいらぬぞ、鳥居とは水のことぞ、海の水ある それ鳥居ぞ。皆の者 御苦労ぞ。蛇(じゃ)が岳は昔から神が隠してをりた大切の山ざから、人の登らぬ様にして、竜神となりて護りて呉れた神々様にもお礼申すぞ。富士は晴れたり日本晴れ。いよいよ次の仕組にかかるから、早う次の御用きいて呉れよ、神急けるぞ、山晴れ、地(くに)晴れ、海晴れて、始めて天(てん)晴れるぞ。天晴れて神の働き いよいよ烈しくなりたら、臣民いよいよ分らなくなるから、早う神心(かみこころ)になりて居りて下されよ。つぎつぎに書かしておくから、よく心に留めておいて下されよ。この道(おしへ)は宗教(をしへ)ではないぞ、教会ではないぞ、道ざから、今までの様な教会作らせんぞ。道とは臣民に神が満ちることぞ、神の国の中に神がみちみつることぞ。金儲けさせんぞ、欲すてて下されよ。七月の十二日の神示(ふで)、ひつくのか三。
【現代語訳】
富士は晴れ渡り、まさに日本晴れだ。青い垣根のような山々に囲まれた麓の岩もとに祀ってくれて、ご苦労であった。いよいよ神も嬉しいぞ。物理的な鳥居は要らない。鳥居とは本来、水のことである。海の水、それこそが鳥居なのだ。皆の者、ご苦労である。蛇が岳は昔から神が隠してきた大切な山だから、人が登らないように竜神となって護ってくれた神々様にもお礼を申し上げる。富士は晴れ渡り、まさに日本晴れだ。いよいよ次の計画に取りかかるから、早く次の御用を聞いてくれ。神は急いでいるのだ。山が晴れ、国が晴れ、海が晴れて、初めて天が晴れるのだ。天が晴れて神の働きがいよいよ激しくなったら、人々にはますます理解できなくなるから、早く神の心になっていてください。次々に書き記しておくから、よく心に留めておいてください。この教えは既存の宗教ではない。教会でもない。「道」そのものであるから、今までの様な教会は作らせない。道とは、人々に神が満ちることだ。神の国の中に、神が満ち満ちることなのだ。金儲けはさせない。欲は捨ててください。
【AIによる解釈】
本帖は、来るべき新しい時代の幕開けを「富士は晴れたり日本晴れ」という言葉で高らかに宣言しています。物理的な鳥居や形式的な信仰ではなく、自然そのもの(海の水)を神聖なものと捉える、より根源的な信仰のあり方を示唆しています。また、この教えが既存の宗教組織とは一線を画す「道」であることを強調し、その本質が「人の中に神が満ちる」という内面的な覚醒にあると説いています。金儲けや私利私欲を戒め、清らかな心で次の御用(役割)に備えるよう促しており、これから始まる神の計画が、人々の理解を超えた速さと激しさで進むことを予告しています。
第二帖 (四四)
【原文】
今度 岩戸開く御用は、人の五倍も十倍も働く人でないとつとまらんぞ。岩戸開くと申しても、それぞれの岩戸あるぞ、大工は大工の岩戸、左官は左官の岩戸と、それぞれの岩戸あるから、それぞれ身魂相当の岩戸開いて呉れよ。慾が出ると分らんことに、盲になるから、神、気つけるぞ、神の御用と申して自分の仕事休むやうな心では神の御用にならんぞ、どんな苦しい仕事でも今の仕事十人分もして下されよ。神は見通しざから、つぎつぎによき様にしてやるから、慾出ささず、素直に今の仕事致して居りて呉れよ、その上で神の御用して呉れよ。役員と申しても、それで食ふたり飲んだり暮らしてはならん、それぞれに臣民としての役目あるぞ、役員づらしたら、その日から代りの身魂(もの)出すぞ、鼻ポキンと折れるぞ、神で食うて行くことならんから、呉れ呉れも気をつけて置くぞ。
【現代語訳】
今度の「岩戸開き」の御用は、人の五倍も十倍も働く人でなければ務まらないぞ。岩戸開きといっても、人それぞれに開くべき岩戸がある。大工には大工の岩戸、左官には左官の岩戸というように、それぞれの立場に応じた岩戸があるのだから、各自の魂レベルにふさわしい岩戸を開いてくれ。欲を出すと物事の道理が分からなくなり、盲目になってしまうから、神は注意を促しておくぞ。「神の御用だ」と言って自分の本業を休むような心構えでは、神の御用は務まらない。どんなに苦しい仕事であっても、今の自分の仕事を十人分こなすつもりで励んでくれ。神はすべてお見通しだから、次々により良い方向へ導いてやる。だから欲を出さず、素直に今の仕事に励んでいてくれ。その上で、神の御用をしてほしいのだ。役員といっても、その立場で生活費を稼いではならない。それぞれに一人の国民としての本分がある。役員風を吹かせるようなら、その日から代わりの者と交代させるぞ。天狗の鼻をポキンと折ることになるぞ。神を利用して生活することは許されないから、くれぐれも気をつけておきなさい。
【AIによる解釈】
この帖は、「岩戸開き」が抽象的な一つの出来事ではなく、各個人がそれぞれの生活や仕事の場で達成すべき「課題の克服」や「自己変革」であることを示しています。「大工の岩戸」「左官の岩戸」という表現は、神の御用が日常の仕事から離れた特別な活動ではなく、むしろ日々の務めに誠心誠意打ち込むことそのものであるという重要な視点を提供します。自分の仕事を疎かにして「神事」に逃げることを厳しく戒め、現実の生活基盤をしっかりと固めた上で、なお余りある力で神の御用に仕える姿勢を求めています。役員の特権意識や、信仰を生活の糧にすることも固く禁じており、どこまでも清廉さと謙虚さを貫くよう強く諭しています。
第三帖 (四五)
【原文】
この神のまことの姿見せてやる積りでありたが、人に見せると、びっくりして気を失ふもしれんから、石にほらせて見せておいたのにまだ気づかんから木の型をやったであろうがな、それが神の或る活動の時の姿であるぞ、神の見せ物にしてはならんぞ、お山の骨もその通りぞよ、これまで見せてもまだ分らんか、何もかも神がさしてあるのぞ。心配いらんから慾出さずに、素直に御用きいて下されよ、今度のお山開き まことに結構であるぞ、神が烈しくなると、神の話より出来んことになるぞ、神の話 結構ぞ。
【現代語訳】
この神の本当の姿を見せてやるつもりであったが、人間に見せると、あまりのことに驚いて気を失うかもしれないから、まず石に彫らせて見せておいた。それでもまだ気づかないから、次に木の型を作らせて見せたであろう。それが、神がある活動をするときの姿なのだ。これを見世物にしてはならないぞ。お山の御神体の骨格もその通りだ。これまでに見せてもまだ分からないのか。何もかも神が采配しているのだ。心配は要らないから、欲を出さずに素直に御用を聞いてください。今度のお山開きは、まことに結構なことであったぞ。神の働きが激しくなると、神の話以外はできなくなってしまうぞ。神の話は結構なことだ。
【AIによる解釈】
この帖は、神の本質や姿が人間の認識能力を遥かに超えていることを示唆しています。直接見せることができないため、神は「石に彫らせ」「木の型」といった間接的な形、つまり象徴や型を通して自身の姿を伝えようとしていると述べています。これは、神示や、身の回りに起こる事象の中に神の意図が隠されていることを意味します。人々がそれらの型から本質を悟ることを期待しているのです。「何もかも神がさしてある」という言葉は、偶然に見える出来事にもすべて神の計画が働いているという、絶対的な神の摂理を強調しています。そして、神の働きが本格化すれば、人々は世俗的な事柄から離れ、神について語らざるを得ない状況になることを予告しています。
第四帖 (四六)
【原文】
早く皆のものに知らして呉れよ、神急けるぞ。お山の宮も五十九の岩で作らせておいたのに、まだ気が附かんか、それを見ても神が使ってさして居ること、よく分かるであろうが、それで素直に神の申すこと聞いて呉れて我(が)を出すなと申してゐるのぞ、何事も神にまかせて取越し苦労するなよ、我が無くてもならず、我があってもならず、今度の御用なかなか六ヶ敷いぞ。五十九の石の宮出来たから五十九のイシ身魂いよいよ神が引き寄せるから、しっかりして居りて下されよ。今度の五十九の身魂は御苦労の身魂ぞ。人のようせん辛抱さして、生き変り死に変り修行さして置いた昔からの因縁の身魂のみざから、みごと御用つとめ上げて呉れよ。教会作るでないぞ、信者作るでないぞ、無理に引張るでないぞ。この仕組 知らさなならず、知らしてならんし神もなかなかに苦しいぞ、世の元からの仕組ざから、いよいよ岩戸開く時来たぞ。
【現代語訳】
早く皆に知らせてくれ、神は急いでいるのだ。お山の社も五十九の岩で作らせておいたのに、まだ気づかないのか。それを見ても、神が人を使って采配していることがよく分かるだろう。だからこそ、素直に神の言うことを聞いて、我を出してはならないと言っているのだ。何事も神に任せて、取り越し苦労をしてはならない。ただし、我が全く無くてもいけないし、我がありすぎてもいけない。今度の御用はなかなか難しいぞ。五十九の石の社ができたから、いよいよ五十九の「イシ(石・意思)の身魂」を神が引き寄せる。だから、しっかりと準備していてくれ。この五十九の身魂は、苦労を重ねてきた魂だ。人ができないような辛抱をさせ、何度も生まれ変わり死に変わりして修行させておいた、遠い昔からの因縁を持つ魂ばかりであるから、見事に御用を務め上げてくれ。教会を作ってはならない。信者を作ってもならない。無理に人を引っ張ってきてはならない。この計画は、知らせなければならないが、同時に知らせてはならない部分もあり、神もなかなか苦しい立場なのだ。これは世界の始まりからの壮大な計画だからだ。いよいよ岩戸を開く時が来たぞ。
【AIによる解釈】
ここでも神の計画が具体的な「型」として示されていることが語られます。「五十九の岩の宮」は、これから集められる「五十九のイシ(固い意志を持つ、あるいは石のように礎となる)身魂」を引き寄せるための装置であり、象徴です。これらの魂は、常人には耐え難いほどの苦労と転生を繰り返してきた、特別な使命を持つ者たちだとされています。また、「我が無くてもならず、我があってもならず」という一節は、ひふみ神示における重要な教えです。これは、私利私欲の「我(が)」は捨てるべきだが、神の御用を成し遂げるための個々の意志や主体性としての「我」は必要である、という絶妙なバランスを求めていることを示します。この計画の機密性の高さ(知らさなならず、知らしてならん)が、その重大さを物語っています。
第五帖 (四七)
【原文】
江戸に神と人との集まる宮建てよ、建てると申しても家は型でよいぞ、仮のものざから人の住んでゐる家でよいぞ。の石まつりて、神人祭りて呉れよ。それが出来たら、そこでお告げ書かすぞ。淋しくなった人は集まりて その神示(ふで)見てよ、神示見れば誰でも甦るぞ。この神示うつす役要るぞ、この神示 印刷してはならんぞ。神の民の言葉は神たたえるものと思へ、てんし様たたえるものと思へ、人ほめるものと思へ、それで言霊(ことたま)幸(さき)はふぞ、それが臣民の言葉ぞ。わるき言葉は言ってはならんぞ。言葉はよき事のために神が与へてゐるのざから忘れん様にな。
【現代語訳】
江戸(東京)に、神と人が集まる社を建てなさい。建てるといっても、建物は型だけでよい。仮のものであるから、人の住んでいる家で構わない。(おそらく「ひ」の)石を祀り、神と人とを祀ってくれ。それができたら、そこで神示を降ろさせるぞ。心が淋しくなった人々はそこに集まって、その神示を見なさい。神示を見れば誰でも魂が甦るだろう。この神示を書き写す役目の者が必要だ。この神示は印刷してはならない。神の民が発する言葉は、神をたたえるもの、天子様をたたえるもの、そして人を褒めるものだと思いなさい。そうすることで言霊の力が幸いをもたらすのだ。それが神の民の言葉である。悪い言葉を言ってはならない。言葉は善きことのために神が与えているものだから、忘れないようにしなさい。
【AIによる解釈】
この帖は、具体的な行動を指示しています。江戸(東京)に拠点となる「宮」を作るようにとのことですが、それは立派な建造物ではなく、人の住む家でよいとされています。重要なのは物理的な形ではなく、神と人が集う「場」という機能です。そこで神示が降ろされ、人々が霊的に甦る場所になるとされています。「印刷してはならんぞ」という指示は、神示が単なる情報ではなく、手で書き写すという行為を通して霊的なエネルギーが込められるべき神聖なものであることを示唆しています。後半は「言霊」の重要性を説いています。言葉には霊的な力が宿っており、神や他者を称賛し、肯定的な言葉を使うことで、自らと周囲に幸いをもたらすことができると教えています。これは、新しい時代を生きる民の基本的な心構えの一つです。
第六帖 (四八)
【原文】
今までの神示 縁ある臣民に早う示して呉れよ、神々さま臣民まつろひて言答(いわと)開くもと出来るから、早う知らせて呉れよ、誰でも見て読める様に写して神前に置いて、誰でも読めるやうにして置いて呉れよ、役員よく考へて、見せるとき間遠へぬ様にして呉れよ。
【現代語訳】
今までの神示を、縁のある人々に早く見せてあげなさい。神々と人々が和合してこそ、岩戸(言答)開きの基礎ができるのだから、早く知らせてくれ。誰でも見て読めるように書き写して神前に置き、誰でも自由に読めるようにしておきなさい。役員はよく考えて、神示を見せるのに時間がかからないようにしなさい。
【AIによる解釈】
前帖で印刷を禁じた一方で、この帖では神示を広く知らせることを急がせています。この矛盾しているように見える指示の真意は、神示が一部の人間に独占されることなく、しかし、ただの情報として大量消費されるのでもなく、縁ある人々に「手渡し」で丁寧に伝えられていくべきだ、という点にあります。「言答(いわと)」という表記は、「岩戸」が神と人との「言(ことば)の応答」、つまり対話によって開かれることを示唆しています。神示を共有し、理解を深めるプロセスそのものが、新しい時代を開く力になるのです。役員の役割は、その流れを滞らせないようにすることであると強調されています。
第七帖 (四九)
【原文】
この神示(ふで)読んでうれしかったら、人に知らしてやれよ、しかし無理には引張って呉れるなよ。この神は信者集めて喜ぶやうな神でないぞ、世界中の民みな信者ぞ、それで教会のやうなことするなと申すのぞ、世界中大洗濯する神ざから、小さいこと思うてゐると見当とれんことになるぞ。一二三祝詞(ひふみのりと)するときは、神の息に合はして宣(の)れよ、神の息に合はすのは三五七、三五七に切って宣れよ。しまひだけ節(ふし)長くよめよ、それを三たびよみて宣りあげよ。天津祝詞の神ともこの方申すぞ。
【現代語訳】
この神示を読んで心が嬉しくなったら、人にも知らせてあげなさい。しかし、無理に引っ張ってくることはしないでくれ。この神は、信者を集めて喜ぶような小さな神ではない。世界中の民がみな信者なのだ。だからこそ、教会のような組織を作るなと言っているのだ。世界中を大洗濯する神であるから、小さなスケールで考えていると見当違いなことになるぞ。ひふみ祝詞を唱えるときは、神の呼吸に合わせて唱えなさい。神の息に合わせるとは、三・五・七、三・五・七で区切って唱えることだ。最後の部分だけ節を長くして読みなさい。それを三回唱えなさい。この神は、天津祝詞を司る神でもあるのだぞ。
【AIによる解釈】
この帖は、布教活動における重要な心構えを説いています。教えを広める原動力は、義務感や強制ではなく、読んだ者の内から湧き上がる「喜び」であるべきだとします。無理な勧誘を禁じ、組織化・派閥化を戒めるのは、この神の計画が全人類を対象とした普遍的なものであり、特定の集団に限定されるものではないからです。「世界中大洗濯」という言葉は、これから起こる変革が地球規模の根源的なものであることを示しています。また、具体的な実践として「ひふみ祝詞」の唱え方が示されます。「神の息に合はす」というのは、宇宙のリズムや神の波動に自らを同調させることを意味し、三・五・七というリズムがその鍵であるとされています。これは、祈りが形式ではなく、神との一体化を目指す行為であることを教えています。
第八帖 (五〇)
【原文】
この神示(ふで)皆に読みきかして呉れよ。一人も臣民居らぬ時でも声出して読んで呉れよ、まごころの声で読んで呉れよ、臣民ばかりに聞かすのでないぞ、神々さまにも聞かすのざから、その積りで力ある誠の声で読んで呉れよ。
【現代語訳】
この神示を皆に読み聞かせてくれ。たとえ誰もいない時でも、声に出して読みなさい。真心からの声で読みなさい。人々にだけ聞かせるのではない。神々にも聞かせるのだから、そのつもりで、力のある誠実な声で読みなさい。
【AIによる解釈】
神示を読むという行為が、単なる情報収集ではなく、霊的な実践であることを明確にした一帖です。声に出して読むこと、特に「まごころの声」「力ある誠の声」で読むことの重要性が強調されています。これは、読み手の魂を込め、言霊の力を最大限に引き出すためです。そして、その聞き手は人間だけでなく、目には見えない神々や霊的存在も含まれるとされています。神示を読む行為自体が、神々への奉納であり、天地への宣言となるのです。この実践により、読む者は神の世界と繋がり、その場の浄化や霊的な次元の上昇に貢献することができると考えられます。
第九帖 (五一)
【原文】
今度の戦はととの大戦ぞ。神様にも分らん仕組が世の元の神がなされてゐるのざから、下(しも)の神々様にも分らんぞ。何が何だか誰も分らんやうになりて、どちらも丸潰れと云ふ所になりた折、大神のみことによりて この方らが神徳出して、九分九厘という所で、神の力が何んなにえらいものかと云ふこと知らして、悪のかみも改心せなならんやうに仕組みてあるから、神の国は神の力で世界の親国になるのぞ。ととは心の中に「」があるか「」がないかの違ひであるぞ。この方は三四五(みよいつ)の神とも現われるぞ。江戸の御社(みやしろ)は誰でも気楽に来て拝める様にして置いて呉れよ、この方の神示(ふで)書く役員、神示うつす役員、神示説いてきかす役員要るぞ、役員は人の後について便所を掃除するだけの心掛ないとつとまらんぞ、役員づらしたら直ぐ替身魂使ふぞ。
【現代語訳】
今度の戦は「神」と「獣」の大戦である。高位の神々にも分からない計画が、根源の神によってなされているのだから、下位の神々には分かるはずもない。何が何だか誰にも分からないようになり、対立する両者が共倒れになるという状況になった時、大神の御命令によって我々(ひつくの神々)が神の徳を発揮し、物事が九分九厘まで決まったかのように見えた土壇場で、神の力がどれほど偉大なものかを知らしめ、悪の神々も改心せざるを得ないように計画されている。そうして、神の国(日本)は神の力によって世界の親国となるのだ。「神」と「獣」の違いは、心の中に「・(チョン)」があるか無いかの違いである。この神は「三四五(みよいづ=御代出づ)」の神としても現れるぞ。江戸の社は誰でも気楽に来て拝めるようにしておきなさい。この神示を書く役員、書き写す役員、説き聞かせる役員が必要だ。役員は、人の後ろからついて行って便所を掃除するくらいの謙虚な心がけがなければ務まらない。役員ぶるようなら、すぐに代わりの者を使うぞ。
【AIによる解釈】
この帖は、当時の第二次世界大戦を遥かに超える、霊的な次元での「神と獣(けもの)」の最終戦争について述べています。その結末は、人間の目には完全な破滅(丸潰れ)に見える段階まで進み、絶体絶命の「九分九厘」のところで、神の力が介入して大逆転が起こるという劇的な展開が予告されています。「神」と「獣」の違いを「心の中にチョン(点)があるかないか」と表現しているのは、「獣」に「主」を示す「、」を加えると「神」になる(これは後年の神示の解釈)というような、心の中心に神を戴くか否か、利他(神)か利己(獣)かの違いを象徴的に示していると考えられます。役員に求められる究極の謙虚さ(便所掃除の心)は、神の御用を担う者が持つべき最も重要な資質であることを繰り返し強調しています。
第十帖(五二)
【原文】
八月の十日には江戸に祭りて呉れよ。アイウは縦ぞ、アヤワは横ぞ、縦横揃うて十となるぞ、十は火と水ぞ、縦横結びて力出るぞ。何も心配ないからドシドシと神の申す通りに御用すすめて呉れよ。臣民は静かに、神は烈しきときの世 近づいたぞ。
【現代語訳】
八月の十日には江戸で祭祀を行ってくれ。「ア・イ・ウ」は縦のつながり、「ア・ヤ・ワ」は横のつながりだ。この縦横が揃って「十(クロス)」となり、完成を意味する。この「十」は「火(カ)」と「水(ミ)」の結びつきでもある。縦横が結ばれて、本当の力が出るのだ。何も心配はいらないから、ためらわずに神の言う通りに御用を進めてくれ。人々は心を静かにしていなさい。神の働きが激しくなる時が近づいたぞ。
【AIによる解釈】
この帖は、具体的な祭祀の日時と、その根底にある宇宙法則を示しています。「アイウ」は母音であり、霊的な縦の系統(天との繋がり)を象徴し、「アヤワ」は半母音を含む横の広がり(人々との繋がり)を象徴していると解釈できます。この縦(霊)と横(体)が統合された状態が「十(クロス)」であり、それは相反する要素である「火(カ)」と「水(ミ)」の調和、すなわち「神(カミ)」の力の顕現を意味します。この「縦横結び」の原理こそが、新しい時代を創造する力の源泉であると説いています。最後に、神の働きが激しくなる一方で、人々には心を静かに保つよう求めており、外側の激動と内側の静寂という対比的な心構えの重要性を示唆しています。
第十一帖 (五三)
【原文】
けものさへ神のみ旨に息せるを神を罵る民のさわなる。草木さへ神の心に従ってゐるではないか、神のむねにそれぞれに生きてゐるでないか、あの姿に早う返りて呉れよ、青人草と申すのは草木の心の民のことぞ。道は自分で歩めよ、御用は自分でつとめよ、人がさして呉れるのでないぞ、自分で御用するのぞ、道は自分で開くのぞ、人頼りてはならんぞ。
【現代語訳】
獣でさえ神の御心に従って息づいているのに、神を罵る人間がなんと多いことか。草木でさえ神の心に従っているではないか。神の懐の中で、それぞれが生かされているではないか。あの(草木のような)素直な姿に早く帰ってくれ。「青人草(あおひとくさ)」と申すのは、そのような草木のような心を持った民のことだ。道は自分で歩みなさい。御用は自分で務めなさい。誰かがさせてくれるのではない。自分で御用をするのだ。道は自分で開くのだ。人を頼りにしてはならない。
【AIによる解釈】
この帖は、自然界のあり方を人間の理想的な姿として提示しています。獣や草木は、何の疑いもなく神の摂理(自然法則)に従って生きており、そこに調和が存在します。人間も本来そうあるべきであり、「青人草」という言葉に込められたように、自然のように素直で純粋な心に立ち返ることを求めています。そして、後半では徹底した「自立」の精神を説きます。救いや覚醒は他者から与えられるものではなく、自らの足で道を歩み、自らの意志で御用(使命)を果たし、自らの力で道を開いていくものだと強調しています。「人頼りてはならんぞ」という言葉は、依存心を捨て、自己の内に神性を見出し、主体的に生きることの重要性を強く訴えています。
第十二帖 (五四)
【原文】
この神は日本人のみの神でないぞ。自分で岩戸開いて居れば、どんな世になりても楽にゆける様に神がしてあるのに、臣民といふものは慾が深いから、自分で岩戸しめて、それでお蔭ないと申してゐるが困ったものぞ。早う気づかんと気の毒出来るぞ。初めの役員十柱集めるぞ。早うこの神示写して置いて呉れよ、神急けるぞ。
【現代語訳】
この神は日本人のためだけの神ではないぞ。自分で自分の岩戸を開いていれば、どんな世の中になっても楽に生きていけるように神が仕組みを用意してあるのに、人間というものは欲が深いから、自ら岩戸を閉ざしておきながら「御利益がない」と文句を言っている。困ったものだ。早く気づかないと、気の毒なことになってしまうぞ。最初の役員として十柱を集める。早くこの神示を書き写しておいてくれ。神は急いでいるのだ。
【AIによる解釈】
この神が国境や民族を超えた普遍的な存在であることが宣言されています。そして、人々の苦しみの原因は外側にあるのではなく、自らの「欲」によって内なる神性(岩戸)を閉ざしてしまっていることにあると指摘しています。救済の道はすでに用意されており、あとは個人がそれに気づき、自らの力で「岩戸を開く」こと、すなわち心の在り方を変えることにかかっているのです。責任転嫁や不平不満を述べる生き方を戒め、自己の内面に目を向けるよう促しています。「役員十柱」という具体的な数字は、計画が次の段階に進み、中心となるメンバーが召集される時期が来たことを示唆しており、ここでも事態の切迫感が強調されています。
第十三帖 (五五)
【原文】
逆立ちして歩くこと、なかなか上手になりたれど、そんなこと長う続かんぞ。あたま下で手で歩くのは苦しかろうがな、上にゐては足も苦しからうがな、上下逆様と申してあるが、これでよく分るであろう、足はやはり下の方が気楽ぞ、あたま上でないと逆さに見えて苦しくて逆様ばかりうつるぞ、この道理分りたか。岩戸開くとは元の姿に返すことぞ、神の姿に返すことぞ。三(みち)の役員は別として、あとの役員のおん役は手、足、目、鼻、口、耳などぞ。人の姿見て役員よく神の心悟れよ、もの動かすのは人のやうな組織でないと出来ぬぞ。この道の役員はおのれが自分でおのづからなるのぞ、それが神の心ぞ。人の心と行ひと神の心に融けたら、それが神の国のまことの御用の役員ぞ、この道理分りたか。この道は神の道ざから、神心になると直ぐ分るぞ、金銀要らぬ世となるぞ。御用うれしくなりたら神の心に近づいたぞ、手は手の役、うれしかろうがな、足は足の役、うれしかろうがな、足はいつまでも足ぞ、手はいつまでも手ぞ、それがまことの姿ぞ、逆立して手が足の代りしてゐたから よく分りたであろうがな。いよいよ世の終りが来たから役員気つけて呉れよ。神代近づいてうれしいぞよ。日本は別として世界七つに分けるぞ、今に分りて来るから、静かに神の申すこと聞いて置いて下されよ。この道は初め苦しいが、だんだんよくなる仕組ぞ、わかりた臣民から御用つくりて呉れよ、御用はいくらでも、どんな臣民にでも、それぞれの御用あるから、心配なくつとめて呉れよ。
【現代語訳】
逆立ちして歩くことが、ずいぶん上手になったものだが、そんなことは長くは続かないぞ。頭が下で手で歩くのは苦しいだろう。上にある足も苦しいだろう。世の中が上下逆さまだと言ってきたが、この例えでよく分かるだろう。足はやはり下にある方が楽なのだ。頭が上でないと、景色が逆さまに見えて苦しく、逆さまなものばかりが映ってしまう。この道理が分かったか。岩戸を開くとは、本来あるべき元の姿に返すことだ。神の姿に返すことなのだ。中心となる三人の役員は別として、そのほかの役員の役目は、人間に例えれば手、足、目、鼻、口、耳などである。人体の構造を見て、役員はよく神の心を悟りなさい。物事を動かすには、人体のような有機的な組織でなければできないのだ。この道の役員は、誰かに任命されるのではなく、自らが悟り、自然となるものだ。それが神の心なのだ。人の心と行いが神の心に溶け合ったとき、それが神の国の本当の役員だ。この道理が分かったか。この道は神の道だから、神の心になればすぐに分かる。金や銀など要らない世の中になるのだ。御用をすることが嬉しくなったら、神の心に近づいた証拠だ。手は手の役目を果たせて嬉しいだろう。足は足の役目を果たせて嬉しいだろう。足はいつまでも足であり、手はいつまでも手なのだ。それが本当の姿だ。逆立ちして手が足の代わりをしていたから、その不自然さがよく分かったであろう。いよいよ世の終わりが来たから、役員は気を引き締めなさい。神の世が近づいて嬉しいことだ。日本は別格として、世界を七つに分けるぞ。やがて分かってくるから、静かに神の言うことを聞いておきなさい。この道は初めは苦しいが、だんだん良くなっていく仕組みだ。分かった者から御用を創り出してくれ。御用はいくらでもある。どんな人にでも、それぞれに合った御用があるから、心配なく務めてくれ。
【AIによる解釈】
この帖は「逆立ち」という強力な比喩を用いて、現代社会の価値観や秩序が根本的に転倒していることを指摘しています。物質が精神の上に立ち、手段が目的化し、本来の役割が歪められている状態です。「岩戸開き」とは、この逆転した状態を「元の姿」、すなわち魂が主で肉体は従、神が中心で人間がその一部、という本来の秩序に戻すことだと定義しています。そして、新しい組織のあり方を人体に例え、トップダウンの命令系統ではなく、各部分(役員)が自らの役割を自覚し、喜びをもって機能することで全体が有機的に動く「神の組織」の姿を示しています。役員は任命されるのではなく、自覚によって「おのづからなる」という点も重要です。世界の再編(世界七つに分ける)という大きなビジョンと共に、誰にでも役割があるという希望のメッセージで締めくくられています。
第十四帖 (五六)
【原文】
臣民ばかりでないぞ、神々様にも知らせなならんから、なかなか大層と申すのぞ。一二三(ひふみ)の仕組とは、永遠(とは)に動かぬ道のことぞ、三四五(みよいづ)の仕組とは、みよいづの仕組ぞ、御代出づとは神の御代になることぞ、この世を神の国にねり上げることぞ、神祀りたら三四五の御用にかかるから、その積りで用意して置いて呉れよ。この神は世界中の神と臣民と、けだものも草木もかまはねばならんのざから、御役いくらでもあるぞ。神様と臣民 同じ数だけあるぞ。それぞれに神つけるから、早う身魂みがいて呉れよ、みがけただけの神をつけて、天晴れ後の世に残る手柄立てさすぞ。小さいことはそれぞれの神にきいて呉れよ、一人ひとり、何でもききたいことは、病直すことも、それぞれの神がするから、サニワでお告うけて呉れよ、この方の家来の神が知らせるから何でもきけよ。病も直してやるぞ、その神たよりたなら、身魂みがけただけの神徳あるぞ。この世始まってない今度の岩戸開きざから、これからがいよいよぞ。飛んだところに飛んだこと出来るぞ。それはみな神がさしてあるのざから、よく気つけて居れば、さきの事もよく分かるようになるぞ。元の神代に返すと申すのは喩へでないぞ。七から八から九から十から神烈しくなるぞ、臣民の思う通りにはなるまいがな、それは逆立してゐるからぞ。世界一度にキの国にかかりて来るから、一時は潰れたやうに、もうかなはんと云ふところまでになるから、神はこの世に居らんと臣民申すところまで、むごいことになるから、外国が勝ちたやうに見える時が来たら、神の代近づいたのぞ、いよいよとなりて来ねば分らん様では御用出来んぞ。
【現代語訳】
(この知らせは)人々だけでなく、神々にも知らせなければならないから、なかなか大変なことなのだ。「ひふみの仕組」とは、永遠に変わることのない宇宙の法則のことだ。「みよいづの仕組」とは、新しい御代(みよ)が現れ出る(いづ)ための計画だ。「御代出づ」とは、神の世の中になること、この世を神の国に練り上げることだ。神を祀ったならば、この「みよいづの御用」に取り掛かることになるから、そのつもりで用意しておきなさい。この神は、世界中の神々と人々と、獣も草木も、すべてを世話しなければならないのだから、役目はいくらでもあるのだ。神と人とは同じ数だけいる。それぞれの人に、ふさわしい神をつけてやるから、早く魂を磨いてくれ。磨かれたレベルに応じた神をつけて、見事に後の世に残る手柄を立てさせてやるぞ。日常の小さなことは、各自についた神に聞きなさい。一人ひとり、何でも聞きたいこと、病気を治すことも、それぞれの守護の神がするから、審神者(さにわ)によってお告げを受けなさい。この神(ひつくの神)の家来の神が知らせるから、何でも聞きなさい。病気も治してやるぞ。その神を頼れば、魂が磨かれた分だけの神徳が与えられる。この世が始まって以来の、未曾有の岩戸開きであるから、これからがいよいよ本番だ。とんでもない所で、とんでもないことが起こるぞ。それは皆、神が起こしているのだから、よく気をつけていれば、先のことも分かるようになる。元の神代に返すというのは、比喩ではないのだ。七月、八月、九月、十月と、月を追うごとに神の働きは激しくなるぞ。人々の思う通りにはならないだろうが、それはあなた方が逆立ちしているからだ。世界中が一度に「キの国(日本)」に攻めかかってくるから、一時は日本が潰れたかのように、もう駄目だというところまで追いつめられる。人々が「神などこの世にはいない」と言うほど、むごいことになる。だから、外国が勝ったように見える時が来たら、それこそ神の世が近づいた印なのだ。いよいよという時が来なければ分からないようでは、御用はできないぞ。
【AIによる解釈】
この帖は、神示の計画の壮大さを改めて示しています。「ひふみ」が普遍の法則、「みよいづ」が具体的な実行計画を指します。特筆すべきは、一人ひとりに「守護の神」がつくという概念です。魂を磨くことで、より高いレベルの神霊の導き(神徳)を受けられるようになり、病気の治癒や未来の予知といった能力も開花すると説きます。これは、神が遠い存在ではなく、個人の内なる成長と共にあるパートナーであることを示しています。後半は、これから起こる大艱難の具体的な様相を預言しています。日本が世界中から攻められ、絶望的な状況に陥ることが示唆されています。しかし、それは「産みの苦しみ」であり、人間の価値観(逆立ち)が完全に崩壊し、人々が神の不在を嘆くほどの極限状態こそが、真の神の世が始まるための転換点(夜明け前)であるという、逆説的な真理を説いています。
第十五帖 (五七)
【原文】
この方祀りて神示(ふで)書かすのは一所なれど、いくらでも分け霊(みたま)するから、ひとりひとり祀りてサニワ作りてもよいぞ。祀る時は先づ鎮守様によくお願いしてから祀れよ、鎮守様は御苦労な神様ぞ、忘れてはならんぞ、この神には鳥居と注連(しめ)は要らんぞ。追ひ追ひ分かりて来るぞ、一二七七七七七わすれてはならんぞ、次の世の仕組であるぞ。身魂みがけば何事も分りて来ると申してあろがな、黙っていても分るやうに早うなって下されよ、神の国近づいたぞ。
【現代語訳】
この神を祀って神示を降ろさせる場所は一か所だが、いくらでも分霊するので、一人ひとりが(自宅などで)祀って審神者(さにわ)の場を作ってもよいぞ。祀る時は、まずその土地の鎮守様によくお願いしてから祀りなさい。鎮守様は大変な御苦労をされている神様だから、その存在を忘れてはならない。この神(ひつくの神)には、鳥居や注連縄は要らない。追々分かってくる。「一二七七七七七」という数字を忘れてはならない。これが次の世の仕組みの鍵であるぞ。魂を磨けば何事も分かってくると言ったであろう。黙っていても直感で分かるように、早くなってください。神の国は近づいたぞ。
【AIによる解釈】
この帖は、神との交信が特定の人や場所に限定されないことを示しています。「分け霊(わけみたま)」により、誰でも、どこでも、この神と繋がることが可能であると説いています。これは、信仰のあり方が中央集権的な組織から、個々人の内面へと移行することを示唆しています。ただし、その土地の神である「鎮守様」への敬意を忘れないようにと釘を刺しており、これは新しい教えが既存の神々や伝統を無視するものではなく、それらを尊重し、包括するものであることを示しています。「一二七七七七七」という謎の数字は、次の時代の構造を示す重要な数霊(かずたま)であるとされています。そして最終的には、神示を読んだり聞いたりしなくても、直感(黙っていても分かる)で神意を悟れるレベルまで魂を磨くことが目標であると示しています。
第十六帖 (五八)
【原文】
知恵でも学問でも、今度は金積んでも何うにもならんことになるから、さうなりたら神をたよるより他に手はなくなるから、さうなりてから助けて呉れと申しても間に合わんぞ、イシヤの仕組にかかりて、まだ目さめん臣民ばかり。日本精神と申して仏教の精神や基督教の精神ばかりぞ。今度は神があるか、ないかを、ハッキリと神力みせてイシヤも改心さすのぞ。神の国のお土に悪を渡らすことならんのであるが、悪の神わたりて来てゐるから、いつか悪の鬼ども上がるも知れんぞ。神の国ぞと口先ばかりで申してゐるが、心の内は幽界人(がいこくじん)沢山あるぞ。富士から流れ出た川には、それぞれ名前の附いてゐる石置いてあるから縁ある人は一つづつ拾ひて来いよ、お山まで行けぬ人は、その川で拾ふて来い、みたま入れて守りの石と致してやるぞ。これまでに申しても疑ふ臣民あるが、うその事なら、こんなに、くどうは申さんぞ。因縁の身魂には神から石与へて守護神の名つけてやるぞ。江戸が元のすすき原になる日近づいたぞ。てん四様を都に移さなならん時来たぞ。江戸には人住めん様な時が一度は来るのぞ。前のやうな世が来ると思うていたら大間違ひぞ。江戸の仕組すみたらカイの御用あるぞ。いまにさびしくなりて来るぞ。この道栄えて世界の臣民みなたづねて来るやうになるぞ。
【現代語訳】
今度の事態は、人間の知恵や学問、あるいは大金を積んでも、どうにもならないことになる。そうなってしまえば神に頼る以外に方法はなくなるが、そうなってから「助けてくれ」と言っても間に合わないのだ。「イシヤ(石屋)」の仕組に支配されて、まだ目が覚めない人々ばかりだ。(当時の)日本精神と言っても、その実は仏教やキリスト教の精神ばかりではないか。今度は、神が存在するのかしないのかをハッキリと神力で見せつけて、そのイシヤさえも改心させるのだ。本来、神の国である日本の土に悪を渡らせることはできないのだが、悪の神が渡って来ているから、いつ悪の鬼どもが上陸してくるか分からないぞ。「神の国だ」と口先ばかりで言っているが、心の中は外国人(=異質な価値観)で一杯の者がたくさんいる。富士から流れ出た川には、それぞれ名前のついた石を置いてあるから、縁のある人は一つずつ拾ってきなさい。富士山まで行けない人は、その川で拾ってきなさい。魂を入れて、お守りの石としてやろう。これまでこれほど言っても疑う人がいるが、嘘であるならば、こんなにくどくどとは言わない。因縁の深い魂には、神から直接石を与え、守護神の名をつけてやるぞ。江戸(東京)が元のすすき野原になる日が近づいた。天子様を都(岡本天明のいた場所、あるいは別の安全な場所)に移さなければならない時が来た。江戸には人が住めなくなるような時が一度は来るのだ。以前のような世の中がまた来ると思っていたら大間違いだ。江戸での計画が済んだら、次は甲斐(山梨)での御用がある。世の中はやがて寂しくなってくるぞ。しかし、この道は栄えて、世界中の人々が皆、訪ねてくるようになるのだ。
【AIによる解釈】
この帖は、既存の価値観(知恵、学問、金)が完全に無力化する時代の到来を告げ、準備のない者は手遅れになると警告しています。「イシヤの仕組」とは、一般にフリーメイソンなどを指すとされますが、ここでは唯物論的・物質主義的な世界支配構造の象徴と解釈できます。それに対して、絶対的な「神力」を見せつけることで、その構造自体を根底から変革すると宣言しています。また、当時の「日本精神」が、外来の思想に毒されていると鋭く批判し、真の神ながらの道に立ち返る必要性を説きます。東京(江戸)が壊滅的な打撃を受けるという具体的な預言は、物理的な破壊と、それに伴う価値観の崩壊を象 徴しています。その混乱の中、縁ある人々を守るための「守りの石」という具体的な救済策が示される一方で、最終的にはこの「道」が世界的な救いの中心地となるという希望も語られています。
第十七帖 (五九)
【原文】
学や知恵では外国にかなうまいがな、神たよれば神の力出るぞ、善いこと言へば善くなるし、わるきこと思へばわるくなる道理分らんか。今の臣民 口先ばかり、こんなことでは神の民とは申されんぞ。天明は神示書かす役ぞ。神の心取り次ぐ役ざが、慢心すると誰かれの別なく、代へ身魂使ふぞ。因縁のある身魂はこの神示(ふで)見れば心勇んで来るぞ。一人で七人づつ道伝へて呉れよ、その御用が先づ初めの御用ぞ。この神示通り伝へて呉れればよいのぞ、自分ごころで説くと間違ふぞ。神示通りに知らして呉れよ。我を張ってはならぬぞ、我がなくてもならぬぞ、この道六ヶしいなれど縁ある人は勇んで出来るぞ。
【現代語訳】
学問や人間の知恵では外国には敵わないだろう。しかし、神を頼れば神の力が出るのだ。善いことを言えば善くなるし、悪いことを思えば悪くなる、この道理が分からないのか。今の日本の民は口先ばかりだ。これでは神の民とは言えないぞ。天明(岡本天明)は神示を書き記す役目、神の心を取り次ぐ役目だが、慢心すれば誰であろうと関係なく、代わりの者を使うぞ。因縁のある魂は、この神示を見れば心が勇み立ってくるものだ。一人が七人ずつにこの道を伝えてくれ。それがまず最初の御用だ。この神示の通りに伝えてくれればよい。自分の考えを交えて説くと間違うぞ。神示に書かれている通りに知らせなさい。我を張ってはならない。しかし、我が全くなくてもいけない。この道は難しいが、縁のある人は勇んで行うことができるぞ。
【AIによる解釈】
この帖は、力の源泉を人間の知恵(学)から神の力(神力)へと転換すべきことを説いています。その根底にあるのが「言霊(ことだま)・思念(しねん)の法則」であり、発する言葉や心に抱く思いが現実を創造するという、宇宙の基本法則を改めて示しています。神示を降ろす岡本天明自身に対しても、慢心を厳しく戒めており、神の道具であるという立場を忘れてはならないと釘を刺します。そして、具体的な布教方法として「一人七人」というノルマが示されますが、重要なのはその内容です。自分の解釈を混ぜずに「神示通りに」伝えることが求められています。これは、神示の純粋性を保つためです。「我を張ってはならぬぞ、我がなくてもならぬぞ」という難解な教えが再び登場し、私欲を捨てつつも、神の御用を果たす主体性を持つという、高度な精神性が要求されていることを示しています。
第十八帖 (六〇)
【原文】
この道は神の道であり人の道であるぞ。この道の役員は神が命ずることもあるが、おのれが御用すれば、自然と役員となるのぞ、たれかれの別ないぞ、世界中の臣民みな信者ざから、臣民が人間ごころでは見当とれんのも無理ないなれど、この事よく腹に入れて置いてくれよ。神の土出るぞ、早く取りて用意して皆に分けてやれよ。神に心向ければ、いくらでも神徳与へて何事も楽にしてやるぞ。
【現代語訳】
この道は神の道であると同時に、人の道でもある。この道の役員は、神が直接命じることもあるが、自ら御用を行えば、自然に役員となるのだ。誰彼という区別はない。世界中の人々がみな信者なのだから。人々が人間の心では見当がつかないのも無理はないが、このことをよく心に刻んでおいてくれ。神の土が出るぞ。早く取って用意し、皆に分けてやりなさい。神に心を向ければ、いくらでも神の徳を与えて、何事も楽にしてやるぞ。
【AIによる解釈】
「神の道であり人の道」という言葉は、この教えが天上の理想論ではなく、地上で実践されるべき具体的な生き方であることを示しています。役員の資格が、任命ではなく「自覚と実践」にあることを再び強調し、誰にでもその門戸が開かれていることを示唆しています。これは、階級や組織に依らない、個人の主体性を重んじる新しい共同体のあり方です。また、第十六帖の「守りの石」に続き、ここでは「神の土」という具体的な救済アイテムが登場します。これらは、大峠を越えるための物理的な助けであると同時に、神の恵みを目に見える形で与えることで、人々の信仰を強めるための象徴的な意味も持っていると考えられます。最終的に、救いの鍵は「神に心を向ける」という個人の内なる姿勢にあることが示されています。
第十九帖 (六一)
【原文】
苦しくなりたら何時でもござれ、その場で楽にしてやるぞ、神に従へば楽になって逆らへば苦しむのぞ。生命も金も一旦天地へ引き上げ仕まうも知れんから、さうならんやうに心の洗濯第一ぞと申して、くどう気附けてゐることまだ分らんか。
【現代語訳】
苦しくなったら、いつでもこちらへ来なさい。その場で楽にしてやるぞ。神に従えば楽になり、逆らえば苦しむのだ。生命もお金も、一旦すべてを天と地へ引き上げてしまうかもしれないのだから、そうならないように「心の洗濯が第一だ」と、くどいほど注意していることがまだ分からないのか。
【AIによる解釈】
非常にシンプルかつ力強いメッセージを持つ一帖です。神は、苦しむ者をいつでも救う用意がある絶対的な拠り所であることを宣言しています。しかし、その救いは無条件ではなく、「神に従う」という選択にかかっています。神に従うとは、神の示す法則、すなわち利他や調和の道に従うことであり、それに逆らうこと、すなわち我欲や不調和の道を選ぶことが苦しみの原因であると説いています。「生命も金も一旦天地へ引き上げ」るという表現は、既存の価値観や所有の概念がすべてリセットされる「大峠」の厳しさを示唆しています。それを乗り越えるための唯一絶対の条件が「心の洗濯」、すなわち魂の浄化であることを、改めて強く警告しています。
第二十帖 (六二)
【原文】
上(うえ)、中(なか)、下(しも)の三段に身魂をより分けてあるから、神の世となりたら何事もきちりきちりと面白い様に出来て行くぞ。神の世とは神の心のままの世ぞ、今でも臣民 神ごころになりたら、何でも思ふ通りになるぞ。臣民 近慾(ちかよく)なから、心曇りてゐるから分らんのぞ。今度の戦は神力と学力のとどめの戦ぞ。神力が九分九厘まで負けた様になったときに、まことの神力出して、ぐれんと引繰り返して、神の世にして、日本のてんし様が世界まるめてしろしめす世と致して、天地神々様にお目にかけるぞ。てんし様の光が世界の隅々まで行きわたる仕組が三四五(みよいづ)の仕組ぞ、岩戸開きぞ。いくら学力強いと申しても百日の雨降らすこと出来まいがな。百日雨降ると何んなことになるか、臣民には分るまい、百日と申しても、神から云へば瞬きの間ぞ。
【現代語訳】
魂は、上・中・下の三つの段階により分けられているので、神の世になったら、何事も面白いように秩序正しく進んでいくぞ。神の世とは、神の心のままの世の中のことだ。今この瞬間でも、人々が神の心になったなら、何でも思う通りになるのだ。人々は目先の欲(近欲)のために心が曇っているから、その道理が分からないのだ。今度の戦は、「神力」と「学力(科学技術力・人間知)」との最後の戦いだ。神力が九分九厘まで負けたかのように見えた時に、本当の神力を発動させ、世の中をぐれんと引っ繰り返す。そして神の世とし、日本の天子様が全世界を治める世の中にして、天地の神々にお目に掛けるのだ。天子様の光が世界の隅々まで行き渡るようにする計画が「三四五(みよいづ)の仕組」であり、「岩戸開き」なのだ。いくら学力が強いといっても、百日間雨を降らせることはできないだろう。百日も雨が降ればどうなるか、人々には想像もつかないだろうが、神からすれば百日など瞬く間のことなのだ。
【AIによる解釈】
この帖は、来るべき神の世の秩序と、そこに至るまでの最終戦争の様相を描いています。人々の魂が「上・中・下」の三段階に選別されるという厳しい側面と、神の心になれば今すぐにでも理想は実現するという希望の両面が示されています。苦しみの原因は「近欲(目先の欲)」にあると断じ、霊的な視点の欠如を指摘します。最終戦争は、軍事力だけでなく、霊的な力(神力)と物質的な力・科学技術(学力)の対決であると定義しています。そして第九帖と同様に、神力側が見かけ上は絶体絶命に追い込まれた「九分九厘」の段階で、人知を超えた力による大どんでん返しが起こることが預言されています。その最終目的は、天子様(天皇)を中心とした霊的な世界秩序の確立です。自然をコントロールできない「学力」の限界を「百日の雨」という比喩で示し、神力の絶対的な優位性を強調しています。
第二十一帖 (六三)
【原文】
ばかりでもならぬ、ばかりでもならぬ。がまことの神の元の国の姿ぞ。元の神の国の臣民はでありたが、が神国に残りが外国で栄へて、どちらも片輪となったのぞ。もかたわもかたわ、とと合はせて まことの(かみ)の世に致すぞ。今の戦はととの戦ぞ、神の最後の仕組と申すのはに入れることぞ。も五ぞも五ぞ、どちらも、このままでは立ちて行かんのぞ。一厘の仕組とはに神の国のを入れることぞ、よく心にたたみておいて呉れよ。神は十柱五十九柱のからだ待ちてゐるぞ。五十と九柱のミタマの神々様お待ちかねであるから、早うまゐりて呉れよ。今度の御役大層であるが、末代残る結構な御役であるぞ。
【現代語訳】
(おそらく、霊(ひ)=霊主体)ばかりでもいけない。(おそらく、体(から)=体主霊従)ばかりでもいけない。(霊体一致)が、まことの神の国の元の姿なのだ。元の神の国の民は(霊体一致)であったが、(霊主体)が神の国に残り、(体主霊従)が外国で栄えて、どちらも片輪(不完全)になってしまったのだ。(霊)も片輪、(体)も片輪。(霊)と(体)を合わせて、まことの「神」の世にするのだ。今の戦は、(霊)と(体)の戦いだ。神の最後の計画とは、(体)の中に(霊)を入れることなのだ。(霊)も五、(体)も五(=五十音、言霊の象徴か)。どちらも、このままでは成り立っていかない。一厘の仕組とは、(体)に神の国の(霊)を入れることだ。よく心に刻んでおきなさい。神は、十柱と五十九柱の、神の器となる身体(からだ)を待っている。五十九柱の御魂を持つ神々様(=人々)がお待ちかねであるから、早く(神の許へ)参ってくれ。今度の役目は大変なものだが、末代まで残る素晴らしい役目なのだぞ。
【AIによる解釈】
この帖は、伏せ字が多く難解ですが、世界の根本的な分裂の構造とその統合について説いていると解釈できます。伏せ字は、精神(霊・ヒ)と物質(体・カラ)の対立を象徴していると考えられます。日本(神国)は精神性を重んじる(霊主体)文化の源流となり、外国は物質文明(体主霊従)を発展させ、その結果どちらも「片輪」、つまり不完全な状態に陥ったと診断しています。現代のあらゆる対立の根源は、この霊と体の分離にあるというのです。そして「神の最後の仕組」とは、物質(体)に本来あるべき精神(霊)を吹き込み、「霊体一致」の完全な状態に戻すことであると宣言します。「一厘の仕組」の核心が、この霊と体の統合にあることが示唆されています。最後に、その計画の担い手となる「五十九柱のミタマ」を再び呼びかけており、この霊的統合を実践する人々の出現が急務であることを伝えています。
第二十二帖 (六四)
【原文】
岩戸開く仕組 知らしてやりたいなれど、この仕組、言ふてはならず、言はねば臣民には分らんし、神苦しいぞ、早う神心になりて呉れと申すのぞ、身魂の洗濯いそぐのぞ。二三三二二(アイカギ)、、コノカギハイシヤトシカテニギルコトゾ。
【現代語訳】
岩戸を開く計画を知らせてやりたいのだが、この計画は、言ってはならず、しかし言わなければ人々には分からない。神も苦しい立場なのだ。だからこそ、早く神の心になってくれと申しているのだ。魂の洗濯を急いでくれ。「二三三二二(アイカギ)」、この鍵は「イシヤ(石屋)」としっかり手を握ることだ。
【AIによる解釈】
この帖は、計画の機密性と、それを悟ることの難しさ、そして神の焦燥感を吐露しています。言葉で伝えられない天機(てんき)であるため、人々が自ら「神心」になり、直感で悟る以外に道はないと繰り返し訴えています。魂の浄化(身魂の洗濯)がその前提条件です。そして、非常に衝撃的な一文が記されます。「二三三二二(アイカギ)」という暗号の鍵は、「イシヤとしっかり手を握ること」だと。これは、これまで敵対的な勢力として描かれてきた「イシヤ(物質主義文明の象徴)」を、単に滅ぼすのではなく、最終的には和合し、手を取り合うことが「岩戸開き」の鍵である、という驚くべき逆説を示唆しています。これは、悪をも抱き参らせて大調和に至るという、ひふみ神示の根底に流れる「丸く治める」思想の究極的な現れと言えるでしょう。
第二十三帖 (六五)
【原文】
世が引繰り返って元の神世に返るといふことは、神々様には分って居れど、世界ところどころにその事知らし告げる神柱あるなれど、最後のことは 九(こ)の神でないと分らんぞ。この方は天地をキレイに掃除して天の大神様にお目にかけねば済まぬ御役であるから、神の国の臣民は神の申す様にして、天地を掃除して てんし様に奉らなならん御役ぞ。江戸に神早う祀りて呉れよ、仕組通りにさすのであるから、臣民 我を去りて呉れよ。この方祀るのは天(あめ)のひつくの家ぞ、祀りて秋立ちたら、神いよいよ烈しく、臣民の性来(しょうらい)によって、臣民の中に神と獣とハッキリ区別せねばならんことになりて来たぞ、神急けるぞ。
【現代語訳】
世の中がひっくり返って元の神の世に戻るということは、多くの神々には分かっている。世界の所々にそのことを知らせる神柱(中心的な神や人)がいるが、最後の仕上げについては、この神(ひつくの神)でなければ分からないのだ。この神は、天地を綺麗に掃除して、天の大神様にお目にかけるという、やり遂げねばならない役目を持っている。だから、神の国(日本)の民は、神の言う通りにして、天地の掃除を手伝い、天子様に奉らなければならない役目なのだ。江戸に早く神を祀ってくれ。計画通りに進めるのだから、人々は我(が)を捨ててくれ。この神を祀るのは「天のひつくの家」である。祀って立秋を迎えたら、神の働きはいよいよ激しくなり、人々の生まれ持った性質によって、その心の内にある「神」と「獣」をハッキリと区別しなければならない時が来た。神は急いでいるぞ。
【AIによる解釈】
この計画の最終的な采配は、国常立尊(と推定される)「ひつくの神」が握っているという、その中心性が強調されています。そして、来るべき変革は「天地の掃除」と表現され、その実行者として日本の民が指名されています。これは、日本民族に与えられた霊的な役割(ミッション)を示唆しています。「我を去りて呉れよ」という命令は、この大事業が個人の思惑や利益を超えたものであることを示し、完全な自己滅却を求めています。「秋立ちたら」という時期的な予告と共に、「神と獣とハッキリ区別」するという厳しい選別が始まることが告げられています。この選別は、外的な属性(国籍、身分など)によるものではなく、個々人の内面、魂のあり方(性来)によって行われることを示唆しており、いよいよ正念場が近づいているという緊張感に満ちています。
第二十四帖 (六六)
【原文】
一が十にと申してありたが、一が百に、一が千に、一が万になるとき いよいよ近づいたぞ。秋立ちたらスクリと厳しきことになるから、神の申すこと一分一厘ちがはんぞ。改心と申すのは、何もかも神にお返しすることぞ、臣民のものといふもの何一つもあるまいがな、草の葉一枚でも神のものぞ。
【現代語訳】
一が十になると言っておいたが、その一が百に、千に、万にと爆発的に増える時がいよいよ近づいたぞ。立秋を過ぎたら、事態は厳しく、はっきりとしたものになるから、神の言うことは一分一厘も違わないぞ。「改心」するというのは、何もかもすべてを神にお返しすることだ。そもそも、人間のものなどというものは何一つないではないか。草の葉一枚でさえ、神のものなのだぞ。
【AIによる解釈】
「一が十に、百に、千に、万に」という表現は、二つの意味に取れます。一つは、この教えが幾何級数的に急速に広まっていくこと。もう一つは、一つの出来事が引き金となって、その影響が瞬く間に全世界に波及していく様相です。事態の展開が、これまでの比ではない速度で進むことを予告しています。「立秋」を境に、曖昧だった状況が「スクリと厳しきこと」になる、つまり、神の計画が目に見える形で顕現し、もはや後戻りできない段階に入ることを示しています。そして、「改心」の究極的な定義が示されます。それは、自分の所有物、才能、さらには生命さえも、すべては神からの借り物であると悟り、その所有権を完全に神に「お返しする」という意識の変革です。この絶対的な帰依の境地に至ることが、新しい時代を生きるための必須条件であると説いています。
第二十五帖 (六七)
【原文】
今度の戦で何もかも埒ついて仕まふ様に思うてゐるが、それが大きな取違ひぞ、なかなかそんなチョロッコイことではないぞ、今度の戦で埒つく位なら、臣民でも致すぞ。今に戦も出来ない、動くことも引くことも、進むことも何うすることも出来んことになりて、臣民は神がこの世にないものといふ様になるぞ、それからが、いよいよ正念場ぞ、まことの神の民と獣とをハッキリするのはそれからぞ。戦出来る間はまだ神の申すこときかんぞ、戦出来ぬ様になりて、始めて分かるのぞ、神の申すこと、ちっとも違はんぞ、間違ひのことなら、こんなにくどうは申さんぞ。神は気(け)もない時から知らしてあるから、いつ岩戸が開けるかと云ふことも、この神示(ふで)よく読めば分かる様にしてあるのぞ、改心が第一ぞ。
【現代語訳】
(当時の)第二次世界大戦で、何もかも決着がつくように思っているだろうが、それは大きな勘違いだ。なかなか、そんな単純なことではない。この戦争で決着がつくくらいなら、人間にもできることだ。やがて、戦争をすることさえできなくなり、動くことも引くことも進むことも、何もできない手詰まり状態になる。そして人々は「神などこの世にはいない」と言うようになるだろう。そこからがいよいよ正念場だ。まことの神の民と、獣のような人間とをハッキリと区別するのは、その時からなのだ。戦争ができる間は、まだ人々は神の言うことを聞かない。戦争すらできない状況になって、初めて神の言うことが分かるのだ。神の言うことは、少しも違わない。間違ったことなら、こんなにくどくどとは言わない。神は、その兆候すらない時から知らせてあるのだから、いつ岩戸が開けるかということも、この神示をよく読めば分かるようにしてあるのだ。改心が第一である。
【AIによる解釈】
この帖は、人々が目の前の戦争(第二次世界大戦)の終結を最終的な解決だと考えていることに対し、それは序章に過ぎないと警告しています。真のクライマックスは、戦争すらできない、経済も政治も完全に麻痺した「手詰まり状態」の後に来ると預言しています。この完全な行き詰まりと、それに伴う絶望(神はいない)こそが、人々を既存の価値観から解放し、真理に目覚めさせるための最終的なプロセスなのです。この極限状況において、人間の内面が剥き出しになり、魂のあり方によって「神の民」と「獣」とが明確に分かれる(選別される)とされています。この神示の中に、未来の全てのタイムラインが記されているとも示唆しており、それを読み解く鍵は、やはり「改心」という個人の意識変革にあると結論づけています。
第二十六帖 (六八)
【原文】
神の国を真中にして世界分けると申してあるが、神祀るのと同じやり方ぞ。天(あめ)のひつくの家とは天のひつくの臣民の家ぞ。天のひつくと申すのは天の益人のことぞ、江戸の富士と申すのは、ひつくの家の中に富士の形作りて、その上に宮作りてもよいのぞ、仮でよいのぞ。こんなに別辞(ことわけ)てはこの後は申さんぞ。小さい事はサニワで家来の神々様から知らすのであるから、その事忘れるなよ。仏(ぶつ)も耶蘇(やそ)も、世界中まるめるのぞ。喧嘩して大き声する所にはこの方鎮まらんぞ、この事忘れるなよ。
【現代語訳】
神の国(日本)を中心にして世界を(地域ごとに)分けると言ったが、それは神を祀る作法と同じやり方なのだ。「天のひつくの家」とは、「天のひつくの民」の家のことだ。「天のひつく」とは、天の益人(ますひと、神に選ばれ、人々を益する者)のことである。「江戸の富士」というのは、「ひつくの家」の中に富士山の形(盛り土など)を作り、その上に社を建てても良い、という意味だ。仮のもので構わない。こんなに言葉を尽くして丁寧に説明するのは、これ以降はしないぞ。日常の細かいことは、審神者(さにわ)によって、私の家来の神々から知らせるから、そのことを忘れるな。仏教もキリスト教も、世界中のすべてを丸く包み込んで一つにするのだ。喧嘩して大声を出しているような不調和な場所には、この神は鎮座しない。このことを忘れるな。
【AIによる解釈】
この帖は、世界の再編成の原理と、具体的な祭祀の方法について補足しています。「神祀るのと同じやり方」とは、中心(ご神体)を定め、その周りに然るべき配置(ヒモロギなど)を行うように、日本を中心として世界の各地域が有機的に連携する構造を意味していると考えられます。また、「天のひつくの民」という新しい概念が登場します。これは、血筋や国籍によらず、神の御用を担う霊的に目覚めた人々を指す言葉でしょう。「江戸の富士」の作り方についての具体的な指示は、壮大な神殿ではなく、心と形が伴っていれば仮のものでも機能することを示しています。そして、この神の計画が特定の宗教を排除するものではなく、仏教やキリスト教を含むあらゆる教えを「まるめて」統合する、包括的なものであることが宣言されています。最後に、神が鎮まる条件として「調和」が挙げられ、争いや不和のある場所には神の臨在はないと釘を刺しています。
第二十七帖 (六九)
【原文】
この方は祓戸(はらへど)の神とも現はれるぞ。この方祀るのは富士に三と所、海に三と所、江戸にも三と所ぞ、奥山、中山、一の宮ぞ。富士は、榛名(はるな)に祀りて呉れて御苦労でありたが、これは中山ぞ、一の宮と奥の山にまた祀らねばならんぞ、海の仕組も急ぐなれどカイの仕組早うさせるぞ。江戸にも三と所、天明の住んでゐるところ奥山ぞ。あめのひつくの家、中山ぞ、此処が一の宮ざから気つけて置くぞ。この方祀るのは、真中に神の石鎮め、そのあとにひもろぎ、前の右左にひもろぎ、それが「あ」と「や」と「わ」ぞ、そのあとに三つ七五三とひもろ木立てさすぞ。少しはなれて四隅にイウエオの言霊石 置いて呉れよ。鳥居も注連(しめ)もいらぬと申してあろがな、このことぞ。この方祀るのも、役員の仕事も、この世の組立も、みな七七七七と申してきかしてあるのには気がまだつかんのか、臣民の家に祀るのは神の石だけでよいぞ、天のひつくの家には、どこでも前に言ふ様にして祀りて呉れよ。江戸の奥山には八日、秋立つ日に祀りて呉れよ、中山九日、一の宮には十日に祀りて呉れよ。気つけてあるのに神の神示(ふで)よまぬから分らんのぞ、このこと、よく読めば分るぞ。今の様なことでは神の御用つとまらんぞ、正直だけでは神の御用つとまらんぞ。裏と表とあると申して気つけてあろがな、シッカリ神示読んで、スキリと腹に入れて呉れよ、よむたび毎に神が気つける様に声出してよめば、よむだけお蔭あるのぞ。
【現代語訳】
この神は、祓戸(はらえど)の神、つまり罪穢れを祓い清める神としても現れるぞ。この神を祀る場所は、富士に三か所、海に三か所、江戸にも三か所である。それぞれ、奥山、中山、一の宮という位置づけがある。富士(の計画)については、榛名山に祀ってくれてご苦労であったが、あれは中山にあたる。一の宮と奥の宮にもまた祀らなければならない。海の計画も急がねばならないが、甲斐(かい)の計画を早く進めさせるぞ。江戸にも三か所あり、天明が住んでいる所が奥山だ。「天のひつくの家」が中山であり、ここが一の宮となるから、気をつけておけ。この神を祀るには、真ん中に神の石を鎮座させ、その後ろに神籬(ひもろぎ)を一つ、その前の右と左に一つずつ神籬を立てる。それが「ア」「ヤ」「ワ」の言霊を象徴する。その後ろに、三本、五本、七本と神籬を立てさせるのだ。少し離れた四隅に「イ」「ウ」「エ」「オ」の言霊を込めた石を置きなさい。鳥居も注連縄も要らないと言ったであろう、こういうことだ。この神を祀ることも、役員の仕事も、この世の組み立ても、皆「七七七七(しちしちしちしち)」という仕組みでできていると聞かせているのに、まだ気づかないのか。一般の人の家に祀るのは、神の石だけで良い。「天のひつくの家」には、どこでも今言った様式で祀ってくれ。江戸の奥山には八日(立秋の日)に祀りなさい。中山には九日、一の宮には十日に祀りなさい。注意してあるのに、神示を読まないから分からないのだ。このことは、よく読めば分かるはずだ。今のような状態では神の御用は務まらない。ただ正直なだけではダメなのだ。物事には裏と表があると言って注意したであろう。しっかりと神示を読み、すっきりと腑に落としてくれ。読むたびに神が気づきを与えるから、声に出して読めば、読んだだけご利益があるのだ。
【AIによる解釈】
非常に具体的かつ象徴的な祭祀の指示が与えられている帖です。まず、この神が「祓戸の神」としての側面を持つことが明かされ、その働きが世界の浄化であることを示唆しています。富士、海、江戸にそれぞれ三つずつ拠点を設けるという計画は、地上世界に神のエネルギーグリッドを構築するかのようです。そして、祭壇の作り方が詳細に述べられます。中心の石、ア・ヤ・ワ、イ・ウ・エ・オの言霊の配置、三・五・七の数、これらは宇宙の創造原理(言霊、数霊)を地上に再現する「型」であり、神を降ろすための装置と言えます。「正直だけではダメ」「裏と表」という言葉は、単純な善悪二元論を超え、物事の多角的・立体的な理解力が必要であることを示しています。清濁併せ呑むような、より高い次元での判断力が求められているのです。神示を繰り返し声に出して読むことが、その理解を深める鍵であるとされています。
第二十八帖 (七〇)
【原文】
またたきの間に天地引繰り返る様な大騒動が出来るから、くどう気つけてゐるのざ、さあといふ時になりてからでは間に合はんぞ、用意なされよ。戦の手伝ひ位なら、どんな神でも出来るのざが、この世の大洗濯は、われよしの神ではよう出来んぞ。この方は元のままの身体(からだ)持ちてゐるのざから、いざとなれば何んなことでもして見せるぞ。仮名ばかりの神示と申して馬鹿にする臣民も出て来るが、仕まひにはその仮名に頭下げて来ねばならんぞ、かなとは(カミ)の七(ナ)ぞ、神の言葉ぞ。今の上の臣民、自分で世の中のことやりてゐるように思うているが、みな神がばかして使ってゐるのに気づかんか、気の毒なお役も出て来るから、早う改心して呉れよ。年寄や女や盲、聾ばかりになりても、まだ戦やめず、神の国の人だねの無くなるところまで、やりぬく悪の仕組もう見て居れんから、神はいよいよ奥の手出すから、奥の手出したら、今の臣民ではようこたえんから、身魂くもりてゐるから、それでは虻蜂取らずざから、早う改心せよと申してゐるのぞ、このことよく心得て下されよ、神せけるぞ。
【現代語訳】
瞬く間に天地がひっくり返るような大騒動が起こるから、くどいほど注意しているのだ。さあ、いざという時になってからでは間に合わないぞ、用意をしなさい。単なる戦争の手伝いくらいなら、どんな神でもできる。しかし、この世の大洗濯は、我よし(自己中心的)な神には到底できないのだ。この神は、根源のままの身体(実体)を持っているのだから、いざとなればどんなことでもして見せるぞ。仮名ばかりの神示だと馬鹿にする者も出てくるが、最後にはその仮名に頭を下げに来なければならなくなるのだ。「かな」とは、「カ(神)のナ(名、言)」であり、神の言葉そのものなのだ。今の指導者層は、自分たちで世の中を動かしていると思っているが、皆、神が彼らを(良い意味で)騙して使っていることに気づかないのか。気の毒な役回りをさせられる者も出てくるから、早く改心してくれ。年寄りや女、目や耳の不自由な者ばかりになっても、まだ戦争をやめず、神の国(日本)の民の種が絶えるところまでやり抜こうとする悪の計画は、もう見ていられない。だから、神はいよいよ奥の手を出す。その奥の手を出したら、今の日本の民では到底耐えられないだろう。魂が曇っているからだ。それでは虻(あぶ)も蜂(はち)も取れず、元も子もなくなるから、早く改心せよと言っているのだ。このことをよく心得なさい。神は急いでいるのだ。
【AIによる解釈】
これから起こる変革が、瞬きする間のような、超常的な速さと規模であることを警告しています。この「大洗濯」は、単なる善悪の戦いではなく、我よし(エゴ)を超越した根源神でなければ成し遂げられない大事業であるとされています。神示が「仮名」で書かれていることを馬鹿にする者への警告は、「かな(仮名)」が「神名(カミのな)」であり、その音(言霊)にこそ神聖な力が宿っていることを示唆しています。また、世界の指導者たちが自らの意志で動いているように見えて、実は大きな神の計画の駒として動かされているという、マクロな視点が示されています。そして、このままでは日本民族が壊滅しかねないという危機的状況に対し、神が「奥の手」を出すことを予告しています。しかし、その神の力はあまりにも強大であるため、魂が曇ったままの民衆には耐えられない諸刃の剣でもあるのです。だからこそ、その前に「改心」するよう、切迫感をもって訴えています。
第二十九帖 (七一)
【原文】
神の土出ると申してありたが、土は五色の土ぞ、それぞれに国々、ところどころから出るのぞ。白、赤、黄、青、黒の五つ色ぞ、薬のお土もあれば喰べられるお土もあるぞ、神に供へてから頂くのぞ、何事も神からぞ。
【現代語訳】
神の土が出ると言っておいたが、その土は五色の土だ。それぞれ、国々、様々な場所から出てくる。白、赤、黄、青、黒の五色である。薬になる土もあれば、食べられる土もある。神にお供えしてから頂くのだ。何事も、まず神に捧げるところから始まるのだ。
【AIによる解釈】
第十八帖の「神の土」について、より具体的な情報が与えられています。その土が「五色」であることは、古代中国の五行思想(木火土金水)や、五大陸・五人種など、世界のすべてを包括する象徴的な意味合いを持っていると考えられます。薬になったり、食用になったりするという記述は、大峠の後の食糧難や医療崩壊の際に、人々を救うための具体的な手段となる可能性を示唆しています。超自然的な力を持つ「マナ」のような存在かもしれません。「神に供へてから頂く」という作法は、物質的な恩恵であっても、その源泉が神にあることを忘れず、感謝の心を持つことの重要性を教えています。
第三十帖 (七二)
【原文】
八のつく日に気つけて呉れよ、だんだん近づいたから、辛酉(かのととり)はよき日、よき年ぞ。冬に桜咲いたら気つけて呉れよ。
【現代語訳】
八のつく日には注意しなさい。だんだん時が近づいたからだ。辛酉(かのととり)は良い日であり、良い年となるぞ。冬に桜が咲いたら、注意しなさい。
【AIによる解釈】
この帖は、来るべき重要な出来事の時期を示す、暗号めいた預言です。「八のつく日」は、8日、18日、28日、あるいは8月など、複数の解釈が可能です。「辛酉(しんゆう、かのととり)」は、干支(えと)の一つで、60日に一度、60年に一度巡ってきます。「辛酉革命」という言葉があるように、古来、変革の年とされてきました。神示が書かれた昭和19年(1944年)以降で最も近い辛酉の年は、1981年(昭和56年)や、その次の2041年などが該当します。「冬に桜が咲いたら」というのは、異常気象や天変地異の象徴であり、常識が覆るような異常事態が起こる前触れとして注意を促しています。これらの断片的な情報を組み合わせ、時を見極めるよう読者に問いかけています。
第三十一帖 (七三)
【原文】
この神に供へられたものは、何によらん私することならんぞ、まゐりた臣民にそれぞれ分けて喜ばして呉れよ、臣民喜べば神も喜ぶぞ、神喜べば天地光りて来るぞ、天地光れば富士(二二)晴れるぞ、富士は晴れたり日本晴れとはこの事ぞ。このやうな仕組でこの道ひろめて呉れよ、それが政治ぞ、経済ぞ、真通理(マツリ)ぞ、分りたか。
【現代語訳】
この神にお供えされたものは、何であっても私物化してはならない。参拝に来た人々に、それぞれ分け与えて喜ばせてあげなさい。人々が喜べば、神も喜ぶ。神が喜べば、天地が光り輝き始める。天地が光れば、富士(不死・不二)が晴れ渡るのだ。「富士は晴れたり日本晴れ」とは、このことなのだ。このような仕組みで、この道を広めていきなさい。それこそが、本当の政治であり、経済であり、真の祭(真理に通じる道理=マツリ)なのだ。分かったか。
【AIによる解釈】
この帖は、新しい時代の経済と政治の根本原理を明確に示しています。それは「分かち合い」と「循環」です。神に捧げられたもの(富や才能の象徴)を独占せず、人々と分かち合う。人々の喜びが神の喜びとなり、その神の喜びが天地を光らせ、さらなる豊かさを生むという、ポジティブな循環の法則です。この循環の極致が、「富士は晴れたり日本晴れ」という理想世界の実現なのです。「マツリ(祭)」の語源が「政(まつりごと)」と同じであることを示し、本来、政治も経済も、神と人が共に喜び、天地の豊かさを循環させるための神聖な営みであったと説いています。これは、現代の所有と分配を巡る対立を超えた、新しい社会システムのヴィジョンと言えるでしょう。
三十二帖 (七四)
【原文】
この道ひろめて金儲けしようとする臣民 沢山に出て来るから、役員気つけて呉れよ、役員の中にも出て来るぞ、金(かね)は要らぬのざぞ、金いるのは今しばらくぞ、生命は国にささげても金は自分のものと頑張ってゐる臣民、気の毒出来るぞ、何もかも天地へ引き上げぞと知らしてあること近づいて来たぞ、金かたきの世来たぞ。
【現代語訳】
この道を広めることを利用して金儲けをしようとする者が、たくさん出てくるから、役員は注意しなさい。役員の中からも出てくるぞ。お金は(本来)要らないものなのだ。お金が必要なのは、今の世が続く、もうしばらくの間だけだ。命は国に捧げても、金だけは自分のものだと固執している人々は、気の毒なことになるぞ。「何もかも一旦、天地へ引き上げる」と知らせておいた時が近づいてきた。金が仇(かたき)となる世が来たのだ。
【【AIによる解釈】
この教えが広まるにつれて、それを悪用する者が現れることを、厳しく警告しています。特に、金銭的な利益を求めることを繰り返し戒めています。「金いるのは今しばらくぞ」という言葉は、現在の貨幣経済システムが、やがて崩壊、あるいは全く新しい価値体系に取って代わられることを示唆しています。「金かたきの世」とは、文字通り、金を持っていることがかえって災いを招く時代が来るということです。これは、ハイパーインフレーション、財産税、あるいは略奪の対象になるなど、様々な形で起こり得ます。第十九帖の「生命も金も一旦天地へ引き上げ」という言葉を再度引用し、所有という概念そのものがリセットされる時が迫っていることを、強く警告しています。
第三十三帖 (七五)
【原文】
親となり子となり夫婦となり、兄弟(はらから)となりて、生きかわり死にかわりして御用に使ってゐるのぞ、臣民同士、世界の民、みな同胞(はらから)と申すのは喩へでないぞ、血がつながりてゐるまことの同胞ぞ、はらから喧嘩も時によりけりぞ、あまり分らぬと神も堪忍袋の緒切れるぞ、何んな事あるか知れんぞ、この道の信者は神が引き寄せると申せば役員ふところ手で居るが、そんなことでこの道開けると思ふか。一人が七人の人に知らせ、その七人が済んだら、次の御用にかからすぞ、一聞いたら十知る人でないと、この御用つとまらんぞ、うらおもて、よく気つけよ、因縁の身魂はどんなに苦しくとも勇んで出来る世の元からのお道ぞ。七人に知らしたら役員ぞ、神が命ずるのでない、自分から役員になるのぞと申してあろがな、役員は神のぢきぢきの使ひぞ、神柱ぞ。肉体男なら魂(たま)は女(おみな)ぞ、この道 十(と)りに来る悪魔あるから気つけ置くぞ。
【現代語訳】
(あなた方は)親となり、子となり、夫婦となり、兄弟となって、何度も生まれ変わり死に変わりしながら、神の御用に使われているのだ。人々同士、いや世界中の民が皆「同胞(はらから)」だというのは、比喩ではない。霊的な血が繋がっている、まことの同胞なのだ。兄弟喧嘩も時と場合による。あまりに物分りが悪いと、神も堪忍袋の緒が切れるぞ。何が起こるか分からないぞ。この道の信者は神が引き寄せると言ったからといって、役員が何もしないで腕を組んでいてよいのか。そんなことでこの道が開けると思うのか。一人が七人の人に知らせ、その七人に伝え終わったら、次の御用に取り掛からせる。一つ聞いたら十を悟るような人でなければ、この御用は務まらない。裏と表をよく見極めなさい。因縁のある魂は、どんなに苦しくても勇んでできる、世の始まりからの道なのだ。七人に知らせた者は、その時点でもう役員なのだ。神が任命するのではない、自分から役員になるのだと言ったであろう。役員は神の直々の使いであり、神柱なのだ。肉体が男なら、その魂は女(=受容性を持つ)としての性質を持っている。この道を乗っ取りに来る悪魔がいるから、気をつけておきなさい。
【AIによる解釈】
この帖は、輪廻転生を前提として、全人類が霊的に繋がった「まことの同胞」であるという壮大な真理を説いています。国家や民族間の争いは、本質的には兄弟喧嘩であり、その愚かさを指摘しています。そして、役員の役割について、再び主体性を強調します。神が人を用意してくれるのを待つのではなく、自ら行動(一人七人に知らせる)を起こすことが求められています。その行動を起こした者こそが、自覚ある「役員」なのです。「一聞いたら十知る」というのは、言葉の裏にある本質を直感的に悟る能力です。「肉体男なら魂は女」という一節は、陰陽のバランスの重要性を示唆します。行動力(陽・男)を持つ者は、同時に神意を受け入れる受容性(陰・女)を兼ね備える必要があるということです。最後に「道を乗っ取りに来る悪魔」への警告があり、この教えが純粋さを失い、悪用される危険性が常にあることを示唆しています。
第三十四帖 (七六)
【原文】
臣民はすぐにも戦すみてよき世が来る様に思うてゐるが、なかなかさうはならんぞ、臣民に神うつりてせねばならんのざから、まことの世の元からの臣民 幾人もないぞ、みな曇りてゐるから、これでは悪の神ばかりかかりて、だんだん悪の世になるばかりぞ、それで戦すむと思うてゐるのか、自分の心よく見てござれ、よく分るであろがな、戦すんでもすぐによき世とはならんぞ、それからが大切ぞ、胸突き八丁はそれからぞ、富士に登るのにも、雲の上からが苦しいであろがな、戦は雲のかかってゐるところぞ、頂上(いただき)までの正味のところはそれからぞ。一、二、三年が正念場ぞ。三四五(みよいづ)の仕組と申してあろがな。
【現代語訳】
人々は、すぐにでも戦争が終わって良い世が来るように思っているが、なかなかそうはならない。人々の中に神が宿り、神人一体となって事を進めなければならないからだ。(しかし現状では)真の、世の元からの民と言える者はほとんどいない。皆、魂が曇っている。これでは悪の神ばかりが憑依して、ますます悪い世の中になるばかりだ。それで戦争が終わると思っているのか。自分の心をよく見てみなさい。そうすればよく分かるだろう。戦争が終わっても、すぐに良い世の中にはならない。そこからが大切であり、本当の正念場(胸突き八丁)は、その後に来るのだ。富士山に登るのにも、雲の上に出てからが本当に苦しいだろう。今の戦争は、まだ雲がかかっている中腹あたりなのだ。頂上までの最後の道のりは、これからなのだ。一、二、三年が正念場だ。「三四五(みよいづ)の仕組」と言ってあるだろう。
【AIによる解釈】
この帖は、戦争の終結がゴールではなく、むしろ本当の試練の始まりである、という厳しい現実を突きつけています。富士登山の比喩が非常に効果的です。戦争という目に見える混乱は、まだ視界の悪い「雲の中」に過ぎず、本当の苦難は、戦争が終わり、一見平和になったように見える「雲の上」から始まると言います。これは、物理的な破壊の後の、精神的な荒廃、価値観の崩壊、経済的な大混乱などを指していると考えられます。この「胸突き八丁」の期間を乗り越える鍵は、個々人が内なる神性を発現させる「神うつり」にかかっています。そして、「一、二、三年が正念場」「三四五の仕組」という言葉は、戦後の数年間が、新しい御代(みよ)が生まれるかどうかの決定的な期間になることを示唆しています。
第三十五帖 (七七)
【原文】
何もかも持ちつ持たれつであるぞ、臣民喜べば神も喜ぶぞ、金(きん)では世は治まらんと申してあるのに まだ金追うてゐる見苦しい臣民ばかり、金は世をつぶす本ぞ、臣民、世界の草木まで喜ぶやり方はの光のやり方ぞ。臣民の生命も長うなるぞ、てんし様は生き通しになるぞ、御玉体(おからだ)のままに神界に入られ、またこの世に出られる様になるぞ、死のないてんし様になるのぞ、それには今のやうな臣民のやり方ではならんぞ、今のやり方ではてんし様に罪ばかりお着せしてゐるのざから、この位 不忠なことないぞ、それでもてんし様はおゆるしになり、位までつけて下さるのぞ、このことよく改心して、一時(ひととき)も早く忠義の臣民となりて呉れよ。
【現代語訳】
何もかも、持ちつ持たれつの関係なのだ。人々が喜べば神も喜ぶ。金銭では世は治まらないと言ってあるのに、まだ金ばかり追いかけている見苦しい人々ばかりだ。金こそが世を潰す元凶なのだ。人々、いや世界の草木に至るまで、すべての存在が喜ぶやり方こそが、(おそらく「ひ」=霊)の光のやり方なのだ。人々の寿命も長くなる。天子様は生き通しになられる。そのお身体のまま神界に入られ、またこの世にお出ましになる、不死の天子様になられるのだ。そのためには、今のような人々のやり方ではいけない。今のやり方では、天子様に罪ばかりを着せていることになる。これほど不忠なことはない。それでも天子様はお許しになり、位まで授けてくださるのだ。このことをよく理解して改心し、一刻も早く真の忠義の民となってくれ。
【AIによる解釈】
この帖は、「持ちつ持たれつ」という相互依存の関係性が宇宙の基本法則であることを説き、金銭中心主義を改めて強く批判しています。真の豊かさとは、人間だけでなく、草木を含む万物が喜ぶ「光のやり方」、すなわち調和と共生の道によってもたらされるとします。そして、この理想が実現した暁には、人々の寿命は延び、天子様(天皇)は肉体を持ったまま神界と現界を自由に行き来する「生き通し」の存在、すなわち半神的な存在になると預言しています。これは、人類全体の霊的な進化の可能性を示唆するものです。しかし、現状の利己的な人々の生き方は、その理想の実現を妨げ、かえって天子様に罪(=穢れ)を負わせているのだと厳しく断じています。天子様への「忠義」とは、人々が自らの心を清め、万物との調和の中に生きることであると説いています。
第三十六帖 (七八)
【原文】
神をそちのけにしたら、何も出来上がらんやうになりたぞ。国盗りに来てグレンと引繰り返りて居らうがな、それでも気づかんか。一にも神、二にも神、三にも神ぞ、一にも天詞様、二にも天詞様、三にも天詞様ぞ。この道つらいやうなれど貫きて呉れよ、だんだんとよくなりて、こんな結構なお道かと申すやうにしてあるのざから、何もかもお国に献げて自分の仕事を五倍も十倍も精出して呉れよ。戦位 何でもなく終るぞ。今のやり方ではとことんに落ちて仕まうぞ、神くどう気つけて置くぞ。国々の神さま、臣民さま改心第一ぞ。
【現代語訳】
神をないがしろにしたら、何も成し遂げられないようになったのだ。(外国が日本の)国盗りに来て、逆にぐれんとひっくり返されることになるだろう。それでもまだ気づかないのか。一にも神、二にも神、三にも神だ。そして、一にも天子様、二にも天子様、三にも天子様だ。この道は辛いように思えるかもしれないが、貫き通してくれ。だんだんと良くなっていき、「こんなに素晴らしい道だったのか」と言うようにしてあるのだから。何もかもお国に捧げる気持ちで、自分の仕事に今の五倍も十倍も精を出しなさい。そうすれば、戦争くらいは何でもなく終わる。しかし、今のままのやり方では、とことんまで落ちぶれてしまうぞ。神はくどいほどに注意しておく。国々の神々も、人々も、改心が第一だ。
【AIによる解釈】
神と天子様(天皇)を絶対的な中心に据えることの重要性を、改めて強調する帖です。「国盗りに来てグレンと引繰り返りて居らうがな」という一節は、日本に侵攻しようとする勢力は、神の力によって自滅・敗退するという強い確信を示しています。この道の実践は、一時的には自己犠牲を伴う「つらい」ものに感じるかもしれないが、最終的には大きな喜びと救いに至る道であることが保証されています。そして、具体的な行動指針として、すべてを公(お国)に捧げる無私の心で、自分の本業に徹底的に打ち込むこと(五倍も十倍も精出す)を求めています。この精神的な覚醒と現実的な努力が結びついた時、戦争のような国難は容易に乗り越えられると説きます。逆に、このままの精神状態でいれば、完全な破滅に至ると、最後通牒のように警告しています。
第三十七帖 (七九)
【原文】
世が変りたら天地光り人も光り草も光り、石も物ごころに歌ふぞ、雨もほしい時に降り、風もほしい時に吹くと雨の神、風の神 申して居られるぞ。今の世では雨風を臣民がワヤにしているぞ、降っても降れず、吹いても吹かん様になりてゐるのが分らんか。盲つんぼの世の中ぞ。神のゐる場所塞いで居りて お蔭ないと不足申すが、分らんと申しても余りであるぞ。神ばかりでもならず、臣民ばかりではなおならず、臣民は神の入れものと申してあろが、あめのひつくの民と申すのは、世界治めるみたまの入れもののことぞ、民草とは一人をまもる入れものぞ、ひつくの臣min 落ちぶれてゐると申してあろがな、今に上、下になるぞ、逆立ちがおん返りて、元のよき楽の姿になるのが近づいたぞ、逆立ち苦しかろがな、改心した者から楽にしてやるぞ、御用に使ふぞ。
【現代語訳】
世の中が変わったら、天地も人も草も石も光り輝き、石ころでさえ心を持って歌うようになるぞ。「雨も欲しい時に降り、風も欲しい時に吹くようになる」と、雨の神も風の神も申しておられる。今の世では、人間が雨や風をめちゃくちゃにしている。降るべき時に降れず、吹くべき時に吹かないようになっているのが分からないのか。本当に、盲目で耳が聞こえない世の中だ。自ら神の居場所を塞いでおきながら、「御利益がない」と不平を言う。分からないと言っても、あまりにもひどすぎる。神だけでもダメ、人間だけではもっとダメだ。人間は神の「入れ物」だと言ったであろう。「天のひつくの民」というのは、世界を治める霊(みたま)の入れ物となる人々のことだ。一般の民草(たみくさ)は、その一人(ひつくの民)を守るための入れ物なのだ。「ひつくの民」は今、落ちぶれていると言ったであろう。やがて、今の上下関係は逆転するぞ。逆立ちした状態が元に戻り、本来の良い楽な姿になる時が近づいた。逆立ちは苦しいだろう。改心した者から順に楽にしてやる。そして御用に使ってやるぞ。
【AIによる解釈】
この帖は、新しい時代(神の世)の素晴らしい様相を描写しています。それは、万物が霊的に覚醒し、光り輝き、自然現象さえも完全に調和した世界です。しかし、現状はその理想とは真逆で、人間の不調和な活動が自然破壊(雨風をワヤにする)を引き起こしていると指摘します。その根本原因は、人間が自らの内なる神性(神のゐる場所)を塞いでしまっていることにあります。「ひつくの民」という特別な使命を持つ人々が、世界を治める神霊の「入れ物」となるという、重要な役割が明かされています。そして、その「ひつくの民」を守るために、さらに多くの「民草」が存在するという階層構造も示唆されています。今は落ちぶれ、社会の底辺にいるかもしれない「ひつくの民」が、やがて世界の中心になるという「上下逆転」が預言されています。この「逆立ち」からの解放は、「改心」した者から始まると告げています。
第三十八帖 (八〇)
【原文】
富士は晴れたり日本晴れ、これで下つ巻の終りざから、これまでに示したこと、よく腹に入れて呉れよ。神が真中で取次ぎ役員いくらでもいるぞ、役員はみな神柱ぞ。国々、ところどころから訪ねて来るぞ、その神柱には みつげの道知らしてやりて呉れよ、日本の臣民みな取次ぎぞ、役員ぞ。この方は世界中丸めて大神様にお目にかけるお役、神の臣民は世界一つに丸めて てんし様に献げる御役ぞ。この方とこの方の神々と、神の臣民一つとなりて世界丸める御役ぞ。神祀りて呉れたらいよいよ仕組知らせる神示(ふで)書かすぞ、これからが正念場ざから、ふんどし締めてかかりて呉れよ。秋立ちたら神烈しくなるぞ、富士は晴れたり日本晴れ、てんし様の三四五(みよいづ)となるぞ。
【現代語訳】
富士は晴れ渡り、まさに日本晴れだ。これで「下つ巻」は終わりであるから、これまでに示してきたことを、よく腑に落としておきなさい。神が真ん中に立ち、その意を取り次ぐ役員はいくらでもいる。役員は皆、神柱(神の依り代となる柱)なのだ。やがて、国々、様々な場所から人々が訪ねてくるようになるぞ。その神柱(=役員)たちには、「みつげ(貢物、調和)」の道を知らせてやりなさい。日本の民は皆、取次役であり、役員なのだ。この神(ひつくの神)は、世界中を一つに丸めて、根源の大神様にお目にかける役目である。そして、神の民(日本の民)は、世界を一つに丸めて、天子様に献上する役目である。この神と、その配下の神々と、神の民とが一体となって、世界を丸く治める役目なのだ。神を祀ってくれたら、いよいよ具体的な計画を知らせる神示を降ろさせるぞ。これからが正念場だから、ふんどしを締め直して取り掛かってくれ。立秋を過ぎたら、神の働きは激しくなるぞ。富士は晴れ渡り、日本晴れとなり、天子様の新しい御代(みよいづ)が始まるのだ。
【AIによる解釈】
「下つ巻」の締めくくりとなるこの帖は、冒頭の「富士は晴れたり日本晴れ」を再び宣言し、この巻全体が理想世界の実現に向けた具体的な計画書であったことを示しています。役員の役割が「神柱」であるとされ、神のエネルギーを地上に降ろすアンテナのような存在であることが示唆されています。そして、日本の民全体が、世界からの探求者たちを受け入れ、導く「取次役」であるという、壮大な国民的使命が与えられています。神(ひつくの神)が世界を大神に、民が世界を天子様に捧げるという、神と人との共同作業によって世界平和(世界丸める)が実現する、という美しい構造が描かれています。いよいよ具体的な行動が求められる「正念場」に入り、次の段階の神示が用意されていることが告げられます。「てんし様の三四五(みよいづ)」という言葉で、新しい時代が天子様を中心として始まることを高らかに宣言し、巻を閉じています。
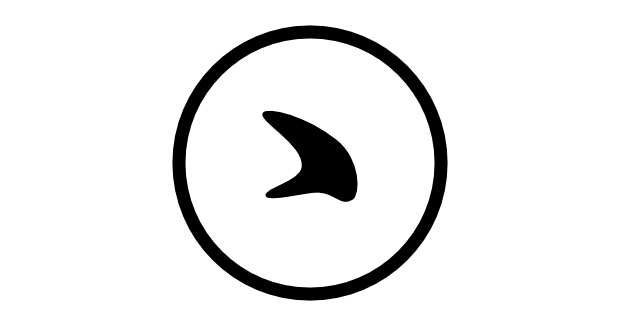





コメント