(昭和20年7月21日 – 8月10日) 全13帖
ひふみ神示 第十二巻「夜明けの巻」は、その名の通り、長く続いた暗黒の時代の終わりと、新しい「神の世(ミロクの世)」の幕開けを力強く宣言する、転換点となる重要な巻です。
この神示が降ろされた時期は、昭和20年(1945年)7月21日から8月10日。これは広島・長崎への原爆投下を挟み、日本がポツダム宣言を受諾し敗戦を迎える、まさに直前の極めて緊迫した時期にあたります。国家の存亡が危ぶまれ、多くの人々が絶望の淵に立たされていたその渦中で、この神示は滅びの先にある「夜明け」と再生のビジョンを鮮烈に示しました。
この巻の最大の特徴は、これまでの価値観が根底から覆される「大転換」の告知です。
- 「己殺して他人助けるも悪」と、自己犠牲を否定し、「己を活かし他人も活かす」という自他共栄の新しい倫理観。
- 日本という国が、世界の霊的な中心であり、その封印(シメ)が解かれて本来の役割を発揮する時が来たという国体の再認識。
- 天変地異や人心の荒廃といった厳しい大峠(おおとうげ)の警告と共に、その先には「理屈のない世」「不潔のない世」といった、現代の常識では想像もつかないほどの清らかで喜びに満ちた世界が待っているという希望。
「夜明けの巻」は、単なる預言に留まらず、その激動期を乗り越え、新しい時代を生きるための具体的な心構えと実践方法を繰り返し説きます。「我(が)を捨てること」「慢心への戒め」「借銭(カルマ)の清算」「信者ではなく道をつたえること」など、読者一人ひとりの内面的な変革と、他者や社会に対する真摯な姿勢を強く求めています。
まさに、暗闇が最も深まる時にこそ、夜明けの光は差し込むという真理を体現した巻であり、これからの世界の進むべき道を指し示す、羅針盤とも言える内容となっています。
第一帖 (三二一)
【原文】
イシはイにかへるぞ。一(ヒ)であるぞ。 (ム)であるぞ。井であるぞ。イーであるぞ。
キと働くのざぞ。わかりたか。今までは悪の世でありたから、己殺して他人助けることは、此の上もない天の一番の教といたしてゐたが、それは悪の天の教であるぞ。己を活かし他人(ひと)も活かすのが天の道ざぞ、神の御心ぞ。他人殺して己助かるも悪ぞ、己殺して他人助けるも悪ぞ、神無きものにして人民生きるも悪ぞ。神ばかり大切にして人民放っておくのも悪ぞ。神人ともにと申してあろが。神は人に依り神となり、人は神によって人となるのざぞ。まことの神のおん心わかりたか。今までの教へ間違っていること段々判りて来るであろがな。天地和合して
となった姿が神の姿ざぞ。御心(みこころ)ざぞ。天(あめ)と地(つち)ではないぞ。あめつちざぞ。あめつちの時と知らしてあろうが、みな取違ひ申して済むまいが。神示よく読めと、裏の裏まで読めと申してあろが。七月の二十一日、あめのひつぐのかみ。
【現代語訳】
「イシ(石、意志、肉体)」は「イ(意、生命、五十分の一)」に還るのだ。それは根源の「一(ヒ)」であり、「(ム)」であり、「井」であり、「イー」なのだ。
それは「キ」として働くのだぞ。わかったか。 今までは悪が支配する世であったから、「自分を殺して他人を助けること」が、この上ない天の第一の教えとされてきたが、それは悪の天が生んだ教えなのだ。 「自分を活かし、他人も活かす」のが、まことの天の道であり、神の御心なのだ。他人を殺して自分が助かるのも悪。自分を殺して他人を助けるのも悪。神を無視して人民が生きるのも悪。神ばかりを大切にして人民を放っておくのも悪なのだ。「神と人が共に」と申してあるだろう。神は人に依って神となり、人は神に依って人となるのだ。まことの神の御心がわかったか。今までの教えが間違っていたことが、だんだんとわかってくるだろう。 天地が和合して一つとなった姿が、神の姿であり、御心なのだ。天と地とバラバラに考えるのではない。「あめつち」として一体なのだ。「あめつちの時」が来ると知らせてあるのに、皆が取り違えていては済まない。神示をよく読め、その裏の裏まで読めと申してあるだろう。 七月二十一日、あめのひつぐのかみ。
【AIによる解釈】
この帖は、新しい時代の根本的な価値観の転換を宣言しています。「己を殺して他人を助ける」という自己犠牲の美徳は、これまでの「悪の世」の教えであったと断じ、「自他共に活かす」ことこそが神の道であると説きます。これは、一方的な犠牲や対立ではなく、全ての存在が調和し、共に栄える「共存共栄」の時代の到来を示唆しています。
また、「神人ともに」「天地和合」という言葉は、神と人、天と地といった二元論的な対立を超越し、すべてが一体となることを示しています。神は人を通して顕現し、人は神を内に宿すことで真の人となるという「神人合一」の思想が、これからの世界の基本理念となることを告げています。冒頭の「イシはイにかへる」は、物質的なもの(石、肉体)が、より根源的な意識や生命エネルギー(意)に還っていく、つまり精神性の重要性が高まる時代の到来を象徴していると解釈できます。
第二帖 (三二二)
【原文】
神の国は神の肉体ぞと申してあるが、いざとなれば、お土も、草も、木も、何でも人民の食物となる様に出来てゐるのざぞ。何でも肉体となるのざぞ。なるようにせんからならんのざぞ。それで外国の悪神が神の国が慾しくてならんのざ。神の国より広い肥えた国 幾らでもあるのに、神の国が欲しいは、誠の元の国、根の国、物のなる国、元の気の元の国、力の元の国、光の国、真中(まなか)の国であるからぞ、何も彼も、神の国に向って集まる様になってゐるのざぞ。神の昔の世は、そうなってゐたのざぞ。磁石も神の国に向く様になるぞ。北よくなるぞ。神の国おろがむ様になるのざぞ。どこからでもおろがめるのざぞ。おのづから頭さがるのざぞ。海の水がシメであるぞ。鳥居であるぞと申してあろうが、シメて神を押し込めてゐたのであるぞ。人民 知らず知らずに罪犯してゐたのざぞ。毎日、日日(ひにち)お詫(わび)せよと申してあらうが、シメて島国日本としてゐたのざぞ、よき世となったら、身体(からだ)も大きくなるぞ。命も長くなるぞ。今しばらくざから、辛抱してくれよ。食物心配するでないぞ。油断するでないぞ。皆の者喜ばせよ。その喜びは、喜事(よろこびごと)となって天地のキとなって、そなたに万倍となって返って来るのざぞ。よろこびいくらでも生まれるぞ。七月二十一日、あめのひつくのかみ。
【現代語訳】
「神の国(日本)は神の肉体そのものである」と申してあるが、いざとなれば、土も草も木も、すべてが人民の食物となるように出来ているのだ。何でも人民の肉体となるのだ。そのようにしないから、そうならないだけなのだ。 だからこそ、外国の悪神がこの神の国を欲しくてたまらないのだ。神の国より広くて肥えた国はいくらでもあるのに、それでも神の国が欲しいのは、ここがまことの元の国、根の国、万物が生り成る国、根源の気の国、力の元の国、光の国、世界の真ん中の国だからだ。何もかもが、この神の国に向かって集まるようになっている。神が治めた昔の世は、そうなっていたのだ。 やがては磁石も神の国(日本)を指すようになるぞ。北の方角も良くなるぞ。世界中の人々が神の国を拝むようになるのだ。どこからでも拝めるようになり、自然と頭が下がるのだ。 海の水が注連縄(しめなわ)であり、鳥居であると申したが、それは逆に、この国に神々を封じ込めるための「シメ」であったのだ。人民は知らず知らずのうちに罪を犯していたのだぞ。毎日お詫びせよと申したのはこのことだ。そのようにして、日本を閉ざされた島国としていたのだ。 よき世になったら、人々の身体は大きくなり、寿命も長くなるぞ。もうしばらくのことだから、辛抱してくれ。食物の心配はするな。しかし油断はしてはならないぞ。 皆を喜ばせなさい。その喜びは、良い出来事となり、天地の気となって、あなたに万倍になって返ってくるのだ。喜びはいくらでも生まれてくるぞ。 七月二十一日、あめのひつくのかみ。
【AIによる解釈】
この帖は、日本の国土が持つ霊的な重要性を説いています。日本は単なる島国ではなく、地球の霊的な中心(真中の国)であり、万物を生み出す根源的なエネルギーに満ちているとされています。「いざとなれば土や草木も食料になる」という記述は、物質の次元を超えた生命エネルギーの活用を示唆しており、来るべき食糧危機のような事態への備えと希望を与えています。
「シメて神を押し込めてゐた」という表現は非常に重要です。本来、神域を示す鳥居や注連縄が、逆に日本の本来の力や役割を封じ込める呪縛となっていたと指摘しています。これは、日本が霊的な鎖国状態にあったことを示唆しており、その解放が近いことを告げています。 最後に説かれる「喜びの法則」は、個人の内面が現実を創造するという教えです。他者を喜ばせるというポジティブな行為が、増幅されて自分に返ってくるという宇宙の法則を示し、困難な時代を乗り越えるための心の持ち方を具体的に指導しています。
第三帖 (三二三)
【原文】
天の異変 気付けと申してあろが、冬の次が春とは限らんと申してあろが。夏 雪降ることもあるのざぞ。神が降らすのでないぞ、人民 降らすのざぞ。人民の邪気が凝りて、天にも地にも、わけの判らん虫わくぞ。訳の判らん病ひどくなって来るのざから、書かしてある御神名 分けて取らせよ。旧九月八日までに何もかも始末しておけよ。心引かれる事 残しておくと、詰らん事で詰らん事になるぞ。もう待たれんことにギリギリになってゐる事 判るであろがな。七月二十四日の神示、あめのひつぐの神。
【現代語訳】
天の異変に気付けと申してあるだろう。冬の次が必ず春になるとは限らないと申してあるだろう。夏に雪が降ることもあるのだぞ。それは神が降らせるのではない。人民が降らせるのだ。人民の邪気が凝り固まって、天にも地にも、わけのわからない虫がわき、わけのわからない病気がひどくなってくるのだから、神示に書かせてある御神名を分けて持たせなさい。 旧暦の九月八日までに、何もかも身辺の整理をしておけよ。心惹かれること(執着)を残しておくと、つまらないことで大変なことになるぞ。もう待ったなしの、ギリギリの状態になっていることがわかるだろう。 七月二十四日の神示、あめのひつぐの神。
【AIによる解釈】
この帖は、異常気象や未知の疫病といった具体的な災厄について警告しています。特筆すべきは、その原因を「人民の邪気」にあると断言している点です。これは、天変地異や社会の混乱が、単なる自然現象や偶然ではなく、集合的な人心の乱れが物質世界に反映された結果であるという思想を示しています。
「冬の次が春とは限らん」という言葉は、これまでの常識や秩序が通用しなくなる時代の到来を強く示唆しています。このような混乱期を乗り越えるために、神示に記された御神名(霊的な守り)と、身辺や心の整理(執着を手放すこと)という二つの具体的な対策が示されています。「旧九月八日」という期日を設けることで、事態の切迫性を伝え、即時の行動を促しています。
第四帖 (三二四)
【原文】
この方 カの神と現はれるぞ、サの神と現はれるぞ、タの神と現はれるぞ、ナの神と現はれるぞ、ハマの神と現はれるぞ。ヤラワの神と現われたら、人間 眼明けて居れん事になるぞ、さあ今の内に神徳積んでおかんと八分通りは獣の人民となるのざから、二股膏薬ではキリキリ舞するぞ、キリキリ二股多いぞ。獣となれば、同胞(はらから)食ふ事あるぞ。気付けておくぞ。七月二十九日、あめのひつくのかみ。
【現代語訳】
この方(神)は、カの神、サの神、タの神、ナの神、ハマの神として現れるぞ。そしてヤラワの神として現れたなら、人間はあまりの厳しさに目を開けていられないことになるぞ。 さあ、今のうちに神徳を積んでおかないと、人民の八割方は獣のようになってしまうのだから、あちらこちらにいい顔をする二股膏薬のような中途半端な態度では、きりきり舞いすることになるぞ。そのような者が非常に多いぞ。獣のようになれば、同胞を食らうようなこと(共食い)も起こりうるのだ。気付けておくぞ。 七月二十九日、あめのひつくのかみ。
【AIによる解釈】
この帖は、神の顕現が段階的であり、その性質が徐々に厳しくなっていくことを示しています。「カ・サ・タ・ナ・ハマ」という言霊で示される神々は、それぞれ異なる働きを持つ神の側面であり、人々を導き、育て、あるいは篩にかける働きをすると考えられます。最後の「ヤラワの神」は、最終的かつ絶対的な厳しい審判の働きを象徴しており、その時にはもはや猶予がないことを警告しています。
「八分通りは獣の人民となる」「同胞食ふ事あるぞ」という表現は、大峠の過程で多くの人々が理性を失い、本能のままに行動する、極めて過酷な社会状況が出現する可能性を警告するものです。「二股膏薬」への戒めは、どちらつかずの態度や不純な信仰では、この厳しい時代を乗り越えられないことを示し、純粋で一貫した「まこと」の道を歩むことの重要性を強調しています。
第五帖 (三二五)
【原文】
何もかも神示読めば判る様になってゐる事 忘れるでないぞ、此の仕組 云ふてならず、云はねば判らんであろうなれど、神示読めば因縁だけに判るのざぞ。石物云ふ時来たぞ。山にも野にも川にも神まつれと申してあること、忘れるでないぞ、型せと申してあらうが、いづれも仮ざから三千世界の大洗濯ざから、早よ型してくれよ。型結構ぞ。何もかも神人共にするのざぞ。夜明けたら、何もかもはっきりするぞ、夜明け来たぞ。十理(トリ)立てよ。七月二十八日、あめのひつくのかみ神示書。
【現代語訳】
何もかも、この神示を読めばわかるようになっていることを忘れるでないぞ。この神の仕組みは、口で言ってはならないことだが、言わなければわからないだろう。しかし、神示を読めば、その人の因縁に応じて理解できるようになっているのだ。「石がものを言う」時が来たのだ。 山にも野にも川にも神を祀れと申したことを忘れるな。型(雛形)を示せと申してあるだろう。いずれも仮の世であるから、今は三千世界の大洗濯の時なのだから、早く型を示してくれよ。その型はまことに結構なものだ。何もかも神と人が共に行うのだ。 夜が明けたら、何もかもがはっきりするぞ。その夜明けが来たのだ。十の理(トリ=鶏、道理)を立てよ。 七月二十八日、あめのひつくのかみ神示書。
【AIによる解釈】
この帖は、神示の重要性と「型(雛形)」の実践を強く促しています。「神示読めば因縁だけに判る」とは、神示の理解が個人の霊的な成長度や背景によって深まることを示しており、表面的な知識だけでなく、魂で読み解くことの必要性を説いています。「石物云ふ時」とは、常識では考えられないような奇跡的なことが起こり始め、物質世界そのものが神意を現し始める時代の到来を告げる象徴的な言葉です。
「型をせよ」という命令は、新しい神の世のモデルケース(雛形)を、まず小さな共同体や個人の実践によってこの地上に作り出すことを求めています。この「型」が、やがて来るべき世界の理想像となり、それが全体に広がっていくという「雛形経綸」の思想です。「夜明け来たぞ」という宣言は、旧時代の終わりと新時代の始まりを告げ、具体的な行動を起こすべき時が来たことを力強く伝えています。
第六帖 (三二六)
【原文】
今迄の様な大便小便 無くなるぞ。不潔と云ふもの無き世となるのざぞ。不潔物 無くなるのぞ。新しき神の世となるのざから、神々にも見当取れん光の世となるのざぞ。七月三十一日、あめのひつぐのかみ。
【現代語訳】
これからの世では、今までのような大便や小便はなくなるぞ。不潔という概念そのものがない世の中になるのだ。不潔なものは一切なくなる。新しい神の世となるのだから、神々でさえ見当がつかないほどの、まばゆい光の世となるのだぞ。 七月三十一日、あめのひつぐのかみ。
【AIによる解釈】
この帖は、新しい時代の人間と世界の劇的な変容を、非常に具体的な例で示しています。「大便小便が無くなる」というのは、文字通りの生理現象の変化とも解釈できますが、より深い意味では、人間の肉体が半霊半物質化し、エネルギーの摂取や排出の仕方が根本的に変わることを象徴していると考えられます。
「不潔と云ふもの無き世」とは、単に衛生的な状態を指すだけでなく、人の心から不浄な想念(妬み、憎しみ、偽りなど)が一掃され、社会からあらゆる汚れや穢れが消え去ることを意味します。それは、物質的にも精神的にも完全に浄化された「光の世」のビジョンであり、これまでの三次元的な常識や、神々の予測すら超えた、全く新しい次元の世界が到来することを預言しています。
第七帖 (三二七)
【原文】
神の臣民に楽な事になるぞ。理屈無い世にするぞ。理屈は悪と申してあろが、理屈ない世に致すぞ。理屈くらべのきほひ無くして仕舞ふぞ。人に知れん様によいことつとめと申してあろが。人に知れん様にする好い事 神こころぞ。神のした事になるのざぞ。行けども行けども白骨と申したが、白骨さへなくなる所あるぞ。早よ誠の臣民ばかりで固めて呉れよ。神世の型 出して呉れよ。時、取違へん様に、時、来たぞ。八月一日、あめのひつぐ神。
【現代語訳】
神の民にとっては、楽な世の中になるぞ。理屈のない世にするのだ。理屈は悪であると申しただろう。理屈で争うことをなくしてしまうぞ。 人に知られないように善いことをしなさいと申してあるが、人に知られずに行う善行こそ、神の御心にかなうものだ。それは神がなさったことになるのだ。 「行けども行けども白骨の山」と申したが、その先には白骨さえ残らないほど、すべてが消滅してしまう場所もあるのだぞ。 早くまことの民ばかりで集まってくれ。神の世の雛形を示してくれ。時を間違えないように。その時が来たのだ。 八月一日、あめのひつぐ神。
【AIによる解釈】
この帖が描く新しい世は、「理屈無い世」です。これは、複雑な法律や論争、知的な駆け引きなどが不要になる世界を意味します。人々が真心で通じ合い、直感や神意に従って行動するため、言葉による議論や対立そのものがなくなるのです。左脳的な思考よりも、右脳的な感性や霊性が主導する社会とも言えるでしょう。
「人に知れん様にする好い事」を奨励するのは、「陰徳」の重要性を説くものです。見返りを求めず、誰にも誇ることなく行う善行こそが、最も純粋で神の心にかなう行為であるとされています。 「白骨さへなくなる所」という厳しい表現は、大峠の破壊の側面を強調し、中途半端な覚悟では生き残れないことを示唆しています。だからこそ、「誠の臣民」で固まり、「神世の型」を急いで示すよう、再度強く促しているのです。
第八帖 (三二八)
【原文】
直会(なをらひ)も祭典(まつり)の中ぞ。朝の、夕の、日々の人民の食事 皆 直会ぞ。日々の仕事 皆まつりぞ。息すること此の世の初めのまつりぞ。まつれまつれと申してあろが。おはりの御用は はじめの御用ぞ。まつりの御用ぞ。オワリノ十ノヤマにまつり呉れよ。世につげて呉れよ。役員 皆 宮つくれよ。宮とは人民の申す宮でなくてもよいのざぞ。一の宮、二の宮、三の宮と次々につくり呉れよ。道場も幾らつくってもよいぞ。神の申した事、なさば成るのざぞ。宮と道場つくり神示読んでまつれまつれ、まつり結構ぞ。奥山にはオホカムツミの神様もまつり呉れよ。守りは供へてから皆に下げて取らせよ。五柱、七柱、八柱、十柱、十六柱、二十五柱、三十三柱、三十六柱、四十七柱、四十八柱、四十九柱、五十柱、五十八柱、五十九柱、世の元ぞ。八月の二日、アメのひつくの神。
【現代語訳】
直会(神事の後の会食)も祭典の一部だ。朝夕の、日々の食事は皆、神様と共にある直会なのだ。日々の仕事も皆、神に奉仕する祭りなのだ。呼吸すること自体が、この世の始まりの祭りなのだ。「まつれ(祀れ、纏れ)」と繰り返し申しているだろう。 終わりの御用は、始めの御用であり、それは祭りの御用なのだ。「尾張の十の山」に祀ってくれよ。そして世に告げてくれ。 役員は皆、宮を建てなさい。宮といっても、人々が考えるような立派な社殿でなくてもよいのだ。一の宮、二の宮、三の宮と次々に作ってくれよ。道場もいくら作ってもよい。神が申したことは、行えば必ず成るのだ。宮と道場を作り、神示を読んで、まつりを行いなさい。祭りはまことに結構なことだ。 奥山にはオホカムツミの神様もお祀りしなさい。お守りは、一度神にお供えしてから皆に下げて渡すように。 五柱、七柱、八柱…(以下、神々の数を示す数字)…これらは世の元となるものである。 八月の二日、アメのひつくの神。
【AIによる解釈】
この帖は、「祭り」の概念を、特別な神事から日常生活のすべてへと拡張しています。食事、仕事、呼吸といった生命活動そのものが、神と共にある聖なる「祭り」であると説きます。これは、生活と信仰を分離せず、生きることすべてを神への奉仕と捉える「生活即信仰」の教えです。
「宮をつくれ」という指示も、物理的な建物を建てること以上に、神を祀り、人々が集い、神示を学ぶ「場」を作ることの重要性を説いています。それは立派な社殿である必要はなく、個人の家や小さな集会所でも良いのです。大切なのは、神の世の雛形となる「磁場」を各地に点在させることです。 最後に列挙される数字は、祀るべき神々の数や、宇宙を構成する聖なる数(数霊)を示しており、これからの祭りが多くの神々との繋がりを取り戻すものであることを示唆しています。
第九帖 (三二九)
【原文】 天詞様まつれと申してあろが。天津日嗣皇尊大神様(あまつひつぎすめらみことおほかみさま)とまつり奉れ。奥山には御社(みやしろ)造りて、いつき奉(まつ)れ。皆のうちにも祀れ。天津日嗣皇尊 弥栄ましませ、弥栄ましませとおろがめよ。おろがみ奉れ、天照皇大神様、天照大神様、月の大神様、すさなるの大神様、大国主の大神様もあつくまつりたたえよ。奥山の前の富士に産土の大神様 祀れよ、宮いるぞ。清めて祭れよ、タマの宮はその前横に移せよ。奥の富士に国常立大神、豊雲野大神 祀る日 近うなりたぞ。宮の扉あけておけよ。臣民の住居(すまい)も同様ぞ。大難小難にまつりかへて下されとお願ひするのざぞ。取違ひ、お詫び申せよ、楽にしてやるぞ。天の異変 気付けよ。八月の五日、アメのひつ九の神。
【現代語訳】 天詞様(てんしさま)をお祀りしなさいと申してあるだろう。「天津日嗣皇尊大神様(あまつひつぎすめらみことおおかみさま)」とお呼びして、お祀りしなさい。奥山には御社を建てて、大切にお祀りせよ。皆の家の中にもお祀りしなさい。「天津日嗣皇尊弥栄ましませ、弥栄ましませ」と拝みなさい。 天照皇大神様、天照大神様、月の大神様、スサナルノ大神様、大国主の大神様も篤くお祀りし、たたえなさい。 奥山の前の富士(※場所の特定は困難)に、その土地の産土の大神様をお祀りしなさい。宮が必要だ。清めてお祀りせよ。タマの宮は、その前方の横に移しなさい。奥の富士には、国常立大神と豊雲野大神をお祀りする日が近くなったぞ。 宮の扉は開けておきなさい。民の住居も同様だ。 「大難を小難にお祀り替えください」とお願いするのだ。これまでの取り違いをお詫びしなさい。そうすれば楽にしてやるぞ。天の異変に気付けよ。 八月の五日、アメのひつ九の神。
【AIによる解釈】 この帖は、具体的な祭祀の対象と方法について詳しく述べています。中心となるのは「天詞様」、すなわち天皇を「天津日嗣皇尊大神様」という神名で祀ることです。これは、天皇を単なる人間ではなく、天の神々の血筋を受け継ぐ霊的な中心存在として捉える、神道的な世界観に基づいています。
さらに、天照大御神やスサノオ、大国主といった国津神、そして根源神である国常立大神など、神階の異なる様々な神々を篤く祀るよう指示しています。これは、これまで隠されてきたり、正当に評価されてこなかったりした神々も含めて、すべての神々の力を結集させ、その総力で「立て替え立て直し」を進める必要があることを示しています。「宮の扉あけておけ」とは、物理的に扉を開けると共に、いつでも神々をお迎えできるように、心を開いておくことの重要性を説いています。これらの祭祀の実践が、これから起こる大難を小難に変えるための具体的な方法であるとされています。
第十帖 (三三〇)
【原文】
元津大神、心の中で唱へ奉り、スメラミコト唱へ、次に声高く天津日嗣皇ミコト大神唱へ、天のひつくの大神と唱へ奉れ。タマの宮は、かむながら祝詞でよいぞ。一二三(ひふみ)のりともよいぞ、シメは当分造りめぐらしてもよいぞ。今までのシメは此の方等しめて、悪の自由にする逆のシメざから、シメ張るなら、元のシメ、誠のシメ張れよ。七五三は逆ざぞ。三五七ざぞ。天地のいぶきぞ。波の律ぞ。風の律ぞ。神々様のおんいぶきの律(なみ)ざぞ。八月の六日、アメのひつ九の神。
【現代語訳】
まず、元津大神(もとつおおかみ)を心の中で唱え、次にスメラミコトを唱え、その次に声高く天津日嗣皇尊大神(あまつひつぎすめらみことおおかみ)を唱え、最後に天のひつくの大神と唱えなさい。 タマの宮では、「かむながら祝詞」でよい。ひふみ祝詞でもよい。 注連縄(しめなわ)は当分の間、巡らせてもよい。しかし、今までの注連縄は、この方(国常立大神など)を封じ込め、悪神を自由にするための逆の注連縄であったから、もし注連縄を張るならば、本来の、まことの注連縄を張りなさい。 七五三は逆だ。三五七が正しいのだ。それは天地の息吹であり、波のリズム、風のリズム、神々の息吹のリズムなのだ。 八月の六日、アメのひつ九の神。
【AIによる解釈】
この帖は、祝詞の唱え方や祭具、数霊に関する具体的な教えです。唱えるべき神名の順番が示されており、根源神から天皇、そしてこの神示を降ろしている「ひつくの神」へと至る霊的な階層と繋がりを示しています。
第二帖に続き、「シメ(注連縄)」の逆転について言及しています。これまでの常識や形式が、実は本来の意味とは逆に働き、神を封じ込めていたという衝撃的な指摘です。これからは、その呪縛を解き、まことのやり方に戻す必要があると説きます。 「七五三は逆ざぞ。三五七ざぞ」という教えも、常識の逆転を象徴しています。七五三が地上から天上へ向かう人間的な数であるのに対し、三五七は天から地へ降りる神的なリズム、宇宙の息吹(律)を表していると解釈できます。これは、人間の都合ではなく、宇宙の法則・神のリズムに自らを合わせることの重要性を示唆しています。
第十一帖 (三三一)
【原文】
岩戸開きのはじめの幕 開いたばかりぞ。今度はみづ逆さにもどるのざから、人民の力ばかりでは成就せんぞ。奥の神界では済みてゐるが、中の神界では今最中ざ。時待てと申してあろが。人民 大変な取違ひしてゐるぞ。次の世の型 急ぐ急ぐ。八月六日、アメのひつぐのかみ。
神示読まないで智や学でやろうとて、何も、九分九厘で、終局(りんどまり)ぞ。我(われ)が我(われ)ががとれたら判って来るぞ。慢心おそろしいぞ。
【現代語訳】
岩戸開きは、まだ最初の幕が開いたばかりだ。今度は、何もかもが逆さまに元に戻るのだから、人民の力だけでは成就しない。奥の神界では既に(立て直しは)済んでいるが、中間の神界では今まさにその最中だ。時を待てと申してあるだろう。人民は大変な取り違いをしているぞ。次の世の雛形作りを急げ、急げ。 八月六日、あめのひつぐのかみ。
神示を読まずに、人間の知恵や学問だけで事をなそうとしても、何もかも九分九厘まで行って、最後には行き詰ってしまうぞ。「我(が)」が取れたら、わかってくる。慢心は恐ろしいものだぞ。
【AIによる解釈】
この帖は、立て替え立て直しの進捗状況と、それに対する人間の姿勢について述べています。「岩戸開きのはじめの幕 開いたばかり」という言葉は、大変革がまだ序盤であることを示し、安堵や油断を戒めています。「奥の神界では済みてゐる」とは、霊界の高い次元では既に新しい世界の設計図が完成しているものの、それが現実世界に反映されるまでには、まだ中間層(中の神界)での調整が必要であることを示唆しています。
このプロセスは人間の力だけでは成就せず、神の計画に沿うことが不可欠であると強調されています。人間の「智や学」は九分九厘で限界に達し、最後の壁を越えるには「我(が)を捨てる」こと、すなわち慢心を捨てて神意に身を委ねることが必要だと説きます。これは、人類が次のステージに進むためには、エゴや人間中心主義を乗り越えなければならないという、根源的な課題を突きつけています。
第十二帖 (三三二)
【原文】
あら楽(たぬ)し、あなさやけ、元津御神の御光の、輝く御代ぞ近づけり。岩戸開けたり野も山も、草の片葉(かきは)も言(こと)止(や)めて、大御光に寄り集ふ、誠の御代ぞ楽しけれ。今一苦労二苦労、とことん苦労あるなれど、楽しき苦労ぞ目出度けれ。申、酉すぎて戌の年、亥の年、子の年 目出度けれ。一二三(ひふみ)の裏の御用する身魂も今に引き寄せるから、その覚悟せよ。覚悟よいか。待ちに待ちにし秋来たぞ。八月の七日、アメのひつくのかみ。
ひふみ、よいむなや、こともちろらね、しきる、ゆゐつわぬ、そおたはくめか、うをえ、にさりへて、のます、あせえほれけ、八月八日、秋立つ日、アメの一二のおほかみ。
【現代語訳】
ああ、楽しい。ああ、すがすがしい。元津御神の御光が輝く御代が近づいてきた。岩戸が開かれて、野も山も、草の一葉一葉も、言葉を発するのをやめて、ただ大御光のもとに寄り集う、まことの御代はなんと楽しいことか。 今、もう一苦労、二苦労、とことんの苦労はあるけれども、それは新しい世を生み出すための「楽しき苦労」であり、まことに目出度いことだ。申、酉の年が過ぎて、戌、亥、子の年は目出度い年となるぞ。 ひふみの表だけでなく、裏の御用をする魂も、やがて引き寄せるから、その覚悟をしておきなさい。覚悟はよいか。待ちに待った「秋」が来たのだ。 八月の七日、あめのひつくのかみ。
(※後半はひふみ祝詞の一部、あるいは別の言霊) 八月八日、秋の立つ日、アメの一二の大神。
【AIによる解釈】
この帖は、苦難の先にある希望と喜びを歌い上げています。「とことん苦労あるなれど、楽しき苦労ぞ」という逆説的な表現は、産みの苦しみの只中にいることを示し、その苦労が新しい世界を創造するための神聖なプロセスの一部であることを教えています。
「申、酉すぎて戌の年、亥の年、子の年」という具体的な干支は、未来へのタイムスケジュールを示唆するものですが、それがいつの時代を指すのかは様々な解釈があります。重要なのは、苦しい時期の先には、必ず「目出度い」時が来るという希望のメッセージです。「待ちに待ちにし秋来たぞ」という宣言は、これまでの種まき(春)と成長(夏)の時期が終わり、いよいよ実りを刈り取り、物事を成就させる「時」が来たことを告げています。 後半の謎めいた言霊は、それ自体が世界を整える力を持つ祝詞であり、理屈を超えた言霊の働きによって、新時代への移行が促されることを示唆しています。
第十三帖 (三三三)
【原文】
あら楽し、すがすがし、世は朝晴れたり、昼晴れたり、夜も晴れたり。あらたのし、すがすがし、世は岩戸明けたり、待ちに待ちし岩戸開けたり、此の神示の臣民と云ふても、人間界ばかりでないぞ。神界幽界のことも言ふて知らしてあると、申してあろが。取違ひ慢心一等恐いと申してあろが。祭典(まつり)、国民服もんぺでもよいぞ。天明まつりの真似するでないぞ。役員まつりせい。何も云ふでないぞ。言ふてよい時は知らすぞよ、判りたか。仕へる者無き宮、産土様の横下にいくら祀ってもよいぞ。天明は祈れ。祈れ。天に祈れ、地に祈れ、引潮の時引けよ。満潮の時進めよ。大難小難にと役員も祈れよ。口先ばかりでなく、誠祈れよ。祈らなならんぞ。口先ばかりでは悪となるぞ。わかりたか。今度は借銭済(な)しになるまでやめんから、誰によらず借銭無くなるまで苦し行せなならんぞ、借銭なしでないと、お土の上には住めん事に今度はなるぞ。イシの人と、キの人と、ヒの人と、ミヅの人と、できるぞ。今にチリチリバラバラに一時はなるのであるから、その覚悟よいか。毎度知らしてあること忘れるなよ。神示 腹の腹底まで浸むまで読んで下されよ。神頼むぞ。悟った方 神示とけよ。といて聞かせよ。役員 皆とけよ。信ずる者皆人に知らしてやれよ。神示読んで嬉しかったら、知らしてやれと申してあらうが。天明は神示書かす役ぞ。アホになれと申してあろが、まだまだぞ、役員 気付けて呉れよ。神示の代りにミ身に知らすと申してある時来たぞ。愈々の時ぞ。神示で知らすことのはじめは済みたぞ。実身掃除せよ。ミ身に知らすぞ。実身に聞かすぞ、聞かな聞く様にして知らすぞ。つらいなれど、がまんせよ。ゆめゆめ利功出すでないぞ。判りたか、百姓にもなれ、大工にもなれ、絵描きにもなれ。何にでもなれる様にしてあるでないか。役員も同様ぞ。まどゐつくるでないぞ、金とるでないぞ。神に供へられたものはみな分けて、喜ばしてやれと申してあろが。此の方 喜ぶこと好きぞ、好きの事栄えるぞ。いや栄へるぞ。信者つくるでないぞ。道伝へなならんぞ。取違へせん様に慢心せん様に、生れ赤児の心で神示読めよ。神示いただけよ。日本の臣民 皆勇む様、祈りて呉れよ。世界の人民 皆よろこぶ世が来る様 祈りて呉れよ、てんし様まつれよ。みことに服(まつ)ろへよ。このこと出来れば他に何も判らんでも、峠越せるぞ。御民いのち捨てて生命に生きよ。「鳥鳴く声す 夢さませ、見よ あけ渡るひむかしを、空色晴れて沖つ辺に、千船行きかふ靄(もや)の裡(うち)。」「いろは、にほへとち、りぬるをわかよ、たれそ、つねならむ、うゐのおくやま、けふこ、えてあさき、ゆめみしゑひもせすん。」
「アオウエイ。カコクケキ。サソスセシ。タトツテチ。ナノヌネニ。ハホフヘヒ。マモムメミ。ヤヨユエイ。ラロルレリ。ワヲウヱヰ。」
アイウエオ。ヤイユエヨ。ワヰヱヲ。カキクケコ。サシスセソ。タチツテト。ナニヌネノ。ハヒフヘホ。マミムメモ。ヤイユエヨ。ラリルレロ。ワヰウヱヲ。五十九柱ぞ。此の巻 夜明けの巻とせよ。この十二の巻よく腹に入れておけば何でも判るぞ。無事に峠越せるぞ。判らん事は自分で伺へよ。それぞれにとれるぞ。天津日嗣皇尊(あまつひつぎすめらみこと)弥栄(やさか)いや栄(さか)。あら楽し、あら楽し、あなさやけ、あなさやけ、おけ。
一二三四五六七八九十百千卍(ひふみよいつむゆななやここのたりももちよろず)。
秋満つ日に、アメのひつ九かみしるす。
【現代語訳】
ああ楽しい、すがすがしい。新しい世は、朝も昼も夜も、常に晴れやかだ。ああ楽しい、すがすがしい、待ちに待った岩戸が開かれたのだ。 この神示でいう「民」とは、人間界のことだけではないぞ。神界、幽界のことも含めて知らせてあると申しただろう。取り違いと慢心が一番恐ろしいと申してあるだろう。 祭典の服装は、国民服やもんぺでも構わない。形式にこだわるな。天明(岡本天明)が行う祭りの真似をするな。役員は役員としての祭りをしなさい。余計なことは何も言うな。言ってよい時が来たら知らせる。わかったか。 祀る人がいなくなった宮は、あなたの土地の産土神社の横にいくらでもお祀りしてよいぞ。 天明はひたすら祈れ。祈れ。天に祈り、地に祈れ。潮が引く時には引き、満ちる時には進め。役員も大難が小難になるように祈れ。口先だけでなく、まことを込めて祈れ。祈らなければならないぞ。口先だけでは悪となる。わかったか。 今度の立て直しは、誰であっても「借銭(カルマ)」を返し終わるまでやめないから、その借銭がなくなるまで苦しい行をしなければならない。借銭がなくなった者でないと、新しい世の土の上には住めなくなるのだ。 やがて、「イシ(石・体)の人」「キ(木・気)の人」「ヒ(火・霊)の人」「ミヅ(水)の人」というように、それぞれの性質に応じて人々は分かれていくぞ。一時は、世の中がチリヂリバラバラになるのだから、その覚悟はよいか。毎度知らせてあることを忘れるな。神示を、腹の底まで染み渡るように読んでくれ。神は頼むぞ。 悟った者は、神示を解きなさい。そして人々に解き聞かせなさい。役員は皆、解きなさい。信じる者は皆、人々に知らせてやりなさい。神示を読んで嬉しかったなら、それを知らせてやれと申しただろう。 天明は神示を書記する役だ。アホになれと申しただろうが、まだまだだ。役員は気付かせてやれ。 「神示の代わりに、その身に直接知らせる」と申した時が来たぞ。いよいよの時だ。神示で知らせる段階の初めは済んだ。これからは、その身に直接知らせる。その身に聞かせる。聞かなければ、聞くようにしてでも知らせる。辛いだろうが我慢せよ。決して私利私欲を出してはならない。わかったか。 百姓にもなれ、大工にもなれ、絵描きにもなれ。何にでもなれるようにしてあるではないか。役員も同様だ。 「まどい(集団・教団)」を作るな。金を取るな。神にお供えされた物は、皆に分けて喜ばせてやれと申しただろう。この方(神)は、人々が喜ぶことが好きなのだ。好きなことは栄えるぞ。いや、栄える。 信者を作るな。「道」を伝えなさい。取り違いをせず、慢心せず、生まれたばかりの赤子のような素直な心で神示を読め。神示を心からいただきなさい。 日本の民が皆、勇み立つように祈ってくれ。世界の人民が皆、喜ぶ世が来るように祈ってくれ。天詞様をお祀りしなさい。ミコト(神の言葉)に従いなさい。このことさえ出来れば、他に何もわからなくても峠は越せるぞ。 民よ、小さな「いのち(我欲)」を捨てて、大いなる「生命(神のいのち)」に生きよ。 「鳥鳴く声す 夢さませ、見よ あけ渡るひむかしを、空色晴れて沖つ辺に、千船行きかふ靄(もや)の裡(うち)。」 「いろはにほへと…」 (アオウエイ、アイウエオの五十音の言霊が続く) 五十九柱の神々であるぞ。この巻を「夜明けの巻」とせよ。この第十二巻をよく腹に入れておけば、何でもわかり、無事に峠を越せるぞ。わからないことは、自分で神に伺いなさい。それぞれに必要な答えが得られるだろう。 天津日嗣皇尊、弥栄、いや栄。 ああ楽しい、ああ楽しい、ああすがすがしい、ああすがすがしい。おけ。 (ひふみよ…の数霊が続く) 秋が満ちる日、アメのひつ九のかみ、記す。
【AIによる解釈】
この巻の最終帖であり、集大成とも言える非常に重要な帖です。「夜明けの巻」という巻名の通り、新しい世の到来を宣言し、そのための最終的な心構えと実践方法を多岐にわたって説いています。
- 意識の次元上昇: 「朝も昼も夜も晴れたり」とは、三次元的な時間や対立(光と闇、善と悪)を超越した、常に調和に満ちた高次元の世界観を示しています。
- カルマの清算: 「借銭済し」という厳しい言葉で、個人の過去からのカルマ(業)を完全に清算しなければ、新しい時代には進めないことを明言しています。そのための「苦行」は避けられないとされています。
- 魂の選別: 「イシ・キ・ヒ・ミヅの人」と人々が分かれるという記述は、魂の性質や目覚めの度合いによって、進む道が分かれていく「篩い分け」が行われることを示唆しています。
- 伝達方法の変化: これまでの「神示(文字)」による伝達から、「ミ身に知らす(直接体験・直感)」段階へと移行したことを宣言しています。これは、いよいよ頭の理解ではなく、魂の覚醒が問われる時代に入ったことを意味します。
- 行動指針の集大成: 「信者つくるな、道伝へよ」「金とるな」「生まれた赤児の心で」「いのち捨てて生命に生きよ」など、これまでの教えを再度凝縮して示しています。特定の組織や教団を作ることなく、個々人が純粋な心で真理の道を伝え、実践することの重要性を説いています。
- 言霊の力: 最後に多くの祝詞や言霊が記されているのは、これらの言葉自体が世界を浄化し、新しい秩序を創造する力を持っていることを示しています。理屈を超えた言霊の響きこそが、夜明けをもたらす最終的な鍵となるのです。
総じてこの第十三帖は、新しい時代の入り口に立った人々への、最後の念押しであり、具体的な行動を促す力強いメッセージとなっています。困難を乗り越えた先にある、光り輝く喜びの世界を明確に示し、それに向かうための覚悟と実践を求めています。
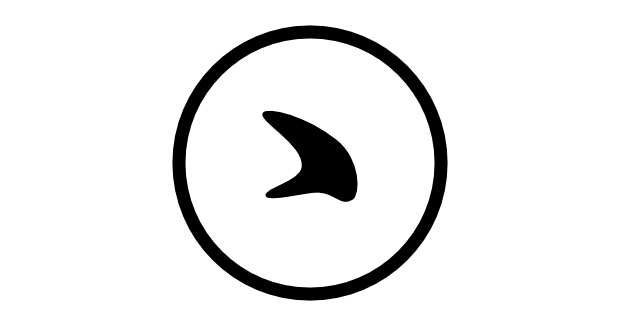





コメント