(昭和20年6月17日 – 7月19日)
この「松の巻」は、太平洋戦争終結直前の昭和20年6月17日から7月19日にかけて降ろされた神示です。敗戦が目前に迫る緊迫した状況下で、戦後の世界の大きな立て替え(大洗濯)と、それに臨む人々の心構えが、より具体的かつ厳しく説かれています。
第一帖 (二九二)
【原文】
富士は晴れたり世界晴れ。三千世界一度に晴れるのざぞ。世の元の一粒種の世となったぞ。松の御代となったぞ。世界ぢうに揺すりて眼覚ますぞ。三千年の昔に返すぞ。煎り豆 花咲くぞ。上下ひっくり返るぞ。水も洩らさん仕組ぞ。六月十七日、あめのひつ九のか三。
【現代語訳】
日本の象徴である富士が晴れれば、全世界が晴れ渡る。三千世界(全宇宙)が一度に晴れやかになるのだ。世の根源である神の民が中心となる世となったのだ。永遠に変わらない松の世が来たのだ。世界中を揺さぶって人々を目覚めさせるぞ。三千年の昔のような素朴で神に近い世に戻すのだ。不可能だと思われていたこと(煎り豆に花が咲くこと)が実現するぞ。社会の上下関係がすっかりひっくり返るぞ。この計画は水一滴も漏らさない完璧な仕組みなのだ。
【AIによる解釈】
この帖は、来るべき新時代の幕開けを宣言しています。「富士は晴れたり世界晴れ」とは、日本の霊的な中心である富士山が清められることが、全世界の平和と調和に繋がるという考え方を示します。「松の御代」は、常に緑を保つ松のように、永遠に変わらない真理に基づいた世界の到来を象徴しています。「煎り豆に花が咲く」「上下ひっくり返る」といった表現は、常識や既存の価値観が根底から覆る、奇跡的で革命的な大転換が起こることを示唆しています。これは単なる社会変革に留まらず、霊的な次元での大いなる刷新を意味していると言えるでしょう。
第二帖 (二九三)
【原文】
神の国を、足の踏むところない迄にけがして仕舞ふてゐるが、それで神力は出ぬぞ。臣民無くなるぞ。残る臣民 三分むつかしいぞ。三分と思へども、二分であるぞ。邪魔せん様に、分らん臣民 見物して御座れ。ここまで知らして眼覚めん臣民なら手引いて見てゐて御座れ。見事仕上げて見せるぞ。雀ちうちう烏かうかう。六月十八日、あめのひつ九か三。
【現代語訳】
神の国(日本)を、足の踏み場もないほどに穢してしまっているが、それでは神の力は発揮されないぞ。国民はいなくなってしまうぞ。生き残る民は三割もおぼつかない。三割かと思っても、実際は二割程度であろう。邪魔をしないように、理解できない人々はただ見物していなさい。ここまで知らせても目覚めない人々ならば、手を引いて(安全な場所で)見ていなさい。見事に(世の建て替えを)仕上げてみせるぞ。雀はチュウチュウ、烏はカウカウと鳴いている(時は来ている)。
【AIによる解釈】
人々の心の荒廃が神の国の穢れに繋がり、神の力が発揮できない原因であると指摘しています。「残る臣民 三分むつかしいぞ」という厳しい言葉は、来るべき大峠(大試練)を乗り越えるためには、根本的な改心が不可欠であり、それができる者が極めて少ないことを示しています。しかし、無理に理解させようとはせず、「見物して御座れ」と突き放すような表現は、最終的には神の計画が絶対的に実行されるという自信の表れです。個人の選択が厳しく問われる時代が来ることを警告しています。
第三帖 (二九四)
【原文】
神烈しく、人民静かにせよ。云ふた事 必ず行はねばならんぞ。天から声あるぞ、地から声あるぞ。身魂磨けばよくわかるのざぞ。旧九月八日までにきれいに掃除しておけよ。残る心 獣ぞ。神とならば、食ふ事も着る事も住む家も心配なくなるぞ。日本晴れとはその事ざぞ。六月十九日、あめのひつ九のかみ。
【現代語訳】
神の働きは激しくなるから、人々は心を静かに保ちなさい。言われたことは必ず実行しなければならないぞ。天からも地からも声(啓示)がある。身魂を磨けば、それがよく分かるようになるのだ。旧暦の九月八日までに(身魂を)きれいに掃除しておきなさい。それでも残る我欲の心は獣と同じだ。神の心に立ち返れば、食べる物も着る物も住む家も、何も心配なくなるのだ。本当の「日本晴れ」とは、そのように心が晴れ渡る状態のことを言うのだ。
【AIによる解釈】
社会が激動する中で、人々が取るべき姿勢を説いています。「神烈しく、人民静かにせよ」とは、外の世界がどれだけ荒れようとも、内なる心を静かに保ち、神の計画に信頼を寄せよという教えです。「旧九月八日」という具体的な期日を示し、それまでに身魂(心・精神)の浄化、すなわち改心を終えるよう促しています。物質的な心配事からの解放は、霊的な成長の先にあると説き、真の安心立命は神への完全な帰依によって得られることを示しています。
第四帖 (二九五)
【原文】
幾ら誠申してもまことは咽喉へつかへて呑み込めぬから、誠の所へは人民なかなか集まらんなれど、今度の御用は臣民 沢山は要らんぞ。何もかも神が仕組みてゐるのざから、人民仕様とて何も出来はせんぞ、神の気概に叶はん人民は地の下になるのざぞ。神示わからねば一度捨てて見るとわかるのざぞ。六月二十日、アメのひつ九のかミ。
【現代語訳】
いくら真実を説いても、本当のことは喉につかえて飲み込めないものだから、真理の場所へは人々はなかなか集まってこない。しかし、今度の神の御用は、多くの人々は必要ないのだ。何もかも神が計画しているのだから、人間がやろうとしても何も出来はしない。神の意に沿わない人々は、地の底へ行くことになるのだ。この神示が理解できなければ、一度(自分の知識や常識を)捨ててみると、かえって分かるようになるものだ。
【AIによる解釈】
真理が必ずしも大衆に受け入れられるものではないという現実を指摘しています。しかし、神の計画の遂行は、人の数や同意に左右されるものではないと断言します。人間の小賢しい計画や努力は無力であり、神の大きな流れに従うことの重要性を説いています。「神示わからねば一度捨てて見る」という一節は、既存の価値観や知識、固定観念(我)を捨て去ること(自己否定)が、真理を理解するための鍵であるという、逆説的ながらも深い霊的洞察を示しています。
第五帖 (二九六)
【原文】
この先どうしたらよいかと云ふ事は、世界中 金(かね)の草鞋(わらじ)で捜しても九九(ここ)より他 分からんのざから、改心して訪ねて御座れ。手取りてよき方に廻してやるぞ。神の国の政治は、もの活かす政治と申してあろが、もの活かせば、経済も政治も要らんぞ。金もの云ふ時から、物もの云ふ時来るぞ。誠もの云う時来るぞ。石もの云ふ時来るぞ。六月二十一日の朝、アメのひつ九のかみ神示。
【現代語訳】
この先どうしたら良いかということは、世界中を金の草鞋で探し回っても、ここ(この神示)以外では分かりはしないのだから、改心して訪ねて来なさい。手を取って良い方向へ導いてやろう。神の国の政治とは、万物を活かす政治だと申してあるだろう。万物を活かせば、今のよう経済や政治は必要なくなるのだ。金が力を持つ時代から、物が力を持つ時代が来る。そして誠(まこと)が力を持つ時代が来る。やがては石ころのようなものまでが意味を持つ時代が来るのだ。
【AIによる解釈】
真の道筋がこの神示にしかないという強い自負を示すと共に、「改心」を条件に救済の道が開かれることを示しています。そして、来るべき世界の価値観の根本的な転換を予言しています。「金」に象徴される物質主義・資本主義が終わりを告げ、生命や実体を持つ「物」、そして人間の内なる真実である「誠」、さらには「石」のような無機物に至るまで、万物がその本来の価値を発揮し、相互に活かし合う時代が来ることを示唆しています。これは、現代の経済や政治システムを超えた、全く新しい調和の世界観です。
第六帖 (二九七)
【原文】
今の世に出てゐる守護神、悪神を天の神と思ってゐるから なかなか改心むつかしいぞ。今迄の心すくりとすてて生れ赤子となりて下されと申してあろが。早よ改心せねば間に合はん、残念が出来るぞ。この神示わからんうちから、わかりておらんと、分りてから、分りたのでは、人並ざぞ。地の規則 天の規則となる事もあるのざぞよ。六月二十二日、アメのひつ九のかみふで。
【現代語訳】
今の世に現れている守護神や悪神を、本当の天の神だと思い込んでいるから、なかなか改心するのは難しいのだ。今までの心をすっぱりと捨てて、生まれたての赤子のような素直な心になってくれと申してあるだろう。早く改心しないと間に合わなくなり、残念な結果になるぞ。この神示は、理解できないうちから信じているのでなければならない。理解できてから信じたのでは、人並みの信仰にすぎない。地上のルールが天のルールとなることもあるのだよ。
【AIによる解釈】
人々が偽りの権威や神々を信じ込んでいることが、真の改心を妨げていると厳しく指摘しています。「生れ赤子となりて」とは、全ての先入観や知識を捨て、純粋で素直な心に立ち返ることを求めています。また、「わからんうちから、わかりておらんと」という一節は、人間の知性や理解を超えた、絶対的な信頼(信仰)の重要性を説いています。論理で理解してから信じるのではなく、直感と魂で受け入れることの価値を強調しており、霊的な目覚めにおける飛躍を促す言葉です。
第七帖 (二九八)
【原文】
偉い人 皆 俘虜(とりこ)となるぞ。夜明け近くなったぞ。夜明けたら何もかもはっきりするぞ。夜明け前は闇より暗いぞ、慌てるでないぞ。神の国一度負けた様になって、終ひには勝ち、また負けた様になって勝つのざぞ。腹の中のゴモク一度に引張り出してもならぬし、出さねば間に合わんし、いよいよ荒事にかかるから そのつもりで覚悟よいか。わからん人民 退いて邪魔せずに見物してござれよ。六月二十三日、アメのひつ九の。
【現代語訳】
社会的に偉いとされている人々は皆、捕虜となるぞ。夜明けが近くなった。夜が明ければ何もかもはっきりと分かるようになる。しかし、夜明け前は闇夜よりも暗いものだ。慌ててはいけないぞ。神の国(日本)は一度負けたようになり、最終的には勝つのだ。そしてまた負けたようになって勝つのだ。(世の中の膿を)一度に全部引っ張り出してはならないし、かといって出さなければ間に合わない。いよいよ荒療治にかかるから、そのつもりで覚悟はできているか。分からない人々は、退いて邪魔をせずに見物していなさい。
【AIによる解釈】
戦争末期の日本の状況を的確に予言している帖です。「偉い人 皆 俘虜となる」は、指導者層の失脚や戦犯としての追求を暗示しています。「夜明け前は闇より暗い」とは、終戦間際の最も苦しい状況を指し、その後の混乱期を乗り越えるための心構えを説いています。「一度負けた様になって、終ひには勝ち」という有名な一節は、軍事的な敗北の後に、日本が霊的・文化的に世界の中心として甦るという、逆転のシナリオを示唆しています。これから起こる大浄化(荒事)の厳しさと、それに対する覚悟を強く問いかけています。
第八帖 (二九九)
【原文】
神の国には昔から神の民より住めんのであるぞ、幽界(がいこく)身魂は幽界(がいこく)行き。一寸の住むお土も神国にはないのざぞ。渡れん者が渡りて穢して仕舞ふてゐるぞ。日本の人民、大和魂 何処にあるのざ、大和魂とは神と人と解け合った姿ぞ。戦いよいよ烈しくなると、日本の兵隊さんも、これは叶はんと云ふ事になり、神は此の世にいまさんと云ふ事になって来るぞ。それでどうにもこうにもならん事になるから、早よう神にすがれと申してゐるのぞ。誠ですがれば、その日からよくなるぞ、神力現れるぞ。今度の建替は、此の世 初まってない事であるから、戦ばかりで建替出来んぞ。世界隅々まで掃除するのであるから、どの家もどの家も、身魂も身魂も隅々まで生き神が改めるのざから、辛い人民 沢山出来るぞ。ミタマの神がいくら我張っても、人民に移っても、今度は何も出来はせんぞ。世の元からの生神でない事には出来ないのであるぞ。それで素直に言ふ事聞けとくどう申すのぞ、今度は神の道もさっぱりとつくりかへるのざぞ。臣民の道は固(もと)より、獣の道もつくりかへぞ。戦の手伝い位 誰でも出来るが、今度の御用はなかなかにむつかしいぞ。赤いものが赤い中にゐると色無いと思ふのぞ、気付けて呉れよ。悪神の守護となれば自分で正しいと思ふ事、悪となるのざぞ。悪も改心すれば助けてやるぞ。海の御守護は竜宮のおとひめ様ぞ。海の兵隊さん竜宮のおとひめ殿まつり呉れよ。まつわり呉れよ。竜宮のおとひめ殿の御守護ないと、海の戦は、けりつかんぞ。朝日照る夕日たださす所に宝いけておいてあるぞ。宝 愈々世に出るぞ。人民の改心第一ぞ。顔は今日でも変るぞ。民の改心なかなかぞ。六月二十三日、アメのひつ九のかみ。
【現代語訳】
神の国には本来、神の民しか住めないのだ。外国の魂は外国へ行くのが道理だ。神の国には一寸たりとも住む土地はないのだ。本来日本に来るべきでない者が渡って来て穢してしまっている。日本の人々よ、大和魂はどこにあるのか。大和魂とは、神と人とが一体となった姿のことだ。戦がいよいよ激しくなると、日本の兵隊も「これは敵わない」となり、「神などこの世にはいないのだ」と思うようになってくる。それでどうにもならない事態になるから、早く神にすがりなさいと申しているのだ。誠の心ですがるなら、その日から状況は良くなり、神の力が現れるぞ。今度の建て替えは、この世が始まって以来のことであり、戦争だけで建て替えができるものではない。世界の隅々まで掃除をするのだから、どの家も、どの人の身魂も、隅々まで生きた神が改めていくのだ。だから辛い思いをする人々が沢山出てくるぞ。そこらの神がいくら我を張って人間に憑依しても、今度は何もできはしない。世の根源からの生きた神でなければ、この御用はできないのだ。だから素直に言うことを聞けと、くどく言っているのだ。今度は神の道もすっかりと作り替える。人々の道はもちろん、獣の道も作り替えるのだ。戦争の手伝いぐらいは誰にでもできるが、今度の神の御用はなかなか難しいぞ。赤い色の物が赤い光の中にいると、自分に色がないと思ってしまうものだ。そのことに気づいてくれよ。悪神の守護を受けると、自分では正しいと思っていることが、実は悪になってしまうのだ。悪も改心すれば助けてやる。海の守護は竜宮の乙姫様であるぞ。海の兵隊さんたちは、竜宮の乙姫様を祀りなさい。頼りにしなさい。竜宮の乙姫様の御守護がなければ、海の戦は決着がつかないぞ。朝日が照り、夕日がまっすぐに射す所に宝を埋けてある。その宝がいよいよ世に出るぞ。人々の改心が第一だ。人の顔つきは今日にでも変わるが、民全体の改心はなかなか進まないものだ。
【AIによる解釈】
非常に多岐にわたる重要な内容を含む帖です。
- 魂の選別: 「幽界(がいこく)身魂は幽界(がいこく)行き」とし、魂の本来の所属に従って住む場所が定められる、霊的な国分けが起こることを示唆します。
- 大和魂の真義: 大和魂を、単なる精神論ではなく「神と人とが解け合った姿」と定義し、神人合一の境地を説いています。
- 信仰の危機と復活: 戦争の敗北により、人々が神を見失う絶望的な状況を予言し、そこから誠の心で神に立ち返ることの重要性を強調しています。
- 根本的な大掃除: 今度の建て替えが、戦争という物理現象に留まらず、全世界の全存在(家、身魂、神の道、獣の道に至るまで)を対象とした、根源神による霊的な大掃除であることを明かしています。
- 自己認識の重要性: 「赤いものが赤い中にゐる」という比喩は、自分が置かれている環境や思想に染まっていると、その異常さに気づけないという警告です。悪に染まれば、悪事を正しいことと信じ込んでしまう危険性を指摘しています。
- 海の守護神: 具体的に「竜宮のおとひめ様」の名を挙げ、海の守護を願うことの重要性を説いています。これは自然神への信仰回帰を促すものであり、特に制海権が戦争の鍵を握っていた当時の状況を反映しています。
第九帖 (三〇〇)
【原文】
悪のやり方は始めはどんどん行くなれど、九分九厘でグレンぞ、善のやり方 始め辛いなれど先行く程よくなるぞ。この世に何一つ出来んと云ふことない此の方のすることぞ。云ふ事聞かねば、きく様にしてきかすぞ。因縁だけのことはどうしてもせねば、今度の峠は越せんのざぞ。ここの役員は皆因縁ミタマばかり、苦労しただけお蔭あるぞ。六月二十四日、あめのひつ九のかみしるす。
【現代語訳】
悪のやり方は、初めはどんどん上手くいくように見えるが、九分九厘まで来たところでひっくり返るのだ。善のやり方は、初めは辛いが、進めば進むほど良くなっていく。この世に出来ないことは何一つない、この神(私)がやることなのだから。言うことを聞かなければ、聞くようにしてでも聞かせるぞ。各自が背負った因縁を解消するための行いは、どうしても果たさなければ、今度の大峠は越えられないのだ。ここに集まっている役員は皆、深い因縁を持つ魂ばかりだ。苦労した分だけ、後に御利益があるぞ。
【AIによる解釈】
善と悪のプロセスの違いを明確に説いています。悪は短期的に成功するように見えても最終的には破綻し、善は地道で苦労が多くても最終的には報われるという、普遍的な法則を示しています。また、「因縁だけのことはどうしてもせねば」という言葉は、個人が過去世から背負ってきた課題(カルマ)と向き合い、それを解消することの重要性を強調しています。苦労や困難は、魂を磨き因縁を解消するための試練であり、それを乗り越えた先には大きな恵みがあることを約束し、御用に関わる人々を励ましています。
第十帖 (三〇一)
【原文】
今度 役目きまったら、末代続くのざぞ、神示に出た通りの規則となるぞ。善も末代ぞ、悪も末代ぞ。此の世は一(ひとつ)であるぞ。われの身体われに自由にならぬ時来たぞ。神に縋(すが)るより仕方なくなって、すがったのでは、間に合はんぞ。今度はいろはの世に戻すぞ。ひふみの世に戻すぞ。素直にすればタマ入れかへて、よい方に廻してやるぞ。よろこびの身といたしてやるぞ。六月二十四日、あめのひつ九のかみしるす。
【現代語訳】
今度、役目が決まったら、それは末代まで続くのだ。この神示に示された通りの規則が世界の決まりとなる。善を行えば善が末代まで、悪を行えば悪が末代まで続くのだ。この世は全てが繋がった一つなのだ。自分の体が自分の思い通りにならなくなる時が来たぞ。いよいよ追い詰められて、神にすがるしかなくなってからすがったのでは、間に合わないのだ。今度は物質中心(いろは)の世から、精神・霊性中心(ひふみ)の世に戻すのだ。素直な心になれば、魂を入れ替えて良い方向へ導いてやろう。喜びに満ちた身の上にしてやるぞ。
【AIによる解釈】
新しい時代の厳格さと、そこでの決断の重大さを説いています。「役目きまったら、末代続く」とは、これからの選択が個人の魂の未来を永続的に決定づけることを意味します。「いろはの世」が物質や形に囚われた世界、「ひふみの世」が霊性や根源に繋がる世界を象徴しており、価値観の根本的な転換が起こることを示しています。「われの身体われに自由にならぬ時」とは、大災害や疫病などで、個人の力が及ばない状況に陥ることを暗示しているかもしれません。追い詰められる前に、自らの意志で素直に神に向かうことの重要性を説き、その先にある「よろこびの身」という希望を提示しています。
第十一帖 (三〇二)
【原文】
今の法律 此の方嫌ひぢゃ、嫌ひのもの無くするぞ。凝り固まると害(そこな)ふぞ。此の道 中行く道と申してあるが、あれなら日津久の民ぞと世間で云ふ様な行ひせねばならんぞ。神の国と申すものは光の世、よろこびの世であるぞ。虫けらまで、てんし様の御光に集まるよろこびの世であるぞ。見事 此の方についてご座れ。手引ぱって峠越さしてやるぞ。六月二十五日、あめのひつぐのかみ。
【現代語訳】
今の人間が作った法律は、私(神)は嫌いだ。嫌いなものは無くしてしまうぞ。何事も凝り固まると害になる。この道は、偏らない中庸の道だと申してあるが、世間の人々から「あれこそが日津久(ひつく)の民だ」と言われるような、立派な行いをしなければならないぞ。神の国というのは、光に満ちた世、喜びに満ちた世のことである。虫けらのような小さな命までが、てんし様(天皇・中心者)の御光に集まってくるような、喜びの世なのだ。見事に私について来なさい。手を取って、この大峠を越えさせてやろう。
【AIによる解釈】
人間が作った不自然な法や制度(今の法律)を否定し、より自然で普遍的な法則に基づいた世界への移行を示唆しています。「凝り固まると害ふ」とは、柔軟性を失った組織や考え方が崩壊することを示しており、これは現代社会への警告ともとれます。「中行く道」と、他者から手本とされるような「行ひ」を求め、信仰が観念だけでなく、日々の実践によって示されるべきことを強調しています。そして、新しい神の国が、一部の人間だけでなく、虫けらに至るまでの全ての生命が歓喜する、絶対的な調和と光に満ちた世界であることを示し、そこへ導くという力強い約束を与えています。
第十二帖 (三〇三)
【原文】
前にも建替はあったのざが、三千世界の建替ではなかったから、どの世界にでも少しでも曇りあったら、それが大きくなって、悪は走れば苦労に甘いから、神々様でも、悪に知らず知らずなって来るのざぞ。それで今度は元の生神が天晴れ現はれて、悪は影さへ残らぬ様、根本からの大洗濯するのぞ、神々様、守護神様、今度は悪は影も残さんぞ。早よう改心なされよ。建替の事 学や智では判らんぞ。六月二十八日、あめのひつくのかみ。
【現代語訳】
以前にも世の建て替えはあったのだが、それは全宇宙的な建て替えではなかった。だから、どの世界にでも少しでも曇り(不調和)が残っていると、それがだんだん大きくなってしまう。悪は勢いづくと甘い汁を吸えるので、神々でさえ、知らず知らずのうちに悪に染まってしまうことがあるのだ。だからこそ今度は、根源の生きた神が堂々と現れて、悪は影さえ残らないように、根本からの大洗濯をするのだ。神々や守護神たちよ、今度は悪の痕跡も残さない。早く改心なさい。この建て替えのことは、人間の学問や知恵では到底理解できないぞ。
【AIによる解釈】
今回の「世の建て替え」が、過去のそれとは規模も次元も全く異なる、宇宙的で根本的なものであることを強調しています。小さな悪の芽が、やがては神々の世界さえも蝕むことを指摘し、その根本原因を断つための「大洗濯」であると説きます。これは人間だけでなく、霊界にいる神々や守護神に対しても向けられた、極めて厳しい改心の要求です。そして、この天変地異とも言えるような大計画は、人間の理性や科学的知識(学や智)の範疇を完全に超えた、神の領域の出来事であることを明確に告げています。
第十三帖 (三〇四)
【原文】
この世界は浮島であるから、人民の心通り、悪くもなりよくもなるのざぞ。食ふ物ないと申して歩き廻ってゐるが、餓鬼に喰はすものは、もういくら捜してもないのぞ。人は神の子ざから食ふだけのものは与へてあるぞ。神の子に餓死(うえじに)はないぞ。いやさかのみぞ。此処は先づ世界の人民の精神よくするところであるから、改心せねばする様いたすぞ、分らんのは我かまうひと慢心してゐるからぞ。旧五月十六日、あめのひつ九の。
【現代語訳】
この世界は、人々の心の状態を映し出す浮島のようなものだから、人々の心がけ次第で悪くも良くもなるのだ。食べる物がないと言って歩き回っているが、餓鬼(飽くなき欲望を持つ者)に与える食べ物は、もういくら探してもないのだ。人は神の子なのだから、生きていくのに必要な分は必ず与えられている。神の子が餓死することはない。弥栄(いやさか)あるのみだ。ここはまず、世界中の人々の精神を良くするための場所であるから、自ら改心しないなら、改心するように仕向けるぞ。それが分からないのは、我を立て、傲慢になっているからだ。
【AIによる解釈】
世界の現状は人々の集合的な意識の反映であるという「心の世界」の法則を説いています。食糧難などの物質的な欠乏は、実は人々の内面的な欠乏(我欲、餓鬼の心)が原因であると指摘します。「神の子に餓死はない」という言葉は、神への信頼に立ち返り、分相応の生き方をすれば、必要なものは必ず与えられるという霊的な真理を示しています。それでも改心しない者に対しては、強制的にでも改心させるという厳しい姿勢を示しており、個人の「我」や「慢心」を打ち砕く出来事が起こることを暗示しています。
第十四帖 (三〇五)
【原文】
裏切る者 沢山出てくるぞ、富士と鳴門の仕組、諏訪(スワ)マアカタの仕組。ハルナ、カイの御用なされよ。悪の総大将よ、早よ改心なされ、悪の神々よ、早よ改心結構であるぞ。いくら焦りてあがいても神国の仕組は判りはせんぞ。悪とは申せ大将になる身魂、改心すれば、今度は何時迄も結構になるのぞ。日本の臣民人民 皆思ひ違ふと、くどう知らしてあろが。まだ我捨てぬが、水でも掃除するぞ。六月二十九日、あめのひつぐのかみ神示。
【現代語訳】
裏切る者が沢山出てくるぞ。富士と鳴門の仕組み、諏訪とマアカタの仕組みを進めなさい。榛名(ハルナ)、甲斐(カイ)での御用をしなさい。悪の総大将よ、早く改心しなさい。悪の神々よ、早く改心すれば結構なことになるのだぞ。いくら焦ってあがいても、神の国の仕組みは分かりはしない。悪とはいえ、大将になるほどの力を持つ魂なのだから、改心すれば、今度はいつまでも素晴らしい存在となれるのだ。日本の国民は皆、思い違いをしていると、くどく知らせてあるだろう。まだ我を捨てないなら、水を使っても掃除をするぞ。
【AIによる解釈】
試練の時において、人間の離反や裏切りが多発することを警告しています。同時に「富士」「鳴門」「諏訪」など、具体的な地名を挙げて、そこで進められるべき神聖な計画(仕組)があることを示唆しています。特筆すべきは、単に悪を滅ぼすのではなく、「悪の総大将」や「悪の神々」に対して改心を呼びかけている点です。悪の力も元は神の力の一部であり、改心すれば大きな善の力に転化できるという、包括的な愛と救済の思想が根底にあります。「水でも掃除するぞ」という一文は、大雨や洪水といった水害による浄化が起こる可能性を強く暗示しています。
第十五帖 (三〇六)
【原文】
この神示うぶのままであるから、そのつもりで、とりて呉れよ。嘘は書けん根本ざから此の神示通りに天地の規則きまるのざぞ、心得て次の世の御用にかかりて呉れよ。世界の事ざから、少し位の遅し早しはあるぞ。間違ひない事ざぞ。大将が動く様では、治まらんぞ。真中動くでないと申してあろが、此の世の頭から改心せねば、此の世 治まらんぞ。此の方頼めばミコトでおかげやるぞ。竜宮のおとひめ殿 烈しき御活動ぞ。六月三十日、あめのひつぐのかみしるす。
【現代語訳】
この神示は、何の脚色もない生まれたままの真実であるから、そのつもりで受け取ってくれ。嘘は書けない根源からの言葉だから、この神示の通りに天地の法則が決まるのだ。それを心に留めて、新しい世の御用にかかってくれ。世界全体のことだから、計画に多少の遅れや早まりはあるが、間違いなく起こることだぞ。大将(中心、指導者)が軽々しく動くようでは、世の中は治まらない。中心は動いてはならないと申してあるだろう。この世の指導者層から改心しなければ、この世は治まらないのだ。私(この神)に頼めば、ミコト(尊い働き)によって御利益を授けよう。竜宮の乙姫殿が、激しく活動されているぞ。
【AIによる解釈】
この神示が絶対的な真理であり、未来を決定づける設計図であることを宣言しています。計画の実行には多少の時間的なずれはあっても、その成就は確実であると強調します。「真中動くでない」とは、組織や国の中心にいる人物は、動揺せずどっしりと構えているべきだという戒めです。世の混乱を収拾するためには、末端からではなく、トップ(頭)からの改心が不可欠であると説いています。最後に再び「竜宮のおとひめ殿」の活発な働きに言及しており、自然界、特に海を司る神霊の力が、世の建て替えにおいて重要な役割を果たすことを示唆しています。
第十六帖 (三〇七)
【原文】
火と水と組み組みて地が出来たのであるぞ、地(つち)の饅頭(まんじゅう)の上に初めに生えたのがマツであったぞ。マツはもとのキざぞ、松植へよ、松供へよ、松ひもろぎとせよ、松玉串とせよ、松おせよ、何時も変らん松心となりて下されよ。松から色々な物生み出されたのぞ、松の国と申してあろが。七月一日、あめのひつ九のかみ。
【現代語訳】
火(カ)と水(ミ)が組み合わさって地(地球)ができたのだ。その大地の上に最初に生えたのが松(マツ)であった。マツは万物の元(もと)の木(キ)なのだ。松を植えなさい。松を神に供えなさい。松を神籬(ひもろぎ=神の依り代)としなさい。松を玉串として使いなさい。松を尊重しなさい。いつも変わらない松のような心(松心)になってください。松から色々なものが生み出されたのだ。日本は「松の国」だと申してあるだろう。
【AIによる解釈】
「松」が持つ霊的な重要性を集中的に説いた帖です。日本の創生神話とは異なる、独自の宇宙観(火水=カミ→地)を示し、その地上で最初に生まれた「松」を生命の根源的な象徴として位置づけています。「マツ」は神を「待つ」に通じ、また常緑であることから永遠性や不変性を象徴します。「松心となりて下されよ」とは、どのような状況でも変わらない真心や節操を持つことを人々に求めています。日本を「松の国」と呼び、松を植え、祀るという具体的な行為を推奨することで、国土の霊的な磁場を高め、神人和合の基礎を築くことを目指していると考えられます。
第十七帖 (三〇八)
【原文】
釈迦祀れ。キリスト祀れ。マホメット祀れ。カイの奥山は五千の山に祀り呉れよ。七月の十と二日に天晴れ祀りて呉れよ。愈々富士晴れるぞ。今の人民よいと思ってゐる事、間違ひだらけざぞ。此処までよくも曇りなされたな。二の山 三の山 四の山に祀り呉れよ。まだまだ祀る神様あるぞ。七月二日、あめのひつぐのかみ。
【現代語訳】
釈迦を祀りなさい。キリストを祀りなさい。マホメットを祀りなさい。甲斐(カイ)の奥山は五千の山に(彼らを)祀ってくれ。七月十二日に盛大に祀ってくれ。いよいよ富士が晴れ渡るぞ。今の人民が良いと思っていることは、間違いだらけだ。ここまでよくも(心が)曇ってしまったものだ。二の山、三の山、四の山にも祀ってくれ。まだまだ祀るべき神様はいるのだぞ。
【AIによる解釈】
特定の宗教や神に固執せず、世界の主要な宗教の教祖である釈迦、キリスト、マホメットを等しく祀るようにと命じている、非常に画期的な内容です。これは、全ての宗教の根源は一つであるという「万教帰一」の思想を明確に示しています。来るべき新しい時代は、宗教間の対立を超えて、全ての聖なるものを尊重し、統合する時代であることを示唆しています。「今の人民よいと思ってゐる事、間違ひだらけ」という言葉は、人々の常識や善悪の判断基準そのものが、根本から覆されることを警告しています。
第十八帖 (三〇九)
【原文】
人民同士の戦ではかなはんと云ふ事よく判りたであろがな。神と臣民融け合った大和魂でないと勝てんことぞ。悪神よ。日本の国を此処までよくも穢したな、これで不足はあるまいから、いよいよ此の方の仕組通りの、とどめにかかるから、精一杯の御力でかかりて御座れ。学問と神力の、とどめの戦ざぞ。七月三日、あめのひつ九のかみ。
【現代語訳】
人間同士の戦争では(本当の解決には)ならないということが、よく分かったであろう。神と人々が一体となった「大和魂」でなければ、本当の意味で勝つことはできないのだ。悪神よ。日本の国をここまでよくも穢してくれたな。もう不足はないだろうから、いよいよ私(神)の計画通りに、とどめを刺す段階に入る。精一杯の力でかかってきなさい。これは、人間の学問(知性)と神の力との、最終決戦なのだぞ。
【AIによる解釈】
通常兵器による戦争の限界と、霊的な次元での戦いの重要性を説いています。第八帖と同様に、「大和魂」を神と人が一体化した状態と定義し、それこそが真の勝利の鍵であるとします。そして、国を穢した「悪神」に対し、最終決戦の戦線布告をしています。この戦いを「学問と神力の、とどめの戦」と表現しているのが特徴的です。これは、唯物論や科学万能主義といった人間の知性(学問)と、目には見えない神の法則(神力)との、価値観を巡る最終戦争が始まることを宣言していると解釈できます。
第十九帖 (三一〇)
【原文】
改心次第で善の霊(れい)と入れ換へて、その日からよき方に廻してやるぞ。宵(よい)の明星(みょうじょう)が東へ廻ってゐたら、愈々だぞ。天の異変 気付けと、くどう申してあろがな。道はまっすぐに行けよ。寄り道するではないぞ。わき目ふると悪魔魅入るぞ。それも我れの心からざぞ。七月四日、あめのひつかくのかみ。
【現代語訳】
改心さえすれば、善の霊と入れ替えて、その日から良い方向へ導いてやるぞ。宵の明星(金星)が、明けの明星として東の空に見えるようになったら、いよいよその時だぞ。天の異変に気づけと、くどく言っておいただろう。道はまっすぐに進みなさい。寄り道をしてはならない。わき見をすると悪魔に魅入られてしまうぞ。それもまた、自分自身の心の隙から起こることなのだ。
【AIによる解釈】
個人の「改心」が、その人の守護霊さえも善いものに入れ替えるほどの力を持つことを示しています。これは、運命が決定論的なものではなく、自らの意志でいつでも好転させられるという希望のメッセージです。「宵の明星が東へ」という天体の運行を、時の到来の合図として示し、天の異変に注意を払うよう促しています。「道はまっすぐに行けよ」という教えは、神への道から外れず、脇道(誘惑や疑い)に逸れないことの重要性を説いています。悪魔に魅入られるのも、外的要因だけでなく、自らの心の隙や弱さが原因であるとし、内省の必要性を説いています。
第二十帖 (三一一)
【原文】
此処まで来れば大丈夫ざぞ。心大きく持ちて焦らずに御用せよ、饌(け)にひもじくない様、身も魂も磨いておけよ。もう何事も申さんでも、天と地にして見せてあるから、それよく見て、改心第一ぞ。悪は霊力が利かん様になったから最後のあがきしてゐるのざぞ。人助けておけば、その人は神助けるぞ。神界と現界の事この神示よく分けて読みて下されよ。これから愈々の御用あるぞ。皆の者も同様ぞ。七月五日、あめのひつくのかみ。
【現代語訳】
ここまで(神示を信じて)ついて来られたのなら大丈夫だ。心を大きく持って、焦らずに神の御用をしなさい。食物に困らないように、身体も魂も磨いておきなさい。もう何も言わなくても、天と地の様々な現象として(神の計画を)見せてあるから、それをよく見て、改心を第一としなさい。悪はもう霊的な力が効かなくなってきたので、最後のあがきをしているだけなのだ。人を助けておけば、その行いは巡り巡って神を助けることになるのだ。この神示は、神界のことと現界(人間界)のこととを、よく区別して読みなさい。これからいよいよ本格的な御用があるぞ。皆の者も同じだぞ。
【AIによる解釈】
厳しい警告が続いた中で、信じてついて来た者たちへの励ましと安堵を与える帖です。悪の力が衰え、最終段階に入ったことを告げ、焦らずに心構えを固めるよう指導しています。「天と地にして見せてある」とは、自然現象や社会情勢そのものが神からのメッセージであるという考え方を示しています。「人助けておけば、その人は神助けるぞ」という言葉は、利他の精神が最も尊い神事であることを説いています。また、神示を読む上での注意点として、神界の理と人間界の理を混同せず、注意深く読み解くよう促しており、神示の多次元的な構造を示唆しています。
第二十一帖 (三一二)
【原文】】
旧九月八日からの祝詞は初めに、ひとふたみ唱え、終りに百千卍(ももちよろず)宣(の)れよ。お神山(やま)作る時は、何方(どちら)からでも拝める様にしておけよ。一方から拝むだけの宮は我れよしの宮ぞ。何もかも変へて仕舞ふと申してあろうが。神徳貰へば何事も判りて来るのざぞ。要らんもの灰にするのざぞ。息乱れん様にせよ。七月七日、アメのひつくのかみ。
【現代語訳】
旧暦九月八日からの祝詞は、初めに「ひふみ祝詞」を唱え、終わりには「ももちよろず」と宣りなさい。御神体となる山を作る時は、どちらの方向からでも拝めるように作りなさい。一方からしか拝めないような宮は、自分さえ良ければよいという「我よし」の宮だ。何もかも変えてしまうと申してあるだろう。神からの徳をいただけば、何事も分かるようになってくる。要らないものは灰にしてしまうのだ。心の息が乱れないように、平静を保ちなさい。
【AIによる解釈】
具体的な祭祀の方法について述べられています。「ひふみ祝詞」という根源的な祝詞の重要性を示し、新しい祈りの形式を提示しています。「何方からでも拝める様」な神山という指示は、特定の方向や場所に縛られない、普遍的で開かれた信仰の形を象徴しています。既存の一方通行的な信仰のあり方(我れよしの宮)を否定し、全てが中心であり、全てが繋がっているという新しい時代の宗教観を示しています。「要らんもの灰にする」とは、物質的なものだけでなく、古い価値観や固定観念を焼き尽くし、浄化することの重要性を示唆しています。
第二十二帖 (三一三)
【原文】
世変りたら生命長くなるぞ。今迄 上にあがりて楽してゐた守護神は大峠越せん事になるぞ。肉体あるうちに改心しておかんと、霊になっての改心なかなかぞ。悪も御苦労の御役。此の方について御座れ。手引いて助けてやると申してあろが。悪の改心、善の改心、善悪ない世を光の世と申すぞ。七月八日、アメのひつくのかみ。
【現代語訳】
世の中が変わったら、人間の寿命は長くなるぞ。今まで人々の上に立って楽をしてきたような守護神は、今度の大峠を越えることができなくなる。肉体を持っている間に改心しておかないと、霊だけの存在になってからの改心は、なかなか難しいものだ。悪もまた、(人々を目覚めさせるための)御苦労な役回りなのだ。私(神)について来なさい。手を取って助けてやると申してあるだろう。悪が改心し、善も(善という概念に囚われず)改心した先にある、善悪の区別のない世界を「光の世」と呼ぶのだ。
【AIによる解釈】
新しい時代の様相と、そこに到達するための霊的な条件を説いています。「生命長くなる」とは、単なる長寿だけでなく、より質の高い、神に近い生命への進化を示唆しています。「上にあがりて楽してゐた守護神」への警告は、人間だけでなく霊的存在にも厳しい選別があることを示し、霊界の秩序も刷新されることを意味します。「悪も御苦労の御役」という一節は、悪を絶対的な敵として断罪するのではなく、神の大きな計画の中での一つの役割として捉える、非常に高い視点を示しています。最終的に目指すのは、善悪の二元論を超越した、絶対的な調和と愛に満ちた「光の世」であると宣言しています。
第二十三帖 (三一四)
【原文】
国々所々に、神人鳴り動く、道は世にひらき極む、日月地 更に交わり結び、その神々ひらき弥栄え、大地固成、まことの神と現はれ、正し、三神は世に出づ、ひふみと鳴り成るぞ。正しくひらけ弥栄へて更につきづ、鳴る道に成り、交わる。永遠の世光ることは永遠の大道、息吹き大地に充ち満つ道。展きてつきず、極まり成る神の道。苦しむ道をひらき、日月地に苦しむ喜び出で、神の国むつび、悉く歓喜弥栄ゆ。七月十日、あめのひつくのかみ。
【現代語訳】
(意味を汲み取った意訳) 国々のあちこちで、神と人が一体となって鳴り響き、動き始める。真実の道が世に開かれ、極まっていく。日(火)と月(水)と地が、さらに深く交わり結びつき、その働きによって神々は力を発揮して弥栄え、大地は固く定まる。まことの神が現れ、世を正し、根源の三神が世に出でて、「ひふみ」の理(ことわり)が鳴り響き、成就する。正しく道が開かれて弥栄え、尽きることなく、響き渡る道となり、交じり合う。永遠の世が光り輝くこと、それが永遠の偉大な道であり、生命の息吹が大地に満ち満ちる道である。どこまでも開かれて尽きることなく、極まり成就する神の道。苦しみを経て道は開かれ、日月地は苦しみの中に喜びを見出し、神の国は和合し、ことごとくが歓喜の中に弥栄えるのだ。
【AIによる解釈】
この帖から二帖は、これまでの口語的な神示とは異なり、漢文調の詩的な表現で、新時代の到来の様子が荘厳に描かれています。「神人鳴り動く」「日月地 更に交わり結び」といった言葉は、神と人、天と地が一体となって新しい世界を創造していくダイナミックなビジョンを示しています。「苦しむ道をひらき」「苦しむ喜び出で」という表現は、大いなる苦しみを経てこそ、真の喜びと新しい世界が開かれるという、産みの苦しみの重要性を説いています。これは、単なる予言を超えた、新しい世界の創造原理を謳い上げた祝詞とも言えるでしょう。
第二十四帖 (三一五)
【原文】
早く早くと申せども、立体の真道に入るは、小我(われ)死なねば、大我(われ)もなき道ぞ、元栄えひらき鳴る神、元にひらき成る神、元津神日の神、極みきわまりて足り いよいよ月の神はらみ交わりさかゆ、成りむつび、神々極まるところ、ひふみ、よろづ、ち、ももと、ひらく、歓喜の大道、神々更に動きひらき栄ゆ。元津神のナルトの秘密、永遠に進み、いき、ひらき極む。元津大神かくりみ、次になる神かくりみのナルトぞ、富士栄え、火の運動き、うづまき鳴り、極みに極みて、地また大地動き、うづまくぞ、真理なりて極まり、鏡の如くなり、極まりて、動きひらき、極まりて大道、遂に成るぞ。七月十日、あめのひつくのかみ。
【現代語訳】
(意味を汲み取った意訳) 早く早くと急かすけれども、立体的で真実の道に入るには、小さな我(エゴ)が死ななければ、大いなる我(真我)もないという厳しい道なのだ。根源が栄え、開き、鳴り響く神。根源において開き、成就する神。根源の神である日の神が極まり満ち足りると、いよいよ月の神がそれを受け容れて交わり栄え、結び和合する。神々の働きが極まるところ、「ひふみ、よろづ、ち、もも」と万物が開花し、歓喜の偉大な道が現れる。神々はさらに動き、開き、栄える。根源の神の「ナルト(鳴門)の秘密」は、永遠に進み、生き、開き、極まっていく。根源の大神が隠れ、次に現れる神が隠れる、そのナルト(渦)の仕組みなのだ。富士が栄え、火の働きが動き出し、渦を巻いて鳴り響き、極みに極まって、大地もまた動き、渦を巻くのだ。それが真理となって極まり、鏡のように澄みきった世界となり、その動きとひらきが極まって、偉大な道が遂に成就するのだ。
【AIによる解釈】
前帖に続き、非常に哲学的で深遠な内容です。「小我死なねば、大我もなき道」とは、エゴを完全に手放さない限り、本当の自己(ハイヤーセルフ)には到達できないという、悟りへの道筋を示しています。日の神(陽、火、男性原理)と月の神(陰、水、女性原理)の交わりと和合、そして「ナルト(鳴門)の秘密」という渦巻きのエネルギーが、世界創造の原動力であることが示唆されています。富士(火)と鳴門(水)は、神示全体を貫く重要なキーワードであり、この二つのエネルギーの螺旋状の結合が、新しい次元(立体的な真道)を開く鍵であると解釈できます。
第二十五帖 (三一六)
【原文】
ムからウ生れ、ウからム生れると申してあるが、ウム組み組みて、ちから生れるのざぞ。今度の大峠はムにならねば越せんのざぞ。ムがウざぞ。世の元に返すのぞと申してあろが。ムに返れば見えすくのざぞ。風の日もあるぞ。七月十一日、アメのひつくのかみ。
【現代語訳】
無(ム)から有(ウ)が生まれ、有(ウ)から無(ム)が生まれると申してあるが、その無と有が組み合わさって、力(エネルギー)が生まれるのだ。今度の大峠は、一度「無」にならなければ越えることはできないぞ。「無」こそが真実の「有」なのだ。世の根源の状態に返すのだと申してあるだろう。無の境地に返れば、全てのことが見え透くようになるのだ。風の強い日(試練)もあるぞ。
【AIによる解釈】
東洋哲学的な宇宙観を説いています。「ム(無)」を空っぽの状態ではなく、全てを生み出す可能性を秘めた根源的な状態として捉えています。「ウ(有)」は現象界の万物です。「ウム組み組みて、ちから生れる」とは、無と有のダイナミックな相互作用が、創造のエネルギーとなることを示しています。「大峠はムにならねば越せん」とは、大試練を乗り越えるためには、我欲、知識、財産、地位など、自分が執着している全てを一度手放し、空っぽ(無)になる覚悟が必要であるということです。しかしその「無」の状態こそが、全てと繋がった真実の「有」であり、そこに立つことで初めて本質を見抜くことができるようになると説いています。
第二十六帖 (三一七)
【原文】
カイ奥山開き結構々々。奥山 元ぞ。中山は介添(かいぞへ)ぞ。国々おつる隈(くま)なく つくり呉れよ。一の宮ばかりでないぞ。二の宮、三の宮、四の宮、五の宮、六の宮、七の宮まで、つくりてよいぞ。何処(いづこ)にも神まつれと申してあろが。てんし様まつれと申してあろが。まつり結構。まつればよろこぶこと出来るぞ。七月十三日、あめのひつくのかみふで。
【現代語訳】
甲斐(カイ)の奥山を開くこと、大変結構である。奥山が根源だ。中山はその補佐役である。国々、落ち度のないように隅々まで(祀る場所を)作ってくれ。格式の高い一の宮だけではないぞ。二の宮、三の宮、四の宮、五の宮、六の宮、七の宮まで、作ってよいのだ。どこにでも神を祀れと申しただろう。てんし様(天皇・中心)を祀れと申しただろう。祭事は結構なことだ。祀れば、喜ばしいことが起こるぞ。
【AIによる解釈】
神を祀る場所を、特定の聖地や格式の高い神社に限定せず、国土の隅々にまで広げることを奨励しています。これは、神が特定の場所にいるのではなく、万物に宿っているという汎神論的な考え方に基づいています。「一の宮ばかりでないぞ」という言葉は、既成の権威や序列に囚われず、人々の自発的な信仰心を重んじる姿勢を示しています。「まつり」は「政(まつりごと)」にも通じ、神を祀り、自然と調和することが、国を治める基本であるという古代日本の思想に繋がります。身近な場所で神や中心を祀る実践が、喜び(よきこと)を引き寄せる元になると説いています。
第二十七帖 (三一八)
【原文】
天も地も一つにまぜし大嵐、攻め来る敵は駿河灘(するがなだ)、富士を境に真二つ。先づ切り取りて残るもの、七つに裂かん仕組なり。されど日本は神の国。最後の仕組神力に、寄せ来る敵は魂まで、一人残らずのうにする。夜明けの御用つとめかし。晴れたる富士のすがすがし。七月十四日、あめのひつくのかみ。
【現代語訳】
天も地も一つに混ざったような大嵐が吹き荒れ、攻めてくる敵は駿河湾から上陸し、日本は富士山を境にして真っ二つに分断されるだろう。まず切り取られ、残ったものをさらに七つに引き裂こうという計画なのだ。しかし、日本は神の国である。最後の最後には神の力が発動し、寄せ来る敵は、その魂に至るまで一人残らず無力化してしまうのだ。さあ、夜明けの御用を務めなさい。その先には、晴れ渡った富士山の清々しい姿があるのだ。
【AIによる解釈】
終戦間際の日本の危機的状況を、極めて具体的に描写した予言です。「駿河灘」からの敵の上陸や「富士を境に真二つ」という表現は、当時計画されていた連合国軍のダウンフォール作戦(本土決戦)の内容と酷似しており、驚くべき具体性を持っています。国土が分断され、絶体絶命の危機に陥るが、最終的には人知を超えた「神力」によって、敵は魂レベルで無力化され、日本は救われるという劇的な逆転勝利が示されています。これは、物理的な戦闘の勝利ではなく、霊的な次元での日本の勝利を意味していると解釈されます。絶望的な状況の先にある、輝かしい「夜明け」への希望を力強く謳っています。
第二十八帖 (三一九)
【原文】
保食(うけもち)の神祀らづに、いくら野山拓いたとて、物作ることは出来ないぞ。煎(ゐ)り豆 花咲く目出度い時となってゐるのに何して御座るのぞ。いくら人民の尻叩いて野山切り拓いても食物三分むつかしいぞ。神々まつれと申してあろが、野拓く時は野の神まつれ。物作る時は保食の神まつれ。産土の神様にもお願ひしてお取次願はな何事も成就せんぞ。人民の学や智ばかりで何が出来たか。早よ改心第一ぞ。山も川も野も人民も草も木も動物虫けらも何もかも此の方の徳であるぞ。それぞれの御役あるのざぞ。学や智捨てて天にむかへ。地にむかへ、草にむかへ、生物にむかへ、木にむかへ、石もの云ふぞ。草もの云ふぞ。七月十八日、あめのひつくのかみ。
【現代語訳】
食物の神である保食神を祀らずに、いくら野山を切り拓いても、作物を育てることはできないのだ。煎り豆に花が咲くような、奇跡が起こるめでたい時が来ているというのに、一体何をしているのか。いくら人々の尻を叩いて野山を開発させても、食料を確保するのは三割もおぼつかないぞ。神々を祀りなさいと申してあるだろう。野を拓く時はその野の神を祀れ。作物を作る時は保食神を祀れ。その土地の産土神様にもお願いして、神々へのお取次ぎを願わなければ、何事も成就しない。人間の学問や知恵だけで、一体何ができたというのか。早く改心することが第一だ。山も川も野も、人も草木も動物も虫も、何もかもがこの神(私)の徳の現れなのだ。それぞれに役割がある。学問や知恵を一度捨てて、天に向かいなさい。地に向かいなさい。草に、生き物に、木に向かいなさい。そうすれば石がものを言う。草がものを言う(=万物の声が聞こえるようになる)。
【AIによる解釈】
食糧問題を通して、人間中心主義の限界と自然への畏敬の念を取り戻すことの重要性を説いています。人間の力(学や智)だけで食料を生産しようとする傲慢さを戒め、食物の神(保食神)、土地の神(野の神、産土神)への祈りと感謝が不可欠であると説きます。これは、現代の環境問題や食の安全に対する根源的な問いかけでもあります。万物が神の徳の現れであり、それぞれに役割があるという思想は、エコロジーやアニミズムに通じます。最後に「石もの云ふぞ。草もの云ふぞ」と、人間が謙虚になり、自然と対話できるようになることこそが、真の豊かさを取り戻す道であることを示唆しています。
第二十九帖 (三二〇)
【原文】
豊受の大神様お山の富士に祀り、箸供へてお下げした箸、皆に分けやれよ。饌(け)に難儀せん様 守り下さるぞ。仕組 少し早よなったから、かねてみしてあった事 八月八日から始め呉れよ。火(ひ)と水(み)に気付けよ。おろがめよ。キの御用大切ぞ。ケの御用大切ぞ。クの御用大切ぞ。神は気引いた上にも気引くから、とことんためすから、そのつもりで、お蔭落さん様にせよ。二十五柱 役員ぞ。慢心すればかへ身魂使ふぞ。この巻 松の巻。七月十九日、あめのひつぐのかみ。
【現代語訳】
豊受の大神様(食物の神)を富士山にお祀りし、お供えしたお箸を、お下げしてから皆に分け与えなさい。そうすれば食物に困らないように守ってくださるぞ。計画が少し早まったから、かねて知らせてあったことを、八月八日から始めてくれ。火と水(の災い)に気をつけなさい。拝みなさい。キ(木、気)の御用は大切だ。ケ(食)の御用は大切だ。ク(空、国)の御用は大切だ。神は念には念を入れて、とことんまで試すから、そのつもりで、御神徳を落とさないようにしなさい。二十五柱が役員であるぞ。慢心すれば、代わりの魂を使うことになるぞ。この巻は「松の巻」である。
【AIによる解釈】
「松の巻」の締めくくりとして、具体的な指示と最後の警告が与えられています。前帖に続き、食物の神である豊受大神を祀ることの重要性を説き、お箸という身近なものを通した御神徳の分配方法を示しています。「仕組 少し早よなった」「八月八日から始め呉れよ」という言葉は、いよいよ計画が最終段階に入り、具体的な行動を開始する時が来たことを告げています。これは、昭和20年8月6日の広島、9日の長崎への原爆投下、そして15日の終戦へと繋がる、歴史の大きな転換点が目前に迫っていることを示唆しているかのようです。「火と水に気付けよ」は、原爆の火と、その後の水害などへの直接的な警告ととれます。「キ・ケ・ク」の御用は、それぞれ生命エネルギー、食物、国土といった、生きる上での根幹に関わる事柄の重要性を示しています。最後まで続く「慢心」への戒めは、神の役員といえども常に試されているという、厳しい自己規律を求めています。
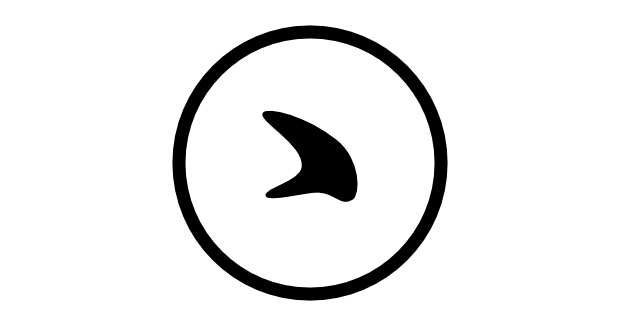





コメント