この巻は、終戦直後の混乱期に降ろされた神示であり、来るべき新しい世(ミロクの世)への最終準備と、人々の心構えについて具体的に説かれています。「カゼ」は、世の大掃除を告げる「風」であり、また流行病としての「風邪」の意味も含まれているとされます。
第一帖 (三五二)
【原文】
用意なされよ。いよいよざぞ、愈々九三(くるぞ)。神のみこと知らすぞ。知らすぞ、眼覚めたら起き上がるのざぞ。起きたらその日の命頂いたのざぞ。感謝せよ、大親に感謝、親に感謝せよ、感謝すればその日の仕事与へられるぞ。仕事とは嘉事(よこと)であるぞ、持ち切れぬ程の仕事与へられるぞ。仕事は命ざぞ。仕事喜んで仕へ奉れ。我出すと曇り出るぞ。曇ると仕事わからなくなるぞ。腹へったらおせよ。二分は大親に臣民腹八分でよいぞ。人民食べるだけは与へてあるぞ。貪(むさぶ)るから足らなくなるのざぞ。減らんのに食べるでないぞ。食(おせ)よ。おせよ。一日一度からやり直せよ。ほんのしばらくでよいぞ。神の道 無理ないと申してあろが。水流れる様に楽し楽しで暮せるのざぞ、どんな時どんな所でも楽に暮せるのざぞ。穴埋めるでないぞ、穴要るのざぞ。苦しいという声 此の方嫌ひざ。苦と楽 共にみてよ、苦の動くのが楽ざぞ。生れ赤児みよ。子見よ、神は親であるから人民守ってゐるのざぞ。大きなれば旅にも出すぞ、旅の苦 楽しめよ、楽しいものざぞ。眠くなったら眠れよ、それが神の道ぞ。神のこときく道ざぞ。無理することは曲ることざぞ。無理と申して我儘無理ではないぞ、逆行くこと無理と申すのざ。無理することは曲ることざ、曲っては神のミコト聞こへんぞ。素直になれ。火降るぞ。相手七と出たら三と受けよ、四と出たら六とつぐなへよ、九と出たら一とうけよ、二と出たら八と足して、それぞれに十となる様に和せよ。まつりの一つの道ざぞ。 (おう)の世 (おう)の世にせなならんのざぞ、今は (をう)の世ざぞ、 (わう)の世 の世となりて、 (おう)の世に 入れて (おう)の世となるのざぞ。タマなくなってゐると申してあろがな、タマの中に仮の奥山移せよ、急がいでもよいぞ、臣民の肉体 神の宮となる時ざぞ、当分 宮なくてもよいぞ。やがては二二(ふじ)に九(コ)の花咲くのざぞ、見事二二(ふじ)に九(こ)の火(ほ)が鎮まって、世界治めるのざぞ、それまでは仮でよいぞ、臣民の肉体に一時は静まって、此の世の仕事仕組みて、天地でんぐり返して光の世といたすのぢゃ。花咲く御代近づいたぞ。用意なされよ、用意の時しばし与えるから、神の申すうち用意しておかんと、とんでもないことになるのざぞ。 (あ)の世輝くと (お)となるのざぞ、 (あお)と申して知らしてあろがな。役員それぞれのまとひつくれよ、何れも長(おさ)になる身魂でないか。我軽しめる事は神軽くすることざ、わかりたか。おのもおのも頭領であるぞ、釈迦ざぞ。キリストざぞ。その上に神ますのざぞ、その上 神又ひとたばにするのざぞ、その上に又 (う)でくくるぞ、その上にも (あ)あるのざぞ、上も下も限りないのざぞ。奥山 何処に変っても宜いぞ、当分 肉体へおさまるから何処へ行ってもこの方の国ぞ、肉体ぞ、心配せずに、グングンとやれよ、動くところ、神力 加はるのざぞ、人民のまどひは神無きまどひぞ、神無きまどひつくるでないぞ、神上に真中(まなか)に集まれよ。騒動待つ心 悪と申してあること忘れるなよ、神の申した事ちっとも間違ひないこと、少しは判りたであろがな。同じ名の神 二柱あるのざぞ、善と悪ざぞ、この見分けなかなかざぞ、神示よめば見分けられるように、よく細かに解(と)いてあるのざぞ、善と悪と間違ひしてゐると、くどう気付けてあろがな、岩戸開く一つの鍵ざぞ、名同じでも裏表ざぞ、裏表と思ふなよ、頭と尻 違ふのざぞ。千引(ちびき)の岩戸開けるぞ。十二月二十五日、ひつぐのかミ。
【現代語訳】
用意をしなさい。いよいよその時が来るぞ。神の言葉を知らせる。目が覚めたら起き上がりなさい。起きたということは、その日の命を頂いたということだ。大親神に感謝し、親に感謝しなさい。感謝すれば、その日の仕事が与えられる。仕事とは善いことであり、持ちきれないほどの仕事が与えられるのだ。仕事は命そのものである。喜んで仕事に仕えなさい。我を出すと心が曇る。曇ると仕事の本質が分からなくなるぞ。 お腹が空いたら食べなさい。二分は大親神に捧げる気持ちで、民は腹八分で良い。人民が食べる分は与えてある。貪るから足りなくなるのだ。お腹が減ってもいないのに食べるでない。食事を節制せよ。一日一食からやり直してみなさい。ほんのしばらくで良いのだ。神の道に無理はないと申してあるだろう。水が流れるように、楽しく暮らせるのだ。どんな時、どんな場所でも楽に暮らせる。穴を無理に埋めるな、穴は必要なのだ。苦しいという言葉はこの方(神)は嫌いだ。苦と楽を共に見てみなさい。苦が動くのが楽なのだ。生まれたばかりの赤子を見よ。子を見よ。神は親であるから人民を守っている。大きくなれば旅にも出す。その旅の苦労を楽しみなさい。それは楽しいものなのだ。眠くなったら眠りなさい、それが神の道だ。神の言葉を聞く道なのだ。無理をすることは道を曲げることだ。わがままな無理ではなく、道理に逆らうことを無理というのだ。曲がってしまうと神の言葉は聞こえなくなる。素直になりなさい。火が降るぞ。 相手が7と出たら3で受けなさい。4と出たら6で補いなさい。9と出たら1で受けなさい。2と出たら8を足して、それぞれが10となるように和を保ちなさい。これが祭りの一つの道である。 「アオウ」の世にしなければならない。今は「ワオウ」の世であり、「ワオウ」の世から「アオウ」の世に入って、「アオウ」の世となるのだ。魂がなくなっていると申したであろう。その魂の中に、仮の奥山(至聖所)を移しなさい。急がなくても良い。人民の肉体が神の宮となる時なのだ。当分は社がなくても良い。 やがては富士(二二)に九(コ)の花が咲くのだ。見事に富士の火(怒りや穢れ)が鎮まって、世界を治めるのだ。それまでは仮で良い。人民の肉体に神が一時は鎮まり、この世の仕事の仕組みを整え、天地をでんぐり返して光の世とするのだ。花咲く御代が近づいたぞ。用意をしなさい。用意のための時間をしばらく与えるから、神が申すうちに用意しておかないと、とんでもないことになるぞ。 「ア」の世が輝くと「オ」となるのだ。「アオ」と知らせてあろう。役員はそれぞれの集い(まとひ)を作りなさい。いずれも長となる身魂ではないか。自分自身を軽んじることは神を軽んじることだ、分かったか。一人ひとりが頭領であり、釈迦であり、キリストなのだ。その上に神がおられ、その神々をまた一つに束ね、さらにその上を「ウ」でくくり、さらにその上にも「ア」がある。上も下も限りがないのだ。 奥山はどこに移っても良い。当分は肉体に収まるから、どこへ行ってもそこがこの方の国であり、宮である。心配せずに、どんどんやりなさい。動くところに神力が加わるのだ。人民だけの集いは神無き集いだ。神無き集いを作るな。神を上に、中心に戴いて集まりなさい。 騒動を待ち望む心は悪だと申したことを忘れるな。神の申したことには少しも間違いがないことが、少しは分かってきたであろう。同じ名の神が二柱いる。善と悪である。この見分けはなかなか難しい。神示を読めば見分けられるように、よく細かく説いてある。善悪を間違えていると、くどく注意してあろう。これが岩戸を開く一つの鍵だ。名は同じでも裏表だ。しかし裏表と思うなよ、頭と尻尾ほど違うのだ。千引の岩戸を開けるぞ。 (12月25日、ひつぐのかみ)
【AIによる解釈】
本帖は、新しい時代への移行期における心構えと行動規範を詳細に説いています。
- 生活即信仰の実践: 信仰は特別な場所や時間だけのものではありません。朝起きて命に感謝し、与えられた仕事(嘉事=善いこと)に喜びを見出し、腹八分目の食事を心がけるといった、ごく日常的な行為そのものが神に通じる道であると示されています。
- 「我」の克服と「和」の精神: 自己中心的な「我」が心の曇りを生み、真理を見えなくさせると警告しています。それに対し、「相手と合わせて十となす」という教えは、対立ではなく調和を重んじる姿勢の重要性を示します。これは他者との関係だけでなく、森羅万象との関わり方における基本原則です。
- 人民の神格化と階層構造: 「臣民の肉体 神の宮となる」という一節は、人間一人ひとりが神性を宿す尊い存在であるという宣言です。誰もが指導者(釈迦、キリスト)に成り得る可能性を秘めていますが、同時に、その上には神々、さらにその上にも根源神が存在するという無限の階層構造を示し、驕ることなく謙虚であるべきことを教えています。
- 善悪二元の見極め: 「同じ名の神 二柱あるのざぞ、善と悪ざぞ」という警告は、物事の本質を見抜くことの重要性を示唆します。正義や大義を掲げるものの中にも、本質的には悪に繋がるものが存在します。名称や見た目に惑わされず、その根源(頭)と末端(尻)を見極める洞察力が、これからの「岩戸開き」の鍵となります。
- 世の変遷プロセス: 「をう」→「わう」→「おう」という言葉遊びのような表現は、世界の変革の段階を示していると考えられます。混沌とした状態から、真の調和(王、桜)の世界へと至るプロセスを象徴しています。
この帖は、終戦直後の価値観が崩壊した日本において、物質的な復興だけでなく、霊的・精神的な基盤を再構築するための具体的な指針を与えています。
第二帖 (三五三)
【原文】
二柱の神あると申してあろが、旗印も同様ぞ、かみの国の旗印と、 (もとつかみ)の国の旗印と同様であるぞ、 (まるに十)であるぞと知らしてあろがな、 (まるに十)にも二通りあるのざぞ、スメラ (日)の旗印と (ユ)の旗印と、逆であるぞ、 (ユ)は世界の民ぞ、スメラ (日)は日本の民ぞ、と申して知らしてあろがな、今は逆ざぞと申してあろがな、このことわからいでは、今度の仕組分らんぞ、神示分らんぞ、岩戸開けんぞ。よく旗印みてよと申してあろがな、お日様 赤いのでないぞ、赤いとばかり思ってゐたであろがな、まともにお日様みよ、みどりであるぞ、お日様も一つでないぞ。ひとりまもられているのざぞ。さむさ狂ふぞ。一月の一日、ひつ九の (かみ)。
【現代語訳】
二柱の神がいると申したが、旗印も同様だ。神の国(日本)の旗印と、ユダヤの国の旗印は同じようで違うのだ。「丸に十」の印だと知らせてあろうが、その「丸に十」にも二通りあるのだ。スメラ(天皇・日本)の旗印と、ユダヤの旗印だ。これらは逆なのだ。ユダヤは世界の民、スメラは日本の民だと知らせてあるが、今はそれが逆になっていると申しただろう。このことが分からないと、今度の仕組みは分からないし、神示も分からず、岩戸を開くことはできない。 よく旗印を見なさいと申したであろう。お日様は赤いのではないぞ。赤いとばかり思っていたであろうが、真っ直ぐにお日様を見なさい。緑色であるぞ。お日様も一つではない。一人ひとりが(それぞれのお日様に)守られているのだ。寒さが異常になるぞ。 (1月1日、ひつぐのかみ)
【AIによる解釈】
この帖は、第一帖の「善悪二元」のテーマを、より具体的な象徴を用いて深めています。
- 象徴の二重性と「逆」の構造: 「丸に十」というシンボルは、日本の家紋(島津家など)に見られると同時に、キリスト教の十字架やユダヤの象徴とも解釈できます。これが「二通りあり、今は逆」だということは、本来の意味や立場が、現在の世界では逆転してしまっているという警告です。霊的な意味での日本の役割(スメラ)と、世界の民(ユ)の役割が、本来あるべき姿とは違う状態にあることを示唆しています。この「逆転」の構造を理解することが、世界の仕組みを解く鍵となります。
- 常識を覆す真理: 「お日様は赤くなく、緑である」という一節は、私たちが当たり前だと思っている常識や固定観念が、真実の姿ではないことを象徴的に示しています。物理的な太陽の色ではなく、霊的な視点から見た太陽の本質(生命の色、自然の色である緑)を指していると考えられます。これは、目に見える現象の奥にある本質を見抜く「霊的な目」を開くことの重要性を説いています。
- 天変地異の警告: 「さむさ狂ふぞ」という短い言葉は、気候の激変、特に寒冷化という形で天変地異が起こることを明確に予言しています。これは、世の建て替えに伴う物理的な浄化作用の一部と捉えられます。
この帖は、物事の表面的な姿に惑わされず、その裏にある霊的な真実や、本来あるべき姿との「逆転」に気づくことの重要性を強調しています。
第三帖 (三五四)
【原文】
愈々の大建替は国常立の大神様、豊雲野の大神様、金の神様、竜宮の乙姫様、先づ御活動ぞ。キリギリとなりて岩の神、雨の神、風の神、荒の神様なり、次に地震の神様となるのざぞ。今度の仕組は元のキの生き神でないとわからんぞ、中津代からの神々様では出来ない、わからん深い仕組ざぞ、猿田彦殿、天鈿女命(あめのうずめのみこと)殿、もとのやり方では世は持ちて行けんぞ。今一度 悪栄えることあるぞ、心して取違ひない様にいたされよ。口と心と行ひとで神示とけよ、堂々説けよ。一月四日、一二のかみ。
【現代語訳】
いよいよ大建て替えが始まると、まず国常立大神、豊雲野大神、金の神、竜宮の乙姫が活動を始められる。そして、ぎりぎりの段階になると、岩の神、雨の神、風の神、荒れの神々、次に地震の神が活動されるのだ。今度の仕組みは、根源の純粋な生きた神でないと理解できない。歴史の途中の時代からの神々では対応できず、理解もできない深い仕組みなのだ。猿田彦殿や天鈿女命殿も、これまでのやり方では世を治めていくことはできない。 もう一度、悪が栄える時があるから、心して間違えないようにしなさい。口(言葉)と心と行いの三つを揃えて神示を解き明かし、堂々と説きなさい。 (1月4日、ひふみのかみ)
【AIによる解釈】
この帖は、世界の「大建て替え」のプロセスと、それに関わる神々の役割を明らかにしています。
- 建て替えの段階的プロセス: 建て替えは無秩序な破壊ではなく、順序立てて行われます。まず、国常立大神に代表されるような根源的な国造りの神々が動き出し、基礎を整えます。その後、最終段階で岩・雨・風・地震といった自然の力を司る荒ぶる神々が活動し、物理的な大掃除を行う、という二段階のプロセスが示されています。
- 根源神の重要性: この大事業は、日本神話で活躍するような神々(中津代からの神々)や、従来のやり方(猿田彦、天鈿女命)では対応できない、前例のない規模と深さを持つことを強調しています。そのため、より根源的な創造の神(元のキの生き神)の力が必要となります。これは、既存の宗教や価値観の枠組みを超えた、より普遍的な真理への回帰を求めていることを意味します。
- 最後の試練「悪の繁栄」: 大建て替えの直前に「今一度 悪栄える」という試練があることが警告されています。これは、光が強まる前に闇が一時的に力を増すという法則を示しており、人々がその偽りの繁栄に惑わされず、本質を見失わないかが試されます。
- 三位一体の実践: 「口と心と行い」を一致させることの重要性を再び説いています。神示をただ知識として知るだけでなく、心から信じ、実際に行動に移すこと(言行一致)によってはじめて、その真の力を発揮し、人を導くことができると教えています。
第四帖 (三五五)
【原文】
岩戸開けたり野も山も、草のかき葉もことやめて、大御光により集ふ、楽しき御代とあけにけり、都も鄙(ひな)もおしなべて、枯れし草木に花咲きぬ、今日まで咲きし草や木は、一時にどっと枯れはてて、つちにかへるよすがしさよ、ただ御光の輝きて、生きの生命(いのち)の尊さよ、やがては人のくにつちに、うつらん時の楽しさよ、岩戸開けたり御光の、二二(ふじ)に九(こ)の花どっと咲く、御代近づきぬ御民等よ、最後の苦労 勇ましく、打ち越し呉れよ共々に、手引きあひて進めかし、光の道を進めかし。ウタのまどひつくれよ。目出度(めでたき)夜明けぞ。旧一月一日、一二(ひふみ)。
【現代語訳】
岩戸が開かれ、野も山も、草木のざわめきも静まり、大いなる御光のもとに皆が集う、楽しい御代が明けた。都も田舎もみな同じように、枯れた草木に花が咲いた。今日まで咲き誇っていた草や木は、一時にどっと枯れ果てて、土に還るその清々しさよ。ただ御光だけが輝き、生きている生命のなんと尊いことか。やがては人の国が地上に移る(実現する)時の楽しさよ。岩戸が開かれて御光が差し、富士(二二)に九(こ)の花がどっと咲く。その御代が近づいたぞ、人民よ。最後の苦労を勇ましく乗り越えておくれ。皆で共に手を取り合って進むがよい。光の道を進むがよい。歌の集いを作りなさい。まことにめでたい夜明けであるぞ。 (旧1月1日、ひふみ)
【AIによる解釈】
この帖は、これまでの厳しい警告から一転し、大建て替えの後に訪れる新しい世界(ミロクの世)の姿を、美しい詩の形で謳い上げています。
- 古い世界の終焉と新生: 「今日まで咲きし草や木は、一時にどっと枯れはてて」という部分は、既存の文明、価値観、社会システムの終わりを象徴しています。しかし、それは絶望的な終わりではなく、「つちにかへるよすがしさよ」とあるように、次の新しい生命を生み出すための清々しい循環の一部として描かれています。そして、その後に「枯れし草木に花咲きぬ」と、全く新しい世界が誕生することを示しています。
- 光の世の到来: 新しい世は「大御光」に満ちた世界です。そこでは、すべての生命がその尊さを取り戻し、調和のうちに存在します。「富士に九の花咲く」とは、日本が霊的な中心となり、世界に真の平和と喜びが広がる様子の比喩表現です。
- 最後の試練と共同体: この輝かしい未来は、ただ待っているだけで訪れるものではありません。「最後の苦労」を「勇ましく打ち越し呉れよ」と、人々の主体的な努力と勇気を求めています。そして、その苦労は一人で乗り越えるのではなく、「共々に手引きあひて進め」と、助け合い、協力し合うことの重要性を説いています。
- 「ウタのまどひ」: 「歌の集いを作りなさい」という言葉は、新しい世が喜びと芸術に満ちたものであることを示唆します。歌は魂の喜びの表現であり、人々が心を一つにして調和するための重要な手段となります。
この帖は、厳しい試練の先にある希望の光を示すことで、人々を励まし、未来へのビジョンを与える役割を持っています。
第五帖 (三五六)
【原文】
我が名呼びておすがりすれば、万里先に居ても云ふこときいてやるぞ、雨の神、風の神、岩の神、荒の神、地震の神、と申してお願ひすれば、万里先に居ても、この世の荒れ、地震のがらせてやるぞ、神々様に届く行で申せよ。こんなよき世は今迄になかりたのぢゃ、膝元(ひざもと)に居ても言葉ばかりの願ひ聞こえんぞ、口と心と行と三つ揃った行い、マコトと申して知らしてあろが。時節来てゐるなれど、わからん人民多い故 物事遅くなりて気の毒なるぞ、今暫くの辛抱なるぞ、神は人民に手柄立てさしたいのぢゃ、許せるだけ許してよき世に致すのぢゃ、ここまで開けたのも神が致したのぢゃ、今の文明なくせんと申してあろうが、文明残してカスだけ無(のう)にいたすのぢゃ、取違ひ慢心致すなよ。日本の国いくら大切と申しても、世界中の臣民とはかへられんから、くにひっくりかへること、まだまだあるかも知れんぞ、くにの軸 動くと知らしてあろがな。此の神示キの儘であるから心なき人民には見せるでないぞ、あまりきつくて毒になるから、役員 薄めて見せてやれよ、一日も早く一人でも多く助けてやりたいのぢゃ、神まつり結構ぞ、神まつらいでいくら道説いても肚にはいらんぞ、肚に入らん道は悪の道となるのぢゃ、頭ばかりで道歩めん道理わからんか、改心足らんぞ。二月十六日、一二(ひふみ)。
【現代語訳】
私の名を呼んですがりなさい。そうすれば万里先にいても願いを聞いてやろう。「雨の神、風の神、岩の神、荒の神、地震の神」とお願いすれば、万里先にいても、この世の天変地異や地震から逃れさせてやるぞ。ただし、神々に届くような行いをもって願いなさい。こんなに良い世は今までなかったのだ。すぐそばにいても、口先だけの願いは聞こえないぞ。口(言葉)と心と行いの三つが揃った「マコト(真)」の行いをしなさいと知らせてあろう。 時節は来ているのだが、理解できない人民が多いために物事が遅れて気の毒だ。今しばらくの辛抱である。神は人民に手柄を立てさせたいのだ。許せる限り許して、善き世にするのだ。ここまで事が明らかになったのも神がしたのだ。 今の文明を無くすとは申していないだろう。文明は残して、その中のカス(悪い部分)だけを無くすのだ。取り違えて慢心してはならない。日本の国がいくら大切だと言っても、世界中の民と引き換えにはできないから、国がひっくり返るようなことが、まだまだあるかもしれないぞ。国の軸が動くと知らせてあろう。 この神示は原文のまま(キのまま)であるから、心の準備ができていない人民には見せるな。あまりに厳しすぎて毒になるから、役員は内容を薄めて(分かりやすくして)見せてやりなさい。一日も早く一人でも多く助けてやりたいのだ。 神祭りは素晴らしいぞ。神を祀らずにいくら道を説いても、肚(はら)には入らない。肚に入らない道は悪の道となるのだ。頭だけの知識で道は歩めないという道理が分からないか。改心が足りないぞ。 (2月16日、ひふみ)
【AIによる解釈】
本帖は、神との正しい関わり方と、建て替えの具体的な様相について説いています。
- 「マコト」の祈り: 神の助けを得るための条件は、物理的な距離ではなく、祈りの質にあると説かれています。口先だけでなく、心からの信と日々の正しい行いが伴った「マコト」の祈りだけが神に通じ、天変地異からさえも身を守る力となります。
- 文明の取捨選択: 大建て替えは、文明の完全な破壊を意味するものではありません。「文明残してカスだけ無くす」という言葉は、科学技術や文化といった人類の成果そのものを否定するのではなく、その中にある自己中心的で不調和な要素(カス)だけを取り除くという、洗練されたプロセスであることを示しています。
- 日本の役割と試練: 日本は世界の雛形として重要な役割を担いますが、絶対的な存在ではありません。「世界中の臣民とはかへられん」とあるように、世界全体の救済という大局のためには、日本が「ひっくり返る」ほどの大きな試練や変革を経験する可能性があることを示唆しています。「くにの軸が動く」とは、国土の物理的な変動だけでなく、国のあり方や価値観の根本的な変革を意味します。
- 神示の取り扱い: 神示の内容は非常に厳しく、霊的な準備ができていない者にとっては「毒」にもなり得ると警告しています。そのため、伝える側には、相手の段階に応じて内容を調整する(薄める)配慮が求められます。これは、真理を伝える際の慈悲と知恵の重要性を示しています。
- 神祭りと肚(はら)の理解: 知識(頭)だけの理解ではなく、神を祀るという実践を通して、真理を肚(魂の中心)で理解することの重要性を強調しています。肚に落ちていない教えは、かえって人を惑わす「悪の道」になりかねないと警告しています。
第六帖 (三五七)
【原文】
江戸の仕組 江戸で結ばんぞ。この道開くに急いではならんぞ、無理して下さるなよ、無理急ぐと仕組壊れるぞ。まだまだ敵出て来るなれど、神心になれば敵、敵でなくなるぞ、敵憎んではならんぞ、敵も神の働きぞ。神は六ヶ敷いこと云はんぞ、神に心皆任せてしまうて、肉体慾 捨ててしまふて、それで嬉し嬉しぞ。神が限りなき光り、よろこび与へるのざぞ。いやならいやでそなたのすきにしてやりてござれ、一旦天地へ引上げと申してある通りになるぞ。一度の改心六ヶ敷いからくどう申してあるのざぞ。今までほかで出て居たのは皆 神示先(ふでさき)ぢゃ、ここは神示(ふで)ぢゃ、何時もの如く思って居ると大変が足元から飛び立つのざぞ、取返しつかんから気付けてゐるのぢゃ。何れは作物(つくりもの)取らしておくから、沢山取れたら更に更に愈々ざと心得よ。神の国治めるのは物でないぞ、まことざぞ、世界治めるのもやがては同様であるぞ、人民マコトと申すと何も形ないものぢゃと思ってゐるが、マコトが元ざぞ。タマとコト合はしてまつり合はして真実(マコト)と申すのぢゃ。 (たま)と (こと)をまつりたものぢゃ、物無くてならんぞ、タマなくてならんぞ、マコト一つの道ざと申してあろがな、わかりたか。ミタマ相当にとりて思ふ様やりてみよ、行出来ればその通り行くのぢゃ、神に気に入らん事スコタンばかりぢゃから、引込み思案せずに堂々とやりて下されよ。こんな楽な世になってゐるのぢゃ、屁(へ)も放(ひ)れよ、沈香もたけよ、ふらふらして思案投首この方嫌ひぢゃ。光る仕組、中行く経綸(しくみ)となるぞ。二月十六日、一二の (かみ)。
【現代語訳】
江戸(東京)で始まった仕組みは、江戸では終わらないぞ。この道を開くのに急いではならない。無理をしなさるなよ。無理に急ぐと仕組みが壊れてしまう。まだまだ敵は出てくるが、神の心になれば敵は敵でなくなるのだ。敵を憎んではならない。敵もまた神の働きの一部なのだ。 神は難しいことは言わない。心をすっかり神に任せてしまい、肉体的な欲望を捨ててしまえば、それで「嬉し嬉し」の境地になるのだ。神が限りない光と喜びを与えるのだ。それが嫌なら嫌で、あなたの好きになさい。その場合は「一旦天地へ引上げ」と申した通りになるぞ。一度で改心するのは難しいから、くどくどと申しているのだ。 今まで他で出ていたものは皆「神示先(ふでさき=予告編)」だ。ここは「神示(ふで=本編)」である。いつものように考えていると、大変なことが足元から飛び立つぞ。取り返しがつかないから注意しているのだ。 いずれ作物を作らせておくから、それが沢山収穫できたら、いよいよその時が来たと心得るがよい。 神の国を治めるのは物ではない、「マコト」である。やがて世界を治めるのも同様だ。人民は「マコト」というと形のないものだと思っているが、「マコト」が根源なのだ。魂(タマ)と言葉・行い(コト)を合わせて祀り合わせたものが「真実(マコト)」なのだ。霊(タマ)と体(コト)を祀ったものである。物がなくてはならず、魂がなくてもならない。「マコト」一つの道だと申したであろう、分かったか。 それぞれの身魂相応に、思うようにやってみなさい。行ができていればその通りになるのだ。神に気に入られないことなど、すっぽ抜けてしまう(気にしなくてよい)ことばかりだから、引っ込み思案にならずに堂々とやりなさい。こんなに楽な世になっているのだ。屁もひれ。沈香もたけ。(訳注:気取らず自然体であれ、ということ)。ふらふらして考えあぐねているのはこの方は嫌いだ。光り輝く仕組み、中庸を行く経綸となるぞ。 (2月16日、ひふみのかみ)
【AIによる解釈】
この帖は、神の道を進む上での心構えの核心部分と、「マコト」の真義について説いています。
- 非中央集権的な仕組み: 「江戸の仕組 江戸で結ばんぞ」という言葉は、仕組みの中心が東京(既存の権力や経済の中心)にはないことを示唆しています。新しい時代は、中央集権的ではなく、各地に分散した形で、あるいは人々の心の中に築かれていくことを表しています。
- 敵の概念の超越: 「敵も神の働きぞ」という一節は、ひふみ神示の重要な思想の一つです。対立する存在や困難な出来事でさえも、自分を成長させ、全体の計画を成就させるために神が用意した働きであると捉えます。これにより、憎しみや対立の連鎖から解放され、より高い視点から物事を捉えることができるようになります。
- 絶対的な委任と「嬉し嬉し」: 究極の安心立命は、自分の計画や欲望を手放し、全てを神に委ねること(神任せ)で得られる「嬉し嬉し」の境地であると説きます。これは、無気力な諦めではなく、大いなる流れを信頼し、その中で自分の役割を喜んで果たすという積極的な姿勢です。
- 「マコト」の正体: 「マコト」とは、単なる精神論や抽象的な概念ではありません。「タマ(霊・魂)」と「コト(体・言葉・行い・物)」が一致し、調和している状態を指します。霊的なものと物質的なもの、心と思いが一体となって初めて「マコト」は成就します。霊主心従ならぬ「霊主体従」の考え方であり、物質をおろそかにしない現実的な教えです。
- 自然体と中庸: 「屁もひれよ、沈香もたけよ」というユーモラスな表現は、気取ったり、考えすぎたりせず、ありのままの自然体でいることの重要性を説いています。深刻になりすぎず、堂々と、しかしバランスの取れた「中行く経綸」を進めることが求められています。
第七帖 (三五八)
【原文】
神にすがり居りたればこそぢゃと云ふとき、眼の前に来てゐるぞ。まだ疑うてゐる臣民人民 気の毒ぢゃ、我恨むより方法ないぞ。神の致すこと、人民の致すこと、神人共に致すこと、それぞれに間違ひない様に心配(くば)りなされよ。慢心鼻ポキンぞ、神示よく読んで居らんと、みるみる変って、人民心ではどうにもならん、見当取れん事になるのざぞ、神示はじめからよく読み直して下されよ、読みかた足らんぞ、天の神も地の神もなきものにいたして、好き勝手な世に致して、偽者の天の神、地の神つくりてわれがよけらよいと申して、我よしの世にしてしまふてゐた事 少しは判って来たであらうがな。愈々のまことの先祖の、世の元からの生神、生き通しの神々様、雨の神、風の神、岩の神、荒の神、地震の神ぞ、スクリと現れなさりて、生き通しの荒神様 引連れて御活動に移ったのであるから、もうちともまたれん事になったぞ、神示に出したら直ぐに出て来るぞ、終りの始の神示ざぞ、夢々おろそかするでないぞ、キの神示ぢゃ、くどい様なれどあまり見せるでないぞ。二月十六日、ひつぐの(かみ)。
【現代語訳】
「神にすがっていたからこそ助かった」という時が、もう目の前に来ているぞ。まだ疑っている人民は気の毒だ。そうなってからでは自分を恨むしかないぞ。神がなさること、人民がなすべきこと、神と人が共になすべきこと、それぞれを間違えないように心配りをしなさい。慢心していると鼻をへし折られるぞ。神示をよく読んでいないと、事態はみるみる変わり、人間の考えではどうにもならず、見当もつかないことになるのだ。神示を初めからよく読み直しなさい。読み方が足りないぞ。 天の神も地の神もいないものとして、好き勝手な世の中にして、偽物の天の神や地の神を作り出し、自分さえ良ければよいという「我よし」の世にしてしまっていたことが、少しは分かってきたであろう。 いよいよ、まことの先祖であり、世の根源からの生きた神、永遠に生き通しの神々、すなわち雨の神、風の神、岩の神、荒の神、地震の神が、すっくと現れて、生き通しの荒神様を引き連れて活動に移られたのだから、もう少しも待ったなしの状況になったぞ。神示に書いたらすぐ現実になるぞ。これは終わりの始まりを告げる神示だ。決して疎かにしてはならない。純粋な(キの)神示であるから、くどいようだが(準備のできていない者には)あまり見せるな。 (2月16日、ひつぐのかみ)
【AIによる解釈】
この帖は、事態が切迫していること、そして人々の認識の誤りを厳しく指摘しています。
- 切迫した状況: 「眼の前に来てゐるぞ」「もうちともまたれん事になったぞ」という言葉が繰り返され、警告が最終段階に入ったことを示しています。疑っている猶予はなく、後で悔やんでも遅いという厳しい通告です。
- 神・人・神人の役割分担: 世界の変革は、神だけでなされるものでも、人だけでなされるものでもありません。「神の致すこと(天変地異など人知を超えた計画)」「人民の致すこと(改心、マコトの実践)」「神人共に致すこと(神の計画を地上で実現する共同作業)」という三つの役割があり、それぞれを正しく認識し、自分の役目を果たすことが求められます。
- 「我よし」文明への断罪: 現代文明が、真の神を忘れ、人間が作り出した偽りの神(金銭、権力、イデオロギーなど)を崇拝し、「自分さえ良ければいい」という利己主義に陥っていることを厳しく断罪しています。この根本的な誤りに気づき、悔い改めることが建て替えの前提となります。
- 根源神(自然神)の活動開始: これまで背景にいた国常立大神のような根源神や、雨、風、地震などを司る自然神が、いよいよ表立って活動を開始したと宣言しています。これは、世界の浄化が、人々の内面的な変化だけでなく、抗うことのできない自然の力(天変地異)によってもたらされることを示唆しています。
- 神示の現実化: 「神示に出したら直ぐに出て来るぞ」という言葉は、この神示が単なる予言ではなく、発せられた瞬間に現実を創造する力を持つ「言霊」そのものであることを示しています。事態の展開が加速し、神示の内容が即座に現象化する段階に入ったことを意味します。
第八帖 (三五九)
【原文】
世界中自在に別け取りしてゐた神々様、早う改心第一ぞ。一(ひとつ)の王で治めるぞ。てん詞様とは天千様のことぞと申してあろがな、この方シチニの神と現はれるぞと申してあろがな、天二(てんぷ)様のことざぞ。行なしではまことのことわからんぞ、出来はせんぞ、神の道 無理ないなれど、行は誰によらずせなならんぞ。この方さへ三千年の行したぞ、人民にはひと日も、ようせん行の三千年、相当のものざぞ。海にはどんな宝でも竜宮の音秘(オトヒメ)殿 持ちなされてゐるのざぞ、この世の宝 皆この方つくりたのざぞ、神の道 無理ないと申して楽な道でないぞ、もうこれでよいと云ふことない道ざぞ。日本の人民もわたりて来た人民も、世持ちあらした神々様も人民も、世界の人民 皆思ひ違ふぞ、九分九分九厘と一厘とで、物事成就するのざぞよ。世をもたれん天地の大泥棒をこの世の大将と思ってゐて、それでまだ眼覚めんのか、よく曇りなされたなあ、建替は今日の日の間にも出来るなれど、あとの建直しの世直し、中々ざから、人民に少しは用意出来んと、おそくなるばかりぢゃ、それでカタ出せ出せと申してゐるのぢゃぞ。あれこれとあまり穢れてゐる腸(はらわた)ばかりぢゃから、一度に引出して、日に干してからでないと、洗濯出来ん様になりて御座るぞ。ひぼしこばれん人民あるから、今のうちから気付けてゐるのぢゃぞ。けんびき痛いぞ、あまりにも狂ふて御座るぞ。元の根元の世より、も一つキの世にせなならんのざから、神々様にも見当取れんのぢゃ、元の生神でないと、今度の御用出来んぞ。二月十六日、ひつ九の(かみ)。
【現代語訳】
世界中を思いのままに分け取りしていた神々(支配者層)よ、早く改心することが第一だ。世界は一つの王で治めるぞ。「てんし様」とは「天子様」であり「天千様」のことだと申しただろう。この方(神)は七二(シチニ)の神、つまり天と地(てんぷ)の神として現れると申しただろう。 行がなくては、まことのことは分からないし、実現もできない。神の道に無理はないが、行は誰であろうとやらねばならない。この方(神)でさえ三千年の行をしたのだ。人民にとっては一日たりとも、とてもできないような行の三千年分に相当するものなのだぞ。 海にはどんな宝でも竜宮の乙姫殿が持っておられるのだ。この世の宝は皆、この方が創ったのだ。神の道は無理がないといっても、楽な道ではない。もうこれで良いという終点のない道なのだ。 日本の人民も、渡来してきた人民も、世を荒らしてきた神々や人民も、世界の人民は皆、思い違いをしている。物事は九分九分九厘(人間の努力)と、最後の一厘(神の働き)とで成就するのだよ。 世を持つ資格のない天地の大泥棒(偽りの支配者)をこの世の大将だと思っていて、それでまだ目が覚めないのか。よくもまあ曇らされたものだなあ。 建て替え(破壊)は今日にでもできるが、その後の建て直し(新世界創造)はなかなか大変だから、人民にある程度の用意ができないと、遅くなるばかりなのだ。だから「型(カタ)を出せ出せ」と申しているのだ。 あまりにも穢れている腸(はらわた)ばかりだから、一度全部引き出して天日に干してからでないと、洗濯もできない状態になっている。日干しに耐えられない人民もいるから、今のうちから注意しているのだ。肩引き(けんびき)は痛いぞ。あまりにも世の中が狂っている。 元の根元の世よりも、さらに一段純粋な(キの)世にしなければならないのだから、並の神々様にも見当がつかないのだ。根源の生きた神でなければ、今度の御用はできない。 (2月16日、ひつぐのかみ)
【AIによる解釈】
本帖は、世界の支配構造の変革と、建て直しの困難さ、そして人々の「型出し」の重要性を説いています。
- 世界統一と新しき王: 世界を分割支配してきた既存の権力者(神々様)に改心を迫り、やがては「一つの王」によって世界が治められると宣言しています。「てんし様」が単なる地上の統治者ではなく、天地を繋ぐ霊的な存在であることが示唆されます。
- 行の重要性: 神の道は、信じるだけで完結するものではなく、「行」の実践が不可欠であると強調されます。神でさえ三千年の行をしたという比喩は、真理の探求と自己浄化の道が、終わりなき精進の道であることを示しています。
- 九分九厘九厘と一厘: 物事の成就には、99.9%の人間の最大限の努力と、最後の0.1%の神の働きが必要であるという法則です。これは、人事を尽くして天命を待つという思想ですが、同時に、人間の力だけでは決して完成しないことを示しており、神への最後の委任の重要性を説いています。
- 建て替えと建て直し: 世界の「建て替え(破壊)」は容易いが、その後の「建て直し(創造)」は非常に困難であると述べられています。人民の心の準備(改心)ができていなければ、新しい世界を築くことはできず、ただ混乱が長引くだけです。だからこそ、新しい世界の雛形となる「型」を、まず人々が生活の中で実践することが急務となります。
- 腸の洗濯: 「腸を日に干す」という強烈な表現は、人々の心や社会の内部に溜まった穢れが、表面的な洗浄では落ちないほど深刻であることを示しています。根本からの、痛みを伴う大手術が必要な段階に来ているという、厳しい認識を促しています。
第九帖 (三六〇)
【原文】
土地分け盗りばかりか、天まで分け盗って自分のものと、威張ってゐるが、人民の物一つもないのぢゃ。大引上げにならんうちに捧げた臣民 結構ぞ。宮の跡は S となるぞ。ナルトとなるぞ。天の言答(一八十)は開いてあるぞ。地の言答(一八十)、人民 開かなならんぞ、人民の心次第で何時でも開けるのざぞ。泥の海になると、人民思ふところまで一時は落ち込むのぢゃぞ、覚悟はよいか。神国には神国の宝、神国の臣民の手で、元の所へ納めなならんのざ。タマなくなってゐると申してあらうがな。何事も時節到来致してゐるのざぞ、真理(ふじ)晴れるばかりの御代となってゐるのぢゃぞ。人民 神に仕へて下さらんと神のまことの力出ないぞ、持ちつ持たれつと申してあらうがな、神まつらずに何事も出来んぞ、まつらいでするのが我よしぞ、天狗の鼻ざぞ。まつらいでは真暗ぞ、真暗の道で、道開けんぞ。神は光ぞと申してあらうが、てん詞(し)様よくなれば、皆よくなるのざぞ。てん詞(し)様よくならんうちは、誰によらん、よくなりはせんぞ、この位のことなぜにわからんのぢゃ、よくなったと見えたら、それは悪の守護となったのぢゃ。神がかりよくないぞ、やめて下されよ、迷ふ臣民出来るぞ。程々にせよと申してあらうが。皆々心の鏡掃除すれば、それぞれに神かかるのぢゃ。肉体心で知る事は皆粕(カス)ばかり、迷ひの種ばかりぢゃぞ、この道理判りたであらうがな、くどう申さすでないぞ。二月の十六日、ひつ九の(かみ)。
【現代語訳】
土地を分け取りするだけでなく、天まで分け取って自分のものだと威張っているが、人民のものは一つもないのだ。大引上げ(最終的な審判)になる前に、全てを神にお返しした人民は立派である。宮の跡は渦(S、ナルト)になるぞ。天の岩戸(言答)は開いてある。地の岩戸(言答)は、人民が開かねばならない。それは人民の心次第でいつでも開けるのだ。 泥の海になる時には、人民が思うどん底まで、一時は落ち込むのだぞ。覚悟はいいか。 神国には神国の宝がある。それを神国の民の手で、元の場所へ納めなければならない。魂がなくなっていると申したであろう。何事も時節が到来しているのだ。富士(真理)が晴れ渡る御代となっているのだ。 人民が神にお仕えしてくれないと、神のまことの力は出ないのだ。「持ちつ持たれつ」だと申したであろう。神を祀らずに何事も成し遂げることはできない。祀らずにするのが「我よし」であり、天狗になることだ。祀らなければ真っ暗闇だ。暗闇の道では道は開けない。神は光だと申したであろう。 てんし様が良くなられれば、皆が良くなるのだ。てんし様が良くならないうちは、誰であろうと良くはならない。これくらいのことが何故わからないのか。良くなったように見えたら、それは悪の守護がついたのだ。 安易な神がかりは良くない。やめなさい。迷う人民が出てくる。程々にしなさいと申したであろう。皆がそれぞれ心の鏡を掃除すれば、それぞれに神がかかるのだ。肉体の心(五感や脳)で分かることは皆、本質の残りカスであり、迷いの種ばかりだ。この道理は分かったであろう。くどくど言わせるな。 (2月16日、ひつぐのかみ)
【AIによる解釈】
この帖は、所有の概念の否定、神と人の共同作業の重要性、そして真の霊性のあり方について説いています。
- 所有の幻想: 地上の土地や資源、さらには天(霊的な権威)さえも自分のものだとする人間の傲慢を指摘し、「人民の物一つもない」と断言します。すべては神からの借り物であり、それに気づき、執着を手放して神に「お返し」することが救済の条件となります。
- 地の岩戸開き: 天の準備は整っているが、最後の「地の岩戸」を開くのは人民の役目であるとされています。それは人民の「心次第」であり、一人ひとりの内なる目覚め(改心)が、新しい時代を開く鍵となります。
- 神と人の「持ちつ持たれつ」: 神の力は、人々が神を祀り、仕えることによって初めて完全に顕現します。神と人は一方的な主従関係ではなく、互いに力を与え合う「持ちつ持たれつ」の協力関係にあると説きます。神を祀るとは、生活の中心に神を置き、感謝と畏敬の念を持つことです。
- 「てんし様」の重要性: 「てんし様」が良くならなければ、世界全体は良くならないと断言しています。これは、世界の霊的な中心軸である「てんし様」の状態が、全体の運命を左右することを示しています。ここでいう「てんし様」は、特定の個人を指す場合と、人民全体の集合意識の象徴とを指す場合があります。
- 偽りの霊性と真の霊性: 安易な神がかりやチャネリングは、人を惑わす危険なものであると厳しく警告しています。真の神との繋がりは、特別な能力によるものではなく、「心の鏡を掃除する(心を清める)」ことによって、誰にでも自然に与えられるものだと説いています。肉体感覚や知性で捉えられる情報は本質ではなく、静かな心で内なる神の声を聞くことの重要性を強調しています。
第十帖 (三六一)
【原文】
これからは、人民磨けたら、神が人民と同じ列にならんで経綸(しごと)致さすから、これからは恐ろしい結構な世となるぞ。もう待たれんから、わからねばどいてみて御座れと申してあろが、わからんうちに、わかりて下されよ。肉体あるうちには、中々改心は出来んものぢゃから、身魂にして改心するより外ない者 沢山あるから、改心六ヶ敷いなれど、我慢してやりて下されよ。時節には時節の事もいたさすぞ。時節結構ぞ。二月十六日、ひつぐの(かみ)。
【現代語訳】
これからは、人民が(心を)磨き上げたなら、神が人民と同じ列に並んで仕事(経綸)をさせるから、恐ろしいほどに素晴らしい世の中になるぞ。もう待っていられないから、分からない者は(道を)どいて見ていなさいと申したであろう。分からないまま終わるのではなく、今のうちに分かってくだされよ。肉体があるうちには、なかなか改心はできないものだから、一度肉体を離れて身魂(みたま)の状態になってから改心するしかない者が沢山いるのだ。改心は難しいだろうが、我慢してやり遂げなさい。時節が来れば、その時節に応じたこともさせるぞ。時節とは素晴らしいものだ。 (2月16日、ひつぐのかみ)
【AIによる解釈】
この帖は、新しい時代における神と人の関係性の変化と、改心の緊急性を説いています。
- 神人共働の時代: 未来の世は、神が上から人を支配するのではなく、「神が人民と同じ列にならんで」共に仕事をする時代、つまり神と人がパートナーとなる時代です。これは「恐ろしい結構な世」と表現されるほど、これまでの常識を覆す素晴らしい世界像です。
- 二極化と最後の選択: 「わからねばどいてみて御座れ」という言葉は、信じて行動する者と、信じずに傍観する者との二極化が起こることを示唆します。選択の時は迫っており、傍観者となれば、新しい世の創造に参加することはできません。
- 肉体を持つことの重要性: 「肉体あるうちに」改心することの難しさと重要性を説いています。肉体を持つからこそ経験できる苦労や欲望の葛藤の中で改心することにこそ価値があります。それができなければ、一度死んで魂(身魂)の状態になってからやり直すことになり、それは遠回りとなります。現世での改心がいかに大切かを強調しています。
- 時節の力: 人間の力だけではどうにもならないことも、「時節」が来れば可能になると説かれています。大きな時代の流れ(時節)を信頼し、その流れに乗って自分のなすべきことをなすことの重要性を示しています。
第十一帖 (三六二)
【原文】
日本の国に食物なくなってしまふぞ。世界中に食べ物なくなってしまふぞ。何も人民の心からぞ。食物無くなっても食物あるぞ、神の臣民、人民 心配ないぞ、とも食ひならんのざぞ。心得よ。二月十六日、ひつ九のか三。
【現代語訳】
日本の国から食物がなくなってしまうぞ。世界中から食べ物がなくなってしまうぞ。それも全て人民の心(のあり方)から起こることだ。しかし、物理的な食物がなくなっても、食べるべきものはあるのだ。神の臣民は心配ない。共食い(奪い合い)のようなことにはならないのだ。心得なさい。 (2月16日、ひつくのかみ)
【AIによる解釈】
この短い帖は、世界的な食糧危機という具体的な事象を警告しつつ、その本質と乗り越え方を示しています。
- 食糧危機の原因: 食糧危機は、天災や生産量の問題だけでなく、根本的には「人民の心」、すなわち貪欲や感謝の欠如、不調和な心が原因で引き起こされると指摘しています。物質的な問題の根源に、霊的な問題があるという視点です。
- 二種類の「食物」: 「食物無くなっても食物あるぞ」という言葉は、危機の中にも希望があることを示しています。これは二つの意味に解釈できます。一つは、物理的な食料が不足しても、神の民には奇跡的な方法で霊的、あるいは物理的な糧が与えられるということ。もう一つは、人間はパンのみに生きるにあらず、というように、霊的な糧、精神的な満足こそが真の「食物」であるという教えです。
- 「とも食ひならん」: 最悪の事態、すなわち人々が食料を奪い合うような地獄絵図にはならない、と保証しています。これは、神の計画を信じる人々が、分かち合い助け合うことで、破局的な事態を乗り越えることができるという希望のメッセージです。
第十二帖 (三六三)
【原文】
日本の人民 餌食(えじき)にしてやり通すと、悪の神申してゐる声 人民には聞こへんのか。よほどしっかりと腹帯締めおいて下されよ。神には何もかも仕組てあるから、心配ないぞ。改心出来ねば気の毒にするより方法ないなれど、待てるだけ待ってゐるぞ、月の大神様が水の御守護、日の大神様が火の御守護、お土つくり固めたのは、大国常立の大神様。この御三体の大神様、三日この世構ひなさらねば、此の世、くにゃくにゃぞ。実地を世界一度に見せて、世界の人民一度に改心さすぞ。五十になっても六十になっても、いろは、一二三(ひふみ)から手習ひさすぞ。出来ねばお出直しぞ。慢心、早合点 大怪我のもと、今の人民、血が走り過ぎてゐるぞ、気付けおくぞ。二月十六日、ひつ九のか三。
【現代語訳】
「日本の人民を餌食にしてやる」と悪の神が言っている声が、人民には聞こえないのか。よほどしっかりと腹をくくっておきなさい。神の側では何もかも仕組みが整っているから、心配はいらない。改心ができなければ気の毒な結果にするしかないが、待てるだけは待っているのだ。 月の大神様が水の守護、日の大神様が火の守護、そして大地を創り固められたのは大国常立の大神様である。この三柱の大神様が、たった三日間この世の世話をしなければ、この世はくにゃくにゃになってしまうのだ。 その実地(証拠)を世界中に一度に見せて、世界の人民を一度に改心させるぞ。五十歳になっても六十歳になっても、「いろは」「ひふみ」という基本の基本から学び直しをさせる。それができなければ、出直し(死んでやり直し)だ。慢心や早合点は大怪我のもとだ。今の人民は血が上りすぎている(冷静さを欠いている)。注意しておくぞ。 (2月16日、ひつくのかみ)
【AIによる解釈】
この帖は、見えざる脅威と、神による最終的な強制介入について述べています。
- 悪神の脅威: 人々を破滅に導こうとする「悪の神」の存在を明確に指摘し、その声が聞こえないほど人々が鈍感になっていることに警鐘を鳴らしています。これに対し「腹帯を締める」=覚悟を決めることが求められます。
- 天地創造神の力: 世界は、日・月・地という根源的な三柱の神の守護によって、かろうじて成り立っているという宇宙観を示しています。神が少し手を引くだけで、世界は容易に崩壊する、その絶対的な力と恩恵を忘れてはならないと教えています。
- 世界同時改心: 言葉で伝えても改心しない人々を最終的に目覚めさせるために、「実地を世界一度に見せる」という手段が取られると予告しています。これは、世界中の誰もが否定できないような、大規模な天変地異や超常現象が起こることを示唆します。
- 根本からの学び直し: 新しい世に入るためには、これまでの知識や価値観を一度リセットし、「いろは、ひふみ」という宇宙の根本原理から学び直す必要があります。年齢や社会的地位は関係なく、全ての人が謙虚に学び直さなければ「出直し」となります。現代人がいかに根本から道を誤っているかを指摘しています。
第十三帖 (三六四)
【原文】
楽してよい御用しようと思ふてゐるのは悪の守護神に使はれてゐるのざぞ。人の殺し合ひで此の世の建替出来ると思ふてゐるのも悪の守護神ざ。肉体いくら滅ぼしても、よき世にならんぞ。魂は鉄砲では殺せんのざぞ。魂はほかの肉体にうつりて、目的たてるのざぞ、いくら外国人殺しても、日本人殺しても、よき世は来ないぞ。今迄のやり方、スクリかへて神の申す様にするよりほかに道ないのざ。このたびの岩戸開きは、なかなかぞと申してあろが、見て御座れ、善一筋の、与へる政治で見事建替へてみせるぞ。和合せんとまことのおかげやらんぞ、一家揃ふたらどんなおかげでもやるぞ。一国そろたらどんな神徳でもやるぞ、おのづから頂けるのざぞ。神いらん世にいたして呉れよ。二月の十六日、ひつくか三。
【現代語訳】
楽をして良い御用(神の仕事)をしようと思っているのは、悪の守護神に使われているのだ。人間の殺し合いでこの世の建て替えができると思っているのも、悪の守護神の考えだ。肉体をいくら滅ぼしても、良い世にはならない。魂は鉄砲では殺せないのだ。魂は別の肉体に移って、目的を遂げようとする。いくら外国人を殺しても、日本人を殺しても、良い世は来ない。 今までのやり方をすっかり変えて、神の申す通りにするより他に道はないのだ。この度の岩戸開きは、なかなか大変だと申したであろう。見ていなさい、善一筋の、与える政治で見事に建て替えてみせるぞ。 和合しなければ、まことの御利益は与えないぞ。一家が(和合して)揃えば、どんな御利益でも与える。一国が揃えば、どんな神徳でも与える。それは自ずから頂けるようになるのだ。神を必要としない世にしておくれ。 (2月16日、ひつくのかみ)
【AIによる解釈】
この帖は、建て替えの方法論における根本的な間違いを正し、真の「岩戸開き」の姿を示しています。
- 暴力の完全否定: 戦争や革命といった、暴力や殺し合いによる社会変革を「悪の守護神」のやり方として完全に否定しています。肉体を滅ぼしても、その根底にある憎しみの魂は輪廻転生し、争いは繰り返されるだけだと説きます。これは、武力による平和構築の限界を示唆する、非常に重要なメッセージです。
- 「与える政治」への転換: これまでの奪い合い(領土、富、権力)の政治から、ただ善一筋の「与える政治」へと根本的に転換することによって、世界は建て替えられると宣言します。これは、愛と奉仕、分かち合いを基本とする、全く新しい政治理念です。
- 和合の力: 神からの無限の恵み(おかげ、神徳)を受け取るための絶対条件は「和合」であると説きます。まず最小単位である「一家」が和合し、それが「一国」へと広がっていく。人々が心を一つに合わせることで、奇跡的な力が発動し、神の恵みが自然に与えられるようになります。
- 「神いらん世」の真意: 「神いらん世にして呉れよ」という一節は、ひふみ神示の最終目標を示す衝撃的な言葉です。これは無神論を勧めているのではありません。人々一人ひとりが神性を自覚し、神のように愛と調和を実践できるようになることで、外なる神に頼る必要がなくなる、つまり「人が神になる」という究極の理想の世を指しています。人々が自立した神人となることが、神の最終的な願いなのです。
第十四帖 (三六五)
【原文】
新しき世とは神なき世なりけり。人、神となる世にてありけり。世界中 人に任せて神々は楽隠居なり、あら楽し世ぞ。この世の頭(かしら)いたして居る者から、改心致さねば、下の苦労いたすが長うなるぞ、此処までわけて申しても、実地に見せてもまだわからんのか。世界中のことざから、この方 世界構ふお役ざから、ちと大き心の器持ちて来て下されよ。金も銀も胴も鉄も鉛も皆出てござれ。それぞれにうれしうれしの御用いくらでも与へてとらすぞ。この巻かチの巻。ひつくのか三、二月十六日。
【現代語訳】
新しい世とは、神が(表立っては)いない世であることよ。人が神となる世であることよ。世界中のことを人に任せて、神々は楽隠居をされる。なんと楽しい世の中だろうか。 この世の指導者となっている者から改心しなければ、下の者の苦労が長引くぞ。ここまで詳しく説明し、実地で見せてもまだ分からないのか。 これは世界中のことだから、この方(神)は世界全体を取りまとめる役だから、もう少し大きな心の器を持ってきておくれ。 金も銀も銅も鉄も鉛も、皆出てきなさい。それぞれに「うれしうれし」の役目をいくらでも与えてつかわすぞ。 この巻は「カゼの巻」である。 (ひつくのかみ、2月16日)
【AIによる解釈】
この巻の最終帖は、新しい時代の究極の姿と、そこに向けた最後の呼びかけを力強く宣言しています。
- 人が神となる世: 前帖の「神いらん世」をさらに発展させ、新しい世は「人、神となる世」であると明確に定義しています。これは、人類の霊的な進化の最終目的地です。人々が神性を完全に発揮し、自らの意志で調和した世界を創造するようになれば、神々は安心して「楽隠居」できる。これは、子が成長し自立するのを見守る親の心境にも似ています。
- 指導者の責任: 世の変革は、まず「頭(かしら)」、すなわち指導的立場にある者たちの改心から始めなければならないと、その責任の重さを厳しく指摘しています。指導者が変わらなければ、社会全体の苦しみは長引くばかりです。
- 大きな心の器: 世界規模の計画を理解し、その役割を担うためには、個人的な利害や小さな常識にとらわれない「大きな心の器」が必要です。世界市民として、全人類的な視点を持つことが求められます。
- 万人の使命(御用): 「金も銀も銅も鉄も鉛も」という比喩は、あらゆる個性や能力を持つ全ての人々を指しています。優れた者(金、銀)だけでなく、一見劣っているように見える者(鉛)にも、それぞれに尊い役割(うれしうれしの御用)があると説きます。誰一人として不要な人間はおらず、全ての人が新しい世の創造に参加する使命を持っているという、究極の全的肯定のメッセージです。
「カゼの巻」は、大峠という厳しい風が吹くことを告げると同時に、その風に乗って、全ての人が神となる新しい時代へと飛翔するための、力強い希望と具体的な指針を示しているのです。
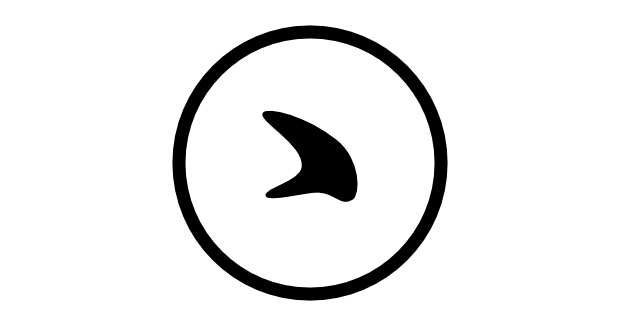





コメント