ひふみ神示の第十三巻「アメの巻」は、第二次世界大戦終結直後の混乱期である昭和20年10月13日から12月19日にかけて降ろされた神示です。全17帖から成り、来るべき世界の大きな変革(建て替え)と、それに伴う人々の心構え、そして新しい世の姿について説かれています。
本巻では、これまでの価値観が根底から覆ること、神と人が一体となる「惟神(かんながら)」の真の意味、そして身魂の洗濯の重要性が繰り返し強調されています。
マルチョンの画像はTOP画像です
第一帖 (三三五)
【原文】
天の日津久の大神(あめの一二の$\大神$)のお神示(ふで)であるぞ、特にお許しもろて書きしらすぞ。十二の巻 説いて知らすのであるぞ、此の巻アメの巻と申せよ、此の度は昔から無かりた事致すのであるから人民には判らん事であるから素直に致すが一等ざぞ、惟神(かんながら)の道とか神道とか日本の道とか今の臣民申してゐるが、それが一等の間違ひざぞと申してあろが、惟神(かんながら)とは神人共に融け合った姿ざぞ。今の臣民 神無くして居るではないか、それで惟神も神道もないぞ、心大きく、深く、広く持ちて下されよ、愈々となるまでは落しておくから見当とれんから、よくこの神示読んでおいて下されよ。世界ぢゅうに面目ない事ないよにせよと申してあろが。足元から鳥立ちてまだ目覚めんのか、神示(ふで)裏の裏までよく読めと申してあろがな。此の道は只の神信心とは根本から違ふと申してあろが、三千世界の大道ざぞ。所の洗濯と身魂の洗濯と一度になる所あるぞ、「イスラ」の十二の流れの源泉(みなもと)判る時来たぞ。命がけで御用つとめてゐると思ふて邪魔ばかり致しておろがな、金や学や智では大峠越せんぞ。神はせよと申すことするなと申すこともあるのぞ、裏の裏とはその事ぞ、よく心得て下さりて取違ひいたすでないぞ。手のひら返すぞ返さすぞ、此の度の岩戸開きは人民使ふて人民助けるなり、人民は神のいれものとなって働くなり、それが御用であるぞ、いつでも神かかれる様に、いつも神かかっていられるようでなくてはならんのざぞ。神の仕組 愈々となったぞ。十月十三日、ひつ九のかみ。
【現代訳】
これは天の日津久の大神(あめの日月の大神)の神示である。特別にお許しをいただいて書き知らせる。第十二巻の内容を説き明かすものであり、この巻を「アメの巻」と呼びなさい。この度のことは、有史以来なかったことを行うのだから、人々には理解できないだろう。だから素直に従うことが一番である。今の民は「惟神(かんながら)の道」や「神道」「日本の道」などと言っているが、それが一番の間違いだと申してあろう。惟神とは、神と人が共に溶け合った姿のことだ。今の民は心に神がいないではないか。それでは惟神も神道もないのだ。心を大きく、深く、広く持ちなさい。いよいよという時が来るまでは落ちぶれさせておくから見当もつかないだろう。だから、よくこの神示を読んでおきなさい。世界中に恥ずかしいことがないようにせよと申してあるだろう。足元から鳥が立つような緊急事態が起きているのに、まだ目覚めないのか。神示は裏の裏までよく読めと申してあるではないか。この道はただの神信心とは根本から違う、三千世界の大道なのだ。土地の浄化(洗濯)と魂の浄化(洗濯)が一度に行われる時が来る。「イスラエル」の十二支族の流れの源がわかる時が来たのだ。命がけで神の務め(御用)をしているつもりで、実際は邪魔ばかりしている者もいる。金や学問、知恵ではこの大峠を越すことはできないぞ。神が「せよ」と言うことを「するな」と言うこともある。裏の裏とはそのことだ。よく心得て、取り違えてはならない。手のひらを返すように態度が変わるぞ、変えさせるぞ。この度の岩戸開きは、人民を使って人民を助けるのだ。人民は神の入れ物となって働く。それが御用である。いつでも神がかりできるよう、常に神がかった状態でなければならない。神の仕組みは、いよいよ最終段階に入ったぞ。
【AIによる解釈】
本帖は「アメの巻」の序論であり、中心的なテーマを提示しています。まず、既存の宗教、特に形式化した神道への批判から入ります。人々が口にする「惟神(かんながら)」は、本来神と人が一体化した状態を指すにもかかわらず、現代人の心には神が不在であるため、それは偽りだと断じています。
そして、これから起こることは人類史上例のない大変革であり、常識や知恵では理解できないため、「素直さ」が最も重要だと説きます。この変革期を「大峠」と表現し、金や学歴、知識では乗り越えられないと断言しています。
また、「神示の裏の裏を読め」「神は『せよ』と言うことを『するな』と言うこともある」という記述は、物事の表面的な意味に囚われず、その奥にある神の真意を汲み取ることの重要性を示唆しています。最後の「人民は神のいれものとなって働く」という一節は、この先の神の計画において、人間が神の意志を体現する能動的な役割を担うことを示しており、ひふみ神示の根幹をなす思想です。
第二帖 (三三六)
【原文】
天の大神様は慈悲深くて何んな偉い臣民にも底知れぬし、地の大神様は力ありすぎて、人民には手におへん見当取れん、そこで神々様を此の世から追い出して悪神の云ふこと聞く人民許りとなりてゐたのであるぞ。七五三(しめ)は神々様をしめ込んで出さぬ為のものと申してある事これで判るであろがな、鳥居は釘付けの形であるぞ、基督(キリスト)の十字架も同様ぞ、基督信者よ改心致されよ、基督を十字架に釘付けしたのは、そなた達であるぞ、懺悔せよ、$\マルチョン$とは外国の事ぞ、$\マルチョン$が神国の旗印ぞ、神国と外国との分けへだて誤ってゐるぞ。大き心持てよ、かがみ掃除せよ、上中下三段に分けてある違ふ血統(ちすじ)を段々に現すぞよ、びっくり箱あくぞ、八九の次は$\マルチョン$であるぞよ。何事もウラハラと申してあろが、ひとがひとがと思ってゐた事 我の事でありたであろがな、よく神示読んでおらんと、キリキリ舞ひせんならんぞ、日本が日本がと思って居た事 外国でありた事もあるであろがな、上下ひっくり返るのざぞ、判りたか。餓鬼までも救はなならんのであるが、餓鬼は食物やれば救はれるが、悪と善と取違へてゐる人民、守護神、神々様 救ふのはなかなかであるぞ、悪を善と取違へ、天を地と信じてゐる臣民人民なかなかに改心六ヶ敷いぞ。我と改心出来ねば今度は止むを得ん事出来るぞ、我程偉い者ないと天狗になりてゐるから気を付ける程 悪ふとりてゐるから、こんな身魂は今度は灰ざぞ、もう待たれん事になったぞ。十月の十四日、ひつ九のかみしるす。
【現代訳】
天の大神様は慈悲が深すぎて、どんなに偉い人間にもその深さは計り知れない。地の大神様は力が強すぎて、人々には手に負えず見当もつかない。だから人々は神々をこの世から追い出し、悪神の言うことばかり聞くようになってしまったのだ。注連縄(しめなわ)は神々を締め出して閉じ込めるためのものだと申したことが、これでわかるだろう。鳥居は神を釘付けにする形であり、キリストの十字架も同様だ。キリスト信者よ、改心しなさい。キリストを十字架に釘付けにしたのは、あなた方自身なのだ。懺悔せよ。「⦿(マルチョン)」は外国のことだと思っているが、「⦿(マルチョン)」こそが神国の旗印なのだ。神国と外国を区別する考え方が間違っている。大きな心を持ちなさい。鏡(心)を掃除せよ。上中下の三段階に分かれている違う血筋を、順々に明らかにいくぞ。びっくり箱が開くのだ。八、九の次は十(⦿)であるぞ。何事も裏腹だと申してあろう。他人事だと思っていたことが、実は自分のことであっただろう。よく神示を読んでいないと、きりきり舞いさせられることになるぞ。「日本のことだ」と思っていたことが、実は外国のことだったということもあるだろう。上下がひっくり返るのだ、わかったか。餓鬼のような者まで救わねばならないが、餓鬼は食べ物を与えれば救われる。しかし、悪と善を取り違えている人々やその守護神、神々を救うのは大変なことだ。悪を善と取り違え、天を地だと信じている人々は、なかなか改心が難しい。自ら改心できなければ、今度はやむを得ない手段をとることになるぞ。自分ほど偉い者はいないと天狗になっているから、気をつけるほどに悪が肥え太っている。こんな魂は、今度は灰にするしかない。もう待っていられない事態になったのだ。
【AIによる解釈】
本帖は、人類が真の神々からいかに離れてしまったかを、象徴的な表現を用いて説明しています。人々が神聖視する注連縄(しめ)や鳥居、さらにはキリストの十字架までもが、実は「神々を封じ込めるための道具」であったという衝撃的な解釈を提示します。これは、形式化・形骸化した信仰が、本来の神の力を妨げているという痛烈な批判です。
「⦿(マルチョン)」が神国の印であり、八、九の次に来る(=十)という記述は、完成・統合を象徴しています。そして、「日本と外国の区別は間違い」「上下がひっくり返る」という言葉は、国境や既存の序列といった人間的な価値観が崩壊し、新しい秩序が生まれることを預言しています。
最も救いがたいのは、物理的に飢えている者ではなく、「悪を善と取り違えている者」だと指摘し、価値観の根本的な転換、すなわち自発的な改心ができなければ、強制的な粛清(灰にする)もやむなしという厳しい警告で締めくくられています。
第三帖 (三三七)
【原文】
草木は身を動物虫けらに捧げるのが嬉しいのであるぞ。種は残して育ててやらねばならんのざぞ、草木の身が動物虫けらの御身(みみ)となるのざぞ、出世するのざから嬉しいのざぞ、草木から動物虫けら生れると申してあろがな、人の身(み)神に捧げるのざぞ、神の御身(みみ)となること嬉しいであろがな、惟神のミミとはその事ぞ、神示よく読めば判るのざぞ、此の道は先に行く程 広く豊かに光り輝き嬉し嬉しの誠の惟神の道で御座るぞ、神示よく読めよ、何んな事でも人に教へてやれる様に知らしてあるのざぞ、いろはに戻すぞ、一二三(ひふみ)に返すぞ、一二三(ひふみ)が元ぞ、天からミロク様みづの御守護遊ばすなり、日の大神様は火の御守護なさるなり、此の事 魂までよくしみておらぬと御恩判らんのざぞ。悪も善に立ち返りて御用するのざぞ。善も悪もないのざぞと申してあろがな、$\マルチョン$の国真中に神国になると申してあろがな、日本も外国も神の目からは無いのざと申してあろうが、神の国あるのみざぞ、判りたか。改心すれば$\マルチョン$(たま)の入れかへ致して其の場からよき方に廻してやるぞ、何事も我がしてゐるなら自由になるのであるぞ。我の自由にならんのはさせられてゐるからざぞ、此の位の事判らんで神の臣民と申されんぞ、国々所々に宮柱太敷キ立てよ、たかしれよ。此の先は神示に出した事もちいんと、我の考へでは何事も一切成就せんのざぞ、まだ我出して居る臣民ばかりであるぞ。従ふ所には従はなならんぞ、従へばその日から楽になって来るのざぞ、高い所から水流れる様にと申して知らしてあろがな。十月の十五日、ひつ九のかみ。
【現代訳】
草木は、その身を動物や虫けらに捧げることを喜んでいるのだ。ただし、種は残して育ててやらねばならない。草木の体が動物や虫けらの体となる。それは出世するのだから嬉しいのだ。草木から動物や虫けらが生まれると申してあろう。同様に、人の身は神に捧げるのだ。神の御身(みみ)となることは嬉しいことだろう。惟神の「ミミ」とはそのことだ。神示をよく読めばわかる。この道は、進めば進むほど広く豊かに光り輝く、喜びの誠の惟神の道なのである。神示をよく読めば、どんなことでも人に教えてやれるように知らせてあるのだ。物事を「いろは」(=終わり、旧来の仕組み)から「ひふみ」(=始まり、根源)に戻すのだ。ひふみが元である。天からは弥勒(ミロク)様が水の御守護をされ、日の大神様は火の御守護をされる。このことが魂の奥底まで染み込んでいないと、御恩はわからないのだ。悪も善に立ち返って神の務めをする。善も悪もないと申してあろう。世界の真ん中に神国ができると申してあろう。日本も外国も、神の目から見れば区別はないのだ。ただ神の国があるだけだ、わかったか。改心すれば、魂(たま)を入れ替えて、その場から良い方へ導いてやる。何事も自分がしているのであれば自由になるはずだ。自分の自由にならないのは、何かに「させられている」からだ。このくらいのことがわからなくては神の民とは言えない。国々、所々に宮柱を太くしっかりと立てなさい。統治しなさい。この先は、神示に示したことを用いなければ、自分の考えでは何事も一切成就しない。まだ我を出している者ばかりだ。従うべきところには従わなければならない。従えばその日から楽になる。水が高い所から低い所へ流れるように、自然の理に従いなさいと知らせてあるだろう。
【AIによる解釈】
本帖は、「自己犠牲と奉仕」の喜びを自然界のサイクルに例えて説明しています。草木が動物に食べられることを「出世」と表現し、それと同様に人間が神に身を捧げることは、より高次の存在へと昇華する喜びの道(惟神の道)であると説きます。
「いろはに戻すぞ、一二三に返すぞ」という言葉は、終末的な旧秩序から根源的な新秩序への回帰を意味します。ここでの「ひふみ」は、万物の始まり、根源的な力を象徴しています。
また、「善も悪もない」「日本も外国もない」という教えは、二元論的な対立を超越した神の視点を示しています。すべての存在は最終的に神の計画に組み込まれ、役割を果たすとされます。真の改心とは、この神の視点を受け入れ、我(が)を捨て、魂(たま)を入れ替えてもらい、自然の理(高い所から水が流れるように)に従うことだと教えています。この「従う」ことは、盲従ではなく、宇宙の法則に沿って生きることを意味しています。
第四帖 (三三八)
【原文】
世界の臣民 皆手引き合って行く時来た位 申さいでも判ってゐるであろが、それでもまだまだ一苦労二苦労あるぞ、頭で判っても肚で判らねば、発根(ほっこん)の改心出来ねば、まだまだ辛い目に会ふのざぞ、人民 自分で首くくる様なことになるのざぞ、判りたであろ。天の御三体の大神様と ちのおつちの先祖様でないと今度の根本のお建替出来んのざぞ、判りても中々判らんであろがな。洗濯足らんのであるぞ。今度はめんめにめんめの心改めて下されよ、神は改めてあるが、神から改めさすのでは人民可哀想なから めんめめんめで改めて下されよ、改まっただけ おかげあるのざぞ。今度の岩戸開いたら末代の事ざぞ、天地の違ひに何事も違ふのざぞ。信者引張りに行って呉れるなよ、神が引き寄せるから、役員の所へも引き寄せるから、訪ねて来た人民に親切尽くして喜ばしてやれと申してあろが、人民喜べば神嬉しきぞと申してあろが、草木喜ばしてやれよ、神示よく読めばどうしたら草木動物喜ぶかと云ふことも知らしてあるのざぞ、今迄の心 大河に流してしまへば何もかもよく判って嬉し嬉しとなるのざぞ、まだまだ世界は日に日にせわしくなりて云ふに云はれん事になって来るのざから、表面(うわつら)許り見てゐると判らんから、心大きく世界の民として世界に目とどけてくれよ、元のキの神の子と、渡りて来た神の子と、渡りて来る神の子と三つ揃ってしまはねばならんのぞ、アとヤとワと申してあるが段々に判りて来るのざぞ。実地のことは実地の誠の生神でないと出来はせんぞ、臣民はお手伝ひぞ、雨風さへどうにもならんであろうが、生物 何んで息してゐるか、それさへ判らいで居て何でも判ってゐると思ってゐるが鼻高ぞと申すのざ、今の内に改心すれば名は現はさずに許してよき方に廻してやるぞ、早う心改めよ。十月十六日、ひつ九のか三。
【現代訳】
世界の民が皆で手を取り合っていく時が来たことくらい、言われなくてもわかっているだろう。それでも、まだまだ一苦労も二苦労もある。頭でわかっても肚(はら)で理解しなければ、根っこからの改心ができなければ、まだまだ辛い目に遭うのだ。人々が自分で自分の首を絞めるようなことになる。わかっただろう。天の御三体の大神様と、地の先祖様でなければ、この度の根本的な建て替えはできないのだ。わかったようでも、なかなか本当にはわからないだろうが。洗濯が足りないのだ。今度は一人ひとりが自分の心を改めなさい。神は準備が整っているが、神の方から改めさせるのでは人々が可哀想だから、各自で改めなさい。改まった分だけ、おかげがあるのだ。この度の岩戸が開いたら、それは末代まで続くことだ。天と地ほどに、何もかもが違ってくるのだ。信者を無理に引っ張ってこようとするな。神が必要な人を引き寄せるから。役員の所へも引き寄せるから、訪ねてきた人には親切を尽くして喜ばせてあげなさいと申してあろう。人々が喜べば神も嬉しいのだと申してあろう。草木も喜ばせてやりなさい。神示をよく読めば、どうすれば草木や動物が喜ぶかも知らせてあるのだ。今までの心を大河に流してしまえば、何もかもがよくわかり、嬉し嬉しとなるのだ。世界はこれから日に日に忙しくなり、言いようのない事態になってくるのだから、表面だけ見ているとわからなくなる。心を大きく持ち、世界の民として世界に目を向けてくれ。「元のキの神の子」(日本古来の霊統)と、「渡りて来た神の子」(大陸などから渡来した霊統)と、「渡りて来る神の子」(これから来る霊統)の三つが揃わなければならないのだ。「ア」と「ヤ」と「ワ」(※三つの霊統を象徴する音)と申してあるが、段々とわかってくるだろう。実際(実地)のことは、実地を司る誠の生神でなければできはしない。民はその手伝いなのだ。雨や風さえどうにもできないだろう。生物がなぜ息をしているのか、それさえわからずに、何でもわかっていると思っているのは鼻高々なのだ。今のうちに改心すれば、名前を公にすることなく許し、良い方へ導いてやる。早く心を改めよ。
【AIによる解釈】
本帖は、来るべき世界統一の時代認識を示しつつ、その過程の困難さを説きます。「頭で判っても肚で判らねば」という言葉は、知識としての理解ではなく、腹の底からの体感的・魂的な納得、すなわち「発根の改心」が不可欠であることを強調しています。
重要なのは、**「めんめめんめに改めて下されよ」**という呼びかけです。神が強制的に変えるのではなく、あくまで個人の自発的な心の変革が求められています。その変革の度合いに応じて神の「おかげ」があるとされ、個人の内面が世界の現実に直結することを示唆します。
また、「元のキの神の子」「渡りて来た神の子」「渡りて来る神の子」の三者が揃う必要があるというビジョンは、特定の民族や人種だけでなく、地球上のあらゆる霊的系統の調和と統合が新しい時代の必須条件であることを示しています。これはひふみ神示が排他的なナショナリズムではなく、普遍的な人類の和合を目指していることを明確にする重要な部分です。
第五帖 (三三九)
【原文】
神示に書かしたら日月の神(一二$\大神$)が天明に書かすのであるから其の通りになるのであるぞ、皆仲よう相談して悪き事は気付け合ってやりて下され、それがまつりであるぞ、王(おー)の世が$\王$(さかさまのおー)の世になって居るのを今度は元に戻すのであるから、その事 早う判っておらんと一寸の地の上にもおれん事になるぞ、今度の戦(いくさ)すみたら世界一平一列一体になると知らしてあるが、一列一平 其の上に神が居ますのざぞ、神なき一平一列は秋の空ぞ、魔の仕組、神の仕組、早う旗印見て悟りて下されよ、神は臣民人民に手柄致さして万劫末代、名残して世界唸らすのざぞ、これ迄の事は一切用ひられん事になるのざと申してあろ、論より実地見て早う改心結構、何事も苦労なしには成就せんのざぞ、苦労なしに誠ないぞ、三十年一切(ひときり)ぞ、ひふみ肚に入れよ、イロハ肚に入れよ、アイウエオ早ようたためよ、皆えらい取違ひして御座るぞ、宮の跡は草ボウボウとなるぞ、祭典(まつり)の仕方スクリと変へさすぞ、誠の神の道に返さすのざから、今度は誠の生神でないと人民やらうとて出来はせんぞ。十月十七日、ひつ九のかミ。
【現代訳】
神示に書かせているのは日月の大神が天明(※岡本天明)に書かせているのだから、その通りになるのだ。皆で仲良く相談し、悪いことは互いに気づかせ合ってやりなさい。それが「まつり(祭り・政)」であるぞ。「王」の世が逆さまの「壬(みずのえ)」の世になっているのを、今度は元に戻すのだから、そのことを早くわかっていないと、わずかな土地の上にもいられなくなるぞ。この度の戦争(第二次大戦)が終わったら世界は一平・一列・一体になると知らせてあるが、その一平・一列の上には神がおられるのだ。神のいない一平・一列は、変わりやすい秋の空のようにはかないものだ。魔の仕組みか、神の仕組みか、早くその旗印を見て悟りなさい。神は民に手柄を立てさせ、万劫末代までその名を残し、世界を唸らせるのだ。これまでのことは一切通用しなくなると申してあろう。議論より、実際に起きることを見て早く改心するのが良い。何事も苦労なしには成就しない。苦労なくして誠はないのだ。三十年で一区切りだ。ひふみ(根源の理)を肚に入れよ。イロハ(旧来の理)を肚に入れよ。アイウエオ(物質的な知恵)は早くたたみ(片付け)なさい。皆、大変な取り違いをしている。神社の跡は草がぼうぼうになるぞ。祭りの仕方もすっかりと変えさせる。誠の神の道に返すのだから、今度は誠の生きた神でなければ、人々がやろうとしてもできはしないのだ。
【AIによる解釈】
本帖は、世の中の秩序が逆転している現状(王の世が逆さまの王=壬の世)を指摘し、これを本来の姿に戻すのが「建て替え」であると定義します。そして、戦後に訪れるであろう「世界一平一列一体」という理想、すなわち世界平和や平等主義が、「神」を頂点に置かない限り、それは脆く、はかない「魔の仕組み」であると警告します。
ここで言う「まつり」とは、単なる儀式ではなく、人々が互いに忠告し合い、高め合う共同体の営みそのものを指しています。これは神示全体を貫く重要な思想です。
また、「ひふみ肚に入れよ、イロハ肚に入れよ、アイウエオ早ようたためよ」という指示は、象徴的です。「ひふみ」(神の理)、「イロハ」(仏の理)、「アイウエオ」(物質科学・唯物論)の三つを指し、これら全てを一度おさめ(肚に入れ、たたみ)、その上で神の理を中心として再構築する必要があることを示唆しています。既存の権威(宮)が廃れ、祭りの仕方も根本から変わると預言しており、全く新しい霊的秩序の到来を告げています。
第六帖 (三四〇)
【原文】
神示よく読めと、神示よく肚に入れと申してあるが、神示肚に入れると胴すわるのざぞ、世界から何んな偉い人が出て来て何んな事尋ねても教へてやれる様になるのざぞ、神示胴に入れて頭下げて天地に働いて下されよ、まつりて下されよ、素直になれば其の場から其の場其の場で何事も神が教へてやるから、力つけて導いてやるから、何んな神力でも授けてやるぞ。一二三四五六七八九十百千卍(ひとふたみよいつむゆななやここのたりももちよろず)授け申して神人となるぞ。我さえよけらよいとまだ思って御座る臣民まだで御座るぞ、自分一人で生きてゆけんぞ、神許りでも生きてゆけんぞ、爪の垢でもだてについてゐるのではないのざぞ、判らんと申しても余りで御座るぞ、まつりせよ、地(つち)にまつろへよ、天(あめ)にまつろへよ、人にまつろへよ、草木動物にまつろへよ、と、くどう知らしてあるのに未だ判らんのか、神拝む許りがまつりでないぞ。待ちに待ちし日の出の御代となりにけり、一二三(ひふみ)いろはの世はたちにけり。身慾信心してゐる臣民人民、今に神示聞けぬ様に いれものつんぼになるのざぞ、きびしくなって来るぞ、毒にも薬にもならん人民、今度は役に立たんのざぞ、悪気ない許りでは一二(ひつき)の御民とは申されんぞ。あら楽し、黒雲一つ払ひけり、次の一つも払ふ日近し。淋しくなりたら神示尋ねて御座れ、神示読まねば益々判らん事になったであろうが、天国に底ない様に地獄にも底ないぞ、何処までも落ちるぞ、鼻高の鼻折らな人民何んと申しても神承知出来ん。十一月二十三日、ひつ九のかミ。
【現代訳】
神示をよく読め、神示をよく肚(はら)に入れろと申してあるが、神示を肚に入れると胴が据わる(覚悟が決まり、動じなくなる)のだ。世界中からどんな偉い人が出てきて何を尋ねられても、教えてやれるようになるのだぞ。神示を胴に入れて、頭を下げて天地のために働きなさい。まつり(奉仕)をしなさい。素直になれば、その時その場で何事も神が教えてやるから、力をつけて導いてやるから、どんな神力でも授けてやるぞ。「ひとふたみよいつむゆななやここのたりももちよろず」の全てを授けて神人(かみひと)となるのだ。自分さえ良ければよいとまだ思っている民は、まだ駄目だ。自分一人では生きてはいけない。神だけでも生きてはいけない。爪の垢ですら、意味なくついているのではないのだ。わからないと言っても、あまりにひどすぎる。まつりをせよ。地にまつろえ(従い奉仕せよ)、天にまつろえ、人にまつろえ、草木動物にまつろえと、くどくど知らせているのにまだわからないのか。神を拝むだけがまつりではないのだ。「待ちに待った日の出の御代となった、ひふみといろはが立つ世となったのだ。」我欲のための信心をしている民は、やがて神示が聞こえないように、器(からだ)が聾(つんぼ)になるのだぞ。厳しくなってくるぞ。毒にも薬にもならないような中途半端な人々は、今度は役に立たない。ただ悪気がないというだけでは、日月(ひつき)の民とは言えないのだ。「ああ、楽しい。黒雲が一つ払われた。次の黒雲を払う日も近い。」寂しくなったら神示を訪ねてきなさい。神示を読まなければ、ますますわからないことになったであろう。天国に底がないように、地獄にも底はないのだ。どこまでも落ちるぞ。天狗になっている者の鼻をへし折らなければ、人々が何を言っても神は承知できない。
【AIによる解釈】
本帖の核心は、「まつり」の真の意味の再定義です。それは神社で神を拝むといった限定的な行為ではなく、天地、人、自然(草木動物)のすべてに対して奉仕し、調和した関係を築くことであると説きます。この普遍的な奉仕の精神こそが、新しい時代を生きる基本姿勢となります。
「神示を肚に入れると胴が据わる」という表現は、神示の教えが単なる知識ではなく、生き方の軸となり、何事にも動じない不動の精神状態(肚が据わる)をもたらすことを示しています。
また、「自分一人で生きてゆけんぞ、神許りでも生きてゆけんぞ」という一節は、神と人との相互依存的な関係を強調しています。神と人が協力して初めて世界は成り立ち、どちらか一方だけでは不完全であるという思想です。
「天国に底ない様に地獄にも底ない」という警告は、人の意識次第で無限に上昇もできれば、無限に堕落もできるという霊的現実の厳しさを示しています。自己中心的な信心や中途半端な態度は許されず、「鼻高(天狗)」、すなわち傲慢さを捨てることが、神の計画を受け入れるための絶対条件であると厳しく諭しています。
第七帖 (三四一)
【原文】
神の心の判りた臣民から助ける御用にかかりて呉れよ、助ける御用とは清めの御用で御座るぞ、天地よく見て悟りて呉れよ。三四五(みよいづ)の御用は出来上がりてしまはんと御用してゐる臣民にはさっぱり判らんのであるぞ、つかわれてゐるから判らんのであるぞ、出来上がりてから これは何んとした結構な事でありたかとビックリするのざぞ。アメのひつ九のか三とはアメの一二の神で御座るぞ、アメの$\日月$(つきひ)の神で御座るぞ、元神で御座るぞ、ムの神ぞ、ウの神ぞ、元のままの肉体持ちて御座る御神様ぞ、つちのひつ九のおん神様ぞ、つちの$\日月$(ひつき)の御神様と今度は御一体となりなされて、今度の仕組 見事成就なされるので御座るぞ、判りたか、九二つちの神 大切申せとくどう知らしてあろがな、今迄の臣民人民、九二の御先祖の神おろそかにしてゐるぞと申して知らしてあらう、神は千に返るぞ、九二つちつくること何んなに難儀な事か人民には判るまいなれど、今度さらつの世にするには人民もその型の型の型位の難儀せなならんのざぞ。それでよう堪(こば)れん臣民 沢山にあるのざぞ、元の神の思ひの何万分の一かの思ひせんならんのざぞ、今度 世変りたら、臣民 此の世の神となるのざぞ。国の洗濯はまだまだ楽であるが、ミタマの洗濯 中々に難しいぞ、人民 可哀想なから延ばしに延ばして御座るのざぞ、幾ら言ひ聞かしても後戻り許りぢゃ、言ひ聞かして改心出来ねば改心する様致すより もう手ない様になってゐるのざ。何時どんな事あっても神は知らんぞ、上から下までも誰によらん今迄の様な我儘させんぞ、役員 馬鹿にならなならんぞ、大のつく阿呆になれよ、$\うかんむり$のつく阿呆にあやまって呉れるなよ、阿呆でないと今度の誠の御用なかなかざぞ。命捨てて命に生きる時と申してあろがな、非常の利巧な臣民人民アフンで御座るぞ、今にキリキリ舞するのが目に見へんのか。何時も変らぬ松心でおれと申して御座ろがな、建替へ致したら世界は一たん寂しくなるぞ、神が物申して居る内に改心せなならんぞ、後悔間に合はんと申してあろがな。十一月二十三日、ひつ九のかミ。
【現代訳】
神の心がわかった民から、人々を助ける務め(御用)にかかってくれ。助ける御用とは、清める御用である。天地の動きをよく見て悟りなさい。「みろく(三四五)の世」を創る御用は、完成するまでは、その務めをしている民にはさっぱりわからないものだ。神に使われている間はわからないのだ。完成してから「これはなんと素晴らしいことであったか」とびっくりするのだ。「アメのひつ九の神」とは「天の日月の神」であり、元つ神であり、「ム(無・始原)」の神、「ウ(有・産霊)」の神であり、もとのままの肉体を持っておられる神様であるぞ。その神が「つちのひつ九の神(国常立尊)」、すなわち「地の日月の神」と、この度一体となられて、今度の仕組みを見事に成就されるのだ。わかったか。「くに(九二)つちの神」を大切にせよと、くどくど知らせてあろう。今までの人々は、国土の祖神をおろそかにしていると知らせてあるだろう。九二(くに)は千(チ・血)に返るのだ。国を創ることがどれほど大変なことか、人々にはわかるまいが、今度、更地(さらつ)の世にするには、人々もその雛形(ひながた)の雛形の雛形くらいの苦労はしなければならないのだ。それで耐えられない民が沢山出てくる。元の神の想いの何万分の一かの想いをしなければならないのだ。この世が変わったら、民はこの世の神となるのだ。国の洗濯(改革)はまだ楽な方だが、魂(ミタマ)の洗濯はなかなか難しいぞ。人々が可哀想だから、延ばしに延ばしているのだ。いくら言い聞かせても後戻りばかりだ。言い聞かせて改心できないなら、改心するように仕向けるより他に手がない状況になっている。いつどんなことがあっても、神は知らないぞ。上の者から下の者まで、誰であろうと今までの様な我儘はさせない。役員は馬鹿にならなければならない。「大」のつく阿呆になりなさい。「宇(宇宙)」のつく阿呆には、あやまるでないぞ(※表面的な阿呆ではなく、本質的な阿呆になれ)。阿呆でないと、この度の誠の御用はなかなか務まらないのだ。命を捨てて、真の命に生きる時だと申してあろう。非常に利口な人々は、息もつけない(アフン)ことになるぞ。やがてきりきり舞いするのが目に見えないのか。いつも変わらぬ松のような心でいなさいと申してあろう。建て替えをしたら、世界は一旦寂しくなる。神がこうして物を言っているうちに改心しなければならない。後悔しても間に合わないと申してあろう。
【AIによる解釈】
本帖では、神の計画の壮大さと、それを担う神々の正体が明かされます。「アメのひつ九の神(天の日月の神)」と「つちのひつ九の神(地の日月の神)」が一体となることで、計画が成就すると述べられています。これは天の原理と地の原理、すなわち霊的世界と物質世界が統合されることを象徴しています。
人々に課せられる試練は、**「国の洗濯」よりもはるかに困難な「ミタマの洗濯」**であると強調されます。これは社会制度の改革よりも、個々人の内面、魂の浄化がいかに難しいかを示しています。
その困難な御用を成し遂げるための心構えとして、**「大のつく阿呆になれ」と説かれます。これは、人間の小賢しい知恵(利口)を捨て、全てを神に委ねる絶対的な素直さと無心さを求めるものです。利口な者ほど、自らの知識や常識が邪魔をして新しい時代に対応できず、破綻(アフン)すると警告します。「命捨てて命に生きる」**とは、自我(小さな命)を捨てて、神と共にある永遠の生命(大きな命)に生きることを意味する、本帖の核心的なメッセージです。
第八帖 (三四二)
【原文】
大難小難にと祈れと申してくどう知らしてあろがな、如何様にでも受け入れてよき様にしてやる様仕組てある神の心判らんか、天災待つは悪の心、邪と知らしてあるがまだ判らんのか、くにまけて大変待ちゐる臣民 沢山あるが、そんな守護神に使はれてゐると気の毒になりて来るぞ、よく神示読んで下されよ。今の守護神、悪の血筋眷属であるぞ、悪も御役ながら奥表に出ては誠おさまらんぞ、悪結構な世は済みて、善結構、悪結構、卍(ホトケ)結構、基(ヤソ)結構、儒結構(コトゴトク)の世となりなる神の仕組 近くなって来たぞ。世の元からの仕組、中行く仕組、天晴(アッパレ)三千世界結構であるぞ、心の不二も晴れ晴れとなるぞ、結構々々。甘くてもならんぞ、辛(カラ)くてもならんぞ、甘さには辛さいるぞ、天の神様許りではならんのざ、くどう申して此処迄知らしてゐるにまだ判らんのか、心さっぱり大河に流して神示読んで下されよ、何時迄も神待たれんぞ、辛さには甘さかげにあるのざぞ、此の道理よく判るであろがな、水の味 火の味 結構ぞ、恐い味ない様な結構な恐さであるぞ、喜びであるぞ、苦しみであるぞ、此の道理よく判りたか。神の御恵み神の御心判りたか、御心とは三つの御心ぞ、一と十と$\うかんむり$とであるぞ、御心結構ぞ、世の元の神の仕組の現はれて三千世界光り輝く、あなさやけ。十一月二十七日、ひつくのか三。
【現代訳】
大難を小難にできるように祈れと、くどくど知らせてあるだろう。どのような事態になっても、それを受け入れて良い方向へ導いてやる仕組みになっている神の心がわからないのか。天災が起こるのを待望むのは悪の心、邪(よこしま)な心だと知らせてあるのに、まだわからないのか。国が負けて大変なことになるのを待ち望んでいる民が沢山いるが、そのような守護神に使われていると気の毒なことになるぞ。よく神示を読みなさい。今の多くの守護神は、悪の血筋の眷属なのだ。悪にも役割はあるが、表に出て威張っていては誠の世は治まらない。悪が幅を利かせる世は終わり、善も結構、悪も結構、仏教も結構、キリスト教も結構、儒教も結構、と全てが結構となる世、そのような神の仕組みが近付いてきたぞ。世の元からの仕組み、中道を行く仕組み、天晴れ、三千世界は結構なものになるのだ。心の中の富士(不二)も晴れ晴れとなるぞ。結構、結構。甘いだけでもいけない。辛いだけでもいけない。甘さには辛さが必要だ。天の神様だけでは世は成り立たないのだ。くどくどとここまで知らせているのに、まだわからないのか。心をさっぱりと大河に流すように空にして、神示を読みなさい。いつまでも神は待ってくれないぞ。辛さの中には甘さが陰としてあるのだ。この道理はよくわかるだろう。水の味も火の味も結構なものだ。恐ろしい味がないかのような、結構な恐ろしさであり、喜びであり、苦しみである。この道理がよくわかったか。神の御恵み、神の御心がわかったか。御心とは三つの御心だ。「一(はじめ)」と「十(すべて)」と「宀(うちゅう)」であるぞ。御心は結構なものだ。世の元からの神の仕組みが現れて、三千世界は光り輝く。ああ、清々しいことよ。
【AIによる解釈】
本帖は、来るべき新しい世が、対立を超えた統合の世界であることを明確に示しています。「善結構、悪結構、卍(仏教)結構、基(キリスト教)結構、儒(儒教)結構」という言葉は、特定の思想や宗教だけが優れているのではなく、全ての教えがその役割を認められ、調和する時代が来ることを預言しています。これは、二元論的な善悪の戦いの終焉を意味します。
しかし、その世界に至るためには、**「甘さには辛さ」「辛さには甘さ」**が必要であるという弁証法的なプロセスが不可欠であると説きます。天の神(霊、理想)だけでも、地の神(物質、現実)だけでも不完全であり、両者の統合が求められます。
「天災待つは悪の心」という警告は、破局を望むような破壊的な思想を厳しく戒めています。神の計画は破壊そのものが目的ではなく、大難を小難に収め、最終的な調和に至ることが本質であると教えています。
最後に示される「三つの御心」、すなわち「一(始原)」「十(十字・統合)」「宀(宇宙・全てを包む)」は、この神の計画の根源、プロセス、そして全体像を象徴的に表しています。
第九帖 (三四三)
【原文】
神の智と学の智とは始は紙一重であるが、先に行く程ンプ出来て来て天地の差となるぞ、$\マルチョン$の神の薬のやり方 悪の神の毒のやり方となるぞ、神の御用が人の御用ぞ、人の御用が神の御用であるなれど、今の臣民 神の御用するのと人の御用するのと二つに分けてゐるが、見苦しき者にはこれからは御用致させん事にきまりたから気付けておくぞ、何事も順正しくやりて下されよ、神は順であるぞ、順乱れた所には神の能(はたらき)現はれんぞ。何もせんでゐて、よき事許り待ちてゐると物事後戻りになるぞ、神の道には後戻りないと申してあろがな、心得なされよ、一(ハジメ)の火 消へてゐるでないか、まだ判らんか、都会へ都会へと人間の作った火に集まる蛾(が)の様な心では今度の御用出来はせんぞ、表面(うわつら)飾りてまことのない教への所へは人集まるなれど、誠の道伝へる所へは臣民なかなか集まらんぞ、見て御座れよ、幾ら人少なくても見事なこと致して御目にかけるぞ、縁ある者は一時に神が引寄せると申してあろがな、人間心で心配致して呉れるなよ。目眩(めまひ)する人も出来るぞ、ふんのびる人も沢山に出来て来るぞ。行けども行けども白骨許りと申してあろがな、今のどさくさにまぎれて悪魔はまだえらい仕組致して上にあがるなれど、上にあがりきらん内にぐれんぞ、せめて三日天下が取れたら見物であるなれど、こうなることは世の元から判ってゐるから もう無茶な事は許さんぞ。軽い者程 上に上に上がって来るぞ、仕組通りなってゐるのざから臣民心配するでないぞ。今度 神の帳面から除かれたら永遠に世に出る事出来んのであるから、近慾に目くれて折角のお恵みはづすでないぞ、神 キつけておくぞ。人の苦しみ見てそれ見た事かと申す様な守護神に使はれてゐる と気の毒出来るぞ、世建替へて先の判る世と致すのぢゃぞ、三エスの神宝(かんだから)と、3S(スリーエス)の神宝とあるぞ、毒と薬でうらはらであるぞ。五と五では力出んぞ、四と六、六と四、三と七、七と三でないと力生れんぞ、力生れるから、カス出来るのざから掃除するのが神の大切な仕事ぞ、人民もカスの掃除する事 大切な御役であるぞ、毒と薬と薬と毒で御座るぞ、搗(つ)きまぜて こねまぜて天晴(あっぱれ)此の世の宝と致す仕組ざぞ、判りたか。一方の3Sより判らんから、人民 何時も悪に落ち込むのぢゃ、此の道は中行く道と申して知らしてあろがな、力余ってならず、力足らんでならず、しかと手握りてじっと待ってゐて下されよ、誠の教ばかりでは何もならんぞ、皆に誠の行(オコナイ)出来んと此の道開けんぞ、理屈申すでないぞ、幾ら理屈立派であっても行(オコナイ)出来ねば悪であるぞ、此の世の事は人民の心次第ぞ。十一月二十七日、ひつくのか三。
【現代訳】
神の智恵と人間の学問の智恵とは、初めは紙一重の差だが、先へ行くほどに差が開き、天と地ほどの違いになる。⦿(マルチョン)の神の薬の用い方が、悪神にとっては毒の用い方となるように、表裏一体なのだ。神の御用は人の御用であり、人の御用は神の御用なのだが、今の民は神の御用と人の御用を二つに分けて考えている。そのような見苦しい者には、これからは御用をさせないことに決まったから、気をつけておくぞ。何事も順序正しく行いなさい。神は順序そのものである。順序が乱れた所には、神の働きは現れない。何もしないで良いことばかり待っていると、物事は後退してしまうぞ。神の道に後戻りはないと申してあろう。心得るがよい。始めの火(情熱・初心)が消えているではないか、まだわからないのか。都会へ都会へと、人間が作った火に集まる蛾のような心では、この度の御用はできはしない。表面を飾った誠のない教えの所には人が集まるが、誠の道を伝える所には民はなかなか集まらないものだ。だが、見ていなさい。いくら人数が少なくても、見事なことをして御目にかける。縁のある者は、時が来れば神が一時に引き寄せると申してあろう。人間的な心で心配してくれるな。めまいがする人や、気絶する人も沢山出てくるぞ。「行けども行けども白骨ばかり」と申してあろう。今の混乱に乗じて悪魔はまだ大掛かりな仕組みで上へのし上がろうとするが、上がりきる前にひっくり返るぞ。せめて三日天下が取れたら見物だが、こうなることは世の元からわかっているから、もう無茶は許さない。軽い者(中身のない者)ほど、上へ上へと上がってくるが、それも仕組み通りなのだから民は心配するな。今度、神の帳面から除かれたら、永遠に世に出ることはできないのだから、目先の欲に目がくらんで、せっかくの御恵みを逃すでないぞ。神は気をつけるように言っておく。人の苦しみを見て「それ見たことか」と言うような守護神に使われていると、気の毒なことになるぞ。世を建て替えて、先のことがわかる世にするのだ。三種の神宝(ミエスのカンダカラ)と、3S(スリーエス)の神宝とがある。毒と薬で裏腹なのだ。五と五では力は出ない。四と六、六と四、三と七、七と三のような陰陽和合でなければ力は生まれない。力が生まれるから、カスもできる。その掃除をするのが神の大切な仕事であり、人々もカスの掃除をすることが大切な役目なのだ。毒と薬、薬と毒なのだ。これらを搗き混ぜ、こね混ぜて、天晴れ、この世の宝とする仕組みなのだ。わかったか。一方の3S(※毒の方)しかわからないから、人々はいつも悪に落ち込むのだ。この道は中道を行く道だと知らせてあろう。力が余ってもいけないし、足りなくてもいけない。しっかりと手を握り合ってじっと待っていなさい。誠の教えだけでは何もならない。皆が誠の行い(オコナイ)をできなければ、この道は開けない。理屈を言うな。いくら理屈が立派でも、行いができなければそれは悪である。この世のことは、人々の心次第なのだ。
【AIによる解釈】
本帖は「智恵」「順序」「行い」をキーワードに、真の信仰のあり方を説きます。神の智恵と人間の学問は似て非なるもので、本質的な違いがあると指摘。そして、神の仕事と自分の仕事を分ける二元論的な考え方を戒め、「順序」、すなわち物事の道理や宇宙の法則に従うことの重要性を強調します。
「都会の火に集まる蛾」という比喩は、物質文明や人工的なものに惹かれる現代人の心を批判し、真理は華やかさの中にはないことを示唆します。
また、「三エスの神宝」と「3Sの神宝」という謎めいた言葉が出てきます。これは同じ「S」の音を持つものが、片や神の宝(Screen, Speed, Sexとも解釈される)となり、片や毒(悪用された科学技術など)となる、表裏一体の関係を示しています。「四と六」「三と七」といった陰陽和合の数理によって力が生まれ、その過程で「カス(不純物)」が出るため、その「掃除」が神と人の重要な役割だと説きます。
最終的に、本帖は「理屈」よりも「行(オコナイ)」を重視します。どんなに立派な教えや理論も、実践が伴わなければ無価値であり、悪でさえあると断じます。そして「この世の事は人民の心次第」と締めくくり、世界の現実は人々の集合的な意識の反映であることを改めて強調しています。
第十帖 (三四四)
【原文】
天の岩戸開いて地の岩戸開きにかかりてゐるのざぞ、我一(いち)力では何事も成就せんぞ、手引き合ってやりて下されと申してあること忘れるでないぞ。霊肉共に岩戸開くのであるから、実地の大峠の愈々となったらもう堪忍して呉れと何んな臣民も申すぞ、人民には実地に目に物見せねば得心せぬし、実地に見せてからでは助かる臣民少ないし神も閉口ぞ。ひどい所程 身魂に借銭あるのぢゃぞ、身魂(みたま)の悪き事してゐる国程 厳しき戒(いまし)め致すのであるぞ。五と五と申してあるが五と五では力出ぬし、四と六、六と四、三と七、七と三ではカス出るしカス出さねば力出んし、それで神は掃除許りしてゐるのざぞ、神の臣民それで神洲清潔する民であるぞ、キが元と申してあるが、キが餓死(うえじに)すると肉体餓死するぞ、キ息吹けば肉息吹くぞ、神の子は神のキ頂いてゐるのざから食ふ物無くなっても死にはせんぞ、キ大きく持てよと申してあるが、キは幾らでも大きく結構に自由になる結構な神のキざぞ。臣民 利巧(りこう)なくなれば神のキ入るぞ、神の息通ふぞ、凝りかたまると凝りになって動き取れんから苦しいのざぞ、馬鹿正直ならんと申してあろがな、三千年余りで身魂の改め致して因縁だけの事は否でも応でも致さすのであるから、今度の御用は此の神示読まいでは三千世界のことであるから、何処(ドコ)探しても人民の力では見当取れんと申してあろがな、何処探しても判りはせんのざぞ、人民の頭で幾ら考へても智しぼっても学ありても判らんのぢゃ。ちょこら判る様な仕組なら こんなに苦労致さんぞ、神々様さえ判らん仕組と知らしてあろが、何より改心第一ぞと気付けてあろが、神示肚にはいれば未来(さき)見え透くのざぞ。此の地(つち)も月と同じであるから、人民の心 其の儘に写るのであるから、人民の心悪くなれば悪くなるのぞ、善くなれば善くなるのぞ。理屈 悪と申してあろが、悪の終りは共食ぢゃ、共食ひして共倒れ、理屈が理屈と悪が悪と共倒れになるのが神の仕組ぢゃ、と判ってゐながら何うにもならん事に今に世界がなって来るのざ、逆に逆にと出て来るのぢゃ、何故そうなって来るか判らんのか、神示読めよ。オロシヤの悪神の仕組 人民には一人も判ってゐないのざぞ。神にはよう判っての今度の仕組であるから仕上げ見て下されよ、此の方に任せておきなされ、一切心配なく此の方の申す様にしておりて見なされ、大舟に乗って居なされ、光の岸に見事つけて喜ばしてやるぞ、何処に居ても助けてやるぞ。雨の神、風の神、地震の神、荒の神、岩の神様に祈りなされよ、世の元からの生き通しの生神様 拝(おろ)がみなされよ。日月の民を練りに練り大和魂の種にするのであるぞ、日月の民とは日本人許りでないぞ、大和魂とは神の魂ぞ、大和の魂ぞ、まつりの魂ぞ、取違ひせん様に気付けおくぞ。でかけのみなとは九九(ココ)ぢゃぞ、皆に知らしてやりて下されよ、幾ら道進んでゐても後戻りぢゃ、此の神示が出発点ぞ、出直して神示から出て下されよ、我張りてやる気ならやりて見よれ、九分九分九厘で鼻ポキンぞ、泣き泣き恥ずかしい思いしてお出直しで御座るから気付けてゐるのぢゃ、足あげて顔の色変へる時近付いたぞ。世建替へて広き光の世と致すのぢゃ、光の世とは光なき世であるぞ、此の方の元へ引寄せて目の前に楽な道と辛い道と作ってあるのぢゃ、気付けてゐて下されよ、何(ど)ちら行くつもりぢゃ。十一月二十七日、一二$\大神$。
【現代訳】
天の岩戸が開いて、今は地の岩戸開きにかかっているのだ。自分一人の力では何事も成就しない。手を取り合ってやりなさいと申したことを忘れるな。霊(たましい)と肉体の両方の岩戸を開くのだから、実地での大峠がいよいよ本格的になったら、どんな民も「もう勘弁してください」と音を上げるぞ。人々には実際に目に物を見せなければ納得しないし、見せてからでは助かる民が少なくなってしまうので、神も困っているのだ。ひどい目に遭う所ほど、魂に借金があるのだ。魂の悪いことをしている国ほど、厳しい戒めを行うのである。五と五では力が出ず、四と六、三と七ではカスが出るが、カスを出さねば力は出ない。だから神は掃除ばかりしているのだ。神の民とは、それで神の国を清潔にする民のことだ。気が元であると申してあるが、気が飢え死にすれば肉体も飢え死にする。気が息吹けば肉体も息吹く。神の子は神の気を頂いているのだから、食べる物がなくなっても死にはしないぞ。気を大きく持てと申してあるが、気はいくらでも大きく、結構に、自由になる素晴らしい神の気なのだ。民が利口さをなくせば、神の気が入り、神の息が通う。凝り固まると「凝り」となって動きが取れなくなるから苦しいのだ。馬鹿正直ではいけないと申してあろう。三千年あまりの期間で魂の改めを行い、それぞれの因縁に応じたことは嫌でも応でもさせるのだから、この度の御用はこの神示を読まなければわからない。三千世界のことであり、どこを探しても人々の力では見当がつかないと申してあろう。どこを探してもわかりはしないのだ。人々の頭でいくら考えても、知恵を絞っても、学問があってもわからないのだ。ちょっと考えればわかるような仕組みなら、こんなに苦労はしない。神々でさえわからない仕組みだと知らせてあろう。何よりも改心が第一だと気づかせているだろう。神示が肚に入れば、未来が見え透くようになるのだ。この地(地球)も月と同じで、人々の心をそのままに映し出すのだから、人々の心が悪くなれば地も悪くなり、善くなれば善くなるのだ。理屈は悪だと申してあろう。悪の終いは共食いだ。共食いして共倒れになる。理屈が理屈と、悪が悪と共倒れになるのが神の仕組みなのだ。そうわかっていながらどうにもならない事態に、やがて世界がなってくる。逆へ逆へと物事が進むのだ。なぜそうなってくるかわからないのか。神示を読め。「ロシアの悪神」の仕組みは、人々には一人もわかっていない。神にはよくわかった上での今回の仕組みであるから、仕上げを見ていなさい。この方に任せておきなさい。一切心配せず、この方の言うようにしていなさい。大舟に乗ったつもりでいなさい。光の岸に見事に送り届けて喜ばせてやるぞ。どこにいても助けてやる。雨の神、風の神、地震の神、荒ぶる神、岩の神に祈りなさい。世の元からの生き通しの生神様を拝みなさい。日月の民を練りに練って、大和魂の種にするのだ。日月の民とは日本人だけではないぞ。大和魂とは神の魂、大和(だいわ)の魂、まつりの魂のことだ。取り違えないように気をつけておく。出かけの港はここ(九二=国)だぞ。皆に知らせてやりなさい。いくら道を進んでいても、それは後戻りだ。この神示が出発点だ。出直して、この神示から出発しなさい。我を張ってやる気ならやってみるがいい。九分九厘九毛で鼻をポキンと折られるぞ。泣きながら恥ずかしい思いをして出直すことになるから、こうして気づかせているのだ。足を上げて(降参して)顔色を変える時が近づいたぞ。世を建て替えて、広い光の世とするのだ。光の世とは、光がない(当たり前にある)世のことだ。この方の元へ引き寄せて、目の前に楽な道と辛い道を作ってある。気をつけていなさい。どちらへ行くつもりか。
【AIによる解釈】 本帖は、神の計画が霊的な「天の岩戸開き」から、物質世界での具体的な変革である「地の岩戸開き」の段階に入ったことを宣言します。この試練は非常に厳しく、ほとんどの人が音を上げるほどだと預言されています。
その中で生き残る鍵は「キ(気)」であると説きます。物質的な食料がなくても、「神のキ」を頂けば死なないと断言し、人間の小賢しい利口さを捨て、心を空にすることで神の気が入ると教えます。これは、生命の本質が物質ではなく、霊的なエネルギーにあるという思想の現れです。
また、「オロシヤ(ロシア)の悪神の仕組」という具体的な国名を挙げて、人知の及ばない大きな力が働いていることを示唆します。しかし、それすらも神の計画の内にあり、心配せずに「大舟に乗って」いれば助かると約束します。
「大和魂とは神の魂ぞ」という定義は、ひふみ神示が国粋主義とは一線を画すことを明確にしています。大和魂は日本人に限定されるものではなく、神と和する普遍的な精神を指します。そして、「この神示が出発点」と宣言し、これまでの信仰や知識を一旦リセットして、ここから再出発することを強く求めています。
第十一帖 (三四五)
【原文】
日の出の神様お出ましぞ、日の出はイであるぞ、イの出であるぞ、キの出であるぞ、判りたか。めんめめんめに心改めよと申してあろがな、人民と云ふ者は人に云はれては腹の立つ事あるものぢゃ、腹立つと邪気起るから めんめめんめに改めよと、くどう申すのぢゃぞ、智や学ではどうにもならんと云ふ事よく判りておりながら、未だ智や学でやる積り、神の国の事する積りでゐるのか。判らんと申して余りでないか、何事も判った臣民 口に出さずに肚に鎮めておけよ、言ふてよい時は肚の中から人民びっくりする声で申すのざ、神が申さすから心配ないぞ、それまでは気(ケ)も出すなよ。二十二日の夜に実地が見せてあろうがな、一所だけ清いけがれん所残しておかな足場なく、こうなってはならんぞ、カタ出さねばならんぞ、神国、神の子は元の神の生神が守ってゐるから、愈々となりたら一寸の火水で うでくり返してやる仕組ざぞ、末代の止(とど)めの建替であるから、よう腰抜かさん様 見て御座れ、長くかかりては一もとらず二もとらさず、国は潰れ、道は滅びてしもうから早う早うと気もない時から気つけてゐるのぢゃが、神の申すこと聞く臣民人民まだまだぞ。此の道 難しい道でないから その儘に説いて聞かしてやれよ、難し説くと判らん様になるのぞ。平とう説いてやれよ、難しいのは理屈入るのざぞ、難しい事も臣民にはあるなれど理屈となるなよ、理屈悪ざぞ。霊術も言霊(ことだま)もよいなれど程々に、三分位でよいぞ、中行かな行かれんのざぞ、銭儲けて口さへすごして行けばよい様に今の臣民まだ思ってゐるが、それは四つ足の四つの悪の守護である位 判りておろがな。悪とは他を退ける事であるぞ、まつりまつりとくどう申してあること未だ判らんのか、今 外国よいと申してゐる臣民は外国へ行っても嫌はれるぞ、外国にも住むところ無くなるぞ、外国も日本もないのざぞ、外国とは我よしの国の事ぞ、神国は大丈夫ざが、外国や日本の国 大丈夫とは申されんぞ、と事分けて申してあろがな、日月の集団作り、境界作ってもならんが$\ミタマ入れた集団作らなならんぞ、\ミタマも作らず\ミタマ$も入らずに力出ない位 判りておろがな、馬鹿正直ならんと申してあること忘れたのか、集団のつくり方知らしてあろが、盲(めくら)には困る困る。人の苦労あてにして我が進んで苦労せん様な人民では神の気感(きかん)に適はんから、今度は苦労のかたまりの花咲くのざ、苦の花咲くのざぞ、二二に 九(コ)の花咲耶姫の神 祀りて呉れと申してあろがな、永遠にしぼまん誠の花咲く世来たぞ。十二月七日、ひつくのか三。
【現代訳】
日の出の神様がお出ましになるぞ。日の出とは「イ(五+十=創造の力)」の出であり、「キ(気)」の出であるぞ。わかったか。一人ひとり心を改めよと申してあろう。人というものは、他人に言われると腹が立つことがあるものだ。腹を立てると邪気が起きるから、各自で改めよとくどく言うのだ。知恵や学問ではどうにもならないということがよくわかっていながら、まだ知恵や学問でやろうとしているのか、神の国のことをするつもりでいるのか。わからないと言っても、あまりではないか。何事もわかった民は、口に出さずに肚に鎮めておきなさい。言うべき時が来たら、肚の底から人々がびっくりするような声で言うことになる。神が言わせるのだから心配はいらない。それまでは気配も出すな。二十二日の夜に、その実地を見せてあろう。一ヶ所だけ清浄な穢れない場所を残しておかなければ、足場がなくなってしまう。こうなってはならないから、型を出さねばならないのだ。神国と神の子は、元の神、生神が守っているから、いよいよとなったらわずかな火と水で、茹でてひっくり返すように世の中を引っくり返す仕組みになっている。末代までの最後の建て替えであるから、腰を抜かさないように見ていなさい。長くかかっては何もかも失ってしまう。国は潰れ、道は滅びてしまうから、早く早く、とまだ気配もないうちから気づかせているのだが、神の言うことを聞く民はまだまだ少ない。この道は難しい道ではないから、ありのままに説いて聞かせてやりなさい。難しく説くとわからなくなってしまう。平易に説いてやりなさい。難しいのは理屈が入るからだ。難しいこともあるだろうが、理屈になってはいけない。理屈は悪だぞ。霊術や言霊も良いが程々にしなさい。三分程度で良い。中道を行かねばならないのだ。金儲けをして、口を糊して生きていけば良いと、今の民はまだ思っているが、それは四足(動物)の四つの悪の守護(※物質主義)であるくらい、わかっているだろう。悪とは他者を排斥することである。「まつり、まつり」とくどく申してあることがまだわからないのか。今、外国が良いと言っている民は、外国へ行っても嫌われるぞ。外国にも住む所がなくなるぞ。そもそも外国も日本もないのだ。外国とは「我良し」の国のことだ。「神国」は大丈夫だが、「外国」や「日本の国」といった人間が作った国が大丈夫とは言えない、と区別して申してあろう。日月の集団を作るにあたり、排他的な境界を作ってはならないが、「御霊(みたま)」を入れた集団を作らねばならない。御霊の無い集団では力が出ないことくらい、わかっているだろう。馬鹿正直ではいけないと申したことを忘れたのか。集団の作り方は知らせてあろう。盲目な者には困ったものだ。人の苦労をあてにして、自分から進んで苦労しないような人民では神の意にかなわないから、今度は苦労の塊から花が咲くのだ。苦労の花が咲くのだぞ。富士(二二)に木花咲耶姫(このはなさくやひめ)の神を祀ってくれと申してあろう。永遠にしぼまない誠の花が咲く世が来たのだ。
【AIによる解釈】
本帖は、新しい時代の幕開け(日の出の神様のお出まし)を告げると共に、そのための具体的な心構えと行動を説きます。「日の出」を「イ(意、五、生命力)の出」「キ(気)の出」と解き、新しい時代の原動力が精神的なエネルギーであることを示しています。
重要なのは、共同体(集団)のあり方です。排他的な「境界」を作るのではなく、「御霊(みたま)を入れた集団」、すなわち同じ精神性を共有する共同体を作るよう指示しています。これは、閉鎖的な組織ではなく、精神的な絆で結ばれた開かれたコミュニティを意味します。
また、「理屈は悪」「霊術も言霊も程々に」という教えは、観念的な知識や特殊な能力に偏ることなく、地に足のついた実践を重んじる姿勢を求めています。「悪とは他を退ける事」と定義し、自分たちの正しさだけを主張する排他的な態度を厳しく戒めます。
「苦労の塊から花が咲く」という言葉は、困難や試練を乗り越えた先にこそ、真の成果(誠の花)があることを示唆しています。富士(二二)に木花咲耶姫を祀れという具体的な指示は、日本の霊的な中心地から、美しくもはかない桜の花のように、古いものが散り、新しい生命が咲き誇る時代の始まりを象徴していると解釈できます。
第十二帖 (三四六)
【原文】
上面(うわっつら)洗へばよくなるなれど、肚の掃除なかなか出来んぞ、道広める者から早う掃除まだまだであるぞ、今度 神から見放されたら末代浮ぶ瀬ないぞ。食ひ物大切に家の中キチンとしておくのがカイの御用ざぞ、初めの行ざぞ。出て来ねば判らん様では、それは神力無いのぞ、軽き輩(やから)ぢゃぞ、それで神示読めとくどう申してゐるのざぞ、神の申す事 誠ざと思ひながら出来んのは守護神が未だ悪神の息から放れてゐぬ証拠ざぞ、息とは初のキであるぞ、気であるぞ。悪神は如何様にでも変化(へんげ)るから、悪に玩具にされてゐる臣民人民 可哀想なから、此の神示読んで言霊高く読み上げて悪のキ絶ちて下されよ、今の内に神示じっくりと読んで肚に入れて高天原となっておりて下されよ。未だ未だ忙しくなって神示読む間もない様になって来るのざから くどう申してゐるのざぞ、悪魔に邪魔されて神示読む気力も無くなる臣民 沢山出て来るから気付けておくのざ。まだまだ人民には見当取れん妙な事が次から次にと湧いて来るから、妙な事 此の方がさしてゐるのざから、神の臣民 心配ないなれど、さうなった神の臣民 未だ未だであろがな、掃除される臣民には掃除する神の心判らんから妙に見えるのも道理ぢゃ。天の様子も変りて来るぞ。何事にもキリと云ふ事あるぞ、臣民 可哀想と申してもキリあるぞ、キリキリ気付けて下され、人に云ふてもらっての改心では役に立たんぞ、我と心から改心致されよ、我でやらうと思ってもやれないのざぞ、それでも我でやって鼻ポキンポキンか、さうならねば人民得心出来んから やりたい者はやって見るのもよいぞ、やって見て得心改心致されよ、今度は鬼でも蛇(ぢゃ)でも改心さすのであるぞ。これまでは夜の守護であったが、愈々日の出の守護と相成ったから物事誤魔化しきかんのぞ、まことの人よ、よく神示見て下され、裏の裏まで見て下され、神国の誠の因縁判らいで、三千年や五千年の近目ではスコタンぞ、と申してあろがな、天四天下平げて、誠の神国に、世界神国に致すのざぞ、世界は神の国、神の国 真中の国は十万や二十万年の昔からでないぞ、世の元からの誠一つの神の事判らな益人とは申されんぞ、神の申すこと一言半句も間違ひないのざぞ。人民は其の心通りに写るから、小さく取るから物事判らんのさぞ、間違ひだらけとなるのざ、人民が楽に行ける道作りて教へてやってゐるのに、我出すから苦しんでゐるのざ、神が苦しめてゐるのでないぞ、人民 自分で苦しんでゐるのざと申してあろがな。十二月七日、七つ九のか三神示。
【現代訳】
うわべを洗うことはできても、肚(はら)の掃除はなかなかできないものだ。この道を広めようとする者からして、まだ掃除が足りていない。今度、神に見放されたら末代まで浮かばれないぞ。食べ物を大切にし、家の中をきちんと整えておくことが「カイの御用」(※始まりの御用)であり、最初の行なのだ。事が起きてからでないとわからないようでは、神力がない軽い輩だ。だから神示を読めとくどく言っているのだ。神の言うことが誠だと思いながら実行できないのは、その者の守護神がまだ悪神の影響下から離れていない証拠だ。息とは最初の気である。悪神はどのようにでも変化(へんげ)するので、悪に弄ばれている民が可哀想だから、この神示を声に出して読み上げ、その言霊の力で悪の気を断ち切りなさい。今のうちに神示をじっくり読んで肚に入れ、自分自身を高天原(神のいます清浄な場所)としておきなさい。これからますます忙しくなり、神示を読む暇もなくなるから、くどく言っているのだ。悪魔に邪魔されて、神示を読む気力さえなくなる民が沢山出てくるから気をつけておく。まだまだ人々には見当もつかない妙なことが次から次へと起こるが、その妙なことはこの方(神)がさせているのだから、神の民は心配ない。しかし、そのように達観できる民はまだまだ少ないだろう。掃除される側の人々には、掃除する神の心はわからないから、妙な出来事に見えるのも道理だ。天の様子も変わってくるぞ。何事にも区切り(キリ)というものがある。民が可哀想だと言っても、限度がある。ぎりぎり(キリキリ)のところで気づきなさい。人に言われてからの改心では役に立たない。自ら心から改心しなさい。自分でやろうと思ってもできないものだ。それでも我を出してやってみて、鼻をポキンポキンに折られるか。そうでなければ人々は納得できないから、やりたい者はやってみるのも良いだろう。やってみて、納得して改心しなさい。今度は鬼でも蛇でも改心させるのだ。これまでは「夜の守護」(悪神が力を振るう時代)であったが、いよいよ「日の出の守護」(善神が力を振るう時代)となったから、物事のごまかしは一切きかないのだ。まことの人よ、よく神示を見なさい。裏の裏まで見なさい。神国の誠の因縁は、三千年や五千年といった短い視点では見誤る(スコタンになる)と申してあろう。天下を平定し、誠の神国、世界を神国にするのだ。世界は神の国であり、その真ん中の国(日本)は、十万年や二十万年前からではない、世の初めからの誠一つである神のことがわからなければ、真の益人(ますひと)とは言えない。神の言うことには一言半句も間違いはないのだ。人々の心通りに世界は映るのだから、物事を小さく捉えるからわからなくなり、間違いだらけになるのだ。人々が楽に行ける道を創って教えてやっているのに、我を出すから苦しんでいるのだ。神が苦しめているのではない。人々が自分で苦しみを作っているのだと申してあろう。
【AIによる解釈】
本帖は、外面的な改革(上面洗い)と内面的な変革(肚の掃除)の困難さの違いを強調します。特に、道を広める立場にある者こそ、内面の浄化が不可欠だと厳しく指摘します。
その浄化の方法として、「神示を言霊高く読み上げる」ことを具体的に推奨しています。これは、神示の言葉自体が持つ霊的な力(言霊)によって、悪神の影響を断ち切り、自己を浄化できるという考えに基づいています。
また、時代の転換点を「夜の守護」から「日の出の守護」へと表現し、これからはごまかしのきかない、真実が明らかになる時代に入ることを宣言します。これは、悪が許容されていた「夜」の時代が終わり、善なる力が支配する「昼」の時代が始まることを意味します。
そして、苦しみの原因は神にあるのではなく、「人民 自分で苦しんでゐる」のだと断言します。世界の現実は人々の心の反映であり、我を出すことが苦しみの根源であるという、ひふみ神示の根本的な思想が改めて力強く説かれています。この自己責任の原則の理解が、大峠を越えるための鍵となります。
第十三帖 (三四七)
【原文】
世界中から神示通りに出て来て足元から火が付いても、まだ我張りてゐる様では今度は灰にするより方法(ほか)ないぞ。恐しなっての改心では御役六ヶ敷いぞ。因縁あるミタマでも曇りひどいと、御用六ヶ敷い事あるぞ、神示頂いたとて役員面(やくいんづら)すると鼻ポキンぞ、と気付けてあろがな、五十九柱いくらでもあるのざぞ、かへミタマあると申してあろがな、務めた上にも務めなならんぞ、因縁深い程 罪も借銭も深いのざぞ、岩戸閉めにもよき身魂あるぞ、岩戸開きにも悪きあるぞ、気付け合ってよき御用結構ざぞ、勇んで務め下されよ。心から勇む仕事よき事ぞ、此の方の好く事ざぞ。木の葉落ちて冬となれば淋しかろがな、紅葉(もみじ)ある内にと気付けおいたが紅葉の山も落ちたであろがな、他で判らん根本のキのこと知らす此の方の神示ぢゃ、三千世界のこと一切の事 説いて聞かして得心させて上げますぞや。落ち付いて聞き落しのない様になされよ、悔しさ目に見へておろがな、どぶつぼに我と落ち込む人民許り出て来て、神の国 臭くて足の踏場もないぞ、なれども見て御座れ、三千世界一度にひらいて世界一列一平一つのてん詞(四)で治めるぞ。地の世界に大将なくなって五大州引繰り返りてゐると申すことまだ判らんのか、目に見せても耳に聞かしても、まだ判らんか、尻の毛まで悪魔に抜かれてゐて まだ判らんのか、あんまりな事ぢゃなあ。是までは高し低しの戦でありたが、是からは誠の深し浅しの戦(いくさ)ざぞ、誠とはコトざぞ 口でないぞ、筆でないぞ コトざぞ、コト気付けと申してあろがな。コト、コト、コト、ざぞ。始めウタあったぞ、終もウタぞ、今も昔もウタざぞ、人民も動物もウタ唄ふのざぞ、終の御用の始はウタぞ、ウタの集団(つどひ)とせよ。此の神示ウタとして知らす集団とせよ、ウタの集団 始ざぞ、表ざぞ、裏の裏ざぞ、表の表ぞ、道開く表の終の御用ぞ、江戸の御用すみたから、尾張の御用と申してあろがな、カイの御用も忘れてならんのざぞ。食物(おしもの)の集団も作らなならんぞ、カイの御用の事ぞ、此の集団も表に出してよいのざぞ、時に応じてどうにでも変化(へんげ)られるのがまことの神の集団ざぞ。不動明王殿も力あるに、あそこ迄落してあるは神に都合ある事ぞ。世に落ちて御座る守護神と 世に落ちてゐる神々様と 世に出てゐる神々様と 世に落ちて出てゐる守護神殿と 和合なさりて物事やって下されよ、二人でしてくれと申してあろがな、判りたか。十二月十八日、ひつくのかみ神示。
【現代訳】
世界中が神示の通りになり、足元から火がつくような事態になっても、まだ我を張っているようでは、今度は灰にするより他に方法はない。恐ろしくなってからの改心では、重要な役目は務まらないぞ。深い因縁のある魂でも、曇りがひどいと御用を務めるのが難しくなることがある。神示を頂いたからといって役員のような顔をすると、鼻を折られるぞと気づかせてあろう。代わりの魂(五十九柱)はいくらでもいるのだ。代えの御霊(みたま)があると申してあろう。務めた上にもさらに務めなければならない。因縁が深いほど、罪も借金も深いのだ。岩戸閉めに加担した者の中にも良い魂はいるし、岩戸開きに携わる者の中にも悪い魂はいる。互いに気づかせ合って良い御用をするのが結構だ。勇んで務めなさい。心から勇んで行う仕事は良いことであり、この方(神)が好むことだ。「木の葉が落ちて冬になれば寂しいだろう、紅葉があるうちに」と気づかせておいたが、その紅葉の山ももう散ってしまっただろう。他ではわからない根本の「キ」のことを知らせるのが、この方の神示だ。三千世界の全てのことごとを説いて聞かせ、納得させてあげよう。落ち着いて、聞き漏らしのないようにしなさい。悔しさが目に見えている。自ら泥沼(どぶつぼ)に落ち込む民ばかりが現れ、神の国は臭くて足の踏み場もない有様だ。だが、見ていなさい。三千世界を一度に開き、世界を一つの天子(てんし)の言(四)で治めるぞ。地の世界に大将(中心軸)がなくなり、五大州がひっくり返っていると申すことがまだわからないのか。目で見せても、耳に聞かせても、まだわからないのか。尻の毛まで悪魔に抜かれるほど何もかも失っても、まだわからないのか。あんまりなことだ。これまでは「高いか低いか」の戦(権力争い)であったが、これからは「誠が深いか浅いか」の戦だ。「誠」とは「コト(言・事・行い)」であるぞ。口先だけではない、書いた文字だけでもない、「コト」そのものだ。「コト」に気づけと申してあろう。コト、コト、コトだ。初めにウタ(言・詩)があった。終わりもウタだ。今も昔もウタなのだ。人も動物も皆ウタを唄うのだ。最後の御用の始まりはウタなのだ。「ウタの集団」を作りなさい。この神示をウタとして知らせる集団にしなさい。ウタの集団が始まりであり、表であり、裏の裏であり、表の表である。道を開く表の最後の御用だ。「江戸の御用」は済んだから、次は「尾張(終わり)の御用」だと申してあろう。「甲斐(始め)の御用」も忘れてはならないぞ。食物の集団も作らなければならない。それが甲斐の御用だ。この集団も表に出して良い。時に応じてどうにでも変化できるのが、誠の神の集団だ。不動明王も力があるのに、あそこまで落とされているのは神の都合によるものだ。世に落ちぶれている守護神と、世に落ちぶれている神々と、世に出ている神々と、世に落ちぶれてからまた出てくる守護神殿と、皆で和合して物事を進めてくれ。「二人でしてくれ」と申してあろう、わかったか。
【AIによる解釈】
本帖は、戦いの質的変化を宣言します。これまでの権力や地位を争う「高し低し」の戦から、これからは内面的な真実性を問う「誠の深し浅しの戦」へと移行すると説きます。その「誠」とは、単なる言葉(口、筆)ではなく、「コト」、すなわちその人の言動、行動、存在そのものであると定義します。
そして、その「コト」を表現し、広めるための具体的な方法として「ウタ(唄・詩)」を挙げます。「ウタの集団」を作るよう指示しており、これは神示の教えを、理屈ではなく、人々の心に直接響く芸術的な形で伝えていくことの重要性を示唆しています。
「江戸の御用(物質文明の中心)が済み、尾張の御用(終わりの仕組み)へ」という言葉は、時代の大きな転換を示しています。同時に「カイ(甲斐・始め)の御用」、すなわち「食物の集団」を作ることも指示されており、これは新しい時代における食の重要性と、霊的な活動と生活基盤の確立が表裏一体であることを示しています。
最後に、力を持ちながらも不遇な立場にある神々(不動明王など)も含め、あらゆる存在が和合して計画を進めるよう呼びかけており、排除ではなく、全ての力を結集する「和合」が神の計画の要であることを示しています。
第十四帖 (三四八)
【原文】
一番尊い所 一番落してあるのぢゃ、此の事判りて来て天晴れ世界唸(うな)るのぢゃ、落した上に落して もう落す所無い様にして上下引繰り返るのぢゃ、引繰り返すのでないぞ、引繰り返るのぢゃぞ、此の事 間違へるでないぞ。此の道 難しい道でないぞ、欲はなれて、命はなれてなる様にしておりて下されたら それでよいのぢゃ。今が神国の初めぞ、今までのことすっかり用ひられんのに未だ今迄の事云ふて今迄の様な事考えてゐるが、それが盲聾(めくらつんぼ)ざぞ、今迄の事自慢すると鼻ポキンぞ、皆 鼻ポキン許りぢゃなあ。まだまだ俘虜(とりこ)になる者 沢山あるなれど、今度の俘虜(とりこ)まだまだぞ、何れ元に帰って来るから、元に帰って又盛り返して来るなれど、またまた繰り返すぞ、次に又捕へられる者 出て来るのざぞ、次はひどいのざぞ、是も因縁ざぞ。神の国は誰が見ても、どう考へても、二度と立ち上がられん、人民 皆外国につく様になって、此の方の申した事、神示に書かした事、皆 嘘(うそ)ざと申す所まで世が落ちてしまうてから始めて神力現れるのざぞ、人民臣民 早合点して御座るが九分九分九厘と申してあろがな、事務所作らいでもよいぞ、事務所作るのは表の仕組ぞ、裏の御用 事務所禁物ぞ、それぞれの役員殿の住むとこ皆それぞれの事務所でないか、よく相談してやりて下され、段々判りて来るぞ。表と裏とあななひぞ、あななひの道と申してあろ、引寄せる身魂は、天で一度改めて引寄せるのであるぞ、今お役に立たん様に臣民の目から、役員の目から見えても袖にするでないぞ、地でも改めしてまだまだ曇り取らなならんぞ、磨けば皆結構な身魂許りぢゃぞ、人民の肚さへたら天もさへるぞ、心鎮(しづ)もれば天も鎮もるぞ、神勇むぞ。我(が)はぢっと奥に鎮めて表面(うわべ)には気(ケ)も出されんぞ、我の無い様な事では、我で失敗(しくじ)た此の方の御用出来ないのざぞ、毒にも薬にもならん人民 草木にかへしてしまふぞ。此の神示 無闇(むやみ)に見せるでないぞ、神示は出ませんと申せよと申してある事 忘れるでないぞ。天の規則 千でやる事になってゐるのざぞ、今度 規則破りたら暗い所へ落ち込んで末代浮ばれんきつい事になるのざから、神くどう気付けておくぞ。次に世に出る番頭殿 まだ神なきものにして御座るから一寸先も判らんぞ、先判らずに人間の勝手な政治して世は治まらん道理ぢゃぞ、三日天下でお出直しぞ、その次もその次も又お出直しぢゃ、此の神示よく見てこの先何うなる、其の先どうなると云ふ事、神はどんな事計画しておいでますと云ふ事判らいで政治ないぞ、すればする程 悪うなるぞ、神にはこうなる事判って呑んでゐるのざから、何んなことあっても心配ないなれど、それでは臣民 可哀想なから、此の神示ウタにして印刷して世によき様にして皆に知らしてやれよ、表の集団でよいぞ、神は天からも地からも日も夜も九十(コト)で知らしてゐるのに、九十(コト)聞く身魂ないから、九十(コト)きく御身(みみ)曇りてゐるから、人民は判らんなれど、余り判らんでは通らんぞ、早う洗濯掃除せよと申してゐるのざ。人の十倍も今の仕事して其の上で神の御用するのが洗濯ぞ、掃除ぞと申して知らした事忘れたか、地に足つけよと申した事判らんのか、百姓になれ、大工になれと申した事判らんのか、$\日月$(てん)の地もあるぞ、天の百姓、大工もあるのざぞ。善と悪と小さく臣民分けるから判らんのざぞ、大きく目ひらけよ。松食(お)せよ、松おせば判らん病直るのぢゃぞ、松心となれよ、何時も変らん松の翠(みどり)の松心、松の御国の御民幸あれ。十二月十八日、ひつ九のかみ。
【現代訳】
一番尊い所を、一番低い所に落としてあるのだ。このことがわかってきた時、世界は天晴れと唸るのだ。落とした上にさらに落とし、もうこれ以上落ちる所がないという状態にしてから、上下がひっくり返るのだ。ひっくり返すのではないぞ、自然にひっくり返るのだぞ。このことを間違えるな。この道は難しい道ではない。欲を離れ、命への執着を離れ、なるようになるという心境でいてくれたらそれで良い。今が神国の始まりなのだ。今までのことはすっかり通用しなくなるのに、まだ今までのことを言い、今までのやり方で考えているが、それが盲目で聾(つんぼ)なのだ。今までのことを自慢すると鼻を折られるぞ。皆、鼻を折られてばかりだな。まだまだ捕虜になる者は沢山いるが、今度の捕虜はまだまだ続く。いずれ元に帰ってきて、また盛り返すが、また繰り返す。次にまた捕らえられる者が出てくるぞ。次はもっとひどいぞ。これも因縁なのだ。神の国(日本)は、誰が見ても、どう考えても、二度と立ち上がれないだろうというところまで落ちぶれ、人々が皆外国側につき、この方(神)が言ったこと、神示に書かせたことは、皆嘘だと断じる所まで世の中が落ちてしまってから、初めて神の力が現れるのだ。人々は早合点しているが、九分九厘九毛まで行くと申してあろう。事務所を作らなくても良い。事務所を作るのは表向きの仕組みだ。裏の御用には事務所は禁物だ。それぞれの役員の住む所が、それぞれの事務所ではないか。よく相談してやりなさい。段々とわかってくるぞ。表と裏は「あなない(相互補完的)」なのだ。「あなないの道」と申してあろう。神が引き寄せる魂は、天で一度改めてから引き寄せるのだ。今、役に立たないように見えても、袖にしてはいけない。地でも改めて、まだまだ曇りを取らねばならないのだ。磨けば皆、素晴らしい魂ばかりだぞ。人々の肚が冴えれば天も冴える。心が鎮まれば天も鎮まる。神も勇むのだ。我(が)は奥にじっと鎮めて、表面には気配も出してはならん。かといって、我がないようではいけない。我によって失敗した経験がなければ、この方の御用はできないのだ。毒にも薬にもならないような中途半端な民は、草木に還してしまうぞ。この神示をむやみに見せるな。「神示は出ません」と言えと申したことを忘れるな。天の規則は千人単位で(※厳格に)事を進めることになっている。今度、規則を破ったら暗い所へ落ち込んで、末代まで浮かばれない厳しいことになるから、神はくどく気をつけておく。次に世を担う番頭(指導者)たちは、まだ神をないがしろにしているから一寸先もわからない。先がわからずに人間の勝手な政治をして、世が治まらないのは道理だ。三日天下でやり直しになるぞ。その次も、その次もまたやり直しだ。この神示をよく見て、この先どうなるか、その先どうなるか、神がどんな計画を立てているのかわからずに政治などない。すればするほど悪くなる。神にはこうなることがわかっていて、全て承知しているのだから、どんなことがあっても心配ないが、それでは民が可哀想だから、この神示をウタ(詩や歌)にして印刷し、世に良い形で皆に知らせてやれ。それは表の集団(※ウタの集団)の役目で良い。神は天からも地からも、昼も夜も「コト(言・事)」で知らせているのに、コトを聞く魂がないから、コトを聞く耳が曇っているから、人々にはわからない。しかし、あまりにわからなさすぎても通らないぞ。早く洗濯掃除をしなさい、と申しているのだ。人の十倍も今の仕事に励み、その上で神の御用をすることが洗濯であり、掃除であると知らせたことを忘れたか。地に足をつけよと申したことがわからないのか。百姓になれ、大工になれと申したことがわからないのか。天の地もあり、天の百姓、天の大工もあるのだぞ。善と悪とを小さく分けるからわからないのだ。大きく目を開け。松を食べなさい。松を食べれば原因不明の病も治る。松の心になりなさい。いつも変わらぬ松の緑のような松の心。松の御国の民よ、幸あれ。
【AIによる解釈】
本帖は、「大逆転の法則」を説いています。「一番尊い所を一番落とす」という言葉は、最も価値あるものが最も低い位置に置かれ、どん底まで落ちてから全てがひっくり返るという、神の計画のダイナミズムを示しています。これは「ひっくり返すのでないぞ、引繰り返るのぢゃぞ」とあるように、人為的な革命ではなく、自然の摂理として起こる現象だとされます。
その大逆転のクライマックスは、「神の国は二度と立ち上がれない」「神示は皆嘘だと申す所まで世が落ちて」から始まると預言されています。これは、人間の希望や予測が完全に尽きた、絶望の淵からこそ真の神力が現れるという、厳しい試練の過程を示唆しています。
組織論についても触れられており、「裏の御用 事務所禁物ぞ」と、形式的な組織化を戒めています。実質的な活動は、個々の役員の生活の場が拠点となる、有機的で非中央集権的なネットワークで行うべきだと教えています。
そして、世の立て直しには「松」が重要な役割を果たすと説かれています。「松食せよ」という具体的な指示は、松の持つ薬効や生命力を取り入れることを意味し、「松心となれ」とは、常緑である松のように、いかなる状況でも変わらない不動の精神を持つことを求めています。
第十五帖 (三四九)
【原文】
四八音(ヨハネ)世に出るぞ、五十音(イソネ)の六十音(ムソネ)と現はれるぞ、用意なされよ。それまでにさっぱりかへてしもうぞ、天も変るぞ地も変るぞ。此の方等が世建直すと申して此の方等が世に出て威張るのでないぞ、世建直して世は臣民に任せて此の方等は隠居ぢゃ、隠れ身ぢゃぞ。地から世持ちて嬉し嬉しと申すこと楽しみぞ、子供よ、親の心よく汲み取りてくれよ。此の神示読まいでやれるならやりてみよれ、彼方(あちら)でこつん 此方(こちら)でくづれぢゃ、大事な仕組 早う申せば邪魔はいるし、申さいでは判らんし、何にしても素直に致すが一番の近道ざぞ、素直になれんのは小才があるからざぞ。鼻高ぢゃからざぞ。神の国は神の国のやり方あると申してあろがな、よきは取り入れ悪きは捨てて皆気付け合って神の国は神の国ぢゃぞ、金は金ぢゃ、銀は銀ぢゃぞと申してあろがな、盲ならんぞ、カイの御用もオワリの仕組も何も彼も裏表あるのざぞ、裏と表の外(ほか)に裏表あるぞ、ウオヱであるぞ、アとヤとワざぞ、三つあるから道ざぞ、神前に向って大きくキを吸ひ肚に入れて下座に向って吐き出せよ、八度繰り返せよ、神のキ頂くのざぞ、キとミとのあいの霊気頂くのざぞ。ひふみがヨハネとなり、五十連(イツラ)となりなって十二の流れとなるのざぞ、ムがウになるぞ、ンになるぞ、ヤとワとほりだして十二の流れ結構ざぞ。知らしてあろがな、是迄の考へ方やり方致すなら建替ではないぞ、何も彼も上中下すっかりと建替へるのざぞ、外国は竜宮の音秘(オトヒメ)様ぐれんと引繰り返しなさるのざぞ、竜宮の音秘(オトヒメ)様、雨の神様の御活動 激しきぞ。今度 次の大層が出て来たら愈々ざぞ。最後の十十$\日月$(トドメ)(透答命)ざぞ、今度こそ猶予ならんのざぞ、キリキリであるから用意なされよ、三四月気付けよ、キきれるぞ。信心なき者ドシドシ取り替へるぞ、此の中、誠一つに清め下されよ、天明まだまだざぞ、世の元の型まだまだざぞ、神の仕組 成就せんぞ、神人共にと申してあろがな、神厳しきぞ、ぬらりくらりぬるくって厳しきぞ、と申してあろがな。役員多くなくても心揃へて胴(十)すへて居りて下されよ、神がするのであるから此の世に足場作りて居りて下されよ、神無理申さんぞと申してあろがな、けれどもちっとも気許しならんのざぞ。身魂相当に皆させてあろがな、掃除早うせよ、己の戦まだすんでゐないであろが、洗濯掃除 早う結構ぞ、此の方の神示元と判り乍ら他の教で此の道開かうとて開けはせんのざぞ、鏡曇ってゐるから曲って写るのざぞ、一人の改心ではまだまだぞ、一家揃って皆改心して手引き合ってやれよ、外国人も日本人もないのざぞ、外国々々と隔て心悪ぢゃぞ。十二月十九日、一二$\大神$。
【現代訳】
四十八音(ヨハネ)が世に出るぞ。五十音(イソネ)が六十音(ムソネ)となって現れるぞ。用意をしなさい。それまでに世の中はすっかり変えてしまうぞ。天も変わるし地も変わる。この方(神々)が世を建て直すと言っても、この方々が世の表に出て威張るのではない。世を建て直した後は、世の運営を民に任せ、この方々は隠居するのだ。隠れ身となるのだ。人々が地から世を盛り立てて「嬉し嬉し」と言うのを見るのが楽しみなのだ。子供(人民)よ、親(神)の心をよく汲み取ってくれ。この神示を読まずにやれるものならやってみるがいい。あちらでぶつかり、こちらで崩れるだけだ。大事な仕組みは、早く言えば邪魔が入り、言わなければわからない。何にしても素直に従うのが一番の近道だ。素直になれないのは、小賢しい才能があるからだ。天狗になっているからだ。神の国には神の国のやり方があると申してあろう。良いものは取り入れ、悪いものは捨て、皆で気づかせ合っていくのが神の国だ。「金は金、銀は銀」と申してあろう。それぞれの価値を正しく見よ、盲目になるな。「甲斐(始め)の御用」も「尾張(終わり)の仕組み」も、何もかも裏表がある。裏と表のさらに外にも裏表があるのだ。「ウオヱ」であり、「ア」と「ヤ」と「ワ」なのだ。三つあるから道となる。神前に向かって大きく気を吸って肚に入れ、下座(人々の方)に向かって吐き出せ。これを八度繰り返しなさい。神の気を頂くのだ。気(キ)と水(ミ)の間の霊気を頂くのだ。「ひふみ」が「ヨハネ(四八音)」となり、「イツラ(五十連)」となって、十二の流れ(イスラエルの十二支族)となるのだ。ム(無)がウ(有)となり、ン(統合)となる。ヤ(八)とワ(輪)を掘り出して、十二の流れは結構なものとなるぞ。知らせてあろう。これまでの考え方ややり方をするなら、それは建て替えではない。何もかも上中下すべてをすっかりと建て替えるのだ。外国は竜宮の乙姫様がぐれんとひっくり返されるのだ。竜宮の乙姫様、雨の神様の活動は激しいぞ。今度、次の大層(大峠)が来たら、いよいよだ。最後のトドメ(十十日月、透答命)だぞ。今度こそ猶予はない。ぎりぎりだから用意をしなさい。三月、四月に気をつけよ。気が切れる(緊張が途切れる)ぞ。信心のない者はどんどん取り替える。この仲間の中だけでも、誠一つに清めてください。天明(岡本天明)、まだまだだぞ。世の元の型もまだまだだ。それでは神の仕組みは成就しない。神と人が共に行うのだと申してあろう。神は厳しいぞ。ぬらりくらりと(表面は)温和に見えて、厳格なのだと申してあろう。役員は多くなくても、心を揃えて肚を据えていてくれ。神がやるのだから、この世に足場を作っていてくれ。神は無理は言わないと申してあろう。しかし、ちっとも気は許せないのだ。魂相応の役目を皆にさせてある。早く掃除をしなさい。自分自身との戦がまだ済んでいないであろう。洗濯掃除を早く済ませるのが良い。この方の神示が元だとわかりながら、他の教えでこの道を開こうとしても開けはしない。鏡が曇っているから、物事が曲がって映るのだ。一人の改心ではまだまだだ。家族揃って皆で改心し、手を取り合ってやりなさい。外国人も日本人もないのだ。外国、外国と隔てる心は悪なのだ。
【AIによる解釈】
本帖は、言霊(ことだま)の進化と、それに伴う世界の変革を預言しています。「四八音(ヨハネ)」「六十音(ムソネ)」という新しい音の体系が現れると示唆しており、これは人類の意識が進化し、より高次元の情報を認識・表現できるようになることを象徴していると解釈できます。
神の役割についても重要な言及があります。神々は世を建て直した後は「隠居」し、統治を人間に任せると述べられています。これは、人類が神から自立し、責任をもって地上を治める「神人共治」の時代が来ることを示しています。
また、具体的な実践法として、呼吸法(神前に向かって気を吸い、下座に向かって吐き出す)が示されています。これは神の気(キ)と自然の霊気(ミ)を取り入れ、自らを浄化し、力を得るための行法です。
「三四月気付けよ」という具体的な時期への警告や、「外国は竜宮の音秘様ぐれんと引繰り返しなさる」という国際情勢の激変の預言も含まれています。最後に、個人的な改心に留まらず、「一家揃って」「外国人も日本人もなく」手を取り合うことの重要性を説き、隔てのない普遍的な愛と和合を求めています。
第十六帖 (三五〇)
【原文】
此の世と申しても臣民の世ばかりでないぞ、神の世界も引くるめて申してゐるのぢゃぞ、勇んでやって下されよ、勇む所 此の方 力添え致すぞ。心配顔 此の方 嫌ひぞ、歌唄ひ下されよ、笑ひて下されよ、笑へば岩戸開けるぞ。今の人民キリキリ舞しながら まだキリキリ舞する様もがいて御座るぞ。つ千に返ると申してあろがな、早う気付いた臣民人民 楽になるぞ。神の守護と申すものは人民からはちっとも判らんのであるぞ、判る様な守護は低い神の守護ざぞ、悪神の守護ざぞ、悪神の守護でも大将の守護ともなれば人民には判らんのざぞ、心せよ、何んな事あっても不足申すでないぞ、不足悪ざぞ、皆 人民の気からぞと くどう申してあろがな、人民キから起って来たのざぞ、我の難儀、我が作るのざぞ、我恨むより方法(ほか)ないぞ、人民の心さへ定まったら、此の方 自ら出て手柄立てさすぞ、手柄結構ざぞ。此の世の物 一切 神の物と云ふ事まだ判らんのか、一切取り上げられてから成程なァと判ったのではおそいから嫌がられても、くどう同じ様な事申してゐるのざぞ、人民の苦しみ此の方の苦しみざぞ、人民も此の方も同じものざぞ、此の道理判りたか、此の方 人民の中に居るのざぞ、別辞(ことわけ)て申してゐるのざぞ。まだまだ大き戦激しきぞ、是で世よくなると思ってゐると大間違ひとなるのざぞ、是からが褌(ふんどし)ざぞ、よき世となれば褌要らんのざぞ、フラリフラリと風に吹かれるヘチマぢゃ、ヘチマ愉快で嬉しひなあ、風の間に間に雨の間に間にユタリユタリと嬉しかろがな、何も彼も嬉し真から楽しき世ざぞよ。誠が神であるぞ、コトが神であるぞ、元であるぞ、道であるぞ、日であるぞ月であるぞ。始めコトありと申してあろがな、キであるぞ、まつりであるぞ。十二月十九日、一二$\大神$。
【現代訳】
この世と言っても、人間の世だけではないぞ。神の世界も含めて言っているのだ。勇んでやりなさい。勇んで行う所には、この方(神)が力添えをするぞ。心配そうな顔はこの方は嫌いだ。歌を唄いなさい。笑いなさい。笑えば岩戸は開けるのだ。今の民はきりきり舞いをしながら、さらにもがいてきりきり舞いするようなことをしている。九二(くに)は千(ち)に返ると申してあろう。早く気づいた民から楽になるぞ。本当の神の守護というものは、人々にはちっともわからないものだ。わかるような守護は、低い神の守護、あるいは悪神の守護だ。悪神の守護でも、その大将クラスともなれば人々にはわからないものだ。心してかかれ。どんなことがあっても不平不満を言うな。不平不満は悪だ。全ては人々の「気」から生じると、くどく申してあろう。人々は気から起こってきたのだ。自分の難儀は、自分が作っているのだ。自分を恨むより他に方法はない。人々の心がさえ定まったら、この方が自ら現れて手柄を立てさせてやる。手柄は結構なことだ。この世の物は一切が神の物だということが、まだわからないのか。全てを取り上げられてから「なるほど」とわかったのでは遅いから、嫌がられてもくどく同じことを言っているのだ。人々の苦しみはこの方の苦しみだ。人々もこの方も同じものなのだ。この道理がわかったか。この方は人々の中にいるのだ。言葉を分けて(別の存在のように)申しているだけなのだ。まだまだ大きな戦は激しいぞ。これで世の中が良くなると思っていると大間違いになる。これからが褌を締め直す時だ。良い世になれば、褌などいらない。ふらりふらりと風に吹かれるヘチマのようになるのだ。ヘチマは愉快で嬉しいなあ。風の合間、雨の合間に、ゆったりゆったりとして嬉しいだろう。何もかもが嬉しく、真から楽しい世になるのだぞ。誠が神であり、コト(言・事)が神であり、元であり、道であり、日であり、月である。初めにコト(言)があったと申してあろう。キ(気)であり、まつり(祭り・政)である。
【AIによる解釈】
本帖は、「勇む心」と「笑い」の重要性を説きます。心配や不満は悪であり、勇気と喜びの心でいる時に神の力添えがあると教えます。特に「笑へば岩戸開けるぞ」という一節は、深刻さや悲壮感ではなく、明るく肯定的な精神状態こそが、閉塞した状況を打破する鍵であることを示しています。
そして、再び自己責任の原則が強調されます。「我の難儀、我が作るのざぞ」と、苦しみの原因は全て自分自身の内にあると断言します。しかし、それは突き放しているのではなく、「人民の苦しみ此の方の苦しみざぞ」「人民も此の方も同じものざぞ」と続くことで、神と人は本来一体であるという深い愛に基づいていることを示しています。神と人は分離した存在ではなく、人々の中(内)に神はいるのだと説きます。
最後に、来るべき理想の世の姿を「風に吹かれるヘチマ」というユニークな比喩で表現します。これは、全ての束縛や緊張から解放され、自然のままに、ゆったりと、ただ存在するだけで喜びを感じられる、完全にリラックスした世界を象徴しています。それは「誠」や「コト」が全てに行き渡った結果として現れる世界です。
第十七帖 (三五一)
【原文】
天地の先祖、元の神の天詞(てんし)様が王の王と現はれなさるぞ、王の王はタマで御現はれなされるのざぞ。礼拝の仕方 書き知らすぞ、節分から始めて下されよ、先づキ整へて暫し目つむり心開きて一拝二拝八拍手せよ、又キ整へて一二三四五六七八九十(ひとふたみよいつむゆななやここのたり)と言(こと)高くのれよ、又キ整へてひふみ三回のれよ、これはこれは喜びの舞、清めの舞、祓の歌であるぞ。世界の臣民 皆のれよ、身も魂も一つになって、のり歌ひ舞へよ、身魂(みたま)全体で拍手するのざぞ、終って又キ整へて一二三四五六七八九十、一二三四五六七八九十百千卍(ももちよろず)と言(こと)高くのれよ、神気整へて天(アメ)の日月の大神様 弥栄ましませ弥栄ましませと祈れよ、これは祈るのざぞ、九二(くに)のひつくの神様 弥栄ましませ弥栄ましませと祈れよ、終りて八拍手せよ、次に雨の神様、風の神様、岩の神様、荒の神様、地震の神様、百々(もも)の神様、世の元からの生神様、産土(うぶすな)の神様に御礼申せよ、終りてから神々様のキ頂けよ、キの頂き方 前に知らしてあろがな、何よりの臣民人民の生(いき)の命の糧(かて)であるぞ、病なくなる元の元のキであるぞ、八度繰り返せと申してあろ、暫くこのやうに拝めよ、神代になる迄にはまだ進むのざぞ、それまではその様にせよ、此の方の申す様にすればその通りになるのざぞ、さまで苦しみなくて大峠越せるぞ、大峠とは王統消(わうとうけ)すのざぞ。新しき元の生命(いのち)と成るのざぞ。神の心となれば誠判るぞ。誠とはマとコトざぞ、神と人民 同じになれば神代ざぞ、神は隠身(かくりみ)に、人民 表に立ちて此の世治まるのざぞ。雀の涙程の物 取り合ひ へし合ひ 何して御座るのぞ、自分のものとまだ思ってゐるのか。御恩とは五つの音の事ざぞ、御音(恩)返さなならんのざぞ、此の事よく考へて間違はん様にして下されよ。此の巻は雨の巻ぞ、次々に知らすからミタマ相当により分けて知らしてやれよ、事分けて一二三(ひふみ)として知らしてやるのもよいぞ。役員皆に手柄立てさしたいのぢゃ、臣民人民 皆にそれぞれに手柄立てさしたいのぢゃ、待たれるだけ待ってゐるのぢゃ、一人で手柄は悪ぢゃ、分けあってやれよ、手握りてやれよ。石もの云ふぞ、十六の八の四の二の一目出度や目出度やなあ。神の仕組の世に出でにけり、あなさやけ、あな面白や、五つの色の七変はり八変はり九(ここ)の十々(たりたり)て百千万(ももちよろず)の神の世弥栄。十二月十九日、ひつ九のかミ。
【現代訳】
天地の先祖、元つ神の天子(てんし)様が「王の王」として現れるぞ。「王の王」は魂(タマ)として現れるのだ。礼拝の仕方を書き知らせる。節分から始めなさい。まず気を整え、しばらく目をつむり心を開いて、一拝、二拝、八拍手しなさい。また気を整えて「ひとふたみよいつむゆななやここのたり」と声高く唱えなさい。また気を整えて「ひふみ」を三回唱えなさい。これは喜びの舞であり、清めの舞であり、祓いの歌である。世界の民よ、皆で唱えなさい。身も魂も一つになって、唱え、歌い、舞いなさい。身魂の全体で拍手をするのだ。終わったらまた気を整えて「ひとふたみよいつむゆななやここのたり、ももちよろず」と声高く唱えなさい。神気を整えて「天の日月の大神様、弥栄ましませ、弥栄ましませ」と祈りなさい。これは祈るのだ。「国のひつぐの神様、弥栄ましませ、弥栄ましませ」と祈りなさい。終わりて八拍手をしなさい。次に、雨の神様、風の神様、岩の神様、荒ぶる神様、地震の神様、八百万の神々様、世の元からの生神様、産土の神様に御礼を申し上げなさい。終わってから神々の気を頂きなさい。気の頂き方は前に知らせてあるだろう。これが何よりの、民の生きる命の糧なのだ。病がなくなる元の元の気であるぞ。八度繰り返せと申してあろう。しばらくはこのように拝みなさい。神代になるまでには、やり方はまだ進化するのだ。それまではそのようにせよ。この方の言うようにすればその通りになる。さほど苦しまずに大峠を越せるぞ。「大峠」とは「王統消す」、すなわち古い権威の系統を消すことなのだ。新しき元の生命(いのち)となるのだ。神の心になれば、誠がわかる。「誠」とは「マ(真)」と「コト(言・事)」だ。神と人々が同じになれば、それが神代だ。神は隠れ身となり、人々が表に立ってこの世は治まるのだ。雀の涙ほどの物を、取り合い、へし合いして、何をしているのか。まだ自分の物だと思っているのか。「御恩」とは「五つの音」のことだ。この御音(恩)を返さなければならないのだ。このことをよく考えて、間違えないようにしなさい。この巻は「アメの巻」だ。次々に知らせるから、魂の段階に応じてより分けて知らせてやりなさい。事柄を分けて「ひふみ」として知らせてやるのも良い。役員皆に手柄を立てさせたいのだ。民一人ひとりに、それぞれ手柄を立てさせたいのだ。待てるだけ待っている。一人で手柄を独占するのは悪だ。分け合ってやりなさい。手を取り合ってやりなさい。石がものを言う時が来るぞ。十六が八に、八が四に、四が二に、二が一つになる。めでたい、めでたい。神の仕組みが世に現れた。ああ清々しい、ああ面白い。五色の光が七変化、八変化し、九(ここ)で満ち足りて、百千万の神の世が弥栄える。
【AIによる解釈】
本巻の最終帖は、新しい礼拝法の具体的な提示で締めくくられます。これは、節分(=季節の分かれ目、時代の転換点)から始めるよう指示されており、特定の拍手の数や祝詞(ひとふたみ、ひふみ)を唱える一連の儀式です。この儀式は、個人の浄化と神との一体化を促し、来るべき「大峠」を乗り越えるための力となるとされます。
「大峠とは王統消すのざぞ」と、大峠の真の意味が「古い権威・支配体制(王統)の終焉」であると明かされます。これは物理的な王政だけでなく、あらゆる旧来の権力構造の解体を意味します。
そして、新しい時代の理想像が語られます。「誠とはマ(真)とコト(言・事)」、すなわち真実の心と言動が一致すること。「神は隠身に、人民 表に立ちて此の世治まる」、すなわち神は背後から支え、人類が主体的に世界を統治する「神人共治」の完成。これが「神代」の姿であると説きます。
最後に「石もの云ふぞ」という象徴的な言葉と、「十六→八→四→二→一」という分裂から統合へ向かう数理、そして「五色の七変はり八変はり」という多様性が調和した世界のビジョンを示し、壮大な神の計画の成就と、光り輝く新しい時代の到来を宣言して、アメの巻を終えます。
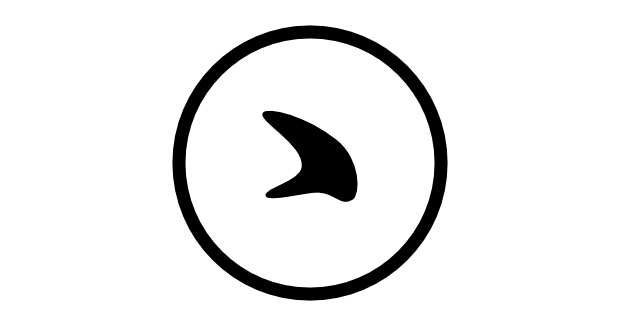





コメント