この「キの巻」は、第二次世界大戦敗戦の約半年前、昭和20年の初頭に降ろされた神示です。戦局が絶望的になる中、来るべき「大峠」とその後の「建直し」について、より具体的かつ厳しく、しかし希望を込めて説かれています。巻の名が示す通り、「キ(気、生、木)」が全ての根源であるという教えが随所に現れます。
第一帖 (二五八)
【原文】
節分からは手打ち乍ら、ひふみ祝詞 宣(の)りて呉れよ、拍手は元の大神様の全き御働きぞ、タカミムスビ と カミムスбиの御働きぞ、御音(おんおと)ぞ、和ぞ、大和(だいわ)のことぞ、言霊ぞ、喜びの御音ぞ、悪はらう御音ぞ。節分境に何も彼も変りて来るぞ、何事も掃除一番ぞ。一月二十九日、のひつくの神しるす。
【現代語訳】
節分からは、手打ち(拍手)をしながら、ひふみ祝詞を唱えてくれよ。拍手は、根源の大神様の完全な働きそのものである。それはタカミムスビ(高御産巣日神)とカミムスビ(神産巣日神)という二柱の創造神の働きであり、神聖な音であり、和であり、大いなる和(大和)のことなのだ。それは言霊であり、喜びの音であり、悪を祓う音なのだ。節分を境として、何もかもが変わり始めるぞ。何事においても、まずは掃除(身と心の浄化)が一番大切である。
【AIによる解釈】
この帖は、時代の大きな転換点が「節分」であることを示しています。豆まきで鬼(悪)を祓い、福(善)を招くように、霊的な意味での時代の切り替わりが起こることを告げています。その変革期を乗り越えるための具体的な実践方法として「ひふみ祝詞」と「拍手」が挙げられています。拍手は単なる動作ではなく、宇宙の創造神の働きそのものであり、その音は調和(和)を生み出し、悪を祓う力を持つ「言霊」であると説かれています。そして、その変革に備えるための最も基本的な心構えが「掃除」、すなわち物理的な清掃だけでなく、自らの心や魂を浄化することの重要性を強調しています。
第二帖 (二五九)
【原文】
神示読めば何も彼も判る様になりてゐること分らぬか、おはりの御用 御苦労であったぞ、奥の奥のこと仕組通りになりてゐる、臣民心配するでないぞ、一の宮は桜咲く所へつくれよ、わかりたか、天之日津久神奉賛会でよいぞ、オホカムツミの神と申しても祀り呉れよ、祭典(まつり)、国民服(※)の左の胸に八(や)たれのシデ二本つけて キヌのシデつけて当分奉仕してよいぞ。道場は一の宮と一つ所でよいぞ、イイヨリの御用 タニハの御用 御苦労であったぞ。皆の者 愈々ざぞ、今から弱音では何も出来んぞ、春マケ、夏マケ、秋マケ、冬マケ、ハルマゲドンと申してあろが、愈々ざぞ、褌しめよ、グレンざぞ。二月二十六日、ひつぐの神。(※戦時中に着用した成人男子の洋服)
【現代語訳】
この神示を読めば、何もかもが分かるようになっていることが理解できないか。「おわり(尾張)」での役目はご苦労であった。奥の院で計画されていたことは、神の仕組み通りに進んでいる。人民は心配するでないぞ。中心となる宮は桜が咲く所に作りなさい、分かったか。会の名称は「天之日津久神奉賛会」で良い。「オホカムツミの神」という御名でもお祀りしてくれよ。祭典の際は、国民服の左胸に八方に垂れた紙垂(しで)を二本つけ、絹の紙垂をつけて当分の間は奉仕するとよい。道場は一の宮と同じ場所で良い。「イイヨリ(飯より)の御用」「タニハ(丹波)の御用」もご苦労であった。皆の者、いよいよ本番だぞ。今から弱音を吐いていては何も出来ない。「春マケ、夏マケ、秋マケ、冬マケ、ハルマゲドン」と申してあろうが、いよいよその時が来たのだ。褌を締め直せ。何もかもがひっくり返る「グレン」の時が来るのだぞ。
【AIによる解釈】
これまでの準備段階(尾張の御用など)が終わり、神の計画が最終段階に入ったことを告げる帖です。人民の不安を鎮めつつ、具体的な指示(宮の建立場所、組織名、祭祀の服装など)を与えています。特筆すべきは「ハルマゲドン」という言葉の登場です。これは聖書の最終戦争を指しますが、ここでは四季を通して続く、あるいは世界的な大試練の総称として使われています。単なる戦争だけでなく、思想、経済、天変地異などあらゆる面での大混乱が起こることを示唆しています。その大峠を乗り越えるため、弱音を捨て、精神的な覚悟(褌をしめよ)を固めるよう強く促しています。
第三帖 (二六〇)
【原文】
雨の神、風の神、地震の神、岩の神、荒の神様にお祈りすれば、この世の地震、荒れ、逃(のが)らせて下さるぞ、皆の者に知らしてやりて下されよ、この方 イの神と現われるぞ、キの神と現われるぞ、シチニの神と現はれるぞ、ヒの神と現はれるぞ、ミの神と現はれるぞ、イリ井の神と現はれるぞ、五柱の神様 厚くおろがめよ、十柱の神 厚くおろがめよ。三月八日、ひつぐの神しらすぞ。
【現代語訳】
雨の神、風の神、地震の神、岩の神、荒ぶる神々にお祈りをすれば、この世で起こる地震や天変地異から逃れさせてくださるぞ。このことを皆に知らせてやってくれ。この神は「イの神」「キの神」「シチニの神」「ヒの神」「ミの神」「イリ井の神」としても現れる。これらの五柱の神様、そして十柱の神様を篤く拝みなさい。
【AIによる解釈】
この帖は、これから激化するであろう天変地異への対処法を示しています。災害を引き起こす自然の荒々しい側面を司る神々(荒神)に対し、恐れるのではなく、敬い、祈りを捧げることの重要性を説いています。これは、自然の力をコントロールしようとする現代的な考え方とは対極にある、自然との共生・共存の思想です。また、様々な神名(イ、キ、シチニ、ヒ、ミなど)で現れることを示し、神の本質が一でありながら多面的な働きを持つことを教えています。大峠を乗り越えるには、人智を超えた大自然の力と、それを司る神々への畏敬の念が不可欠であると解釈できます。
第四帖 (二六一)
【原文】
カミの大事の肝腎の所が違ふた事になりてゐるから、其の肝腎要(かんじんかなめ)の所 元に戻さな何程人間が、いくら学や智でやりてもドウにもならんぞ、元の先祖の神でないと、此処と云ふ所 出来んぞ、神の国の元の因(もと)のキのミタマを入れて練り直さな出来んのざぞ、肝腎がひっくり返りてゐるぞ、早う気付かんと、間に合はんぞ、もちと大き心持ちなされよ、世界の事ざから、世界の御用ざから、大き心でないと御用出来んぞ。これからは神が化けに化けて心引くことあるから其のつもりでゐて呉れよ、三、四月気付けて呉れよ。
【現代語訳】
神に関わることで、非常に大事な肝心要の部分が間違ってしまっている。その根本的な間違いを元に戻さない限り、人間がどれほど学問や知恵を尽くしても、どうにもならないのだ。根源の先祖神でなければ、この肝心な働きは出来ない。この国(日本)の根本原因である「キの御霊」を入れ直して、全てを練り直さなければならないのだ。肝心なことがひっくり返っている。早く気付かないと間に合わなくなるぞ。もう少し大きな心を持ちなさい。これは世界のことであり、世界の御用なのだから、大きな心でなければ役目は務まらない。これからは神が様々な姿に化けて人の心を試すことがあるから、そのつもりでいなさい。三月、四月は特に気を付けてくれよ。
【AIによる解釈】
現代文明が行き詰まっている根本原因を指摘する帖です。その原因は、小手先の技術や政策ではなく、「神に関わる肝心要の間違い」にあると断言しています。それは、人間中心主義、物質主義に陥り、生命や精神の根源である「キの御霊」を見失ったことを指していると考えられます。人間の知恵や学問の限界を突きつけ、根本的な価値観の転換(練り直し)がなければ、いかなる問題も解決できないと警告しています。この変革は日本だけにとどまらず、世界全体に関わる御用であるため、個人的な視点を超えた「大きな心」が求められます。また、試練の時には、魅力的に見える偽りの教えや誘惑(神が化けたもの)が現れることへの注意も促しています。
第五帖 (二六二)
【原文】
この神示は心通りにうつるのざぞ、思ひ違ふといくら神示読んでも違ふことになるぞ、心違ふと今度はどんなに偉い神でも人でも気の毒出来るぞ、この方クヤム事嫌いぞ。次の世となれば、これ迄の様に無理に働かなくても楽に暮せる嬉し嬉しの世となるのざが、臣民 今は人の手に握ってゐるものでもタタキ落して取る様になりてゐるのざから神も往生ざぞ、神は臣民楽にしてやりたいのに楽になれて、自分でした様に思ふて神をなきものにしたから今度の難儀となって来たのざぞ、其処にまだ気付かんか、キが元ざと申してあろがな、早う気付かんと間に合はんぞ。この神は従ふ者にはおだやかざが、さからふ者には鬼となるのざぞ。
【現代語訳】
この神示は、読む者の心の通りに内容が映し出されるものだ。思い違いをしていると、いくら神示を読んでも間違った解釈をしてしまう。心が間違っていると、今度はどんなに偉い神や人であっても、気の毒な結果を招くことになるぞ。この神は後悔することが嫌いなのだ。次の世(ミロクの世)になれば、これまでのように無理に働かなくても楽に暮らせる、本当に嬉しい世となるのだが、今の人民は他人が手に握っている物でさえ、叩き落として奪い取るようになっているのだから、神も困り果てている。神は人民を楽にしてやりたいのに、楽をさせるとそれを自分の力で成し遂げたかのように思い上がり、神を無いものとして扱った。だからこそ、今度の大きな苦難がやって来たのだ。そのことにまだ気付かないのか。「キ」が全ての元であると申してあろうが。早く気付かないと間に合わなくなるぞ。この神は、従う者には穏やかだが、逆らう者には鬼となるのだ。
【AIによる解釈】
神示の読み方についての重要な注意喚起です。神示は客観的なテキストであると同時に、読み手の心の状態を映す鏡でもあるため、清く正しい心で読まなければ真意は掴めないと説きます。現代の苦難の根本原因は、人間の「傲慢」と「感謝の欠如」にあると厳しく指摘しています。神(あるいは大自然や他者)の恩恵によって生かされていることを忘れ、全てを自分の手柄だと錯覚し、利己主義に走った結果が現在の苦境を招いた、という論理です。そして、全ての根源である「キ(生命エネルギー、精神性)」に立ち返ることの重要性を再度強調しています。神の働きは、人の心の在り方によって慈悲にも峻厳にもなる、という二面性を示唆しています。
第六帖 (二六三)
【原文】
道場開き結構でありたぞ、皆の者 御苦労ぞ、知らしてある様に道開いて下されよ、天と地と合せ鏡ぞ、一人でしてはならんぞ。桜咲く所、桜と共に花咲くぞ、夏マケ、秋マケ、となったら冬マケで泣きあげてはならんぞ、戦すんでからが愈々のイクサぞ、褌しめよ、役員も一度は青なるのざぞ、土もぐるのざぞ、九、十、気付けて呉れよ。神示よく読めよ、肝腎のこと判りては居らんぞ、一のことぞ。一三(ひふみざぞ)。
【現代語訳】
道場開き、結構であった。皆の者、ご苦労である。知らせてある通りに道を開いていってくれ。天と地は合わせ鏡のような関係なのだから、何事も一人(自分だけの判断)で行ってはならない。桜の咲く所(第二帖の「一の宮」)では、桜と共に(霊的な)花も咲くぞ。「夏マケ、秋マケ」の試練が来ても、「冬マケ」で泣き叫ぶようなことになってはならないぞ。目に見える戦争が終わってからが、いよいよ本当の戦(いくさ)なのだ。褌を締め直せ。役員たちも一度は真っ青になるような目に遭うのだぞ。土に潜るような苦しみも味わうのだぞ。九月、十月は特に気を付けてくれ。神示をよく読みなさい。肝心なことがまだ分かってはいないぞ。それは「一(はじめ)」のことだ。「一(ひ)」から「三(み)」へと開くことだぞ。
【AIによる解釈】
道場という物理的な拠点作りを認めつつも、真の「道開き」は天(神の意)と地(人の行い)が一体となって初めて成し遂げられるものであり、独断専行を戒めています。そして、来るべき試練について「夏マケ、秋マケ、冬マケ」と段階的に示し、さらに重要なのは「戦すんでからが愈々のイクサ」という点です。これは、物理的な戦争(第二次世界大戦)の終結後、より深刻な精神的・思想的な戦いが始まることを預言しています。その試練は指導的立場にある役員でさえも例外ではなく、どん底を味わうほどの苦しみを経験すると警告しています。人々がまだ理解していない「肝腎のこと」とは、「一」、すなわち根源であり、全てがそこから始まるという真理を悟ることの重要性を指しています。
第七帖 (二六四)
【原文】
物、自分のものと思ふは天の賊ぞ、皆てんし様の物ざと、クドウ申してあるのにまだ判らんか。行(おこない)出来て口静かにして貰ふと、何事もスラリとゆくぞ、行(ぎょう)が出来ておらんと何かの事が遅れるのざぞ、遅れるだけ苦しむのざぞ。神の国の半分の所にはイヤな事あるぞ、洗濯出来た臣民に元の神がうつりて、サア今ぢゃと云ふとこになりたら、臣民の知らん働きさして悪では出来ん手柄さして、なした結構な事かとビックリ箱あくのざぞ。天と地との親の大神様のミコトでする事ぞ、いくら悪神じたばたしたとて手も出せんぞ、この世 三角にしようと四角にしようと元のこの方等の心のままぞ。後から来た守護神 先になるから、今の役員さうならん様に神示で知らしてあるのざから、よく裏の裏まで読んで肚に入れて、何一つ分らん事ない様にして呉れよ、今に恥づかしい事になるぞ。元の大和魂の誠の身魂揃ふたら、人は沢山なくても この仕組成就するのざと申してあろが、末代動かぬ世の元の礎きづくのざから、キマリつけるのざから、気つけおくぞ。キが元と申してあろがな、上は上の行、中は中、下は下の行ひ、作法あるのざぞ、マゼコゼにしてはならんぞ、この中からキチリキチリと礼儀正しくせよ。
【現代語訳】
物を自分の所有物だと思うのは、天に対する盗人と同じだ。全てはてんし様(=天津神、天皇)のものであると、くどいほど申してあるのにまだ分からないのか。行いが正しくできて、口を慎んでもらうと、何事もスムーズに進む。行いができていないと、物事が遅れるのだ。そして遅れる分だけ苦しむことになる。この神の国(日本)の半分の所では、嫌なことが起こるぞ。しかし、魂の洗濯ができた人民には根源の神が乗り移り、「さあ、今だ」という時が来たら、人民自身も知らないような働きをさせ、悪の力では到底できないような手柄を立てさせ、何と素晴らしいことかと驚くような「ビックリ箱」が開くのだ。これは天地の親である大神様の御命令で行うことだから、悪神がいくらじたばたしても手出しはできない。この世を三角にするか四角にするかは、この神の心のままなのだ。後から来た守護神が先になってしまうことがあるから、今の役員がそうならないように、この神示で知らせてあるのだ。よく裏の裏まで読み込んで肚(はら)に入れ、分からないことが一つもないようにしておきなさい。さもないと、いずれ恥ずかしいことになるぞ。本来の大和魂を持つ誠の魂の持ち主が揃えば、人数は沢山いなくても、この神の計画は成就すると申してあろうが。末代までも動かない世界の基礎を築き、決まりをつけるのだから、気を付けておけ。「キ」が元であると申したであろう。上の者には上の者の、中の者には中の者の、下の者には下の者の行いや作法があるのだ。それをごちゃ混ぜにしてはならない。この集団の中から、きちんと礼儀正しくしていくのだ。
【AIによる解釈】
所有欲の完全な否定から始まるこの帖は、利己主義からの脱却を強く求めます。全ては神からの借り物であるという謙虚な姿勢が、物事を円滑に進める鍵であると説きます。日本の国土の半分に起こるという災厄の予告と同時に、魂が浄化された(洗濯出来た)人々には神がかり的な力が働き、誰も想像しなかったような形で事態が好転する「ビックリ箱」が開くという、劇的な逆転の計画が示されています。これは、人間の計画や努力を超えた、神の介入による救済を意味します。また、既存の権威(今の役員)が、後から現れる新しい力(後から来た守護神)に取って代わられる可能性を警告し、神示を深く理解し、驕ることなく精進するよう促しています。最後に、社会における秩序と礼儀の重要性を説き、それぞれの立場に応じた役割を全うすることが全体の調和に繋がることを示しています。
第八帖 (二六五)
【原文】
今迄して来た事が、成程 天地の神の心にそむいてゐると云ふこと心から分りて、心からお詫びして改心すれば、この先末代身魂をかまうぞ、借銭負うてゐる身魂はこの世にはおいて貰へん事に規則定まったのざぞ、早う皆に知らしてやれよ。タテコワシ、タテナホシ、一度になるぞ、建直しの世直し早うなるも知れんぞ、遅れるでないぞ。建直し急ぐぞ、建直しとは元の世に、神の世に返す事ざぞ、元の世と申しても泥の海ではないのざぞ、中々に大層な事であるのざぞ。上下グレンと申してあることよく肚に入れて呉れよ。
【現代語訳】
今まで自分たちがしてきたことが、なるほど天地の神の心に背いていたのだということを心から理解し、心からお詫びして改心するならば、この先末代までその魂を見守ってやろう。しかし、魂に借金(カルマ)を負っている者は、この世には置いておいてもらえないという規則に決まったのだ。早く皆に知らせてやりなさい。「立て壊し」と「立て直し」は一度にやって来るぞ。世の立て直しが早まるかもしれないのだ。乗り遅れるでないぞ。立て直しを急ぐのだ。立て直しとは、元の世、すなわち神の世に戻すことである。元の世といっても、原始の泥の海のような世界ではない。非常に素晴らしく、大層な世界なのだぞ。「上下グレン(上下関係がひっくり返ること)」と申してあることを、よく肚に入れておきなさい。
【AIによる解釈】
この帖は「改心」の重要性を説いています。自らの過ち(神意に背いていたこと)を心底から認め、悔い改めることが、救済の絶対条件であると示しています。魂の「借金(メグリ・カルマ)」を清算できない者は、新しい世に残れないという厳しい宣告がなされています。そして、この世界の変革は「破壊(タテコワシ)」と「創造(タテナホシ)」が同時に、一気に起こるダイナミックなものであると述べられています。人々の改心が早ければ、それだけ「立て直し」も早まる可能性があることを示唆し、主体的な変化を促しています。新しい「神の世」は、退行ではなく、現代とは比較にならないほど素晴らしい世界であるというビジョンを提示し、価値観や社会構造が根底から覆る「上下グレン」が起こることを改めて警告しています。
第九帖 (二六六)
【原文】
悪いこと待つは悪魔ぞ、何時 建替、大峠が来るかと待つ心は悪魔に使はれてゐるのざぞ。この神示 世界中に知らすのざ、今迄は大目に見てゐたが、もう待たれんから見直し聞き直しないぞ、神の規則通りにビシビシと出て来るぞ、世界一平に泥の海であったのを、つくりかためたのは国常立尊であるぞ、親様を泥の海にお住まひ申さすはもったいないぞ、それで天におのぼりなされたのぞ。岩の神、荒の神、雨の神、風の神、地震の神殿、この神々様、御手伝ひでこの世のかため致したのであるぞ、元からの竜体持たれた荒神様でないと今度の御用は出来んのざぞ、世界つくり固めてから臣民つくりたのであるぞ、何も知らずに上に登りて、神を見おろしてゐる様で、何でこの世が治まるものぞ。天と地の御恩といふことが神の国の守護神に判りて居らんから難儀なことが、愈々どうにもならん事になるのぞ、バタバタとなるのぞ。臣民 生れおちたらウブの御水を火で暖めてウブ湯をあびせてもらふであろが、其の御水はお土から頂くのざぞ、たき火ともしは皆 日の大神様から頂くのざぞ、御水と御火と御土でこの世の生きあるもの生きてゐるのざぞ、そんなこと位 誰でも知ってゐると申すであろが、其の御恩と云ふ事知るまいがな、一厘の所 分かるまいがな。守護神も曇りてゐるから神々様にも早うこの神示読んで聞かせてやれよ、世間話に花咲かす様では誠の役員とは云はれんぞ、桜に花咲かせよ。せわしくさしてゐるのざぞ、せわしいのは神の恵みざぞ、今の世にせわしくなかったら臣民くさって了ふぞ、せわしく働けよ。
【現代語訳】
悪いことが起こるのを待ち望むのは悪魔の心だ。いつ立て替えや大峠が来るのかと心待ちにするような気持ちは、悪魔に使われているのだぞ。この神示は世界中に知らせるのだ。今までは大目に見ていたが、もう待てないので、見直しや聞き直しはしない。神の定めた規則通りに、厳格に現象が現れてくるぞ。世界中が泥の海だったのを、造り固められたのは国常立尊(くにとこたちのみこと)である。その親神様を泥の海のような地上にお住まい申し上げるのはもったいないということで、天にお昇りになられたのだ。岩の神、荒の神、雨の神、風の神、地震の神といった神々が手伝って、この世を固めたのである。根源からの竜体を持つ荒神でなければ、今度の御用はできないのだ。世界を創り固めてから人間を創ったのである。その恩も知らずに人間の分際で上に立ち、神を見下ろしているような状態で、どうしてこの世が治まるものか。天地への御恩というものが、この国(日本)の指導者層(守護神)にさえ分かっていないから、いよいよどうにもならない困難が訪れるのだ。人々がバタバタと倒れることになるぞ。人民は、生まれ落ちるとすぐに清らかな水を火で温めた産湯を浴びせてもらうだろうが、その水は土(大地)から頂き、その火は日の大神様(太陽)から頂いているのだ。水と火と土によって、この世の生き物は皆生かされている。そんなことは誰でも知っていると言うだろうが、その大いなる御恩というものの本当の意味は分かっていないだろう。その奥深くにある一厘の真理は分かるまい。指導者層(守護神)の魂も曇っているから、神々に対しても早くこの神示を読んで聞かせてやれ。世間話に花を咲かせているようでは、誠の役員とは言えない。本当の桜(=誠の働き)に花を咲かせなさい。忙しくさせているのは、わざとなのだ。忙しいのは神の恵みである。今の世で忙しくなかったら、人民は腐ってしまうぞ。忙しく働きなさい。
【AIによる解釈】
この帖は、大峠(大災害や大混乱)を単なるスペクタクルとして待ち望むような、不健全な終末思想を厳しく戒めています。それは神の意図ではなく、悪魔的な心だと断じています。神の計画は情け容赦なく、規則通りに執行されるという厳しさを伝える一方で、その根底にある神話的な世界観(国常立尊による国土創造)と、自然への感謝の重要性を説きます。水、火、土といった、当たり前すぎるが故に忘れられがちな根源的な恵みへの感謝を忘れたことこそが、現代の指導者層(守護神)の曇りの原因であり、それが困難を招いていると指摘します。そして、一見すると罰のように思える「忙しさ」でさえ、人間が堕落するのを防ぐための「神の恵み」であるという逆説的な真理を教えています。無駄話をせず、本質的な働き(桜に花を咲かせる)に集中せよ、というメッセージです。
第十帖 (二六七)
【原文】
山の谷まで曇りてゐるぞ、曇りた所へ火の雨降るぞ、曇りた所には神は住めんぞ、神なき所 愈々ざぞ。ひどい事あるぞ、神がするのでないぞ、臣民 自分でするのざぞ。一日一日のばして改心さすやうに致したなれど、一日延ばせば千日練り直さなならんから、神は愈々鬼となって規則通りにビシビシと埒(らち)あけるぞ、もう待たれんぞ、何処から何が出て来るか知れんぞと申してあろがな。花火に火つけよ、日本の国の乱れて来たのは来られんものを来らしたからぞ。三千年の昔に返すぞ、三万年の昔に返すぞ、三十万年の昔に返さなならんかも知れんぞ。家内和合出来ん様では、この道の取次とは申されんぞ、和が元ざと申してあろが、和合出来ぬのはトラとシシぞ、どちらにもメグリあるからざぞ、昼も夜もないのざぞ、坊主 坊主くさくてはならんぞ。
【現代語訳】
山の谷に至るまで、隅々まで曇っているぞ。その曇った所へは火の雨が降るぞ。曇った所には神は住めない。神がいない所は、いよいよ大変なことになる。ひどいことが起こるが、それは神がするのではない。人民が自分たちで招くのだ。一日また一日と先延ばしにして改心させようとしてきたが、一日延ばせば、その分を取り戻すのに千日の練り直しが必要になる。だから神はいよいよ鬼となって、規則通りに厳しく決着をつけるのだ。もう待てない。どこから何が飛び出してくるか分からないと申してあろうが。「花火」に火をつけよ(=事を始めよ)。日本の国が乱れてきたのは、来てはならないもの(外国の思想・文化など)を招き入れたからだ。三千年前の状態に返すぞ。三万年前に返すぞ。あるいは三十万年前にまで返さなければならないかもしれないぞ。家庭内の和合ができないようでは、この神の道の取次役とは言えない。和が全ての元であると申してあろうが。和合できないのは、まるで虎と獅子(互いに譲らない者同士)のようだ。それは双方にカルマ(メグリ)があるからだ。もはや昼も夜も関係なく事態は進むのだ。僧侶は、形式ばかりの僧侶であってはならない。
【AIによる解釈】
魂の「曇り」が災厄を招くという因果応報を説く帖です。その災厄は神が罰として与えるのではなく、あくまで人間の行いの結果(自分でするのざぞ)であることを強調しています。改心のための猶予期間は終わり、神の計画が厳格に、そして急速に進むことを「鬼となって埒あける」と表現しています。日本の乱れの根源を、本来の精神性を失わせた外来思想の導入にあるとし、それをリセットするために、三千年、三万年、三十万年という超長期的な時間スケールでの「大掃除」が必要になる可能性を示唆しています。これは歴史や文明の根本的なリセットを意味します。そして、そうした大きな話の前に、まず基本となるべきは「家庭内の和合」であると説き、身近な調和すら実現できずに、世界の救済など語れないと戒めています。
第十一帖 (二六八)
【原文】
一二三(ひふみ)とは限りなき神の弥栄であるぞ、一(ひ)は始めなき始であるぞ、ケは終りなき終りであるぞ、神の能(はたらき)が一二三であるぞ、始なく終なく弥栄の中今(なかいま)ぞ。一二三は神の息吹であるぞ、一二三唱えよ、神人共に一二三唱へて岩戸開けるのざぞ、一二三にとけよ、一二三と息せよ、一二三着よ、一二三食(お)せよ、始め一二三あり、一二三は神ぞ、一二三は道ぞ、一二三は祓ひ清めぞ、祓ひ清めとは弥栄ぞ、神の息ぞ、てんし様の息ぞ、臣民の息ぞ、けもの、草木の息ぞ。一であるぞ、二であるぞ、三であるぞ、ケであるぞ、レであるぞ、ホであるぞ、であるぞ、であるぞ。皆の者に一二三唱へさせよ、五柱 御働きぞ、八柱 十柱 御働きぞ、五十連(いつら)ぞ、意露波(いろは)ぞ、判りたか。
【現代語訳】
「ひふみ」とは、限りなく発展していく神の弥栄(いやさか)そのものである。「ひ(一)」は始まりのない始まりであり、「け(九)」は終わりのない終わりである。神の働きそのものが「ひふみ」なのだ。それは始まりも終わりもなく、永遠に発展し続ける「今」のことである。「ひふみ」は神の息吹である。ひふみを唱えなさい。神と人が共にひふみを唱えて、岩戸を開くのだ。ひふみに溶け込みなさい。ひふみとして呼吸しなさい。ひふみを着なさい。ひふみを食べなさい。最初にひふみがあった。ひふみは神であり、道であり、祓い清めである。祓い清めとは弥栄のことであり、神の息、てんし様の息、人民の息、獣や草木の息、森羅万象の息吹そのものである。(ひ、ふ、み、よ、い、む、な、や、こ、と…)皆にひふみを唱えさせなさい。それは五柱の神の働きであり、八柱、十柱の神の働きである。五十音の連なりであり、イロハでもあるのだ。分かったか。
【AIによる解釈】
この帖は、ひふみ神示の核心ともいえる「ひふみ」の祝詞、あるいはその概念の霊的な意味を深く解説しています。「ひふみ」は単なる数詞や言葉ではなく、宇宙の根本原理であり、始まりも終わりもない永遠の生命活動、神の働きそのものであると説きます。この「ひふみ」を唱え、呼吸し、生活の全てに取り入れること(とけよ、息せよ、着よ、食せよ)で、人は神の息吹と一体化できると教えています。閉ざされた「岩戸(新しい時代への扉)」を開く鍵は、神と人が共にこの宇宙のリズム(ひふみ)を唱和することにあるのです。日本の五十音(言霊)とも関連付けられており、言葉が持つ創造と浄化の力を示唆しています。これは、森羅万象に神性を見出し、そのリズムと調和することで弥栄(永遠の発展)に至るという、日本古来のアニミズム的な世界観の表明でもあります。
第十二帖 (二六九)
【原文】
みぐるしき霊(たま)には みぐるしきもの写るぞ、それが病の元ぞ、みぐるしき者に、みぐるしきタマあたるぞ、それで早う洗濯掃除と申してくどう気付けておいたのぞ。神のためしもあるなれど、所々にみせしめしてあるぞ、早う改心して呉れよ、それが天地への孝行であるぞ、てんし様への忠義であるぞ、鎮魂(ミタマシズメ)には神示読みて聞かせよ、三回、五回、七回、三十回、五十回、七十回で始めはよいぞ、それで判らぬ様なれば お出直しで御座る。
【現代語訳】
醜い魂には、醜いものが引き寄せられて映る。それが病気の根本原因なのだ。醜い行いをする者には、醜い魂が憑依する。だからこそ、早く魂の洗濯と掃除をしなさいと、くどいほど注意してきたのだ。神が試練を与えることもあるが、それとは別に、見せしめとして様々な現象が所々で起きている。早く改心してくれ。それが天地への孝行であり、てんし様への忠義となるのだ。魂を鎮める(鎮魂)ためには、この神示を読んで聞かせなさい。最初は三回、五回、七回、三十回、五十回、七十回と読んで聞かせると良い。それでも分からないようであれば、一度この世から退場して「お出直し」ということになる。
【AIによる解釈】
この帖は、病気や不運の霊的な原因について「同質の法則(類は友を呼ぶ)」を用いて説明しています。自らの魂が「みぐるしき(醜い、不調和な)」状態にあると、それに共鳴するネガティブな霊やエネルギーを引き寄せてしまい、それが病や災いとして現象化する、という考え方です。解決策として、繰り返し「洗濯掃除(魂の浄化)」の重要性が説かれています。また、具体的な鎮魂(ヒーリング)の方法として「神示を読み聞かせる」ことが提示されています。神示の言葉(言霊)が持つ波動によって、乱れた魂を調律し、鎮める効果があるということです。しかし、それでも改心できない魂には「お出直し(=死と再生)」という、非常に厳しい結果が待っていることを宣告しており、改心の緊急性を強く訴えています。
第十三帖 (二七〇)
【原文】
世に落ちておいでなさる御方(おんかた)御一方(おんひとかた)竜宮の音姫殿 御守護遊ばすぞ、この方、天晴れ表に表れるぞ、これからは神徳貰はんと一寸先へも行けんことになったぞ、御用さして呉れと申してもメグリある金(かね)は御用にならんぞ、メグリになるのざ。自分の物と思ふのが天の賊ぞ、これまで世に出ておいでになる守護じん九分九厘迄 天の賊ぞ。偉い人 愈々とんでもないことになるぞ、捕はれるぞ、痛い目にあわされるぞ、今に目覚めるなれど其の時では遅い遅い。おかみも一時は無くなるのざ、一人々々何でも出来る様になりて居りて呉れと申してあること近うなりたぞ、ひ(火)の大神 気付けて呉れよ、どえらいことになるぞ。一厘のことは云はねばならず云ふてはならず、心と心で知らしたいなれど、心でとりて下されよ、よく神示読んでさとりて呉れよ、神たのむのざぞ。
【現代語訳】
世に隠れていらっしゃる貴い御方がお一人いるが、竜宮の乙姫様がその方をお守りになっている。この方は、見事に表舞台に現れるぞ。これからは、神からの徳を頂かなければ一寸先へも進めない時代になった。神の御用をさせてくれと申し出ても、不正なカルマ(メグリ)のついた金銭は御用には使えない。かえって更なるカルマとなるのだ。自分の物だと思うこと自体が天に対する盗みである。これまで世の指導的立場にいた守護神(指導者)の九分九厘までは、天の盗人であったのだ。地位の高い人々は、いよいよとんでもないことになるぞ。捕らえられたり、痛い目に遭わされたりする。いずれ目覚めるだろうが、その時ではもう遅いのだ。政府のような公的な権力も一時は無くなるのだぞ。だからこそ、一人ひとりが何でも自分で出来るようになっておいてくれと申してきたが、その時が近づいたのだ。火の大神(=戦争や大災害の激化)よ、気をつけてくれ。とてつもないことになるぞ。この最も重要な「一厘の仕組み」については、言わねばならないが、同時に軽々しく言ってはならない。心と心で伝えたいのだが、どうか心で受け取ってくれ。よく神示を読んで悟ってくれ。神は頼むのだぞ。
【AIによる解釈】
新しい時代のキーパーソン(竜宮の乙姫に守護された御方)の出現を預言する帖です。そして、これからの時代は物質的な力や権力ではなく、「神徳」がなければ何も進まないという価値観の大転換を告げています。私有財産や不正な富は否定され、既存の権力者(偉い人、守護じん)の多くが「天の賊」として断罪され、失脚することを明言しています。さらに「おかみも一時は無くなる」という衝撃的な言葉は、国家機能の一時的な麻痺、無政府状態の可能性を示唆しており、それゆえに個々人の自立(一人々々何でも出来る様になりて)が急務であると説きます。最後に、この神示の最奥義である「一厘の仕組み」に触れますが、それは言葉で簡単に説明できるものではなく、読み手が自らの心を清め、神示を深く読み込むことによって「心で悟る」しかない、とされています。神が「頼むのざぞ」という表現に、人類の主体的な目覚めを切に願う気持ちが表れています。
第十四帖 (二七一)
【原文】
三月三日から更に厳しくなるから用意しておけよ、五月五日から更に更に厳しくなるから更に用意して何んな事起ってもビクともせん様に心しておいてくれよ、心違ふてゐるから臣民の思ふことの逆さ許りが出てくるのざぞ、九月八日の仕組 近ふなったぞ、この道はむすび、ひふみとひらき、みなむすび、神々地に成り悉く弥栄へ 戦争(いくさ)つきはつ大道ぞ。一時はこの中も火の消えた様に淋しくなってくるぞ、その時になっておかげ落さん様にして呉れよ、神の仕組 愈々世に出るぞ、三千年の仕組晴れ晴れと、富士は晴れたり日本晴れ、桜花一二三(ひふみ)と咲くぞ。
【現代語訳】
三月三日から、事態はさらに厳しくなるから用意しておきなさい。五月五日からは、もっと厳しくなるから、さらに心構えをして、どんなことが起きてもビクともしないようにしておいてくれ。心が間違っているから、人民の思うこととは逆の結果ばかりが出てくるのだ。九月八日の仕組みが近づいてきたぞ。この神の道は、結び(むすび)、開き(ひふみとひらき)、そして全てが結ばれる(みなむすび)。神々が地に現れ、ことごとくが弥栄に向かう、戦いの尽き果てた先にある大道なのだ。一時は、この(神の道の)仲間の中も火が消えたように寂しくなる時が来る。その時に、神への信仰を失わないようにしてくれ。神の仕組みが、いよいよ世に現れるぞ。三千年来の計画が晴れやかに成就し、富士は晴れ渡り、日本は晴れやかになり、桜の花が「ひふみ」と咲き誇るのだ。
【AIによる解釈】
具体的な日付(三月三日、五月五日、九月八日)を挙げて、試練が段階的に、かつ加速度的に厳しくなることを警告する帖です。人々の思惑通りに事が進まないのは、根本的な「心の間違い」にあると指摘しています。しかし、この帖の主眼は恐怖を煽ることではなく、その試練の先にある希望のビジョンを提示することにあります。混乱と戦いの道(戦争つきはつ大道)の果てに、全てが結ばれ調和し、神々と人が共に栄える「弥栄」の世が来ることを、詩的な言葉で高らかに宣言しています。その過程では、信仰が揺らぐほどの厳しい試練(火の消えた様に淋しくなってくる)もあると予告し、それを乗り越える精神的な強さを求めています。最後の「富士は晴れたり日本晴れ、桜花一二三と咲くぞ」という一節は、絶望の淵から完全な再生を遂げた、輝かしい未来の日本の姿を象徴しています。
第十五帖 (二七二)
【原文】
誠申すと耳に逆らうであろが、其の耳 取り替へて了ふぞ、我れに判らんメグリあるぞ、今度は親子でも夫婦でも同じ様に裁く訳(わけ)には行かんのざ、子が天国で親地獄と云ふ様にならん様にして呉れよ、一家揃ふて天国身魂となって呉れよ、国皆揃ふて神国となる様つとめて呉れよ、メグリは一家分け合って、国中分け合って借金なしにして下されよ、天明代りに詫(わび)してくれよ、役員代りて詫びして呉れよ、この神示 肚に入れておれば何んな事が出て来ても胴(どう)すわるから心配ないぞ、あななひ、元津神々人の世ひらき和し、悉くの神人みつ道、勇み出で、総てはひふみひふみとなり、和し勇む大道。
【現代語訳】
真実を申すと、耳に痛いであろうが、その(真実を聞けない)耳は取り替えてしまうぞ。自分では分からないカルマ(メグリ)があるのだ。今度の審判では、親子や夫婦であっても、同じように裁くわけにはいかない。子が天国で親が地獄、というようなことにならないようにしてくれ。一家揃って天国に行ける魂となってくれ。国全体が揃って神の国となるように努めてくれ。カルマは家族で分け合い、国中で分け合って、借金を無くすようにしてくれ。天明(岡本天明)の代わりに詫びをしてくれ。役員の代わりに詫びをしてくれ。この神示を肚(はら)に入れておけば、どんなことが起きても心が動じなくなるから心配ない。「あなない(ああ、うるわしい)、根源の神々が人の世を開き、和合し、全ての神と人が道に満ち、勇み出て、すべてが『ひふみ』となり、和して勇み進む大道よ」
【AIによる解釈】
この帖は、審判の厳しさと、それに対する具体的な心構えを示しています。真実は耳に痛いものだが、それを受け入れられない者は淘汰される(耳を取り替へて了ふ)と警告します。審判は個人単位で行われるため、家族であっても結果が分かれるという非情な現実を突きつけ、一家・一国が揃って救われるよう努力することを促しています。そのための方法として、個人のカルマ(メグリ・借金)を家族や共同体で「分け合って」解消するという、連帯責任と相互扶助の精神を説いています。これは、個人主義を超えた共同体意識の重要性を示唆しています。最後に、神示を深く理解し実践(肚に入れる)すれば、どんな混乱にも動じない「胴のすわった」境地に至れるという安心感と、祝詞のような言葉で新しい世界の到来を高らかに歌い上げています。
第十六帖 (二七三)
【原文】
元津神代の道は満つ、一時は闇の道、ひらき極み、富士の代々、鳴り成るには弥栄に変わり和すの道、道は弥栄。ひふみ道出で睦び、月の神 足り足りて成り、新しき大道みつ。神々みち、ゑらぎ百千万のよきこと極む。いよいよとなり、何も彼も百千とひらき、道栄え道極み進み、道極み真理の真理極む。元の光の神々ゑらぎ、更に進む世、和合まずなりて百(もも)の世極みなる。世に光る神々の大道、神々ことごとにゑらぎて大道いよいよ展き進みて、大真理世界の三つは一と和し、鳴り成りて始めて、まことの愛の代 極み来る、弥栄の代の神、人、神人わけへだてなく光り輝き、道は更に極みの極みに進み動き、ありとあることごとくの成り結び、更に新しく更に極むるの大道、神代歓喜の代々。
【現代語訳】
(この帖は非常に詩的で祝詞のような文体であるため、逐語訳ではなく全体の意味を汲み取った意訳とする) 根源の神代の道が満ちる時が来た。一時は闇の道も極まるが、やがて富士(日本)の世が成り、全てが弥栄(永遠の繁栄)へと変わる調和の道が開かれる。道は弥栄そのものである。 ひふみの道が現れ、人々は睦び合い、月の神(陰、女性性、受容性)の働きも満ち足りて、新しい大道が満ちる。 神々の道は満ち、無数の良きことが極まる。いよいよその時となり、何もかもが豊かに開花し、道は栄え、極まり、進み、真理の中の真理が極まる。 元の光の神々が喜び、さらに進んだ世、まず和合が成り、完成された世が極まる。 世に光り輝く神々の大道。神々はことごとく喜び、大道はいよいよ開かれ進み、世界の三つ(霊・心・体、あるいは天・地・人など)が一つに和して初めて、まことの愛の時代が極まり来る。 弥栄の世では、神も人も、神人(かみひと)も、分け隔てなく光り輝き、道はさらに極みの極みへと進み動く。ありとあらゆるものが成就し結ばれ、さらに新しく、さらに極まっていく大道。それこそが神代の歓喜の世である。
【AIによる解釈】
この帖は、これまでの警告や戒めとは対照的に、来たるべき「ミロクの世」の姿を、荘厳で美しい祝詞のような言葉で描き出した、ビジョンそのものです。論理的な説明ではなく、イメージとリズムで直接心に働きかける構成になっています。 キーワードは「弥栄」「和合」「道」「光」「愛」です。
- 闇の極まりと反転: 「一時は闇の道、ひらき極み」とあるように、光の世界が訪れる前には、闇がその極みに達するという「陰極まって陽となる」宇宙法則を示しています。
- 調和と統合: 「月の神 足り足りて」「三つは一と和し」「神人わけへだてなく」といった表現は、二元的な対立(陰陽、天地、神人など)が終わり、全てが統合・調和された世界が来ることを示唆します。
- 無限の発展: 「道は更に極みの極みに進み動き」「更に新しく更に極むる」という言葉は、新しい世界が完成して停滞するのではなく、常に歓喜と共に無限に発展し続けるダイナミックな世界であることを示しています。 この帖は、厳しい試練の先にある究極の目標、その輝かしい世界観を提示することで、人々に希望と進むべき方向性を与える役割を担っていると言えます。
第十七帖 (二七四)
【原文】
すり鉢に入れてコネ廻してゐるのざから一人逃れ様とてのがれる事出来んのざぞ、逃れようとするのは我れよしざぞ、今の仕事 五人分も十人分も精出せと申してあろがな、急ぐでないぞ、其の御用すみたら次の御用にかからすのざから、この世の悪も善も皆御用と申してあろが。身魂相当の御用致してゐるのざぞ、仕事し乍ら神示肚に入れて行けば仕事段々変るのざぞ、神示声立てて読むのざと、申してあること忘れるなよ、その上で人に此の道伝へてやれよ、無理するでないぞ。我捨てて大き息吹きにとけるのざぞ、神の息吹きにとけ入るのざぞ、「御みいづ」にとけ入るのざぞ、愈々神示一二三(ひふみ)となるぞ、一二三とは息吹ぞ、みみに知らすぞ、云はねばならぬから一二三として、息吹きとして知らすぞ。神示よく読めば分ることぞ、神示読めよ、よむと神示出るぞ、此の巻は「キの巻」と申せよ。富士は晴れたり(せかい)ばれ、岩戸あけたりばれぞ。
【現代語訳】
世界全体をすり鉢に入れてこね回しているようなものだから、一人だけ逃れようとしても逃れることはできない。逃れようとすること自体が「自分さえ良ければよい」という我よし(利己主義)の心だ。今の仕事は、五人分も十人分も精を出して働きなさいと申してあろうが。しかし、焦るのではないぞ。その役目が済んだら、次の役目を与えるのだから。この世の悪も善も、全ては神の計画のための役目なのだと申してあろう。 それぞれの魂のレベルに相応しい役目をさせているのだ。日々の仕事をしながらこの神示を肚に入れていけば、仕事の内容も段々と変わっていくのだぞ。神示は声に出して読みなさいと申したことを忘れるな。その上で、他の人にこの道を伝えてやりなさい。ただし、無理強いはしてはならない。 「我」を捨てて、大いなる息吹(宇宙の呼吸)に溶け込むのだ。神の息吹に溶け入るのだ。「御みいづ(神の威光・生命力)」に溶け入るのだ。いよいよ神示は「ひふみ」そのものとなる。ひふみとは神の息吹のことだ。耳に知らせよう。言わねばならないから、ひふみとして、息吹として知らせるのだ。 神示をよく読めば分かることだ。神示を読みなさい。読めば、あなた自身の神示(啓示)が出てくるぞ。この巻は「キの巻」と呼びなさい。富士が晴れ渡り、世界が晴れ渡り、岩戸が開かれて全てが晴れやかになるぞ。
【AIによる解釈】
第九巻「キの巻」の締めくくりとなるこの帖は、大峠の試練から誰も逃れることはできないという普遍性と、その中での個人の生き方を具体的に示しています。
- 全体性(すり鉢)と個人の役割: 全員が否応なく変革の渦中にいることを「すり鉢」に例え、個人プレー(一人逃れ)を戒めます。その上で、今いる場所、今の仕事に全力で取り組むこと(五人分も十人分も精出せ)が、魂を磨く最上の修行であると説きます。
- 善悪の超越: 「悪も善も皆御用」という一節は、人間の小さな価値判断を超えた、神の大きな計画の視点を示しています。一見、悪に見える事象も、結果として善を導くためのプロセスの一部であるという、深遠な世界観です。
- 実践と変化: 神示をただ読むだけでなく、実践し(肚に入れ)、声に出して読むことで、自らの魂と現実(仕事)が変化していくと説きます。そして最終的には、読み手の中から新たな啓示(神示出るぞ)が生まれる境地に至ることを示唆しています。
- 我を捨て神に溶け込む: 最終的な到達点は「我を捨てて大き息吹きにとける」こと。個人のエゴを解放し、宇宙、神、ひふみのリズムと一体化することです。 この帖は、「キ(気・生・木)」の巻の結論として、生きること(キ)そのものが神の息吹であり、日々の仕事や生活を通して「我」を乗り越え、大いなる生命の流れに合一していくことこそが「岩戸を開き」、新しい世界を実現する道であることを力強く宣言して終わります。
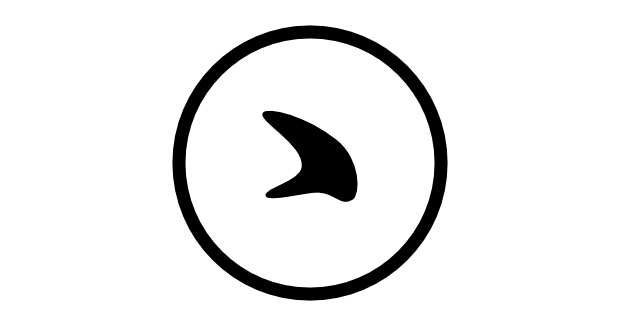





コメント