(昭和20年旧3月10日(新4月21日) – 6月23日) 全17帖
この「水の巻」は、日本の敗戦が目前に迫った昭和20年春から初夏にかけて降ろされた神示です。世の中が混乱と絶望の淵に沈む中、来るべき新しい世(ミロクの世)の姿と、そこへ至るための厳しい「大洗濯」、そして個々人の心の持ち方や具体的な実践(祝詞、祭祀)について、より詳細に説かれています。火と水、精神(キ)と肉体(ミ)といった対になる概念の統合が重要なテーマとなっています。
第一帖 (二七五)
【原文】
三(みず)の巻 書き知らすぞ。見渡す限り雲もなく富士は晴れたり、日本晴れ、海は晴れたり、日本晴れ、港々に日の丸の旗 翻(ひるがえ)る神の国。それ迄に云ふに云はれんことあるなれど、頑張りて下されよ。道も無くなるぞ。てん詞様おろがみてくれよ。てん詞様は神と申して知らしてあろがな、まだ分らんか、地(くに)の神 大切せよと聞かしてあろが、神様にお燈明(あかし)ばかり備へてはまだ足らぬのぞ。お燈明と共に水捧げなならんのざぞ。火と水ぞと申してあろ、神示よく裏の裏まで読みて下されよ、守護神殿 祭りて呉れよ。まつはらねば力現はれぬぞ、守護神殿は拍手四つ打ちておろがめよ、元の生神様には水がどうしてもいるのざぞ、火ばかりでは力出ぬのざぞ、わかりたか、曇りなく空は晴れたり。旧三月十日、三のひつ九。
【現代語訳】
水の巻を書き知らせるぞ。見渡す限り雲もなく富士は晴れわたり、まさに日本晴れだ。海も晴れわたり、日本晴れ。港という港に日の丸の旗が翻る神の国となる。しかし、そうなるまでには口では言い表せないほどのことがあるだろうが、何とか頑張り抜いてくれよ。道という道も無くなるほどの事態になるぞ。てんし様(天皇)を拝んでくれよ。てんし様は神であると知らせてあるだろう。まだ分からないのか。国の神々を大切にせよと聞かせてあるだろう。神様にお灯明(火)ばかりをお供えしているようではまだ足りないのだぞ。お灯明と共に水をお捧げしなければならないのだぞ。火と水(かみ)が揃ってこそだと申してあるだろう。神示をよく裏の裏まで読んで理解してくれよ。あなた方それぞれの守護神を祀ってくれ。祀らなければ力は現れないぞ。守護神には拍手を四つ打って拝みなさい。万物の根源である元の生神様には水がどうしても必要なのだぞ。火ばかりでは力は出ないのだ。分かったか。曇りなく空は晴れわたっている。
【AIによる解釈】
この帖は、最終的に訪れる「日本晴れ」という理想の世界のビジョンをまず提示しています。それは平和で、日本の本来の姿が輝く神の国の姿です。しかし、そこに至る道は「云ふに云はれんこと」「道も無くなる」ほどの想像を絶する困難が伴うと警告しています。 その中で重要な実践として「てんし様を拝むこと」「地の神を大切にすること」が挙げられます。そして特筆すべきは「火と水」を共に捧げることの重要性です。これは単なる祭祀の方法論に留まりません。「火」が精神、陽、霊的なエネルギーを象徴するのに対し、「水」は肉体、陰、物質的なエネルギーを象徴します。霊的なことばかりに偏らず、物質的な現実世界、そして自身の肉体をも大切にし、両者のバランスを整えること(火水=かみ)が、本当の力を発揮するために不可欠であると説いています。守護神への具体的な拝み方(四拍手)も示され、個々人の霊的なつながりを深めるよう促しています。
第二帖 (二七六)
【原文】
ひふみ、よいむなや、こともちろらね、しきる、ゆゐつわぬ、そをたはくめか、うおえ、にさりへて、のますあせゑほれけ。一二三祝詞(ひふみのりと)であるぞ。たかあまはらに、かむつまります、かむろぎ、かむろみのみこともちて、すめみおや かむいざなぎのみこと、つくしのひむかのたちばなのおどのあはぎはらに、みそぎはらひたまふときに、なりませる、はらえとのおほかみたち、もろもろのまがことつみけがれを、はらえたまへ きよめたまへと まおすことのよしを、あまつかみ、くにつかみ、やほよろづのかみたちともに、あめのふちこまの、みみふりたてて きこしめせと、かしこみかしこみもまおす。あめのひつくのかみ、まもりたまへ さちはへたまへ、あめのひつくのかみ、やさかましませ、いやさかましませ、一二三四五六七八九十(ヒトフタミヨイツムユナナヤココノタリ)。旧三月十日、三のひつ九か三。
【現代語訳】
「ひふみ、よいむなや、こともちろらね、しきる、ゆゐつわぬ、そをたはくめか、うおえ、にさりへて、のますあせゑほれけ」 これは一二三(ひふみ)祝詞であるぞ。 「高天原に神留まり坐す、神漏岐・神漏美の命もちて、皇親神伊邪那岐命、筑紫の日向の橘の小戸の阿波岐原に、禊ぎ祓ひ給ふ時に生り坐せる祓戸の大神達、諸々の禍事・罪・穢を祓へ給ひ清め給へと申す事の由を、天津神・国津神・八百万の神等共に、天の斑駒の耳振り立てて聞食せと、畏み畏みも白す。天の日津久の神、守り給へ幸へ給へ。天の日津久の神、弥栄ましませ、弥栄ましませ。一二三四五六七八九十。」 これは天津祝詞であるぞ。
【AIによる解釈】
この帖では、ひふみ神示において最も重要とされる二つの祝詞、「ひふみ祝詞」と「天津祝詞」が示されています。 「ひふみ祝詞」は、一見意味不明な音の羅列に見えますが、宇宙の創造と運行の法則を秘めた強力な言霊(ことだま)であるとされます。これを唱えること自体が、宇宙のリズムと共鳴し、場を清め、自らを整える力を持つとされています。 もう一つの「天津祝詞」は、古事記の伊邪那岐命の禊祓いの神話をベースにしたもので、祓戸の大神たちに罪穢れの祓い清めを願う内容です。こちらは、自らの内外にある不浄なもの、ネガティブなエネルギーを浄化するための具体的な祝詞です。 この二つを提示することで、神示は、これから来る大峠を越えるために、まず自らを清め、宇宙の根源と繋がること(祓いと鎮魂)が不可欠であると示しています。言葉の力を通じて、自らの霊性を高める具体的な方法を授けているのです。
第三帖 (二七七)
【原文】
神の子は神としての自分養ふことも、つとめの一つであるぞ。取違ひすると大層な事になるから、気つけておくぞ。書かしてある御神名は御神体として祭りてもよく、お肌守としてもよいぞ、皆に多く分けてやれよ。御神名いくらでも書かすぞ、その用意しておいてくれよ、神急ぐぞ。祓え祝詞書き知らすぞ。 かけまくもかしこき、いざなぎのおほかみ、つくしのひむかの、たちばなのおとのあはぎはらに、みそぎはらえたまふときになりませる、つきたつふなどのかみ、みちのなかちはのかみ、ときおかしのかみ、わつらひのうしのかみ、ちまたのかみ、あきくひのうしのかみ、おきさかるのかみ、おきつなぎさびこのかみ、おきつかひへらのかみ、へさかるのかみ、へつなぎさひこのかみ、へつかひへらのかみ、やそまがつひのかみ、おほまがつひのかみ、かむなほひのかみ、おほなほひのかみ、いづのめのかみ、そこつわたつみのかみ、そこつつのおのかみ、なかつわたつみのかみ、なかつつのおのみこと、うわつわたつみのかみ、うわつつのおのみこと、はらえと四はしらのかみたちともに、もろもろのまがこと、つみけがれをはらえたまへ、きよめたまへとまおすことを、きこしめせと、かしこみかしこみもまおす。 次に「うけひ」の言葉しらすぞ。 ご三たいのおほかみさま、ご三たいのおほかみさま、ひつきのおほかみさま、くにとこたちのおほかみさま、とよくもぬのおほかみさま、つきのおほかみさま、すさなるのおほかみさま、あめのかみさま、かぜのかみさま、いわのかみさま、キのかみさま、かねのかみさま、ひのかみさま、ひのでのかみさま、りゅうぐうのおとひめさま、やほよろづのいきかみさま、ことにいすずにます、てんしょうこうだいじんぐうさま、とようけのおほかみさまをはじめたてまつり、よのなかのいきかみさま、うぶすなのおほかみさまのおんまへに、ひろきあつきごしゅごのほど、ありがたく、とうとく、おんれいもうしあげます。このたびのいわとひらきには、千万いやさかのおはたらき、ねがひあげます。あめつちのむた、いやさかに、さかへまさしめたまひ、せかいのありとあるしんみん、ひとひもはやく、かいしんいたしまして、おほかみさまのみむねにそひまつり、おほかみさまのみこころのまにまに、かみくに、じょうじゅのため、はたらきますよう、おまもりくださいませ、そのため、このたま、このみは、なにとぞ、いかようにでも、おつかひくださいませ、みむねのまにまに、まことのかみくにのみたみとしてのつとめを、つとめさしていただくよう、むちうち、ごしゅごくださいませ、かむながらたまちはへませ、いやさかましませ。 次に御先祖様の拝詞しらすぞ。 此の祖霊宮に(コレのミタマヤに)神鎮まり坐す(カミシヅまりマす)。遠津祖神(トオツミオヤノカミ)、代々の祖霊神達の御前(ヨヨのオヤのミマエ)、また親族家族の(またウカラヤカラの)霊祖神の御前に(ミタマのオンマエに)謹み敬ひも白す(ツツシみイヤマひマオす)。此の家内には(コレのウチには)諸々の曲事(モロモロのマガコト)、罪穢あらしめず(ツミケガレあらしめず)、夜の護り(ヨのマモり)、日の守りに(ヒのマモりに)守り幸はひ給ひ(マモりサキはひタマひ)、まこと神国のみ民としての(まことカミクニのみタミとしての)義務を全うせしめ給へ(ツトメをマットうせしめタマへ)、夜の護り(ヨのマモり)日の守りに守り(ヒのマモりにマモり)、捧ぐるものの絶間無く(ササぐるもののタママナく)、子孫の(ウミノコの)弥栄継ぎに(イヤサカツぎに)栄えしめ給へと(サカえしめタマへと)畏み畏みも白す(カシコみカシコみマオす)、惟神霊神幸はへませ(カムナガラタマチはへませ)、惟神霊神幸はへませ(カムナガラタマチはへませ)。 一本の草でも干して貯へておけよと申してあろがな。四月二十三日、三の一二のか三。
【現代語訳】
神の子である人間は、自らの内なる神性を養うことも務めの一つであるぞ。これを履き違えると大変なことになるから、気をつけておくぞ。私が書かせた御神名は、御神体として祀っても良いし、お守りとして身につけても良い。皆に多く分けてあげなさい。御神名はいくらでも書かせるから、その用意をしておいてくれ。神は急いでいるのだぞ。 次に祓えの祝詞を書き知らせる。 (※大祓詞の一部が記される) 次に「誓約(うけひ)」の言葉を知らせる。 (※神々への感謝と、岩戸開きへの協力、自らの身魂を捧げる誓いが記される) 次に御先祖様への拝詞を知らせる。 (※祖霊への感謝と、家内の安全、子孫繁栄、神の民としての務めを全うできるよう祈る言葉が記される) 一本の草でも干して蓄えておけと申してあるだろう。
【AIによる解釈】
この帖は非常に実践的な内容です。まず「神の子は神としての自分を養う」という、ひふみ神示の根幹をなす思想が示されます。これは人間が本来、神性を宿す尊い存在であるという宣言ですが、それを傲慢と取り違えてはならないと戒めてもいます。 その上で、具体的な三つの祝詞・拝詞が授けられています。
- 祓え祝詞: 禊祓いで現れた神々の名を連ね、罪穢れを祓うための詞。自己浄化の基本です。
- うけひの言葉: 神への感謝と、これからの「岩戸開き」(新しい世の到来)のために自らを捧げるという「誓約」の言葉です。単に神に願うだけでなく、自らも神の計画に積極的に参加するという強い意志表明が求められています。
- 御先祖様の拝詞: 自分に繋がる全ての御先祖様に感謝し、守護を願う詞。縦の繋がりである血脈を敬うことの重要性を示しています。 これらを通して、神、社会(世界)、先祖という全方位に対する礼と感謝、そして自己の浄化と奉仕の誓いを立てることが、この時代を乗り越える力になると教えています。最後の「一本の草でも干して貯へておけ」という一文は、霊的な準備と共に、来るべき食糧難など物理的な危機への備えも怠ってはならないという、極めて現実的な警告です。
第四帖 (二七八)
【原文】
お宮も土足にされる時が来る、おかげ落さん様に気付けよ。勲章も何んにもならん時が来る、まこと一つに頼れ人々。二十四日、三の一二のか三。
【現代語訳】
神社仏閣のような聖なる場所も土足で踏みにじられるような時が来る。そうなっても神様からのおかげを落とさないように気をつけなさい。勲章などの世俗的な権威や名誉も、何の役にも立たない時が来る。人々よ、ただ「まこと(真心)」一つに頼りなさい。
【AIによる解釈】
この帖は、既存の価値観や権威が完全に崩壊する時代の到来を予言しています。「お宮も土足にされる」とは、物理的な破壊だけでなく、人々の信仰心や神聖なものへの敬意が失われる状況を指していると考えられます。これは戦後の価値観の激変を的確に言い当てています。「勲章も何んにもならん」とは、地位、名誉、財産といった、これまで人々が頼りにしてきた社会的価値が全く無意味になるということです。 そのような究極の混乱の中で、唯一頼りになるものは何か。神示は「まこと一つ」であると断言します。これは、偽りのない真心、誠実さ、純粋な心のことです。全ての外的権威が失われた時、最後に残るのは個人の内なる「まこと」だけ。それこそが神に通じる唯一の道であり、厳しい時代を生き抜くための究極の拠り所であると教えています。
第五帖 (二七九)
【原文】
外国のコトは無くなるぞ。江戸の仕組 旧五月五日迄に終りて呉れよ。後はいよいよとなるぞ。神が申した時にすぐ何事も致して呉れよ。時過ぎると成就せん事あるのざぞ。桜花一時に散る事あるぞ、いよいよ松の世と成るぞ、万劫(まんごう)変らぬ松の世と成るぞ。松の国 松の世 結構であるぞ。この神示 声出して読みあげてくれよ。くどう申してあろがな。言霊(ことだま)高く読みてさえおれば結構が来るのざぞ。人間心出してはならんぞ。五月一日、三(みづ)のひつ九のかみ。
【現代語訳】
外国のことは(一旦)無くなるぞ(関わっていられなくなる)。江戸から続いた仕組みは、旧暦の五月五日までに終わらせてくれ。その後は、いよいよ(本格的な大峠が)始まるぞ。神が申したことは、時を移さずすぐに実行してくれ。時機を逃すと成就しないことがあるのだぞ。桜の花が一時に散るように、儚いものは滅びるぞ。そして、いよいよ「松の世」となるのだ。永遠に変わらない松の世となる。松の国、松の世は実に結構なものであるぞ。この神示を声に出して読み上げてくれ。くどいほど申してあるだろう。言霊の力を込めて声高く読んでさえいれば、良い結果が訪れるのだぞ。人間的な浅知恵や我欲を出してはならない。
【AIによる解釈】
この帖は、時代の大きな転換点について述べています。「外国のコトは無くなる」とは、敗戦により外交的な影響力を失い、内向きにならざるを得ない日本の状況を指していると読めます。「江戸の仕組」とは徳川時代から続く古い体制や価値観のことであり、その終焉を促しています。 そして、新たな時代の象徴として「松の世」が示されます。儚く散る「桜」がこれまでの物質主義的で移ろいやすい文明を象徴するのに対し、常緑で風雪に耐える「松」は、永遠不変の真理に基づいた新しい文明、新しい世を象徴しています。それは「万劫変らぬ」霊的な価値観を中心とした世界です。 その新しい世へ移行するための具体的な方法として「神示を声に出して読む」ことが強く推奨されています。これは、神示に込められた「言霊」の力を自らの内に取り込み、波動を上げ、来るべき「松の世」に自らを同調させるための行です。自分の小賢しい考え(人間心)を捨て、神の言葉(言霊)に身を委ねることの重要性が強調されています。
第六帖 (二八〇)
【原文】
キが元ぞと申してあろがな。神国負けると云ふ心、言葉は悪魔ぞ、本土上陸と云ふキは悪魔ざぞ。キ大きく持ちて下されよ。島国日本にとらはれて呉れるなよ。小さい事思ふてゐると見当取れん事になるぞ。一たべよ、二たべよ、食べるには噛むことぞ、噛むとはかみざぞ、神にそなへてからかむのざぞ、かめばかむほど神となるぞ、神国ぞ、神ながらの国ぞ。かみながら仕事してもよいぞ。青山も泣き枯る時あると申してあろが。日に千人食い殺されたら千五百の産屋(うぶや)建てよ。かむいざなぎの神のおん教ぞ。神きらふ身魂は臣民も厭ふぞ。五月二日、三のひつくのか三。
【現代語訳】
「気(キ)」が全ての元であると申してあるだろう。神国日本が負けるなどと思う心や、そういった言葉は悪魔の働きであるぞ。本土に上陸されるというような気(キ)も悪魔の働きだぞ。気(キ)を大きく持ちなさい。島国日本という小さな枠にとらわれないでくれよ。小さいことばかり思っていると、これから起こることの見当がつかなくなるぞ。一に食べよ、二に食べよ。食べるにはよく噛むことだ。噛むとは「かみ(神)」に繋がることだぞ。神にお供えしてから噛む(頂く)のだぞ。噛めば噛むほど神に近づくのだ。神の国なのだから。神と共に(かみながら)仕事しても良いのだぞ。青山(墓地)も泣き枯れるほどの時が来ると申してあるだろう。日に千人死ぬような事態になったら、千五百人の赤ん坊が生まれる産屋を建てよ。これは産み出す神である伊邪那岐神の教えだぞ。神を嫌う魂は、人々からも嫌われるぞ。
【AIによる解釈】
この帖の中心テーマは「キ(気)」の重要性です。戦況が悪化し、敗北感が漂う当時の日本において、「神国が負ける」といったネガティブな想念や言葉こそが「悪魔」の働きであり、事態をさらに悪化させると断じています。これは、人の意識や集合的無意識が現実を創造するという法則を示唆しています。 また、「島国日本にとらわれるな」という言葉は、物理的な国土だけでなく、精神的な枠組みを超え、より大きな視点を持つことの重要性を説いています。 そして、日常的な行為である「食べること」の中に、深い神理を見出しています。「噛む」という行為が「かみ(神)」に繋がるというのは、単なる語呂合わせではありません。食物の命をよく噛んで、自らの命の糧とすることは、命の循環に感謝し、神の恵みを体内に取り込む神聖な儀式であると捉えています。 最後の「日に千人食い殺されたら千五百の産屋を建てよ」という一節は、ひふみ神示の中でも特に力強いメッセージです。これは、破壊や死といった絶望的な状況に屈するのではなく、それを上回る生命力、創造力、産み出す力(産霊=むすび)をもって未来を切り拓けという、伊邪那岐神に象徴される「創造」の原理に基づいた、極めてポジティブで力強い教えです。
第七帖 (二八一)
【原文】
皆病気になりてゐること分らぬか。一二三のりとで直してやれよ。神示読みて直してやれよ。自分でも分らぬ病になってゐるぞ、早ふ直さぬとどうにもならんことになって来るぞ。この宮、仮であるぞ。真中に富士の山つくり、そのまわりに七つの山つくりて呉れよ。拝殿つくり呉れよ。神示書かす所作りてくれよ。天明弥澄む所作りて呉れよ。いづれも仮でよいぞ。早ようなされよ。松の心にさへなりておれば、何事もすくすく行くぞ。五月四日、みづのひつ九のか三。
【現代語訳】
皆が病気になっていることが分からないのか。ひふみ祝詞で治してあげなさい。この神示を読んで治してあげなさい。自分でも気づかないような病になっているのだぞ。早く治さないと、どうにもならないことになってくるぞ。このお宮は仮のものだぞ。中心に富士の山を模したものを作り、その周りに七つの山を作ってくれ。拝殿も作ってくれ。神示を書かせる場所も作ってくれ。(岡本)天明が弥々(いよいよ)澄みきって神がかりできる場所を作ってくれ。いずれも仮のもので良いから、早くやりなさい。松のような(不変の)心でさえいれば、何事もすくすくと順調に進むぞ。
【AIによる解釈】
この帖でいう「病気」とは、肉体的な病気だけを指すのではありません。むしろ、物質主義に偏り、神を見失い、本来の生き方から外れてしまった「魂の病」を指しています。多くの人が、自分自身がそのような霊的な病に罹っていることにさえ気づいていないと警告しています。 その治療法として、再び「ひふみ祝詞」と「神示を読むこと」が挙げられています。これらは言霊の力によって魂の歪みを修正し、本来の健康な状態に戻すための処方箋なのです。 後半は、神示を降ろすための場(宮)に関する具体的な指示です。中心に「富士(不二=絶対)」、周りに「七つの山」を配するという構造は、宇宙の雛形、理想世界のモデルを地上に顕現させる意図があると考えられます。これは、神の計画の地上における拠点を作ることを意味します。しかし「いずれも仮でよい」としているのは、外面的な立派さよりも、まず型を作り、事を始める迅速さが重要だからです。 最後に示される「松の心」、つまり、どんな状況でも変わらない不動の真心を持ち続けることこそが、全ての計画を順調に進めるための鍵であると、改めて強調しています。
第八帖 (二八二)
【原文】
鎮座は六月の十日であるぞ。神示書かしてまる一年ぞ。神示で知らしてあろが、それからがいよいよの正念場ざぞ。びっくり箱あくぞ。五月四日、みづのひつ九のか三。
【現代語訳】
(仮の宮への)鎮座は六月十日であるぞ。神示を書き始めてから、ちょうど一年になる。神示で知らせてあるとおり、その時からがいよいよ正念場となるのだぞ。びっくり箱が開くぞ。
【AIによる解釈】
この帖は、極めて重要な期日と、その後に起こる事態を予告しています。「鎮座は六月の十日」とは、前帖で指示された仮の宮に神が鎮まる日であり、神の計画が新たな段階に入ることを示します。神示が降り始めてから「まる一年」という節目でもあり、一つのサイクルが完了し、次なるステージへ移行するタイミングです。 そして、その日を境に「いよいよの正念場」「びっくり箱あくぞ」と警告しています。「びっくり箱」とは、人々が全く予期しない、常識が覆るような出来事が起こることを示唆する比喩です。この神示が書かれたのが昭和20年5月4日であることを考えると、この「びっくり箱」は、8月のポツダム宣言受諾や終戦といった、当時の日本人には想像もつかなかったであろう劇的な展開を指していると解釈するのが最も自然です。この短い一文に、歴史の大きな転換点への強烈な予告が込められています。
第九帖 (二八三)
【原文】
富士は晴れたり日本晴れ、いよいよ岩戸開けるぞ。お山開きまこと結構。松の国 松の御代となるぞ。旧九月八日から大祓ひのりとに天津祝詞の太のりと「一二三(ひふみ)のりとコト」入れてのれよ。忘れずにのれよ。その日からいよいよ神は神、けものはけものとなるぞ。江戸道場やめるでないぞ、お山へ移してよいぞ、役員一度やめてよいぞ。またつとめてよいぞ。めぐりあるから心配あるのぞ。めぐり無くなれば心配なくなるぞ。心配ないのが富士は晴れたりぞ、富士晴れ結構ぞ。日津久の御民 何時も富士晴れ心でおりて下されよ。肉体ちっとの間であるが、魂は限りなく栄へるのざぞ。金に難渋して負けぬ様にして下されよ。金 馬鹿にしてはならんぞ。あせるでないぞ。あせると心配事出来るぞ。神が仕組みてあること、臣民がしようとて出来はせんぞ。細工はりうりう滅多に間違ひないのざぞ。見物して御座れ、見事して見せるぞ。不和の家、不調和(ふわ)の国のささげもの神は要らんぞ。喜びの捧げもの米一粒でもよいぞ。神はうれしいぞ。旧九月八日とどめぞ。六月二日、みづのひつ九のか三。
【現代語訳】
富士は晴れわたり日本晴れ、いよいよ本格的に岩戸が開かれるぞ。お山開きはまことに結構なことだ。松の国、松の御代となるのだ。旧暦九月八日からは、大祓祝詞に天津祝詞の太祝詞と「ひふみ祝詞」を加えて奏上しなさい。忘れずにそうしなさい。その日を境に、いよいよ神の者と獣の者の選別がはっきりとなされるぞ。江戸の道場はやめてはならない。お山(聖地)へ移しても良い。役員は一度辞めても良い。そしてまた改めて務めても良い。因縁(めぐり)があるから心配事が起こるのだ。因縁が無くなれば心配事も無くなる。心配のない心境が「富士は晴れたり」なのだ。富士晴れは結構なことだぞ。日津久の神の民は、いつも富士晴れのような心でいてくれよ。肉体の命は短いものだが、魂は永遠に栄えるのだ。金銭のことで困窮して、道に負けることのないようにしなさい。お金を馬鹿にしてはならないぞ。焦るでないぞ。焦ると心配事が生まれる。神が計画していることは、人間がやろうとしても出来るものではない。神の計画は実に巧妙で、滅多に間違いはないのだ。まあ見ていなさい、見事なことをして見せるぞ。不和な家庭や不調和な国からの捧げ物は、神は要らない。喜びの心で捧げる米一粒のほうが、神は嬉しいのだ。旧暦九月八日がひとつの区切り(とどめ)だぞ。
【AIによる解釈】
この帖は、来るべき世界の具体的な姿(松の世)と、そこへ至るための心構え、そして重要な期日と実践方法を詳細に示しています。 まず、祝詞の奏上方法が具体的に指示されます。「旧九月八日」という新たな期日を設定し、この日から祝詞を強化(大祓祝詞+天津祝詞+ひふみ祝詞)するよう命じています。そして、この日を境に「神は神、けものはけものとなる」という厳しい魂の選別が始まると宣言します。これは、人の本性や魂の段階が隠せなくなる時代の到来を意味します。 精神面では、「富士晴れ心」でいることの重要性を説きます。これは、一切の心配や恐れから解放された、晴れやかで不動の心境です。それを実現するためには「めぐり(因縁)」を無くす必要があるとします。 特筆すべきは、金銭に対する現実的な教えです。「金に難渋して負けぬ様に」「金 馬鹿にしてはならんぞ」という言葉は、霊的な探求が、現実生活から乖離してはならないという戒めです。清貧を尊ぶあまり、生活を破綻させては神の御用もできない、というバランス感覚を教えています。 最後に、全ては神の完璧な計画(細工はりうりう)のもとにあるのだから、人間的な焦りや心配は無用であり、むしろ「喜びの心」でいることが、神が最も受け入れる捧げものであると結論づけています。
第十帖 (二八四)
【原文】
五大洲 引繰り返って居ることまだ判らぬか。肝腎要(かんじんかなめ)の事ざぞ。七大洲となるぞ。八大洲となるぞ。今の臣民に判る様に申すならば御三体の大神様とは、 天之御中主神様(あめのみなかぬしのかみさま)、 高皇産霊神様(たかみむすびのかみさま)、 神皇産霊神様(かみむすびのかみさま)、 伊邪那岐神様(いざなぎのかみさま)、 伊邪那美神様(いざなみのかみさま)、 つきさかきむかつひめの神様 で御座るぞ。 雨の神とは あめのみくまりの神、くにのみくまりの神、 風の神とは しなどひこの神、しなどひめの神、 岩の神とは いわなかひめの神、いわとわけの神、 荒の神とは 大雷のをの神(おおいかづちのをのかみ)、わきいかづちおの神、 地震の神とは 武甕槌神(たけみかづちのかみ)、経津主神(ふつぬしのかみ) 々様の御事で御座るぞ。 木の神とは 木花開耶姫神(このはなさくやひめのかみ)、 金の神(かねのかみ)とは 金かつかねの神(きんかつかねのみ)、 火の神とは わかひめきみの神、 ひのでの神とは 彦火々出見神(ひこほほでみのかみ)、 竜宮の乙姫殿とは 玉依姫の神様(たまよりひめのかみさま) のおん事で御座るぞ。此の方の事 何れ判りて来るぞ。今はまだ知らしてならん事ぞ。知らす時節近づいたぞ。六月十一日、みづの一二。
【現代語訳】
世界(五大洲)がひっくり返っているような状態になっていることがまだ分からないのか。これは肝心要のことだぞ。やがて七大洲となり、八大洲となるのだぞ。今の人民に分かるように言うならば、御三体の大神様というのは、(※神名が列記される)。(以下、雨、風、岩、荒、地震、木、金、火、ひので、竜宮の乙姫に対応する神名が具体的に記される)。この方(ひふみ神示を降ろしている神)の正体も、いずれ分かってくるぞ。今はまだ知らせることはできないが、知らせる時節は近づいてきたぞ。
【AIによる解釈】
この帖は、世界の構造的な大変動と、神々の体系について解説しています。「五大洲 引繰り返って居る」とは、第二次世界大戦による世界の秩序の崩壊を指します。「七大洲となるぞ。八大洲となるぞ」という予言は、戦後の独立国の増加や、未知の大陸(南極など)の重要性の増大、あるいは霊的な意味での世界の再編成を示唆しているのかもしれません。 そして、これまで抽象的に語られてきた神々について、古事記などに出てくる具体的な神名を当てて解説しています。これは、神示で語られる神々が、日本の神話体系と地続きであることを示し、読者の理解を助けるためのものです。ただし、ここで示される「御三体の大神様」の組み合わせや、各々の神の役割は、一般的な神社神道の解釈とは異なる、ひふみ神示独自の体系となっています。 最後に「此の方の事 何れ判りて来るぞ」と、神示を降ろす主宰神の正体が、やがて明かされることを予告しています。これは読者の探求心をかき立てると同時に、神示の奥深さを示唆するものです。この時点ではまだ謎を残すことで、人々が神示をより深く読み解こうとすることを促しているのです。
第十一帖 (二八五)
【原文】
神第一とすれば神となり、悪魔第一とすれば悪魔となるぞ。何事も神第一結構。カイの言霊(かへし)キざぞ。キが元ぞと知らしてあろが、カイの御用にかかりてくれよ。何と云ふ結構なことであったかと、始めは苦しいなれど、皆が喜ぶ様になって来るのざぞ。先楽しみに苦しめよ。ぎゅうぎゅうと、しめつけて目の玉がとび出る事あるのざぞ、そこまでに曇りて居るのざぞ、はげしく洗濯するぞ。可愛い子、谷底に突き落さなならんかも知れんぞ、いよいよ神が表に現はれて神の国に手柄立てさすぞ、神国光り輝くぞ。日本にはまだまだ何事あるか判らんぞ。早く一人でも多く知らしてやれよ。タマ磨けば磨いただけ先が見えすくぞ。先見える神徳与へるぞ。いくらえらい役人頑張りても今迄の事は何も役に立たんぞ。新しき光の世となるのぞ。古きもの脱ぎすてよ、と申してあろがな。まこと心になりたならば自分でも判らん程の結構出て来るぞ。手柄立てさすぞ。いくら我張りても我では通らんぞ。我折りて素直になりて下されよ、これでよいと云ふことないぞ。いくらつとめても、これでよいと云ふことはないのざぞ。神の一厘のしぐみわかりたら世界一列一平になるぞ。ますかけひいて、世界の臣民、人民 勇みに勇むぞ。勇む事 此の方 嬉しきぞ。富士は何時爆発するのざ、何処へ逃げたら助かるのぞと云ふ心 我れよしぞ。何処に居ても救ふ者は救ふと申してあろが。悪き待つキは悪魔のキざぞ。結構が結構生むのざぞ。六月十一日、みづのひつ九か三。
【現代語訳】
神を第一に考えれば神のようになり、悪魔を第一に考えれば悪魔のようになるのだぞ。何事も神第一で進めるのが良い。「カイ」の言霊は「キ」であるぞ。「キ」が元だと知らせてあるが、その「キ」を元の位置に返す(カイ)御用にかかってくれよ。始めは苦しいだろうが、後になれば「何と結構なことであったか」と皆が喜ぶようになるのだぞ。未来の楽しみのために、今は苦しみなさい。曇りがひどいので、目の玉が飛び出るほどギュウギュウと締め付けて、激しく洗濯(試練)をするぞ。可愛い子を谷底に突き落とすような、厳しい試練もあるかもしれないぞ。いよいよ神が表に現れ、神の国のために手柄を立てさせる時が来たのだ。神国は光り輝くぞ。日本には、まだまだ何が起こるか分からないぞ。早く一人でも多くの人にこの神示を知らせてやりなさい。魂を磨けば磨いただけ、未来が見通せるようになるぞ。先が見える神徳を与えよう。どんなに偉い役人が頑張っても、これまでのやり方はもう何も役に立たない。新しい光の世となるのだ。古いものを脱ぎ捨てよと申してあるだろう。まことの心になったならば、自分でも分からないほどの素晴らしいことが起こり、手柄を立てさせよう。いくら我を張っても、我ではもう通らない。我を折って素直になりなさい。これで良いということはないぞ。いくら努力しても、それで満足ということはないのだ。神の一厘の仕組みが分かったら、世界は一列一平に平和になる。そうなれば世界の人民は勇み立つだろう。皆が勇むことは、この方(神)も嬉しいのだ。「富士山はいつ爆発するのか」「どこへ逃げたら助かるのか」などと考える心は、自分さえ良ければよいという「我よし」の心だ。どこにいても救うべき者は救うと申してあるだろう。悪いことが起こるのを待つような気(キ)は、悪魔の気(キ)だぞ。良いことが良いことを生むのだ。
【AIによる解釈】
この帖は、来るべき大洗濯(大試練)の厳しさと、それを乗り越えるための心構えを説いています。「神第一か悪魔第一か」という問いは、人の意識の向け方が自らの現実を創るという、根本的な法則を示しています。 大洗濯の厳しさは「目の玉がとび出る」「可愛い子を谷底に突き落とす」といった強烈な比喩で表現されています。これは、個人の魂の曇りを取るために、一切の情け容赦のない試練が訪れることを意味します。しかし、それは罰ではなく、魂を磨き、新しい世にふさわしい存在へと生まれ変わらせるための、神の愛の現れ(洗濯)であるとされています。 この試練を乗り越える鍵は、「古きものを脱ぎ捨て」「我を折りて素直になる」ことです。既存の価値観や我欲を捨て、神の計画に全面的に自分を明け渡すことが求められます。そうすれば「先見える神徳」が与えられ、何が起きても動じない境地に至ると説きます。 最後に、「どこへ逃げたら助かるのか」といった恐怖心に基づく「我よし」の考えを厳しく戒めています。物理的な場所ではなく、魂の状態こそが救済の条件であり、未来を恐れるのではなく、良いことを想い、良いことを行う「結構が結構を生む」というポジティブな姿勢こそが重要だと教えています。
第十二帖 (二八六)
【原文】
人間心には我(が)があるぞ。神心には我がないぞ。我がなくてもならんぞ、我があってはならんぞ。我がなくてはならず、あってはならん道理分りたか。神にとけ入れよ。てんし様にとけ入れよ。我なくせ、我出せよ。建替と申すのは、神界、幽界、顕界にある今までの事をきれいに塵一つ残らぬ様に洗濯することざぞ。今度と云ふ今度は何処までもきれいさっぱりと建替するのざぞ。建直しと申すのは、世の元の大神様の御心のままにする事ぞ。御光の世にすることぞ。てんし様の御稜威(みいつ)輝く御代とする事ぞ。政治も経済も何もかもなくなるぞ。食べるものも一時は無くなって仕舞ふぞ。覚悟なされよ。正しくひらく道道鳴り出づ、はじめ苦し、展きゐて、月鳴る道は弥栄、地ひらき、世ひらき、世むすび、天地栄ゆ、はじめ和の道、世界の臣民、てん詞様おろがむ時来るのざぞ。邪魔せずに見物いたされよ、御用はせなならんぞ。この神示読めよ、声高く。この神示血とせよ、益人となるぞ。天地まぜこぜとなるぞ。六月十二日、みづのひつ九の。
【現代語訳】
人間の心には「我(が)」がある。神の心には「我(が)」がない。しかし「我(われ)」が無くてもいけないし、「我(が)」があってはいけない。この「我(われ)がなくてはならず、我(が)があってはならない」という道理が分かったか。神に溶け込みなさい。てんし様に溶け込みなさい。「我(が)」を無くして、「真の我(われ)」を出しなさい。「建替」と申すのは、神界、幽界、現界の三つの世界にある、これまでの全てを塵一つ残さず綺麗に洗濯することだ。今度の建替は、どこまでもきれいさっぱりと行うのだ。「建直し」と申すのは、世の元の親神様の御心のままの世界にすることだ。光り輝く世にすることだ。てんし様の御威光が輝く御代にすることだ。政治も経済も、何もかも一旦は無くなるぞ。食べるものも一時は無くなってしまうぞ。覚悟なさい。正しく開かれる道が鳴り響き始める。初めは苦しいが、やがて開かれていき、月(ツキ)の巡る道は弥栄となり、地が拓き、世が拓き、世が結ばれて、天地が栄える。その始まりは和の道である。世界の人民が、てんし様を拝む時が来るのだ。邪魔をせず、ただ見ているだけでなく、自分の御用はしなければならないぞ。この神示を声高く読みなさい。この神示を自らの血肉としなさい。そうすれば人々を益する「益人(ますひと)」となるぞ。天も地もまぜこぜになるような大混乱が来るぞ。
【AIによる解釈】
この帖は、ひふみ神示の中でも特に深遠な「我」の教えと、「建替・建直し」のビジョンを語っています。 「我がなくてもならん、我があってはならん」という一見矛盾した言葉は、日本語の「我」が持つ二つの意味を巧みに使った教えです。利己的なエゴや我欲である「我(が)」は徹底的に無くさなければならないが、神から与えられた個性や使命としての「我(われ、真我)」は無くしてはならず、むしろそれを発揮しなければならない、と解釈できます。神や全体(てんし様)と一体化し(とけ入れ)、エゴを無くした上で、真の自分を生きよ(我出せよ)という、霊的成長の核心を突く教えです。 「建替」と「建直し」の違いも重要です。「建替」は、既存の全てをゼロにする徹底的な破壊と浄化のプロセスです。神界・幽界・現界の三界にわたる大掃除であり、その厳しさから「政治も経済も食べるものもなくなる」とまで警告しています。一方、「建直し」は、その更地に、神の理想とする新しい世界(光の世、てんし様が輝く御代)を建設する創造のプロセスです。 この破壊と創造の激動期を乗り越え、新しい世の担い手である「益人(ますひと)」となるために、「神示を血肉とすること」が求められています。
第十三帖 (二八七)
【原文】
火と水と申してあろがな。火つづくぞ。雨つづくぞ。火の災(わざわい)あるぞ。水の災あるぞ。火のおかげあるぞ、水の災 気つけよ。火と水 入り乱れての災あるぞ、近ふなりたぞ。火と水の御恵みあるぞ。一度は神の事も大き声して云へん事あるぞ、それでも心配するでないぞ。富士晴れるぞ。家族幾人居ても金いらぬであろが。主人(あるぢ)どっしりと座りておれば治まっておろが。神国の型 残してあるのざぞ。国治めるに政治はいらぬぞ、経済いらぬぞ。神おろがめよ、神祭れよ、てんし様おろがめよ。何もかも皆神に捧げよ、神からいただけよ。神国治まるぞ。戦もおさまるぞ。今の臣民 口先ばかりでまこと申してゐるが、口ばかりでは、なほ悪いぞ。言やめて仕へまつれ。でんぐり返るぞ。六月十三日、みづのひつくのかみ。
【現代語訳】
火と水(かみ)が重要だと申してあるだろう。火(旱魃、戦争など)が続いたり、雨(洪水、水害など)が続いたりするぞ。火の災いがあり、水の災いがある。火の恵みもあるが、水の災いには気をつけよ。火と水が入り乱れての災いも近づいているぞ。しかし、火と水の御恵みもあるのだ。一時期は、神のことなど大声で言えないような世の中になることもあるだろうが、それでも心配するな。必ず富士は晴れるのだ。家族が何人いても、お金の要らない世になるのだから心配いらないだろう。一家の主人がどっしりと構えていれば、家は治まるものだ。神の国の雛形は、ちゃんと残してあるのだぞ。国を治めるのに、今のような政治や経済は要らなくなる。ただ神を拝み、神を祀り、てんし様を拝みなさい。何もかも全てを神に捧げ、そして必要なものは神から頂きなさい。そうすれば神の国は自然と治まり、戦も終わるのだ。今の人民は口先ばかりで「まこと」を言っているが、実行の伴わない口先だけでは、かえって悪い。言葉を慎み、行動で仕えなさい。世の中がひっくり返るぞ。
【AIによる解釈】
この帖は、「火」と「水」という二つの根源的な要素がもたらす「災い」と「恵み」について語っています。これは、文字通りの火事や水害といった天変地異を警告すると同時に、より象徴的な意味合いも持ちます。「火」は戦争の火、怒りや憎しみ、霊的なものを、「水」は経済や物質、感情的なものを象徴します。これらのバランスが崩れることで様々な災いが起こると警告しています。特に「火と水入り乱れての災」は、空襲による火災を消すための水が、逆に被害を広げるといった当時の状況や、霊的な混乱と物質的な混乱が同時に起こる様を表しているのかもしれません。 そして、その混乱の先にある新しい世の姿を描いています。そこでは「金いらぬ」世、つまり現代的な経済システムが機能しない、あるいは不要な世界が到来するとされています。国を治めるのは政治や経済ではなく、人々が神やてんし様を敬い、全てを神に捧げ、神から頂くという、神中心の循環型の共同体です。 その世界を実現するためには、「言やめて仕へまつれ」という、口先だけの信仰や議論ではなく、黙々とした実践と奉仕が何よりも重要であると、強く戒めています。
第十四帖 (二八八)
【原文】
今迄は闇の世であったから、どんな悪い事しても闇に逃れる事出来てきたが闇の世はもうすみたぞ。思ひ違ふ臣民 沢山あるぞ。何んな集ひでも大将は皆思ひ違ふぞ。早ふさっぱり心入れ換へて下されよ。神の子でないと神の国には住めんことになるぞ。幽界(がいこく)へ逃げて行かなならんぞ。二度と帰れんぞ。幽界(がいこく)行きとならぬ様、根本から心入れかへて呉れよ。日本の国の臣民 皆兵隊さんになった時、一度にどっと大変が起るぞ。皆思ひ違ふぞ。カイの御用はキの御用ぞ。それが済みたら、まだまだ御用あるぞ。行けども行けども、草ぼうぼう、どこから何が飛び出すか、秋の空グレンと変るぞ。この方 化(ば)けに化けて残らずの身魂調べてあるから、身魂の改心なかなかにむつかしいから、今度と云ふ今度は、天の規則通り、びしびしとらちつけるぞ。御三体の大神様 三日此の世をかまひなさらぬと この世はクニャクニャとなるのざぞ。結構近づいて居るのざぞ。大層が近づいて居るのざぞ。この神示読みて神々様にも守護神殿にも聞かせて呉れよ。いよいよあめの日津久の神様おんかかりなされるぞ。六月十五日、みづのひつ九か三。
【現代語訳】
これまでは闇の世であったから、どんな悪いことをしても闇に紛れてごまかすことが出来たが、もうその闇の世は終わったのだぞ。勘違いしている人民が沢山いる。どんな集まりでも、そのトップに立つ者は皆、根本的に思い違いをしている。早くさっぱりと心を入れ替えなさい。神の子としての自覚がなければ、これからの神の国には住めなくなるぞ。外国(幽界)へ逃げて行かねばならなくなる。そうなったら二度と帰っては来れないぞ。外国(幽界)行きとならないように、根本から心を入れ替えなさい。日本の国の人民が、皆兵隊のようになる時(国民総動員)、一度にどっと大変なことが起こるぞ。皆、思い違いをしているのだ。「カイの御用」は「キの御用」であるぞ。それが済んだら、まだまだ御用は続くのだ。行けども行けども道は草ぼうぼうで、どこから何が飛び出すか分からない。秋の空のように、事態はがらりと変わるぞ。この方(神)は、様々な姿に化けて全ての者の魂を調べ尽くしてある。魂の改心はなかなか難しいものだから、今度の建て替えでは、天の規則通りに、ビシビシと決着をつけるぞ。御三体の大神様がたった三日間、この世から手を引かれただけで、この世はくにゃくにゃになってしまうのだぞ。素晴らしい世の中(結構)が近づいているのだ。大変なこと(大層)も近づいているのだ。この神示を読んで、神々様やあなたの守護神にも聞かせてあげなさい。いよいよ、天の日津久の神が本格的に動き出されるぞ。
【AIによる解釈】
この帖は、時代の転換が「闇の世」から「光の世」への移行であり、それによって全ての嘘やごまかしが通用しなくなることを宣言しています。特に指導者層(大将)の「思ひ違ひ」を厳しく指摘しており、トップから心を入れ替える必要性を説いています。 「神の子でないと神の国には住めん」「幽界(がいこく)へ逃げて行かなならん」という言葉は、厳しい魂の選別を示唆します。ここでいう「幽界(がいこく)」は、物理的な外国だけでなく、波長の合わない者が行くことになる霊的な異世界をも意味していると考えられます。 「日本の国の臣民 皆兵隊さんになった時」とは、国民義勇隊の結成など、国民総動員体制が極限に達した時を指し、その頂点で「どっと大変が起る」(=敗戦)ことを予言しています。「カイの御用はキの御用」とは、ミロク(五六七)の世を作る準備(カイ)は、まず人々の気(キ)を立て直し、本来あるべき状態に返す(カイ)ことから始まる、という意味でしょう。 神は全ての魂を見通しており、改心しない者には天の規則通り、厳しい処置が下されると述べられています。世界の存立がいかに危ういものであるか(神が三日手を引けば崩壊する)、そして「結構(素晴らしい世)」と「大層(大変なこと)」が同時に近づいているという、建替の二面性を強調しています。
第十五帖 (二八九)
【原文】
富士、火吐かぬ様おろがみて呉れよ、大難小難にまつりかへる様おろがみて呉れよ。食物(たべもの)頂く時はよくよく噛めと申してあろが、上の歯は火ざぞ、下の歯は水ざぞ。火と水と合すのざぞ。かむろぎ かむろみぞ。噛むと力生れるぞ。血となるぞ、肉となるぞ。六月十七日、ひつ九のかみ。
【現代語訳】
富士山が噴火しないように祈ってくれよ。大きな難が小さな難で済むように「まつりかえ」て(祀り変えて)くれよ。食べ物を頂く時は、よくよく噛みなさいと申してあるだろう。上の歯は「火」で、下の歯は「水」だ。火と水とを合わせるのだ。それが神漏岐(かむろぎ)・神漏美(かむろみ)という産霊(むすび)の働きなのだ。噛むことで力が生まれ、それが血となり肉となるのだ。
【AIによる解釈】
この帖は、人々の祈りの力によって、天変地異のような大難を小難にすることができる(まつりかえる)という、重要な教えを示しています。富士山の噴火という具体的な事象を挙げ、それを鎮めるための祈りを促しています。これは、人間の意識が、地球の物理現象に影響を与えることができるという思想に基づいています。 そして再び、「噛む」ことの重要性に言及します。ここではさらに深い神学的解釈が加えられます。上の歯を「火」(陽、天、霊)、下の歯を「水」(陰、地、体)とし、噛むという行為を、その火と水、陰陽二つのエネルギーを統合(合す)する神聖な儀式と捉えています。この統合こそが、日本神話における創造の神である「神漏岐(かむろぎ)・神漏美(かむろみ)」の働き、すなわち「産霊(むすび)」の力そのものであると説きます。 食べ物がただの栄養源ではなく、よく噛むという意識的な行為を通じて、神聖な創造のエネルギーとなり、自らの血肉、生命力に変わるのだという、日常の中に秘められた深遠な真理を教えています。
十六帖 (二九〇)
【原文】
まだまだ御苦労あるぞ。たまの宮つくりてよいぞ。われの事言はれて腹のたつ様な小さい心では、今度の御用出来はせんのざぞ。心大きく持てと申してあろがな。六月二十日、ひつ九のかみ。
【現代語訳】
まだまだ御苦労は続くぞ。(魂を磨くための)魂の宮(たまのみや)を(心の中に)作って良いのだぞ。自分のことを何か言われて腹を立てるような小さい心では、これからの神の御用は務まらないのだぞ。心を大きく持てと申してあるだろう。
【AIによる解釈】
この短い帖は、精神的な成熟を強く促すメッセージです。「まだまだ御苦労あるぞ」と、試練がまだ続くことを念押しした上で、「たまの宮つくりてよいぞ」と告げます。これは物理的な宮の建設だけでなく、自らの心の中に、神を祀る神聖な場所、すなわち「魂の宮」を確立せよ、という意味合いが強いでしょう。 その上で、どのような心が求められるかを具体的に示しています。「われの事言はれて腹のたつ様な小さい心」では、神の御用は務まらない、と。これは、他者からの批判や悪口に一喜一憂するような、自己中心的な小さなエゴを乗り越えよ、という戒めです。これから起こる大峠においては、個人的な感情に囚われず、全てを受け入れる「大きい心」を持つことが不可欠であると、改めて強調しています。
第十七帖 (二九一)
【原文】
カイの御用はキの御用であるぞ。臣民はミの御用つとめて呉れよ。キとミの御用であるぞ。ミの御用とは体(からだ)の御用であるぞ。身 養ふ正しき道開いて伝へて呉れよ。今迄の神示読めばわかる様にしてあるぞ。キの御用に使ふものもあるぞ。キミの御用さす者もあるぞ、お守りの石どしどしさげてよいぞ。水の巻これで終りぞ。六月二十三日、三(みず)の一二。
【現代語訳】
「カイ」の御用(ミロクの世の準備)は、まず「キ」(気、霊)の御用から始まる。「臣民(人民)」は、「ミ」(身、体、実)の御用を務めてくれ。「キ(霊)」と「ミ(体)」の両方の御用が重要なのだ。「ミの御用」とは、体の御用である。身体を養う正しい道(食生活や健康法など)を開いて、人々に伝えてくれ。これまでの神示を読めば、その方法は分かるようにしてあるぞ。中には「キの御用」に使う者もいる。「キ」と「ミ」両方の御用をさせる者もいる。お守りの石は、どんどん下げて良いぞ。水の巻はこれで終わりである。
【AIによる解釈】
「水の巻」の締めくくりとなるこの帖は、「キ」と「ミ」という二つの重要な概念で、人々の役割分担を明確にしています。
- キの御用: 「気」「霊」に関する御用。祝詞を奏上したり、神示を取り次いだりといった、霊的な働きかけを指します。
- ミの御用: 「身」「体」「実」に関する御用。肉体を健全に保つための正しい生活法(食事、健康法など)を自ら実践し、それを人々に広めるという、現実的・物理的な働きかけを指します。 神示は、霊的なこと(キ)だけに偏ってはならず、肉体を整え、現実世界で実践する(ミ)ことが同等に重要であると説きます。「キ」と「ミ」が揃って初めて「キミ(君)」となり、一人前の働きができる、という意味も含まれているかもしれません。 「身 養ふ正しき道」はこれまでの神示(よく噛むこと、感謝して食べることなど)に示されており、それを読み解き実践することが求められます。人にはそれぞれ役割があり、「キの御用」専門の人、「キミ両方」を担う人もいると示唆しています。 「水の巻」全体を通して語られた「火(キ)と水(ミ)」の統合というテーマが、ここで具体的な人々の「御用(役割)」として落とし込まれ、巻が締められています。霊的世界と現実世界、その両方における実践こそが、新しい世を創る力となるのです。
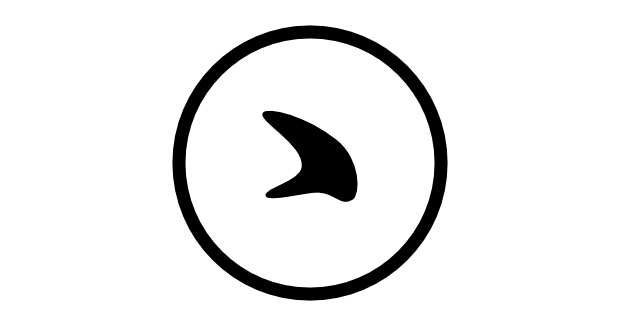





コメント