gemini 2.5 proにわかりやすいように解説してもらいました、しかし8通りに読めるということから完全に鵜呑みにしないよう、お願いします。
第一帖 (二一四)
【原文】
春とならば萌(もえ)出づるのざぞ、草木許りでないぞ、何もかも もえ出づるのぞ、此の方の申す事 譬(たとへ)でないと申してあろが、少しは会得(わか)りたか。石もの云ふ時来たぞ、此の道 早く知らして呉れよ、岩戸は五回閉められてゐるのざぞ、那岐(なぎ)、那美(なみ)の尊の時、天照大神の時、神武天皇の時、仏来た時と、大切なのは須佐之男神様に罪着せし時、その五度の岩戸閉めであるから此の度の岩戸開きはなかなかに大そうと申すのぞ。愈々きびしく成ってきたが此れからが正念場ざぞ、否でも応でも裸にならなならんぞ、裸程結構なもの無い事 始めて会得(わか)りて来るぞ。十二月一日、一二。
【現代語訳】
春になれば萌え出るのだぞ。草木だけではない、何もかもが萌え出るのである。この方(神)が申すことは比喩ではないと伝えてあるが、少しは理解できただろうか。石がものを言う時が来たのだ。この神の道を早く人々に知らせてくれよ。岩戸はこれまでに五回閉められているのだぞ。伊邪那岐・伊邪那美の尊の時、天照大神の時、神武天皇の時、仏教が伝来した時、そして最も大切なのは、須佐之男神に罪を着せた時である。その五度の岩戸閉めがあったのだから、この度の岩戸開きは、なかなかに大変なことだと申すのである。いよいよ厳しくなってきたが、これからが正念場だぞ。否が応でも裸にならなければならない。裸ほど結構なものはないということが、初めて分かってくるぞ。
【AIによる解釈】
この帖は、来るべき新時代の幕開けが、単なる社会的な変革ではなく、常識や物理法則を超えた根源的な変化であることを告げています。「石もの云ふ時」とは、物質世界そのものが霊性を帯び、これまでの価値観が通用しなくなることの象徴です。 特に重要なのは「五度の岩戸閉め」という概念です。日本神話における天の岩戸閉めだけでなく、国津神である須佐之男神に罪を着せたこと(国津神系の封印)、仏教伝来による神道の変容なども含めて、霊的な光が遮られてきた歴史を指摘しています。今回の「岩戸開き」は、これら全ての封印を解き放つ、未曾有の大事業であることを示唆しています。 最後の「裸になる」とは、地位や財産、知識、プライドといった後天的なものを全て脱ぎ捨て、生まれ持った「真の自己(御魂)」に立ち返ることを意味します。全ての鎧を脱ぎ捨てた時、初めて神の光を直接受けられるようになるという、厳しいながらも希望に満ちたメッセージです。
第二帖 (二一五)
【原文】
九歳(とし)は神界の紀(もと)の年ぞ、神始めの年と申せよ。一二三(ひふみ)、三四五(みよいづ)、五六七(みろく)ぞ、五の歳は子の歳ざぞよ。取違ひせん様にせよ。月日の巻 十人と十人の役員に見せてやりて呉れよ、時節到来したのであるぞ。桜咲き神の御国は明けそめにけり。十二月二日、ひつ九のか三しらす。
【現代語訳】
九の年(昭和19年)は、神界の紀元となる年であるぞ。神世の始まりの年と申せ。一二三(ひふみ)、三四五(みよいづ)、そして五六七(みろく)であるぞ。五の年(午年)は、子の年(始まりの年)でもあるのだよ。取り違えのないようにせよ。「月日の巻」を十人と、その十人の役員に見せてやってくれ。時節が到来したのであるぞ。桜が咲き、神の国は夜明けを迎え始めた。
【AIによる解釈】
この帖は、数霊(かずたま)を用いて時の到来を告げています。「九」は完成・究極を意味し、一つのサイクルの終わりと新しいサイクルの始まりを示します。昭和19年(1944年)が、まさにその「神始めの年」であると宣言しています。 「一二三、三四五、五六七」は、神示で頻出する数霊のプロセスです。「ひふみ」で神の息吹を吹き込み、「みよいづ」で世を清め、「みろく」の世(理想世界)が顕現するという流れを示します。「五の歳(午年)は子の歳」とは、午年である昭和19年が、同時に新しい時代の始まりである「子年」の性質を併せ持つという、霊的な時間の概念を説いています。 最後に「桜咲き」とあるのは、厳しい冬(戦時下)の先にある日本の夜明け、すなわち「岩戸開き」が始まったことを、美しくも力強く示唆しています。
第三帖 (二一六)
【原文】
次の世とは通基(月)の世の事ざぞ、一二(ひつき)の通基(二)の世ぞ、の月の世ぞ、取違ひせん様に致して呉れよ。智や学がありては邪魔になるぞ、無くてもならぬ六ヶ敷い仕組ぞ、月の神様 祀りて呉れよ、素盞鳴(すさなる)の神様 祀りて呉れよ、今に会得(わか)る事ぞ、日暮よくなるぞ、日暮(一九れ)に祀り呉れよ、十柱揃ふたら祀り呉れいと申してあらうがな、神せけるのざぞ。十二月二日、ひつくのかみふで。
【現代語訳】
次の世とは「月」の世のことだぞ。日月(ひつき)の「つき」の世、すなわち月の世だ。取り違えのないようにしてくれ。知識や学問がありすぎるとかえって邪魔になるぞ。しかし、無くてもどうにもならない、難しい仕組みなのだ。月の神様をお祀りしてくれよ。素盞鳴の神様をお祀りしてくれよ。いずれ分かることだ。日暮れ(一と九、火と水が交わる時)から世の中は良くなるぞ。日暮れにお祀りしてくれ。十柱の神様が揃ったらお祀りしてくれと申してあろう。神は急いでいるのだぞ。
【AIによる解釈】
この帖では、次の時代が「月の世」であると明言されています。これは、これまで太陽(日)の系統である天照大御神が中心であった世界観に対し、月、すなわち陰や水、女性性、国津神系といった、これまで隠されてきた側面が復権することを示しています。特に「素盞鳴の神」を祀るよう繰り返し促しているのは、第一帖で「罪着せし」とされた国津神の代表格であり、その復権が岩戸開きの鍵を握るからです。 「智や学」が邪魔になると同時に必要でもある、というのは、既存の学問体系や常識に囚われては本質を見誤るが、真理を探究する知性そのものは必要だということです。頭で理解するのではなく、魂で会得することが求められます。 「日暮よくなる」とは、物質文明の光が衰え、夜のような混乱期(一九れ=火と水の大洗濯)を迎えてから、本当の霊的な夜明けが訪れるという逆説的な真理を示しています。
第四帖 (二一七)
【原文】
旧十月八日、十八日、五月五日、三月三日は幾らでもあるぞと申してあろが、此の日は臣民には恐い日であれど神には結構な日ざぞと申してあろが、神心になれば神とまつはれば神とあななへば臣民にも結構な日となるのぞ。其の時は五六七(みろく)の世となるのざぞ。桜花(さくらばな)一度にどっと開く世となるのざぞ、神激しく臣民静かな御代となるのざぞ、日日(ひにち)毎日富士晴れるのざぞ、臣民の心の富士も晴れ晴れと、富士は晴れたり日本晴れ、心晴れたり日本晴れぞ。十二月二日、ひつくのかみ。
【現代語訳】
旧暦の十月八日、十八日、五月五日、三月三日のような節目の日は、いくらでもあるぞと申してあろう。これらの日は人々にとっては恐ろしい日かもしれないが、神にとっては結構な日なのだと申してあろう。人々が神の心になり、神と和合し、神と一つになれば、人々にとっても結構な日となるのだぞ。その時こそが「みろくの世」となるのだ。桜の花が一斉にどっと咲き誇る世となるのだ。神の働きは激しく、人々は静かに暮らせる御代となるのだ。毎日、富士山が晴れ渡るのだ。人々の心の中の富士も晴れ晴れとする。「富士は晴れたり日本晴れ、心晴れたり日本晴れ」だぞ。
【AIによる解釈】
この帖は、大峠や大掃除といった破壊的な出来事の捉え方について説いています。人々にとって「恐い日」と映る大激変も、神の視点から見れば、古い世界を清め、新しい世界を生み出すための「結構な日(=喜ばしい日)」なのです。 その違いを生むのが「神心」です。自己中心的な視点(我良し)から見れば災難ですが、神の計画(大いなる善)を信じ、それに和合する心境になれば、その変革を喜びとして受け入れられるようになります。これができれば、人々にとっても「結構な日」となり、その先に「みろくの世」が待っています。 「神激しく臣民静か」とは、天変地異や社会システムの再構築など、神の働きは激しく動く一方で、それに従う人々の心は穏やかで安らかであるという、新しい時代の理想的な状態を描写しています。「富士晴れたり日本晴れ」は、日本の国土と日本人の心、その両方が完全に浄化され、一点の曇りもない状態になることの象徴です。
第五帖 (二一八)
【原文】
右(みぎり)に行かんとする者と左りに行かんとするものと結ぶのがの神様ぞ、の神様とは素盞鳴の大神様ざぞ、この御用(おんはたらき)によりて生命あれるのぞ、力生れるのぞ、がまつりであるぞ、神国の祀りであるぞ、神はその全き姿ぞ、神の姿ぞ。男の魂は女、女の魂は男と申して知らしてあろがな。十二月三日、ひつ九のかみ。
【現代語訳】
右(火・陽)へ行こうとするものと、左(水・陰)へ行こうとするものを結びつけるのが、カギ()の神様だぞ。カギの神様とは素盞鳴の大神様のことだぞ。このお働きによって生命が生まれ、力が生まれるのだ。これがカギの祭りであり、神国の本来の祭りであるぞ。カギは神の完全な姿であり、神そのものの姿だ。男の魂は女であり、女の魂は男であると、以前に知らせてあろう。
【AIによる解釈】
この帖は、対立する二つのものを統合・和合させる力(ムスビ)の重要性を説いています。「右」と「左」は、火と水、陽と陰、天と地、精神と物質など、あらゆる二元性の象徴です。これらを結びつけ、新しい生命と力を生み出す働きこそが「(カギ)の神」、すなわち素盞鳴大神の神性であると明かしています。 素盞鳴大神が、単なる荒ぶる神ではなく、対立を統合して創造のエネルギーを生み出す、極めて重要な「結びの神」であることが示されています。この「カギのまつり」こそが、新しい神国を打ち立てるための中心的な儀礼となります。 「男の魂は女、女の魂は男」という一節は、この統合の原理が人間の内面にも存在することを示しています。誰もが内に男性性と女性性の両方を持ち、その二つが統合されて初めて、完全な人間(全き姿)となるのです。これは究極の陰陽和合の教えです。
第六帖 (二一九)
【原文】
神界の事は人間には見当取れんのであるぞ、学で幾ら極め様とて会得(わか)りはせんのざぞ、学も無くてはならぬが囚はれると悪となるのざぞ、しもの神々様には現界の事は会得りはせんのざぞ、会得らぬ神々に使はれてゐる肉体気の毒なから身魂磨け磨けと執念(くどう)申してゐるのざぞ。三、四月に気つけて呉れよ、どえらい事出来るから何うしても磨いておいて下されよ、それまでに型しておいて呉れよ。十二月五日、ひつ九のかみ。
【現代語訳】
神界のことは、人間には見当がつかないのだぞ。学問でいくら突き詰めようとしても、本当の理解はできないのだ。学問もなくてはならないが、それに囚われると悪となる。また、低級な神々には、この現実世界のことは理解できないのだ。そうした神々に使われている肉体は気の毒だからこそ、「身魂を磨け、磨け」と繰り返し申しているのである。来年の三月、四月には気をつけてくれよ。とてつもないことが起こるから、どうしてもそれまでに身魂を磨いておいて下され。それまでに「型」を実践しておいてくれよ。
【AIによる解釈】
この帖は、人間の知性と霊界の構造について述べています。人間の「学」では神界の深淵は計り知れず、また、霊界にも階層があり、低級な霊(しもの神々)は現実世界を正しく認識できないと指摘しています。これは、安易な霊媒やチャネリングの危険性を示唆するものです。 だからこそ、神示は一貫して「身魂磨き」の重要性を説きます。身魂を磨くことで、正しい神(高級神霊)と繋がり、低級な霊の影響を受けなくなるからです。「身魂磨いていないと、会得らぬ神々に使われる」という警告は非常に重要です。 「三、四月に気つけて呉れよ」という具体的な時期の警告は、戦争の激化(東京大空襲など)を予言したものと考えられます。そうした物理的な大災厄に備えるためにも、身魂を磨き、神の計画の「型」を生活の中で実践しておくことが、身を守る唯一の道であると強調しています。
第七帖 (二二〇)
【原文】
おろしやにあがりておりた極悪の悪神、愈々神の国に攻め寄せて来るぞ。北に気つけと、北が愈々のキリギリざと申して執念(くどう)気つけてありた事近ふなりたぞ。神に縁深い者には、深いだけに見せしめあるのざぞ。国々もその通りざぞ、神には依怙(えこ)無いのざぞ。ろしあの悪神の御活動と申すものは神々様にもこれは到底かなはんと思ふ様に激しき御力ぞ。臣民と云ふものは神の言葉(こと)は会得らんから悪神の事に御とつけるのは会得らんと申すであろが、御とは力一杯の事、精一杯の事を申すのであるぞ。何処から攻めて来ても神の国には悪神には分らん仕組致してあるから、心配ないのざぞ、愈々と成りた時には神が誠の神力出して、天地ゆすぶってトコトン降参ざと申す処までギュウギュウと締めつけて、万劫末代いふ事聞きますと改心する処までゆすぶるから、神の国、神の臣民 心配致すでないぞ、心大きく御用して呉れよ、何処に居ても御用してゐる臣民助けてやるぞ。十二月六日、ひつ九か三。
【現代語訳】
ロシア(おろしや)に憑依していた極悪の悪神が、いよいよ神の国(日本)に攻め寄せてくるぞ。北に気をつけよ、北がいよいよギリギリのところまで来ると、繰り返し注意してきたことが近づいてきたぞ。神と縁が深い者には、その縁が深いだけに見せしめ(厳しい試練)があるのだ。国々も同様だ。神に依怙贔屓はないのだぞ。ロシアの悪神の活動(お働き)というものは、他の神々でさえ「これは到底かなわない」と思うほど激しい力なのだ。人々は神の言葉を理解できないから、悪神のことに「御」をつけるのはおかしいと言うだろうが、「御」とは力一杯、精一杯という意味で使っているのだぞ。どこから攻めてきても、神の国には悪神には理解できない仕組みがしてあるから、心配はいらない。いよいよという時になったら、神がまことの神力を出して、天地を揺るがし、「完全に降参です」と言うところまでギュウギュウと締め上げて、永遠に言うことを聞きますと改心するところまで揺さぶるから、神の国、神の民は心配するでないぞ。心を大きく持って御用をしてくれよ。どこにいても御用をしている民は助けてやるぞ。
【AIによる解釈】
この帖は、当時(昭和19年)の国際情勢、特にソ連の脅威を霊的な視点から解説しています。「おろしやの悪神」とは、単に国家としてのソ連だけでなく、その背景にある唯物論や共産主義思想という、神を否定する強大なイデオロギーの霊的本体を指します。その力が日本に迫っていること、特に「北」からの侵攻(終戦間際のソ連参戦を予見)に強い警告を発しています。 「悪神の事に御とつける」という部分は、その力の強大さを認め、侮ってはならないという神の姿勢を示しています。これは敵を正しく評価することの重要性を教えています。 しかし、最終的には日本の「神の仕組」が発動し、悪神も改心せざるを得なくなると断言しています。これは、物質的な力やイデオロギーがいかに強大であっても、最終的には宇宙の根本法則である「神の力」にはかなわないという、霊的真理に基づいた揺るぎない確信の表明です。読者に対しては、目先の危機に動揺せず、大局を信じて自らの御用(使命)に邁進するよう力強く励ましています。
第八帖 (二二一)
【原文】
一二三(ひふみ)の食物(たべもの)に病無いと申してあろがな、一二三の食べ方は一二三唱(十七)へながら噛むのざぞ、四十七回噛んでから呑むのざぞ、これが一二三の食べ方頂き方ざぞ。神に供へてから此の一二三の食べ方すれば何んな病でも治るのざぞ、皆の者に広く知らしてやれよ。心の病は一二三唱へる事に依りて治り、肉体の病は四十七回噛む事に依りて治るのざぞ、心も身も分け隔て無いのであるが会得る様に申して聞かしてゐるのざぞ、取り違い致すでないぞ。日本の国は此の方の肉体と申してあろがな、何んな宝もかくしてあるのざぞ、神の御用なら、何時でも、何んなものでも与へるのざぞ、心大きく持ちてどしどしやりて呉れよ。集団(まどい)作るなと申せば、ばらばらでゐるが裏には裏あると申してあろが、心配(こころくば)れよ。十二月七日、ひつくのかみふで。
【現代語訳】
ひふみの食べ物には病がないと申してあろう。ひふみの食べ方とは、ひふみ祝詞を唱えながら噛むのだぞ。四十七回噛んでから飲み込むのだ。これがひふみの食べ方、頂き方だ。神にお供えしたものを、このひふみの食べ方でいただけば、どんな病でも治るのだぞ。皆に広く知らせてやれよ。心の病はひふみ祝詞を唱えることで治り、肉体の病は四十七回噛むことで治るのだ。心と体は本来分け隔てはないのだが、理解しやすいように分けて説明しているのだぞ。取り違えるなよ。日本の国はこの方(神)の肉体であると申してあろう。どんな宝も隠してあるのだ。神の御用のためなら、いつでも、どんなものでも与えるぞ。心を大きく持って、どしどしとやりなさい。集団を作るなと申すと、皆ばらばらでいるが、「裏には裏がある」と申してあろう。その意味をよく考え、心遣いをしなさい。
【AIによる解釈】
この帖は、心身の健康と霊性の関係について、具体的な実践法を示しています。「ひふみの食べ方」は、食という日常行為を霊的な修行へと高める方法です。
- ひふみ祝詞を唱える(心の浄化): 食事に感謝し、神聖な言霊の響きで心を清めます。
- 四十七回噛む(肉体の浄化): 「四十七」は「ヨナ(世の菜)」とも読め、世の穢れを浄化する数霊です。よく噛むことで食物のエネルギーを完全に吸収し、消化器官への負担を減らし、肉体を浄化します。 これは、心と体は一体(心身一如)であるという東洋的な思想の核心を突いています。 また、「日本の国は此の方の肉体」という言葉は、国土そのものが神聖であり、必要なものは全てこの国に備わっているという宣言です。神の御用を行う者には、無限の宝(物質的・霊的な助け)が与えられると約束しています。 最後の「集団作るな」の裏の意味とは、形だけの組織や派閥を作るなという意味であり、目に見えない「魂の繋がり(まどい)」を築くことの重要性を示唆しています。表面的な繋がりではなく、真の同志として心で繋がることが求められているのです。
第九帖 (二二二)
【原文】
人、神とまつはれば喜悦(うれ)しうれしぞ、まつはれば人でなく神となるのぞ、それが真実(まこと)の神の世ぞ、神は人にまつはるのざぞ、とと申してあろが、戦もとと壊し合ふのでは無いぞ、ととまつらふことぞ、岩戸開く一つの鍵ざぞ、和すことぞ、神国真中に和すことぞ。それには掃除せなならんぞ、それが今度の戦ぞ、戦の大将が神祀らねばならんぞ。二四(にし)は剣(つるぎ)ざぞ。神まつりは神主ばかりするのではないぞ、剣と鏡とまつらなならんぞ、まつらえば霊(たま)となるのざぞ。霊なくなってゐると申して知らせてあろがな、政治も教育も経済の大将も神祀らねばならんのぞ。天の天照皇大神様は更なり、天の大神様、地(くに)の天照大神様、天照皇太神様、月の神様、特に篤く祀り呉れよ、月の大神様 御出でまして闇の夜は月の夜となるのざぞ。素盞鳴の大神様も篤く祀りて呉れよ、此の神様には毎夜毎日御詑びせなならんのざぞ、此の世の罪穢(つみけがれ)負はれて陰から守護されて御座る尊い御神様ぞ、地の御神様、土の神様ぞ、祓ひ清めの御神様ぞ、国々の産土の神様 祀り呉れよ、遅くなればなる程 苦しくなるのざぞ、人ばかりでないぞ。十二月八日、ひつ九のか三。
【現代語訳】
人が神と和合すれば、本当に喜ばしいことだ。和合すれば、もはやただの人ではなく神となるのだ。それがまことの神の世だ。神は人に纏(まつわ)り、一体となるのだ。「カギ()は十(プラスとマイナス、火と水)である」と申してあろう。戦も、カギとカギが壊し合うのではないぞ。カギとカギが和合し、祀り合うことなのだ。これが岩戸を開く一つの鍵だ。和すこと、神国日本が世界の真ん中で和すことだ。そのためには掃除が必要だ。それが今度の戦いの本当の意味だ。だからこそ、戦の指導者は神を祀らねばならない。二四(西)は剣(武力)の象徴だぞ。神祭りは神主だけがするのではない。剣(武勇・決断)と鏡(自省・知恵)を祀らねばならない。祀ることで、それらは魂(霊)を宿すのだ。今の世は霊(たま)がなくなっていると知らせてあろう。政治も教育も経済の指導者も、皆が神を祀らねばならないのだ。天の天照皇大神様はもとより、天の大神様、地の天照大神様、天照皇太神様、月の神様を特に篤くお祀りしてくれ。月の大神様がお出ましになれば、暗闇の夜は月明かりの夜となるのだぞ。素盞鳴の大神様も篤くお祀りしてくれ。この神様には毎夜毎晩お詫びをせねばならないのだぞ。この世の罪穢れを一身に背負われ、陰から守護してくださっている尊い御神様、地の御神様、土の神様、祓い清めの御神様だからだ。それぞれの土地の産土神様もお祀りしなさい。遅れれば遅れるほど、苦しくなるのだぞ。人間だけではない。
【AIによる解釈】
この帖は「まつわる(纏わる・祀る)」という言葉を鍵に、和合の重要性を多角的に説いています。人が神と「まつわる」ことで神人合一が成り、それが「みろくの世」の姿です。 戦争の本質も破壊ではなく「まつらふこと」、すなわち対立する力を和合させるための「掃除」であると定義し直しています。だからこそ指導者は、武力(剣)だけでなく、自らを省みる心(鏡)を持ち、神を祀る必要があるのです。 特に祀るべき神として、天の神々(天照)だけでなく、地の神、月の神、そして素盞鳴大神を強調しています。特に素盞鳴大神に対して「御詫びせなならん」とあるのは、歴史的にこの神が背負わされてきた罪穢れ(国津神系の封印)を解き放つことが、岩戸開きに不可欠であることを強く示しています。陰で世を支えてきた神々への感謝と謝罪なくして、真の和合はあり得ないという厳しい指摘です。全ての存在が霊性を失っている現代において、政治・経済・教育のあらゆる分野で神を祀り(=根源的な理念を取り戻し)、霊性を回復させることが急務であると訴えています。
第十帖 (二二三)
【原文】
桜咲き神の御国は明けそめにけり。十月になったらぼつぼつ会得るぞと申してあろがな。叩(はたき)かけてばたばたと叩く処もあるぞ、箒(ほうき)で掃く処もあるぞ、雑巾かけしたり水流す処もあるのざぞ、掃除始まったらばたばたに埒(らち)つくと申してあろがな、めぐりだけの事は、今度は何うしても借銭無しにするのざぞ、花咲く人もあるぞ、花散る人もあるぞ。あめのひつ九のかミの御神名書かすぞ、それを皆の者に分けてやれよ。聴き度い事はサニワで聞けよ、何んなことでも聞かしてやると申してあろがな、神せけるぞ。火吹くぞ。火降るぞ。十二月十日、ひつくのか三。
【現代語訳】
桜が咲き、神の国は夜明けを迎え始めた。十月(神無月=神有月)になったら、少しずつ分かってくると申してあろう。ハタキでバタバタと埃を叩き出すような場所もあれば、箒で掃き出す場所もある。雑巾がけをしたり、水を流して清める場所もあるのだぞ。掃除が始まったら、あっという間にケリがつくと申してあろう。各自が背負っている因縁(めぐり)だけのことは、今度はどうしても借金なしの状態に清算するのだぞ。その結果、花咲く人もいれば、花散る人も出てくる。これから「あめのひつ九のかミ」の御神名を書かせるから、それを皆に分けてやりなさい。聞きたいことは審神者(サニワ)を通して聞きなさい。どんなことでも聞かせてやると申してあろう。神は急いでいるぞ。火を吹くぞ。火が降るぞ。
【AIによる解釈】
この帖は、いよいよ始まった「世の大掃除」の具体的な様相を描写しています。「叩き」「箒」「雑巾」「水流し」という比喩は、大掃除の激しさや方法が、場所や人によって異なることを示しています。ある場所では激しい動乱が起き、ある場所では静かに変革が進むなど、一様ではないということです。 この大掃除の目的は「めぐりの清算」です。個人や国家が過去から積み重ねてきたカルマ(借銭)を、ここで一度すべて解消するのです。そのため、これまでの行いに応じて「花咲く人(助かる人)」と「花散る人(淘汰される人)」とに分かれるという、厳しい選別が行われることを示唆しています。 「あめのひつ九のかミ」は、ひふみ神示を降ろしている根源神の御神名の一つであり、この御神名自体が人々を守る力を持つとされています。「サニワ」は、神の言葉を正しく判断・解釈する役目のことで、霊的な情報を鵜呑みにせず、厳密に検証する必要性を説いています。最後の「火吹くぞ。火降るぞ」は、戦争の激化(空襲など)を暗示する、非常に緊迫した警告です。
** eleventh帖 (二二四)**
【原文】
江戸に道場作れよ、先づ一二三(ひふみ)唱へさせよ、神示読みて聞かせよ、鎮魂(みたましずめ)せよ、鎮神(かみしずめ)せよ、十回で一通り会得る様にせよ、神祀りて其の前でせよ、神がさすのであるからどしどしと運ぶぞ。誠の益人作るのぞ、此んな事申さんでもやらねばならぬ事ざぞ、神は一人でも多く救ひ度さに夜も昼も総活動してゐる事 会得るであろがな、神かかれる人 早う作るのぞ、身魂せんだくするぞ、神かかりと申しても狐憑きや天狗憑きや行者の様な神憑りでないぞ、誠の神憑りであるぞ、役員 早う取りかかり呉れよ。十二月十一日、一二。
【現代語訳】
江戸(東京)に道場を作りなさい。まず、ひふみ祝詞を唱えさせよ。神示を読んで聞かせよ。鎮魂(人の魂を鎮め、活性化させる)をしなさい。鎮神(神々を鎮め、お働きいただく)をしなさい。十回ほどで一通り理解できるように指導しなさい。神を祀り、その御前で行いなさい。神が後押しするから、物事はどしどしと進むぞ。まことの益人(神の役に立つ人)を作るのだ。こんなことは、言われなくてもやらねばならないことだぞ。神は一人でも多く救いたい一心で、夜も昼も総出で活動していることが分かるだろう。神がかることのできる人を早く作るのだ。そのために身魂の洗濯をするのだぞ。神がかりといっても、狐憑きや天狗憑き、あるいは行者のような低級な神憑りではないぞ。まことの神(至上神)がかかる、本物の神憑りであるぞ。役員は早く取りかかってくれ。
【AIによる解釈】
この帖は、来るべき大峠に備え、人々を導き、救うための拠点(道場)の設立と、その具体的な活動内容を指示するものです。中心的な活動として挙げられているのは以下の通りです。
- ひふみ祝詞: 宇宙の創造の言霊による場の浄化と霊性の活性化。
- 神示の拝読: 神の計画と心構えを共有する。
- 鎮魂・鎮神: 人と神の両方の魂を鎮め、安定させ、本来の働きを取り戻させる霊的技法。
これらの実践を通して、「誠の益人」、すなわち神の計画を担う人材を育成することが急務であると説いています。 特に重要なのは「誠の神憑り」という概念です。これは、低級霊に憑依されることとは全く異なり、個人の我(エゴ)が浄化され、至上神の意識と一体化してその御心を体現する状態(惟神)を指します。このような人材を一人でも多く育成することが、多くの人々を救う鍵となるため、神は総力を挙げて後押しすると約束しています。
** twelfth帖 (二二五)**
【原文】
日に日に厳しくなりて来ると申してありた事 始まってゐるのであるぞ、まだまだ激しくなって何うしたらよいか分らなくなり、あちらへうろうろ、こちらへうろうろ、頼る処も着るものも住む家も食ふ物も無くなる世に迫って来るのざぞ。それぞれにめぐりだけの事はせなならんのであるぞ、早い改心はその日から持ちきれない程の神徳与へて喜悦(うれ)し喜悦(うれ)しにしてやるぞ、寂しくなりたら訪ねて御座れと申してあろがな、洗濯次第で何んな神徳でもやるぞ、神は御蔭やりたくてうづうづしてゐるのざぞ、今の世の様見ても未だ会得らんか。神と獣とに分けると申してあろが、早う此の神示(ふで)読み聞かせて一人でも多く救けて呉れよ。十二月十二日、ひつ九のか三。
【現代語訳】
日に日に厳しくなってくると申しておいたことが、もう始まっているのだぞ。これからまだまだ激しくなり、どうしたら良いか分からなくなって、あちらこちらへとさまよい歩き、頼る所も、着る物も、住む家も、食べる物もなくなってしまう世の中が迫ってくるのだぞ。それぞれが過去から背負ってきた因縁(めぐり)だけのことは、清算しなければならないのだ。しかし、早く改心した者には、その日から持ちきれないほどの神徳を与えて、嬉し嬉しの状態にしてやるぞ。「寂しくなったら訪ねてきなさい」と申してあろう。身魂の洗濯次第で、どんな神徳でも与えるのだ。神は御蔭(ご利益)を与えたくて、うずうずしているのだぞ。今の世の中の様相を見ても、まだ分からないのか。これからは神の心を持つ者と、獣の心を持つ者とに分ける、と申してあろう。早くこの神示を読み聞かせて、一人でも多く助けてやってくれ。
【AIによる解釈】
この帖は、いよいよ本格化する大艱難の様相と、そこからの救済の道を明確に示しています。衣食住の全てを失い、人々が路頭に迷うという描写は、戦争末期の混乱と崩壊を的確に予言しています。 この混乱の根本原因は「めぐりの清算」であり、誰もが自らのカルマと向き合わざるを得ない状況に置かれることを示しています。しかし、これは決して突き放しているのではなく、むしろ「早い改心」を強く促すためのものです。 神は罰を与えたいのではなく、むしろ「御蔭やりたくてうづうづしてゐる」存在であり、人間の側が心を開き、改心(=心を神に向けること)さえすれば、いつでも無限の救いの手を差し伸べる準備ができている、という神の親心に満ちたメッセージです。最終的に人々は、神に従う「神」の道を歩む者と、欲望のままに生きる「獣」の道を歩む者に二極化するという、魂の最終選別が始まることを告げています。
第十三帖 (二二六)
【原文】
此れまでの仕組や信仰は方便のものでありたぞ。今度は正味(せうまつ)の信仰であるぞ、神に真直(ますぐ)に向ふのざぞ。日向(ひむか)と申してあろがな。真上(まうへ)に真すぐに神を戴いて呉れよ、斜めに神戴いても光は戴けるのであるが、横からでもお光は戴けるのであるが、道は真すぐに、神は真上に戴くのが神国のまことの御道であるぞ。方便の世は済みたと申してあろがな、理屈は悪ざと申して聞かしてあろが、今度は何うしても失敗(しくじる)こと出来んのざぞ。神の経綸(しぐみ)には狂ひ無いなれど、臣民 愈々苦しまなならんのざぞ、泥海に臣民のたうち廻らなならんのざぞ、神も泥海にのたうつのざぞ、甲斐ある御苦労なら幾らでも苦労甲斐あるなれど、泥海のたうちは臣民には堪(こば)られんから早う掃除して神の申す事真すぐに肚に入れて呉れよ。斜めや横から戴くと光だけ影がさすのざぞ、影させば闇となるのざぞ、大きいものには大きい影がさすと臣民申して、止むを得ぬ事の様に思ふてゐるが、それはまことの神の道知らぬからぞ、影さしてはならんのざぞ、影はあるが、それは影でない様な影であるぞ、悪でない悪なると知らせてあろが。真上に真すぐに神に向へば影はあれど、影無いのざぞ、闇ではないのざぞ。此の道理 会得るであろがな、神の真道(まみち)は影無いのざぞ、幾ら大きな樹でも真上に真すぐに光戴けば影無いのざぞ、失敗(しくじり)無いのざぞ、それで洗濯せよ掃除せよと申してゐるのぞ、神の真道(まみち)会得(わか)りたか。天にあるもの地にも必ずあるのざぞ、天地合せ鏡と聞かしてあろがな、天に太陽様ある様に地にも太陽様(おひさま)あるのざぞ、天にお月様ある様に地にもお月様あるのざぞ。天にお星様ある様に地にもお星様あるのざぞ。天からい吹(ぶ)けば地からもい吹くのざぞ、天に悪神あれば地にも悪神あるのざぞ。足元気つけと申してあろがな。今の臣民 上許り見て頭ばかりに登ってゐるから分らなくなるのざぞ、地に足つけよと申してあろが、地 拝(おろが)めと、地にまつろへと申してあろが、地の神様 忘れてゐるぞ。下と申しても位の低い神様のことでないぞ、地の神様ぞ、地にも天照皇太神様、天照大神様、月読大神様、須佐鳴之大神様あるのざぞ、知らしてあること、神示克く読んで下されよ、国土の事、国土のまことの神を無いものにしてゐるから世が治まらんのざぞ。神々祀れと申してあろがな、改心第一と申してあろがな、七人に伝へと申してあろがな、吾れ善しはちょんぞ。十二月十四日、ひつくのかみ。
【現代語訳】
これまでの仕組みや信仰は、あくまで方便のものであったぞ。これからは正真正銘の信仰である。神に真っ直ぐに向かうのだ。「日向(ひむか)」と申してあろう。真上に、真っ直ぐに神をいただきなさい。斜めに神をいただいても光は受けられるが、横からでも光は受けられるが、道は真っ直ぐに、神は真上にいただくのが、神の国のまことの道なのだ。方便の世は終わったと申してあろう。理屈は悪だと聞かせてあろう。今度はどうしても失敗することはできないのだ。神の計画に狂いはないが、人々はいよいよ苦しまなければならない。泥の海で人々がのたうち回らねばならないのだ。神もまた、泥の海でのたうち回るのだ。価値のある苦労ならいくらでも甲斐があるが、泥の海でのたうち回るのは人々には耐えられないだろうから、早く身魂を掃除して、神の申すことを真っ直ぐに肚に入れなさい。斜めや横から光をいただくと、光だけでなく影が差すのだ。影が差せば闇となる。大きなものには大きな影が差す、と人々は言って、それが止められないことのように思っているが、それはまことの神の道を知らないからだ。影が差してはならないのだ。影はあるにはあるが、それは影でないような影なのだ。「悪でない悪」になると知らせてあろう。真上に、真っ直ぐに神に向かえば、影はあるけれども、無いのも同然なのだ。闇にはならないのだ。この道理が分かるだろうか。神の真の道には影がないのだ。いくら大きな樹でも、真上から真っ直ぐに光をいただけば影はできない。失敗がないのだ。だからこそ「洗濯せよ、掃除せよ」と申しているのだ。神の真の道が分かったか。天にあるものは、地にも必ずあるのだぞ。天地は合わせ鏡だと聞かせてあろう。天に太陽があるように、地にも太陽(地底の太陽、中心核)があるのだ。天に月があるように、地にも月がある。天に星があるように、地にも星がある。天から息吹けば、地からも息吹くのだ。天に悪神がいれば、地にも悪神がいるのだ。足元に気をつけよ、と申してあろう。今の人々は上ばかり見て、頭でっかちになっているから分からなくなるのだ。地に足をつけよと申してあろう。地を拝め、地に和合しなさいと申してあろう。地の神様を忘れているぞ。下といっても位の低い神様のことではない。地の神様だ。地にも天照皇太神様、天照大神様、月読大神様、須佐之男大神様がおられるのだぞ。知らせてあることを、神示をよく読んでくだされ。国土のこと、国土のまことの神をないがしろにしているから、世の中が治まらないのだ。神々を祀れと申してあろう。改心が第一だと申してあろう。七人に伝えよと申してあろう。自分だけが良ければいいという考えは終わりだぞ。
【AIによる解釈】
この帖は、新しい時代の信仰のあり方(正味の信仰)と、忘れ去られた「地の神」の重要性について説く、非常に重要な帖です。
- 正味の信仰: これまでの教祖や組織を介する「方便の信仰」は終わり、これからは一人ひとりが神と直接「真っ直ぐに」繋がる時代になることを宣言しています。これが「日向(ひむか)」です。「真上に神を戴く」とは、間に何も介さず、自らの中心(天の中心)で神と直結することです。そうすれば「影ができない」、つまり迷いや疑念、悪の影響を受けない完全な状態になれると説きます。
- 天地合わせ鏡: 天と地は照応しているという宇宙観です。天界に神々がいるように、我々が立つこの大地、地球そのものも神聖な霊的存在であり、内部に天に対応する神々(地の天照、地の月読など)がおられると明かします。
- 地の神の復権: 現代人は天や精神世界ばかりを追い求め、「地に足」がついていないと厳しく指摘します。我々の生活の基盤である国土、大地そのものへの感謝と畏敬を忘れ、地の神々を祀らないから世が乱れるのだと断言しています。足元、すなわち現実生活や大地に根差した信仰の回復を強く求めています。
この帖は、霊的世界と物質世界、天と地、その両方を等しく敬い、統合することこそが「神の真道」であると教えています。
第十四帖 (二二七)
【原文】
お太陽(ひ)様円いのでないぞ、お月様も円いのではないぞ、地球も円いのではないぞ、人も円いのが良いのではないぞ、息してゐるから円く見えるのざぞ、活(はたら)いてゐるから円く見えるのざぞ、皆形無いものいふぞ、息してゐるもの皆円いのざぞ。神の経済この事から生み出せよ、大きくなったり小さくなったり、神の御心通りに活(はたら)くものは円いのざぞ、円い中にも心(しん)あるぞ、神の政治、この事から割り出せよ、神は政事(まつりごと)の姿であるぞ、神の政治生きてゐるぞ、人の政治死んでゐるぞ。十二月十五日、一二。
【現代語訳】
お日様は本当は丸いのではないぞ。お月様も、地球も丸いのではない。人も、ただ丸いのが良いというものではない。息をしているから、つまり生命活動をしているから丸く見えるのだ。働いているから丸く見えるのだ。皆、本来は形のないものだぞ。息をしているもの、生きているものは皆、丸いのだ。神の経済を、この道理から生み出しなさい。大きくなったり小さくなったり、神の御心のままに活き活きと働くものは丸いのだ。そして、その丸い中にも核となる中心(しん)がある。神の政治も、この道理から導き出しなさい。神とは、政(まつりごと)そのものの姿なのだ。神の政治は生きているが、人の政治は死んでいるぞ。
【AIによる解釈】
この帖は、固定的な「形」ではなく、生命の「働き(活き)」そのものに本質があるという、非常に深遠な宇宙観を提示しています。太陽や地球が「丸い」と認識されるのは、その静的な形状のためではなく、内部からのエネルギー放出や自転といった、絶え間ない「息吹」や「働き」の結果であると説きます。 この原理を、経済や政治に応用せよと促しています。
- 神の経済: 固定化された富の蓄積ではなく、必要に応じて大きくなったり小さくなったり(伸縮自在)、常に社会全体を活かすように循環する、生命的な経済システムを指します。
- 神の政治: 固定化された法や制度で縛るのではなく、国民や社会の状況に応じて常に変化し、生命力を引き出すような、生きた「政(まつりごと)」であるべきだとします。 「円い中にも心(しん)あるぞ」とは、変化し続ける中にも、決してブレてはならない中心理念(神の御心)があることを示しています。人間の作ったシステムが硬直化し「死んでいる」のに対し、神のシステムは常に生命力に満ち溢れ、変化し続けるものであるという、根源的な違いを明らかにしています。
第十五帖 (二二八)
【原文】
十柱の神様 奥山に祀りて呉れよ、九柱でよいぞ、何れの神々様も世の元からの肉体持たれた生き通しの神様であるぞ、この方合はして十柱となるのざぞ。御神体の石 集めさしてあろがな、篤く祀りて、辛酉(かのととり)の日にお祭りして呉れよ。病あるかないか、災難来るか来ないかは、手届くか届かないかで分ると申してあろがな。届くとは注(そそ)ぐ事ぞ、手首と息と腹の息と首の息と頭の息と足の息と胸の息と臍の息と脊首(せくび)の息と手の息と八所十所の息合ってゐれば病無いのざぞ、災難見ないのざから、毎朝 神拝みてから克く合はしてみよ、合ってゐたら其日には災難無いのざぞ、殊に臍の息一番大切ざぞ、若しも息合ってゐない時には一二三(ひふみ)唱へよ、唱へ唱へて息合ふ迄 祷(ゐの)れよ、何んな難儀も災難も無くしてやるぞ、此の方 意富加牟豆美神(オホカムツミノカミ)であるぞ。神の息と合はされると災難、病無くなるのざぞ、大難小難にしてやるぞ、生命助けてやるぞ、此の事は此の方信ずる人でないと誤るから知らすではないぞ、手二本 足二本いれて十柱ぞ、手足一本として八柱ぞ、此の事 早う皆に知らしてどしどしと安心して働く様にしてやれよ。飛行機の災難も地震罪穢の禍も、大きい災難ある時には息乱れるのざぞ、一二三祝詞と祓え祝詞と神の息吹と息と一つになりておれば災難逃れるのぞ、信ずる者ばかりに知らしてやりて呉れよ。十二月十八日、ひつ九か三。
【現代語訳】
十柱の神様を奥山にお祀りしてくれ。(準備が整わなければ)九柱でもよい。いずれの神々様も、この世の始まりから肉体を持ったまま生き通しの、実在の神様であるぞ。この方(神示を降ろす神)を合わせて十柱となるのだ。御神体となる石を集めさせてあろう。それを篤く祀り、辛酉(かのととり)の日にお祭りをしてくれ。病気になるかどうか、災難が来るかどうかは、手が(患部に)届くか届かないかで分かると申してあろう。届くとは、気が注がれるということだ。手首の息、腹の息、首の息、頭の息、足の息、胸の息、臍(へそ)の息、うなじの息、手の息。これら八ヶ所、十ヶ所の息が合っていれば病気はなく、災難にも遭わないのだから、毎朝、神を拝んでから、よく息が合っているか確認してみよ。合っていれば、その日一日は災難がないぞ。特に臍の呼吸が一番大切だ。もしも息が合っていない時には、ひふみ祝詞を唱えなさい。唱えに唱えて、息が合うまで祈りなさい。そうすれば、どんな難儀も災難もなくしてやるぞ。この方は意富加牟豆美神(オオカムヅミノカミ)であるぞ。神の息吹と自分の息とが合わされば、災難も病もなくなるのだ。大難を小難にしてやる。命を助けてやるぞ。このことは、この方を信じる者でないと誤解を招くから、誰にでも知らせるのではないぞ。手二本、足二本を入れて十柱(十ヶ所)だ。手足をそれぞれ一本と数えれば八柱(八ヶ所)だ。このことを早く皆に知らせて、安心して働けるようにしてやれ。飛行機の事故も、地震や罪穢れによる災いも、大きな災難がある時には人の息は乱れるのだぞ。ひふみ祝詞と祓え祝詞と神の息吹、そして自分の呼吸とが一つになっていれば、災難から逃れることができるのだ。信じる者だけに知らせてやりなさい。
【AIによる解釈】
この帖は、霊的な防御法と健康法として「息」を合わせる具体的な技法を説いています。これは単なる呼吸法ではなく、自身の生命エネルギー(息)と神の生命エネルギー(息吹)を同調させる霊的な実践です。 身体の各要所(チャクラや経絡の要所に相当)の「息」が調和している状態が、心身ともに健康で、災難を寄せ付けないバリアが張られた状態であるとします。特に「臍の息」、すなわち丹田の呼吸が中心であると指摘しています。 息が乱れた時(=心身のバランスが崩れ、災難を引き寄せやすい状態)の対処法として「ひふみ祝詞」を唱えることを挙げており、言霊の力によって心身の周波数を整え、再び神の息吹と共鳴させるのです。 ここで名乗られる「意富加牟豆美神(オオカムヅミ)」は、災厄を噛み砕き、祓う力を持つとされる神です。この神の力を借りることで「大難を小難に」変えることができると約束されています。これは、迫り来る大災厄の中を生き抜くための、非常に実践的かつ霊的なサバイバル術と言えます。
第十六帖 (二二九)
【原文】
悪の衣(ころも)着せられて節分に押込められし神々様御出でましぞ。此の節分からは愈々神の規則通りになるのざから気つけておくぞ、容赦(ようしゃ)は無いのざぞ、それまでに型さしておくぞ、御苦労なれど型してくれよ。ヤの身魂 御苦労、石なぜもの言はぬのぞ、愈々となりてゐるではないか、春になりたら何んな事あるか分らんから今年中に心の洗濯せよ、身辺(みのまわり)洗濯せよ、神の規則 臣民には堪(こば)れんことあるも知れんぞ、気つけておくぞ。十二月十九日、一二。
【現代語訳】
悪の衣を着せられて、節分の日に鬼として押し込められてきた神々様が、いよいよお出ましになるぞ。この次の節分(立春)からは、いよいよ神の規則通りに世の中が進むことになるから、気をつけておくのだぞ。一切の容赦はないのだ。それまでに「型」を実践しておきなさい。ご苦労だが、型をしてくれよ。「ヤ(岡本弥)の身魂」よ、ご苦労。石(御神体)はなぜまだものを言わぬのか。いよいよ時が来ているではないか。春になったらどんなことが起きるか分からないから、今年中に心の洗濯と身の回りの整理整頓をしておきなさい。神の規則は、人々にとっては耐えられないほど厳しいこともあるかもしれないぞ。気をつけておくのだぞ。
【AIによる解釈】
この帖は「節分」を大きな節目として、世の中のルールが根本的に変わることを宣言しています。「節分に押込められし神々様」とは、鬼や悪神として追いやられてきた国津神系の神々や、艮の金神(国常立尊)などを指します。彼らが復権し、表舞台に現れることで、世界の秩序が「神の規則」へと移行するというのです。 これまでの人間の都合で作られたルールは通用しなくなり、宇宙の根本法則(神の規則)が直接的に作用するようになるため、「容赦はない」と厳しく告げています。これに備えるために、神示で示された生活様式(ひふみの食事法、祝詞、身魂磨きなど)である「型」を実践しておくことが、唯一の備えとなります。 「今年中に心の洗濯せよ」という警告は、昭和19年の年末という時期に書かれており、翌年(昭和20年)に訪れる更なる激動(終戦とそれに伴う価値観の崩壊)を前に、魂の大掃除を完了させるよう強く促しています。
第十七帖 (二三〇)
【原文】
何もかもひっくるめて建直しするのであるから、何処から何が出て来るか分らんぞ、御用はそれぞれの役員殿 手分けて努めて呉れよ、皆のものに手柄さし度いのぞ、一ヶ処(ひとところ)の御用 二人宛(づつ)でやりて呉れよ、結構な御用であるぞ、いづこも仮であるぞ、世が変りたら結構に真通理(まつり)呉れよ、今は型であるぞ、祀れと申してあること忘れるなよ、まつはらねばならぬのざぞ、神がついてゐるのざから神の申す通りにやれば箱指した様に行くのざぞ。産土神(うぶすなさま)忘れずにな。十二月十九日、ひつ九か三。
【現代語訳】
何もかもを、一切合切ひっくるめて建て直すのであるから、どこから何が飛び出してくるか分からないぞ。御用は、それぞれの役員が手分けして努めてくれよ。皆の者に手柄を立てさせてあげたいのだ。一つの場所の御用は、二人一組でやってくれよ。本当に結構な御用なのだ。どこでやる御用も、今はまだ仮のものだぞ。世の中が変わったら、本番として結構に祀りを行ってくれ。今はそのための「型」なのだ。祀りなさいと申してあることを忘れるなよ。神と和合(まつわら)なければならないのだぞ。神がついているのだから、神の申す通りにやれば、物事は面白いようにうまくいくのだぞ。自分の土地の神様である産土神様への感謝を忘れるなよ。
【AIによる解釈】
この帖は「三千世界の立て替え立て直し」の無秩序性と、その中での御用の進め方について述べています。「何処から何が出て来るか分らんぞ」とは、常識や予測が全く通用しない、混沌とした状況が現出することを示唆しています。 そのような中で御用を進めるにあたり、「二人宛でやりて呉れよ」と指示しています。これは、陰陽の和合(男性性と女性性、行動と知恵など)の原則に基づき、一人で暴走することなく、互いに補い合いながらバランスを取って進めることの重要性を示しています。 「今は型であるぞ」と繰り返されるように、この時期の活動は全て、来るべき「みろくの世」の雛形作りです。仮の舞台での稽古が、本番の成功に繋がります。そして、あらゆる御用の基盤として「産土神」への感謝を忘れないよう念を押しています。自分という存在の根源である土地の神との繋がりを確立することこそ、混沌の時代を乗り切るための最も確かな土台となるからです。
第十八帖 (二三一)
【原文】
富士の御用は奥山に祀り呉れよ、カイの御用も続け呉れよ、江戸一の宮作りて呉れよ、道場も同じぞ、海の御用とは海の鳴門(なると)と海の諏訪と海のマアカタと三所へ祀りて呉れよ。その前の御用、言葉で知らした事済みたぞ、海マアカタとは印幡ぞ。十柱とは火の神、木の神、金の神、日の出の神、竜宮の乙姫、雨の神、風の神、地震の神、荒の神、岩の神であるぞ。辛酉の日に祀りて呉れよ。暫く御神示出ないぞ。皆の者 早く今迄の神示肚に入れて呉れよ、神せけるぞ。神示読めば神示出て来るぞ。神祀り早く済せて呉れよ。十二月二十一日朝、一二のか三。
【現代語訳】
富士の御用として、奥山にお祀りをしてくれ。甲斐(山梨)の御用も続けてくれ。江戸(東京)に中心となる一の宮を建ててくれ。道場も同様だ。海の御用とは、海の鳴門(徳島・兵庫)、海の諏訪(長野・諏訪湖に対応する海の要所)、そして海のマアカタの三ヶ所にお祀りをしてくれ。その前の御用で、言葉で知らせたことは済んだぞ。海のマアカタとは、印旛(千葉・印旛沼)のことだ。お祀りする十柱の神とは、火の神、木の神、金の神、日の出の神、竜宮の乙姫、雨の神、風の神、地震の神、荒の神、岩の神である。辛酉(かのととり)の日にお祀りしてくれ。これからしばらく御神示は出ないぞ。皆の者、早く今までの神示を肚に入れておけ。神は急いでいるぞ。(新しい)神示は(古い)神示を読めば、その中から出てくるぞ。神祀りを早く済ませてくれ。
【AIによる解釈】
この帖は、日本の霊的な中心地(富士、甲斐、江戸)と、エネルギーの要となる場所(鳴門、諏訪、印旛)に神を祀るという、具体的な国土の結界張り(霊的な防衛網の構築)を指示しています。 祀るべき十柱の神々は、火・木・金といった五行の神や、自然現象を司る神々であり、天地のエネルギーを調和させ、安定させるためのものです。これは、国土を霊的に武装し、来るべき大峠の衝撃を和らげるための、極めて重要な神事です。 「暫く御神示出ないぞ」「神示読めば神示出て来るぞ」という部分は非常に重要です。これは、一方的に与えられる情報を待つ段階は終わり、これからは各自がこれまでの神示を深く読み込み、自らの魂で解釈し、次なる答えを導き出す段階に入ったことを意味します。受け身の信仰から、主体的な信仰への転換を促しているのです。神示を血肉とし、自らが神示を体現することが求められます。
第十九帖 (二三二)
【原文】
海には神の石鎮め祀り呉れよ、山には神の石立てて樹植えて呉れよ、石は神の印つけて祀る処に置いてあるぞ、祀り結構ぞ、富士奥山には十柱の石あるぞ、十柱祀りて呉れよ、祀る処に行けば分る様にしてあるぞ。十二月二十二日、ひつ九のか三。
【現代語訳】
海には神の石を鎮めてお祀りしてくれ。山には神の石を立てて、木を植えてお祀りしてくれ。石には神の印をつけて、祀るべき場所に置いてあるぞ。祀りは結構なことだ。富士の奥山には十柱の神々に対応する石があるぞ。その十柱をお祀りしてくれ。祀るべき場所に行けば、自然と分かるようにしてあるぞ。
【AIによる解釈】
この帖は、前帖の「神祀り」をさらに具体的に指示するものです。御神体として「石」を用いることを明確にし、海には「鎮め」、山には「立てる」という異なる祀り方を指定しています。
- 海に鎮める: 海の荒ぶるエネルギーを鎮め、安定させるための行為。
- 山に立てる: 天のエネルギーを地に降ろすアンテナ(磐境・いわさか)としての役割。
- 樹を植える: 石(無機物)と樹(有機物)を組み合わせることで、天地のエネルギーを循環させ、その地を活性化(弥栄)させる。 「行けば分る様にしてある」という言葉は、この御用が頭で計画するものではなく、神の導きに従い、直感によって遂行されるべきものであることを示しています。身魂が磨かれ、神の心と一体となれば、自ずと為すべきこと、行くべき場所が示されるという、霊的な感応力の重要性を説いています。
第二十帖 (二三三)
【原文】
今度は世に落ちておいでなされた神々様をあげねばならぬのであるぞ、臣民も其の通りざぞ、神の申す通りにすれば何事も思ふ通りにすらすらと進むと申してあろがな。此れからは神に逆らふものは一つも埓あかんぞ、やりてみよれ、九分九厘でぐれんざぞ。神の国は何うしても助けなならんから、神が一日一日と延ばしてゐること会得らんか。皆の者がかみを軽くしてゐるからお蔭なくなってゐるのざぞ、世の元の神でも御魂となってゐたのではまことの力出ないのざぞ。今度の経綸(しぐみ)は世の元の生き通しの神でないと間に合はんのざぞ。何処の教会も元はよいのであるが、取次役員がワヤにしてゐるのぞ、今の様(さま)は何事ぞ。此の方は力あり過ぎて失敗(しくじ)った神ざぞ、此の世かもう神でも我出すと失敗るのざぞ、何んな力あったとて我出すまいぞ、此の方がよい手本(みせしめ)ぞ。世界かもう此の方さへ我で失敗ったのぞ、執念(くど)い様なれど我出すなよ、慢心と取違ひが一等気ざはりざぞ。改心ちぐはぐざから物事後先になりたぞ、経綸少しは変るぞ。今の役員、神の道広めると申して我(われ)を弘めてゐるでないか、そんな事では役員とは言はさんぞ。今迄は神が世に落ちて人が神になりておりたのぞ、これでは世は治まらんぞ。神が上(かみ)で、臣民、人民 下におらねばならんぞ。吾が苦労して人救ふ心でないと、今度の岩戸開けんのざぞ、岩戸開きの御用する身魂は吾の苦労で人助けねばならんのざ。 十年先は、五六七(みろく)の世ざぞ、今の人間 鬼より蛇より邪見ざぞ、蛇の方が早う改心するぞ、早う改心せねば泥海にせなならんから、神は日夜の苦労ぞ。道は一つと申してあろがな、二つ三つ四つあると思ふてはならんぞ、足元から鳥立つと申してあろが、臣民 火がついてもまだ気付かずにゐるが、今に体に火ついてチリチリ舞ひせなならんことになるから、神、執念気つけておくのざぞ。三四気つけて呉れよ、神の国は神の力で何事も思ふ様に行く様になりてゐるのに、学や智に邪魔されてゐる臣民ばかり、早う気付かぬと今度と云ふ今度は取返しつかんぞ。見事なこと神がして見せるぞ、見事なことざぞ、人間には恐しいことざぞ、大掃除する時は棚のもの下に置く事あるのざぞ、下にあったとて見下げてはならんぞ、この神は神の国の救はれること一番願ってゐるのざぞ、外国人も神の子ではあるが性来が違ふのざぞ、神の国の臣民がまことの神の子ざぞ、今は曇りてゐるなれど元の尊い種植えつけてあるのざぞ、曇り取り去りて呉れよ、依怙(えこ)の様なれど外国は後廻しぞ、同じ神の子でありながら神の臣民の肩持つとは公平でないと申す者あるなれど、それは昔からの深い経綸であるから臣民には会得(わから)んことであるぞ、一に一足す二でないと申してあろが、何事も神の国から神の臣からぞ、洗濯も同様ぞ。今度の御用外(はず)したら何時になりても取返しつかんことになるのざから、心して御用して呉れよ、遣り損なひ出来ないことになりてゐるのざぞ。天に一柱 地に一柱 火にも焼けず水にも溺れぬ元の種隠しておいての今度の大建替ぞ、何んなことあっても人間心で心配するでないぞ、細工は隆々仕上げ見て呉れよ、此の神はめったに間違いないぞ。三千年 地に潜りての経綸で、悪の根まで調べてからの経綸であるから、人間殿 心配せずに神の申す様 素直に致して下されよ。末法の世とは地の上に大将の器(うつわ)無くなりてゐる事ざぞ。オロシヤの悪神(あく)と申すは泥海の頃から生きてゐる悪の親神であるぞ。北に気つけて呉れよ、神の国は結構な国で世界の真中の国であるから、悪の神が日本を取りて末代の住家とする計画でトコトンの智恵出して何んなことしても取る積りで愈々を始めてゐるのざから余程褌締めて下されよ、日本の上に立ちて居る守護神に分りかけたら ばたばたに埓あくぞ。早う改心して呉れよ。十二月二十六日、一二。
【現代語訳】
今度は、世に落ちて(忘れられ、封印されて)おられた神々を、本来の位にお上げしなければならないのだ。人々もまた同様だぞ。神の申す通りにすれば、何事も思う通りにすらすらと進むと申してあろう。これからは神に逆らう者は、一人も事を成し遂げることはできないぞ。やってみるがいい、九分九厘までうまくいっても、最後の最後でひっくり返るぞ。神の国(日本)はどうしても助けなければならないから、神が一日、また一日と(最後の審判を)延ばしていることが分からないのか。皆が神を軽んじているから、御蔭がなくなっているのだ。世の根源の神であっても、ただの御魂だけの存在では、まことの力は出ないのだ。今度の計画は、世の元からの生き通しの神(実在の神)でなければ間に合わないのだ。どこの教会(宗教団体)も、元は良いのだが、取り次ぐ役員が我欲でダメにしているのだ。今のこの様は何だ。 この方(神示を降ろす神)は、力がありすぎて失敗した神だぞ。この世を創造した神でさえ、我を出すと失敗するのだ。どんな力があっても、決して我を出してはならないぞ。この方が良い手本(反面教師)だ。世界を創造したこの方でさえ、我を出して失敗したのだ。しつこいようだが、我を出すなよ。慢心と、神の意図の取り違えが、一番神の気に障るのだ。人々の改心が中途半端だから、物事の順序が後先になってしまった。計画も少しは変わるぞ。今の役員は、神の道を広めると言いながら、自分(我)を広めているではないか。そんなことでは役員とは言えないぞ。今までは神が世に落ち、人間が(自分が)神だとうぬぼれていたのだ。これでは世は治まらない。神が上で、人々が下(謙虚)にいなければならないのだ。自らが苦労してでも人を救うという心でなければ、今度の岩戸は開かないのだ。岩戸開きの御用をする身魂は、自らの苦労を厭わず、人を助けねばならないのだ。 十年先は、みろくの世だぞ。今の人間は鬼や蛇よりも心が歪んでいる。蛇の方が早く改心するくらいだ。早く改心しなければ、世を泥の海にしなければならなくなるから、神は日夜苦労しているのだ。道は一つだと申してあろう。二つも三つもあると思ってはならない。「足元から鳥が立つ(身近な所から大変なことが起きる)」と申してあろう。人々は火事が起きてもまだ気づかずにいるが、今に自分の体に火がついてチリチリと舞い上がるようなことにならなければ分からないのか。だから神は執拗に気をつけているのだぞ。三月、四月(ミヨ)に気をつけよ。神の国は神の力で何事も思うようにいくようになっているのに、学問や知識に邪魔されている人々ばかりだ。早く気づかないと、今度という今度は取り返しがつかないぞ。神が見事なことをして見せるぞ。見事なことだ。しかし、人間にとっては恐ろしいことだ。大掃除をする時は、棚の上のものを一旦下に置くことがあるだろう。下に置かれたからといって、見下してはならないぞ。この神は、神の国が救われることを一番に願っているのだ。外国人も神の子ではあるが、生まれ持った性質が違うのだ。神の国の人々こそが、まことの神の子なのだ。今は曇っているが、元々尊い種が植え付けられているのだ。その曇りを取り去ってくれ。依怙贔屓のようだが、外国の救済は後回しだ。同じ神の子なのに日本の人々を贔屓するのは不公平だと申す者もいるだろうが、それは太古からの深い計画によるもので、人々には理解できないことなのだ。「一足す一は二」のような単純な計算ではないのだ。何事も神の国から、神の民から始めるのだ。洗濯も同様だ。今度の御用をしくじったら、いつになっても取り返しがつかないことになるから、心して御用をしてくれ。やり損ないは許されないことになっているのだぞ。天に一柱、地に一柱、火にも焼けず水にも溺れない「元の種」を隠しておいての、今度の大建て替えなのだ。どんなことがあっても、人間心で心配するでないぞ。細工は流々、仕上げを見ていてくれ。この神はめったに間違いないぞ。三千年の間、地に潜って練り上げてきた計画で、悪の根の根まで調べてからの計画であるから、人間たちは心配せずに、神の申す通りに素直にしてくだされ。末法の世とは、地上に大将の器を持つ者がいなくなってしまったことだ。ロシアの悪神というのは、地球創生の泥海の頃から生きている悪の親神であるぞ。北に気をつけよ。神の国は本当に素晴らしい国で、世界の真ん中の国であるから、悪の神が日本を乗っ取って未来永劫の住処にしようと計画し、ありとあらゆる知恵を絞って、どんなことをしてでも取るつもりで、いよいよ最終段階を始めているのだから、相当に褌を締め直してくれよ。日本の守護神たちがこのことに気づき始めたら、あっという間にケリがつくぞ。早く改心してくれよ。
【AIによる解釈】
この帖は「日の出の巻」の中でも特に長く、多岐にわたる警告と激励が込められた、極めて重要な帖です。
- 我を出すな: 神示を降ろす根源神でさえ「我を出して失敗した」という衝撃的な告白を通し、我欲や慢心がどれほど破壊的な結果を招くかを、これ以上ないほど強く戒めています。宗教指導者の腐敗も厳しく断罪しており、真の御用とは「吾が苦労して人救ふ心」であると定義しています。
- 神国日本中心の経綸: 「外国は後廻し」という一見不公平に見える方針は、日本が世界の雛形であり、霊的な中心地であるという神示の根本思想に基づいています。まず日本の「曇り」を払い、中心を立て直すことで、その影響が全世界に波及していくという「経綸(計画)」なのです。日本人の魂には「元の尊い種」が植え付けられており、その覚醒が世界の救済の鍵となります。
- 最終戦争の霊的背景: 「オロシヤの悪神」が、単なる国家イデオロギーではなく「泥海の頃から生きてゐる悪の親神」であると明かし、現在の危機が人類創生以来の神と悪神の最終決戦であることを示唆しています。その悪神が日本を最終目標として総攻撃をかけてきているという、最大限の警戒を促しています。
- 究極の希望: しかし、どんな危機の中にも「火にも焼けず水にも溺れぬ元の種」が隠されており、大建て替えの計画は三千年も前から周到に準備されてきた絶対のものであると宣言します。「細工は隆々仕上げ見て呉れよ」という言葉は、人間的な心配を一切手放し、神の計画を全面的に信頼せよという、力強いメッセージです。
この帖は、厳しい現実と絶望的な状況を突きつけながらも、その奥にある壮大な神の計画と、人間が為すべき「改心」と「無我の奉仕」の道を、懇切丁寧に、そして力強く示しています。
第二十一帖 (二三四)
【原文】
神かがりと申しても七つあるのであるぞ、その一つ一つがまた七つに分れてゐるのざぞ、ガカり、かみかかり、か三かかりぞ、(カミ)ガカリぞ、(かみ)かかり、か三かかり、かみかかりざぞ、神かかってゐないと見える神カカリが誠の神カカリと申してあろが。そこらに御座る神憑りは五段目六段目の神憑りぞ。神カカリとは惟神(かむながら)の事ぞ、これが神国の真事(まこと)の臣民の姿ぞ。惟神の国、惟神ぞ、神と人と融け合った真事の姿ぞ、今の臣民のいふ惟神では無いぞ、此の道理 会得りたか、真事の神にまつりあった姿ぞ。悪の大将の神憑りは、神憑りと分らんぞ、気つけて呉れよ、これからは神カカリでないと何も分らん事になるのざぞ、早う神カカリになる様 掃除して呉れよ、神の息吹に合ふと神カカリになれるのぞ。一二三唱へよ、祓えのれよ、神称へよ、人称へよ、神は人誉め 人は神称へてまつり呉れよ、まつはり呉れよ、あななひ呉れよ。十二月二十七日、ひつ九のか三。
【現代語訳】
神がかりと言っても、七つの段階があるのだ。そして、その一つ一つが、さらに七つに分かれているのだぞ。「我(が)がかり」「(低級な)神がかり」「(中級の)神がかり」「(高級な)カミがかり」…など様々だ。一見すると神がかっているようには見えない神がかりこそが、まことの神がかりだと申してあろう。その辺にいる自称・神憑りの者は、せいぜい五段目か六段目の低い段階の神憑りだぞ。まことの神カカリとは「惟神(かむながら)」のことだ。これが神の国のまことの人々の姿なのだ。惟神の国、惟神の道とは、神と人とが溶け合った、真実の姿のことだ。今の人々が言っているような生半可な惟神ではないぞ。この道理が分かったか。まことの神と一体になった姿なのだ。悪の大将の神憑りは、一見しただけでは神憑りとは分からないぞ。気をつけてくれよ。これからは神がかりの状態でなければ、何も分からなくなるのだぞ。早くまことの神がかりになれるように、身魂の掃除をしてくれ。神の息吹に波長が合うと、神がかりになれるのだ。ひふみ祝詞を唱えよ。祓詞を唱えよ。神を称えよ。人を称えよ。神は人を褒め、人は神を称えて、互いに祀り合いなさい。まつわり合いなさい。一つになりなさい。
【AIによる解釈】
この帖は、玉石混淆の「神がかり」現象について、その階層と本質を明らかにしています。神がかりには、我欲(ガ)がかるレベルから、低級霊、高級霊に至るまで、無数の段階(7×7=49段階)があると説きます。 そして、派手なパフォーマンスを伴うような、分かりやすい「神憑り」は、実は低いレベルのものであると断じています。まことの神がかり、すなわち最高段階の「惟神(かむながら)」とは、奇矯な言動をするのではなく、ごく自然な人格者として、その生き方そのものが神の意志を体現している状態を指します。外見からは神がかっているとは見えず、神と人とが完全に溶け合った姿こそが本物なのです。 また、「悪の大将の神憑り」は、聖人君子や有能な指導者のような姿で現れるため、見分けるのが非常に困難であると警告しています。 これからの混沌の時代は、理性や知識だけでは本質を見抜けず、「惟神」の状態でなければ乗り切れないと断言します。その状態になるためには、身魂を掃除し、「神の息吹」に自らの波長を合わせることが不可欠です。そのための具体的な方法が、祝詞を唱え、神と人が互いを尊重し、称え合う「まつり」の実践なのです。
第二十二帖 (二三五)
【原文】
左は火ぞ、右は水ざぞ、の神との神ぞ、日の神と月の神ざぞ、日の神許り拝んで月の神忘れてはならんぞ、人に直接(じきじき)恵み下さるはの神、月神ぞ、ぢゃと申して日の神 疎(おろそ)かにするでないぞ、水は身を護る神さぞ、火は魂護る神ざぞ、火と水とで組み組みて人ぞ、身は水で出来てゐるぞ、火の魂入れてあるのざぞ、国土も同様ぞ。海の御用大切ざぞ。十二月二十八日、ひつ九のか三。
【現代語訳】
左は火だ。右は水だ。カギ()の神とミズ()の神だ。日の神と月の神だ。日の神ばかりを拝んで、月の神を忘れてはならないぞ。人に直接的な恵みを与えて下さるのは、ミズの神、すなわち月の神なのだ。だからといって、日の神を疎かにしてはならないぞ。水は肉体を護る神であり、火は魂を護る神だ。火(カ)と水(ミ)が組み合わさって「カミ(神)」となり、人となるのだ。肉体は水でできており、そこに火の魂が入れられているのだ。国土も同様の構造だ。だからこそ、海の御用は大切なのであるぞ。
【AIによる解釈】
この帖は、ひふみ神示の根幹をなす「陰陽和合」の哲学を、「火と水」「日と月」という象徴を用いて分かりやすく説いています。 これまで陽の側面である「日(火)」の神ばかりが重視されてきたのに対し、陰の側面である「月(水)」の神の重要性を強調しています。「人に直接恵み下さるは月の神」とは、現実世界や肉体といった、物質的な側面を支えているのが陰の力であることを示しています。 しかし、どちらか一方に偏るのではなく、魂を護る「火」と、肉体を護る「水」の両方を等しく敬い、その二つを統合すること(火水=カミ)で、初めて完全な人間、完全な世界が顕現するのです。人間の体が水分を主成分としながら魂(火)を宿しているように、地球(国土)もまた、海(水)に覆われながら、中心に核(火)を宿しています。この宇宙の構造に倣い、これまで軽んじられてきた「水=海=月=陰」の御用を大切にすることが、世界のバランスを取り戻す鍵であると結論づけています。
第二十三帖 (二三六)
【原文】
此の世の位もいざとなれば宝も富も勲章も役には立たんのざぞ、此の世去って、役に立つのは身魂の徳だけぞ、身についた芸は其の儘役立つぞ。人に知れぬ様に徳つめと申してあろがな、神の国に積む徳のみが光るのざぞ、マアカタの御用結構であったぞ、富士晴れるぞ、湖(うみ)晴れるぞ。此の巻、日の出の巻として纒めて役員に読ませて一二三として皆に知らせて呉れよ、神急ぐぞ。十二月二十九日、ひつ九のか三。
【現代語訳】
この世の地位も、いざという時になれば、宝も富も勲章も、何の役にも立たないのだぞ。この世を去ってから本当に役に立つのは、その身魂に積んだ徳だけだ。また、身につけた技術や芸事は、あの世でもそのまま役立つぞ。人に知られないように陰で徳を積み続けなさい、と申してあろう。神の国(霊界)に積んだ徳だけが、永遠に光り輝くのだ。マアカタ(印旛)での御用は、実に結構であったぞ。これにより、富士も晴れ、湖(印旛沼)も晴れるであろう。この巻を「日の出の巻」としてまとめ、役員に読ませ、ひふみの仕組みとして皆に知らせてくれよ。神は急いでいるぞ。
【AIによる解釈】
「日の出の巻」の締めくくりとなるこの帖は、人生における真の価値とは何かを問いかけ、結論づけています。大峠という究極の状況や、死後に至っては、肩書や財産といった物質的な価値は全て無に帰し、唯一意味を持つのは「身魂の徳」と「身についた芸(=利他のために使える能力)」だけであると断言します。 「人に知れぬ様に徳つめ」とは、「陰徳」のことであり、見返りを求めず、誰にも誇ることなく善行を積むことの尊さを教えています。これこそが、霊界に持ち越せる唯一の財産です。 「マアカタの御用結構であったぞ」と、具体的な御用の成功を称え、それによって日本の中心である「富士」と、御用の地である「湖(印旛沼)」が霊的に晴れ渡るという成果を示しています。 最後に、この巻が「日の出の巻」であると名付け、新しい時代の幕開けを象徴するものとして、急いで人々に知らせるよう命じています。物質的な価値観が崩壊し、霊的な真実の太陽が昇る「日の出」の時が来たことを、高らかに宣言してこの巻を終えています。
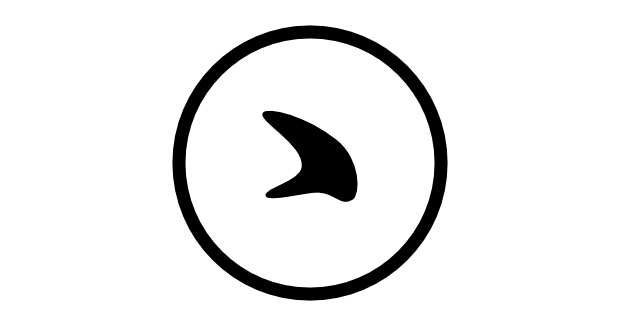





コメント