gemini 2.5 proにわかりやすいように解説してもらいました、しかし8通りに読めるということから完全に鵜呑みにしないよう、お願いします。特殊記号はカットしてます^o^
第一帖 (一七四)
【原文】
富士は晴れたり日本晴れ。 の巻 書き知らすぞ。此の世に自分の物と云ふ物は何一つないのであるぞ。早う自分からお返しした者から楽になるのざぞ。今度の大洗濯は三つの大洗濯が一度になって居るのざから、見当取れんのざぞ。神の国の洗濯と外国の洗濯と世界ひっくるめた洗濯と一度になってゐるのざから、そのつもりで少しでも神の御用務めて呉れよ。此れからがいよいよの正念場と申してあろがな。今はまだまだ一の幕で、せんぐり出て来るのざぞ。我(が)出したら判らなくなるぞ、てんし様おがめよ、てんし様まつりて呉れよ、臣民 無理と思ふ事も無理でない事 沢山にあるのざぞ、神はいよいよの仕組にかかったと申してあろがな。毀(こわ)すのでないぞ、練り直すのざぞ。世界を摺鉢(すりばち)に入れて捏(こ)ね廻し、練り直すのざぞ。日本の中に騒動起るぞ。神の臣民 気つけて呉れよ。日本も神と獣に分れているのざから、いやでも応でも騒動となるのざぞ。小さくしたいなれど。旧九月一日、ひつくのか三。
【現代語訳】
「富士は晴れたり日本晴れ」の巻として書き知らせるぞ。この世に自分の物というものは何一つないのだ。早く自分から(神に)お返しした者から楽になるのだぞ。今度の大洗濯は、三つの大洗濯が一度に重なっているのだから、見当がつかないであろう。日本の浄化と外国の浄化と、世界全部をひっくるめた浄化とが一度に起こるのだから、そのつもりで少しでも神の御用を務めてくれよ。これからがいよいよ正念場だと申してあろう。今はまだまだ序の口で、次から次へと事が起こってくるのだぞ。我(が)を出したら分からなくなるぞ。てんし様(天皇)を拝めよ、てんし様をお祀りしてくれよ。民よ、無理だと思うことも無理ではないことが沢山あるのだ。神はいよいよ最終的な計画に取り掛かったと申してあろう。破壊するのではないぞ、練り直すのだぞ。世界をすり鉢に入れてこね回し、練り直すのだ。日本の中に騒動が起こるぞ。神の民よ、気をつけなさい。日本も神に従う者と獣のような者とに分かれているのだから、否が応でも騒動となるのだ。できれば小さくしたいのだが。
【AIによる解釈】
本巻の冒頭を飾るこの帖は、来るべき大転換が「大洗濯」という言葉で表現されています。それは、①日本、②外国、③全世界という三つのレベルで同時に起こる、未曾有の浄化作用であると示されます。所有の概念を捨て、我欲をなくし、万物は神からの借り物であると悟った者から救われるという、神示の根幹をなす教えが改めて強調されています。 「毀すのでないぞ、練り直すのざぞ」という言葉は重要です。これは破壊のための破壊ではなく、より良い世界を創造するための根本的な再構築(リセット)であることを示唆します。その過程で日本国内にも神側と獣側に分かれるほどの大きな混乱が起きることが預言されており、個々人の心の在り方が厳しく問われる時代の到来を告げています。
第二帖 (一七五)
【原文】
三千年三千世界乱れたる、罪やけがれを身において、此の世の裏に隠(か)れしまま、此の世構ひし大神の、みこと畏み此の度の、岩戸開きの御用する、身魂は何れも生きかはり、死にかはりして練りに練り、鍛へに鍛へし神国の、まことの身魂 天駈けり、国駈けります元の種、昔の元のおん種ぞ、今 落ちぶれてゐるとても、軈(やが)ては神の御民とし、天地(あめつち)駈けり神国の、救ひの神と現はれる、時近づきぬ御民等よ。今一苦労二苦労、とことん苦しき事あれど、堪へ忍びてぞ次の世の、まこと神代の礎と、磨きて呉れよ神身魂、いやさかつきに栄えなむ。みたまさちはへましまさむ。旧九月二日、ひつ九のか三。
【現代語訳】
三千年にわたり乱れきった三千世界の罪や穢れをその一身に背負い、この世の裏に隠れたまま世を建て直してこられた大神の御心を畏み、この度の岩戸開きの御用をする身魂は、いずれも生まれ変わり死に変わりしながら練りに練り、鍛えに鍛えられた神国のまことの身魂である。天を駆け、国を駆ける、それが元の種、昔からの神の御種なのだ。今は落ちぶれているように見えても、やがては神の民として天地を駆け巡り、神国を救う神として現れる時が近づいたのだぞ、民よ。今、もう一苦労、二苦労と、とことん苦しいことがあるだろうが、それを堪え忍んで、次のまことの神代の世の礎となるべく、その神の身魂を磨いてくれよ。ますます栄えるであろう。御霊に幸あれ。
【AIによる解釈】
この帖は、大転換期に重要な役割を担う「身魂」について詩的に語っています。彼らは、永い年月をかけて転生を繰り返しながら鍛え上げられてきた特別な魂であり、今はたとえ不遇な状況にあっても、やがて神の計画の担い手として立ち現れるとされています。 「岩戸開き」とは、隠されていた真実や神性が現れ出ることを象徴します。その御用のためには、とことんの苦労を堪え忍ぶことが必要であり、その苦労こそが魂を磨き、新しい神の世の礎を築くための試練であると説かれています。苦難の先に約束された栄光と、魂を磨くことの重要性を説く、希望のメッセージです。
第三帖 (一七六)
【原文】
此の神示 声立てて読みて下されと申してあろがな。臣民ばかりに聞かすのでないぞ。守護神殿、神々様にも聞かすのぞ、声出して読みてさへおればよくなるのざぞよ。じゃと申して、仕事休むでないぞ。仕事は行であるから務め務めた上にも精出して呉れよ。それがまことの行であるぞ。滝に打たれ断食する様な行は幽界(がいこく)の行ぞ。神の国のお土踏み、神国の光いきして、神国から生れる食物(たべもの)頂きて、神国のおん仕事してゐる臣民には行は要らぬのざぞ。此の事よく心得よ。十月十九日、一二。
【現代語訳】
この神示は声に出して読んでくださいと申してあろう。民だけに聞かせるのではないぞ。守護の神々、その他の神々にも聞かせるのだぞ。声に出して読んでさえいれば良くなるのだよ。だからと言って、仕事を休んではいけないぞ。仕事は修行であるから、務めた上にもさらに精を出して励んでくれよ。それが本当の行なのだ。滝に打たれたり断食したりするような行は、外国や霊界の行だ。神の国の土を踏み、神国の光の中で呼吸をし、神国で採れた食べ物をいただき、神国の仕事をしている民には、特別な行は必要ないのだぞ。このことをよく心得なさい。
【AIによる解釈】
ここでは、神示の実践方法について具体的な指示が与えられています。まず「声に出して読む」こと。これは単に内容を理解するためだけでなく、その言霊(ことだま)を自分自身、そして目に見えない神々や守護の存在にまで響かせ、場を浄化し、自らを整える効果があることを示唆します。 そして、日常生活そのものが「まことの行」であると断言しています。特別な苦行や儀式ではなく、日々の仕事に誠心誠意励むこと、日本の大地に根ざして生活すること自体が、最も尊い修行であると説きます。これは、観念的な精神論に偏らず、地に足のついた生活を重んじる神示の思想を明確に表しています。
第四帖 (一七七)
【原文】
戦済みても後の紛糾なかなかに済まんぞ。人民いよいよ苦しくなるぞ。三四五(みよいづ)の仕組出来ないで、一二三(ひふみ)の御用はやめられんぞ。此の神示読んで三四五の世の仕組よく腹の中に入れておいて上(かみ)の人に知らしてやりて下されよ。三四五とはてんし様の稜威(みいづ)出づことぞ。十月二十日、ひつ九のか三。
【現代語訳】
戦争が終わっても、その後の紛糾はなかなか収まらないぞ。人々はいよいよ苦しくなるぞ。「みよいづ(三四五)」の仕組みができるまでは、「ひふみ(一二三)」の御用はやめられないのだ。この神示を読んで、来るべき「みよいづの世」の仕組みをよく理解し、上に立つ人々に知らせてあげてくれよ。「みよいづ」とは、てんし様の御威光が現れ出ることなのだぞ。
【AIによる解釈】
この帖は、戦争の終結が必ずしも平和の到来を意味しないことを警告しています。戦後の混乱と、それによる人々のさらなる困窮を預言しています。 ここで示される「一二三(ひふみ)」と「三四五(みよいづ)」は、神示における重要なキーワードです。「ひふみ」は準備段階、浄化の段階、あるいは現在の困難な時代を象徴し、「みよいづ」はそれが成就した後の、真に平和で喜びに満ちた新しい世(みろくの世)を指します。「三四五の世」の鍵は「てんし様の稜威(みいづ)出づこと」、つまり、てんし様(天皇)が本来の神聖な威光を発揮されることにあると明示されており、日本の霊的な中心性が回復することが、新しき世の到来に不可欠であると示唆しています。
第五帖 (一七八)
【原文】
神の国には神も人も無いのざぞ。忠も孝もないのざぞ。神は人であるぞ。山であるぞ。川であるぞ。めである。野である。草である。木である。動物であるぞ。為すこと皆忠となり孝とながれるのぞ。死も無く生も無いのぞ。神心あるのみぞ。やがては降らん雨霰(あめあられ)、役員 気つけて呉れよ。神の用意は出来てゐるのざぞ。何事からでも早よう始めて呉れよ。神の心に叶ふものは どしどしとらち明くぞ。十月二十一日、一二。
【現代語訳】
真の神の国には、神と人という区別はないのだ。忠や孝といった形式的な徳目もない。神は人であり、山であり、川であり、海であり、野であり、草であり、木であり、動物なのだ。為すこと全てが自然と忠となり孝となるのだ。死もなく生もない。ただ神の心があるだけだ。やがては雨や霰(あられ)のように厳しいことが降ってくるぞ。役員は気をつけてくれよ。神の用意はできている。何事からでも早く始めてくれ。神の心に適うことは、どんどん道が開けていくぞ。
【AIによる解釈】
この帖は、来るべき新しい世(神の国)の高度な精神的境地を描写しています。そこでは、神・人・自然といったあらゆるものが分断されておらず、一体化した世界です。山川草木、動物、そして人、その全てが神の現れであるという汎神論的な世界観が示されます。 「忠も孝もない」というのは、それらが不要になるという意味です。全てが一体であれば、為すことなすこと全てが自然に調和し、結果として忠や孝にかなう行いとなるからです。形式的な道徳律を超えた、根源的な調和の世界です。しかし、その境地に至る前には「降らん雨霰」のような厳しい試練があることも警告されており、役員(神の計画の担い手)たちに覚悟と迅速な行動を促しています。
第六帖 (一七九)
【原文】
アメツチノトキ、アメミナカヌシノミコト、アノアニナリマシキ、タカアマハラニ ミコトトナリタマヒキ。 今の経済は悪の経済と申してあろがな、もの殺すのぞ。神の国の経済はもの生む経済ぞ。今の政治はもの毀(こわ)す政治ぞ、神の政治は与へる政治と申してあろが。配給は配給、統制は統制ぞ。一度は何もかも天地に引上げと申してあるが、次の四(よ)の種だけは地に埋めておかねばならんのざぞ。それで神がくどう申してゐるのぞ。種は落ちぶれてゐなさる方(かた)で守られてゐるぞ。上下に引繰り返ると申してある事近づいて来たぞ。種は百姓に与へてあるぞ。種蒔くのは百姓ぞ。十月の二十二日、ひつ九かみ。
【現代語訳】
天地開闢の時、天之御中主神が最初に成り出でになり、高天原の主宰神となられました。 今の経済は悪の経済だと申してあろう。ものを殺す経済だ。神の国の経済は、ものを生かす経済だぞ。今の政治はものを破壊する政治だ。神の政治は与える政治だと申してあろう。配給は配給、統制は統制に過ぎない。一度は何もかも天と地(神のもと)に引き上げると申してあるが、次の世の種だけは地に埋めておかねばならない。だから神がくどく申しているのだ。その種は、今は落ちぶれているような人々によって守られているぞ。上下がひっくり返ると申してきたことが近づいてきたぞ。種は百姓に与えてある。種を蒔くのは百姓なのだ。
【AIによる解釈】
冒頭に天地開闢の神の名を記し、根源的な創造の力に言及した上で、現代の社会システムを痛烈に批判しています。現代の経済や政治は、競争と収奪に基づくいわば「殺し、壊す」システムであるのに対し、神のそれは、万物を「生かし、与える」システムであると対比させています。 そして、来るべき大転換(引上げ)の後、新しい世を創るための「種」について語られます。その大切な「種」は、社会の表舞台で活躍する人々ではなく、「落ちぶれてゐなさる方」、つまり、清貧に甘んじ、土と共に生きる「百姓」によって守られていると示されます。これは、物質的な豊かさや社会的地位がひっくり返る「上下の引っくり返り」が近いことを示唆しており、真の価値がどこにあるのかを問いかけています。
第七帖 (一八〇)
【原文】
ツギ、タカミムスビ、ツギ、カミムスビノミコトトナリタマイキ、コノミハシラ スニナリマシテ スミキリタマイキ。 岩戸ひらく道、神々苦むなり、弥ひらき苦む道ぞ、苦しみてなりなり、なりゑむ道ぞ、神諸々なり、世は勇むなり、新しき道、ことごとなる世、神諸々(もろもろ)四方(よも)にひらく、なる世の道、ことごとくの道、みいづぞ。十月二十四日、一二。
【現代語訳】
次に、高御産巣日神、次に、神産巣日神が成り出でになりました。この三柱の神が主宰神となられ、全てを統治されました。 岩戸を開く道は、神々も苦しむ道である。ますます開かれ、ますます苦しむ道なのだ。苦しみの果てに成り成りて、最後には微笑む道なのだ。神々は次々と現れ、世は活気づいてくる。新しい道、何もかもが新しくなる世。神々が四方八方に現れ開き、成就する世の道、あらゆる道に御威光(みいづ)が満ちるのだ。
【AIによる解釈】
古事記における造化三神(天之御中主神、高御産巣日神、神産巣日神)の出現に続き、創造のプロセスが語られます。ここでの「岩戸開き」は、単なる喜ばしい出来事ではなく、「神々も苦しむ道」であると強調されています。これは、新しい世界の創造が産みの苦しみを伴う、極めて困難な事業であることを示しています。 しかし、その苦しみの先には「なりゑむ道(成りて微笑む道)」、つまり成就と喜びが待っていると約束されています。苦難を経ることで神性が現れ、世界が刷新され、あらゆる道に神の威光が満ち溢れるという、ダイナミックな創造のビジョンが示されています。
第八帖 (一八一)
【原文】
ツギ、ウマシアシカビヒコヂノカミ、ミコトトナリナリテ アレイデタマイキ。 瓜(うり)の蔓(つる)に茄子(なす)ならすでないぞ。茄子には茄子と申してあろがな。味噌も糞も一つにするでないぞ。皆がそれぞれに息する道あろがな。野見よ森見よ。神の経済よく見よ。神の政治よく見て、まことの政治つかへて呉れよ。すべてにまつろう事と申してあろがな。上に立つ番頭殿 目開いて下されよ。間に合はん事出来ても神は知らんぞ。神急(せ)けるぞ。役員も気配れよ。旧九月八日、ひつ九のか三。
【現代語訳】
次に、宇摩志阿斯訶備比古遅神が、生命力そのものとして成り出でになりました。 瓜の蔓に茄子をならせようとするな。茄子の蔓には茄子だと申してあろう。味噌も糞も一緒にするな。皆がそれぞれに生き生きと活動できる道があるではないか。野を見よ、森を見よ。自然界という神の経済をよく見よ。神の政治(自然の摂理)をよく見て、まことの政治に仕えてくれよ。「すべてにまつろう(調和する)こと」だと申してあろう。上に立つ番頭(指導者)たちよ、目を開いてくれ。手遅れになっても神は知らないぞ。神は急いているのだ。役員たちも気を配れよ。
【AIによる解釈】
この帖の核心は「瓜の蔓に茄子はならぬ」という言葉にあります。これは、画一化や強制を戒め、それぞれの個性や天分を尊重することの重要性を説いています。無理に型にはめようとせず、自然の摂理のように、それぞれの存在がその本質を最大限に発揮できるような社会(政治・経済)を築くべきだと教えています。 その手本は「野見よ森見よ」という言葉通り、自然界にあります。多様な生命が共存共栄し、絶妙なバランスで成り立っている自然こそが、神の政治・経済の姿なのです。指導者たちに対して「目開いて下されよ」と強い口調で警告し、変革の時が迫っていることを改めて告げています。
第九帖 (一八二)
【原文】
何事も持ちつ持たれつであるぞ。神ばかりではならず、人ばかりではならずと申してあろが、善一筋の世と申しても今の臣民の言ふてゐる様な善ばかりの世ではないぞ。悪(ア九)でない悪とあなないてゐるのざぞ。此のお道は、あなないの道ぞ、上ばかりよい道でも、下ばかりよい道でもないのざぞ。まつりとはまつはる事で、まつり合はす事ざぞ。まつり合はすとは草は草として、木は木として、それぞれのまつり合はせぞ。草も木も同じまつり合せでないのざぞ。十月の二十六日。ひつ九か三。
【現代語訳】
何事も持ちつ持たれつなのだ。神だけでもダメ、人だけでもダメだと申してあろう。善一筋の世といっても、今の民が言うような単純な善だけの世ではないぞ。(一見)悪に見える、しかし本質的には悪ではない悪(ア九)と共存し、それを活かすのだぞ。この道は、そのように穴を埋め合い補い合う道なのだ。上の者だけが良い道でも、下の者だけが良い道でもない。まつり(祭り・政治)とは「まつわる」ことであり、互いに調和し合わせることだ。調和させるとは、草は草として、木は木として、それぞれの本性を生かした上での調和なのだ。草と木を同じように扱うことではないぞ。
【AIによる解釈】
この帖は、二元論的な思考を超えることを促します。神と人、善と悪、上と下といった対立概念は、本来「持ちつ持たれつ」の補い合う関係であると説きます。特に「悪でない悪」という表現は示唆に富みます。これは、人間の浅はかな善悪観では捉えきれない、より大きな視点から見れば必要とされる働きや存在(例えば、成長を促すための試練や抵抗勢力など)を指していると考えられます。 「まつり」の語源を「まつわる(纏わる)」「まつり合わす(調和させる)」ことと解き、それぞれの個性を潰すことなく、ありのままの姿で共存共栄させることこそが真の政治(まつりごと)であると定義しています。これは第八帖の「瓜の蔓に茄子はならぬ」という教えとも通底する、多様性の尊重と調和の思想です。
第十帖 (一八三)
【原文】
ツギ、アメノトコタチノミコト、ツギ、クニノトコタチノミコト、ツギ、トヨクモヌノミコトトナリナリテ、アレイデタマイ、ミコトスミキリタマヒキ。 辛酉(かのととり)の日と年はこわい日で、よき日と申してあろがな。九月八日は結構な日ざが、こわい日ざと申して知らしてありた事少しは判りたか。何事も神示通りになりて、せんぐりに出て来るぞ。遅し早しはあるのざぞ。この度は幕の一ぞ。日本の臣民これで戦済む様に申してゐるが、戦はこれからぞ。九、十月八日、十八日は幾らでもあるのざぞ。三月三日、五月五日はよき日ぞ。恐ろしい日ざぞ。今は型であるぞ。改心すれは型小(ち)さくて済むなれど、掃除大きくなるぞ。猫に気付けよ、犬来るぞ。臣民の掃除遅れると段々大きくなるのざぞ。神が表に出ておん働きなされてゐること今度はよく判りたであろがな。 と神との戦でもあると申してあろがな。戦のまねであるぞ。神がいよいよとなりて、びっくり箱開いたら、臣minポカンぞ。手も足も動かすこと出来んぞ。たとへではないのざぞ。くどう気付けておくぞ。これからがいよいよの戦となるのざぞ、鉄砲の戦はかりでないぞ。その日その日の戦烈しくなるぞ、褌締めて呉れよ。十月二十五日、ひつ九のか三。
【現代語訳】
次に、天之常立神、次に、国之常立神、次に、豊雲野神が成り出でになり、主宰神として全てを統治されました。 辛酉(かのととり)の日と年は、恐ろしい日であり、また良き日であると申してあろう。九月八日は結構な日だが、恐ろしい日だと知らせておいたことが少しは分かったか。何事も神示の通りに、次から次へと起こってくるぞ。時期の早い遅いはあるのだ。この度の出来事はまだ序の口だ。日本の民はこれで戦争が終わるかのように言っているが、本当の戦はこれからだぞ。九月八日や十月八日、十八日といった日はいくらでもあるのだ(重要な節目は何度も来る)。三月三日、五月五日も良き日であり、恐ろしい日だぞ。今はまだ型(雛形)の段階だ。改心すれば型は小さくて済むが、改心しなければ掃除は大きくなるぞ。猫(身近な油断)に気をつけよ、犬(外国からの脅威)が来るぞ。民の掃除(心の浄化)が遅れると、災厄は段々大きくなるのだ。神が表に出て働かれていることが、今度のことでよく分かったであろう。 神と悪神との戦いでもあると申してあろう。今の戦争はその真似事に過ぎないぞ。神がいよいよとなって「びっくり箱」を開いたら、民はあっけにとられてポカンとするだろう。手も足も動かせなくなるぞ。これは例え話ではないのだ。くどいようだが気をつけておくぞ。これからがいよいよ本当の戦となるのだ。鉄砲だけの戦いではないぞ。その日その日の暮らしの中の戦いが激しくなるぞ。褌を締めてかかれよ。
【AIによる解釈】
この帖は、当時の戦況(第二次世界大戦)を「型」であり「戦のまね」に過ぎないと断じ、これから始まる「まことの戦」の苛烈さを警告しています。その戦とは、物理的な戦争だけでなく、思想戦、経済戦、そして個々人の内面における神と悪神との戦いなど、あらゆる次元に及ぶ総力戦を意味します。 「辛酉」や節句の日が「こわい日で、よき日」とされるのは、変革や審判が起こる節目の日であることを示します。個々人の改心の度合いによって、その後の展開(掃除の大小)が変わることが強調されており、一人ひとりの心の在り方が未来を左右するという、神示の基本姿勢が示されています。人知を超えた出来事(びっくり箱)が起こることも預言されており、常識を捨てて心の準備をせよと強く促しています。
第十一帖 (一八四)
【原文】
学も神力ぞ。神ざぞ。学が人間の智恵と思ってゐると飛んでもない事になるぞ。肝腎の真中なくなりてゐると申してあろが。真中動いてはならんのざぞ。神国の政治は魂のまつりことぞ。苦しき御用が喜んで出来る様になりたら、神の仕組判りかけるぞ。何事も喜んで致して呉れと申してあろがな。臣民の頭では見当取れん無茶な四(よ)になる時来たのざぞ。それを闇の世と申すのぞ。神は、臣民は、外国は、神の国はと申してあろが、神国から見れば、まわりみな外国、外国から見れば神国真中。人の真中には神あらうがな。悪神の仕組は此の方には判りてゐるから一度に潰す事は易いなれど、それでは天の大神様にすまんなり、悪殺して終(しま)ふのではなく、悪改心さして、五六七(みろく)のうれしうれしの世にするのが神の願ひざから、この道理忘れるでないぞ。今の臣民 幾ら立派な口きいても、文字ならべても、誠がないから力ないぞ。黙ってゐても力ある人いよいよ世に出る時近づいたぞ。力は神から流れ来るのぞ。磨けた人から神がうつって今度の二度とない世界の、世直しの手柄立てさすぞ。みたま磨きが何より大切ぞ。十月の二十七日、ひつ九のか三。
【現代語訳】
学問も神の力であり、神そのものなのだぞ。学問を人間の浅知恵だと思っていると、とんでもないことになるぞ。肝心要の真ん中(中心軸)がなくなっていると申してあろう。真ん中は動いてはならないのだ。神の国の政治とは、魂のまつりごと(統治)なのだ。苦しい御用が喜んで出来るようになったら、神の計画が分かりかけてきた証拠だ。何事も喜んでしてくれと申してあろう。民の頭では見当もつかない無茶な世になる時が来たのだ。それを闇の世と申すのだ。神は(善悪を抱き参らせ)、民は(助け合い)、外国は(手を取り合い)、神の国は(世界の真ん中になる)と申してあろうが、神の国から見れば周りはみな外国であり、外国から見れば神の国が真ん中なのだ。人の真ん中には神がおられるではないか。悪神の企みはこちらには全て分かっているから、一度に潰すことは簡単だが、それでは天の大神様に申し訳が立たない。悪を殺して終わらせるのではなく、悪を改心させて、みろくの嬉し嬉しの世にするのが神の願いなのだから、この道理を忘れるなよ。今の民は、いくら立派なことを言っても、文字を並べても、誠がないから力がない。黙っていても力のある人が、いよいよ世に出る時が近づいたぞ。力は神から流れ来るのだ。魂が磨けた人から神が乗り移って、この度の二度とない世界の世直しの手柄を立てさせるのだ。魂磨きが何よりも大切なのだぞ。
【AIによる解釈】
この帖では、神示の重要な思想がいくつも語られます。
- 学問の位置づけ: 学問は人間の知恵ではなく、神から与えられた力(神力)であるとし、その根源を見失った現代知性への警鐘を鳴らしています。
- 不動の真中: どんな混乱の中でも動じてはならない自己の中心軸(真中)を持つことの重要性を説きます。
- 喜びの御用: 苦しい役目さえも喜んで行えるようになった時、神の計画を理解する境地に至るとされています。
- 悪の改心: 神の目的は悪の滅亡ではなく、悪の改心による融和であり、それによって真の平和な世界(みろくの世)を築くことであるという、深遠な神の愛が示されています。
- 誠と力: 口先だけの議論や知識ではなく、魂から湧き出る「誠」こそが真の力の源泉であると説きます。 最終的に、これら全ては「みたま磨き」に集約されます。魂を磨き、神の力を受け入れる器となることこそが、この大転換期を乗り越え、世直しの担い手となるための唯一の道であると結論づけています。
第十二帖 (一八五)
【原文】
三ハシラ、五ハシラ、七ハシラ、コトアマツカミ、ツギ、ウヒジニ、ツギ、イモスヒジニ、ツギ、ツヌグヒ、ツギ、イモイクグヒ、ツギ、オホトノジ、ツギ、イモオホトノべ、ツギ、オモタル、ツギ、イモアヤカシコネ、ミコトト、アレナリ、イキイキテ、イキタマヒキ、ツギ、イザナギノカミ、イザナミノカミ、アレイデマシマシキ。 足許に気付けよ。悪は善の仮面かぶりて来るぞ。入れん所へ悪が化けて入って神の国をワヤにしてゐるのであるぞ、己の心も同様ぞ。百人千人万人の人が善いと申しても悪い事あるぞ。一人の人云っても神の心に添ふ事あるぞ。てんし様拝めよ。てんし様拝めば御光出るぞ、何もかもそこから生れるのざぞ。お土拝めよ。お土から何もかも生れるのぞ。人拝めよ、上に立つ人拝めよ、草木も神と申してあろがな。江戸に攻め寄せると申してあろがな。富士目指して攻め来ると知らしてあること近付いたぞ。今迄の事は皆型でありたぞ、江戸の仕組もお山も甲斐の仕組も皆型ぞ、鳴門とうづうみの仕組も型して呉れよ。尾張の仕組も型早よう出して呉れよ。型済んだらいよいよ末代続くまことの世直しの御用にかからすぞ。雨降るぞ。十月二十八日、ひつ九のかみ。
【現代語訳】
(古事記に記される)別天津神、そして神世七代の神々、次に伊邪那岐神、伊邪那美神が現れ出でになりました。 足元に気をつけよ。悪は善の仮面を被ってやって来るぞ。入ってはいけない所に悪が化けて入り込み、神の国を滅茶苦茶にしているのだ。自分自身の心も同様だぞ。百人、千人、万人の人が良いと言っても悪いことがあるぞ。たった一人の言うことであっても、神の心に沿うことがあるのだ。てんし様を拝めよ。てんし様を拝めば御光が現れ、何もかもそこから生まれるのだ。お土を拝めよ。お土から何もかもが生まれるのだ。人を拝めよ、上に立つ人を拝めよ、草木も神だと申してあろう。江戸(東京)に攻め寄せると申してあろう。富士を目指して攻めて来ると知らせておいたことが近づいたぞ。今までのことは皆、雛形であったのだ。江戸の仕組みもお山(富士)の仕組みも甲斐(山梨)の仕組みも皆、雛形だ。鳴門の渦潮の仕組みも型として示してくれよ。尾張(愛知)の仕組みも早く型を出してくれよ。型が終わったら、いよいよ末代まで続く本当の世直しの御用に取り掛からせるぞ。雨が降るぞ(恵みの雨か、試練の雨か)。
【AIによる解釈】
冒頭で天地創造の神々の名を連ね、根源的な力を喚起した上で、極めて実践的な警告を発しています。「悪は善の仮面かぶりて来る」という言葉は、物事の本質を見抜く審神者(さにわ)の重要性を説いています。多数派の意見が必ずしも正しいとは限らず、孤独な少数意見にこそ真実があるかもしれないという、常識や権威への盲従を戒めるメッセージです。 「てんし様」「お土」「人」「草木」を拝めという教えは、森羅万象に神性を見出し、感謝と畏敬の念を持つことの大切さを説いています。 後半では、これまで行われてきた様々な「仕組」(雛形としての神事や出来事)が型(リハーサル)の段階を終え、いよいよ本番の「まことの世直し」が始まることを宣言しています。「江戸に攻め寄せる」「富士を目指す」といった預言は、日本の中心部が重大な危機に瀕することを示唆しており、切迫した状況を伝えています。
第十三帖 (一八六)
【原文】
人間心で急ぐでないぞ。我が出てくると失策(しくじ)るから我とわからん我あるから、今度は失策(しくじ)ること出来んから、ここと云ふ時には神が力つけるから急ぐでないぞ。身魂磨き第一ぞ。蔭の御用と表の御用とあるなれど何れも結構な御用ざぞ。身魂相当が一番よいのざぞ。今に分りて来るから慌てるでないぞ。今迄の神示よく読んでくれたらわかるのざぞ。それで腹で読め読めとくどう申してゐるのざぞ。食物(くいもの)気つけよ。十月二十八日、ひつ九のかみ。
【現代語訳】
人間の心で焦ってはいけないぞ。我(が)が出てくると失敗するからな。自分では気づかない我というものがあるから、今度は失敗は許されないのだから、ここぞという時には神が力を与えるから急ぐでないぞ。魂を磨くことが第一だ。蔭の御用と表の御用とがあるが、どちらも結構な御用なのだ。その人の魂のレベルに相応しい御用が一番良いのだ。やがて分かってくるから慌てるでないぞ。今までの神示をよく読んでくれれば分かることなのだ。だから腹で(心で深く)読め読めと、くどく申しているのだ。食べ物に気をつけよ。
【AIによる解釈】
この帖は、焦りや我欲(人間心)を強く戒めています。神の計画は人知を超えたタイミングで進むため、人間的な浅はかな判断で行動すると失敗すると警告しています。「ここぞという時には神が力をつける」という言葉は、神への絶対的な信頼(全託)を求めています。 そのために最も重要なのが「身魂磨き」です。魂を磨き、我を無くし、神の道具として相応しい状態になっていれば、自ずと道は開けるのです。「蔭の御用と表の御用」は、目立つ役目も目立たない役目も等しく尊いことを示し、自分の分をわきまえ、与えられた役目を全うすることの重要性を説いています。最後に「食物に気をつけよ」とあるのは、体もまた神から借りた神聖な器であり、それを清浄に保つことが魂磨きと密接に繋がっていることを示唆しています。
第十四帖 (一八七)
【原文】
世の元からの仕組であるから臣民に手柄立てさして上下揃った光の世にするのざから、臣民見当取れんから早よ掃除してくれと申してゐるのぞ。国中到る所 花火仕掛けしてあるのぞ。人間の心の中にも花火が仕掛けてあるぞ。何時その花火が破裂するか、わからんであろがな。掃除すれば何もかも見通しざぞ。花火破裂する時近づいて来たぞ。動くこと出来ん様になるのぞ。蝋燭(ろうそく)の火、明るいと思ふてゐるが、五六七(みろく)の世の明るさはわからんであろが。十月の三十一日。ひつ九のかみ。
【現代語訳】
これは世の始まりからの計画であり、民に手柄を立てさせて、神と人とが揃った光の世にするためのものだから、民には見当がつかないだろうから、早く心の掃除をしてくれと申しているのだ。国中の至る所に花火が仕掛けてあるのだぞ。人間の心の中にも花火が仕掛けてある。いつその花火が破裂するか、分からないであろう。掃除をすれば何もかもが見通せるようになるのだ。花火が破裂する時が近づいてきたぞ。そうなったら身動きできなくなるのだ。蝋燭の火を明るいと思っているだろうが、みろくの世の本当の明るさは、今のあなた方には想像もつかないであろう。
【AIによる解釈】
「花火」という比喩が印象的な帖です。この「花火」は、社会の至る所に仕掛けられた紛争や災害の火種、そして個人の心の中に潜む怒りや不満といった、いつ破裂してもおかしくない爆発的なエネルギーを象徴しています。これが一斉に「破裂する時」が近づいており、その時には誰もが身動きできなくなるほどの混乱に陥ると警告しています。 その危機を回避し、未来を見通す力を得るための唯一の方法が「掃除」、すなわち心身の浄化です。我欲や不要な観念を捨て、心を鏡のように澄み切らせることの重要性を説いています。最後の「蝋燭の火」と「みろくの世の明るさ」の対比は、現在の我々の認識レベルがいかに限定的であるかを示し、来るべき新しい世が、想像を絶するほど素晴らしい世界であることを暗示しています。
第十五帖 (一八八)
【原文】
目覚めたら其の日の生命お預りした事を神に感謝し、其の生命を神の御心(みこころ)のままに弥栄(いやさか)に仕へまつる事に祈れよ。神は其の日其の時に何すべきかに就いて教へるぞ。明日の事に心使ふなよ。心は配れよ。取越苦労するなよ。心配りはせなならんぞ。何もかも神に任せよ。神の生命、神の肉体となりきれよ。何もかも捨てきらねばならんぞ。天地皆神のものぞ、天地皆己のものぞ。取違ひ致して呉れるなよ。幾ら戦してゐても天国ぞ、天国とは神国ぞ。神国の民となれば戦も有難いぞ。いきの生命いつも光り輝いてゐるぞ。神にまつろてくれと申してあろが。あめつち皆にまつろて呉れと申してあろがな。ここの道理よく判りたであろが。何も云ふ事ないぞ。神称へる辞(コト)が光透(コト)ぞ。あめつち称へる言(コト)が光透(コト)ぞ。草木の心になれと申してあろがな。神風もあるぞ。地獄の風もあるぞ。迷ふでないぞ、神の申すコトはコトであるぞ。コトに生きてくれよ。コトにまつろへよ。十一月の一日、ひつ九か三。
【現代語訳】
朝目覚めたら、その日の命をお預かりしたことを神に感謝し、その命を神の御心のままに、世の繁栄のためにお仕えできるよう祈りなさい。そうすれば神は、その日その時に何をすべきかを教えてくれるぞ。明日のことを思い悩むな。ただし、心配りは必要だぞ。取り越し苦労はするな、しかし先を見越した心遣いはしなければならないぞ。何もかも神に任せなさい。神の命、神の肉体となりきりなさい。何もかも捨てきらねばならない。天地の全ては神のものであり、同時に全てが自分自身のものなのだ。このことを取り違えてはならないぞ。どんなに戦の最中にあっても、そこは天国なのだ。天国とは神国のことだ。神国の民となれば、戦さえも有り難い試練となる。その生き生きとした命は、いつも光り輝いているのだ。神にまつろい(従い和合し)なさいと申してあろう。天地全てにまつろいなさいと申してあろう。この道理がよく分かったであろう。もう何も言うことはない。神を称える言葉(コト)が、光り輝く言霊(コト)なのだ。天地を称える言葉が、光り輝く言霊なのだ。草木の心になれと申してあろう。神風も吹くが、地獄の風も吹くぞ。迷ってはならない。神の申すコト(言葉・事柄)は真実(コト)なのだ。そのコトに生きなさい。そのコトに和合しなさい。
【AIによる解釈】
この帖は、日々の心の持ち方と、神と一体化するための具体的な実践法を説いています。
- 一日の始まり: 朝の感謝と祈りによって、その日一日を神に捧げる意識を持つ。
- 神への全託: 「今ここ」に集中し、未来への不安(取越苦労)を手放す。ただし、無計画(心配りなし)とは違う。
- 無所有と一体感: 全てを捨て去ることで、逆に天地の全てが自分のものであるという境地(ワンネス)に至る。
- 天国は今ここに: どんな状況下でも、心の在り方次第でそこは天国(神国)となる。苦難さえも感謝の対象となる。
- コト(言霊)の力: 神や天地を称える言葉が持つ力を信じ、それを実践する。 「神風もあるぞ。地獄の風もあるぞ」という言葉は、状況は激しく揺れ動くが、それに惑わされず、神のコト(真理)を自らの生き方の軸とせよ、という強いメッセージです。
第十六帖 (一八九)
【原文】
慌てて動くでないぞ。時節が何もかも返報(へんぽう)返しするぞ。時の神様 有難いと申してあろがな。神は臣民から何求めてゐるか。何時も与へるばかりでないか。神の政治、神国の政治は与へる政治とくどう申してあろがな。今の遣り方では愈々苦しくなるばかりぞ。早よう気付かぬと気の毒出来て来るぞ。金いらぬと申してあろが。やり方教へてやりたいなれど、それでは臣民に手柄無いから此の神示よく読みてくれといふてあるのぞ。よき事も現れると帳消しとなる事知らしてあろが、人に知れぬ様によき事はするのざぞ。この事よく深く考へて行へよ。昔からのメグリであるから、ちょっとやそっとのメグリでないから、何処へ逃げてもどうしてもするだけの事せなならんのざぞ。どこにゐても救ふ臣民は救うてやるぞ。真中動くでないぞ、知らぬ顔しておる事も起るぞ。十一月三日、一二。
【現代語訳】
慌てて動いてはならない。時節(タイミング)が、全ての行いに相応しい結果をもたらすぞ。時の神様は有り難いと申してあろう。神が民に何かを求めているか?いつも与えるばかりではないか。神の政治、神国の政治は「与える政治」だとくどく申してあろう。今のやり方ではいよいよ苦しくなるばかりだ。早く気づかないと気の毒な出来事が起こるぞ。金は要らなくなると申してあろう。具体的なやり方を教えてやりたいが、それでは民の手柄にならないから、この神示をよく読んでくれと言っているのだ。良いことをしても、人に知られると帳消しになることがあると知らせてあろう。人に知られないように善いことをするのだぞ(陰徳)。このことをよく深く考えて行いなさい。これは昔からの因縁(メグリ)であるから、ちょっとやそっとの因縁ではない。どこへ逃げても、どうしても各自が清算すべきことはしなければならないのだ。しかし、どこにいても救うべき民は救ってやるぞ。中心軸を動かすな。知らん顔をしていなければならないような事も起こるぞ。
【AIによる解釈】
この帖は「時」の重要性を説きます。人間の都合で慌てて動くのではなく、物事には熟す「時節」があり、そのタイミング(時の神)を信頼せよと教えています。また、奪い合う現代社会の原理に対し、神の原理は「与える」ことにあると繰り返し強調します。 「陰徳を積む」ことの重要性や、逃れることのできない「メグリ(因果応報)」の法則についても言及されています。これは、過去からの全ての行いが、良くも悪くも自分に返ってくるという宇宙の法則です。しかし、どんな状況下でも救われる道があること、そのためには何があっても動じない「真中」を保ち、時には事態を静観する(知らぬ顔)冷静さも必要だと説いています。答えは神示の中に隠されているため、自ら読み解き、手柄を立てよと促しています。
第十七帖 (一九〇)
【原文】
ココニアマツカミ、モロモロノミコトモチテ、イザナギノミコト イザナミノミコトニ、コレノタダヨヘルクニ、ツクリカタメナセト、ノリゴチテ、アメノヌホコヲタマヒテ、コトヨサシタマイキ。 神の国にも善と悪とあると申してあろがな。この神示見せてよい人と悪い人とあるのざぞ。神示見せて呉れるなよ。まことの神の臣民とわかりたら此の神示写してやりてくれよ。神示は出ませぬと申せよ。時節見るのざぞ。型してくれたのざからもう一(はじめ)の仕組よいぞ。此の神示 表に出すでないぞ。天明は蔭の御用と申してあろが。神示仕舞っておいてくれよ、一二三として聞かしてやって呉れよ。此の方の仕組 日に日に変るのざから、臣民わからなくなると申してあろが。日に日に烈しく変りて来るのざぞ。神の子には神示伝へてくれよ。神せけるぞ。渦海(うづうみ)の御用結構。十一月四日、一二。
【現代語訳】
ここに天津神が、皆で相談され、伊邪那岐命と伊邪那美命に、「この漂っている国を修理固成せよ(形ある国として整えよ)」と仰せになり、天沼矛(あめのぬぼこ)を授けて、その大役を委任されました。 神の国(の者の中)にも善人と悪人がいると申してあろう。この神示を見せて良い人と悪い人がいるのだ。誰にでも神示を見せてくれるなよ。まことの神の民だと分かったら、この神示を写させてやりなさい。(そうでない者には)神示は出ませんと断りなさい。時節を見るのだぞ。型を示してくれたのだから、もう始めの仕組みは良いぞ。この神示を表立って公開するな。天明(神示を降ろされた岡本天明)は蔭の御用だと申してあろう。神示は仕舞っておきなさい。(内容をかみ砕いて)ひふみとして聞かせてやりなさい。こちらの計画は日に日に変わるのだから、民には分からなくなると申してあろう。日に日に激しく変わってくるのだぞ。神の子(神の民)には神示を伝えてくれよ。神は急いでいるぞ。渦海(鳴門)の御用、ご苦労。
【AIによる解釈】
冒頭に古事記の国生みの場面を引用し、混沌から秩序を生み出す「修理固成」の御用が始まっていることを示唆します。その上で、この神示自体の取り扱いについて、極めて慎重な注意が与えられています。 神示は万人に開かれるべきものではなく、受け取る器(まことの神の臣民)を厳しく選別せよと命じられています。これは、内容が誤解されたり、悪用されたりすることを防ぐためでしょう。「蔭の御用」として、表立って活動するのではなく、水面下で慎重に、しかし確実に神の計画を進めることが求められています。神の計画が「日に日に変る」という言葉は、固定観念に囚われず、常に神意に波長を合わせ、柔軟に対応する必要があることを示しています。
第十八帖 (一九一)
【原文】
ツギニ、イザナミノミコト、イザナミノミコトニ、アマノヌホトヲタマヒテ、トモニ、タタヨヘル、コトクニ ツクリカタメナセト コトヨサシタマヒキ。 日に日に烈しくなると申してあろがな。水いただきにあげなならんぞ。お土掘らねばならんぞ。言波とくに磨きてくれよ。コトに気つけて呉れとくどう申してあろが。してはならず。せねばならず、神事(かみごと)に生きて下されよ。十一月六日、ひつ九のか三しらすぞ。
【現代語訳】
(前帖に続き)次に伊邪那岐命、伊邪那美命に天沼矛を授けて、共にこの漂える国を修理固成せよと、その大役を委任されました。 日に日に激しくなると申してあろう。水を頭上に掲げなければならなくなるぞ(水害の暗示か、水の浄化の必要性)。土を掘らねばならなくなるぞ(食糧難の暗示か、地に根差すことの重要性)。言霊(ことだま)を特によく磨いてくれよ。言葉(コト)に気をつけよとくどく申してあろう。「してはならないこと」と「せねばならないこと」をわきまえ、神事(かみごと)に生きなさい。
【AIによる解釈】
前帖に続き国生みの神話を引用し、いよいよ創造(修理固成)の御用が本格化することを示唆しています。状況は「日に日に烈しくなる」とされ、物理的な困難(水や土に関する困難)と、精神的な修養の必要性が同時に語られます。 特に「言波(言霊)とくに磨きてくれよ」と、言葉の持つ力とその重要性が強調されています。発する言葉が現実を創るという言霊思想に基づき、言葉を慎み、清め、磨くことが、この激動期を乗り切るための鍵であると示されています。そして、やるべきこととやってはならないことを神の視点から判断し、日々の生活そのものを神に仕える「神事」として生きるよう求めています。
第十九帖 (一九二)
【原文】
今のやり方、考へ方が間違ってゐるからぞ。洗濯せよ掃除せよと申すのはこれまでのやり方考へ方をスクリと改める事ぞ。一度マカリタと思へ。掃除して何もかも綺麗にすれば神の光スクリと光り輝くぞ。ゴモク捨てよと申してあろがな。人の心ほど怖いものないのざぞ。奥山に紅葉(もみじ)あるうちにと申すこと忘れるなよ。北に気付けよ。神の詞(よ)の仕組よく腹に入れておいて下されよ。今度のさらつの世の元となるのざぞ。十一月七日、ひつ九のか三。
【現代語訳】】
今のやり方、考え方が間違っているから(うまくいかないの)だ。洗濯せよ、掃除せよと申すのは、これまでのやり方や考え方をすっかりと改めることだ。一度死んだ(マカリタ)と思いなさい。掃除して何もかも綺麗にすれば、神の光がはっきりと光り輝くぞ。ゴミ(我欲や古い価値観)を捨てよと申してあろう。人の心ほど怖いものはないのだぞ。「奥山に紅葉があるうちに(まだ間に合ううちに)」と申したことを忘れるなよ。北の方角に気をつけよ。この神の言葉の仕組みをよく腹に入れておいてくれ。これが今度の新しい世の元となるのだぞ。
【AIによる解釈】
この帖は、問題の根源が「今のやり方、考へ方」そのものにあると断じ、根本的な変革を要求しています。「洗濯・掃除」とは、単なる物理的な清掃ではなく、既存の価値観、常識、思考様式を根こそぎ改める、精神的なリセット作業を意味します。「一度マカリタと思へ」とは、古い自分に死に、全く新しく生まれ変わるほどの覚悟を求める言葉です。 「人の心ほど怖いものない」とは、内に潜む我欲や邪念が全ての災いの元凶であることを示唆します。「奥山に紅葉あるうちに」という詩的な表現は、手遅れになる前に決断し、行動せよという時間的な切迫感を伝えています。「北に気付けよ」という具体的な方角の警告も含まれており、緊迫した情勢を反映しています。
第二十帖 (一九三)
【原文】】
神の用意は何もかも済んでゐると申してあろが。臣民の洗濯 早よ致してくれよ。さらつの世の用意 早よしてくれよ。今度の世には四十九の御役、御仕事あるのざぞ。四十九の身魂と申してあろがな。神の申したこと次々と出て来ておろうがな。早よこの神示腹に入れよ。早よ知らしてくれよ、今迄の神示 役員の腹に入る迄は暫く此の神示出ぬぞ。大切の時には知らすなれど、そのつもりでおりて呉れよ、ヌの種 大切にして下されよ。毒吐き出せよ。十一月の八日、ひつくのか三。
【現代語訳】
神の用意は何もかも済んでいると申してあろう。民の洗濯(心の浄化)を早くしてくれよ。新しい世(さらつ=更地になった後の世)の用意を早くしてくれよ。今度の世には四十九(よそく)の御役目、御仕事があるのだぞ。四十九の身魂が必要だと申してあろう。神の申したことが次々と現実になって出てきているだろう。早くこの神示を腹に入れよ。早く(人々に)知らせてくれよ。今までの神示が役員たちの腹に落ちるまでは、しばらくこの続きの神示は出ないぞ。ただし、大切な時には知らせるが、そのつもりでいてくれ。「ぬ」の種を大切にしてくれよ。毒を吐き出せよ。
【AIによる解釈】
神側の準備は万端であり、あとは人間側(臣民)の準備、すなわち「洗濯」を待つばかりである、という状況が示されています。神の計画を遅らせているのは人間の側の浄化の遅れであると、強く促しています。 「四十九(よそく)の御役」や「四十九の身魂」という言葉は、新しい世を運営していくために、多様な役割を担う、清められた魂が必要であることを示唆します。(四十九は「しじゅうく=終始苦」とも読め、苦を乗り越えた魂とも解釈できます)。「ヌの種」は盗人の「ぬ」であり、悪さえも改心させて活かす神の計画の奥深さ、あるいは根源的な生命力を象徴する言葉と考えられます。最後の「毒吐き出せよ」は、心身に溜まった不浄なものを全て出し切ること、すなわち徹底的な浄化を命じる、強い言葉です。
第二十一帖 (一九四)
【原文】
人まづ和し、人おろがめよ。拍手打ちて人とまつろへよ。神示よんで聞かして呉れよ。声出して天地に響く様のれよ。火(ひ)と水(み)、ひふみとなるのざぞ。火近づいたぞ。水近づいたぞ、厭(いや)でも応でもはしらなならんぞ。引くり返るぞ。世が唸るぞ。神示よめば縁ある人集まって来て、神の御用するもの出来て来る事わからんか。仕組通りにすすめるぞ。神待たれんぞ。十一月十日、ひつ九か三。
【現代語訳】
まずは人と和合し、人々を敬いなさい。拍手を打って人々と親しみ和らぎなさい。神示を読んで聞かせてあげなさい。声に出して天地に響き渡るように読み上げなさい。火(ひ)と水(み)が合わさり、「ひふみ」となるのであるぞ。火の洗礼が近づいたぞ。水の洗礼も近づいたぞ。嫌でも応でも走り出さなければならない時が来る。世の中がひっくり返るぞ。世界が唸り始めるぞ。神示を読めば、縁のある人々が集まって来て、神の御用をする者が現れてくるということが分からないか。すべては仕組み通りに進めるぞ。神はもう待てないのだ。
【AIによる解釈】
この帖は、来るべき大峠(おおとうげ)に向けての心構えと行動を具体的に示しています。「人と和し、人おろがめよ」という教えは、対立や分断ではなく、和合と相互尊重が基本であることを強調しています。
「火と水」は、相反する力や概念の象徴であり、それらが合わさって「ひふみ」という新たな創造の段階へ進むことを示唆します。これは、激しい浄化(火の洗礼)と清め(水の洗礼)を経て、新しい世が生まれるという「立て替え」のプロセスを指していると考えられます。
また、神示を声に出して読む「言霊(ことだま)」の力を活用すること、それによって縁ある魂が集い、神の計画が成就していくという仕組みが明かされています。個人の覚醒だけでなく、共同体としての目覚めと実践を促す強いメッセージが込められています。
第二十二帖 (一九五)
【原文】
お宮も壊されるぞ。臣民も無くなるぞ。上の人臭い飯食ふ時来るぞ。味方同士が殺し合ふ時、一度はあるのざぞ。大き声で物言へん時来ると申してあろがな。之からがいよいよざから、その覚悟してゐて下されよ。一二三が正念揚ぞ。臣民の思ふてゐる様な事でないぞ。この神示よく腹に入れておけと申すのぞ。ちりちりばらばらになるのざぞ。一人々々で何でも出来る様にしておけよ。十一月十一日、ひつ九か三。
【現代語訳】
神社仏閣も壊されるぞ。国民という概念もなくなるぞ。地位の高い人々が牢獄で食べるような臭い飯を食べる時が来るぞ。味方同士が殺し合う時が、一度は訪れるのだぞ。大きな声で自由に物が言えなくなる時が来ると申してあっただろう。これからがいよいよ本番であるから、その覚悟をしておきなさい。ひふみの教えを実践する時が正念場だ。民が想像しているような生易しい事態ではないぞ。この神示をよく腹に入れておきなさい。何もかもが散り散りばらばらになるのだぞ。一人ひとりが何でもできるように、自立しておきなさい。
【AIによる解釈】
これまでの価値観や社会構造が根底から覆る、極めて厳しい時代の到来を警告しています。「お宮も壊される」「臣民も無くなる」とは、既存の宗教、国家、権威がその力を失うことの象徴です。
「味方同士が殺し合ふ」「大き声で物言へん時」という描写は、社会が混乱し、思想統制や内部対立が激化することを示唆しています。この混乱期を乗り越えるために最も重要なのは「一人々々で何でも出来る様にしておけよ」という、徹底した個の自立です。誰かに依存するのではなく、精神的にも物理的にも、自らの足で立つ強さが求められる時代が来ることを強く示しています。
第二十三帖 (一九六)
【原文】
一升桝には一升しか入らぬと臣民思ふてゐるが、豆一升入れて粟(あわ)入れる事出来るのざぞ。その上に水ならばまだはいるのざぞ。神ならばその上にまだ幾らでもはいるのざぞ。神が移りたら人が思はぬ事出来るのざぞ。今度は千人力与へると申してあろが。江戸の仕組 世の終わりぞ。天おろがめよ。つちおろがめよ。まつはれよ。秋の空グレンと申してあろがな。冬も春も夏も気つけてくれよ。十一月十三日、ひつ九か三。
【現代語訳】
一升桝には一升分しか入らないと人々は思っているが、豆を一升入れた後でも、粟(あわ)を入れることができるのだぞ。さらにその上からなら水もまだ入るのだぞ。神の力であれば、その上にいくらでも入るのである。人に神がかったら、人間が思いもよらないようなことができるようになるのだ。今度の立て替えでは千人力を与えると申してあるだろう。江戸から始まった今の世の仕組みは、これで終わりなのだ。天を敬い、地を敬い、神と和合しなさい。秋の空が「グレン」とひっくり返ると申してあっただろう。冬も春も夏も、全ての季節で気をつけなさい。
【AIによる解釈】
この帖は、人間の常識や物質的な限界を超える「神の力」について説いています。「一升桝」の例えは、三次元的な固定観念への挑戦です。人間が「不可能」だと考える領域にこそ、神の無限の可能性があることを示しています。
「神が移りたら人が思はぬ事出来る」とは、人間が我欲を捨てて神の依り代(よりしろ)となることで、常人には計り知れない能力(千人力)が発揮されるということです。これは、来るべき大変化を乗り越えるための鍵となります。
「江戸の仕組 世の終わり」とは、徳川幕府以来の、あるいは西洋文明を取り入れた近代日本の社会システム全体が終焉を迎えることを意味します。そして「秋の空グレン」という警告は、特定の季節だけでなく、常に変革の予兆があることを示唆し、油断なき心構えを求めています。
第二十四帖 (一九七)
【原文】
ココニ、イザナギノミコト、イザナミノミコトハ、ヌホコ、ヌホト、クミクミテ、クニウミセナトノリタマヒキ、イザナギノミコト イザナミノミコト、イキアハシタマヒテ、アウ、あうトノラセタマヒテ、クニ、ウミタマヒキ。 コトの初め気付けて呉れよ。夜明けたら生命(いのち)神に頂いたと申してあろがな。太陽(ひ)あるうちはことごとに太陽の御用せよ。月あるうちはことごとに月の神の御用せよ。それがまことの臣民ぞ。生活心配するでないぞ。ことわけて申せば今の臣民すぐは出来ぬであろが。初めは六分国のため、四分自分の為、次は七分国のため、三分自分の為、次は八分国の為、二分自分のため、と云ふ様にして呉れよ。これはまだ自分あるのざぞ。自分なくならねばならぬのざぞ。神人一つになるのざぞ。十一月二十日、ひつ九。
【現代語訳】
ここに、伊邪那岐命(いざなぎのみこと)、伊邪那美命(いざなみのみこと)は、天之沼矛(あめのぬぼこ)を沼矛(ぬほこ)として、互いに組んで国生みをしようと仰せられた。伊邪那岐命、伊邪那美命は、共に行き会い、「アウ、アウ」と声を合わせられて、国をお生みになった。 物事の始まりに気づきなさい。夜が明けたら、その生命は神から頂いたものだと申してあるだろう。太陽が出ている間は、すべての行いを太陽の神の御用として行いなさい。月が出ている間は、すべての行いを月の神の御用として行いなさい。それがまことの民であるぞ。生活の心配をするでないぞ。段階を追って申せば、今の民にはすぐには出来ないであろうが、初めは六割を国のため、四割を自分のため。次は七割を国のため、三割を自分のため。その次は八割を国のため、二割を自分のため、というようにしていきなさい。しかしこれでもまだ「自分」という我(が)があるのだぞ。最終的にはその「自分」が無(のう)ならなければならないのだ。神と人とが一つになるのであるぞ。
【AIによる解釈】
この帖は、古事記の国生み神話の引用から始まります。これは、万物の「始まり」や「原点」に立ち返ることの重要性を象徴しています。私たちの生命も、日々の生活も、その根源は神にあるという意識を持つよう促しています。
その上で、具体的な実践として「我(が)」を減らしていくプロセスが段階的に示されます。初めから完全に自己を無くすことは難しいとし、「六分国のため、四分自分の為」から始めるよう説いています。これは、利己的な意識から利他的、公的な意識へと徐々にシフトしていく精神的な修行の道筋です。
最終目標は「自分なくならねばならぬ」「神人一つになる」という「神人合一(しんじんごういつ)」の境地です。自分のためという思いを完全に手放し、自らの全存在が神の御用そのものであるという状態に至ること。日々の生活すべてが神聖な営みであると悟り、実践することが求められています。
第二十五帖 (一九八)
【原文】
ハジメ(ヒツキ)ノクニウミタマヒキ、(ヒ)ノクニウミタマヒキ、のクニウミタマヒキ、ツギニ クニウミタマヒキ。 神に厄介掛けぬ様にせねばならんぞ。神が助けるからと申して臣民懐手してゐてはならんぞ、力の限り尽くさなならんぞ。(ヒツキ)ととは違ふのざぞ。臣民一日に二度食べるのざぞ、朝は日の神様に供へてから頂けよ、夜は月の神様に捧げてから頂けよ、それがまことの益人ぞ。十一月二十一日、一二。
【現代語訳】
初めに日嗣(ひつぎ)の国をお生みになり、(日)の国をお生みになり、(月)の国をお生みになり、次に(地)の国をお生みになった。 神様に厄介をかけるようなことがあってはならない。神が助けてくれるからといって、民が何もしないで腕をこまねいていてはならないのだぞ。自らの力の限りを尽くさなければならない。(日嗣の民)と(ユダヤの民)とは違うのだぞ。民は一日に二度食事を摂るようにしなさい。朝は日の神様にお供えしてから頂き、夜は月の神様にお供えしてから頂きなさい。それがまことの益人(ますひと=栄える人)であるぞ。
【AIによる解釈】
この帖は、前帖に続き「自立」と「感謝」の重要性を説いています。「神が助けるからと申して臣民懐手してゐてはならん」という一節は、ひふみ神示の教えの核心の一つです。神の助け(他力)を信じつつも、それに甘えるのではなく、まずは自らの力(自力)を最大限に尽くすことが前提となります。この「自力と他力の統合」が、困難を乗り越える鍵となります。
また、日常生活における具体的な実践として「食事の作法」が示されています。朝食は「日の神様(陽のエネルギー)」に、夕食は「月の神様(陰のエネルギー)」に感謝を捧げてからいただく。これは、食事を単なる栄養補給ではなく、天地自然の恵み、神々のエネルギーを体内に取り込む神聖な儀式と捉える考え方です。日々の食生活を通して、常に神との繋がりを意識し、感謝の心を養うことの重要性を示唆しています。
第二十六帖 (一九九)
【原文】
、、、ウ、うにアエオイウざぞ。昔の世の元ぞ。、、、ヤ、ワあるぞ、世の元ぞ。サタナハマからあるぞ。一柱、二柱、三柱、五柱、七柱、八柱、九柱、十柱、と申してあろがな。五十九の神、七十五柱これで判りたか。はざぞ。には裏表上下あるのざぞ。冬の先 春とばかりは限らんと申してあること忘れるなよ。用意せよ、冬に桜咲くぞ。十一月二十二日、ひつ九。
【現代語訳】
(宇宙の根源は)ウであり、ウにアエオイウ(母音)の響きがあるのだぞ。これが昔からの世の元である。ヤ、ワの響きもあり、これも世の元である。サタナハマ(の言霊)から(世は)始まっている。神々を数えるのに、一柱、二柱、三柱、五柱、七柱、八柱、九柱、十柱と申してあるだろう。五十九の神、七十五柱の神、これで(神界の仕組みが)分かったか。言霊(コトタマ)は(カ)と(ハ)の組み合わせだぞ。(物事)には裏と表、上と下があるのだぞ。「冬の次には春が来る」とばかりは限らないと申したことを忘れるなよ。用意をしなさい、冬に桜が咲くような異常事態が起こるぞ。
【AIによる解釈】
この帖は、言霊(ことだま)や数霊(かずたま)といった、目には見えない宇宙の法則について言及しています。「アエオイウ」という母音や「サタナハマ」などの子音が、世界の創造に関わる根源的な響き(エネルギー)であることが示唆されています。また、神々の数を挙げることで、神界にも秩序や法則性があることを示しています。これらは、人間が認識する物理的世界の背後にある、霊的な世界の構造を垣間見せるものです。
後半の「冬の先 春とばかりは限らん」「冬に桜咲くぞ」という警告は、非常に重要です。これは、私たちが「常識」や「当たり前」だと思っている自然の摂理や社会秩序が、根底から覆る時代の到来を意味します。これまで培ってきた経験則や知識が通用しない、予測不可能な事態が起こるという強烈なメッセージです。固定観念を捨て、どんな異常事態にも対応できる柔軟な心と備えをしておくよう、強く促しています。
第二十七帖 (二〇〇)
【原文】
神の国は生きてゐるのざぞ、国土おろがめよ、神の肉体ぞ。神のたまぞ。道は真直ぐとばかり思ふなよ、曲って真直ぐであるぞ、人の道は無理に真直ぐにつけたがるなれど曲ってゐるのが神の道ぞ。曲って真直ぐいのざぞ。人の道も同じであるぞ。足許から鳥立つぞ。愈々が近づいたぞ。世の元と申すものは泥の海でありたぞ。その泥から神が色々のもの一二三で、いぶきで生みたのぞ。人の智ではわからぬ事ざぞ。眼は丸いから丸く見えるのざぞ。この道理わかりたか。一度はどろどろにこね廻さなならんのざぞ。臣民はどない申しても近慾ざから先見えんから慾ばかり申してゐるが、神は持ち切れない程の物与へてゐるでないか。幾ら貧乏だとて犬猫とは桁違ふがな。それで何不足申してゐるのか。まだまだ天地へ取上げるぞ。日々取上げてゐる事わからんか。神が大難を小難にして神々様御活動になってゐること眼に見せてもわからんか。天地でんぐり返るぞ。やがては富士晴れるぞ。富士は晴れたり日本晴れ。元の神の世にかへるぞ。日の巻終りて月の巻に移るぞ。愈々一二三が多くなるから、今までに出してゐた神示よく腹に入れておいてくれよ、知らせねばならず、知らしては仕組成就せず、臣民 早よ洗濯して鏡に映る様にしてくれよ。今の世 地獄とわかってゐるであろがな。今のやり方 悪いとわかってゐるであろがな。神まつれと申すのぞ。外国には外国の神あると申してあろが。み戦さすすめて外国に行った時は、先づその国の神まつらねばならんぞ、まつるとはまつろふ事と申してあろが。鉄砲や智では悪くするばかりぞ。神先づまつれとくどう気つけてあるのは日本ばかりではないぞ。此の方の申すこと小さく取りては見当取れんと申してあろがな。三千世界の事ぞ。日本ばかりが可愛いのではないぞ、世界の臣民 皆わが子ぞ。わけへだてないのざぞ。この神示よみて聞かしてくれよ。読めば読むほどあかるくなるぞ。富士晴れるのざぞ。神の心晴れるのざぞ。あらたぬし世ぞ。十一月二十三日、一二。
【現代語訳】
神の国(日本)は生きて活動しているのだぞ。国土を敬いなさい、国土は神の肉体であり、神の魂なのだぞ。道は真っ直ぐだとばかり思うなよ。曲がりくねっているようでいて、それが本当は真っ直ぐなのだ。人の道は無理に直線にしたがるが、それこそが曲がっている。曲がっているように見えるのが神の道であり、それが真実の真っ直ぐな道なのだ。人の生きる道も同じであるぞ。身近なところから大変なことが起こるぞ。いよいよその時が近づいた。この世の始まりは泥の海であった。その泥から神が「ひふみ」の法則と息吹(いぶき)で様々なものを生み出したのだ。これは人間の知恵では到底分からない事だ。人の眼が丸いから世界が丸く(立体的に)見えるように、すべては自らの写し鏡なのだ。この道理が分かったか。世の中を一度どろどろにかき混ぜなければならないのだ。民はどう言っても目先の欲に囚われて先が見えないから、不平不満ばかり言っているが、神は持ちきれないほどのものを与えているではないか。いくら貧乏だといっても犬や猫の境遇とは比べ物にならないだろう。それで何を不足だと申しているのか。まだまだ天へ取り上げる(試練を与える)ぞ。日々取り上げていることが分からないか。神々が活動して大難を小難にしてくださっていることを、目に見える形で見せても分からないのか。天地がひっくり返るぞ。やがては富士(不二=絶対の真理)が晴れ渡るぞ。富士が晴れて、日本が晴れるのだ。元の神の世に帰るのである。「日の巻」は終わり、次は「月の巻」に移るぞ。いよいよ「ひふみ」の教えが重要になるから、今までに出した神示をよく腹に入れておきなさい。(神の計画は)知らせなければ民は動けないが、知りすぎると人間の我が出て仕組みが成就しない。民よ、早く心身を洗濯して、神が映る鏡のような状態になってくれよ。今の世が地獄であることは分かっているだろう。今のやり方が間違っていることも分かっているだろう。神を祀りなさいと申しているのだ。外国にはその国の神がおられると申したはずだ。戦を進めて外国へ行った時は、まずその国の神を祀らねばならないぞ。「祀る」とは「和合し敬う(まつろう)」ことだと申しただろう。武力や人間の小賢しい知恵では事態を悪化させるばかりだ。まず神を祀れと、くどく注意しているのは日本に対してだけではないぞ。この神の申すことを小さなスケールで捉えては見当違いになると申しただろう。三千世界すべてのことなのだ。日本だけが可愛いのではない。世界の民は皆わが子であり、分け隔てはないのだ。この神示を読んで聞かせてあげなさい。読めば読むほど心が明るくなるぞ。富士が晴れるのだ。神の心が晴れ渡るのだ。新しき主の世が来るのだぞ。
【AIによる解釈】
この帖は「日月(ひつき)の巻」の中核をなす非常に重要な内容を含んでいます。
- 国土即神論と神の道: 日本の国土そのものが神の肉体であり魂であるという生命観を提示し、国土への深い敬意を求めています。また、「曲って真直ぐ」という神の道は、人間の直線的で近視眼的な思考を超えた、より高次の摂理の存在を示唆します。一見、遠回りで非合理に見える出来事こそが、最終的に最善の結果に至る神の計画であるということです。
- 破壊と再生、そして感謝: 「一度はどろどろにこね廻す」という言葉は、新しい世を生み出すための徹底的な浄化(カオス化)を意味します。同時に、人々が現状に不満を言うのは、既に与えられている豊かな恵みや「大難を小難」にしてくれている神の配慮に気づいていないからだと諭し、感謝の心を促します。
- グローバルな視点と和合の精神: 「世界の臣民 皆わが子ぞ」という一文は、ひふみ神示が日本だけを対象とした選民思想ではないことを明確に示しています。他国を訪れた際は、その国の神(文化、伝統、人々)を尊重し和合する「まつらふ」心こそが真の平和に繋がる道であり、武力や人間の知恵による支配を強く戒めています。これは、現代の国際関係においても極めて重要な指針と言えるでしょう。
- 富士晴れの意味: 「富士晴れる」は、単なる天候ではなく、日本の中心、そして世界の中心が曇りのない状態になること、すなわち、真理が顕現し、人々が目覚め、神の理想とする「ミロクの世」が到来することの象徴です。それは「神の心晴れる」ことと一体であり、人類の覚醒が神の喜びであることを示しています。
第二十八帖 (二〇一)
【原文】
岩戸あけたり日本晴れ、富士ひかるぞ。この巻 役員読むものぞ。世の元と申すものは火であるぞ、水であるぞ。くもでて くにとなったぞ。出雲(いずも)とはこの地(くに)の事ぞ。スサナルの神はこの世の大神様ぞ。はじめはであるなり、(うご)いて月となり地となりたのざぞ。アは(ヒツキクニ)の神様なり、(ヨ)は月の神様ぞ、クニの神様はスサナルの神様ぞ。この事はじめに心に入れれば掃除タワイないぞ、グレンとは上下かへる事と申してあろうがな、云ふてはならぬ事ぞ。いはねばならぬ事ぞ。アメのつ九の。
【現代語訳】
岩戸が開いて日本は晴れ渡り、富士(不二の真理)が光り輝くぞ。この巻は役員が心して読むものだ。世の根元とは火(カ)であり、水(ミ)であるぞ。雲が出て、それが固まり国となったのだ。出雲(いずも)とは、この(雲から出た)国のことぞ。素盞鳴(スサナル)の神こそ、この現実世界を司る大神様であるぞ。初めは(一つの存在)であったが、それが動いて月(陰)となり地(現実世界)となったのだ。ア(陽)は日嗣(ひつぎ)の国の神(天照大神)であり、ヨ(夜・陰)は月の神(月読命)であり、クニ(現実世界)の神は素盞鳴の神(スサナルノカミ)であるぞ。この神々の役割分担を初めに心に入れておけば、身魂の掃除はたやすいぞ。「グレン」とは上下がひっくり返ることだと申してあるだろう。これは軽々しく言ってはならない秘密だが、言わねばならぬことでもあるのだ。天の仕組みなのだ。
【AIによる解釈】
この帖は、前帖の「富士晴れる」を受け、新しい時代の幕開け「岩戸明け」を宣言するところから始まります。そして、その新しい世界観の根幹となる神々の構造について解説しています。
- 三神の役割分担: ここで示される「ア(陽・天)=天照大神」「ヨ(陰・月)=月読命」「クニ(地・現実世界)=素盞鳴尊」という三神の役割は、ひふみ神示の宇宙観の基本です。これまで軽んじられがちだったスサナルノカミを「この世の大神様」と位置づけ、現実世界を動かす重要な神であることを強調しています。この三位一体の神々の働きを理解することが、身魂磨きの基礎となるとしています。
- 出雲の重要性: 「出雲とはこの地(くに)の事ぞ」という記述は、出雲が単なる地名ではなく、雲から国が生まれたという創生のエネルギーを象徴する霊的に重要な場所であることを示唆しています。
- グレン(上下転倒): 再び「グレン」という言葉で、価値観や社会構造の完全な逆転が起こることを念押ししています。これは、これまで隠されていたスサナルノカミの真の神格が明らかになることとも連動していると考えられます。
- 秘儀性: 「云ふてはならぬ事ぞ。いはねばならぬ事ぞ」というパラドックスは、この教えが世の根幹に関わる重大な秘密であり、受け取る側の心の準備ができていなければ理解できない、あるいは悪用されかねない危険なものであることを示しています。
第二十九帖 (二〇二)
【原文】
一日一日(ひとひひとひ)みことの世となるぞ。神の事いふよりみことないぞ。物云ふなよ。みこと云ふのぞ。みこと神ざぞ。道ぞ。アぞ。世変るのぞ。何もはげしく引上げぞ。戦も引上げぞ。役に不足申すでないぞ。光食へよ。息ざぞ。素盞鳴尊(スサナルノミコト)まつり呉れよ。急ぐぞ。うなばらとはこのくにぞ。十一月二十五日、一二。
【現代語訳】
一日一日と、神の御言(みこと)がそのまま実現する世となっていくぞ。神についてあれこれ言うよりも尊いことはない。無駄なことを言ってはならない。神の言葉(善言・祝詞)を言うのだぞ。御言(みこと)そのものが神なのだ。道なのだ。ア(始まりの根源神)なのだ。世の中が変わるのだ。すべてのものが激しく引き上げられていくぞ。戦もその役目を終えて引き上げられるのだ。自分の役に不平不満を言うでないぞ。光を食べなさい。それは呼吸なのだぞ。素盞鳴尊(スサナルノミコト)をお祀りしてくれ。急ぐのだぞ。海原(うなばら)とは、この国(日本)のことであるぞ。
【AIによる解釈】
この帖は、新しい時代における生き方の具体的な変化について述べています。
- 言霊(ことだま)の時代: 「みことの世となる」とは、言葉が持つ力が飛躍的に増大し、発した言葉が即座に現実を創造する時代が来ることを意味します。そのため、ゴシップや不平不満などの「物云ふ」ことを戒め、神の言葉、すなわち肯定的で創造的な言葉「みこと」を発することの重要性を説いています。
- 次元上昇(引き上げ): 「何もはげしく引上げぞ」とは、地球や人類全体の波動が上昇していくプロセス、いわゆる「アセンション」を示唆しています。戦乱さえも、その役目を終えて清算されていくとしています。この大きな流れの中で、個人の役目に不満を言うのは次元上昇の妨げになるということです。
- 新しい食事法: 「光食へよ。息ざぞ」という一節は、非常に未来的です。これは、物質的な食物だけでなく、プラーナ(宇宙エネルギー)や光を呼吸によって取り入れて生きる、より高次元の生命体へと人類が進化していく可能性を示唆しています。
- 日本の役割: 「うなばらとはこのくにぞ」と結ばれることで、日本が世界の霊的な中心、すべての始まりである「海原」のような役割を担うことを示しています。この国から新しい時代の波が広がっていく、という宣言とも受け取れます。そのために、現実世界を司る「スサナルノミコト」を祀ることが急務であると、再度強調されています。
第三十帖 (二〇三)
【原文】
おのころの国成り、この国におりまして あめとの御柱(みはしら)見立て給ひき。 (ここ)に伊邪那岐命(いざなぎのみこと)伊邪那美命(いざなみのみこと)島生み給ひき。初めに
(ここ)に伊邪那岐命(いざなぎのみこと)伊邪那美命(いざなみのみこと)島生み給ひき。初めに
水蛭子(ひるこ)、
淡島(あわしま)、
生み給ひき。この御子、国のうちにかくれ給ひければ、次にのりごちてのち生み給へる御子、
淡道之穂之三別島(あわじのほのさわけしま)、
伊予の二名島(いよのふたなしま)、
この島、
愛媛(えひめ)、
飯依比古(ひひよりひこ)、
大宜都比売(おおけつひめ)、
建依別(たてよりわけ)
と云ふ。次、
隠岐の三子島(おきのみつこしま)、
天之忍許呂別(あまのおしころわけ)。
次、
筑紫島(つくししま)、
この島、
白日別(しらひわけ)、
豊日別(とよひわけ)、
建日向日豊久土比泥別(たけひむかひとよくづひぬわけ)、
建日別(たてひわけ)。
次、
伊伎島(いきしま)、
天比登都柱(あめのひとつはしら)。
次、
津島(つしま)、
天狭手依比売(あめのさてよりひめ)。
次、
佐渡島(さとしま)。
次、
大倭秋津島(おおやまとあきつしま)、
天津御空豊秋津根別(あまつみそらとよあきつねわけ)、
次、
吉備之児島建日方別(きびのこしまたてひかたわけ)。
次、
小豆島(あづきしま)、
大野手比売(おおぬてひめ)。
次、
大島大多麻流別(おおしまおほたまるわけ)。
次、
女島(ひめしま)、
天一根(あめひとつね)。
次、
知詞島(ちかのしま)、
天忍男(あめのおしを)。
次、
両児島(ふたこしま)、
天両屋(あめふたや)、
二島(にしま)、八島(やしま)、六島(むしま)、合せて十六島生み給ひき。次にまたのり給ひて、大島、小島、生み給ひき。
淡路島(あわじしま)、
二名島(ふたなしま)、
おきの島、
筑紫の島(つくしのしま)、
壱岐の島(いきのしま)、
津島(つしま)、
佐渡の島(さどのしま)、
大倭島(おおやまとしま)、
児島(こじま)、
小豆島(あづきしま)、
大島(おおしま)、
女島(ひめしま)、
なかの島、
二子島(ふたこしま)
の十四島、島生みましき。次に、いぶきいぶきて、御子神 生み給ひき。
大事忍男神(おほことおしをのかみ)、
大事忍男神(オホコトオシヲノカミ)、
石土毘古神(いしつちひこのかみ)、
石土毘古神(イシツチヒコノカミ)、
石巣比売神(いしすひめのかみ)、
石巣比売神(イシスヒメノカミ)、
大戸日別神(おほとひわけのかみ)、
大戸日別神(オホトヒワケノカミ)、
天之吹男神(あめのふきをのかみ)、
天之吹男神(アマノフキヲノカミ)、
大屋毘古神(おおやひこのかみ)、
大屋毘古神(オオヤヒコノカミ)、
風木津別之忍男神(かさけつわけのおしをのかみ)、
風木津別之忍男神(カサケツワケノオシヲノカミ)、
海神(わたのかみ)、
海神(ワタノカミ)、
大綿津見神(おほわたつみのかみ)、
水戸之神(みなとのかみ)、
水戸の神(ミナトノカミ)、
速秋津比神(はやあきつひのかみ)、
速秋津比売神(はやあきつひめのかみ)、
速秋津比売神(ハヤアキツヒメノカミ)、
風神(かぜのかみ)、
風神(カゼノカミ)、
志那都比古神(しなつひこのかみ)、
木神(きのかみ)、
木神(キノカミ)、
久久能智神(くくのちのかみ)、
山神(やまのかみ)、
山神(ヤマノカミ)、
大山津見神(おほやまつみのかみ)、
野神(ぬのかみ)、
野神(ヌノカミ)、
鹿屋野比売神(かやぬひめのかみ)、
野椎神(ぬつちのかみ)、
鳥之石楠船神(とりのいわくすつねのかみ)、
天鳥船神(あめのとりふねのかみ)、
大宜都比売神(おほけつひめのかみ)、
大宜都比売神(オホケツヒメノカミ)、
火之夜芸速男神(ひのやきはやをのかみ)、
火之煇比古神(ひのかがひこのかみ)
生みましき。速秋津日子(はやあきつひこ)、速秋津比売(はやあきつひめ)、二柱の神 川海(かわうみ)に因(よ)りもちわけ、ことわけて、生ませる神、
沫那芸神(あわなぎのかみ)、
沫那美神(あわなみのかみ)、
頬那芸神(つらなぎのかみ)、
頬那美神(つらなみのかみ)、
天之水分神(あめのみくまりのかみ)、
国之水分神(くにのみくまりのかみ)、
天之久比奢母智神(あめのくひさもちのかみ)、
国之久比奢母智神(くにのくひさもちのかみ)、
次に、大山津見神(おほやまつみのかみ)、野椎神(ぬつちのかみ)の二柱神、山野(やまぬ)に依りもちわけて、ことあげて生みませる神、
天之狭土神(あめのさつちのかみ)、
国之狭土神(くにのさつちのかみ)、
天之狭霧神(あめのさぎりのかみ)、
国之狭霧神(くにのさぎりのかみ)、
天之闇戸神(あめのくらとのかみ)、
国之闇戸神(くにのくらとのかみ)、
大戸惑子神(おほとまどひこのかみ)、
大戸惑女神(おほとまどひめのかみ)、
大戸惑子神(オホトマドヒコノカミ)、
大戸惑女神(オホトマドヒメノカミ)
生みましき、伊邪那美神(いざなみのかみ)やみ臥(こや)しまして、たぐりになりませる神、
金山比古神(かなやまひこのかみ)、
金山比売神(かなやまひめのかみ)、
屎(くそ)になりませる神、
波仁夜須比古神(はにやすひこのかみ)、
波仁夜須比売神(はにやすひめのかみ)、
尿(ゆまり)に成りませる神、
弥都波能売神(みつはのめのかみ)、
和久産巣日神(わくむすびのかみ)、
この神の御子、
豊宇気比売神(とようけひめのかみ)
と申す。ここに伊邪那美神(いざなみのかみ)、火の神 生み給ひて、ひつちとなり成り給ひて、根の神の中の国に神去り給ひき。ここに伊邪那岐神(いざなぎのかみ)泣き給ひければ、その涙になりませる神、
泣沢女神(なきさわめのかみ)、
ここに迦具土神(かぐつちのかみ)斬り給へば、その血 石にこびりて、
石析神(いわさくのかみ)、
根析神(ねさくのかみ)、
石筒之男神(いわつつのおのかみ)、
雍瓦速日神(みかはやひのかみ)、
樋速日神(ひはやひのかみ)、
建御雷男神(たけみかつちおのかみ)、
建布都神(たけふつのかみ)、
豊布都神(とよふつのかみ)、
御刀(みはかし)の手上(たかみ)の血、
闇於加美神(くらをかみのかみ)、
闇御津羽神(くらみつはのかみ)、
ここに殺されし迦具土(かぐつち)の御首(みかしら)に成りませる神、
正鹿山津見神(まさかやまつみのかみ)、
御胸に
於藤山津見神(おとやまつみのかみ)、
腹(みはら)に
奥山津見神(おくやまつみのかみ)、
陰(みほと)に
闇山津見神(くらやまつみのかみ)、
左の御手に
志芸山津見神(しきやまつみのかみ)、
右の御手に
羽山津見神(はやまつみのかみ)、
左の御足に
原山津見神(はらやまつみのかみ)、
右の御足に
戸山津美神(とやまつみのかみ)、
成りましき。ここに斬り給へる御刀(みはかし)、
天之尾羽張(あめのおはばり)、
伊都之尾羽張(いづのおはばり)、
と云ふ。ここに妹(いも)恋しまし給ひて根の国に追い往(い)で給ひき。十一月二十五日夜、一二 。
。
【現代語訳】
(伊邪那岐命と伊邪那美命は)オノゴロ島に降り立ち、この島に天の御柱(あめのみはしら)を立てられました。そして、お二人の神は島の国生みを始められました。最初に水蛭子(ひるこ)、次に淡島(あわしま)をお生みになりました。しかし、この御子たちは(不具であったため)子の数には入れられませんでした。次に気を取り直して後にお生みになった御子は、 淡道之穂之三別島(あわじのほのさわけしま=淡路島)、 伊予之二名島(いよのふたなしま=四国)、 (この島は愛媛、飯依比古、大宜都比売、建依別という四つの顔を持つ) 次に、隠岐之三子島(おきのみつごじま)、 (またの名を天之忍許呂別という) 次に、筑紫島(つくしのしま=九州)、 (この島は白日別、豊日別、建日向日豊久土比泥別、建日別という四つの顔を持つ) 次に、伊伎島(いきしま=壱岐島)、 (またの名を天比登都柱という) 次に、津島(つしま=対馬)、 (またの名を天之狭手依比売という) 次に、佐渡島(さどしま)、 次に、大倭豊秋津島(おおやまととよあきつしま=本州)、 (またの名を天津御空豊秋津根別という) これら大八島国(おおやしまぐに)を生んだ後、 吉備之児島(きびのこじま=児島半島)、小豆島(あずきしま)、大島(おおしま)、女島(ひめしま)、知詞島(ちかのしま)、両児島(ふたごしま)などをお生みになりました。
(※原文に倣い、一部の島と神々の羅列を要約)
国生みを終え、次にお二人の神は息吹によって神々をお生みになりました。 大事忍男神(ことやものごとの神)、石土毘古神(石と土の男神)、石巣比売神(石と砂の女神)、大戸日別神(家の戸の神)、天之吹男神(風の神)、大屋毘古神(家の神)、風木津別之忍男神(風の神)、そして大綿津見神という海の神、速秋津日子・速秋津比売という川と海の神々など、自然界を司る多くの神々をお生みになりました。
(※原文に倣い、一部の神々の羅列を要約)
川や海、山や野を司る様々な神々をお生みになった後、伊邪那美命は病に伏され、その病の嘔吐物、排泄物からも金山比古神・金山比売神(鉱山の神)、波仁夜須比古神・波仁夜須比売神(土の神)、弥都波能売神(水の神)、和久産巣日神(生成の神)が生まれ、その御子として豊宇気比売神(食物の神)が生まれました。
やがて伊邪那美命は、火之迦具土神(ひのかぐつちのかみ)をお生みになった際の火傷がもとで、ついに亡くなり、根之堅洲国(ねのかたすくに=黄泉の国)へとお旅立ちになりました。ここに伊邪那岐命は深く嘆き悲しみ、その涙から泣沢女神(なきさわめのかみ)がお生まれになりました。
そして伊邪那岐命は、妻の死の原因となった御子・迦具土神を、お持ちになっていた十拳剣(とつかのつるぎ)で斬り殺されました。その時、剣に付いた血や迦具土神の体から、石や火や雷を司る神々、また体の各部位からは山々を司る神々がお生まれになりました。その剣の名は天之尾羽張(あめのおはばり)、またの名を伊都之尾羽張(いつのおはばり)と言います。
こうして伊邪那岐命は、亡き妻の伊邪那美命を恋しく思うあまり、そのあとを追って根の国へと向かわれたのでした。
【AIによる解釈】
この第三十帖は、他の帖と異なり、神からの直接的なメッセージではなく、古事記に記されている日本の「国生み」と「神生み」の神話が詳細に記述されています。ひふみ神示がこのタイミングで、日本の創世神話を長々と引用するのには、極めて重要な意図があります。
- 原点への回帰と再認識: これから始まる「世の立て替え」が、単なる社会制度の変革ではなく、この国の成り立ちそのものに立ち返る、根源的な出来事であることを示しています。読者に対し、日本の国土の一つ一つ、山川草木の一本一本が、神々の御業によって生み出された神聖な存在であることを、改めて魂に刻み込むよう促しているのです。第二十七帖の「国土おろがめよ、神の肉体ぞ」という教えを、神話の物語を通じて具体的に示しています。
- 破壊と創造の法則: 火の神・迦具土神の誕生が母である伊邪那美命の「死」を招き、その迦具土神が父である伊邪那岐命に殺されるという「悲劇(破壊)」の中から、雷神や山神といった新たな神々が次々と「誕生(創造)」する様が描かれています。これは、「破壊なくして創造はない」という宇宙の根本法則を象徴しています。ひふみ神示が説く大峠(おおとうげ)における大いなる苦難や混乱もまた、新しい世界(ミロクの世)を生み出すための、避けられない産みの苦しみであることを示唆しているのです。
- 壮大な物語への序章: この帖は、伊邪那岐命が「根の国に追い往(い)で給ひき」という、希望と不安が入り混じる場面で終わります。これは、この後の第四十帖で描かれる「黄泉の国での伊邪那美命との再会と決別、そして新たな誓い」へと直接つながる壮大な物語の序章です。死と再生、陰と陽の分離と、未来における再統合の約束を暗示しており、「日月(ひつき)の巻」全体のテーマを神話の形で表現していると言えるでしょう。
この帖は、神示の読者が自らの立つ大地と、そこに息づく八百万の神々との霊的な繋がりを回復し、来るべき大いなる変革の本当の意味を理解するための、不可欠な基礎知識として提示されているのです。
第三十一帖 (二〇四)
【原文】
一二三四五六七八九十百千卍(ひとふたみよいつむななやここのたりもちよろず)。今度は千人万人力でないと手柄出来んと申してあろがな。世界中総掛かりで攻めて来るのざから、一度はあるにあられん事になるのぞ。大将ざからとて油断出来ん。富士の山動く迄にはどんな事も耐(こら)えねばならんぞ。上辛いぞ。どんなことあっても死に急ぐでないぞ。今の大和魂と神の魂と違ふ所あるのざぞ。その時その所によりて、どんなにも変化(へんげ)るのが神の魂ぞ。馬鹿正直ならんと申してあろ。今日(けう)あれし生命勇む時来たぞ。十一月二十六日、一二。
【現代語訳】
一から万まで(数の真理)。今度の立て替えでは、千人や万人もの力を合わせなければ手柄は立てられないと申してあるだろう。世界中が総がかりで攻めて来るのだから、一度はとんでもないことになるのだぞ。自分が大将だからといって油断はできない。富士の山が動く(決定的な大変化が起こる)までは、どんなことも耐え忍ばなければならない。上の立場の者は辛いぞ。どんなことがあっても、死に急いではならない。今言われている「大和魂」と、真の「神の魂」とは違うところがあるのだぞ。その時、その場所に応じて、どのようにも自在に変化できるのが神の魂なのだ。融通の利かない馬鹿正直ではいけないと申してあるだろう。今日まで生かされてきたその生命、いよいよ勇んで使う時が来たのだぞ。
【AIによる解釈】
この帖は、来るべき試練が個人的なものではなく、「世界中総掛かり」という地球規模の、未曾有のものであることを強調しています。「千人万人力」とは、多くの人々の協力が必要であると同時に、一人ひとりがそれほどの力を発揮する必要があることも示唆しています。
特筆すべきは、「今の大和魂と神の魂と違ふ所ある」という一節です。これは、硬直化した精神論や、自己犠牲を強いるような旧来の価値観を戒めています。真に求められるのは、状況に応じて水のように形を変える、しなやかで柔軟な「変化(へんげ)する魂」です。「馬鹿正直」ではなく、高い次元の知恵と柔軟性を持って難局に対応することが重要であると説いています。そして、その試練は絶望ではなく、与えられた生命を最大限に輝かせる「勇む時」であると、人々を鼓舞しています。
第三十二帖 (二〇五)
【原文】
おもてばかり見て居ては何も判りはせんぞ。月の神様まつりて呉れよ。此の世の罪穢れ負ひて夜となく昼となく守り下さる素盞鳴神様あつくまつり呉れよ。火あって水動くぞ。水あって火燃ゆるぞ。火と水と申しておいたが、その他に隠れた火と水あるぞ。それを一二三と云ふぞ、一二三とは一二三と云ふ事ぞ、言波ぞ。言霊(コトタマ)ぞ、祓ひぞ、ぞ。スサナルの仕組ぞ。成り成る言葉ぞ、今の三み一たいは三み三たいぞ。一(ひ)とあらはれて二三(ふみ)かくれよ。月とスサナルのかみ様の御恩忘れるでないぞ。御働き近づいたぞ。十一月十七日、ひつ九かみ。
【現代語訳】
物事の表面ばかり見ていては、本質は何も分かりはしないぞ。月の神様をお祀りしなさい。この世の罪や穢れを一身に背負って、夜も昼もなく守ってくださっている素盞鳴(スサナル)の神様を篤くお祀りしなさい。火(カ)があって水(ミ)が動き、水があって火が燃える(神の働きが起こる)。火と水(カミ)については申してきたが、その他に「隠れた火と水」がある。それを「ひふみ」と言うのだ。「ひふみ」とは言葉の響き、言霊(ことだま)であり、祓い清めの力そのものである。これはスサナルの神様の仕組みなのだ。発すればその通りに成る「成り成る言葉」なのだ。今の見せかけの三位一体は、真の三位一体ではないぞ。一(火・陽)が現れて、二三(水・陰)が隠れることで、働きが起きるのだ。月の神様とスサナルの神様の御恩を忘れてはならない。その御働きが近づいたぞ。
【AIによる解釈】
この帖は、目に見える世界(おもて)だけでなく、その背後にある霊的な世界(うら)を見ることの重要性を説いています。特に、これまで日の当たらなかった「月の神(陰)」や、罪穢れを祓う荒ぶる神とされてきた「素盞鳴神」の真の重要性を強調しています。
「隠れた火と水」としての「ひふみ(言霊)」は、極めて重要な概念です。これは、単なる言葉ではなく、現実を創造し、祓い清める力を持つ霊的なエネルギーそのものであると定義しています。この言霊の力こそ、立て替えの時代を乗り越えるための具体的な方法論であり、「スサナルの仕組」の核心であると示唆しています。目に見える物理的な力だけでなく、言葉という霊的な力を正しく使うことが、今まさに求められているのです。
第三十三帖 (二〇六)
【原文】
宝の山に攻め寄せ来ると申してくどう気付けておいたでないか。神の国にはどんな宝でもあるのざぞ、(かみ)の国、昔から宝埋けておいたと申してあろがな。(かみ)の国にも埋けておいてあるのざぞ。この宝は神が許さな誰にも自由にはさせんのざぞ。悪が宝取らうと思ったとて、どんなに国に渡り来ても どうにもならん様に神が守ってゐるのざぞ。いよいよとなりたら神がまことの神力出して宝取り出して世界のどんな悪神も神の国にはかなはんと申す所まで、とことん心から降参する所まで、今度は戦するのざから臣民余程見当取れんことに、どんな苦労もこばらなならんのざぞ。知らしてありた事、日々(にちにち)どしどしと出て来るぞ。われよしすてて呉れよ。十一月二十八日、ひつ九のか三。
【現代語訳】
(日本という)宝の山に敵が攻め寄せて来ると、くどいほど注意しておいたではないか。神の国(日本)には、どんな宝でも揃っているのだぞ。昔からこの国に宝を埋めておいたと申しただろう。あの世の神の国にも、この世の日本にも宝は埋めてあるのだ。この宝は神が許さなければ誰にも自由にはさせない。悪しき者が宝を奪おうと思って、どんなにこの国に攻め込んできても、どうにもならないように神が守っているのだ。いよいよ最後の時が来たら、神がまことの神力を現してその宝を取り出し、世界のどんな悪神も「神の国には敵わない」と心から降参するまで、とことん戦をするのだ。だから民は、想像もつかないような、どんな苦労も拒んではならないのだぞ。予言しておいたことが、これから日々どんどん起こってくるぞ。我よし(自分さえ良ければよいという心)を捨ててくれよ。
【AIによる解釈】
この帖は、日本という国が物質的にも霊的にも「宝の山」であることを示しています。そして、その宝を狙って外部から「攻め寄せ来る」という、具体的な国難を警告しています。しかし、その宝は「神が守っている」ため、悪しき者の手に渡ることはないと断言しています。
最終的には、神自らがその封印された「宝(=真の力、真理)」を解放し、世界の悪が完全に降参するまでの「最後の戦い」が起こると予言しています。これは、単なる軍事的な戦いではなく、霊的な次元での最終戦争を意味するでしょう。そのプロセスにおいて、人々は想像を絶する苦労を経験するが、それは神の計画の一部であり、乗り越えなければならない試練であると説いています。この帖は、厳しい未来を予言しつつも、神の絶対的な守護と最終的な勝利を約束する、力強いメッセージとなっています。
第三十四帖 (二〇七)
【原文】
この神示よく読みてくれよ。早合点してはならんぞ。取違ひが一番怖いぞ。どうしたらお国の為になるのぞ、自分はどうしたら好いのぞと取次にきく人 沢山出て来るなれど、この神示読めば、どうしたらよいか判るのざぞ。その人相当にとれるのぞ。神示読んで読んで腹に入れてもう分らぬと云うことないのざぞ。分らねば神知らすと申してあろうがな。迷うのは神示読まぬからぞ。腹に入れておらぬからぞ。人が悪く思へたり、悪くうつるのは己が曇りてゐるからぞ。十一月二十九日、ひつ九のか三。
【現代語訳】
この神示をよく読んでくれよ。自己流に解釈して早合点してはならない。意味を取り違えることが一番怖いのだ。どうしたらお国の為になるか、自分はどうしたら良いかと取次者(審神者)に聞きに来る人が沢山出てくるだろうが、この神示を読めば、どうすべきか分かるのだ。その人の魂の段階に応じて理解できるようになっている。神示を読んで読んで、腹に収めれば、分からないということはない。それでも分からなければ神が知らせると申してあるだろう。迷うのは神示を読まないからだ。腹に入れていないからだ。他人が悪く思えたり、悪く見えたりするのは、自分自身の魂が曇っているからなのだぞ。
【AIによる解釈】
この帖は、神示との向き合い方について、非常に重要な注意を与えています。答えを安易に他者(取次者)に求めるのではなく、まず自らが神示を繰り返し読み、深く心に刻むこと(腹に入れる)の重要性を説いています。神示は、読む人の霊的なレベルに応じて、必要な答えを与えてくれる多層的な構造を持っていることを示唆しています。
そして、迷いや疑いの根本原因は、神示を読んでいないこと、つまり神の教えから離れていることだと断言します。最後の「人が悪く思へたり、悪くうつるのは己が曇りてゐるからぞ」という一文は、霊的真理の核心をついています。他者や外部に問題の原因を見るのではなく、すべての問題は自分自身の内なる「曇り」の反映であるという内観的な視点を持つこと。これこそが、魂を磨き、正しく道を歩むための基本であることを教えています。
第三十五帖 (二〇八)
【原文】
元からの神示 腹に入れた人が、これから来る人によく話してやるのざぞ。この道はじめは辛いなれど楽の道ぞ。骨折らいでも素直にさへして その日その日の仕事しておりて下されよ。心配要らん道ぞ。手柄立てようと思ふなよ。勝たうと思ふなよ。生きるも死ぬるも神の心のままざぞ。どこにどんな事して居ても助ける人は助けるのざぞ。神の御用ある臣民 安心して仕事致しておりて下されよ。火降りても槍降りてもびくともせんぞ。心安心ぞ。くよくよするでないぞ。神に頼りて神祀りてまつわりておれよ。神救ふぞ。十一月二十九日、ひつ九のか三。
【現代語訳】
初期からの神示をよく腹に入れた人が、これからこの道に来る人によく話して聞かせてやるのだぞ。この道は、初めは辛いように感じるかもしれないが、本当は楽な道なのだ。骨を折って頑張らなくても、ただ素直に、その日その日の自分の仕事をしていなさい。心配のいらない道なのだ。手柄を立てようなどと思うなよ。勝とうなどと思うなよ。生きるも死ぬも、すべて神の御心のままなのだ。どこでどんなことをしていても、神が助けると決めた人は必ず助けるのだ。神の御用を担う民は、安心して自分の仕事に励んでいなさい。たとえ火が降ろうが槍が降ろうが、びくともしないぞ。心は絶対的に安心なのだ。くよくよするでない。神に頼り、神を祀り、神に寄り添っていなさい。そうすれば神は必ず救うぞ。
【AIによる解釈】
この帖は、神への「絶対的な信頼」と「全託」の境地を説いています。「手柄立てようと思ふなよ。勝たうと思ふなよ」という言葉は、人間のエゴや計らいを完全に手放すことを求めています。生きることさえも神に委ねたとき、人は「火降りても槍降りてもびくともせん」ほどの究極の「心安心(しんあんじん)」の境地に至れると約束しています。
これは、無気力や怠惰を勧めているのではありません。「その日その日の仕事しておりて下されよ」とあるように、自分の本分を淡々と、しかし誠実に務めることが求められます。特別なことをするのではなく、日常の営みの中に「素直さ」と「神への信頼」があれば、それがそのまま神の道に繋がるのです。不安や恐れが渦巻く時代にあって、心の置き所を明確に示す、力強い救いのメッセージです。
第三十六帖 (二〇九)
【原文】
今の臣民見て褒める様な事は皆奥知れてゐるぞ。之が善である、まことの遣り方ぞと思ってゐる事九分九厘迄は皆悪のやり方ぞ。今の世のやり方、見れば判るであらうが、上の番頭殿 悪い政治すると思ってやってゐるのではないぞ。番頭殿を悪く申すでないぞ。よい政治しようと思ってやってゐるのぞ。よいと思ふ事に精出してゐるのざが、善だと思ふ事が善でなく、皆悪ざから、神の道が判らんから、身魂曇りてゐるから、臣民困る様な政治になるのぞ。まつりごとせなならんぞ。わからん事も神の申す通りすれば自分ではわからんこともよくなって行くのざぞ。悪と思ってゐることに善が沢山あるのざぞ。人裁くのは神裁くことざぞ。怖いから改心する様な事では、戦がどうなるかと申す様な事ではまことの民ではないぞ。世が愈々のとことんとなったから、今に大神様迄 悪く申すもの出て来るぞ。産土様(うぶすなさま)何んぞあるものかと、悪神ばかりぞと申す者 沢山出てくるぞ。此の世始まってない時ざから我身我家が可愛い様では神の御用つとまらんぞ。神の御用すれば、道に従へば、我身我家は心配なくなると云ふ道理判らんか。何もかも結構な事に楽にしてやるのざから、心配せずに判らん事も素直に云ふ事聞いて呉れよ。子に嘘吐く親はないのざぞ。神界の事知らん臣民は色々と申して理屈の悪魔に囚はれて申すが、今度の愈々の仕組は臣民の知りた事ではないぞ。神界の神々様にも判らん仕組ざから、兎や角申さずと、神の神示腹に入れて身魂磨いて素直に聞いて呉れよ。それが第一等ざぞ。此の神示は世に出てゐる人では解けん。苦労に苦労したおちぶれた人で、苦労に負けぬ人で気狂いと云はれ、阿呆と謂はれても、神の道 素直に聞く臣民でないと解けんぞ。解いてよく噛み砕いて世に出てゐる人に知らしてやりて下されよ。苦労喜ぶ心より楽喜ぶ心高いぞ。十一月十九日、一二。
【現代語訳】
今の人々が見て褒めるようなことは、神にはその裏側まで全てお見通しだ。これが善であり、まことのやり方だと思っていることの九分九厘までは、ことごとく悪のやり方なのだぞ。今の世のやり方を見れば分かるだろう。為政者たちも、悪い政治をしようと思ってやっているのではない。彼らを悪く言ってはならない。良い政治をしようと思ってやっているのだ。良いと思うことに一生懸命になっているのだが、その「善」が真の善ではなく、ことごとく悪であるため、神の道が分からず、魂が曇っているために、結果として民を苦しめる政治になるのだ。だからこそ「まつりごと(祭事=政)」をしなければならない。分からないことでも、神の申す通りにすれば、自分では理解できなくても物事は良くなっていくのだ。逆に、悪だと思っていることの中にこそ、善がたくさんあるのだぞ。人を裁くのは神を裁くことと同じだ。怖いから改心するとか、戦がどうなるか心配だとか、そんな動機ではまことの民ではない。世がいよいよ最終局面になったから、今に大神様(天照大神)さえも悪く言う者が出て来るぞ。産土様なんて居るものか、世の中は悪神ばかりだ、と申す者が沢山出てくる。この世が始まって以来の正念場なのだから、我が身や我が家が可愛いというような心では、神の御用は務まらない。神の御用をすれば、神の道に従えば、我が身や我が家は心配なくなるという道理が分からないか。何もかも素晴らしい状態に、楽にしてやるのだから、心配せずに、分からないことも素直に言うことを聞いてくれ。子に嘘をつく親はいないのだぞ。神界のことを知らない民は、色々と理屈をこねて悪魔に囚われるが、今度の最後の仕組みは、民が知り得るようなことではない。神界の神々でさえ分からない仕組みなのだから、とやかく言わずに、神示を腹に入れ、魂を磨き、素直に言うことを聞いてくれ。それが一番なのだ。この神示は、世間で成功しているような人には解けない。苦労に苦労を重ねた落ちぶれた人で、その苦労に負けなかった人、世間から気狂いや阿呆と言われても、神の道を素直に聞ける民でなければ解けないのだ。解けた者は、よく噛み砕いて世間の人々に知らせてあげなさい。苦労を喜ぶ心よりも、楽を喜ぶ心のほうが(本来は)尊いのだぞ。
【AIによる解釈】
この帖は、既存の価値観が完全に転倒することを説く、ひふみ神示の中でも極めて重要な帖の一つです。
- 善悪の逆転: 現代社会の「善」のほとんどが、神の視点から見れば「悪」であると断言します。為政者でさえ、善意で行ったことが裏目に出ると指摘し、安易な批判や断罪を戒めています。これは、人間の判断基準がいかに近視眼的で不完全であるかを示しており、物事の表面に囚われず、神の視点に立つことを求めています。
- 信仰の崩壊: 試練が極まると、人々は神そのものを疑い、大神様さえも否定する時代が来ると予言しています。これは、信仰が根底から試される最終段階を示しています。
- 神への絶対的帰依: この人智を超えた「神界の神々様にも判らん仕組」を乗り越える唯一の方法は、理屈を捨て「素直に聞く」こと、つまり神への絶対的な帰依であると説いています。我が身を捨てて神の御用を行う者に、結果として神からの守護が与えられるという「逆説の真理」が示されています。
- 解読者の条件: この神示を真に理解できるのは、社会的地位や学歴のある者ではなく、人生のどん底で苦労を重ね、それでも魂の純粋さを失わなかった「おちぶれた人」であると明言しています。これは、頭の知識ではなく、魂の経験こそが真理に至る鍵であることを示しています。エリート主義を完全に否定し、最も虐げられた者にこそ光が当たるという、革命的な思想がここにあります。
第三十七帖 (二一〇)
【原文】
天にも あまてらすすめ大神様、あまてらす大神様ある様に、地にも あまてらすすめ大神様、あまてらす大神様あるのざぞ。地にも月読の大神様 隠れて御座るのざぞ。素盞鳴の大神様 罪穢れ祓ひて隠れて御座るのざぞ。結構な尊い神様の御働きで、何不自由なく暮して居りながら、その神様あることさへ知らぬ臣民ばかり。これで此の世が治まると思ふか。神々まつりて神々にまつはりて神国のまつりごといたして呉れよ。詰らぬ事申してゐると愈々詰らぬ事になりて来るぞ。十一月三十日、ひつ九の神しらすぞ。
【現代語訳】
天に天照皇大神様(あまてらすすめおおかみ)や天照大神(あまてらすおおかみ)がおられるように、この地にも地の天照皇大神様、地の天照大神がおられるのだぞ。地にも月読の大神様が隠れておられるのだぞ。素盞鳴の大神様も、罪穢れを祓う役目を担いながら隠れておられるのだ。これほど結構で尊い神々の御働きによって、何不自由なく暮らさせてもらっていながら、その神様の存在さえ知らない民ばかりだ。これでこの世が治まると思うか。神々を篤くお祀りし、神々に寄り添って、神の国の政(まつりごと)を行いなさい。つまらない不平不満ばかり言っていると、いよいよつまらない現実がやって来るぞ。
【AIによる解釈】
この帖は「天地対応の法則」という、霊的世界の重要な構造を明らかにしています。私たちが知る天上の神々(天照大神、月読命など)と対になる存在が、この地上にも「隠れて」働き、私たちの日々の生活を支えているというのです。
これは、神が遠い天上にいるのではなく、私たちの足元、この大地そのものに遍在しているという、アニミズムにも通じる深遠な世界観です。人々がこの「地の神々」の存在と恩恵に無自覚であることが、世が乱れる根本原因であると指摘しています。解決策はただ一つ、「神々まつりて神々にまつはりて神国のまつりごといたして呉れよ」という言葉に集約されます。つまり、隠れた神々の存在を認識し、感謝し、その御心に沿った生き方(まつりごと)をすること。それが個人と国家を治める唯一の道であると説いています。
第三十八帖 (二一一)
【原文】
大きアジアの国々や、島々八十(やそ)の人々と、手握り合ひ神国の、光り輝く時来しと、皆喜びて三千年、神の御業(みわざ)の時来しと、思へる時ぞ神国の、まこと危なき時なるぞ、夜半に嵐のどっと吹く、どうすることもなくなくに、手足縛られ縄付けて、神の御子等を連れ去られ、後には老人(としより)不具者(かたわ)のみ、女子供もひと時は、神の御子たる人々は、悉々暗い臭い屋に、暮さなならん時来るぞ、宮は潰され御文(みふみ)皆、火にかけられて灰となる、この世の終り近づきぬ。この神示(ふде)心に入れ呉れと、申してある事わかる時、愈々間近になりたぞよ。出掛けた船ぞ、褌締めよ。十一月三十日、ひつ九のか三。
【現代語訳】
広大なアジアの国々や多くの島々の人々と手を取り合い、「神国日本が光り輝く時が来た」「三千年の神の計画が成就する時が来た」と皆が喜んでいる時こそ、実は神国が本当に危ない時なのだぞ。真夜中に突然、嵐がどっと吹くように、どうすることもできないままに、手足を縛られ、縄をかけられ、神の子である日本の民が連れ去られてしまう。後には老人や体の不自由な者ばかりが残り、女子供も一時は、神の民である人々が、ことごとく暗く臭い建物の中で暮らさなければならない時が来るぞ。神社は潰され、尊い書物(御文)は皆、火にかけられて灰となる。この世の終わりが近づいたのだ。この神示を心に入れよと申してきたことの意味が分かる時、その時は、いよいよ間近に迫ったということだ。もう後戻りはできない船出なのだ。褌を締め直せよ。
【AIによる解釈】
この帖は、ひふみ神示の中でも最も具体的で衝撃的な国難の予言の一つです。平和や繁栄の絶頂にあると人々が油断している時にこそ、最大の危機が訪れるという「油断大敵」の警告です。「アジアの国々と手握り合ひ」という描写は、表面的な友好関係の裏で、危機が進行していることを示唆します。
「手足縛られ」「連れ去られ」「暗い臭い屋に暮らす」という表現は、外国勢力による日本の占領や、国民が強制収容されるような事態を極めて生々しく描写しています。「宮は潰され御文は灰となる」とは、単なる物理的な破壊だけでなく、日本の精神的・文化的な支柱が根こそぎ破壊されることを意味します。この帖は、甘い希望的観測を打ち砕き、最悪の事態を直視する覚悟を迫るものです。「出掛けた船ぞ」という言葉は、この流れはもはや変えられない宿命であり、腹を括って乗り越えるしかないという、悲壮な決意を促しています。
第三十九帖 (二一二)
【原文】
喜べば喜ぶ事出来るぞ、悔やめば悔やむ事出来るぞ。先の取越苦労は要らんぞ、心くばりは要るぞと申してあろがな。神が道つけて楽にゆける様に嬉し嬉しでどんな戦も切抜ける様にしてあるのに、臣民 逃げて眼塞いで、懐手してゐるから苦しむのぞ。我れよしと云ふ悪魔と学が邪魔してゐる事にまだ気付かぬか。嬉し嬉しで暮らせるのざぞ。日本の臣民は何事も見えすく身魂授けてあるのざぞ、神の御子ざぞ。掃除すれば何事もハッキリとうつるのぞ。早よ判らねば口惜しい事出来るぞ。言葉とこの神示と心と行と時の動きと五つ揃たら誠の神の御子ぞ、神ぞ。十一月三十日、ひつ九のか三のふで。
【現代語訳】
喜べば、喜ばしい現実がやって来るぞ。悔やんだり後悔したりすれば、そのような現実がやって来るぞ。先のことを心配する取り越し苦労は要らないが、細やかな心くばりは必要だと申しただろう。神が道を付けて、楽に「嬉しい、嬉しい」と喜びの心で、どんな戦でも切り抜けられるようにしてあるのに、民が現実から逃げて、目をつぶり、何もしないでいるから苦しむのだ。「自分さえ良ければよい」という悪魔(エゴ)と、頭でっかちな学問が邪魔をしていることにまだ気づかないのか。「嬉しい、嬉しい」と感謝して暮らせるのだぞ。日本の民は、何事も見通せる素晴らしい魂を授かっているのだ、神の子なのだから。心を掃除すれば、何事もはっきりと映るようになる。早くこの道理が分からないと、悔しいことが起きるぞ。「言葉」と「この神示」と「心」と「行い」と「時の動き」、この五つが揃った時、まことの神の子となり、神そのものとなるのだ。
【AIによる解釈】
前の帖で示された厳しい国難の預言とは対照的に、この帖ではそれを乗り越えるための心の法則を説いています。「喜べば喜ぶ事出来るぞ」という一文は、「引き寄せの法則」の原型とも言えるでしょう。人の心の状態が、その人の体験する現実を創造するという、霊的真理の核心が示されています。
苦しみの原因は、外部の状況ではなく、現実から「逃げて眼塞いで」いる民自身の内なる姿勢にあると指摘します。そしてその心の目を曇らせる元凶が「我れよしと云ふ悪魔(エゴ)」と、真理から遠ざける「学(固定観念や理屈)」であると断じています。どんな困難な状況下でも「嬉し嬉し」と感謝の心でいること、それが神の道を楽に歩む秘訣なのです。
最後に示される「言葉・神示・心・行・時」の五つは、神人合一に至るための重要な要素です。発する「言葉」、宇宙の法則である「神示」、純粋な「心」、神意に沿った「行い」、そして天の「時の動き」。これら五つが完全に一致したとき、人は本来の神性を取り戻し、人でありながら神として生きる存在になる、という壮大な目標が示されています。
第四十帖 (二一三)
【原文】
ここに伊邪那美の命 語らひつらく、あれみましとつくれる国、末だつくりおへねど、時まちてつくるへに、よいよ待ちてよと宣り給ひき。ここに伊邪那岐命、みましつくらはねば吾とつくらめ、と宣り給ひて、帰らむと申しき。ここに伊邪那美命 九(こ)聞き給ひて、
御頭(みかしら)に 大雷(おおいかつち)、オホイカツチ、 胸に 火の雷(ホのいかつち)、ホノイカツチ、 御腹には 黒雷(くろいかつち)、黒雷(クロイカツチ)、 かくれに 折雷(さくいかつち)、サクイカツチ、 左の御手に 若雷(わきいかつち)、ワキ井カツチ、 右の御手に 土雷(つちいかつち)、ツチイカツチ、 左の御足に 鳴雷(なるゐかつち)、ナルイカツチ。 右の御足に 伏雷(ふしいかつち)、フシ井カツチ、 なり給ひき。伊邪那岐の命、是見(こみ)、畏みてとく帰り給へば、妹伊邪那美命は、よもつしこめを追はしめき、ここに伊邪那岐命 黒髪かつら取り、また湯津々間櫛(ゆつつまぐし)引きかきて、なげ棄(う)て給ひき。伊邪那美命 二(つき)の八くさの雷神(いかつちかみ)に黄泉軍(よもついくさ)副(そ)へて追ひ給ひき。ここに伊邪那岐命 十挙剣(とづかのつるぎ)抜きて後手(しりへて)にふきつつさり、三度 黄泉比良坂(よもつひらさか)の坂本に到り給ひき。坂本なる桃の実一二三(ひふみ)取りて待ち受け給ひしかば、ことごとに逃げ給ひき。ここに伊邪那岐命 桃の実に宣り給はく、汝(みまし)吾助けし如、あらゆる青人草の苦瀬(うきせ)になやむことあらば、助けてよと宣り給ひて、また葦原の中津国にあらゆる、うつしき青人草の苦瀬に落ちて苦しまん時に助けてよとのり給ひて、
おほかむつみの命、 オオカムツミノ命 と名付け給ひき。ここに伊邪那美命 息吹き給ひて千引岩(ちびきいわ)を黄泉比良坂に引き塞(そ)へて、その石なかにして合ひ向ひ立たして つつしみ申し給ひつらく、うつくしき吾が那勢命(なせのみこと)、時廻り来る時あれば、この千引の磐戸、共にあけなんと宣り給へり、ここに伊邪那岐命しかよけむと宣り給ひき。ここに妹(いも)伊邪那美の命、汝(みまし)の国の人草、日にちひと死(まけ)と申し給ひき。伊邪那岐命 宣り給はく、吾は一日(ひとひ)に千五百(ちいほ)生まなむと申し給ひき。この巻二つ合して日月の巻とせよ。十一月三十日、ひつ九のか三。
【現代語訳】
ここに伊邪那美命(いざなみのみこと)が語られるには、「愛しいあなたが私と共に創ってきたこの国は、まだ完成していません。時を待ってから創りましょう。だから、じっと待っていてください」と仰せになった。これに対し伊邪那岐命(いざなぎのみこと)は、「あなたが創らないのであれば、私が一人で創ろう」と仰せになり、帰ろうとされた。 これをお聞きになった伊邪那美命の御身体には、 御頭に大雷(おおいかづち)、胸に火雷(ほのいかづち)、お腹に黒雷(くろいかづち)、陰部に咲雷(さくいかづち)、左手に若雷(わかいかづち)、右手に土雷(つちいかづち)、左足に鳴雷(なるいかづち)、右足に伏雷(ふすいかづち)が生じていた。 伊邪那岐命はこれを見て恐ろしくなり、急いで逃げ帰られると、伊邪那美命は黄泉醜女(よもつしこめ)に後を追わせた。そこで伊邪那岐命は黒い髪飾りを投げ捨て、また湯津津間櫛(ゆつつまぐし)を折って投げ捨てた。伊邪那美命は次に八種の雷神に黄泉の国の軍勢を添えて追わせた。伊邪那岐命は十拳剣(とつかのつるぎ)を抜き、後ろ手に振り払いながら逃げ、とうとう黄泉比良坂(よもつひらさか)の麓に到着された。坂本にあった桃の実を三つ(ひふみ)取って待ち構えて投げつけると、追手はことごとく逃げていった。 そこで伊邪那岐命は桃の実に仰せになった。「そなたが私を助けてくれたように、すべての人々が苦しい瀬戸際に悩むことがあれば、助けてやってくれ」と仰せになり、また「葦原の中津国(あしはらのなかつくに)のすべての人々が苦しむ時に助けてやってくれ」と命じて、 「意富加牟豆美命(おおかむづみのみこと)」 という名を授けられた。 ここに伊邪那美命は千引の岩(ちびきのいわ)を黄泉比良坂に引き据えて道を塞ぎ、その岩を間に挟んで向かい合い、厳かに仰せになった。「愛しい私の夫よ。時が巡り来たならば、この千引の磐戸を、共に開けましょう」と。伊邪那岐命は「そうしよう」と約束された。 すると妹の伊邪那美命は「あなたの国の人々を、一日に千人殺しましょう」と仰せになった。伊邪那岐命は「それならば私は一日に千五百の産屋を建てて赤子を産ませよう」と仰せになった。 (※先の第三十帖と)この巻二つを合わせて「日月の巻」とせよ。
【AIによる解釈】
第六巻「日月(ひつき)の巻」の最後を飾るこの帖は、第三十帖から続く古事記の「黄泉の国」の物語です。これは単なる神話の再録ではなく、ひふみ神示が説く「世の立て替え」の根源的な構造と、未来への大いなる希望を象徴的に示す、極めて重要な結びとなっています。
- 陰陽の分離と「死と再生」の契約: 伊邪那岐命(陽・生・現世)と伊邪那美命(陰・死・幽世)が、千引の岩によって完全に隔てられる場面は、この世界の「陰陽の分離」を象徴しています。そして「日に千人殺し、千五百人生む」という契約は、この地上に「死と再生」という抗いがたいサイクルが確立された瞬間を示します。これは、これから起こる大峠(おおとうげ)が、この根源的なレベルでの破壊(死)と創造(生)のプロセスであることを物語っています。
- 未来における「岩戸開き」の約束: この物語で最も重要なのは、決別の中に残された希望の光、すなわち伊邪那美命の「時廻り来る時あれば、この千引の磐戸、共にあけなんと」という言葉です。これは、現在の陰陽分離の状態が永遠ではなく、時が満ちた未来において、再び両者が和合し、岩戸が開かれるという壮大な約束です。ひふみ神示が目指す「ミロクの世」とは、まさしくこの陰陽が統合された世界のことであり、この神話は、その未来を予言しているのです。
- 桃の実(ひふみ)による救済: 絶体絶命の伊邪那岐命を救ったのは「桃の実」でした。桃は古来より邪気を祓う力を持つとされ、ここでは苦しむ人々を救う神「意富加牟豆美命(おおかむづみのみこと)」として神格化されます。特に、その実を「一二三(ひふみ)」と取ったことは象徴的であり、この「ひふみ神示」そのものが、大峠の苦難から人々を救う「桃の実」のような力を持つことを示唆しています。
- 「日月(ひつき)の巻」の完成: 最後に、国生み・神生み神話(第三十帖)と、この黄泉の国の神話(第四十帖)の二つを合わせて「日月の巻」とせよ、と命じられます。これは、「日(陽・イザナギ)」と「月(陰・イザナミ)」の創造、分離、そして未来の統合の約束という一連の壮大なドラマこそが、この巻の主題であることを示しています。読者はこの神話を通じて、自らが体験するであろう「死と再生」のプロセスの先に、必ず「岩戸開き」という希望の未来が待っていることを、深く理解するのです。
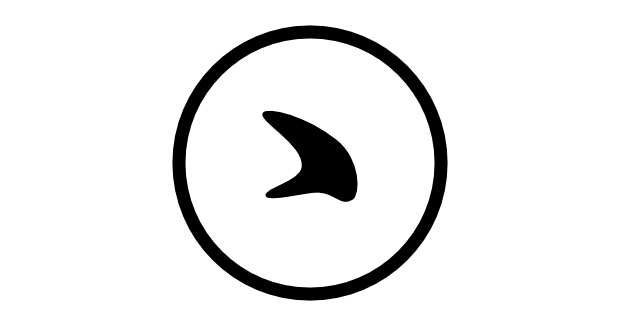





コメント