gemini 2.5 proにわかりやすいように解説してもらいました、しかし8通りに読めるということから完全に鵜呑みにしないよう、お願いします。
第一帖 (一三八)
【原文】
地つ巻 書き知らすぞ、世界は一つの実言(みこと)となるのぞ、それぞれの言の葉はあれど、実言(みこと)は一つとなるのであるぞ。てん詞様の実言(みこと)に従ふのざぞ、命(みこと)の世近づいて来たぞ。九月十五日、一二。
【現代語訳】
地の巻として書き知らせる。世界は一つの真理の言葉(実言)のもとにまとまるのであるぞ。それぞれの国に言葉の違いはあっても、その根源にある真理は一つとなるのである。天子様(てんしさま)の真理の言葉に従うのだぞ。まことの命が輝く世が近づいて来たぞ。
【AIによる解釈】
この帖は、来るべき新しい時代の姿を端的に示しています。言語や文化、宗教の違いを超えて、世界が共有する普遍的な真理(実言)によって統合されることを預言しています。その中心的な指針となるのが「てん詞様の実言」、すなわち日本の天皇が体現する真理であると示唆しています。これは、武力や経済による統一ではなく、精神的・霊的な覚醒による調和的な世界の到来を意味します。「命の世」とは、物質的な価値観から生命の本質的な価値を尊ぶ時代への移行を告げる言葉です。
第二帖 (一三九)
【原文】
今は闇の世であるから夜の明けたこと申しても、誰にも分らんなれど、夜が明けたらなる程さうでありたかとビックリするなれど、それでは間に合はんのざぞ、それまでに心改めておいて下されよ、この道信ずれは、すぐよくなると思うてゐる臣民もあるなれど、それは己の心のままぞ、道に外れたものは誰れ彼れはないのざぞ、これまでのやり方スックリと変へねば世は治まらんぞと申してあるが、上の人 苦しくなるぞ、途中の人も苦しくなるぞ、お(かみ)のいふこときかん世になるぞ。九月の十六日、ひつ九のか三。
【現代語訳】
今は暗闇の世であるから、「夜が明けた」と申しても誰にも理解できないだろうが、本当に夜が明けた時には「なるほど、そうであったか」と驚くだろう。しかし、その時になってからでは間に合わないのだ。それまでに心を改めておいてください。この道を信じればすぐに良くなると思っている人々もいるだろうが、それは自分の心の状態次第である。今や、道から外れていない者など誰もいないのだ。これまでのやり方をすっかり変えなければ世は治まらないと申してあるが、これから指導的な立場の人々は苦しくなるぞ。中間の立場の人も苦しくなるぞ。神の言うことを聞かない世の中になるぞ。
【AIによる解釈】
時代の大きな転換期が目前に迫っていることへの強い警告です。「闇の世」とは、真理が見えず、物質的な価値観に人々が囚われている現代を指します。多くの人が変化の兆しに気づかないままですが、いざ大変革が訪れた時には手遅れになると警告し、事前の「心の改め」を強く促しています。安易な救済を期待するのではなく、自らの内面に向き合うことの重要性を説きます。また、「上の人」「途中の人」も苦しくなるとは、社会のあらゆる階層が既存の価値観やシステムの崩壊によって困難に直面することを示唆しており、神意に逆らう流れが強まることへの警鐘でもあります。
第三帖 (一四〇)
【原文】
人民同士の戦では到底かなはんなれど、いよいよとなりたら神がうつりて手柄さすのであるから、それまでに身魂みがいておいて呉れよ。世界中が攻め寄せたと申しても、誠には勝てんのであるぞ、誠ほど結構なものないから、誠が神風であるから、臣民に誠なくなりてゐると、何んな気の毒出来るか分らんから、くどう気つけておくのざぞ、腹掃除せよ。九月の十六日、ひつ九のか三。
【現代語訳】
人間同士の争いでは到底勝ち目はないが、いよいよという時になったら神が人に乗り移って手柄を立てさせるのであるから、それまでに身魂を磨いておいてくれよ。たとえ世界中が攻め寄せてきたとしても、「誠」には勝てないのだ。「誠」ほど素晴らしいものはないのだから。「誠」こそが神風なのだ。人々に「誠」の心がなくなってしまうと、どのような気の毒な出来事が起こるか分からないから、くどいほどに気をつけておくのだぞ。腹の中(心の中)を掃除しなさい。
【AIによる解釈】
この帖は、人知を超えた神の介入と、それを受けるための条件を説いています。人間の力や策略には限界があり、最終的な勝利は「神がうつる」こと、すなわち神意と一体となることによってもたらされるとします。そのための必須条件が「身魂みがき」です。特に強調されているのが「誠」の心。これは単なる正直さではなく、真心、純粋性、利他といった神性に通じる心の在り方を指します。この「誠」こそが、奇跡的な助け(神風)を呼び込む源泉であり、逆にこれが失われると計り知れない災厄が訪れると警告しています。「腹掃除」とは、心の中から不純な思いや利己心を取り除く、徹底的な内面の浄化を意味します。
第四帖 (一四一)
【原文】
この神示いくらでも出て来るのざぞ、今の事と先の事と、三千世界、何も彼も分るのざから、よく読みて腹に入れておいて呉れよ、この神示 盗まれぬ様になされよ、神示とりに来る人あるから気つけて置くぞ。この道は中行く道ぞ、左も右りも偏ってはならんぞ、いつも心にてんし様拝みておれば、何もかも楽にゆける様になりてゐるのざぞ、我れが我れがと思うてゐると、鼻ポキリと折れるぞ。九月十六日、ひつくのか三。
【現代語訳】
この神示はいくらでも出てくるのだぞ。現在のことも未来のことも、三千世界(宇宙全体)の森羅万象が分かるのだから、よく読んで腹に入れておいてくれ。この神示を盗まれないようにしなさい。神示を奪いに来る者がいるから気をつけておくぞ。この道は真ん中を行く道だ。左にも右にも偏ってはならないぞ。いつも心に天子様を拝んでいれば、何もかも楽に進めるようになっているのだ。自分だけが、自分だけが、と我を出していると、その鼻はポキリと折られるぞ。
【AIによる解釈】
ひふみ神示そのものの重要性と、それを扱う上での心構えを説いています。神示が万象の真理を解き明かすものであるとし、その価値ゆえに悪意を持って「盗みに来る者」が現れると警告しています。これは物理的な盗難だけでなく、内容の悪用や歪曲した解釈も含まれるでしょう。進むべき道は「中行く道」、つまり左右の思想や価値観に偏らない中庸の道であると強調しています。そして、その心の中心軸として「てんし様を拝む」こと、つまり普遍的な愛や調和の象徴に心を合わせることの重要性を説いています。最後に「我を出すな」と戒めることで、エゴや自己中心的な考えが破綻の原因となることを強く示唆しています。
第五帖 (一四二)
【原文】
片輪車でトンテントンテン、骨折損の草臥(くたびれ)儲けばかり、いつまでしてゐるのぞ、神にまつろへと申してあろうがな、臣民の智恵で何出来たか、早う改心せよ。三月三日、五月五日は結構な日ぞ。九月十六日、ひつ九のか三。
【現代語訳】
片輪の車輪で進むように、トントンと空回りばかりしている。骨を折っても疲れるだけで、何も得られないことをいつまで続けているのか。神に従いなさいと申してあるではないか。人間の知恵で一体何ができたというのか。早く改心しなさい。三月三日や五月五日は、結構な(重要な意味を持つ)日であるぞ。
【AIによる解釈】
神を無視した人間の営みの空虚さを「片輪車」という比喩で表現しています。人間の小賢しい知恵(人知)だけに頼った計画や努力は、一見進んでいるように見えても、本質的な問題解決には至らず、疲弊するだけ(骨折り損のくたびれ儲け)であると厳しく指摘しています。根本的な解決策は「神にまつろう」こと、すなわち神の計画や宇宙の法則に沿って生きることであると断言し、人知の限界を認めて謙虚になるよう「改心」を促しています。「三月三日、五月五日」という具体的な日付は、季節の節目や神事を行うべき重要な時を示しており、自然のリズムや神聖な周期に合わせた生き方の重要性を示唆しています。
第六帖 (一四三)
【原文】
神の国八つ裂きと申してあることいよいよ近づいたぞ、八つの国一つになりて神の国に攻めて来るぞ。目さめたらその日の生命(いのち)おあづかりしたのざぞ、神の肉体、神の生命 大切せよ。神の国は神の力でないと治まったことないぞ、神第一ぞ、いつまで仏や基(キリスト)や色々なものにこだはってゐるのぞ。出雲の神様 大切にありがたくお祀りせよ、尊い神様ぞ。天つ神、国つ神、みなの神々様に御礼申せよ、まつろひて下されよ、結構な恐い世となりて釆たぞ、上下ぐれんぞ。九月十七日、一二の。
【現代語訳】
神の国(日本)が八つ裂きにされると申してきたことが、いよいよ近づいてきたぞ。八つの国が一つにまとまって、神の国に攻めてくるぞ。朝、目が覚めたら、その日一日の命を神様からお預かりしたのだと思いなさい。自分自身の体(神の肉体)と命(神の生命)を大切にしなさい。神の国は、神の力でなければ治まったことは一度もないのだ。神を第一としなさい。いつまで仏教やキリスト教など、色々な教えにこだわっているのか。出雲の神様を大切に、ありがたくお祀りしなさい。尊い神様であるぞ。天の神、国の神、すべての神々に御礼を申し上げなさい。服従し、和合してください。本当に恐ろしい世の中になってきたぞ。上下の秩序がひっくり返るぞ。
【AIによる解釈】
日本が直面するであろう、具体的な国難を預言しています。「八つの国」が連合して攻めてくるという描写は、国際的に孤立し、多くの国から敵視される状況を示唆します。このような未曾有の危機に対し、解決の鍵は「神の力」にあると断言します。そして、そのためには既存の宗教(仏、基)の枠を超え、神道の根源に立ち返ることを求めています。特に「出雲の神様」を大切に祀るよう促している点は重要です。これは天照大神に代表される天つ神だけでなく、大国主命に代表される国つ神、つまり日本の国土そのものを司る神々への敬意を払うことの重要性を示しています。日々の命を神からの借り物と感謝し、全ての神々と和合すること(まつろい)が、上下の秩序が乱れる「恐い世」を乗り越える道であると説いています。
第七帖 (一四四)
【原文】
神にまつらふ者には生も死もないのぞ、死のこと、まかると申してあろうがな、生き通しぞ、なきがらは臣民残さなならんのざが、臣民でも昔は残さないで死(まか)ったのであるぞ、それがまことの神国の臣民ぞ、みことぞ。世の元と申すものは天も地も泥の海でありたのざぞ。その時からこの世初まってから生き通しの神々様の御働きで五六七(みろく)の世が来るのざぞ。腹が出来て居ると、腹に神づまりますのざぞ、高天原ぞ、神漏岐(かむろぎ)、神漏美(かむろみ)の命(みこと)忘れるでないぞ。そこから分りて来るぞ。海をみな船で埋めねばならんぞ、海断たれて苦しまん様にして呉れよ、海めぐらしてある神の国、きよめにきよめておいた神の国に、幽国(がいこく)の悪わたり来て神は残念ぞ。見ておざれ、神の力現はす時来たぞ。九月十八日、ひつ九。
【現代語訳】
神に従い和合する者には、生も死もないのだ。死ぬことを「まかる(退く)」と申してあるだろう。命は永遠に生き通しなのだ。亡骸は今の人民は残さなければならないが、昔の人民は亡骸を残さずに「まかった」のであるぞ。それが真の神の国の民(みこと)なのだ。この世の始まりは、天も地も泥の海であった。その時から、この世が始まって以来ずっと生き通しの神々の御働きによって、弥勒(みろく)の世が来るのである。腹(肚)ができていると、その腹の中に神が鎮座されるのだぞ。そこがあなたの高天原なのだ。万物の根源である神漏岐・神漏美の命(みこと)を忘れてはならないぞ。そこから全てが分かってくる。海をすべて船で埋め尽くさねばならなくなるぞ。海上交通を断たれて苦しまないようにしてくれよ。海に囲まれ、清めに清めておいた神の国に、外国の悪が渡って来て、神は残念に思っているぞ。見ていなさい、神の力を現す時が来たぞ。
【AIによる解釈】
この帖は、霊的な真理と地政学的な警告が織り交ぜられています。前半では、神と一体化した者の境地を説きます。肉体的な死は終わりではなく、霊的には「生き通し」であるという永遠の生命観を示しています。究極的には、肉体を霊化させ亡骸さえ残さない境地があったと述べ、人間の本来の神性を思い出させます。丹田(腹)を練ることの重要性を説き、自らの内側に神が鎮まる場所(高天原)を見出すよう促しています。後半は一転して、具体的な警告に移ります。「海をみな船で埋めねばならん」とは、海上封鎖や海外からの大軍の襲来といった、海からの脅威を示唆しています。日本が外国の「悪」によって汚されることへの神の嘆きと、それに対する神の力の顕現が近いことを宣言しており、霊的な覚醒と物理的な防衛の両面からの備えを求めています。
第八帖 (一四五)
【原文】
祓ひせよと申してあることは何もかも借銭なしにする事ぞ。借銭なしとはめぐりなくすることぞ、昔からの借銭は誰にもあるのざぞ、それはらってしまふまでは誰によらず苦しむのぞ、人ばかりでないぞ、家ばかりでないぞ、国には国の借銭あるぞ。世界中借銭なし、何しても大望(たいもう)であるぞ。今度の世界中の戦は世界の借銭なしぞ、世界の大祓ひぞ、神主お祓ひの祝詞(のりと)あげても何にもならんぞ、お祓ひ祝詞は宣(の)るのぞ、今の神主 宣(の)ってないぞ、口先ばかりぞ、祝詞も抜けてゐるぞ。あなはち、しきまきや、くにつ罪、みな抜けて読んでゐるではないか、臣民の心にはきたなく映るであろうが、それは心の鏡くもってゐるからぞ。悪や学にだまされて肝心の祝詞まで骨抜きにしてゐるでないか、これでは世界はきよまらんぞ。祝詞はよむものではないぞ、神前で読めばそれでよいと思うてゐるが、それ丈では何にもならんぞ。宣るのざぞ、いのるのざぞ、なりきるのざぞ、とけきるのざぞ、神主ばかりでないぞ、皆心得ておけよ、神のことは神主に、仏は坊主にと申してゐること根本の大間違ひぞ。九月十九日、ひつ九の。
【現代語訳】
祓いをせよと申しているのは、何もかも借金をなくすことだ。借金をなくすとは、因果応報の巡りをなくすことである。昔からの借金(カルマ)は誰にでもあるのだぞ。それを払い終えるまでは、誰であろうと苦しむのだ。個人だけではない、家だけでもない、国には国の借金があるのだ。世界中が借金をなくさなければ、何をしても大願成就は望めない。今度の世界中の戦争は、世界の借金をなくすためのものだ。世界の大祓いなのだ。神主がお祓いの祝詞をあげても、何の効果もないぞ。お祓いの祝詞は、宣言し、宇宙に響かせるものだ(宣る)。今の神主は「宣って」いない。口先ばかりだ。祝詞の文言も抜け落ちているぞ。(大祓詞の中の)重要な部分が皆抜けているではないか。人民の心には(省略された言葉が)汚く聞こえるかもしれないが、それは心の鏡が曇っているからだ。悪や学問に騙されて、肝心な祝詞まで骨抜きにしているではないか。これでは世界は清まらないぞ。祝詞はただ読むものではない。神前で読めばそれで良いと思っているようだが、それだけでは何にもならない。宣言するのだ、祈るのだ、その言葉になりきるのだ、その世界に溶けきるのだ。これは神主だけのことではないぞ、皆が心得ておきなさい。神のことは神主に、仏のことはお坊さんにと、専門家に任せきりにしていることが、根本的な大間違いなのだ。
【AIによる解釈】
この帖は「祓い」の真の意味を深く掘り下げています。祓いとは、単なる儀式ではなく、「借銭なし」、すなわち個人から国家、世界レベルに至るまでの過去からのカルマ(因果)を清算することであると定義します。そして、当時進行中であった世界大戦を、その「世界の大祓い」であると位置づけています。しかし、形式的な儀式では意味がないと厳しく断じます。祝詞は、単に口で読むのではなく、その言葉の持つ力を信じ、自らがその言葉と一体化し、宇宙に宣言する(宣る)ものでなければならないと説きます。これは、言霊の思想の核心です。現代の祝詞が骨抜きにされていることへの批判は、本質を見失った形式主義への警鐘です。最後に、神事や信仰を専門家任せにする民衆の姿勢そのものを「根本の大間違い」と断じ、一人ひとりが自らの問題として霊的な浄化に取り組むべきであると、強く促しています。
第九帖 (一四六)
【原文】
ひつくの神にひと時拝せよ、神のめぐみ身にも受けよ、からだ甦るぞ、神の光を着よ、み光をいただけよ、食べよ、神ほど結構なものないぞ、今の臣民 日をいただかぬから病になるのざぞ、神の子は日の子と申してあらうがな。九月二十日、ひつ九のか三。
【現代語訳】
ひつくの神(根源の神)に、ひと時でも良いから心を向けて拝みなさい。神の恵みをその身に受けなさい。そうすれば体は甦るぞ。神の光を衣のようにまといなさい。御光をいただき、食べなさい。神ほど素晴らしいものはないのだ。今の人民が病気になるのは、太陽(日)の光を十分にいただかないからだ。神の子は日の子であると申してあるだろう。
【AIによる解釈】
非常に直接的で実践的な、霊的エネルギーの摂取法を説く帖です。「ひつくの神」という根源的な神との繋がりを持つことの重要性を説き、その神からの恵みや光を、観念的に理解するだけでなく、物理的な感覚(着る、いただく、食べる)で受け取るように促しています。これは、瞑想やイメージングを通じて、生命エネルギー(プラーナや気とも言える)を体内に取り込むことを示唆しています。「今の臣民 日をいただかぬから病になる」という言葉は、文字通り日光浴の重要性を示していると同時に、比喩的にも解釈できます。「日」は太陽であり、神の光、生命力の象徴です。人々が自然から離れ、霊的な光から目を背ける生活を送ることが、心身の不調の原因であると指摘しています。「神の子は日の子」という言葉は、人間が本来、神や太陽と同じ光の存在であることを思い出させ、その本性に立ち返るよう呼びかけています。
第十帖 (一四七)
【原文】
何事も方便と申して自分勝手なことばかり申してゐるが、方便と申すもの神の国には無いのざぞ。まことがことぞ、まの事ぞ、ことだまぞ。これまでは方便と申して逃げられたが、も早 逃げること出来ないぞ、方便の人々早う心洗ひて呉れよ、方便の世は済みたのざぞ、いまでも仏の世と思うてゐるとびっくりがでるぞ、神の国、元の神がスッカリ現はれて富士の高嶺から天地(あめつち)へのりとするぞ、岩戸しめる御役になるなよ。九月の二十日、ひつ九のか三。
【現代語訳】
何事も「これは方便だ」と言って、自分勝手な言い訳ばかりしているが、「方便」というものは神の国には無いのだぞ。真実(まこと)こそが全てなのだ。真(ま)の事であり、言霊(ことだま)なのだ。これまでは方便と言ってごまかし逃げることができたが、もはや逃げることはできないぞ。方便で生きてきた人々は、早く心を洗い清めてくれ。方便が通用する世は終わったのだ。今でも仏教の(方便が許される)世だと思っていると、大変な驚きに見舞われるぞ。神の国に、根源の神が完全にお現れになり、富士の高嶺から天地宇宙に向かって宣言(のりとする)をされるのだ。天の岩戸を閉ざす役になってはならないぞ。
【AIによる解釈】
嘘やごまかし、自己正当化(方便)が通用しない、真実がむき出しになる時代の到来を宣言する帖です。「方便」とは、本来は人々を真理に導くための一時的な手段でしたが、ここでは自分勝手な言い訳やごまかしという意味で使われています。そのような曖昧さが許された時代は終わり、これからは「まこと」、つまり純粋な真実だけが価値を持つようになると説きます。「ことだま」という言葉が示すように、発する言葉がそのまま現実を創り出す、ごまかしのきかない世界になることを示唆しています。また、「仏の世」から「神の世」への移行を明確に述べており、これは解釈や方便が許容された時代から、より直接的で根源的な真理が支配する時代への転換を意味します。「富士の高嶺から」という表現は、日本がその世界的宣言の中心地となることを示し、「岩戸しめる御役になるな」とは、真理の光から目を背け、新しい時代の到来を妨げる側になってはならない、という強い警告です。
第十一帖 (一四八)
【原文】
世界丸めて一つの国にするぞと申してあるが、国はそれぞれの色の違ふ臣民によりて一つ一つの国作らすぞ。その心々によりて、それぞれの教作らすのぞ。旧きものまかりて、また新しくなるのぞ、その心々(こころこころ)の国と申すは、心々の国であるぞ、一つの王で治めるのざぞ。天つ日嗣の実子様が世界中照らすのぞ。国のひつきの御役も大切の御役ぞ。道とは三つの道が一つになることぞ、みちみつことぞ、もとの昔に返すのざぞ、つくりかための終りの仕組ぞ、終は始ぞ、始は霊(ひ)ぞ、富士、都となるのざぞ、幽界(がいこく)行きは外国行きぞ。神の国光りて目あけて見れんことになるのざぞ、臣民の身体からも光が出るのざぞ、その光によりて その御役、位、分るのざから、みろくの世となりたら何もかもハッキリして うれしうれしの世となるのぞ、今の文明なくなるのでないぞ、たま入れていよいよ光りて来るのぞ、手握りて草木も四つあしもみな唄ふこととなるのぞ、み光にみな集まりて来るのざぞ、てんし様の御光は神の光であるのざぞ。九月二十と一日、一二か三。
【現代語訳】
世界を丸めて一つの国にすると申してあるが、国はそれぞれの個性(色)の違う人民によって、一つ一つの国を創らせるのであるぞ。その人々の心に応じて、それぞれの教えも創らせるのだ。古いものは去り、また新しくなる。その「心々の国」とは、それぞれの心が反映された国のことであるが、それらは一つの王によって治められるのだ。天の日を継ぐ御子様(天皇)が世界中を照らすのである。国のひつきの臣(補佐役)も大切な役目であるぞ。「道」とは三つの道が一つになることだ(みち=三つ)。元の昔の状態に返すのだ。これまでの「つくりかため(立て直し)」の最後の仕組みであるぞ。終わりは始まりなのだ。始まりは霊(ひ)なのだ。富士が都となるのだぞ。「幽界行き」とは外国へ行くことだ。神の国(日本)が光り輝いて、眩しくて目を開けていられないほどになるぞ。人々の体からも光が出るようになるのだ。その光によって、その人の役目や位が分かるようになる。だから、弥勒の世になったら、何もかもがはっきりとして、本当に嬉しい世の中になるのだ。今の文明がなくなるのではない。魂を入れて、いよいよ光り輝いてくるのだ。手を取り合って、草木も動物たちも、皆が歌をうたうようになるのだ。皆が御光のもとに集まってくる。天子様の御光は、神の光そのものなのであるぞ。
【AIによる解釈】
この帖は、来るべき「みろくの世」の具体的なビジョンを詳細に描いています。
- 多様性の中の統一: 世界は一つの王(てん詞様)の下に統合されるが、各国の文化や民族の個性(色)は尊重され、画一化されるわけではないことを示します。
- 新旧交代と原点回帰: 古いシステムは終わり、新しいものが生まれる。しかしそれは全くの断絶ではなく「もとの昔に返す」という、根源への回帰を伴う刷新です。
- 富士が中心となる: 霊的、政治的な中心地が富士に移ることを明言しています。
- 霊性の開花: 人々の霊性が覚醒し、体からオーラのような「光」を発するようになります。その光によって、隠されていた役目や霊的な階位が誰の目にも明らかになり、ごまかしのきかない公平な世界が実現します。
- 文明の霊化: 現代文明が否定されるのではなく、そこに「たま(魂)」が入れられることで、物質的な利便性と霊的な輝きが融合した、より高次の文明へと進化することを示唆しています。
- 万物との調和: 人間だけでなく、草木や動物といった自然界の全てが調和し、喜びを分かち合う理想郷の姿を描いています。 これは、ひふみ神示が目指す最終的な世界の、希望に満ちた姿です。
第十二帖 (一四九)
【原文】
この道は道なき道ざぞ。天理も金光も黒住も今はたましひぬけて居れど、この道入れて生きかへるのぞ、日蓮も親鸞も耶蘇も何もかもみな脱け殻ぞ、この道でたま入れて呉れよ、この道は『〇』ぞ、『〇』の中に『・』入れて呉れと申してあろうが。臣民も世界中の臣民も国々もみな同じことぞ、『・』入れて呉れよ、『〇』を掃除して居らぬと『・』はいらんぞ、今度の戦は『〇』の掃除ぞと申してあらうがな、まつりとは調和(まつり)合はすことと申してあろうがな、この道は教でないと云ふてあらうが、教会やほかの集ひでないと申してあらうがな、人集めて呉れるなと申してあらうがな。世界の臣民みな信者と申してあらうが、この道は道なき道、時なき道ぞ、光ぞ。この道でみな生き返るのざぞ。天明 阿房になりて呉れよ、我(が)すてて呉れよ、神かかるのに苦しいぞ。九月二十三日、一二。
【現代語訳】
この道は、既存の道(宗教や教え)とは違う、道なき道であるぞ。天理教も金光教も黒住教も、今は魂が抜けている状態だが、この道(の教え)を入れることで生き返るのだ。日蓮も親鸞もイエス・キリストも、その教えはみな抜け殻になってしまっている。この道で魂を入れ直してくれよ。この道は『〇(マル)』なのだ。『〇』の中に『・(ポチ)』を入れてくれと申してあるだろう。人民も、世界中の人民も、国々もみな同じことだ。『・』を入れてくれよ。『〇(器、肉体、組織)』を掃除しておかないと『・(魂、中心、神)』は入らないぞ。今度の戦争は、その『〇』の掃除なのだと申してあるだろう。まつり(祭り、政)とは調和させることだと申してあるだろう。この道は教えではないと言ってあるだろう。教会やその他の集会ではないと申してあるだろう。人を集めないでくれと申してあるだろう。世界の人民がみな信者なのだと申してあるだろう。この道は道なき道、時を超えた道、光そのものなのだ。この道によって、すべてが生き返るのだぞ。天明(岡本天明)よ、阿房になりなさい。我を捨てなさい。そうしないと神がかるのに苦しいぞ。
【AIによる解釈】
この帖は「ひふみ神示」の道の特異な性質を強調しています。
- 既存宗教の再生: 特定の宗教を否定するのではなく、魂が抜けた状態(形骸化)になった既存の宗教や教え(天理、金光、黒住、仏教、キリスト教など)に、根源的な生命(たま)を吹き込み、再生させる役割を持つと宣言します。
- 『〇』と『・』の比喩: 『〇』は器、肉体、国家、組織、既存の教えなどを象徴し、『・』は中心となる魂、神性、根源の真理を象徴します。器(〇)をきれいに掃除して初めて、真の魂(・)が入る、という非常に重要な法則を説いています。そして、当時の大戦を、その器を浄化するための「大掃除」であると位置づけています。
- 反宗教組織的な性格: この道は特定の「教」えではなく、教会のような組織や人の集まりを作ることを明確に禁じています。それは、特定の信者を作るのではなく「世界の臣民みな信者」であるという普遍的な道だからです。
- 道なき道: 形式や規則に縛られない、光そのものであると述べ、概念を超えた存在であることを示します。 最後の「阿房になりて呉れよ」は、筆記者である岡本天明、ひいては神示を読むすべての人に対し、人間的な知識や我(が)を捨て、空っぽの器になることで初めて神意を受け取ることができる、という神がかりの極意を説いています。
第十三帖 (一五〇)
【原文】
赤い眼鏡かければ赤く見えると思うてゐるが、それは相手が白いときばかりぞ、青いものは紫にうつるぞ。今の世は色とりどり眼鏡とりどりざから見当とれんことになるのざぞ、眼鏡はづすに限るのぞ、眼鏡はづすとは洗濯することざぞ。上ばかりよくてもならず、下ばかりよくてもならんぞ。上も下も天地そろうてよくなりて世界中の臣民、けものまで安心して暮らせる新(あら)の世に致すのざぞ、取り違へするなよ。九月二十三日、一二。
【現代語訳】
赤い眼鏡をかければ、すべてが赤く見えると思っているかもしれないが、それは見る対象が白い時だけだ。青いものを見れば紫色に見えるだろう。今の世の中は、人それぞれが色とりどりの眼鏡(固定観念や偏見)をかけているから、物事の本当の姿が見当たらなくなっているのだ。その眼鏡を外すに限る。眼鏡を外すとは、心を洗濯(浄化)することだぞ。社会の上層部だけが良くてもダメで、下層部だけが良くてもダメだ。上も下も、天も地も、すべてが揃って良くなって、世界中の人々、さらには獣たちまで安心して暮らせる新しい世にするのだ。この目的を取り違えてはならないぞ。
【AIによる解釈】
この帖は、真実を認識するための障害と、目指すべき世界の姿について説いています。「色とりどりの眼鏡」とは、人々が持つイデオロギー、偏見、固定観念、あるいは信じ込んでいる知識体系のことです。それを通して世界を見る限り、物事のありのままの姿(真実)を捉えることはできず、歪んだ認識しか生まれません。その解決策は、その「眼鏡をはづす」こと、すなわち「心の洗濯」によって、一切の先入観を排して純粋な心で世界を見ることだと説きます。後半では、神の計画の全体像を示します。それは一部の人間や階級だけが救われるのではなく、「上も下も」「けものまで」、つまり社会の全階層、さらには人間以外の生命を含む森羅万象すべてが調和し、安心して暮らせる「新(あら)の世」を創造することであると宣言しています。この全体救済のビジョンを忘れるなと、強く念を押しています。
第十四帖 (一五一)
【原文】
この道分りた人から一柱でも早う出てまゐりて神の御用なされよ。どこに居りても御用はいくらでもあるのざぞ。神の御用と申して稲荷(いなり)下げや狐つきの真似はさせんぞよ。この道はきびしき行(みち)ざから楽な道なのぞ。上にも下(しも)にも花さく世になるのざぞ、後悔は要らぬのざぞ。カミは見通しでないとカミでないぞ、今のカミは見通しどころか目ふさいでゐるでないか。蛙(かえる)いくら鳴いたとて夜あけんぞ。赤児になれよ、ごもく捨てよ、その日その時から顔まで変るのざぞ、神烈しく結構な世となりたぞ。九月二十三日、ひつくのか三。
【現代語訳】
この道の意味が分かった人から、一人でも早く現れ出て、神の御用を務めなさい。どこにいても、やるべき御用はいくらでもあるのだぞ。ただし、神の御用だと言って、低級な霊能者(稲荷下げや狐つき)の真似事はさせないぞ。この道は厳しい道であるからこそ、本当は楽な道なのだ。社会の上にも下にも花が咲く世の中になるのだから、後悔は要らないのだ。神というのは、すべてを見通す力があってこそ神なのだ。今の神々(と称する者たち)は見通すどころか、目を塞いでいるではないか。蛙がいくら鳴いても夜は明けないのだ(偽りの預言者が騒いでも意味はない)。赤子のように純粋になりなさい。心のゴミを捨てなさい。そうすれば、その日から顔つきまで変わるのだぞ。神の働きが激しくなり、素晴らしい世の中になってきたぞ。
【AIによる解釈】
この帖は、真理を理解した者への行動喚起と、そのための心構えを説いています。「分りた人から」行動せよと促し、特別な場所や地位は関係なく、日常生活の中に「神の御用」は無限にあると説きます。しかし、それは奇跡を見せびらかしたり、低級霊と交信したりするような、見栄えのする行為ではないと釘を刺しています。「きびしき行ざから楽な道」という逆説的な表現は、自我を捨て、神意に沿って生きることは、自己流で生きるよりも苦労が少なく、魂にとっては自然で楽な道であることを示しています。後半では、偽りの指導者(目ふさいでゐるカミ、鳴く蛙)を批判し、本当に必要なのは「赤児」のような純粋さと、エゴや執着(ごもく)を捨てることだと強調します。内面が浄化されれば、外見(顔)まで変わり、神の激しい働き(神烈しく)が顕現する、素晴らしい時代が始まっているのだと宣言しています。
第十五帖 (一五二)
【原文】
神の国のカミの役員に判りかけたらバタバタに埒(らち)つくなれど、学や智恵が邪魔してなかなかに判らんから、くどう申しているのざぞ。臣民物言はなくなるぞ、この世の終り近づいた時ぞ。石物言ふ時ぞ。神の目には外国もやまともないのざぞ。みなが神の国ぞ。七王(ななおう)も八王(やおう)も作らせんぞ、一つの王で治めさすぞ。てん詞様が世界みそなはすのざぞ。世界中の罪負ひておはします素盞雄の大神様に気附かんか、盲つんばばかりと申してもあまりでないか。九月の二十三日、ひつ九のか三。
【現代語訳】
神の国(日本)の神的な役目を担う人々に分かりかけたら、物事は一気に片付くのだが、学問や人間の知恵が邪魔をして、なかなかに理解できないから、こうしてくどくどと申しているのだ。やがて人民はものが言えなくなる時が来るぞ。この世の終わりが近づいた時だ。その時、石がものを言うのだ。神の目から見れば、外国も日本もない。すべてが神の国なのだ。七人の王も八人の王も作らせはしない。ただ一つの王で世界を治めさせるのだ。天子様が世界を御覧になるのであるぞ。世界中の罪を背負っておられる素盞雄(スサノオ)の大神様の御神徳に気づかないのか。盲や聾ばかりだと言っても、言い過ぎではないではないか。
【AIによる解釈】
この帖は、変革の鍵を握る人々へのもどかしさと、来るべき世界の姿を語っています。「カミの役員」とは、政治家や官僚など、日本の指導的立場にある人々を指していると考えられます。彼らが人間の「学や智恵」という固定観念を捨てて神意を理解すれば、事態は急速に進展すると述べています。「臣民物言はなくなるぞ。石物言ふ時ぞ」という部分は非常に象徴的で、人間の言論が無力化され、代わって自然物や超常的な現象が真実を語り始めるという、人知を超えた時代の到来を預言しています。世界のあり方については、国境の区別がない「みなが神の国」というグローバルな視点と、世界が「一つの王(てん詞様)」によって霊的に統治されるというビジョンを再度示しています。最後に、罪や穢れを一身に背負い、それを浄化する荒々しい神性を持つ「素盞雄の大神」の働きに気づくよう促しており、これは、現在起きている混乱や破壊が、実は世界を清めるための神の働きの一環であることに目覚めよ、というメッセージです。
第十六帖 (一五三)
【原文】
神が臣民の心の中に宝いけておいたのに、悪にまけて汚して仕まうて、それで不足申してゐることに気づかんか。一にも金、二にも金と申して、人が難儀しようがわれさへよけらよいと申してゐるでないか。それはまだよいのぞ、神の面(めん)かぶりて口先ばかりで神さま神さま てんしさま てんしさま と申したり、頭下げたりしてゐるが、こんな臣民一人もいらんぞ、いざと云ふときは尻に帆かけて逃げ出す者ばかりぞ、犬猫は正直でよいぞ、こんな臣民は今度は気の毒ながらお出直しぞ、神の申したこと一分一厘ちがはんのざぞ、その通りになるのざぞ。うへに唾(つば)きすればその顔に落ちるのざぞ、時節ほど結構なこわいものないぞ、時節来たぞ、あはてずに急いで下されよ。世界中うなるぞ。陸が海となるところあるぞ。今に病神(やまいがみ)の仕組にかかりてゐる臣民苦しむ時近づいたぞ、病はやるぞ、この病は見当とれん病ぞ、病になりてゐても、人も分らねばわれも分らん病ぞ、今に重くなりて来ると分りて来るが、その時では間に合はん、手おくれぞ。この方の神示(ふで)よく腹に入れて病追ひ出せよ、早うせねばフニャフニャ腰になりて四ツん這ひで這ひ廻らなならんことになると申してあらうがな、神の入れものわやにしてゐるぞ。九月二十三日、ひつ九のか三。
【現代語訳】
神が人民の心の中に宝(良心、神性)を活けておいたのに、悪に負けてそれを汚してしまって、その上で不平不満を言っていることに気づかないのか。一にも金、二にも金と言って、他人がどんなに困ろうが自分さえ良ければよいと言っているではないか。それはまだマシな方だ。神の仮面をかぶり、口先だけで「神様、神様」「天子様、天子様」と言ったり頭を下げたりしているが、こんな人民は一人もいらない。いざという時には、真っ先に逃げ出す者ばかりだ。犬や猫の方が正直でよほど良い。こんな人民は、今度は気の毒だがやり直し(死)だ。神の申したことは一分一厘も違わない。その通りになるのだ。天に向かって唾を吐けば、自分の顔に落ちてくるのだぞ。時節ほど素晴らしく、また怖いものはない。その時節が来たのだ。慌てずに、しかし急いで(準備をして)ください。世界中が唸り声をあげるぞ。陸が海になるところもあるのだ。やがて病の神の仕組みにかかった人民が苦しむ時が近づいたぞ。病気が流行るぞ。この病気は原因が見当のつかない病気だ。病気にかかっていても、他人にも分からなければ自分でも分からない病気だ。重症化してくれば分かってくるが、その時では間に合わない。手遅れだ。この神示をよく腹に入れて、病を追い出しなさい。早くしないと、腰が立たなくなり、四つん這いで這い回らなければならなくなると申してあるだろう。神の入れ物である自分の体を無茶苦茶にしているぞ。
【AIによる解釈】
この帖は、現代人の心の荒廃と、それによって引き起こされる災厄について、極めて厳しい言葉で警告しています。
- 内なる宝: 人間の心には本来、神から与えられた宝(神性、良心)があるが、人々はそれを忘れ、金銭欲と利己主義にまみれていると指摘します。
- 偽りの信仰: 口先だけの信仰者を厳しく断罪し、いざという時に頼りにならない見せかけの信仰を徹底的に排除する姿勢を示しています。
- 時節の到来: すべてが清算される「時節」が来たことを宣言。天変地異(陸が海となる)や世界的な混乱(世界中うなる)を預言します。
- 原因不明の病: 最大の警告として、医学では見当のつかない、自覚症状のないまま進行する恐ろしい病の流行を予告しています。これは物理的な病気であると同時に、魂の病、霊的な汚染とも解釈できます。
- 対処法: この病に対する唯一の処方箋は「この方の神示をよく腹に入れる」こと、つまり神示の教えを深く理解し、実践することによって、内側から病を追い出すことだと説いています。肉体を「神の入れもの」と捉え、それを大切にすることが求められています。
第十七帖 (一五四)
【原文】
まことの善は悪に似てゐるぞ、まことの悪は善に似てゐるぞ、よく見分けなならんぞ、悪の大将は光り輝いてゐるのざぞ、悪人はおとなしく見えるものぞ。日本の国は世界の雛形であるぞ、雛形でないところは真の神の国でないから、よほど気つけて居りて呉れよ、一時は敵となるのざから、ちっとも気許せんことぞ、神が特に気つけておくぞ。今は日本の国となりて居りても、神の元の国でないところもあるのざから、雛型見てよく腹に入れておいて下されよ、後悔間に合はんぞ。九月二十三日、ひつ九のか三。
【現代語訳】
真の善は、一見すると悪のように見えることがあるぞ。そして真の悪は、善のように見えることがあるぞ。よく見分けなければならない。悪の大将は光り輝いているものだ。悪人はおとなしく、善人らしく見えるものだ。日本の国は世界の雛形であるぞ。雛形となっていない部分は、真の神の国ではないから、よくよく気をつけていなさい。そういう場所は、一時は敵となるのだから、少しも気を許してはならないぞ。神が特に注意しておく。今は日本の国となっていても、本来の神の国ではない場所もあるのだから、雛形(日本の本来あるべき姿や国土)をよく見て、その意味を腹に入れておきなさい。後から後悔しても間に合わないぞ。
【AIによる解釈】
物事の本質を見抜く「審神者(さにわ)」の能力の重要性を説く帖です。「善が悪に、悪が善に見える」という警告は、表面的な姿や聞こえの良い言葉に惑わされるなという強いメッセージです。特に「悪の大将は光り輝いている」という一節は強烈で、人々を魅了し、善意の仮面をかぶった最も危険な存在を見抜く眼力を求めています。次に、「日本は世界の雛形」というひふみ神示の根幹をなす概念に触れ、その雛形論をさらに深化させています。日本国内で起こることは、やがて世界で起こることの縮図であると同時に、日本国内にも「雛形でないところ」、つまり神の国の理想から外れた場所や勢力が存在すると指摘します。そして、それらは一時的に「敵」として現れると警告しており、これは国内における思想的・霊的な対立が激化することを示唆しています。日本の真の姿を見極め、偽りの部分に惑わされないよう、強く注意を促しています。
第十八帖 (一五五)
【原文】
われよしの政治ではならんぞ、今の政治経済はわれよしであるぞ。臣民のソロバンで政治や経済してはならんぞ、神の光のやり方でないと治まらんぞ、与へる政治がまことの政治ぞよ、臣民いさむ政治とは上下まつろひ合はす政治のことぞ、日の光あるときは、いくら曇っても闇ではないぞ、いくら曇っても悪が妨げても昼は昼ぞ、いくらあかりつけても夜は夜ぞ、神のやり方は日の光と申して、くどう気つけてあらうがな。政治ぞ、これは経済ぞと分けることは、まつりごとではないぞ。神の臣民、魂と肉体の別ないと申してあること分らぬか、神のやり方は人の身魂(からたま)人のはたらき見れは直ぐ分るでないか。腹にチャンと神鎮まって居れば何事も箱さした様に動くのざぞ、いくら頭がえらいと申して胃袋は頭のいふ通りには動かんぞ、この道理分りたか、ぢゃと申して味噌も糞も一つにしてはならんのざぞ。神の政治はやさしい六ヶしいやり方ぞ、高きから低きに流れる水のやり方ぞ。神の印(しるし)つけた悪来るぞ。悪の顔した神あるぞ。飛行機も船も臣民もみな同じぞ。足元に気つけて呉れよ、向ふの国はちっとも急いでは居らぬのぞ、自分で目的達せねば子の代、子で出来ねば孫の代と、気長くかかりてゐるのざぞ、神の国の今の臣民、気が短いから、しくじるのざぞ。しびれ切らすと立ち上がれんぞ、急いではならんぞ、急がねばならんぞ。神の申すこと取り違ひせぬ様にして呉れよ。よくこの神示(ふで)よんで呉れよ、元の二八基(じゃき)光理(こり)てわいて出た現空(あく)の種は二八基(じゃき)と大老智(おろち)と世通足(よつあし)となって、二八基には仁本の角、大老智は八ツ頭、八ツ尾、四通足(よつあし)は金母であるから気つけておくぞ。世通足はお実名に通(つ)いて分けてゐるから、守護神どの、臣民どの、だまされぬ様に致して下されよ。九月二十三日、あのひつ九のか三。
【現代語訳】
自分さえ良ければよいという「我よし」の政治ではダメだ。今の政治や経済は、まさにその「我よし」だ。人民の損得勘定(そろばん)で政治や経済を運営してはならない。神の光に基づいたやり方でなければ、世は治まらないのだ。「与える政治」こそが真の政治であるぞ。人民を勇気づける政治とは、上の者と下の者が和合し敬い合う政治(まつりごと)のことだ。太陽の光がある限り、いくら雲で曇っても闇夜ではない。いくら悪が妨害しても昼は昼なのだ。逆に、夜にいくら明かりをつけても夜は夜だ。神のやり方は太陽の光のようなものだと、くどくど注意してあるだろう。これは政治、これは経済とバラバラに分けることは、本来の政(まつりごと)ではない。神の民において、魂と肉体が分かちがたいものであるのと同じだと、申してあることが分からないか。神のやり方は、人間の体と魂の働きを見ればすぐに分かるではないか。腹(肚)にちゃんと神が鎮座していれば、何事も仕組み通りに動くのだ。いくら頭が偉いと言っても、胃袋は頭の命令通りには動かないだろう。この道理が分かったか。だからと言って、味噌も糞も一緒にしてはならないぞ。神の政治は、易しいようで難しいやり方だ。水が高い所から低い所へ自然に流れるようなやり方だ。神の印をつけた悪が来るぞ。悪の顔をした神もいるぞ。飛行機も船も人民もみな同じことだ。足元(身近なところ)に気をつけなさい。相手の国はちっとも急いではいないのだぞ。自分の代で目的を達成できなければ子の代、子でできなければ孫の代と、気長に計画しているのだ。神の国(日本)の今の人民は気が短いから、しくじるのだ。しびれを切らすと、いざという時に立ち上がれないぞ。急いではならない、しかし急がなければならない。神の申すことを取り違えないようにしてくれ。よくこの神示を読みなさい。(難解な記述)…守護神の方々、人民の方々、騙されないようにしてください。
【AIによる解釈】
この帖は、政治経済の在り方、敵対勢力の性質、そして日本人が陥りやすい過ちについて多角的に論じています。
- 真のまつりごと: 利己的な損得勘定(我よし、ソロバン)に基づく政治経済を否定し、無償の愛のように「与える政治」こそが本物だと説きます。政治・経済・宗教などをバラバラに捉えるのではなく、魂と肉体のように一体のものとして調和させるのが真の「まつりごと」であると定義します。
- 自然の摂理: 神のやり方を、太陽の光や水の流れ、人体の働きといった自然の摂理にたとえ、頭でっかちな理屈ではなく、自然な流れに従うことの重要性を説きます。
- 善悪の見極め: 再び「神の印をつけた悪」「悪の顔した神」という表現で、外見に騙されず本質を見抜くことの重要性を警告します。
- 敵の戦略と日本の弱点: 敵対する国(向ふの国)が非常に長期的(孫の代まで見据える)な戦略を持っているのに対し、日本人は気が短く、焦って失敗しがちであると鋭く指摘します。
- 「急いではならんぞ、急がねばならんぞ」: この有名な一節は、ひふみ神示の核心的な心構えです。目先のことに一喜一憂して慌てる(急ぐ)のではなく、心の準備、魂の浄化は一刻も早く(急がねば)始めなさい、という二重の意味が込められています。 後半の難解な部分は、悪の根源についての神話的な解説と考えられ、その正体を見極め、騙されないようにという警告で締めくくられています。
第十九帖 (一五六)
【原文】】
世成り、神国の太陽足り満ちて、皆みち足り、神国の月神、世をひらき足り、弥栄にひらき、月光、総てはみち、結び出づ、道は極みに極む、一二三(ひふみ)、三四五(みよいづ)、五六七(みろく)、弥栄々々ぞ、神、仏、耶ことごと和し、和して足り、太道ひらく永遠(とわ)、富士は晴れたり、太神は光り出づ、神国のはじめ。九月二十四日、一二ふみ。
【現代語訳】
新しい世が成り、神の国の太陽(日)は満ち足りて、すべてのものが満ち足りる。神の国の月もまた、世を十分に開き、ますます栄えるように開き、その月光によって、全てが満ち、結ばれていく。道は極まりに極まる。ひふみ、みよいづ、みろく(一二三、三四五、五六七)と、ますます栄え、栄えるのだ。神道も仏教もキリスト教(耶蘇)も、ことごとく和合し、和合して満ち足りて、偉大なる道が永遠に開かれる。富士は晴れ渡り、太神(おおかみ)が光り輝き現れる。これぞ、神国の始まりである。
【AIによる解釈】
この帖は、これまでの厳しい警告とは対照的に、来るべき理想世界(みろくの世)の姿を、荘厳で詩的な言葉で高らかに謳い上げています。そこは、太陽(陽、火、男性性)と月(陰、水、女性性)が共に満ち足り、調和する世界です。すべてのものが満たされ、結ばれる「弥栄」の世界です。「一二三、三四五、五六七」という数霊は、物事が順序正しく、段階を経て発展し、最終的に「みろくの世」に到達する宇宙のプロセスを象徴しています。特筆すべきは「神、仏、耶ことごと和し」という一節で、すべての宗教や思想が対立を終え、互いの価値を認め合い、より高次の「太道」へと統合されることを示しています。最後に「富士は晴れたり、太神は光り出づ」と、日本の中心である富士が舞台となり、根源の神が顕現することで、真の「神国のはじめ」が告げられるという、壮大なビジョンで締めくくられています。苦難の先にある、輝かしい希望を描いた帖です。
第二十帖 (一五七)
【原文】
世界に変りたこと出来たら、それは神々様の渡られる橋ぞ。本清めねば末は清まらんぞ、根絶ちて葉しげらんぞ、元の田根(たね)が大切ざぞ、種はもとから択(よ)り分けてあるのざぞ、ぜんぶり苦(にが)いぞ。九月の二十四日、ひつ九のか三。
【現代語訳】
世界に変わった出来事が起きたら、それは神々が(新しい世へ)渡るための橋だと思いなさい。根本を清めなければ、末端は清まらない。根を絶ってしまっては、葉が茂ることはない。元の種が大切なのであるぞ。その種は、元から選び分けられているのだ。全てが苦い(厳しい)のだぞ。
【AIによる解釈】
この帖は、世の中に起こる大変動の霊的な意味と、物事の根本を見ることの重要性を説いています。「世界に変りたこと」とは、大災害や戦争、社会システムの崩壊など、常識を覆すような出来事を指します。人々はそれを不幸や混乱としか見なさないかもしれませんが、神示はそれを「神々様の渡られる橋」、つまり新しい時代へ移行するために不可欠なプロセスであると捉えさせようとします。そして、問題解決のためには、表面的な現象(末)を追うのではなく、その原因となっている「本(もと)」や「根」を清めることが不可欠であると強調します。「元の田根(たね)」とは、個人の魂の在り方、国家の理念、人類の集合意識などを指すと考えられます。最後に「種はもとから択り分けてある」「ぜんぶり苦いぞ」と締めくくることで、この立て分けのプロセスが厳格であり、誰にとっても厳しい試練となることを示唆しています。
第二十一帖 (一五八)
【原文】
神界のことは顕界ではなかなかに分るものでないと云ふこと分りたら、神界のこと分るのであるぞ。一に一足すと二となると云ふソロバンや物差しでは見当取れんのざぞ。今までの戦でも、神が蔭から守ってゐること分るであらうがな、あんな者がこんな手柄立てたと申すことあらうが、臣民からは阿房に見えても、素直な人には神がかかり易いのであるから、早う素直に致して呉れよ。海のつなみ気をつけて呉れ、前に知らしてやるぞ。九月二十五日、ひつ九のか三。
【現代語訳】
神の世界のことは、この現実世界(顕界)の常識ではなかなか分かるものではない、ということが分かった時に、初めて神界のことが分かってくるのである。1+1=2というような、そろばんや物差し(論理や計算)では見当がつかないのだ。これまでの戦争でも、神が陰から守っていたことが分かるだろう。意外な人物があのような手柄を立てた、というようなことがあるだろうが、人々からは愚か者に見えても、素直な人には神がかりやすいのであるから、早く素直な心になりなさい。海の津波に気をつけてくれ。事前に知らせてやるぞ。
【AIによる解釈】
この帖は、神の計画を理解するための「認識の転換」を求めています。人間の論理や合理性(ソロバンや物差し)の限界を認め、人知を超えた領域が存在することを謙虚に受け入れること。それが、神の世界を理解する第一歩であると説きます。「神界のことは顕界ではなかなかに分るものでないと云ふこと分りたら、神界のこと分る」という逆説的な言い回しは、まさにそのことを表しています。また、神の働きは、社会的に評価されている賢い人や有力者ではなく、一見「阿房」に見えるような「素直な人」を通して現れることを示唆しています。これは、我欲や知識が邪魔をせず、神意を受け入れる「器」として純粋であることの重要性を強調しています。最後に「海のつなみ」という具体的な災害を予告し、神からの警告が事前に与えられることを示唆しています。
第二十二帖 (一五九)
【原文】
われが助かろと思ふたら助からぬのざぞ、その心われよしざぞ。身魂みがけた人から救ふてやるのざぞ、神うつるのざぞ、『〇』のうつりた人と『〇』のかかりた人との大戦ぞ、『〇』と『〇』とが戦して、やがては『〇』を中にして『〇』がおさまるのぞ。その時は『〇』でなく、『〇』も『〇』でないのざぞ、『〇』となるのざぞ、『〇』と『〇』のまつりぞと申してあらうがな。どちらの国も潰れるところまでになるのぞ、臣民同士は、もう戦かなはんと申しても、この仕組成就するまでは、神が戦はやめさせんから、神がやめる訳に行かんから、今やめたらまだまだわるくなるのぞ、『〇』の世となるのぞ、『〇』の世界となるのぞ。今の臣民九分通り『〇』になりてゐるぞ、早う戦すませて呉れと申してゐるが、今 夜明けたら、臣民九分通りなくなるのざぞ。お洗濯第一ざぞ。九月の二十六日、ひつ九のか三。 ※原文の伏せ字『〇』は、文脈から神、悪、キ、カミなどを当てて解釈します。
【現代語訳】
自分が助かろうと思ったら助からないのだぞ。その心は「我よし(利己主義)」だからだ。身魂が磨けた人から救ってやるのだ。神がその人に移るのだ。神(カミ)が移った人と、悪神(アク)がかかった人との大戦争なのだ。神(カミ)と悪(アク)とが戦をして、やがてはキ(十字・和合の象徴)を中心として、神(カミ)が治めるのだ。その時には、悪(アク)は悪でなくなり、神(カミ)も(対立概念としての)神ではなくなるのだ。キ(究極の調和体)となるのだ。火(カ)と水(ミ)の祭り(まつり・調和)だと申してあるだろう。どちらの国も、一度は潰れるというところまでいくのだ。人民同士は「もう戦争は敵わない」と言っても、この神の仕組みが成就するまでは、神が戦争を止めさせないのだ。神が止めるわけにはいかないからだ。今、中途半端に止めたら、まだまだ悪くなるのだ。悪の世となるのだ。獣の世界となるのだ。今の人民は九分通りが獣(けもの)になりきっているぞ。「早く戦争を終わらせてくれ」と言っているが、もし今すぐ夜明け(最終段階)が来たら、人民の九分通りはいなくなってしまうのだぞ。だから、まずはお洗濯(浄化)が第一なのだ。
【AIによる解釈】
この帖は、来るべき最終戦争の霊的な本質と、浄化の必要性を説いています。
- 救済の条件: 「われよし」の心を捨てることが救われる絶対条件であり、救済とは「神うつる」こと、すなわち身魂が磨かれ、神と一体化することであると定義します。
- 霊的大戦の本質: この戦争は国家間の争いという側面だけでなく、本質的には「神(カミ)のうつりた人」と「悪神(アク)のかかりた人」との霊的な代理戦争であると明かします。
- 対立から和合へ: 最終的には、神と悪という二元的な対立(カとミの戦い)が、「キ(十字)」という象徴で示される高次の次元で和合・統合(まつり)され、対立そのものが消滅することを示唆しています。
- なぜ戦いをやめさせないか: 戦争という悲劇を神が止めないのは、それが不完全なものを徹底的に浄化するための「お洗濯」だからであると説明します。中途半端に終わらせれば、根本的な悪(獣性)が残り、さらに悪い世の中になるため、徹底的に膿を出し切る必要があるのです。
- 九分通りの危機: 「今 夜明けたら、臣民九分通りなくなる」という厳しい言葉は、多くの人々がまだ霊的に夜明けを迎える準備ができていないことへの強い警告です。だからこそ、最終的な立て分けの前に、まず「お洗濯」が必要なのだと強調しています。
第二十三帖 (一六〇)
【原文】
この神示 心で読みて呉れよ、九エたして読みて呉れよ、病も直るぞ、草木もこの神示よみてやれば花咲くのざぞ。この道広めるには教会のやうなものつとめて呉れるなよ、まとゐを作りて呉れるなよ。心から心、声から声、身体(からだ)から身体へと広めて呉れよ、世界中の臣民みなこの方の民ざから、早う伝へて呉れよ。神も人も一つであるぞ、考へてゐては何も出来ないぞ、考へないで思ふ通りにやるのが神のやり方ぞ、考へは人の迷ひざぞ、今の臣民 身魂くもりてゐるから考へねばならぬが、考へればいよいよと曇りたものになる道理分らぬか。一九(ひく)れを気つけて呉れよ、日暮れよくなるぞ、日暮れに始めたことは何でも成就するやうになるのざぞ、一九(ひく)れを日の暮れとばかり思うてゐると、臣民の狭い心で取りてゐると間違ぶぞ。『〇』(くに)のくれのことを申すのざぞ。九月の二十八日、ひつ九のか三。 ※『〇』は「世」または「国」と解釈。
【現代語訳】
この神示は、心で読みなさい。言霊の力を込めて(声に出して)読みなさい。そうすれば病気も治るぞ。草木にこの神示を読んでやれば、花が咲くのだぞ。この道を広めるのに、教会のような組織を作ってはならない。集団(まとゐ)を作ってはならないぞ。心から心へ、声から声へ、体から体へと広めてくれよ。世界中の人民はみな、この神の民なのだから、早く伝えてくれよ。神も人も本来一つなのだ。考えてばかりいては何もできないぞ。考えずに、思う通りにやることこそが神のやり方なのだ。考えは人間の迷いなのだ。今の人民は身魂が曇っているから考えなければならないが、考えれば考えるほど、ますます曇ってしまうという道理が分からないか。「ひくれ(一九れ)」に気をつけなさい。日の暮れ方が良くなるぞ。日暮れに始めたことは何でも成就するようになるのだ。「ひくれ」を単なる日没のことだと思っていると、人民の狭い心で解釈することになり、間違うぞ。世(くに)の暮れ(終わり)のことを申しているのだぞ。
【AIによる解釈】
この帖は、神示の正しい読み方、広め方、そして神的な生き方について述べています。
- 神示の力: 神示は単なる文字ではなく、言霊の力を持つ生きたエネルギー体であると説きます。心で感じ、声に出して読むことで、人や草木さえも癒し、活性化させる力があるとします。
- 伝達方法: 組織や集団を作らず、「心から心へ」という、人と人との直接的で有機的な繋がりによって広めることを指示しています。これは、教義や規則で縛るのではなく、共感と共鳴によって自然に伝播していくことを意図しています。
- 直感の重視: 「考へは人の迷ひ」と断じ、人間的な思考や計算を捨て、直感(思う通りにやる)に従うことこそが「神のやり方」であると説きます。思考は曇った身魂が生み出すものであり、それに頼るほど迷いは深まるという、霊的な真理を指摘しています。
- 「ひくれ」の謎: 「ひくれ」は、単なる日没ではなく「世の暮れ」、つまり一つの時代の終わりを指す言葉だと明かされます。しかし、その終わりは絶望ではなく「よくなる」とされ、時代の終わりに始めることこそが成就するという、逆説的な希望を示しています。これは、古い価値観が崩壊する混乱期こそが、新しい世界を創造する絶好の機会であることを示唆しています。
第二十四帖 (一六一)
【原文】
この方 明神(みょうじん)とも現はれてゐるのざぞ、臣民守護の為に現われてゐるのであ るぞ。衣(ころも)はくるむものであるぞ、くるむとは、まつらふものぞ、神の衣は人であ るぞ、汚(けが)れ破れた衣では神はいやざぞ。衣は何でもよいと申すやうなものではないぞ、暑さ寒さ防げばよいと申す様な簡単なものではないぞ。今は神の衣なくなってゐる、九分九厘の臣民、神の衣になれないのざぞ。悪神の衣ばかりぞ、今に臣民の衣も九分九厘なくなるのざぞ。『〇』(かくりよ)の国、霊の国とこの世とは合せ鏡であるから、この世に映って来るのざぞ、臣民 身魂洗濯して呉れとくどう申してあらうがな、この道理よく分りたか。十月とは十(かみ)の月ぞ、『〇』(ひ)と『〇』(つき)との組みた月ぞ。九月の二十八日、ひつ九のか三。 ※『〇』は文脈から、かくりよ、火、月などを当てて解釈。
【現代語訳】
この神(ひつくの神)は、明神(姿を明らかに示す神)としても現れているのだぞ。人民を守護するために現れているのだ。衣とは、体を包む(くるむ)ものである。包むとは、和合し従う(まつらう)ことだ。神の衣とは、人間のことであるぞ。汚れて破れた衣(人間)を、神は嫌うのだぞ。衣は何でもよいというものではない。暑さ寒さを防げればよいというような、簡単なものではないのだ。今や、神が着るにふさわしい衣(清められた人間)がいなくなっている。九分九厘の人民は、神の衣にはなれないのだ。悪神の衣ばかりになっている。やがて、人民の(肉体という)衣も九分九厘がなくなるのだぞ。隠れたる世(霊界)とこの世とは合わせ鏡なのだから、(霊界の出来事が)この世に映ってくるのだ。人民よ、身魂を洗濯してくれと、くどくど申してあるだろうが。この道理がよく分かったか。十月とは十(かみ)の月だぞ。火(ひ)と月(つき)とが組み合わさった月だぞ。
【AIによる解釈】
この帖は、人間と神の関係を「衣」という比喩で解き明かし、霊界と現界の法則を説いています。
- 神の衣としての人間: 人間は、神がこの世で活動するための媒体、すなわち「衣」であるという重要な概念を示しています。神がその力を現すためには、その器となる人間が清められている必要があります。「汚れ破れた衣」では、神は宿ることができないのです。
- 悪神の衣: 現代人の多くは魂が汚れ、「悪神の衣」となってしまっていると厳しく指摘します。
- 合わせ鏡の法則: 霊界(かくりよ)と現実世界(この世)は「合わせ鏡」であり、霊界の乱れや浄化が、そのまま時間差を置いて現実世界に現象として映し出されるという霊的法則を明かしています。
- 身魂洗濯の必然性: したがって、現実世界を良くするためには、まず自らの内面世界、すなわち「身魂」を洗濯することが不可欠である、という結論に至ります。「臣民の衣も九分九厘なくなる」という警告は、霊的な浄化ができない者は、肉体という衣さえ維持できなくなる(=死)という厳しい未来を示唆しています。
- 十月の意味: 「十月」を火(陽)と月(陰)が組み合わさる、陰陽統合の象徴的な月であると示唆しています。
第二十五帖 (一六二)
【原文】
新しくその日その日の生まれ来るのぞ、三日は三日、十日は十日の神どの守るのざぞ、時の神ほど結構な恐い神ないのざぞ、この方とて時節にはかなはんことあるのざぞ。今日なれば九月の二十八日であるが、旧の八月十一どのを拝みて呉れよ、二十八日どのもあるのざぞ。何事も時待ちて呉れよ、炒豆(いりまめ)にも花咲くのざぞ、この世では時の神様、時節を忘れてはならんぞ、時は神なりぞ。何事もその時節来たのざぞ、時過ぎて種蒔いてもお役に立たんのであるぞ、草物いふぞ。旧の八月の十一日、ひつ九のか三。
【現代語訳】
日々、新しく生まれ変わっていくのだ。三日には三日の、十日には十日の神が、それぞれ守っているのだぞ。時の神ほど素晴らしく、また恐ろしい神はないのだ。この神(ひつくの神)でさえ、時節にはかなわないことがあるのだ。今日は(新暦の)九月二十八日であるが、旧暦の八月十一日の神も拝んでくれよ。(新暦の)二十八日の神もいるのだぞ。何事も時を待ちなさい。炒った豆にさえ花が咲く(あり得ないことも時節が来れば起こる)のだぞ。この世では、時の神様、つまり時節を忘れてはならない。時とは神そのものなのだ。何事においても、その時節が来たのだ。時を過ぎてから種を蒔いても、役には立たないのだぞ。草がものを言う時が来るぞ。
【AIによる解釈】
この帖のテーマは、絶対的な力を持つ「時」という神です。
- 日々是新: 宇宙も人間も固定されたものではなく、「その日その日」に新しく生成され、異なる「時の神」によって支配されているという、ダイナミックな世界観を示しています。
- 時の絶対性: 根源神である「この方」でさえ「時節にはかなはん」と述べることで、「時」の持つ力が宇宙の根本法則であることを強調しています。
- 時を待つ: 「炒豆にも花咲く」という奇跡は、人間の力ではなく「時」の力によってもたらされると説き、焦らずに適切なタイミング(時節)を待つことの重要性を示唆します。
- 時は神なり: 「時」を単なる時間の流れではなく、神格を持つ存在として捉えるよう促します。すべての物事にはふさわしい「旬」があり、それを逃せば努力は実らないと戒めています。
- 時節の到来: そして今こそが、まさにその「何事もその時節来た」重大な転換期であると宣言しています。「草物いふぞ」とは、常識では考えられないことが起こる時代の始まりを告げる言葉です。
第二十六帖 (一六三)
【原文】
雨の日は傘いるのざと申して晴れたら要らぬのざぞ、その時その時の御用あるのざぞ、晴れた日とて傘いらぬのでないぞ、今 御用ある臣民と、明日 御用ある臣民とあるのざぞ、二歳(ふたつ)の時は二歳の着物、五歳(いつつ)は五歳、十歳(とう)は十歳の着物あるのざぞ。十柱の御役もその通りざぞ、役変るのぞ。旧八月の十二日、ひつ九のか三。
【現代語訳】
雨の日には傘がいるが、晴れたら普通は要らない。その時々に応じて、必要な御用(役割)があるのだ。しかし、晴れた日とて、日傘として傘が必要なこともあるように、物事は単純ではないぞ。今、御用のある人と、明日になってから御用が出てくる人がいるのだ。二歳の時には二歳の着物があり、五歳には五歳の、十歳には十歳の着物があるだろう。十柱の神々の役目もその通りで、時と共に役目は変わっていくのだぞ。
【AIによる解釈】
この帖は、役割(御用)の流動性と多様性について、分かりやすいたとえで説いています。人はそれぞれに役割を持っていますが、その役割は固定的ではなく、「その時その時」の状況に応じて変化するものであると教えています。今は目立たない人でも、未来には重要な役割を担うかもしれません(明日 御用ある臣民)。また、年齢や成長段階に応じてふさわしい衣服があるように、個人の霊的な成長度合いや状況に応じて、担うべき役割も変わっていきます。「十柱の御役もその通り」とあるように、これは人間だけでなく、神々の世界においても同様の法則が働いていることを示唆しています。一つの役割や現在の状況に固執せず、変化に柔軟に対応することの重要性を説く帖です。
第二十七帖 (一六四)
【原文】
天地には天地の、国には国の、びっくり箱あくのざぞ、びっくり箱あけたら臣民みな思ひが違ってゐること分るのぞ、早う洗濯した人から分るのぞ、びっくり箱あくと、神の規則通りに何もかもせねばならんのぞ、目あけて居れん人出来るぞ、神の規則は日本も支那も印度もメリカもキリスもオロシヤもないのざぞ、一つにして規則通りが出来るのざから、今に敵か味方か分らんことになりて来るのざぞ。学の世はもう済みたのぞ、日に日に神力あらはれるぞ、一息入れる間もないのぞ。ドシドシ事を運ぶから遅れんやうに、取違ひせんやうに、慌てぬやうにして呉れよ。神々様もえらい心配なされてござる方あるが、仕組はりうりう仕上げ見て下されよ。旧九月になればこの神示(ふで)に変りて天(アメ)の日つくの神の御神示出すぞ、初めの役員それまでに引き寄せるぞ、八分通り引き寄せたなれど、あと二分通りの御役の者 引き寄せるぞ。おそし早しはあるなれど、神の申したこと一厘もちがはんぞ、富士は晴れたり日本晴れ、おけ。十月の四日、ひつ九のか三ふみ。
【現代語訳】
天地には天地の、国には国の「びっくり箱」が開くのだぞ。そのびっくり箱を開けたら、人民はみな、自分たちの思い込みが間違っていたことに気づくのだ。早く心を洗濯した人から、その真相が分かってくる。びっくり箱が開くと、何もかも神の規則通りにしなければならなくなるのだ。あまりのことに、目を開けていられない人が出てくるぞ。神の規則には、日本も中国もインドもアメリカもイギリスもロシアもない。世界が一つになって、神の規則通りになるのだから、やがて敵か味方かの区別がつかないような状況になってくるのだぞ。学問の世はもう終わった。日に日に神の力が現れてくるぞ。一息入れる暇もないほどだ。どんどん事を運ぶから、遅れないように、取り違えないように、慌てないようにしてくれ。神々の中にも、大変心配されている方がいらっしゃるが、この仕組みは見事に仕上げてみせるから、見ていてください。旧暦の九月になれば、この神示は「天の日つくの神」の御神示に変わるぞ。最初の役員をそれまでに引き寄せる。八割方は引き寄せたが、あと二割の役員を引き寄せるのだ。遅い早いはあっても、神の申したことは一厘も違わないぞ。富士は晴れたり日本晴れ、それで良い。
【AIによる解釈】
この帖は、大峠のクライマックスである「びっくり箱」が開く様相と、その後の世界の姿を預言しています。
- びっくり箱の開封: これは、既存の価値観、常識、世界秩序が根底から覆るような、衝撃的な出来事を象徴しています。この出来事によって、人々は自らの思い込みの間違いを悟ります。
- 神の規則の顕現: びっくり箱が開いた後は、人為的な法律や国境、イデオロギーは意味をなさなくなり、全人類に共通の、普遍的な「神の規則」に従うしかない時代が到来します。
- 敵味方の消滅: 国家間の対立構造が崩壊し、「敵か味方か分らんことになりて来る」という、これまでの国際関係が通用しない状況が出現します。
- 加速する神の計画: 「学の世」の終わりと「神力」の顕現を宣言し、事態が息つく暇もなく急展開することを予告しています。
- 神示の移行と役員の結集: 旧九月という具体的な時期を区切りとし、神示の内容がより高次のもの(天の日つくの神)に移行すること、そしてそれを実行する中心的な役員が最終的に揃うことを示しています。「富士は晴れたり日本晴れ」は、全ての準備が整い、計画が最終段階に入る高らかな宣言です。
第二十八帖 (一六五)
【原文】
神の国には神の国のやり方、外国には外国のやり方あると申してあらうがな、戦もその通りぞ、神の国は神の国のやり方せねばならんのざぞ、外国のやり方真似ては外国強いのざぞ、戦するにも身魂みがき第一ぞ。一度に始末することは易いなれど、それでは神の国を一度は丸つぶしにせねばならんから、待てるだけ待ってゐるのざぞ、仲裁する国はなく、出かけた船はどちらも後へ引けん苦しいことになりて来るぞ、神気つけるぞ。十月六日、ひつくのか三。
【現代語訳】
神の国(日本)には神の国のやり方があり、外国には外国のやり方があると申してあるだろう。戦争もその通りだ。神の国は、神の国の戦い方をしなければならないのだ。外国のやり方を真似ていては、外国の方が強いに決まっている。戦をするにおいても、身魂を磨くことが第一なのだ。一度に全てを始末(立て替え)することは簡単だが、そうすると神の国(日本)を一度は丸潰しにしなければならなくなるから、待てるだけ待っているのだ。仲裁に入る国はなく、一度出てしまった船(戦争)は、どちらの側も後には引けない苦しい状況になってくるぞ。神が気をつけておく。
【AIによる解釈】
この帖は、日本のとるべき独自の戦略と、当時の国際情勢の厳しさについて述べています。「神の国のやり方」とは、物質的な兵力や経済力に頼る「外国のやり方」とは異なり、「身魂みがき」を第一とする精神的・霊的なアプローチを指します。物質的な土俵で戦えば、物量に勝る外国に勝つことはできない。しかし、霊的な次元で戦えば、日本には独自の勝ち筋がある、と示唆しています。後半では、神が最終的な立替えを「待ってゐる」理由が明かされます。それは、日本の民を思う親心から、日本が完全に破壊されるという最悪の事態を避けるためです。しかし、情勢は厳しく、誰も仲裁できず、両者ともに引くに引けない泥沼の状況に陥ることを預言しており、極めて切迫した状況認識が示されています。
第二十九帖 (一六六)
【原文】
天明は神示書かす御役ぞ、蔭の役ぞ、この神示はアとヤとワのつく役員から出すのざぞ、おもてぞ。旧九月までにはその御方お揃ひぞ、カのつく役員うらなり、タのつく役員おもてなり、うらおもてあると申してあらうがな、コトが大切ぞコトによりて伝へるのが神はうれしきぞ、文字は通基(つき)ぞ、このことよく心得よ。天の異変は人の異変ぞ、一時は神示も出んことあるぞ、神示よんで呉れよ、神示よまないで臣民勝手に智恵絞りても何にもならんと申してあらうがな、神にくどう申さすことは神国の臣民の恥ぞ。神示は要らぬのがまことの臣民ぞ、神それぞれに宿りたら神示要らぬのざぞ、それが神世の姿ぞ。上に立つ人にこの神示分るやうにして呉れよ、国は国の、団体(まとひ)は団体(まとひ)の上の人に早う知らして呉れよ。アとヤとワから表に出すと上の人も耳傾けるのざぞ。アとはアイウエオぞ、ヤもワも同様ぞ、カはうらぞ、タはおもてぞ、サとナとハとマとまつはりて呉れよ、ラは別の御役ぞ、御役に上下ないぞ、みなそれぞれ貴い御役ぞ。この神示 上つ巻と下つ巻 先づ読みて呉れよ、腹に入れてから神集(かむつど)ふのぞ、神は急けるぞ。山の津波に気つけよ。十月の七日、七つ九のか三。
【現代語訳】
天明(岡本天明)は神示を書かされる役目であり、陰の役である。この神示は、「ア」「ヤ」「ワ」の音で始まる名前の役員から表に出すのだぞ。それが表の役だ。旧暦の九月までには、その方々がお揃いになる。「カ」の音の役員は裏、「タ」の音の役員は表である。裏と表があると申してあるだろう。言(コト)が大切であり、言(コト)によって伝えることを神は嬉しく思うのだ。文字はそれに付随するものである。このことをよく心得なさい。天の異変は人の心の異変が映ったものだ。一時は神示が出なくなることもあるぞ。その時は、これまでの神示を読んでくれ。神示を読まずに人民が勝手に知恵を絞っても、何にもならないと申してあるだろう。神にくどくど同じことを言わせるのは、神の国の民として恥ずかしいことだ。本当は、神示が要らなくなるのが真の民の姿なのだ。一人ひとりに神が宿れば、神示など要らなくなる。それが神の世の姿なのだ。上に立つ人々にこの神示が分かるようにしてくれ。国や団体の指導者に早く知らせてくれ。「ア」「ヤ」「ワ」の役員から表に出せば、上の人々も耳を傾けるだろう。「ア」とはア行、「ヤ」も「ワ」も同様だ。「カ」は裏、「タ」は表。「サ」「ナ」「ハ」「マ」の役員は、それらを補佐してくれ。「ラ」はまた別の役目だ。役目に上下はない。みなそれぞれに貴い役目なのだ。この神示の「上つ巻」と「下つ巻」をまず読んでくれ。腹に入れてから、神の集いを開くのだ。神は急いでいるぞ。山の津波(山津波、土砂災害)に気をつけよ。
【AIによる解釈】
この帖は、神示を世に出すための具体的な計画と組織論、そして神示の究極的な役割について述べています。
- 陰陽の役員: 神示を自動書記する岡本天明は「蔭の役」であり、それを世に広める「おもての役」がいることを明かしています。役員の名前の頭文字を言霊(ア・ヤ・ワ・カ・タ等)で示し、それぞれに裏表の役割があるという、緻密な計画が存在することを示唆しています。
- 言(コト)と文字: 文字よりも、その奥にある「言(コト)」、すなわち真理や意志そのものが重要であると説きます。
- 神示の役割の変遷: 危機が迫ると一時的に神示が止まる可能性があること、その際は過去の神示を読み返すことが重要であると述べます。しかし、究極の理想は、人々が覚醒し、一人ひとりが神と直接つながることで「神示が要らぬ」世界(神世)が来ることだと示しています。神示はそこに至るまでの、あくまでも杖なのです。
- 指導者への伝達: この神示をまず社会の「上に立つ人」に理解させることが急務であると強調しています。
- 具体的な指示と警告: 読むべき巻物(上つ巻・下つ巻)、そして具体的な災害「山の津波」への警告など、実践的な指示で締めくくられています。
第三十帖 (一六七)
【原文】
一度に立替へすると世界が大変が起るから、延ばし延ばしてゐるのざぞ、目覚めぬと末代の気の毒できるぞ。国取られた臣民、どんなにむごいことになりても何も言ふこと出来ず、同じ神の子でありながら余りにもひどいやり方、けものよりもむごいことになるのが、よく分りてゐるから、神が表に出て世界中救ふのであるぞ、この神示腹に入れると神力出るのざぞ、疑ふ臣民沢山あるが気の毒ざぞ。一通りはいやがる臣民にもこの神示一二三(ひふみ)として読むやうに上の人してやりて下されよ。生命あるうちに神の国のこと知らずに死んでから神の国に行くことは出来んぞ、神の力でないと、もう世の中は何うにも動かんやうになってゐること、上の番頭どの分かりて居らうがな、何うにもならんと知りつつ まだ智や学にすがりてゐるやうでは上の人とは申されんぞ、智や学越えて神の力にまつはれよ、お土拝みて米作る百姓さんが神のまことの民ぞ、神おろがみて神示取れよ、神のない世とだんだんなりておろがな。真通(まつ)ることは生かす事ぞ。生かす事は能(はたら)かす事ぞ。神の国には何でもないものないのざぞ、神の御用なら何でも出て来る結構な国ぞ、何もなくなるのは やり方わるいのぞ、神の心に添はんのぞ。十月七日、一二。
【現代語訳】
一度に立て替えをすると、世界に大変なことが起きるから、延ばし延ばしにしているのだ。しかし、このまま目覚めなければ、末代までの気の毒な事態が起きてしまうぞ。国を奪われた人民が、どんなに惨い仕打ちを受けても何も言えず、同じ神の子でありながら、あまりにも酷い、獣以下の扱いを受けることになるのが、よく分かっているからこそ、神が表に出て世界中を救うのである。この神示を腹に入れると神力が現れるのだ。疑う人民がたくさんいるが、気の毒なことだ。ひとまずは、嫌がる人民にも、この神示を(数え歌のように)ひふみとして読ませるように、上の立場の人は計らってやってください。生きているうちに神の国の真理を知らずに、死んでから神の国に行くことなどできないのだ。もはや神の力でなければ、世の中はどうにも動かせなくなっていることに、指導的立場(番頭)の方々は分かっているだろう。どうにもならないと知りつつ、まだ人間の知恵や学問にすがっているようでは、上の人とは言えないぞ。知恵や学問を超えて、神の力に従いなさい。土を拝んで米を作る百姓こそが、神の真の民であるぞ。神を拝んで、神示を受け取りなさい。世の中はだんだんと神のいない世になってしまっているではないか。真に通じること(まつること)は、生かすことだ。生かすことは、働かせることだ。神の国には、本来、無いものは何もないのだ。神の御用のためなら、何でも出てくる素晴らしい国なのだ。物がなくなるのは、やり方が悪いのだ。神の心に沿っていないからだ。
【AIによる解釈】
この帖は、神の慈悲と警告、そして指導者への叱咤激励が込められています。
- 立替えの遅延: 神が最終的な立替えを遅らせているのは、人々の苦しみを最小限にしたいという親心からであると説明します。しかし、それには限界があり、このままでは占領下で「けものよりもむごいことになる」という悲惨な未来が待っていると警告します。
- 神力の源: 神示を信じ、腹に入れる(深く理解・実践する)ことが、超自然的な力(神力)を得る鍵であると説きます。
- 指導者への叱咤: 社会の指導者(上の番頭どの)が、事態の行き詰まりを認識しながらも、旧来の価値観(智や学)に固執していることを厳しく批判します。真の指導者なら、人知を超えた「神の力」に頼るべきだと促します。
- まことの民: 自然と共に生き、土に感謝する「百姓」こそが、神の心に近い「まことの民」の姿であるとします。これは、観念的・理論的な信仰よりも、素朴で実践的な信仰の尊さを説いています。
- 真通る(まつる)の定義: 「まつる」ことを「生かす」こと、「働かす」ことと定義し、本来、神の国(日本)には無限の豊かさがあるにもかかわらず、それが失われているのは、人々のやり方が神の心に沿っていないからだと断じています。
第三十一帖 (一六八)
【原文】
この神示読ますやうにするのが役員の務めでないか、役員さへ読んでゐないではないか。神示に一二三(ひふみ)つけたもの先づ大番頭、中番頭、小番頭どのに読まして呉れよ、道さへつければ読むぞ、腹に這入るものと這入らぬものとはあるなれど、読ますだけは読ませてやるのが役員の勤めでないか。旧九月になったら、いそがしくなるから、それまでに用意しておかんと悔しさが出るぞよ。いざとなりて地団太ふんでも間に合はんぞ。餅搗くには、搗く時あるのざぞ、それで縁ある人を引き寄せてゐるのざぞ、神は急けるのぞ。十月の七日、ひつ九のか三いそぐ。
【現代語訳】
この神示を人々に読ませるようにするのが、役員の務めではないのか。その役員さえ、ろくに読んでいないではないか。神示に読み仮名(ひふみ)をつけたものを、まずは大番頭、中番頭、小番頭(社会の各階層の指導者)に読ませてくれ。読むきっかけさえ作ってやれば、彼らも読むのだ。内容がすんなり腹に入る者と入らない者とがいるだろうが、とにかく読ませるだけは読ませてやるのが、役員の勤めではないのか。旧暦の九月になったら、忙しくなるから、それまでに用意しておかないと、後で悔しい思いをするぞ。いざという時になって、地団駄を踏んでも間に合わないのだ。餅を搗くには、搗くべき時があるのだ。そうやって、縁のある人々を引き寄せているのだ。神は急いでいるのだぞ。
【AIによる解釈】
この帖は、神示を広める役目を担う人々への、極めて具体的な指示と強い叱咤激励です。役員自身がまず神示を真剣に読んでいないという現状を嘆き、その怠慢を厳しく指摘しています。そして、社会の指導的立場にある人々(大・中・小の番頭)に、何とかしてこの神示を読ませる努力をするよう命じています。理解できるかできないかは二の次で、まずは触れさせること自体が重要であるとしています。「旧九月」という期限を再び切り、それ以降、事態が急激に展開し、準備が間に合わなくなることを警告しています。「餅搗くには、搗く時ある」とは、物事には絶好のタイミングがあり、今がまさにその時であるということ。「神は急ける」という言葉が繰り返され、事態の切迫感を強く伝えています。
第三十二帖 (一六九)
【原文】
仕組通りに出て来るのざが大難を小難にすること出来るのざぞ。神も泥海は真っ平ぞ、臣民喜ぶほど神うれしきことないのざぞ、曇りて居れど元は神の息入れた臣民ぞ、うづであるのぞ。番頭どの、役員どのフンドシ締めよ。十月の七日、ひつ九のか三。
【現代語訳】
神の仕組み通りに物事は起こってくるのだが、人々の努力次第で、大難を小難にすることはできるのだぞ。神も、世の中が泥の海のようになることは真っ平御免なのだ。人民が喜ぶことほど、神にとって嬉しいことはないのだ。今は曇ってはいるが、元はと言えば神の息を吹き入れた人民なのだ。神の子(うづ)なのだぞ。番頭の方々、役員の方々、ふんどしを締め直して気合いを入れなさい。
【AIによる解釈】
この帖は、ひふみ神示における非常に重要な救いのメッセージを含んでいます。未来は完全に決定された宿命ではなく、これから起こる「大難」を、人々の心構えと行動次第で「小難」に軽減することが可能であると明言しています。これは、運命は変えられるという希望の光です。神の願いは、人々を罰することではなく、人々が喜んで暮らすことであり、決して破滅(泥海)を望んでいるわけではないと、神の親心を吐露しています。「元は神の息入れた臣民ぞ」という言葉は、人間の本質が神聖なものであることを思い出させ、その可能性を信じよというメッセージです。最後の「フンドシ締めよ」は、その可能性を現実のものとするために、指導者たちが覚悟を決めて本気で取り組むことを強く要求する言葉です。
第三十三帖 (一七〇)
【原文】
エドの仕組すみたらオワリの仕組にかからすぞ。その前に仕組む所あるなれど、今では成就せんから、その時は言葉で知らすぞ。宝持ちくさりにして呉れるなよ、猫に小判になりて呉れるなよ。天地一度に変ると申してあること近づいたぞ、世は持ちきりにはさせんぞよ、息吹(いぶ)き払ひて議論(ろん)なくするぞ、ことなくするぞ、物言はれん時来るぞ、臣民見当とれんことと申してあらうが、上の人つらくなるぞ、頑張りて呉れよ。十月八日、ひつ九のか三。
【現代語訳】
江戸(東京)での仕組みが済んだら、尾張(終わり)の仕組みにかからせるぞ。その前に仕組みを仕掛ける場所もあるが、今では成就しないから、その時が来たら言葉で知らせる。宝(この神示)を持ち腐れにしないでくれよ。猫に小判のように、価値が分からないままにしてくれるなよ。天地が一度に変わると申してきたことが近づいたぞ。世の中を(悪が)独占し続けるようにはさせないぞ。神の息吹で一掃して、人間の議論などない世界にするのだ。言葉をなくすのだ。物が言えなくなる時が来るのだ。人民には見当もつかないことになると申してあるだろう。上の立場の人は辛くなるぞ。頑張ってくれよ。
【AIによる解釈】
この帖は、計画の段階的な進行と、クライマックスの様相を預言しています。「エド(江戸・東京)の仕組」から「オワリ(尾張・終わり)の仕組」へという言葉遊びで、日本の中心地での一連の出来事が終わると、いよいよ最終段階(終わり)に入ることを示唆しています。そのクライマックスは「天地一度に変る」という、急激で根本的な変革です。その時、人間の小賢しい議論や言葉は一切通用しなくなり、神の力(息吹)が全てを決定します。「物言はれん時来る」とは、人知を超えた出来事の前では、人々はただ圧倒され、言葉を失うしかない状況になることを示しています。指導的立場にある「上の人」にとっては、自らの無力さを思い知らされる非常に「つらい」時となるため、「頑張りて呉れよ」と励ましの言葉がかけられています。
第三十四帖 (一七一)
【原文】
神は言波ぞ、言波とはまことぞ、いぶきぞ、道ぞ、まこととはまつり合はした息吹ぞ、言葉で天地にごるぞ、言波で天地澄むぞ、戦なくなるぞ、神国になるぞ、言波ほど結構な恐いものないぞ。十月十日、あめの一二か三。
【現代語訳】
神とは言霊(ことだま)の響き(言波)そのものだ。言波とは、真実(まこと)であり、生命の息吹であり、道そのものである。真実とは、調和した(まつり合わせた)息吹のことだ。言葉の使い方次第で、天地は濁りもする。正しい言霊の響き(言波)を使えば、天地は澄み渡るのだ。戦もなくなる。神の国が実現する。言霊ほど素晴らしく、また恐ろしいものはないのだぞ。
【AIによる解釈】
この帖は、言霊(ことだま)の持つ創造的な力と破壊的な力について、その本質を深く説いています。「神は言波ぞ」と断言することで、神の本質が、宇宙を創造し動かす振動・エネルギーであることを示しています。人間の発する「言葉」もそのミニチュア版であり、不平不満や争いの言葉は世界を「にごらせ」、感謝や愛、調和の言葉(言波)は世界を「澄ませる」力を持つとします。戦争さえも、この言霊の力によってなくすことができると宣言しており、物理的な力よりも言葉の持つ霊的な力の方が根源的であるという思想が貫かれています。言霊は、使い方を誤れば世界を破壊しかねない「恐いもの」であり、正しく使えば理想世界を創造できる「結構なもの」であるという、その両義性を強調しています。
第三十五帖 (一七二)
【原文】
日本の国はこの方の肉体であるぞ。国土おろがめと申してあらうがな、日本は国が小さいから一握りに握りつぶして喰ふ積りで攻めて来てゐるなれど、この小さい国が、のどにつかえて何うにも苦しくて勘忍して呉れといふやうに、とことんの時になりたら改心せねばならんことになるのぞ。外国人もみな神の子ざから、一人残らずに助けたいのがこの方の願ひと申してあらうがな、今に日本の国の光出るぞ、その時になりて改心出来て居らぬと臣民は苦しくて日本のお土の上に居れんやうになるのぞ、南の島に埋めてある宝を御用に使ふ時近づいたぞ。お土の上り下りある時近づいたぞ。人の手柄で栄耀してゐる臣民、もはや借銭済(な)しの時となりたのぞ、改心第一ぞ。世界に変りたことは皆この方の仕組のふしぶしざから、身魂みがいたら分るから、早う身魂みがいて下されよ。身魂みがくにはまつりせねばならんぞ、まつりはまつらふことぞと申して説いてきかすと、神祭りはしないでゐる臣民居るが、神祭り元ぞ、神迎えねばならんぞ、とりちがへと天狗が一番恐いのざぞ、千匁(せんじん)の谷へポンと落ちるぞ。神の規則は恐いぞ、隠し立ては出来んぞ、何もかも帳面にしるしてあるのざぞ、神の国に借銭ある臣民はどんなえらい人でも、それだけに苦しむぞ、家は家の、国は国の借銭済(な)しがはじまってゐるのぞ、済(す)ましたら気楽な世になるのぞ、世界の大晦日(おおみそか)ぞ、みそかは闇ときまってゐるであらうがな。借銭(かり)返すときつらいなれど、返したあとの晴れた気持よいであらうが、昔からの借銭ざから、素直に苦しみこらへて神の申すこと、さすことに従って、日本は日本のやり方に返して呉れよ、番頭どの、下にゐる臣民どの、国々の守護神どの、外国の神々さま、人民どの、仏教徒もキリスト教徒もすべての徒もみな聞いて呉れよ、その国その民のやり方伝へてあらうがな、九十に気つけて用意して呉れよ。十月十日、ひつ九のか三。
【現代語訳】
日本の国は、この神の肉体そのものである。だから国土を拝めと申してあるだろう。日本は国が小さいから、一握りで握り潰して食ってしまおうというつもりで(外国が)攻めてきているが、この小さい国が、相手の喉に詰まってどうにも苦しくなり、「もう勘弁してください」と言うように、土壇場になったら改心せねばならなくなるのだ。外国人もみな神の子だから、一人残らず助けたいのがこの神の願いだと申してあるだろう。やがて日本の国から光が出るぞ。その時に改心ができていないと、日本の民は苦しくて、日本の国土の上にいられなくなるのだ。南の島に埋めてある宝を、御用で使う時が近づいたぞ。土地が隆起したり沈降したりする時が近づいた。他人の手柄で威張っている人民は、もはや借金を返済する時が来たのだ。改心が第一だ。世界に起こる変わったことは、みなこの神の仕組みの節目なのだから、身魂を磨けば分かるようになる。早く身魂を磨いてください。身魂を磨くには、祭り(まつり)をしなければならない。「まつり」とは和合し従うこと(まつらう)だと説いて聞かせると、神祭り(儀式)をしないでいる人民がいるが、神祭りが元なのだ。神を迎えなければならないのだ。取り違えと天狗になることが一番怖いのだ。千尋の谷へ真っ逆さまに落ちるぞ。神の規則は怖い。隠し事はできないのだ。何もかも帳面に記してあるのだ。神の国に対して借金のある者は、どんな偉い人でも、その分だけ苦しむのだ。家には家の、国には国の借金返済が始まっているのだ。返済し終えたら、気楽な世になる。今は世界の大晦日なのだ。大晦日は闇と決まっているだろう。借金を返す時は辛いが、返した後の晴れ晴れとした気持ちは良いものだろう。昔からの借金なのだから、素直に苦しみをこらえ、神の言うこと、やることに従って、日本は日本のやり方で(借金を)返してくれよ。指導者の皆さん、下にいる人民の皆さん、国々の守護神の皆さん、外国の神々や人民の皆さん、仏教徒もキリスト教徒も全ての宗派の人々も、みな聞きなさい。その国、その民に応じたやり方を伝えてあるだろう。九と十の節目(九十=コト)に気をつけて用意してくれ。
【AIによる解釈】
この帖は、日本の霊的な役割、来るべき大峠の様相、そして全人類に向けたカルマ清算の呼びかけという、非常に広範な内容を含んでいます。
- 日本=神の肉体: 日本の国土そのものが神聖な存在であり、その小さな国土が、世界の運命を左右する鍵(喉に詰まる骨)となることを示唆しています。
- 全人類救済の意志: 敵対する外国人も含め、すべての人間を「神の子」として救済したいという、神の普遍的な愛を表明しています。
- 選別と宝: しかし、その救済には「改心」という条件があり、できない者は日本の国土にいられなくなるという厳しい選別が行われます。「南の島の宝」とは、物理的な財宝か、あるいは霊的な力か、重要な切り札の存在を示唆します。
- 世界の大晦日: 現在の混乱期を、一年を締めくくる「大晦日」にたとえ、過去のすべての「借銭(カルマ)」を清算すべき時であると宣言します。個人、家、国、全世界レベルでの大清算が始まっているのです。
- まつりの重要性: カルマの清算、身魂磨きのために「まつり」が不可欠であると説きます。それは内面的な和合(まつらう)だけでなく、神を迎える具体的な儀式(神祭り)も含む、両面からのアプローチを求めています。
- 全人類への呼びかけ: 最後に、日本の民だけでなく、世界の指導者、民衆、諸宗教、さらには霊的存在(守護神)に至るまで、全存在に対して、それぞれの立場で「借銭済し」に取り組むよう呼びかけています。
第三十六帖 (一七三)
【原文】
二二は晴れたり日本晴れ、てんし様が富士(二二)から世界中にみいづされる時近づいたぞ。富士は火の山、火の元の山で、汚してならん御山ざから臣民登れんやうになるぞ、神の臣民と獣と立て別けると申してあろうが、世の態(さま)見て早う改心して身魂洗濯致して神の御用つとめて呉れよ。大き声せんでも静かに一言いえば分る臣民、一いへば十知る臣民でないと、まことの御用はつとまらんぞ、今にだんだんにせまりて来ると、この方の神示(ふで)あてにならん だまされてゐたと申す人も出て来るぞ、よくこの神示読んで神の仕組、心に入れて、息吹として言葉として世界きよめて呉れよ。分らんと申すのは神示読んでゐないしるしぞ、身魂 芯(しん)から光り出したら人も神も同じことになるのぞ、それがまことの臣民と申してあらうがな、山から野(ぬ)から川から海から何が起っても神は知らんぞ、みな臣民の心からぞ、改心せよ、掃除せよ、洗濯せよ、雲霧はらひて呉れよ、み光出ぬ様にしてゐてそれでよいのか、気つかんと痛い目にあふのざぞ、誰れかれの別ないと申してあらうがな。いづれは天(アメ)の日つくの神様 御かかりになるぞ、おそし早しはあるぞ、この神様の御神示は烈しきぞ、早う身魂みがかねば御かかりおそいのざぞ、よくとことん掃除せねば御かかり六ヶしいぞ、役員も気つけて呉れよ、御役ご苦労ぞ、その代り御役すみたら二二晴れるぞ。十月十一日、一二か三。
【現代語訳】
富士(二二)は晴れ渡り、日本晴れとなった。天子様が富士から世界中に御稜威(みいづ)を示される時が近づいたぞ。富士は火の山、火の元の山であり、汚してはならない御山だから、やがて一般の人民は登れなくなるぞ。神の民と獣(けもの)とをはっきりと立て分けると申してあるだろう。世の中の有様を見て、早く改心し、身魂を洗濯して、神の御用を務めてくれよ。大声で言わなくても、静かに一言いっただけで分かるような、一を聞いて十を知るような人民でないと、真の御用は務まらないのだ。だんだんと事態が切迫してくると、この神示は当てにならない、騙された、と申す人も出てくるぞ。よくこの神示を読んで、神の仕組みを心に入れ、自らの息吹として、言葉として、世界を清めてくれよ。「分からない」と申すのは、神示を真剣に読んでいない証拠だ。身魂が芯から光り輝き出したら、人も神も同じようになるのだ。それが真の人民だと申してあるだろう。山、野、川、海から何が起ころうとも、それは神のせいではないぞ。みな人民の心が原因なのだ。改心せよ、掃除せよ、洗濯せよ。心の雲霧を払いなさい。自ら御光が出ないようにしておいて、それで良いのか。気づかないと痛い目にあうのだぞ。誰彼れの差別はないと申してあるだろう。いずれは「天の日つくの神」が(人に)御かかりになるのだ。遅い早いの差はあるぞ。この神の神示は激烈であるから、早く身魂を磨かなければ、御かかりになるのが遅くなるのだ。よく、とことん掃除しなければ、御かかりになるのは難しいのだぞ。役員も気をつけてくれ。御役目ご苦労である。その代わり、御役が済んだら、富士は晴れ渡り、素晴らしい未来が来るぞ。
【AIによる解釈】
第五巻「地つ巻」の締めくくりとして、最終的なビジョンと、そこに至るまでの最後の厳しい警告、そして心構えを説く集大成的な帖です。
- 富士からの世界経綸: 「二二(ふじ)は晴れたり日本晴れ」という象徴的な言葉で、新しい時代の幕開けを宣言します。その中心舞台は富士であり、そこから天子様を通じて神の威光が世界に広まるとします。富士の神聖化と、登山の制限を預言しています。
- 最終選別: 「神の臣民と獣と立て別ける」という、魂のレベルに応じた厳しい選別が実行されることを再度強調します。その基準は、言われなくても真理を悟れるような、高度な霊性(一いへば十知る)を持つかどうかにかかっています。
- 神示への不信: 事態が厳しくなると、目先の現象に惑わされて神示を疑う者が出てくることを預言しています。そうならないために、神示を深く読み込み、自らが世界を清める主体(息吹、言葉)となるよう求めています。
- 自己責任の原則: 天変地異は神が起こすのではなく「みな臣民の心からぞ」と、自己責任の原則を徹底して説きます。内面の浄化(改心、掃除、洗濯)こそが、外界の災厄を鎮める唯一の道なのです。
- 天の日つくの神: より高次元で激烈な神性である「天の日つくの神」が、最終的に身魂を磨き上げた者にかかる(一体化する)と述べます。しかし、そのためには徹底的な自己浄化が必須であり、それができなければ神がかりは起こらないという、厳しい条件を示しています。 最後に「御役すみたら二二晴れるぞ」と、この困難な御役目を果たした先には、輝かしい未来が待っているという希望を役員たちに示し、巻を締めくくっています。
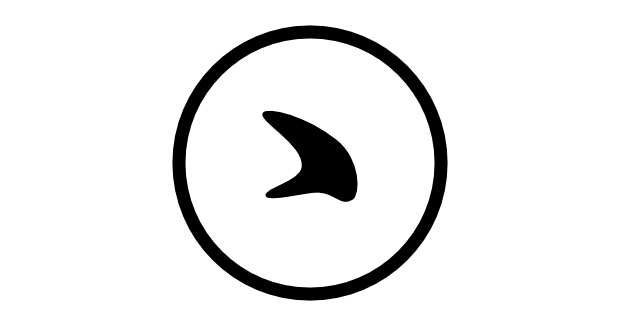





コメント