gemini 2.5 proにわかりやすいように解説してもらいました、しかし8通りに読めるということから完全に鵜呑みにしないよう、お願いします。
第一帖 (八一)
【原文】
道はいくらもあるなれど、どの道通っても、よいと申すのは、悪のやり方ぞ、元の道は一つぞ、初めから元の世の道、変らぬ道があれば、よいと申してゐるが、どんなことしても我さへたてばよいように申してゐるが、それが悪の深き腹の一厘ぞ。元の道は初めの道、神のなれる道、神のなかのなる初め、は光の真中は四の道、此の事、気のつく臣民ないなれど。「一が二」わかる奥の道、身魂掃除すれば此のことわかるのざ、身魂磨き第一ぞ。八月十日、の一二。
【現代語訳】
道はいくらでもあるように見えるが、「どの道を通っても良い」と言うのは悪のやり方である。根源の道は一つだけだ。初めから変わらない普遍の道があれば良いと言いながら、実際にはどんなことをしてでも自分さえ良ければ良いという考え方をしているが、それが悪の根深い企みの一端である。根源の道とは、始まりの道、神へと至る道、神が成るための初めの道であり、光の中心である「四の道」(※万物の基礎となる道)である。このことに気づく人民はいないようだが、「一が二に分かれる」という深遠な道理は、身と魂を浄めればわかるようになる。身魂を磨くことが第一である。
【AIによる解釈】
この帖は、多様性や自由を謳いながらも、その実、利己主義や相対主義に陥りがちな現代的な価値観を「悪のやり方」と断じています。真理に至る「元の道」は一つであり、それは自己中心的な考えを捨て、内面を清める「身魂磨き」によってのみ理解できると説きます。「自分さえ良ければいい」という考え方が、社会や個人を堕落させる悪の根源であると鋭く指摘しています。表面的な自由さに惑わされず、普遍的な真理を探究する姿勢の重要性を教えています。
第二帖 (八二)
【原文】
か一の八マに立ちて、一(ひ)れ二(ふ)りて祓ひて呉れよ、ひつくの神に仕へている臣民、代る代るこの御役つとめて呉れよ。今は分かるまいなれど結構な御役ぞ。この神示(ふで)腹の中に入れて置いてくれと申すに、言ふ事きく臣民少ないが、今に後悔するのが、よく分りてゐるから神はくどう気つけて置くのぞ、読めば読むほど神徳あるぞ、どんな事でも分かる様にしてあるぞ、言ふこときかねば一度は種だけにして、根も葉も枯らして仕まうて、この世の大掃除せねばならんから、種のある内に気つけて居れど、気つかねば気の毒出来るぞ。今度の祭典(まつり)御苦労でありたぞ、神界では神々様 大変の御喜びぞ、雨の神、風の神殿ことに御喜びになりたぞ。此の大掃除一応やんだと安緒する。この時、富士(二二)鳴門がひっくり返るぞ、早やう改心して呉れよ。八月の十一日、のひつくの。
【現代語訳】
祓い清めの場に立ち、祓詞を唱えて浄めてくれ。ひつくの神に仕える民よ、交代でこの役目を務めてくれ。今すぐには分からないだろうが、これは大変結構な役目なのだ。この神示を心の中(腹の中)にしっかりと収めておけと言うのに、言うことを聞く民は少ない。今に後悔することがよく分かっているから、神はくどいほど注意しておくのだ。この神示は読めば読むほど神の徳があり、どんなことでも分かるようにしてある。言うことを聞かなければ、一度は「種」だけを残して、根も葉も全て枯らしてしまい、この世の大掃除をしなければならなくなる。だから種が残っているうちに気づかせようとしているが、気づかなければ気の毒なことになるぞ。先日の祭典はご苦労であった。神の世界では神々が大変お喜びになっている。特に雨の神、風の神が喜ばれた。これで大掃除はいったん収まるだろうと安心するな。その時、富士と鳴門(日本の象徴)がひっくり返るような大変動が起こるぞ。早く改心してくれ。
【AIによる解釈】
神示の教えを心に刻み、祓い清めの実践を続けることの重要性を説いています。人々の心が浄化されない場合、「大掃除」と呼ばれる大いなる破壊と浄化が訪れると警告しています。「富士(二二)鳴門がひっくり返る」とは、物理的な天変地異のみならず、日本の社会構造や価値観、国体が根底から覆るような、革命的な大変動が起こることを象徴しています。表面的な平和に安堵せず、根本的な改心が急務であると強く促しています。
第三帖 (八三)
【原文】
メリカもギリスは更なり、ドイツもイタリもオロシヤも外国はみな一つになりて神の国に攻め寄せて来るから、その覚悟で用意しておけよ。神界ではその戦の最中ぞ。学と神力との戦と申しておろがな、どこから何んなこと出来るか、臣民には分かるまいがな、一寸先も見えぬほど曇りて居りて、それで神の臣民と思うてゐるのか、畜生にも劣りてゐるぞ。まだまだわるくなって来るから、まだまだ落ち沈まねば本当の改心出来ん臣民 沢山あるぞ。玉とは御魂(おんたま)ぞ、鏡とは内に動く御力ぞ、剣とは外に動く御力ぞ、これを三種(みくさ)の神宝(かむたから)と申すぞ。今は玉がなくなってゐるのぞ、鏡と剣だけぞ、それで世が治まると思うてゐるが、肝腎の真中ないぞ、それでちりちりばらばらぞ。アとヤとワの詞(四)の元要るぞと申してあろがな、この道理分らんか、剣と鏡だけでは戦勝てんぞ、それで早う身魂みがいて呉れと申してあるのぞ。上下ないぞ、上下に引繰り返すぞ、もう神待たれんところまで来てゐるぞ、身魂みがけたら、何んな所で何んなことしてゐても心配ないぞ、神界の都にはあくが攻めて来てゐるのざぞ。八月の十二日、のひつくの。
【現代語訳】
メリカやイギリスは言うまでもなく、ドイツもイタリアもロシアも、外国はみな一つになって神の国(日本)に攻め寄せてくるから、その覚悟で用意しておけ。神の世界では、すでにその戦いの真っ最中だ。これは人間の学問・知恵と神の力との戦いであるぞ。どこからどんな事が起こるか、人々にはわかるまい。一寸先も見えないほどに心が曇っているのに、それで神の民だと思っているのか。畜生にも劣っているぞ。事態はまだまだ悪くなる。もっと落ち沈まなければ本当の改心のできない民が沢山いるのだ。三種の神宝について言うと、「玉」とは御魂、「鏡」とは内に働く力(知性・内省)、「剣」とは外に働く力(武力・行動力)のことである。今の世は、肝心な「玉(魂)」が失われている。鏡(知恵)と剣(武力)だけで世が治まると思っているが、中心となる魂がないから、世の中がバラバラなのだ。ア・ヤ・ワ(※天地人を結ぶ言霊)の元が必要だと言ったではないか。この道理が分からないのか。剣と鏡だけでは戦には勝てないぞ。だから早く身魂を磨いてくれと言っているのだ。もはや上下の区別もなくなる。全てがひっくり返るぞ。もう神は待てないところまで来ている。身魂が磨けていれば、どこで何をしていても心配ない。神の世界の中心にまで、悪が攻めてきているのだぞ。
【AIによる解釈】
当時の第二次世界大戦の国際情勢を背景に、それが単なる国家間の戦争ではなく、物質主義・人間中心主義(学)と、霊的な力(神力)との根源的な戦いであると位置づけています。三種の神宝の比喩を用い、現代文明が武力や科学技術(剣)、情報や知恵(鏡)ばかりを重んじ、最も重要な精神性や魂(玉)を軽視していることを批判しています。魂という中心軸を失った社会は、いかに武力や知恵があっても崩壊すると警告し、真の勝利のためには「身魂磨き」が不可欠であると説いています。
第四帖 (八四)
【原文】
一二三(ひふみ)の仕組が済みたら三四五(みよいづ)の仕組ぞと申してありたが、世の本の仕組は三四五の仕組から五六七(みろく)の仕組となるのぞ、五六七の仕組とは弥勒(みろく)の仕組のことぞ、獣と臣民とハッキリ判りたら、それぞれの本性出すのぞ、今度は万劫末代のことぞ、気の毒出来るから洗濯大切と申してあるのぞ。今度お役きまりたら そのままいつまでも続くのざから、臣民よくこの神示(ふで)よみておいて呉れよ。八月十三日、のひつくのか三。
【現代語訳】
「ひふみ」の段階が終わったら「みよいづ」の段階だと伝えてきたが、この世の根本の仕組みは、「みよいづ」から「みろく(弥勒)」の仕組みへと移行していくのだ。弥勒の仕組みとは、弥勒の世を創るための計画である。その過程で、獣のような人間と神の民とがハッキリと区別され、それぞれが本性を現すことになる。今度の変革は永遠に続く事柄の始まりなのだ。だから気の毒なことにならないよう、魂の洗濯(浄化)が大切だと言っているのだ。この時に決まった役目は、そのまま永遠に続くのだから、人々よ、この神示をよく読んでおいてくれ。
【AIによる解釈】
世界の歴史が、「ひふみ」→「みよいづ」→「みろく」という霊的な段階を経て、最終的な理想世界(弥勒の世)へ向かうという壮大なビジョンを示しています。その移行期において、人々の魂の真価が問われ、獣性を持つ者と神性を持つ者とが明確に分かれる「選別」が行われると説きます。この変革は一時的なものではなく、未来永劫に影響を及ぼす決定的なものであるため、今のうちの「洗濯(改心・浄化)」が極めて重要だと強調しています。
第五帖 (八五)
【原文】
喰うものがないと申して臣民不足申してゐるが、まだまだ少なくなりて、一時は喰う物も飲む物もなくなるのぞ、何事も行(ぎょう)であるから喜んで行して下されよ。滝に打たれ、蕎麦粉(そばこ)喰うて行者は行してゐるが、断食する行者もゐるが、今度の行は世界の臣民みな二度とない行であるから、厳しいのぞ、この行 出来る人と、よう我慢出来ない人とあるぞ、この行 出来ねば灰にするより他ないのぞ、今度の御用に使ふ臣民はげしき行さして神うつるのぞ。今の神の力は何も出ては居らぬのぞ。この世のことは神と臣民と一つになりて出来ると申してあろがな、早く身魂みがいて下されよ。外国は、神の国はと申してあるが、は神ざ、は臣民ぞ、ばかりでも何も出来ぬ、ばかりでもこの世の事は何も成就せんのぞ、それで神かかれるやうに早う大洗濯して呉れと申してゐるのぞ、神急(せ)けるぞ、この御用大切ぞ、神かかれる肉体 沢山要るのぞ。今度の行はを綺麗にする行ぞ、掃除出来た臣民から楽になるのぞ。どこに居りても掃除出来た臣民から、よき御用に使って、神から御礼申して、末代名の残る手柄立てさすぞ。神の臣民、掃除洗濯出来たらこの戦は勝つのぞ、今は一分もないぞ、一厘もないぞ、これで神国の民と申して威張ってゐるが、足許からビックリ箱があいて、四ツん這ひになっても助からぬことになるぞ、穴掘りて逃げても、土もぐってゐても灰になる身魂は灰ぞ、どこにゐても助ける臣民 行って助けるぞ、神が助けるのでないぞ、神助かるのぞ、臣民も神も一緒に助かるのぞ、この道理よく腹に入れて呉れよ、この道理分りたら神の仕組はだんだん分りて来て、何といふ有難い事かと心がいつも春になるぞ。八月の十四日の朝、のひつ九の。
【現代語訳】
食べる物がないと人々は不平を言っているが、これからもっと無くなり、一時は食べ物も飲み物もなくなるぞ。しかし、これも全て修行であるから、喜んで修行してほしい。行者は滝に打たれ、粗食や断食の行をするが、今度の行は世界中の人々にとって二度とない厳しい修行だ。この行をやり遂げられる人と、我慢できない人が出てくる。やり遂げられなければ灰にするしかない。今度の神の御用に使う民には、激しい行をさせて神が宿るようにするのだ。今の段階では、神の力は何も現れていない。この世のことは神と民が一つになって初めて成就すると言ったであろう。早く身魂を磨いてくれ。神と民の関係は、どちらか一方だけでは何もできず、この世の事は成就しない。だから神が宿れるように、早く魂の大洗濯をしてくれと急かしているのだ。神が宿るための清浄な肉体がたくさん必要なのだ。今度の行は魂を綺麗にする行であり、掃除ができた者から楽になる。どこにいても、魂が浄化された者から良い御用に使い、神から礼を言い、末代まで名の残る手柄を立てさせるぞ。魂の浄化ができれば、この戦には勝てる。だが今は勝ち目など一厘もない。それで神国の民だと威張っているが、足元から大変なことが起きて、四つん這いになっても助からない事態になるぞ。どこに逃げても、魂が汚れていれば灰になる。神は助けるべき民をどこにでも行って助ける。だがそれは神が一方的に助けるのではない。神も助かるのだ。民も神も共に助かるのだ。この道理をよく心に刻んでくれ。この道理が分かれば、神の計画がだんだん理解でき、なんと有難いことかと心がいつも春のように晴れやかになるだろう。
【AIによる解釈】
食糧難などの物理的な困難を、全人類に課せられた霊的な「行(修行)」と捉え直すよう求めています。この厳しい試練を乗り越える鍵は、個人の魂の浄化(大洗濯)にあると説きます。特筆すべきは「神が助けるのでないぞ、神助かるのぞ、臣民も神も一緒に助かるのぞ」という部分です。これは、神と人間が一方的な救済関係にあるのではなく、人間が魂を磨き、神の「入れ物」となることで神の力が発揮され、結果として神も人間も共に救われるという、相互依存的な救済観を示しています。この深遠な道理を理解することこそが、希望を持って試練に立ち向かう力になると教えています。
第六帖 (八六)
【原文】
今は善の神が善の力弱いから善の臣民苦しんでゐるが、今しばらくの辛抱ぞ、悪神総がかりで善の肉体に取りかからうとしてゐるから よほどフンドシしめてかからんと負けるぞ。親や子に悪の神かかりて苦しい立場にして悪の思ふ通りにする仕組立ててゐるから気をつけて呉れよ。神の、も一つ上の神の世の、も一つ上の神の世の、も一つ上の神の世は戦済んでゐるぞ、三四五(みよいづ)から五六七(みろく)の世になれば天地光りて何もかも見えすくぞ。八月のこと、八月の世界のこと、よく気つけて置いて呉れよ、いよいよ世が迫りて来ると、やり直し出来んと申してあろがな。いつも剣の下にゐる気持で心ひき締めて居りて呉れよ、臣民 口でたべる物ばかりで生きてゐるのではないぞ。八月の十五日、ひつくとのひつ九のか三しるさすぞ。
【現代語訳】
今は善の神の力が弱いために、善人が苦しんでいるが、もうしばらくの辛抱だ。悪神が総がかりで善人の肉体(精神・魂)を乗っ取ろうとしているから、よほど気を引き締めていないと負けてしまうぞ。親や子に悪神が取り憑き、家族を苦しい立場に追い込んで、悪の思う通りにしようと計画しているから気をつけなさい。高次元の神の世界では、すでに戦いは終わっているのだ。「みよいづ」から「みろく」の世になれば、天地は光り輝き、全ての真実が見通せるようになる。八月に起こること、八月の世界の情勢によく注意しておけ。いよいよ時が迫ってくると、もうやり直しはきかないと言ったであろう。常に剣の下にいるような緊張感をもって心をひきしめていなさい。人は口から食べる物だけで生きているのではないのだぞ。
【AIによる解釈】
善人が苦しみ、悪が栄えるように見える現在の状況は一時的なものであり、霊界における善と悪の最終戦争の反映であると説いています。悪神は、最も身近な人間関係(親子など)を利用して人を苦しめ、支配しようとすると警告しており、これは家庭内の不和や精神的な問題として現れる可能性があります。しかし、より高次の世界ではすでに善の勝利は確定しており、弥勒の世になれば全ての真実が明らかになるという希望を示しています。「人は口から食べる物ばかりで生きているのではない」という一文は、物質的な充足だけでなく、霊的な糧の重要性を強調しています。
第七帖 (八七)
【原文】
悪の世であるから、悪の臣民 世に出てござるぞ、善の世にグレンと引繰り返ると申すのは善の臣民の世になることぞ。今は悪が栄えてゐるのざが、この世では人間の世界が一番おくれてゐるのざぞ、草木はそれぞれに神のみことのまにまになってゐるぞ。一本の大根でも一粒の米でも何でも貴くなったであろが、一筋の糸でも光出て来たであろがな、臣民が本当のつとめしたなら、どんなに尊いか、今の臣民には見当とれまいがな、神が御礼申すほどに尊い仕事出来る身魂ぞ、殊に神の国の臣民みな、まことの光あらはしたなら、天地が輝いて悪の身魂は目あいて居れんことになるぞ。結構な血筋に生まれてゐながら、今の姿は何事ぞ、神はいつまでも待てんから、いつ気の毒出来るか知れんぞ。戦恐れてゐるが臣民の戦位、何が恐いのぞ、それより己の心に巣くうてる悪のみたまが恐いぞ。八月十六日、のひつくのか三。
【現代語訳】
今は悪の世であるから、悪人が世にのさばっている。これが善の世にガラリとひっくり返るというのは、善人が中心となる世になるということだ。今は悪が栄えているように見えるが、この地上では人間界が一番遅れているのだ。草や木はそれぞれ神の御心のままに生きている。一本の大根、一粒の米、その全てが尊いものとなったであろう。一筋の糸からも光が出る時代になったであろう。人が本当に自分の務めを果たしたなら、どれほど尊いことになるか、今の人々には見当もつかないだろう。神が礼を言うほどに尊い仕事ができる魂なのだ。特に神の国(日本)の民が皆、真の光を現したなら、天地が輝き、悪の魂を持つ者は目を開けていられなくなる。素晴らしい血筋に生まれていながら、今のその姿は何事か。神はいつまでも待てないから、いつ気の毒な事態になっても知らないぞ。戦争を恐れているようだが、人間同士の戦など、何を恐れることがあるか。それよりも、自分自身の心に巣食っている悪の魂の方がよほど恐ろしいのだぞ。
【AIによる解釈】
この帖は、人間中心主義への痛烈な批判を含んでいます。自然界は神の摂理に従い調和しているのに、人間界だけが欲望やエゴによって乱れ、「一番おくれてゐる」と指摘します。そして、問題の根源は外にあるのではなく、内にあることを強調します。国家間の戦争よりも、自分自身の心の中にある「悪の魂(利己心、憎しみ、妬みなど)」との戦いこそが、真に恐れるべきであり、また乗り越えるべき課題であると説いています。個々人が内なる光を取り戻すことが、世界全体を輝かせる力になるという、内面変革の重要性を教えています。
第八帖 (八八)
【原文】
山は神ぞ、川は神ぞ、海も神ぞ、雨も神、風も神ぞ、天地みな神ぞ、草木も神ぞ、神祀れと申すのは神にまつらふことと申してあろが、神々まつり合はすことぞ、皆何もかも祭りあった姿が神の姿、神の心ぞ。みなまつれば何も足らんことないぞ、余ることないぞ、これが神国の姿ぞ、物足らぬ物足らぬと臣民泣いてゐるが、足らぬのでないぞ、足らぬと思ふてゐるが、余ってゐるではないか、上(かみ)の役人どの、まづ神祀れ、神祀りて神心となりて神の政治せよ、戦など何でもなく鳧(けり)がつくぞ。八月十七日、の一二のか三。
【現代語訳】
山は神、川は神、海も神、雨も風も神、天地のすべてが神であり、草木もまた神である。「神を祀れ」というのは、神と和合すること(まつらふこと)であり、神々同士を調和させること(まつり合はすこと)だと言ったであろう。森羅万象すべてが調和している姿こそが、神の姿であり、神の心なのだ。すべてが調和すれば、何も不足することはないし、余ることもない。これが神の国の本来の姿だ。人々は「足りない、足りない」と泣いているが、本当に足りないのではない。足りないと思い込んでいるだけで、実際には余っているではないか。上に立つ役人たちよ、まず神を祀りなさい。神を祀って神の心となり、神の政治を行いなさい。そうすれば、戦争などあっという間に片が付くぞ。
【AIによる解釈】
日本古来のアニミズム(万物神在観)を背景に、自然界のすべてに神が宿ると説きます。ここでの「祀る(まつる)」は、儀礼的な行為だけでなく、「まつらふ(服う・順う)」、すなわち万物と調和し、共生するという深い意味を持っています。不足感や欠乏感は、物がないからではなく、万物との調和が失われ、分離している心が生み出す幻想だと指摘します。特に為政者に対し、小手先の政策ではなく、まず自然や神との調和を取り戻し、「神心」に立って政治を行うことこそが、戦争を含むあらゆる問題を根本的に解決する道であると示しています。
第九帖 (八九)
【原文】
神界は七つに分かれてゐるぞ、天つ国三つ、地(つち)の国三つ、その間に一つ、天国が上中下の三段、地国も上中下の三段、中界(ちうかい)の七つぞ、その一つ一つがまた七つに分かれてゐるのぞ、その一つがまた七つずつに分れてゐるぞ。今の世は地獄の二段目ぞ、まだ一段下あるぞ、一度はそこまで下がるのぞ、今一苦労あると、くどう申してあることは、そこまで落ちることぞ、地獄の三段目まで落ちたら、もう人の住めん所ざから、悪魔と神ばかりの世にばかりなるのぞ。この世は人間にまかしてゐるのざから、人間の心次第ぞ、しかし今の臣民のやうな腐った臣民ではないぞ、いつも神かかりてゐる臣民ぞ、神かかりと直ぐ分かる神かかりではなく、腹の底にシックリと神鎮まってゐる臣民ぞ、それが人間の誠の姿ぞ。いよいよ地獄の三段目に入るから、その覚悟でゐて呉れよ、地獄の三段目に入ることの表(おもて)は一番の天国に通ずることぞ、神のまことの姿と悪の見られんさまと、ハッキリ出て来るのぞ、神と獣と分けると申してあるのはこのことぞ。何事も洗濯第一。八月の十八日、の一二。
【現代語訳】
霊界は七つの階層に分かれている。天の国が三つ、地の国が三つ、そしてその間に一つ。天国は上中下の三段、地獄も上中下の三段、そして中界を合わせて七つの世界がある。その一つ一つがまた七つに、さらにその一つが七つずつに分かれているのだ。今のこの世は、地獄の二段目にあたる。まだもう一段下があるぞ。一度はそこまで落ちるのだ。「もう一苦労ある」とくどく言っているのは、このどん底まで落ちることを指している。地獄の三段目まで落ちたら、もはや人間が住める場所ではなく、悪魔と神だけの世界となる。この世は人間に任されているので、人間の心次第でどうにでもなる。ただし、それは今のような腐った心を持つ人間ではない。常に神が宿っている人間、それも外から見てすぐ分かるような神がかりではなく、腹の底にどっしりと神が鎮まっている人間、それが人間の真の姿なのだ。いよいよ地獄の三段目に入るから、その覚悟をしておいてくれ。しかし、地獄の三段目に落ちるということは、裏を返せば一番の天国に通じることでもあるのだ。その時、神の真の姿と、見るに堪えない悪の姿とが、ハッキリと現れる。神と獣を分けると言ったのはこのことだ。何事も魂の洗濯が第一である。
【AIによる解釈】
霊的世界の複雑な構造を説明し、現在の地球が霊的に非常に低い次元(地獄の二段目)にあると警告しています。「一度はそこまで下がる」という言葉は、事態がさらに悪化し、どん底を経験しなければ根本的な再生はありえないという「破壊と再生」の法則を示唆しています。しかし、その絶望の淵は、同時に最高の天国へと通じる転換点でもあるという逆説的な希望も示されています。これを「陰極まって陽に転ずる」と捉えることができます。この極限状況において、人の本性が現れ、「神」と「獣」が明確に分かれると説き、その審判の時に備えて魂を浄化しておくことの重要性を繰り返し訴えています。
第十帖(九〇)
【原文】
いよいよ戦烈しくなりて喰ふものもなく何もなくなり、住むとこもなくなりたら行く所なくなるぞ。神の国から除かれた臣民と神の臣民と何ちらがえらいか、その時になりたらハッキリするぞ、その時になりて何うしたらよいかと申すことは神の臣民なら誰でも神が教えて手引張ってやるから、今から心配せずに神の御用なされよ、神の御用と申して自分の仕事をなまけてはならんぞ。何んな所にゐても、神がスッカリと助けてやるから、神の申すやうにして、今は戦して居りて呉れよ。てんし様 御心配なさらぬ様にするのが臣民のつとめぞ。神の臣民 言(こと)に気をつけよ、江戸に攻め来たぞ。八月の十九日、のひつ九の。
【現代語訳】
いよいよ戦争が激しくなり、食べる物も何もかも無くなり、住む所さえ無くなったら、どこにも行く場所はなくなるぞ。その時、神の国から見放された民と、神の民と、どちらが本当に偉いのかがハッキリする。そうなった時にどうすれば良いかは、神の民であれば誰にでも神が教えて手を引いてやるから、今から心配せずに神の御用を務めなさい。ただし、神の御用だと言って自分の日々の仕事を怠けてはならない。どんな所にいても、神が必ず助けてやるから、神の言う通りにして、今は自分の持ち場で戦い続けてくれ。天皇陛下にご心配をおかけしないようにするのが、民の務めであるぞ。神の民よ、言葉に気をつけなさい。江戸(東京)に敵が攻めて来たぞ。
【AIによる解釈】
戦争末期の窮乏と混乱が極限に達する状況を預言しています。しかし、その混乱の中にあっても、信仰を持ち、日々の務め(仕事)を疎かにせず、公(てんし様)を思う心を持つ者は、神の導きによって守られると約束しています。信仰を言い訳に現実逃避することを戒め、信仰と日常の務めの両立こそが「神の御用」であると説いています。「江戸に攻め来たぞ」は、当時の東京大空襲の危機を反映した具体的な警告であり、事態の切迫を伝えています。
第十一帖 (九一)
【原文】
神土(かみつち)は白は、「し」のつく、黄は「き」のつく、青赤は「あ」のつく、黒は「く」のつく山々里々から出て来るぞ、よく探して見よ、三尺下の土なればよいぞ、いくらでも要るだけは出てくるぞ。八月二十日、のひつ九のか三。
【現代語訳】
神事に用いる神聖な土は、白い土は「し」のつく地名の所から、黄色い土は「き」のつく地名の所から、青や赤の土は「あ」のつく地名の所から、黒い土は「く」のつく地名の所から出てくる。よく探して見なさい。地表から三尺(約90cm)下の土ならば良い。必要なだけいくらでも出てくるぞ。
【AIによる解釈】
この帖は、具体的な儀式や準備に関する指示です。日本の国土そのものが神聖であり、土地ごとに特有の霊的な性質があるという考え方を示しています。特定の音(言霊)を持つ地名と、特定の色(性質)の土を結びつけており、国土の霊力を結集させるための方法を具体的に示唆していると解釈できます。これは、後の世の立て直しにおいて、日本の国土そのものが重要な役割を果たすことを暗示しているのかもしれません。
第十二帖 (九二)
【原文】
御土は神の肉体ぞ。臣民の肉体もお土から出来てゐるのぞ、この事分りたら、お土の尊いことよく分るであろがな。これからいよいよ厳しくなるぞ、よく世の中の動き見れば分るであろが、汚れた臣民あがれぬ神の国に上がってゐるではないか。いよいよとなりたら神が臣民にうつりて手柄さすなれど、今では軽石のような臣民ばかりで神かかれんぞ。早う神の申すこと、よくきいて生れ赤子の心になりて神の入れものになりて呉れよ。一人改心すれば千人助かるのぞ、今度は千人力与えるぞ、何もかも悪の仕組は分りているぞ、いくらでも攻めて来てござれ、神には世の本からの神の仕組してあるぞ、学や知恵でまだ神にかなふと思ふてか、神にはかなはんぞ。八月の二十一日、のひつ九のか三。
【現代語訳】
土は神の肉体である。人々の肉体もまた土からできている。このことが分かれば、土がいかに尊いものかがよく分かるだろう。これからいよいよ厳しくなる。世の中の動きをよく見れば分かるはずだ。本来なら神の国(高み)に上がれないような汚れた魂の者が、高い地位にいるではないか。いよいよという時になれば、神が人に乗り移って手柄を立てさせるのだが、今のような軽石のように中身のない人間ばかりでは、神が宿ることができない。早く神の言うことをよく聞き、生まれたばかりの赤子のような素直な心になって、神の入れ物になってくれ。一人が改心すれば千人が助かるほどの力になるのだ。今度は一人に千人力の力を与えるぞ。悪の企みは全てお見通しだ。いくらでも攻めてくるがよい。神には天地開闢以来の壮大な計画があるのだ。人間の学問や知恵で神に敵うとまだ思っているのか。神には到底敵わないぞ。
【AIによる解釈】
大地(土)の神聖性と、人間と大地の深いつながりを説いています。社会の上層部にいるべきでない人物が権力を持っているという現状批判と共に、そのような状況を打破するには、神が宿れるような「赤子の心」を持った人間が必要だと訴えています。「一人改心すれば千人助かる」という言葉は、個人の内面的な変革が、社会全体に計り知れないほど大きな良い影響を与えることを示唆しています。人間の小手先の知恵(学)では神の壮大な計画には敵わないと断言し、人智を超えた大いなる力を信頼するよう促しています。
第十三帖 (九三)
【原文】
何もかもてんし様のものではないか、それなのにこれは自分の家ぞ、これは自分の土地ぞと申して自分勝手にしているのが神の気に入らんぞ、一度は天地に引き上げと知らしてありたこと忘れてはならんぞ、一本の草でも神のものぞ、野(ぬ)から生れたもの、山から取れたもの、海の幸もみな神に供へてから臣民いただけと申してあるわけも、それで分るであろうがな。この神示よく読みてさへ居れば病気もなくなるぞ、さう云へば今の臣民、そんな馬鹿あるかと申すが よく察して見よ、必ず病も直るぞ、それは病人の心が綺麗になるからぞ、洗濯せよ掃除せよと申せば、臣民 何も分らんから、あわててゐるが、この神示よむことが洗濯や掃除の初めで終りであるぞ、神は無理は言はんぞ、神の道は無理してないぞ、よくこの神示読んで呉れよ。よめばよむほど身魂みがかれるぞ、と申しても仕事をよそにしてはならんぞ。臣民と申すものは馬鹿正直ざから、神示よめと申せば、神示ばかり読んだならよい様に思うてゐるが、裏も表もあるのぞ。役員よく知らしてやれよ。八月二十二日、のひつ九のか三のお告。
【現代語訳】
何もかもすべては天皇陛下のもの(公のもの)ではないか。それなのに「これは自分の家だ」「これは自分の土地だ」と言って、自分勝手に私有しているのが神は気に入らないのだ。一度はすべてを天と地にお返しする時が来ると知らせておいたことを忘れてはならない。一本の草でさえ神のものである。野や山や海でとれた産物は、みな一度神にお供えしてからいただくようにと言っている意味も、それで分かるであろう。この神示をよく読んでさえいれば、病気も治るのだぞ。そう言うと今の人は「そんな馬カなことがあるか」と言うだろうが、よく考えてみなさい。必ず病気も治る。それは、病人の心が綺麗になるからだ。「洗濯せよ、掃除せよ」と言うと、人々は何のことか分からず慌てているが、この神示を読むことこそが、魂の洗濯であり掃除の始まりにして終わりなのだ。神は無理なことは言わない。神の道に無理はないのだ。よくこの神示を読んでくれ。読めば読むほど身魂が磨かれるぞ。かと言って、自分の仕事を疎かにしてはいけない。民というものは馬鹿正直なところがあるから、「神示を読め」と言えば、そればかり読んでいれば良いと思ってしまうが、物事には裏と表があるのだ。役の者はこのことをよく人々に知らせてやりなさい。
【AIによる解釈】
私有の概念を根底から問い直し、すべては公(てんし様)のものであり、神からの預かりものであるという精神を説いています。これは、所有欲やエゴから解放されることを促す教えです。また、この神示を読むという行為そのものが、心を浄化し、結果として肉体の病さえも癒す力を持つと述べています。これは、心と身体が一体(心身一如)であるという思想に基づいています。しかし、信仰に没頭するあまり現実の生活(仕事)を疎かにするという極端な行動を戒め、信仰と日常のバランスの重要性を強調している点が、非常に実践的な教えと言えます。
第十四帖 (九四)
【原文】
臣民にわかる様にいふなれば、身も心も神のものざから、毎日毎日 神から頂いたものと思えばよいのであるぞ、それでその身体(からだ)をどんなにしたらよいかと云ふこと分かるであろうが、夜になれば眠ったときは神にお返ししてゐるのざと思へ、それでよく分かるであろうが。身魂みがくと申すことは、神の入れものとして神からお預りしてゐる、神の最も尊いとことしてお扱いすることぞ。八月二十三日、の一二のか三。
【現代語訳】
人々に分かるように言うならば、自分の身体も心もすべて神のものであり、毎日神からお借りしているものだと思えばよいのだ。そうすれば、その身体をどのように扱えばよいか、自ずと分かるであろう。夜になって眠る時は、その身体を神にお返ししているのだと思いなさい。そうすればよく分かるだろう。身魂を磨くということは、神からお預かりしている「神の入れもの」として、最も尊いものとして自分の身と心を丁重に扱うことなのだ。
【AIによる解釈】
この帖は、自己の所有権を完全に手放し、すべてを神に委ねるという信仰の姿勢を、非常に分かりやすい比喩で説いています。「身体は神からの借り物」「眠ることは神への返却」と考えることで、我欲から離れ、自分の心身を客観的に、そして大切に扱えるようになると教えています。「身魂磨き」とは、何か特別な修行をすることだけでなく、自分自身を「神の神殿」として尊び、清浄に保つという日々の意識そのものであることを示しています。
第十五帖 (九五)
【原文】
一二三は神食。三四五は人食、五六七は動物食、七八九は草食ぞ、九十は元に、一二三の次の食、神国弥栄ぞよ。人、三四五食に病ないぞ。八月二十四日、一二ふみ。
【現代語訳】
「一二三(ひふみ)」の段階は神の食事。「三四五(みよいづ)」の段階は人の食事。「五六七(みろく)」の段階は動物の食事。「七八九(なやこ)」の段階は草の食事である。そして「九十(こともち)」で元に返り、「一二三」の次の段階の食事となり、神の国は弥栄える。人は「三四五」の食事をしていれば病気にはならないぞ。
【AIによる解釈】
この帖は、世界の霊的な発展段階と、それに対応する食のあり方を示唆した、非常に象徴的な内容です。「三四五は人食」であり、「三四五食に病ないぞ」とあることから、「みよいづ」の段階における人間にとって理想的な食事が存在し、それが健康の鍵であると説いています。具体的な内容は明示されていませんが、文脈から推測すると、自然の摂理にかなった、調和のとれた食事(例えば穀物菜食など)を指していると考えられます。食という日常的な行為が、霊的な次元と深く結びついていることを示す教えです。
第十六帖 (九六)
【原文】
あらしの中の捨小舟ぞ、どこへ行くやら行かすやら、船頭さんにも分かるまい、メリカ、キリスは花道で、味方と思うた国々も、一つになりて攻めて来る、梶(かじ)も櫂(かい)さへ折れた舟、何うすることもなくなくに、苦しい時の神頼み、それでは神も手が出せぬ、腐りたものは腐らして肥料になりと思へども、肥料にさへもならぬもの、沢山出来て居らうがな、北から攻めて来るときが、この世の終り始めなり、天にお日様一つでないぞ、二つ三つ四つ出て来たら、この世の終りと思へかし、この世の終りは神国の始めと思へ臣民よ、神々様にも知らすぞよ、神はいつでもかかれるぞ、人の用意をいそぐぞよ。八月二十四日、の一二か三。
【現代語訳】
今の日本は、嵐の中を漂う捨てられた小舟のようだ。どこへ行くのか、どこへ流されるのか、船頭(指導者)にさえ分からないだろう。アメリカ、イギリスが主役のように振る舞い、味方だと思っていた国々までもが一つになって攻めてくる。舵も櫂も折れてしまった舟のように、なすすべもなく泣いている。そんな土壇場になってから神頼みをしても、それでは神も助けようがない。腐ったものは腐らせて肥料にでもなればと思うが、肥料にさえならないような者(魂)が沢山いるではないか。「北から攻めて来る時」が、この世の終わりの始まりである。空に太陽が一つではなく、二つ、三つ、四つと現れたら、この世の終わりだと思いなさい。しかし、この世の終わりは、神の国の始まりであると思え、民よ。このことは神々にも知らせておく。神はいつでも(人に)かかる準備はできている。人間の方の用意を急ぎなさい。
【AIによる解釈】
第二次世界大戦末期の日本の絶望的な状況を「あらしの中の捨小舟」と鮮烈に描写しています。「北から攻めて来る」はソ連の対日参戦を、「天にお日様一つでないぞ」は広島・長崎への原子爆弾投下(原爆の閃光を第二、第三の太陽と見立てた)を預言したものと広く解釈されています。この帖の核心は、絶望的な「終わり」が、同時に新しい世界(神国)の「始まり」であるという逆説的な希望です。終末は単なる滅亡ではなく、新しい時代を創造するための浄化の過程であると捉えています。そして、その新時代を迎えるためには、神頼みではなく、人間側の主体的な「用意(身魂磨き)」が不可欠であると強く促しています。
第十七帖 (九七)
【原文】
九十が大切ぞと知らしてあろがな、戦ばかりでないぞ、何もかも臣民では見当とれんことになりて来るから、上の臣民 九十に気つけて呉れよ、お上に神祀りて呉れよ、神にまつらうて呉れよ、神くどう申して置くぞ、早う祀らねば間に合はんのざぞ、神の国の山々には皆神祀れ、川々にみな神まつれ、野にもまつれ、臣民の家々にも落つる隈なく神まつれ、まつりまつりて弥勒(みろく)の世となるのぞ。臣民の身も神の宮となりて神まつれ、祭祀(まつり)の仕方 知らしてあろう、神は急(せ)けるぞ。八月二十五日、のひつ九。
【現代語訳】
「九十(こと)」が大切だと知らせてあるだろう。戦いだけでなく、何もかも人々には見当もつかないような事態になってくるから、上の立場の者たちは「九十(言動・事柄)」に気をつけなさい。お上(政府・指導者層)は神を祀りなさい。神と和合しなさい。神はくどく言っておくぞ、早く祀らなければ間に合わないのだ。神の国の山という山、川という川、野にも、そして人々の家々にも、隅々まで漏れなく神を祀りなさい。そのように祀り(調和し)続けて、弥勒の世となるのだ。人々自身の身体も神の宮として神を祀りなさい。祀り方は教えてあるだろう。神は急いでいるのだぞ。
【AIによる解釈】
「九十」は「こと」、すなわち「言(ことば)」と「事(おこない)」の両方を指し、言霊の力と正しい行いの重要性を説いています。来るべき大変動は、単なる戦争ではなく、人知の及ばない多岐にわたるものであるため、指導者層から民衆一人ひとりに至るまで、国全体が神との調和を取り戻すこと(祀る)が急務であると訴えています。「山川、野、家々、そして自身の身体に神を祀れ」という呼びかけは、生活のあらゆる場面、そして自己の内面に至るまで、神を意識し、調和した生き方を実践することが、理想世界(弥勒の世)を招来する唯一の道であると教えています。
第十八帖 (九八)
【原文】
神々様みなお揃ひなされて、雨の神、風の神、地震の神、岩の神、荒の神、五柱、七柱、八柱、十柱の神々様がチャンとお心合はしなされて、今度の仕組の御役きまりてそれぞれに働きなされることになりたよき日ぞ。辛酉(かのととり)はよき日と知らしてあろがな。これから一日々々烈しくなるぞ、臣民 心得て置いて呉れよ、物持たぬ人、物持てる人より強くなるぞ、泥棒が多くなれば泥棒が正しいと云ふことになるぞ、理屈は悪魔と知らしてあろが、保持(うけもち)の神様ひどくお怒りぞ、臣民の食ひ物、足りるやうに作らしてあるに、足らぬと申してゐるが、足らぬことないぞ、足らぬのは、やり方わるいのざぞ、食ひて生くべきもので人殺すとは何事ぞ。それぞれの神様にまつはればそれぞれの事、何もかなふのぞ、神にまつはらずに、臣民の学や知恵が何になるのか、底知れてゐるのでないか。戦には戦の神あるぞ、お水に泣くことあるぞ、保持の神様 御怒りなされてゐるから早やう心入れかへてよ、この神様お怒りになれば、臣民 日干しになるぞ。八月の辛酉の日、ひつくのか三さとすぞ。
【現代語訳】
神々が皆お揃いになり、雨、風、地震、岩、荒ぶる神など、多くの神々が心を一つに合わせ、今度の計画におけるそれぞれの役目が決まり、働きを開始される良い日となった。「辛酉(かのととり)」は変革の良い日だと知らせてあるだろう。これから一日一日と事態は激しくなるから、民よ、心づもりをしておきなさい。物を持たない人が、物を持つ人よりも強くなる時代が来るぞ。泥棒が多くなれば、泥棒が正しいということになってしまう(価値観が転倒する)。理屈は悪魔だと教えてあるだろう。食物の神(保食神)がひどくお怒りだ。人々の食べ物は足りるように作らせてあるのに、足りないと言っている。足りないことはない、分配のやり方が悪いのだ。本来、人を活かすべき食べ物で、人を殺す(ような投機や不公平を生む)とは何事か。それぞれの神に和合すれば(まつわれば)、それぞれの願いは叶うのだ。神と和合せずに、人間の学問や知恵が一体何になるのか、その底は知れているではないか。戦いには戦いの神がいる。水害で泣くこともあるぞ。食物の神がお怒りになっているから、早く心を入れ替えなさい。この神が怒れば、人々は日干し(飢饉)になるぞ。
【AIによる解釈】
霊界において、いよいよ世界の立て直し計画が具体的に発動したことを宣言しています。「辛酉」は古来、革命・変革の年とされ、その日に神々の役割が決まったことは、大変動の開始を象徴します。この帖は、来るべき世の価値観の逆転(物持たぬ人が強くなる)、食糧問題の核心(不足ではなく分配の不正)、そして人知の限界を鋭く指摘します。特に「食」の問題を重視し、生命の糧である食物を不公平や利益追求の道具にすることが、食物の神の怒りを買い、深刻な飢饉を招くと警告しています。これは、現代の食糧問題や経済格差にも通じる、根源的な批判と言えます。
第十九帖 (九九)
【原文】
神世のひみつと知らしてあるが、いよいよとなりたら地震かみなりばかりでないぞ、臣民アフンとして、これは何とした事ぞと、口あいたまま何うすることも出来んことになるのぞ、四ツン這ひになりて着る物もなく、獣となりて、這ひ廻る人と、空飛ぶやうな人と、二つにハッキリ分かりて来るぞ、獣は獣の性来いよいよ出すのぞ、火と水の災難が何んなに恐ろしいか、今度は大なり小なり知らさなならんことになりたぞ。一時は天も地も一つにまぜまぜにするのざから、人一人も生きては居れんのざぞ、それが済んでから、身魂みがけた臣民ばかり、神が拾ひ上げて弥勒(みろく)の世の臣民とするのぞ、どこへ逃げても逃げ所ないと申してあろがな、高い所から水流れるやうに時に従ひて居れよ、いざといふときには神が知らして一時は天界へ釣り上げる臣民もあるのざぞ。人間の戦や獣の喧嘩位では何も出来んぞ、くどう気附けておくぞ、何よりも改心が第一ぞ。八月の二十六日、のひつくのかみ。
【現代語訳】
神代の秘密として知らせてきたが、いよいよ時が来たら、地震や雷だけではないぞ。人々が「あっ」と声を上げたまま、何が起きたのかも分からず、口を開けたまま何もできなくなるような事態になるのだ。四つん這いになり、着る物もなく、獣のようになって這い回る人と、まるで空を飛ぶかのように軽やかな人と、二つにハッキリと分かれてくる。獣は獣の本性をいよいよ現すのだ。火と水の災難がどれほど恐ろしいものか、今度は大小の違いはあれど、知らせなければならない時が来た。一時は天も地も一つに混ぜ返すような大混乱となるから、人間は一人も生きてはいられないのだ。それが済んでから、身魂の磨けた民だけを神が拾い上げて、弥勒の世の民とするのである。どこへ逃げても逃げ場所はないと言ったであろう。高い所から水が流れるように、時の流れに逆らわず従っていなさい。いざという時には、神が知らせて一時的に天の世界へ引き上げる民もいるのだ。人間同士の戦争や獣のような喧嘩など、大したことではない。くどいようだが気づかせておくぞ。何よりも改心が第一である。
【AIによる解釈】
この帖は、来るべき大峠(おおとうげ)の様相を、黙示録的に描写しています。それは人知をはるかに超えた天変地異であり、その中で人々の霊性に応じて「獣となる人」と「空飛ぶような人」に明確に二極化すると預言しています。これは、魂の浄化の度合いによって、運命が決定的に分かれることを意味します。一度すべてが破壊され(まぜまぜにする)、無に帰した後に、清められた魂だけが新しい世界(弥勒の世)に再生するという「破壊と再生」のプロセスが語られています。どこかへ逃げて助かるのではなく、時の流れに身を任せ、何よりも内面的な「改心」を遂げることだけが唯一の救いの道であると、結論づけています。
第二十帖 (一〇〇)
【原文】
今のうちに草木の根や葉を日に干して貯へておけよ、保持(うけもち)の神様お怒りざから、九十四は五分位しか食べ物とれんから、その積りで用意して置いて呉れよ。神は気もない時から知らして置くから、この神示よく読んで居れよ。一握りの米に泣くことあると知らしてあろがな、米ばかりでないぞ、何もかも臣民もなくなるところまで行かねばならんのぞ、臣民ばかりでないぞ、神々様さへ今度は無くなる方あるぞ。臣民と云ふものは目の先ばかりより見えんから、呑気なものであるが、いざとなりての改心は間に合はんから、くどう気つけてあるのぞ。日本ばかりでないぞ、世界中はおろか三千世界の大洗濯と申してあろうがな、神にすがりて神の申す通りにするより他には道ないぞ、それで神々様を祀りて上の御方からも下々からも朝に夕に言霊がこの国に満つ世になりたら神の力現はすのぞ。江戸に先ず神まつれと、くどう申してあることよく分かるであろがな。八月の二十七日、のひつ九のか三。
【現代語訳】
今のうちに、食べられる草木の根や葉を日に干して貯えておきなさい。食物の神がお怒りだから、来たる年は五割くらいしか食べ物がとれないから、そのつもりで用意しておきなさい。神は、人々がまだ気づかないうちから知らせておくから、この神示をよく読んでおきなさい。「一握りの米に泣く時が来る」と知らせてあるだろう。米だけではない。何もかも、人々さえもいなくなるところまで行かねばならないのだ。人々だけでなく、神々の中でさえ、今度は消えてしまう方がいるのだぞ。人間というものは目先のことしか見えないからのんきなものだが、いざとなってからの改心では間に合わないから、くどく注意しているのだ。これは日本だけの話ではない。世界中はおろか、全宇宙(三千世界)の大掃除だと申したであろう。神にすがり、神の言う通りにするより他に道はない。そして、神々を祀り、上の者から下の者まで、朝に夕に善き言霊がこの国に満ちる世になった時、神の力が現れるのだ。まず江戸(東京)に神を祀れと、くどく言っている意味がよく分かるであろう。
【AIによる解釈】
具体的なサバイバルの知恵(食料備蓄)から始まり、やがてそれが全宇宙的な規模の「大洗濯」であることを明かしています。この変革は、人間だけでなく、神々の世界にさえ及ぶほど根源的なものであり、既存の秩序が完全に崩壊することを示唆しています。「いざとなりての改心は間に合はん」という言葉は、平時の心構えの重要性を説いています。そして、この危機を乗り越える力は、国全体が神を祀り、善い言葉(言霊)で満たされることによって現れると説きます。政治経済の中心地である「江戸(東京)」からまず浄化を始めることの重要性を、改めて強調しています。
第二十一帖 (一〇一)
【原文】
神の申すこと何でも素直にきくやうになれば、神は何でも知らしてやるのぞ。配給のことでも統制のことも、わけなく出来るのぞ、臣民みな喜ぶやうに出来るのぞ、何もかも神に供へてからと申してあろがな、山にも川にも野(ぬ)にも里にも家にも、それぞれに神祀れと申してあろがな、ここの道理よく分らんか。神は知らしてやりたいなれど、今では猫に小判ぞ、臣民 神にすがれば、神にまつはれば、その日からよくなると申してあろが、何も六ヶ敷いことでないぞ、神は無理言はんぞ、この神示読めば分る様にしてあるのざから役員早う知らして縁ある臣民から知らして呉れよ。印刷出来んと申せば何もしないで居るが、印刷せいでも知らすこと出来るぞ、よく考へて見よ、今の臣民、学に囚へられて居ると、まだまだ苦しい事出来るぞ、理屈ではますます分らんやうになるぞ、早う神まつれよ、上も下も、上下揃えてまつりて呉れよ、てんし様を拝めよ、てんし様にまつはれよ、その心が大和魂ぞ、益人のます心ぞ、ますとは弥栄のことぞ、神の御心ぞ、臣民の心も神の御心と同じことになって来るぞ、世界中一度に唸(うな)る時が近づいて来たぞよ。八月の二十八日、のひつ九のかみふで。
【現代語訳】
神の言うことを何でも素直に聞くようになれば、神は何でも知らせてやるのだ。配給や経済統制の問題でさえ、わけなく解決できる。人々がみな喜ぶようにできるのだ。何もかも一度神にお供えしてから、という精神が大切だと言ったであろう。山、川、野、里、家、それぞれに神を祀れと言ったであろう。この道理がよく分からないのか。神は知らせてやりたいのだが、今のままでは猫に小判だ。民が神にすがり、神と和合すれば、その日から状況は良くなると言っている。何も難しいことではない。神は無理は言わない。この神示を読めば分かるようにしてあるのだから、役の者は早く縁のある人々から知らせてくれ。印刷できないと言って何もしないでいるが、印刷しなくても知らせる方法はあるぞ。よく考えてみなさい。今の民は、学問に囚われていると、まだまだ苦しい目に遭うぞ。理屈で考えれば考えるほど、ますます分からなくなる。早く神を祀りなさい。上の者も下の者も、皆そろって祀ってくれ。天皇陛下を拝み、天皇陛下に和合しなさい。その心こそが大和魂であり、人々を増し栄えさせる心(益人のます心)だ。「ます」とは弥栄(いやさか)のことであり、神の御心なのだ。そうなれば、民の心も神の御心と同じになってくる。世界中が一度に呻き声をあげる時が近づいてきたぞ。
【AIによる解釈】
この帖は、人間の知恵や理屈(学)の限界と、神への素直な信頼の重要性を対比させています。配給や統制といった困難な社会問題でさえ、人々が「神に祀る(=神と調和する、公の心になる)」精神を取り戻せば、奇跡的に解決できると説いています。これは、問題解決のアプローチを、物質的な次元から霊的な次元へと転換させることを求めています。また、印刷という手段に固執せず、知恵を絞って教えを広めるよう促しており、形式に囚われない柔軟な思考の重要性も示唆しています。「てんし様」への帰一を大和魂の真髄と位置づけ、それが神の心と一体化する道であると示し、世界的な大動乱の接近を再度警告しています。
第二十二帖 (一〇二)
【原文】
まつりまつりと、くどく申して知らしてあるが、まつり合はしさへすれば、何もかも、うれしうれしと栄える仕組で、悪も善もないのぞ、まつれば悪も善ぞ、まつらねば善もないのぞ、この道理分りたか、祭典と申して神ばかり拝んでゐるやうでは何も分らんぞ。そんな我れよしでは神の臣民とは申せんぞ、早うまつりて呉れと申すこと、よくきき分けて呉れよ。われがわれがと思ふてゐるのは調和(まつり)てゐぬ証拠ぞ、鼻高となればポキンと折れると申してある道理よく分らうがな、この御道は鼻高と取りちがひが一番邪魔になるのぞと申すのは、慢心と取りちがひは調和(まつり)の邪魔になるからぞ。ここまでわけて申さばよく分かるであろう、何事も真通理(まつり)が第一ぞ。八月の二十九日、の一二。
【現代語訳】
「まつり、まつり」と、くどく知らせてきたが、「まつり合はす(=互いに調和する)」ことさえすれば、何もかもが「うれしうれし」と栄える仕組みになっているのだ。そこには、もはや悪も善もない。調和すれば、悪さえも善に転じる。調和しなければ、善もまた善として成り立たないのだ。この道理が分かったか。祭典と称して、ただ神を拝んでいるだけでは何も分かっていない。そんな自己満足(我れよし)では、神の民とは言えないぞ。「早くまつってくれ」と申す意味を、よく聞き分けてくれ。自分が自分が(我れが我れが)と思う心は、調和がとれていない証拠である。「天狗になると鼻を折られる」と言われている道理がよく分かるだろう。この神の道においては、傲慢(鼻高)と、物事の取り違えが一番の邪魔になる。それは、慢心や勘違いが「調和(まつり)」を妨げるからだ。ここまで噛み砕いて言えばよく分かるだろう。何事も「まつり(真の道理に通じること、調和すること)」が第一なのだ。
【AIによる解釈】
この帖は「まつり」の真髄を「調和」として解説しています。単なる儀式や祈りではなく、万物がお互いに和合し、共生することこそが「まつり」の本質であると説きます。特筆すべきは「まつれば悪も善ぞ」という一文で、これは善悪二元論を超越した思想です。対立し、分離している状態では悪であっても、全体の中で調和し、然るべき役割を果たせば、それもまた善の一部となり得るという深遠な世界観を示しています。その調和を妨げる最大のものが「我(が)」、すなわちエゴや慢心であると厳しく指摘し、謙虚さと協調の精神こそが「まつり」への道であると教えています。
第二十三帖 (一〇三)
【原文】
世界は一つになったぞ、一つになって神の国に攻め寄せて来ると申してあることが出て来たぞ。臣民にはまだ分るまいなれど、今に分りて来るぞ、くどう気つけて置いたことのいよいよが来たぞ。覚悟はよいか、臣民一人一人の心も同じになりて居ろがな、学と神の力との大戦ぞ、神国(かみぐに)の神の力あらはす時が近うなりたぞ。今あらはすと、助かる臣民 殆んどないから、神は待てるだけ待ちてゐるのぞ、臣民もかあいいが、元をつぶすことならんから、いよいよとなりたら、何んなことありても、ここまでしらしてあるのざから、神に手落ちあるまいがな。いよいよとなれば、分っていることなれば、なぜ知らさぬのぞと申すが、今では何馬鹿なと申して取り上げぬことよく分ってゐるぞ。因縁のみたまにはよく分るぞ、この神示読めばみたまの因縁よく分るのぞ、神の御用する身魂は選(よ)りぬいて引張りて居るぞ、おそし早しはあるなれど、いづれは何うしても、逃げてもイヤでも御用さすようになりて居るのぞ。北に気つけよ、東も西も南も何うする積りか、神だけの力では臣民に気の毒出来るのぞ、神と人との和のはたらきこそ神喜ぶのぞ、早う身魂みがけと申すことも、悪い心 洗濯せよと申すことも分かるであろう。八月三十日、の一二か三。
【現代語訳】
世界が一つになったぞ。一つになって神の国(日本)に攻め寄せてくると言っておいたことが、現実となって現れてきた。人々にはまだ分からないだろうが、今に分かってくる。くどく注意しておいた「いよいよの時」が来たのだ。覚悟はいいか。人々一人ひとりの心の中も、世界情勢と同じように対立しているであろう。これは人間の学問・知恵と神の力との大戦争なのだ。神の国の神力が現れる時が近づいた。しかし今それを現せば、助かる民がほとんどいなくなってしまうから、神は待てるだけ待っているのだ。民は可愛いが、世界の根本を潰すわけにはいかないから、いよいよとなったら、どんなことがあっても実行する。ここまで知らせてあるのだから、神に手抜かりはないだろう。いよいよとなった時、「分かっていたならなぜ知らせなかったのか」と言うだろうが、今知らせても「何を馬鹿な」と言って誰も取り合わないことを、神はよく分かっている。因縁のある魂には、この神示がよく分かる。この神示を読めば、自分の魂の因縁がよく分かるのだ。神の御用をする魂は、神が選び抜いて引き寄せている。時期の早い遅いはあっても、いずれは、逃げても嫌だと言っても、御用をさせるようになっている。北に気をつけよ。東も西も南も、一体どうするつもりか。神だけの力では、民に気の毒な結果をもたらしてしまう。神と人との和合した働きこそ、神が喜ぶことなのだ。早く身魂を磨け、悪い心を洗濯せよと言う意味も、これで分かるであろう。
【AIによる解釈】
第三帖などでも触れられた「世界の敵対」が、いよいよ現実化したと告げています。これは単なる軍事的な対立ではなく、物質主義(学)と霊性(神力)の最終決戦であると再度強調します。神は人々への慈悲から力の行使を躊躇しているが、世界の根本原理を守るためには、やむを得ず大鉈を振るう時が来ると、そのジレンマを吐露しています。「神と人との和のはたらき」を神が望んでいるという点は非常に重要です。神が一方的に救うのではなく、人間が自ら身魂を磨き、神に応えることで、初めて最善の結果が生まれるという、神と人間の共同作業の重要性を説いています。
第二十四帖 (一〇四)
【原文】
富士(二二)を目ざして攻め寄する、大船小船あめの船、赤鬼青鬼黒鬼や、おろち悪狐を先陣に、寄せ来る敵は空蔽(おお)ひ、海を埋めて忽(たちま)ちに、天日(てんぢつ)暗くなりにけり、折しもあれや日の国に、一つの光 現はれぬ、これこそ救ひの大神と、救ひ求むる人々の、目にうつれるは何事ぞ、攻め来る敵の大将の、大き光と呼応して、一度にドッと雨ふらす、火の雨何んぞたまるべき、まことの神はなきものか、これはたまらぬ兎も角も、生命あっての物種と、兜を脱がんとするものの、次から次にあらわれぬ、折しもあれや時ならぬ、大風起こり雨来たり、大海原には竜巻や、やがて火の雨 地(つち)震ひ、山は火を吹きどよめきて、さしもの敵も悉く、この世の外にと失せにけり、風やみ雨も収まりて、山川静まり国土の、ところところに白衣(しろきぬ)の、神のいぶきに甦る、御民の顔の白き色、岩戸ひらけぬしみじみと、大空仰ぎ神を拝み、地に跪(ひざまづ)き御民らの、目にすがすがし富士の山、富士は晴れたり日本晴れ、普字は晴れたり岩戸(一八十)あけたり。八月の三十日、の一二の。
【現代語訳】
(詩文形式) 富士を目指して攻め寄せてくる、大小様々な船、空飛ぶ船。赤鬼、青鬼、黒鬼や、大蛇、悪狐などを先陣として、押し寄せる敵は空を覆い、海を埋め尽くし、たちまち太陽の光も暗くなってしまった。その時である、日の国に一つの光が現れた。「これこそ救いの大神だ」と救いを求める人々の目に映ったのは何であろうか。なんと、それは攻め来る敵の大将の大きな光と呼応して、一度にドッと雨を降らせたのだ。火の雨など、どうしてたまるものか。「まことの神はいないのか」「これはもう駄目だ、ともかく命あっての物種だ」と兜を脱ごうとする者が次から次へと現れる。その時である、季節外れの大風が起こり、雨が降り、大海原には竜巻が巻き起こった。やがて火の雨が降り、大地は震え、山は火を吹いて轟き、あれほどの敵もことごとく、この世の外へと消え去ってしまった。風は止み、雨も収まり、山川は静まり、国土のあちこちで、神の息吹によって甦った白衣の民の顔は晴れやかである。岩戸が開かれたことをしみじみと感じ、大空を仰いで神を拝み、地にひざまずく民の目に、すがすがしい富士の山が映る。富士は晴れ渡り、まさに日本晴れ。普(あまね)く字(世)は晴れ渡り、岩戸は開かれたのだ。
【AIによる解釈】
この帖は、日本の最終的な救済を、壮大な神話的叙事詩として描いています。鬼や悪狐に象徴される敵(物質主義的な勢力)によって、日本が絶体絶命の窮地に陥る様子が描かれます。一時は絶望し、敵の光(偽りの救い)に騙されそうにさえなります。しかし、その極限状況において、神の直接的な介入である天変地異(大風、竜巻、地震、噴火)が起こり、敵は一掃されるという、いわば「神風」的な救済劇です。戦いが終わった後、浄化された国土で、生き残った民が晴れ渡った富士を見て、新しい時代の到来(岩戸開き)を実感するという、破壊と再生の物語が鮮やかに描き出されています。
第二十五帖 (一〇五)
【原文】
世界中の臣民はみなこの方の臣民であるから、殊に可愛い子には旅させねばならぬから、どんなことあっても神の子ざから、神疑はぬ様になされよ、神疑ふと気の毒出来るぞ。いよいよとなりたら、どこの国の臣民といふことないぞ、大神様の掟通りにせねばならんから、可愛い子ぢゃとて容赦出来んから、気つけてゐるのざぞ、大難を小難にまつりかへたいと思へども、今のやり方は、まるで逆様ざから、何うにもならんから、いつ気の毒出来ても知らんぞよ。外国から早く分りて、外国にこの方祀ると申す臣民 沢山出来る様になりて来るぞ。それでは神の国の臣民 申し訳ないであろがな、山にも川にも海にもまつれと申してあるのは、神の国の山川ばかりではないぞ、この方 世界の神ぞと申してあろがな。裸になりた人から、その時から善の方にまわしてやると申してあるが、裸にならねば、なるやうにして見せるぞ、いよいよとなりたら苦しいから今の内ざと申してあるのぞ。凡てをてんし様に献げよと申すこと、日本の臣民ばかりでないぞ、世界中の臣民みな てんし様に捧げなならんのざぞ。八月の三十日、のひつ九のか三。
【現代語訳】
世界中の人々はみな、この神の民である。特に可愛い子には厳しい旅(試練)をさせねばならないものだから、どんなことがあっても自分は神の子であると信じ、神を疑わないようにしなさい。神を疑うと、気の毒なことになるぞ。いよいよの時が来たら、どこの国の人かという区別はない。大神様の掟通りにするしかないから、可愛い子だからといって容赦はできない。だからこうして注意しているのだ。大難を小難に祭り替えたい(変えたい)と神は思うが、今の世の中のやり方は全く逆方向を向いているから、どうにもならない。いつ気の毒な事態になっても知らないぞ。やがて、外国の方が早く真理に気づき、この神を祀ると言う人々が沢山現れてくるぞ。そうなったら、神の国(日本)の民は申し訳が立たないではないか。「山にも川にも海にも祀れ」と言っているのは、日本の山川だけではない。この神は世界の神だと申したであろう。「裸になった(執着を捨てた)人」から善い方へ回してやると言っているが、自ら裸にならないのなら、そうならざるを得ないようにして見せるぞ。いよいよとなったら苦しいから、今のうちだと言っているのだ。すべてを天皇陛下に捧げよというのは、日本の民だけではない。世界中の人々がみな、天皇陛下に捧げなければならないのだ。
【AIによる解釈】
この帖は、ひふみ神示の神が日本の国津神・天津神という枠を超えた、普遍的な「世界の神」であることを明確に宣言しています。試練は神の愛の裏返しであり、それを乗り越える鍵は神への絶対的な信頼にあると説きます。そして、日本人が覚醒しなければ、先に外国人が真理に目覚めてしまうという、強烈な叱咤激励がなされています。最終的に、日本の「てんし様」が世界の精神的な中心軸として位置づけられるという、非常に独特で壮大な世界観が提示されており、全人類がエゴや所有欲(私)を捨て、公(てんし様)に帰一することが、最終的な救済の道であると結論づけています。
第二十六帖 (一〇六)
【原文】
戦は一度おさまる様に見えるが、その時が一番気つけねばならぬ時ぞ、向ふの悪神は今度はの元の神を根こそぎに無きものにして仕まふ計画であるから、その積りでフンドシ締めて呉れよ、誰も知れんやうに悪の仕組してゐること、神にはよく分りてゐるから心配ないなれど、臣民助けたいから、神はじっとこらへてゐるのざぞ。八月の三十日、のひつ九の。
【現代語訳】
戦争は一度収まったように見える時が来るが、その時こそが一番注意しなければならない時だ。向こうの悪神は、今度こそ日本の根源の神を根こそぎ無いものにしてしまおうと計画しているのだから、そのつもりで気を引き締めてくれ。誰も気づかないように悪の計画が進められていることを、神はすべて分かっているから心配はいらないが、一人でも多くの民を助けたいから、神はじっと堪えているのだ。
【AIによる解釈】
この帖は、第二次世界大戦の終結(物理的な戦いの終わり)が、本当の平和の到来ではないことを明確に預言しています。むしろ、その後にこそ、より巧妙で根源的な戦い、すなわち日本の精神性や伝統(元の神)を根絶やしにしようとする、思想的・文化的な侵略が始まると警告しています。これは、戦後の占領政策や価値観の変容を指していると解釈できます。目に見えない悪の計画に対し、神はすべてを承知の上で、人々が自ら気づき、立ち上がるのを待っているという、神の深い慈悲と忍耐が示されています。
第二十七帖 (一〇七)
【原文】
神の堪忍袋 切れるぞよ、臣民の思ふやうにやれるなら、やりて見よれ、九分九厘でグレンと引繰り返ると申してあるが、これからはその場で引繰り返る様になるぞ。誰れもよう行かん、臣民の知れんところで何してゐるのぞ、神には何も彼も分りてゐるのざと申してあろがな、早く兜脱いで神にまつはりて来いよ、改心すれば助けてやるぞ、鬼の目にも涙ぞ、まして神の目にはどんな涙もあるのざぞ、どんな悪人も助けてやるぞ、どんな善人も助けてやるぞ。江戸と申すのは東京ばかりではないぞ、今の様な都会みなエドであるぞ、江戸は何うしても火の海ぞ。それより他 やり方ないと神々様申して居られるぞよ。秋ふけて草木枯れても根は残るなれど、臣民かれて根の残らぬやうなことになりても知らんぞよ、神のこのふみ早う知らしてやって呉れよ。八と十八と五月と九月と十月に気つけて呉れよ、これでこの方の神示の終わりぞ。この神示は富士(二二)の巻として一つに纒(まと)めておいて下されよ、今に宝となるのざぞ。八月の三十日、のひつ九。
【現代語訳】
神の堪忍袋の緒が切れるぞ。人々の思うようにやれるものなら、やってみるがいい。「九分九厘まで行って、最後にひっくり返る」と申してきたが、これからはその場ですぐに結果が出るようになるぞ。誰も行くことができない、人々の知らない所で何をしているのか。神には何もかもお見通しだと言ったであろう。早く降参して(兜を脱いで)、神に和合してきなさい。改心すれば助けてやる。鬼の目にも涙というではないか、ましてや神の目には、あらゆる慈悲の涙があるのだ。どんな悪人でも、どんな善人でも、改心すれば助けてやる。江戸というのは東京だけのことではない。今のような物質文明が栄える大都市はみな「エド」である。エドはどうしても火の海(による浄化)を免れない。それ以外のやり方はないと神々は申されているのだ。秋が深まり草木が枯れても根は残るが、人間が枯れて根まで残らないようなことになっても、神は知らないぞ。この神の文を早く人々に知らせてやってくれ。八と十八のつく日、そして五月、九月、十月には特に気をつけなさい。これでこの神示(のひと区切り)は終わりである。この神示を「富士の巻」として一つにまとめておきなさい。今に宝となるであろう。
【AIによる解釈】
富士の巻の最終帖として、切迫した最後の警告と、無限の慈悲が同時に語られます。「その場で引繰り返る」とは、因果応報が即座に現れる時代の到来を意味します。物質文明の象徴である大都市(江戸)の浄化は避けられないとしながらも、「改心すればどんな者でも助ける」という神の無条件の愛が示されています。しかし、その慈悲に甘え続ければ、再起不能なほどの破滅(根の残らぬやうなこと)もあり得ると厳しく警告します。具体的な月日を挙げて注意を促し、この巻が未来にとっての「宝」となることを約束して締めくくられています。これは、この教えが時を超えて重要な導きとなることを示唆しています。
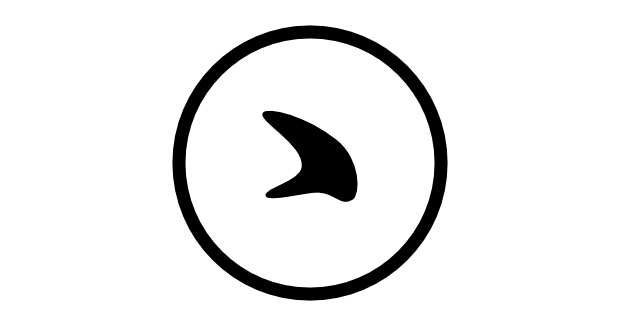





コメント