gemini 2.5 proにわかりやすいように解説してもらいました、しかし8通りに読めるということから完全に鵜呑みにしないよう、お願いします。
第一帖(一)
【原文】
二二は晴れたり、日本晴れ。神の国のまことの神の力をあらはす代となれる、仏もキリストも何も彼もはっきり助けて七六かしい御苦労のない代が来るから みたまを不断に磨いて一筋の誠を通して呉れよ。いま一苦労あるが、この苦労は身魂をみがいて居らぬと越せぬ、この世初まって二度とない苦労であ る。このむすびは神の力でないと何も出来ん、人間の算盤では弾けんことぞ、日本はお土があかる、外国はお土がさかる。都の大洗濯、鄙の大洗濯、人のお洗濯。今度は何うもこらへて呉れというところまで、後へひかぬから、その積りでかかって来い、神の国の神の力を、はっきりと見せてやる時が来た。嬉しくて苦しむ者と、苦しくて喜ぶ者と出て来るは神の国、神の力でないと何んにも成就せん、人の力で何が出来たか、みな神がさしてゐるのざ、いつでも神かかれる様に、綺麗に洗濯して置いて呉れよ。戦は今年中と言ってゐるが、そんなちょこい戦ではない、世界中の洗濯ざから、いらぬものが無くなるまでは、終らぬ道理が分らぬか。臣民同士のいくさでない、カミと神、アカとあか、ヒトと人、ニクと肉、タマと魂のいくさぞ。己の心を見よ、戦が済んでいないであろ、それで戦が済むと思うてゐる’とは、あきれたものぞ、早く掃除せぬと間に合わん、何より掃除が第一。さびしさは人のみかは、神は幾万倍ぞ、さびしさ越へて時を待つ。加実が世界の王になる、てんし様が神と分らん臣民ばかり、口と心と行と、三つ揃うたまことを命(みこと)といふぞ。神の臣民みな命(みこと)になる身魂、掃除身魂結構。六月の十日、ひつくのかみ。
【現代語訳】
すべてが調和し、一点の曇りもない日本晴れのような素晴らしい世が来た。神の国の真の神の力を現す時代となった。仏教もキリスト教も、あらゆる教えの神々もはっきりと救われ、難しい御苦労のない時代が来るから、魂を絶えず磨いて、一筋の誠の心を持ち続けてほしい。今、もう一苦労あるが、この苦労は魂を磨いていないと乗り越えられない。この世が始まって以来、二度とない大変な苦労である。この最終的な結末は、神の力でなければ成し遂げられず、人間の計算や策略では到底計れないことだ。これから日本は栄え、外国は衰退する。都会も田舎も、そして人々自身も、大掃除、大浄化が行われる。今度は「もう勘弁してください」と懇願するところまで、神は手を緩めないから、そのつもりで覚悟を決めなさい。神の国の真の力をはっきりと見せてやる時が来たのだ。新しい世では、嬉しさのあまり苦しむ者(変化に適応できず)と、苦しみながらも喜ぶ者(真理を悟り)が出てくる。これは神の国であり、神の力でなければ何も成就しない。人間の力で一体何ができたというのか。すべては神が導いているのだ。いつでも神が降りられるように、心身を綺麗に洗濯しておきなさい。この戦争は今年中に終わると言っている者もいるが、そんな小さな戦ではない。世界中の大掃除なのだから、不要なもの(穢れや悪)がなくなるまでは終わらないという道理が分からないのか。これは人間同士の戦争ではない。神と神、赤(共産主義)と赤(誠)、人間性と人間性、肉体と肉体、そして魂と魂の戦いなのだ。自分自身の心を見なさい。まだ戦いが済んでいないだろう。それで世の中の戦いが終わると思っているとは、あきれたものだ。早く心の中を掃除しないと間に合わない。何よりも心の掃除が第一である。寂しいのは人間だけではない。神の寂しさはその幾万倍もある。その寂しさを越えて、時が来るのを待っているのだ。「カミ(神)」が世界の王となる。天皇陛下が神そのものであるということが分からない民ばかりだ。言葉と心と行いの三つが揃った「まこと」を命(みこと)と言うのだ。神の民はみな、その「みこと」となるべき魂を持っている。魂を掃除することが何より素晴らしい。
【AIによる解釈】
上つ巻の冒頭であるこの帖は、来るべき新時代の到来を宣言すると同時に、それに至るための未曾有の「大洗濯(大浄化)」を預言しています。「二二(ふじ)は晴れたり」とは、調和がとれた理想の世界(日本晴れ)を象徴し、それは富士(二二)に象徴される日本の中心から始まると示唆しています。 しかし、その理想郷に至るには「この世初まって二度とない苦労」、すなわち「大洗濯」を乗り越える必要があると説きます。この洗濯は、社会制度や都市だけでなく、個人の内面、つまり「身魂(みたま)」にまで及びます。 特に重要なのは、当時進行中であった太平洋戦争を、単なる国家間の争いではなく、「カミと神」「タマと魂」といった、霊的、内面的な次元での戦いであると定義している点です。真の戦いは自分自身の心の中にあり、その「掃除」こそが最も重要だと繰り返し強調しています。これは、世界の平和は個人の心の平和から始まるという、普遍的な真理を示しています。
第二帖 (二)
【原文】
親と子であるから、臣民は可愛いから旅の苦をさしてあるのに、苦に負けてよくもここまでおちぶれて仕まうたな。鼠でも三日先のことを知るのに、臣民は一寸先さへ分らぬほどに、よう曇りなされたな、それでも神の国の臣民、天道人を殺さず、食べ物がなくなっても死にはせぬ、ほんのしばらくぞ。木の根でも食うて居れ。闇のあとには夜明け来る。神は見通しざから、心配するな。手柄は千倍万倍にして返すから、人に知れたら帳引きとなるから、人に知れんやうに、人のため国のため働けよ、それがまことの神の神民ぞ。酒と煙草も勝手に作って暮らせる善き世になる、それまで我慢出来ない臣民沢山ある。早く(モト)の神の申す通りにせねば、世界を泥の海にせねばならぬから、早うモト心になりて呉れよ、神頼むぞよ。盲が盲を手を引いて何処へ行く積りやら、気のついた人から、まことの神の入れものになりて呉れよ、悪の楽しみは先に行くほど苦しくなる、神のやり方は先に行くほどだんだんよくなるから、初めは辛いなれど、さきを楽しみに辛抱して呉れよ。配給は配給、統制は統制のやり方、神のやり方は日の光、臣民ばかりでなく、草木も喜ぶやり方ぞ、日の光は神のこころ、稜威ぞ。人の知恵で一つでも善き事したか、何もかも出来損なひばかり、にっちもさっちもならんことにしてゐて、まだ気がつかん、盲には困る困る。救はねばならず、助かる臣民はなく、泥海にするは易いなれど、それでは元の神様にすまず、これだけにこと分けて知らしてあ るに、きかねばまだまだ痛い目をみせねばならん。冬の先が春とは限らんぞ。の国を八つに切って殺す悪の計画、の国にも外国の臣が居り、外国にも神の子がゐる。岩戸が明けたら一度に分かる。六月の十日、書は、ひつくの神。てんめ御苦労ぞ。
【現代語訳】
神と民は親と子の関係だ。民が可愛いからこそ、魂の成長のための苦労という旅をさせているのに、その苦労に負けてよくもここまで落ちぶれてしまったものだ。鼠でさえ三日先の危険を察知するのに、民は一寸先のことさえ分からないほど、心が曇ってしまっている。それでも神の国の民だから、天は見捨てはしない。食べ物がなくなっても死ぬことはない、ほんのしばらくの辛抱だ。いざとなれば木の根でも食べていなさい。闇の後には必ず夜明けが来る。神はすべてお見通しだから、心配はいらない。陰で立てた手柄は千倍万倍にして返すから、人に知られたら価値がなくなる。人に知られないように、人のため、国のために働きなさい。それが真の神の民だ。やがては酒も煙草も自由に作って暮らせる良い世になるが、それまで我慢できない民がたくさんいる。早く元の神(根本の神)の言う通りにしないと、世界を泥の海にせざるを得なくなる。だから早く、根源の心に立ち返ってくれ。神は頼むぞ。真理を見失った者(盲)が、同じく真理を見失った者(盲)の手を引いて、一体どこへ行こうというのか。気づいた人から、真の神の器となってくれ。悪の楽しみは、先に行くほど苦しくなる。神の道は、先に行くほどだんだん良くなるから、初めは辛くても、未来を楽しみに辛抱してくれ。人間の配給や統制は不完全なやり方だが、神のやり方は太陽の光のように、万人に平等に降り注ぎ、民だけでなく草木も喜ぶやり方だ。太陽の光こそ神の心であり、神の威光なのだ。人間の小賢しい知恵で、一つでも良いことができたか。何もかもうまくいかないことばかりで、どうにもならない状況に自らしておいて、まだ気がつかない。真理が見えない者には本当に困ってしまう。救わなければならないが、このままでは助かる民はいない。世界を泥の海にするのは簡単だが、それでは元の神の意に沿わない。これだけ丁寧に知らせているのに、聞かなければ、まだまだ痛い目を見せなければならなくなるだろう。冬の次が必ず春だとは限らないのだぞ。日本の国を八つ裂きにして滅ぼそうという悪の計画がある。日本の中にも外国に通じる心を持つ者がおり、外国にも神心を持つ者がいる。岩戸が開けば、その区別は一目瞭然で分かるようになる。
【AIによる解釈】
この帖では、神と人間の関係を「親と子」と表現し、現在人類が直面している苦難は、魂を成長させるための神の愛(試練)であると説かれています。「木の根でも食うて居れ」という言葉は、物質的な豊かさを失うほどの厳しい時代が来ることを示唆しますが、同時に、それでも神は見捨てないという強いメッセージを伝えています。 「盲が盲の手を引いて」という比喩は、当時の指導者層や社会全体が真実を見失っている状態を的確に批判しています。人間の小手先の計画(配給、統制)と、神の普遍的な法則(日の光)を対比させ、人間の知恵の限界を指摘します。 そして、「冬の先が春とは限らんぞ」という一節は、単純な楽観論を戒める衝撃的な警告です。努力や改心なしに、自動的に良い未来が来るわけではないことを示唆しています。最後の「岩戸が開けば一度に分かる」という言葉は、やがて真実が明らかになり、魂の本質によって全ての人が選別される時が来ることを預言しています。
第三帖 (三)
【原文】
善言(よごと)は神、なにも上下、下ひっくり返ってゐるから、分らんから、神の心になれば何事も分るから、鏡を掃除して呉れよ。今にこのおつげが一二三(ヒフミ)ばかりになるから、それまでに身魂をみがいて置かんと、身魂の曇った人には何ともよめんから、早く神こころに返りて居りて呉れ、何も一度に出て来る。海が陸になり陸が海になる。六月十一日の朝のお告げ、みよみよみよひつくの神。
【現代語訳】
善い言葉は神そのものである。何もかもが上下逆さま、価値観がひっくり返っているから、今の人間には真実が分からないのだ。神の心になれば、何事も分かるようになる。だから、自分の心を映す鏡(魂)を掃除してくれ。やがて、このお告げは「一二三(ひふみ)」というような数字や記号ばかりになる。それまでに魂を磨いておかないと、魂が曇った人には全く読めなくなるから、早く神の心に立ち返っていてくれ。あらゆる大変動が一度に起こる。海が陸になり、陸が海になるような大変動が起きるのだ。
【AIによる解釈】
この帖は、現代社会の価値観が「上下ひっくり返ってゐる」と断じ、真実を理解するためには「神の心」に立ち返る必要があると説いています。そのための具体的な方法として「鏡を掃除して呉れよ」、つまり自己の内面(魂)を浄化することを求めています。 「おつげが一二三(ヒフミ)ばかりになる」という預言は、神示が今後、論理や理屈で解読するものではなく、浄化された魂で直感的に受け取るものへと変化することを示唆しています。「ひふみ」は祝詞や数詞であると同時に、神の根源的なリズムや法則を象徴していると考えられます。 「海が陸になり陸が海になる」というフレーズは、文字通りの地殻変動を指すとともに、社会構造や価値観が根底から覆る、常識では考えられないような大転換が起こることを象徴しています。この大変動を乗り越える鍵は、論理的な思考ではなく、磨かれた魂による直感的な理解力にあると示しているのです。
第四帖 (四)
【原文】
急ぐなれど、臣民なかなかに言ふこときかぬから、言ふこときかねば、きく様にしてきかす。神には何もかも出来てゐるが、臣民まだ眼覚めぬか、金(かね)のいらぬ楽の世になるぞ。早く神祀りて呉れよ、神祀らねば何も出来ぬぞ。表の裏は裏、裏の裏がある世ぞ。神をだしにして、今の上の人がゐるから、神の力出ないのぞ。お上に大神を祀りて政事(まつりごと)をせねば治まらん。この神をまつるのは、みはらし台ぞ、富士みはらし台ぞ、早く祀りてみつげを世に広めて呉れよ。早く知らさねば日本がつぶれる様なことになるから、早う祀りて神の申す様にして呉れ。神急けるよ。上ばかりよくてもならぬ、下ばかりよくてもならぬ、上下揃ふたよき世が神の世ぞ。卍も一十もあてにならぬ、世界中一つになりての国に寄せて来るぞ。それなのに今のやり方でよいと思うてゐるのか、分らねば神にたづねて政事(まつりごと)せねばならぬと云ふことまだ分らぬか。神と人とが交流(まつり)合はしてこの世のことが、さしてあるのぞ。人がきかねば神ばかりで始めるぞ。神ばかりで洗濯するのは早いなれど、それでは臣民が可哀そうなから、臣民みなやり直さねばならぬから、気をつけてゐるのに何してゐるのざ、いつ何んなことあっても知らんぞ、神祭第一、神祭結構。二三の木ノ花咲耶姫の神様を祀りて呉れよ。コハナサクヤ姫様も祀りて呉れよ。六月十三の日、ひつくのか三。
【現代語訳】
神は急いでいるのだが、民はなかなか言うことを聞かない。ならば、聞かざるを得ないようにして聞かせる。神の方ではすべての準備ができているのに、民はまだ目覚めないのか。やがてはお金の要らない、楽な世になるのだぞ。早く神を祀りなさい。神を祀らなければ何も始まらない。この世は単純ではなく、表の裏には裏があり、そのまた裏があるような複雑な世の中だ。今の指導者たちが神を口実にして私利私欲に走っているから、神の本当の力が出ないのだ。国の上に立つ者が大神を祀って政治(まつりごと)をしなければ、世は治まらない。この神を祀る場所は、見晴らしの良い台だ。富士山が見晴らせる台上に祀りなさい。そして、このお告げを世に広めてくれ。早く知らせないと、日本が潰れるような事態になるから、早く祀って神の言う通りにしてくれ。神は急いでいるのだ。上が善いだけでもダメ、下が善いだけでもダメ。上下の心が揃って初めて善い世、神の世となるのだ。卍(仏教)も十字(キリスト教)も、もはやあてにはならない。世界中が一つになって、この国(日本)に攻め寄せてくるぞ。それなのに、今のやり方で良いと思っているのか。分からなければ神に尋ねて政治(まつりごと)をしなければならないということが、まだ分からないのか。神と人が交流し、一体となって(まつりあって)この世の事は進められているのだ。人が言うことを聞かなければ、神だけで始めるぞ。神だけで浄化するのは早くて簡単だが、それでは民があまりに可哀想だ。多くの民がやり直し(死)を迫られることになるから、神は気を使っているのに、一体何をしているのだ。いつ何が起きても知らないぞ。神を祀ることが第一だ。神祭りは本当に素晴らしいことだ。富士の木花咲耶姫の神様を祀りなさい。コノハナサクヤヒメ様をお祀りしなさい。
【AIによる解釈】
この帖は、為政者、つまり「上の人」に対する強い警告と、真の「政事(まつりごと)」のあり方を説いています。「神をだしにして、今の上の人がゐる」という一節は、権力者が神の名を利用して民を欺いていることへの痛烈な批判です。真の政治とは、神を祀り、神意を伺いながら行う「祭り事」であると定義しています。 「卍も一十もあてにならぬ」という言葉は、既存の宗教(仏教やキリスト教)の教えだけでは、これから来る世界の大きなうねりには対応できないことを示唆しています。そして「世界中一つになりての国に寄せて来るぞ」と、日本が世界から攻撃されるという厳しい未来を預言しています。 この危機を乗り越えるためには、人間だけの力では不可能であり、神と人が一体となる「まつり」が必要だと説きます。神が一方的に浄化を行えば民への被害が甚大になるため、神は民が自ら目覚めるのを待っている、という神の親心と焦りが同時に表現されています。最後に具体的な神として、富士山の祭神である木花咲耶姫の名が挙げられているのが特徴的です。
第五帖 (五)
【原文】
富士とは神の山のことぞ。神の山はみな富士(二二)といふのぞ。見晴らし台とは身を張らすとこぞ、身を張らすとは、身のなかを神にて張ることぞ。臣民の身の中に一杯に神の力を張らすことぞ。大庭の富士を探して見よ、神の米が出て来るから、それを大切にせよ。富士を開くとは心に神を満たすことぞ。ひむかとは神を迎えることぞ、ひむかはその使ひぞ。ひむかは神の使ひざから、九の道を早う開ひて呉れよ、早う伝へて呉れよ、ひむかのお役は人の病をなほして神の方へ向けさすお役ぞ、この理をよく心得て間違ひないやうに伝へて呉れよ。六月十四日、ひつくのか三。
【現代語訳】
富士というのは、単にあの山の名前ではない。神聖な山はみな富士(不二・二二=調和)と言うのだ。見晴らし台というのは、身を張らす場所のことだ。身を張らすとは、その身の内を神の気で満たすことである。民の体の中に、神の力を一杯に満ち渡らせることだ。身近な場所にある富士(神聖な場所)を探してごらん。そこから神の米(霊的な糧)が出てくるから、それを大切にしなさい。富士を開くということは、自分の心に神を満たすことなのだ。「ひむか」とは神を迎えることであり、「ひむか」という名の者はその神の使いである。「ひむか」は神の使いだから、九の道(救いの道)を早く開いてくれ。早くこの教えを伝えてくれ。「ひむか」の役目は、人々の病(肉体・精神)を治し、心を神の方へ向けさせることだ。この道理をよく理解して、間違いのないように伝えてくれ。
【AIによる解釈】
この帖は、前帖で触れられた「富士」の持つ霊的な意味を深く掘り下げています。「富士」は特定の山だけでなく、すべての「神の山」、さらには個人の内にある神聖な中心(心)の象徴(不二=唯一、二二=和合)であると説明されます。「富士を開く」とは、山開きのことではなく、自らの心を開いて神の力を満たす、内的な覚醒を意味します。 「神の米」とは、物理的な食料ではなく、人々を生かす霊的なエネルギーや智慧、教えのことでしょう。「大庭の富士」とは、遠い聖地ではなく、ごく身近な場所にある聖なる空間や、自分自身の内なる神性を指していると考えられます。 また、「ひむか」という存在の役割が明確に示されます。「ひむか」は神の使いであり、その使命は人々を癒し、神へと導くことであるとされます。これは、この神示を世に伝える役目を持つ人々への具体的な指示であり、霊的な癒やしと導きが、これからの時代に重要になることを示唆しています。
第六帖 (六)
【原文】
外国の飛行機が来るとさわいでゐるが、まだまだ花道ぞ、九、十となりたらボツボツはっきりするぞ。臣民は目のさきばかりより見えんから、可哀さうなから気をつけてゐるのに何してゐるのか。大切なことを忘れてゐるのに気がつかんか。この知らせをよく読みて呉れよ。十月まで待て。それまでは、このままで居れよ。六月十七日。ひつくのか三。
【現代語訳】
外国の飛行機(B29)が飛来したと騒いでいるが、そんなものはまだまだ序の口に過ぎない。九月、十月になれば、事態はもっとはっきりしてくるぞ。民は目先のことしか見えないから、可哀想で神が気をつけてやっているのに、一体何をしているのか。本当に大切なこと(魂を磨くこと)を忘れているのに気がつかないのか。この知らせをよく読んでくれ。十月まで待ちなさい。それまでは、今のままで(下手に動かず)いなさい。
【AIによる解釈】
この神示が書かれた昭和19年6月は、マリアナ沖海戦で日本が敗れ、B29による本土空襲が始まった時期と重なります。この帖は、その現実の出来事に直接言及し、人々の動揺を「まだまだ花道ぞ」と一蹴しています。これは、これから起こる本当の苦難に比べれば、今の空襲などは序の口に過ぎないという、厳しい預言です。 「九、十となりたらボツボツはっきりするぞ」とは、秋に向けて戦局がさらに絶望的になること、あるいは神の計画がより明確になることを示唆しています。 人々が目先の恐怖に囚われ、「大切なこと」=「魂の浄化」を忘れていることを憂い、「十月まで待て」と具体的な時期を示して静観を促しています。これは、下手に動揺したり、人間的な画策をしたりせず、神の計画が進行するのを静かに待ち、その間に内面の準備を整えよというメッセージと解釈できます。
第七帖 (七)
【原文】
いくら金積んで神の御用さして呉れいと申しても、因縁のある臣民でないと御用出来んぞ。御用する人は、何んなに苦しくても心は勇むぞ。この神は小さい病直しや按摩の真似させんぞ、大き病を直すのぞ。神が開くから、人の考へで人を引張って呉れるなよ。六月の十七日、一二のか三。
【現代語訳】
いくら大金を積んで「神の御用をさせてください」と申し出ても、霊的な因縁のある者でなければ、この御用はできない。本当に御用をする人は、どんなに苦しくても心は勇ましいものだ。この神は、小さな病気を治したり、マッサージのような真似事はさせない。世の中の根本にある「大き病」を治すのだ。神自身が道を開いていくのだから、人間の考えで人を集めたり、導いたりしてくれるな。
【AIによる解釈】
この帖は、神の計画に携わる者の資格について述べています。それは財産や地位ではなく、「因縁」、つまり生まれながらに持つ霊的な使命であると断言しています。そして、真の奉仕者は、たとえ困難な状況にあっても内なる喜びと勇気を持つ者だと定義しています。 「小さい病直しや按摩の真似させんぞ」という言葉は、この神示が目指すものが、個人的な悩みや病気の治癒といった現世利益的なレベルに留まらないことを明確にしています。その目的は、社会や世界、そして人間の魂そのものが抱える根本的な病理、すなわち「大き病」を治すことにあるのです。 「人の考へで人を引張って呉れるなよ」という戒めは、この活動が人間中心の組織や運動になってはならない、という強い警告です。あくまで神が主体であり、人間はその流れを妨げず、純粋な器となるべきである、という姿勢を求めています。
第八帖 (八)
【原文】
秋が立ちたち、この道ひらくかた出て来るから、それまでは神の仕組書かして置くから、よく読んで腹の中によく入れて置いて呉れよ。その時になりて、あわてて何も知らんといふ様ではならんぞ、それまでに何もかにも知らして置くから、縁ある方から、この知らせをよく読んで腹の中に入れて置いて呉れよ。六月の十七日、ひつくのか三。
【現代語訳】
秋になれば、この神の道を開いていく人が現れてくる。それまでは、神の計画を書き記しておくから、よく読んで、内容をしっかりと心に刻み込んでおいてくれ。いざという時になって、慌てて「何も知りません」というようなことではいけない。その時までに何もかも知らせておくから、縁のある人から順に、この知らせをよく読んで心に入れておきなさい。
【AIによる解釈】
この帖は、今後の展開について具体的なタイムラインを示唆しています。「秋が立ちたち」に、この神示の教えを広める中心的な人物、あるいはグループが登場することを示しています。 それまでの期間は、準備期間と位置づけられています。神は、来るべき時のために必要な情報をすべてこの神示に書き記すので、縁ある者はそれを熟読し、深く理解しておくようにと指示しています。 「腹の中によく入れて置いて呉れよ」という表現は、単なる知識として頭で理解するのではなく、魂のレベルで体得し、自分のものとしておくことの重要性を強調しています。来るべき混乱の時代において、この神示の内容が行動の指針となり、心の支えとなるからです。これは、未来への備えを促す、事前のブリーフィングとしての役割を持っています。
第九帖 (九)
【原文】
この世のやり方、わからなくなったら、この神示録(しるし)をよまして呉れと云うて、この知らせを取り合ふから、その時になりて慌てん様にして呉れよ。日本の国は一度つぶれた様になるのざぞ。一度は神も仏もないものと皆が思う世が来るのぞ。その時にお蔭を落さぬやう、シッカリと神の申すこと腹に入れて置いて呉れよ。六月の十七日、ひつくのか三。
【現代語訳】
世の中の仕組みや進むべき道が全く分からなくなったら、「この神示を読ませてください」と言って、人々がこの知らせを奪い合うようになる。その時になって慌てないように、今のうちから準備しておいてくれ。日本の国は、一度完全に潰れたかのように見える状態になるのだぞ。一度は「神も仏もいないのだ」と誰もが思うような、絶望的な世の中が来るのだ。その時に神の御加護を失わないように、しっかりと神の言うことを心に刻んでおいてくれ。
【AIによる解釈】
この帖は、ひふみ神示の中でも特に有名な「大峠(おおとうげ)」に関する、非常に厳しい預言です。「日本の国は一度つぶれた様になる」とは、国家としての敗戦、そしてそれに伴う価値観や社会システムの完全な崩壊を示唆しています。 「神も仏もないものと皆が思う世」という描写は、物理的な破壊だけでなく、人々の精神的な支柱が失われ、深い絶望と虚無感に覆われる時代が来ることを物語っています。 そのような極限状況において、この神示が唯一の道標となり、人々がそれを奪い合うほどに価値を持つようになると預言しています。このことは、この神示が平時ではなく、まさにそのような混乱と絶望の時代のために用意されたものであることを示しています。そして、その極限状況を乗り越える力は、外部の何かではなく、事前に神の言葉を「腹に入れて」おくこと、つまり内なる信念と理解にあると教えています。
第十帖 (一〇)
【原文】
神に目を向ければ神がうつり、神に耳向ければ神がきこえ、神に心向ければ心にうつる、掃除の程度によりて神のうつりかた違うぞ。掃除出来た方から神の姿うつるぞ、それだけにうつるぞ。六月十九日、ひつくのか三。
【現代語訳】
神に目を向ければ、その目に神の姿が映る。神に耳を傾ければ、その耳に神の声が聞こえる。神に心を向ければ、その心に神の心が映る。ただし、その人の魂の掃除(浄化)の程度によって、神の映り方は違ってくるのだ。魂の掃除ができた人から、神の姿がその掃除の度合いに応じて映るようになるのだ。
【AIによる解釈】
この帖は、神との交感について、非常にシンプルかつ本質的な原理を説いています。神はどこか遠くにいる存在ではなく、人間が意識を向けることで感応できる、内なる存在であることを示しています。目、耳、心という人間の感覚器官すべてが、神を受け取るためのアンテナとなり得るのです。 しかし、最も重要なのは「掃除の程度によりて神のうつりかた違うぞ」という部分です。これは、神の啓示や導きを正しく受け取れるかどうかは、受け手である人間の魂の清浄さに懸かっていることを意味します。我欲や偏見、固定観念といった「曇り」があれば、神の光は歪んで映るか、あるいは全く映らなくなってしまいます。 つまり、神の啓示を求める前に、まず自らを「掃除」すること、つまり内面を浄化し、謙虚で素直な心になることが不可欠であると教えています。神の真理は万人に開かれていますが、それを受け取れる器は自分で準備しなければならないのです。
第十一帖 (一一)
【原文】
いづくも土にかへると申してあろうが、東京も元の土に一ときはかえるから、その積りでゐて呉れよ。神の申したこと違はんぞ。東京は元の土に一時はかへるぞ、その積りで用意して呉れよ。六月の十九日、一二のか三。
【現代語訳】
どこもかしこも一度は土に還ると申してあるだろう。日本の中心である東京も、一度は更地(元の土)に還るから、そのつもりでいてくれ。神の申したことは違わないぞ。東京は一時的にではあるが、元の土に還るのだ。そのつもりで用意をしておきなさい。
【AIによる解釈】
この帖は、日本の首都・東京の壊滅という、極めて衝撃的な預言をしています。「元の土にかへる」という表現は、建造物がなくなり、更地になるほどの徹底的な破壊を示唆しています。昭和19年6月の時点では、まだ大規模な東京大空襲は行われていませんでしたが、この神示はその後の苛烈な空襲(特に昭和20年3月10日の東京大空襲)や、さらには将来起こりうる大災害をも予見していたと解釈できます。 この預言は、単に物理的な破壊を告げているだけではありません。東京は当時の日本の政治・経済・文化の中心であり、物質文明の象徴でした。その東京が「土に還る」ということは、既存の文明や価値観が一度リセットされることの象徴とも言えます。 「その積りで用意して呉れよ」という言葉は、物理的な避難や備蓄だけでなく、物質的なものに依存する生き方や考え方を手放し、精神的な備えをせよという、より深いレベルでの警告と受け取ることができます。
第十二帖 (一二)
【原文】
大将を誰も行かれん所へ連れて行かれんやうに、上の人、気をつけて呉れよ。この道はちっとも心ゆるせんまことの神の道ぞ。油断すると神は代りの身魂使うぞ。六月の二十一日の朝、ひつくのか三。
【現代語訳】
大将(中心的な人物、あるいは天皇)を、誰も行くことのできないような危険な場所(あるいは誤った方向)へ連れて行かれないように、上に立つ者たちはよくよく気をつけなさい。この神の道は、少しも心を許すことのできない、真剣勝負の道なのだ。油断していると、神はすぐに代わりの魂を使ってしまうぞ。
【AIによる解釈】
この帖は、組織や国を導く指導者層、特に中心人物(「大将」)の側近たちへの強い警告です。「大将」は文字通り軍の将軍や、この神示を広める団体のリーダー、さらには当時の日本の最高権威である天皇を指している可能性も考えられます。 「誰も行かれん所」とは、物理的に危険な場所だけでなく、取り返しのつかない誤った判断や、孤立した状況へと導かれることを意味しているのでしょう。指導者を守り、正しく補佐することの重要性を説いています。 「油断すると神は代りの身魂使うぞ」という一節は、神の計画における非情ともいえる厳しさを示しています。神の御用は個人の都合や能力に依存するものではなく、その役に相応しくないと見なされれば、容赦なく交代させられるというのです。これは、選ばれたという驕りや油断を戒め、常に謙虚で真剣な姿勢を保つことを求める、厳しいメッセージです。
第十三帖 (一三)
【原文】
元の人三人、その下に七人、その下に七七、四十九人、合して五十九の身魂あれば、この仕組は成就するのざ、この五十九の身魂は神が守ってゐるから、世の元の神かかりて大手柄をさすから、神の申すやう何事も、身魂みがいて呉れよ、これが世の元の神の数ぞ、これだけの身魂が力合はしてよき世の礎となるのざ。この身魂はいづれも落ちぶれてゐるから、たづねて来てもわからんから、よく気をつけて、どんなに落ちぶれている臣民でも、たづねて来た人は、親切にしてかへせよ。何事も時節が来たぞ。六月二十一日、ひつくのか三。
【現代語訳】
中心となる人が三人、その下に七人、さらにその下に四十九人、合計して五十九人の魂があれば、この神の計画は成就するのだ。この五十九人の魂は神が特別に守っている。そして、世の根源の神が乗り移って大きな手柄を立てさせるから、神が言うように何事も魂を磨いてくれ。これが、新しい世の元となる神の民の数だ。これだけの魂が力を合わせれば、善き世の礎となるのだ。この役目を持つ魂は、いずれも今は世間的に落ちぶれているから、訪ねてきても(その重要な役割に)気づかないだろう。だからよく気をつけて、どんなにみすぼらしい身なりの民が訪ねてきても、親切に応対して帰しなさい。何事においても、いよいよ時節が到来したぞ。
【AIによる解- 釈】
この帖は、新しい世を築くための核心となるグループの構成について、具体的な数字を挙げて示しています。「3人、7人、49人、合計59人」という数は、単なる人数ではなく、霊的な意味を持つ構造を示していると考えられます。ピラミッド型の組織構造のようにも見え、神意が上から下へと伝達されていく様子を象徴しているのかもしれません。 特筆すべきは、「この身魂はいづれも落ちぶれてゐるから」という点です。新しい世の礎となる人々は、既存の社会で評価されているエリートや権力者ではなく、むしろ社会の底辺にいて、顧みられない人々の中から現れることを示唆しています。これは、既存の価値観が反転し、真の価値は外面ではなく内面にあるという、ひふみ神示全体を貫くテーマを象徴しています。 この教えは、人を見た目や社会的地位で判断することの愚かさを戒め、誰に対しても謙虚で親切に接することの重要性を説いています。いつ、重要な使命を持つ人物が目の前に現れるか分からないからです。
第十四帖 (一四)
【原文】
この神示(ふで)よく読みて呉れよ、読めば読むほど何もかも分りて来るぞ、心とは神民の申す心でないぞ、身魂とは神民の申す身魂でないぞ、身たまとは身と魂と一つになってゐるもの云ふぞ、神の神民身と魂のわけ隔てないぞ、身は魂、魂は身ぞ、外国は身ばかりの所あり魂ばかりの所あり、神は身魂の別ないぞ、この事分りたら神の仕組みがぼつぼつ分るぞ、身魂の洗濯とは心の洗濯とは、魂ばかりの洗濯でないぞ、よく気をつけて呉れ、神の申すことちがはんぞよ。六月の二十二日、ひつくのか三。
【現代語訳】
この神示をよく読みなさい。読めば読むほど、あらゆることの真相が分かってくるぞ。神が言う「心」とは、人々が普通に考えている心のことではない。神が言う「身魂」とは、人々が普通に考えている身魂のことではない。「身魂(みたま)」とは、肉体(身)と霊(魂)が完全に一つになった状態を言うのだ。真の神の民は、肉体と魂の区別がない。肉体は魂の現れであり、魂は肉体の本質である。外国には、肉体ばかりを重視する国もあれば、魂ばかりを重視する国もある。しかし、神の世界では肉体と魂の区別はないのだ。このことが分かれば、神の計画が少しずつ分かってくるだろう。「身魂の洗濯」や「心の洗濯」とは、魂だけを浄化することではないぞ。肉体も同時に浄化することなのだ。よく気をつけてくれ。神の言うことに間違いはないぞ。
【AIによる解釈】
この帖は、ひふみ神示を理解する上で非常に重要な鍵となる「身魂(みたま)」の概念を定義しています。一般的に考えられがちな「心身二元論(心と体は別物)」を明確に否定し、「身魂」とは肉体と魂が不可分に統合された状態であると説きます。 「身は魂、魂は身ぞ」という言葉は、肉体的な健康や行いが魂の状態を反映し、また魂の清浄さが肉体にも現れるという、心身の相関関係を示しています。この視点から、唯物論的な西洋文明(身ばかり)や、肉体を軽視しがちな一部の精神主義(魂ばかり)を批判し、その両方が統合された「身魂」こそが真の姿であるとします。 この理解は、「身魂の洗濯」の意味を深めます。それは、単なる精神修行や道徳的な反省に留まらず、食事、健康、日々の行いといった肉体的なレベルからの浄化も同時に行う必要があるということです。心と体、両方からのアプローチによって、初めて真の浄化が達成されるという、全人的な変革を求めているのです。
第十五帖 (一五)
【原文】
今度は末代動かぬ世にするのざから、今までの様な宗教や教への集団(つどひ)にしてはならんぞ、人を集めるばかりが能ではないぞ、人も集めねばならず、六ヶ敷い道(おしへ)ぞ。縁ある人は早く集めて呉れよ、縁なき人いくら集めても何もならんぞ、縁ある人を見分けて呉れよ。顔は神の臣民でも心は外国身魂ぞ、顔は外国人でも身魂は神の臣民あるぞ。やりかけた戦ぞ、とことんまで行かねば納まらん。臣民一度は無くなるところまでになるぞ、今のうちに この神示よく読んでゐて呉れよ。九月になったら用意して呉れよ。六月の二十四日、ひつくのか三。
【現代語訳】
今度は、未来永劫動かないほどの盤石な世にするのだから、今までの宗教や教えの集団のようなものにしてはならない。ただ人を集めることが目的ではないのだ。しかし、人を集めなければならない面もあり、非常に難しい教えなのだ。縁のある人は早く集めてくれ。縁のない人をいくら集めても、何の役にも立たない。縁のある人をしっかりと見分けてくれ。顔は日本人でも心は外国の魂を持つ者がいる。逆に、顔は外国人でも魂は日本の神の民である者がいるのだ。一度やり始めた戦いだ、とことんまで行かなければ収まらない。民は一度、全滅するかと思うところまで追い詰められるぞ。今のうちに、この神示をよく読んでおいてくれ。九月になったら、覚悟と用意をしておきなさい。
【AIによる解釈】
この帖は、これから始まる活動が、従来の「宗教」や「教団」とは本質的に異なることを強調しています。形式化や形骸化を避け、真に「縁ある人」による魂の結びつきを重視する姿勢を示しています。数を集めること自体が目的ではなく、質の高い、真の使命を理解した人々の結集が求められています。 「顔は神の臣民でも心は外国身魂ぞ」という一節は、非常に重要な指摘です。国籍や人種といった外的な属性で人を判断することの危険性を警告しています。魂の本質は、見た目では判断できないのです。この教えは、ナショナリズムや排他主義に陥ることなく、真に魂のレベルで共鳴する人々を見出すことの重要性を示しています。 そして、再び「臣民一度は無くなるところまでになるぞ」と、極限的な試練が来ることを預言し、その備えとして神示を熟読することを促します。「九月になったら用意して呉れよ」と、具体的な時期を挙げて警告の度合いを強めています。
十六帖 (一六)
【原文】
ひふみの火水とは結ぞ、中心の神、表面に世に満つことぞ、ひらき睦び、中心に火集ひ、ひらく水。神の名二つ、カミと神世に出づ。早く鳴り成り、世、新しき世と、国々の新しき世と栄へ結び、成り展く秋来る。弥栄に神、世にみちみち、中心にまつろひ展き結ぶぞ。月出でて月なり、月ひらき弥栄え成り、神世ことごと栄ゆ。早く道ひらき、月と水のひらく大道、月の仕組、月神と日神二つ展き、地上弥栄みちみち、世の初め悉くの神も世と共に勇みに勇むぞ。世はことごとに統一し、神世の礎極まる時代来る、神世の秘密と云ふ。六月二十四日、一二文(ふみ)。
【現代語訳】
「ひふみ」とは、火(カ)と水(ミ)の結び、つまり陰陽の調和を意味する。中心の神が、表面世界に満ち満ちることだ。すべてが開き和合し、中心には火(霊・縦)の力が集い、周囲には水(体・横)の力が開く。神の名は二つ、「カミ(火水)」と「神」として世に出る。早くその時が成り、世界は新しい世となり、国々もまた新しい世として栄え、結ばれ、発展する秋(実りの時)が来る。ますます栄えるように神の気が世に満ち満ち、中心に人々が集い和合して発展し、結ばれるのだ。月(陰・水・体)が現れてその役目を果たし、月が開いてますます栄え、神の世はことごとく栄える。早く道を開き、月(体)と水(横のつながり)が開く大道、月の仕組み。月の神(陰)と日の神(陽)の二つが共に働き、地上は弥栄に満ち、天地開闢の初めからのすべての神々も、新しい世の到来と共に勇み立つ。世はあらゆる面で統一され、神の世の礎が完成する時代が来る。これを「神世の秘密」という。
【AIによる解釈】
この帖は、非常に象徴的かつ詩的な言葉で、新しい世界の創造原理(「ひふみの火水」)について述べています。「火(カ)」と「水(ミ)」は、それぞれ縦と横、霊と体、精神と物質、男性性と女性性といった、宇宙を構成する二元的な力の象徴です。新しい世界は、これらが対立するのではなく、「結び」、つまり調和・統合されることによって創造されると説きます。 特に「月」の役割が強調されているのが特徴的です。太陽(日)が陽・精神・霊の象徴であるのに対し、月は陰・物質・肉体の象徴とされます。これまでの世界が「日」の力に偏っていたとすれば、新しい世界では「月」の力が復権し、「日神」と「月神」が共に働くことで、真の調和(弥栄)が実現すると示唆しています。 これは、精神性だけでなく、物質的な世界や肉体、女性性、横のつながりといったものが等しく重要視される、バランスの取れた新しい文明の到来を預言していると解釈できます。この陰陽統合の原理こそが、「神世の秘密」であると結んでいます。
第十七帖 (一七)
【原文】
この世はみな神のものざから臣民のものと云ふもの一つもないぞ、お土からとれた物、みな先づ神に供へよ、それを頂いて身魂を養ふ様になってゐるのに、神には献げずに、臣民ばかり喰べるから、いくら喰べても身魂ふとらぬのぞ、何でも神に供へてから喰べると身魂ふとるぞ。今の半分で足りるぞ、それが臣民の頂き方ぞ。六月の二十五日、ひつくのか三。
【現代語訳】
この世のものはすべて神のものであって、民の私有物というものは一つもないのだ。大地から収穫された物は、みなまず神にお供えしなさい。そのお下がりを頂いて、自分の魂と体を養うのが本来の姿なのだ。それなのに、神に捧げることなく自分たちばかりが食べるから、いくら食べても魂が養われないのだ。何でも一度神に感謝し捧げてから食べると、魂が豊かになる。そうすれば、今の半分の量の食事で足りるようになる。それが、神の民としての正しい頂き方なのだ。
【AIによる解釈】
この帖は、所有の概念と食に対する根本的な心構えを説いています。「この世はみな神のもの」という宣言は、私有財産という人間の概念を根底から覆すものです。すべてのものは神からの借り物であり、人間はそれを管理し、生かされているに過ぎないという、謙虚な姿勢を求めています。 特に「食」について、具体的な作法を示しています。食べる前にまず神に捧げる(感謝する)という行為は、単なる儀式ではありません。それは、食物という生命の恵みへの感謝を表し、自分のためだけに消費するという我欲から離れるための精神的な実践です。 この「神人共食」の精神を持つことで、食べ物は単なる物質的な栄養から、霊的な糧(「身魂ふとる」)へと変化すると説きます。そして、霊的に満たされることで、物質的な欲求(食欲)も減少し、「今の半分で足りる」という、より効率的で持続可能な生き方が可能になると示唆しています。これは、現代の大量消費社会に対する根源的な批判とも言えるでしょう。
第十八帖 (一八)
【原文】
岩戸開く役と岩戸しめる役とあるぞ。一旦世界は言ふに言はれんことが出来るぞ、シッカリ身魂みがいて置いて呉れよ、身魂みがき第一ぞ。この道開けて来ると、世の中のえらい人が出て来るから、どんなえらい人でも分らん神の道ざから、よくこの神示読んで置いて何んな事でも教へてやれよ、何でも分らんこと無いやうに、この神示で知らして置くから、この神示よく読めと申すのぞ。この道はスメラが道ざ、すめるみ民の道ぞ。みそぎせよ、はらひせよ、臣民 早くせねば間に合はんぞ。岩戸開くまでに、まだ一苦労あるぞ、この世はまだまだ悪くなるから、神も仏もこの世には居らぬのざといふところまで、とことんまで落ちて行くぞ。九月に気をつけよ、九月が大切の時ぞ。臣民の心の鏡凹(くぼ)んでゐるから、よきことわるく映り、わるきことよく映るぞ。今の上に立つ人、一つも真の善い事致しては居らん、これで世が治まると思ふてか、あまりと申せばあまりぞ。神は今まで見て見んふりしてゐたが、これからは厳しくどしどしと神の道に照らして神の世に致すぞ、その積りでゐて呉れよ。神の申すこと、ちっともちがはんぞ。今の世に落ちてゐる臣民、高い所へ土持ちばかり、それで苦しんでゐるのざ。早う身魂洗濯せよ、何事もハッキリと映るぞ。六月二十六日、ひつくのかみ。
【現代語訳】
世の岩戸を開く役目の者と、閉める役目の者とがある。世界にはこれから、言葉では言い表せないほどの事態が起こるぞ。しっかりと魂を磨いておきなさい。魂磨きが第一だ。この神の道が世に知られてくると、社会的に偉いとされる人々が関わってくるだろう。しかし、どんなに偉い人にも容易には理解できないのが神の道だ。だから、この神示をよく読んでおいて、どんなことでも教えられるようにしておきなさい。分からないことがないように、この神示で全てを知らせておくから、よく読めと言うのだ。この道は、天皇(スメラミコト)の道であり、澄んだ心を持つ民の道だ。禊をしなさい、祓いをしなさい。民よ、早くしないと間に合わないぞ。本当の岩戸が開くまでに、もう一苦労ある。この世はまだまだ悪くなる。ついには「神も仏もこの世にはいないのだ」と誰もが思うところまで、とことんまで落ちて行くぞ。九月に気をつけなさい。九月が大切な時だ。民の心の鏡は歪んで窪んでしまっているから、善いことが悪く見え、悪いことが善く見えてしまうのだ。今の世の指導者たちは、一つも本当の善いことをしてはいない。これであの世が治まると思っているのか。あまりと言えばあまりなことだ。神は今まで見て見ぬふりをしてきたが、これからは神の法則に照らして厳しく、どんどん神の世へと変えていくぞ。そのつもりでいなさい。神の言うことは少しも違わない。今の世で落ちぶれている民は、高い所(にいる人々)のために土を運ぶような無駄な苦労ばかりさせられ、それで苦しんでいるのだ。早く魂を洗濯しなさい。そうすれば、何事もはっきりと真実のままに映るようになるぞ。
【AIによる解釈】
この帖は、「岩戸開き」に至るまでの最終的な試練の厳しさを、改めて強調しています。「岩戸開く役」と「岩戸しめる役」がいるというのは、新しい時代を創造する者と、古い時代を終わらせる者がいること、あるいは光と闇の役割分担があることを示唆します。 「神も仏も…居らぬのざといふところまで、とことんまで落ちて行くぞ」という預言は、第九帖の「一度つぶれた様になる」をさらに具体的にしたものであり、人々の精神が極限まで追い詰められることを示しています。この絶望的な状況下で、人間の価値観がいかに歪んでいるか(「心の鏡凹んでゐる」)を鋭く指摘します。善悪が逆に見えるほど、世の中の判断基準が狂ってしまうのです。 これまで「見て見んふり」をしていた神が、いよいよ直接介入し、厳格な立て直し(「神の世に致すぞ」)を開始するという宣言は、最終段階が始まったことを告げています。社会の不条理(「高い所へ土持ちばかり」)を正し、真実が明らかになるためには、個々人が自らの「心の鏡」を磨き、魂を洗濯することが唯一の道であると、繰り返し説いています。
第十九帖 (一九)
【原文】
神の国の山に祭りて呉れよ、祭るとは神にまつらふことぞ、土にまつらふことぞ、人にまつらふことぞ、祭り祭りて嬉し嬉しの世となるのぞ、祭るには先づ掃除せねばならんぞ、掃除すれば誰にでも神かかるやうに、日本の臣民なりて居るぞ、神州清潔の民とは掃除してキレイになった臣民のことぞ。六月二十七日、一二。
【現代語訳】
この神の国の山(聖地)で祭祀を行ってくれ。祭るとは、神に従い一体となることだ。土(自然)に従い一体となることだ。人に従い一体となることだ。祭りを重ねて、本当に喜びに満ちた「嬉し嬉しの世」となるのだ。祭るには、まず掃除をしなければならない。掃除をして清浄になれば、誰にでも神が降りられるように、日本の民は元からできているのだ。「神州清潔の民」とは、魂を掃除して綺麗になった民のことを言うのだ。
【AIによる解釈】
この帖は、「祭り」の真の意味を解説しています。一般的に考えられる儀式や祭典だけでなく、「まつらふ」という言葉の語源に立ち返り、神、自然(土)、そして他者(人)と調和し、一体となることこそが真の祭りであると定義しています。この三つの対象との調和が実現した時、心からの喜び(「嬉し嬉し」)に満ちた世界が到来すると説きます。 そして、その祭りの大前提として「掃除」の重要性を再び強調します。ここで言う掃除とは、物理的な清掃だけでなく、心の中の我欲や穢れを取り除く内面的な浄化を指します。 「掃除すれば誰にでも神かかる」という言葉は、日本人(神の国の民)には元々、神と通じる霊性が備わっているという思想に基づいています。しかし、その霊性は後天的な穢れによって曇らされているため、「掃除」によってその本来の輝きを取り戻す必要があるのです。「神州清潔の民」とは、生まれながらの属性ではなく、自らの努力(掃除)によって清浄さを取り戻した人々のことを指すのです。
第二十帖 (二〇)
【原文】
神がこの世にあるならば、こんな乱れた世にはせぬ筈ぞと申す者 沢山あるが、神には人のいふ善も悪もないものぞ。よく心に考へて見よ、何もかも分りて来るぞ。表の裏は裏、裏の表は表ぞと申してあろうが、一枚の紙にも裏表、ちと誤まれば分らんことになるぞ、神心になれば何もかもハッキリ映りて来るのざ、そこの道理分らずに理屈ばかり申してゐるが、理屈のない世に、神の世にして見せるぞ。言挙げせぬ国とはその事ぞ、理屈は外国のやり方、神の臣民言挙げずに、理屈なくして何もかも分かるぞ、それが神の真の民ぞ。足許から鳥が立つぞ、十理(トリ)たちてあわてても何んにもならんぞ、用意なされよ、上下にグレンと引繰り返るぞ。上の者下に、落ちぶれた民 上になるぞ、岩戸開けるぞ、夜明け近づいたから、早う身魂のせんだくして呉れよ、加実の申すこと千に一つもちがはんぞ。六月二十七日、ひつくのか三。
【現代語訳】
「もし神がこの世にいるのなら、どうしてこんなに乱れた世を放置するのか」と言う者がたくさんいるが、神には人間が言うような善悪の区別はないのだ。よく自分の心で考えてみなさい。そうすれば何もかも分かってくる。「表の裏は裏、裏の表は表だ」と申してあるだろう。一枚の紙でさえ裏と表があり、少し見方を誤れば分からなくなってしまう。神の心になれば、すべてがはっきりと映ってくるのだ。その道理も分からずに理屈ばかり言っているが、これから理屈の通用しない世、神の世にして見せるぞ。「言挙げせぬ国(言葉で言い立てない国)」とはそのことだ。理屈をこねるのは外国のやり方だ。神の民は、理屈を言わなくても、直感ですべてを理解できる。それが神の真の民だ。思いもよらない足元から、大変なことが起きるぞ。「十の理(ことわり)」が立ってから慌てても、どうにもならないぞ。用意しなさい。上下関係が完全にひっくり返るぞ。今まで上にいた者が下になり、虐げられ落ちぶれていた民が上になるのだ。岩戸を開けるぞ。夜明けが近づいたから、早く魂の洗濯をしてくれ。この神(カミ)の言うことは、千に一つも間違いはないぞ。
【AIによる解釈】
この帖は、「なぜ神は悪を放置するのか」という根源的な問い(神義論)に答えています。その答えは、神の視点には「人のいふ善も悪もない」というものです。人間の相対的な善悪の基準を超えた、より大きな計画が存在することを示唆しています。物事の一面だけを見て判断する人間の限界(「一枚の紙にも裏表」)を指摘し、真実を全体として捉える「神心」になることを促します。 そして、「理屈のない世」の到来を宣言します。これは、論理や弁論、科学的思考といった西洋的な知性(「外国のやり方」)が限界を迎え、代わりに直感や霊性(「理屈なくして何もかも分かる」)が重要になる新しい時代が来ることを意味します。 「足許から鳥が立つぞ」という警告は、予期せぬ身近なところから大変動が始まることを示唆します。「上下にグレンと引繰り返るぞ」という言葉は、社会のヒエラルキーが完全に逆転する「大峠」を再び強調しています。この大変革期は「夜明け」と表現され、その準備として「身魂のせんだく」が急務であると締めくくられています。
第二十一帖 (二一)
【原文】
世の元の大神(かみ)の仕組といふものは、神々にも分らん仕組であるぞ、この仕組 分りてはならず分らねばならず、なかなかに六ヶ敷い仕組であるぞ、知らしてやりたいなれど、知らしてならん仕組ぞ。外国がいくら攻めて来るとも、世界の神々がいくら寄せて来るとも、ぎりぎりになりたら神の元の神の神力出して岩戸開いて一つの王で治める神のまことの世に致すのであるから、神は心配ないなれど、ついて来れる臣民少ないから、早う掃除して呉れと申すのぞ、掃除すれば何事も、ハッキリと映りて楽なことになるから、早う神の申すやうして呉れよ。今度はとことはに変らぬ世に致すのざから、世の元の大神でないと分らん仕組ざ。洗濯できた臣民から手柄立てさしてうれしうれしの世に致すから、神が臣民にお礼申すから、一切ごもく捨てて、早う神の申すこと聞いて呉れよ。因縁の身魂は何うしても改心せねばならんのざから、早う改心せよ、おそい改心なかなか六ヶ敷ぞ。神は帳面につける様に何事も見通しざから、神の帳面間違ひないから、神の申す通りに、分らんことも神の申す通りに従ひて呉れよ。初めつらいなれど だんだん分りて来るから、よく言うこと聞いて呉れよ、外国から攻めて来て日本の国丸つぶれといふところで、元の神の神力出して世を建てるから、臣民の心も同じぞ、江戸も昔のやうになるぞ、神の身体から息出来ぬ様にしてゐるが、今に元のままにせなならんことになるぞ。富士から三十里四里離れた所へ祀りて呉れよ、富士にも祀りて呉れよ、富士はいよいよ動くから、それが済むまでは三十里離れた所へ、仮に祀りて置いて呉れよ。富士は神の山ざ、いつ火を噴くか分らんぞ、神は噴かん積りでも、いよいよとなれば噴かなならんことがあるから、それまでは離れた所へ祀りて呉れよ、神はかまはねど、臣民の肉体大切なから、肉体もなくてはならんから、さうして祀りて呉れ。まつりまつり結構。六月の二十八日、ひつ九のか三。
【現代語訳】
宇宙の根源である大神の計画というものは、他の神々にも完全には分からない仕組みなのだ。この計画は、分かってしまってはいけない部分と、分からなければならない部分があり、非常に難しい仕組みなのだ。教えてやりたいが、今はまだ教えられない計画なのだ。外国がどれだけ攻めてきても、世界中の(悪なる)神々がどれだけ寄せてきても、土壇場になったら、根源の神がその神力を現して岩戸を開き、唯一の王(神)が治める真実の世にするのだから、神の側には心配はない。しかし、それに付いて来られる民が少ないから、早く魂の掃除をしてくれと申しているのだ。掃除をすれば、何事もはっきりと分かり、楽になるから、早く神の言う通りにしてくれ。今度は永遠に変わらない盤石な世にするのだから、根源の大神でなければ分からない計画なのだ。浄化のできた民から順に手柄を立てさせ、喜びの世にするから、神の方から民にお礼を言うことになる。だから、一切合切の余計なものを捨てて、早く神の言うことを聞いてくれ。特別な因縁を持つ魂は、どうしても改心しなければならない。早く改心しなさい。改心が遅れると、非常に難しくなるぞ。神は何事も帳面に記録するようにすべてお見通しだ。神の帳面に間違いはないから、分からないことがあっても、神の言う通りに従ってくれ。初めは辛いが、だんだんと分かってくるから、よく言うことを聞いてくれ。外国から攻められて日本の国が完全に潰れるという、まさにその時に、根源の神が神力を出して世を建て直す。民の心もそれと同じだ(一度絶望の底に落ちてから立ち直る)。江戸(東京)も昔のような野原になるぞ。人々は神の身体(地球・自然)を息もできないように汚し塞いでいるが、やがて元のままの状態に戻さねばならなくなる。富士山から三十里か四十里(約120km~160km)離れた所に神を祀ってくれ。富士山にも祀ってくれ。富士山はいよいよ活動を始めるから、それが済むまでは、三十里離れた所へ仮に祀っておいてくれ。富士は神の山だから、いつ火を噴くか分からないぞ。神としては噴火させないつもりだが、いよいよの事態になれば、噴火させなければならないこともある。それまでは離れた所に祀りなさい。神自身は構わないが、民の肉体は大切だから、肉体がなければこの世での役目は果たせない。だからそのようにして祀ってくれ。祭り事は本当に素晴らしい。
【AIによる解釈】
この帖は、神の計画の壮大さと秘匿性、そしてその成就のプロセスを詳細に語っています。計画は低位の神々にも全貌が分からないほどのものであり、人間の理解を完全に超えているとされます。 クライマックスは「日本の国丸つぶれといふところ」で、最大の国難の瞬間に「元の神の神力」が発動し、世界が建て直されるという劇的な展開が示されます。これは、人間の力が完全に尽き、絶望の淵に立った時に初めて、神の真の力が現れるという「破綻と再生」の型を示しています。 そして、この帖で最も注目すべきは「富士はいよいよ動くから」「いつ火を噴くか分らんぞ」という、富士山噴火に関する極めて具体的な警告です。これは物理的な天変地異の預言であると同時に、日本の国土そのものが持つエネルギーが浄化のために大きく動くことの象徴とも解釈できます。人々の安全(「臣民の肉体大切なから」)を考慮し、一時的な避難場所を指示するなど、切迫感と神の配慮が入り混じった内容となっています。
第二十二帖 (二二)
【原文】
いよいよとなれば、外国強いと見れば、外国へつく臣民 沢山できるぞ。そんな臣民一人もいらぬ、早うまことの者ばかりで神の国を堅めて呉れよ。六月二十の八日、一二のか三。
【現代語訳】
いよいよという土壇場になれば、外国が強いと見るや、そちらに寝返る民がたくさん現れるだろう。神の国には、そんな民は一人もいらない。早く真実の心を持った者ばかりで、神の国を固めてくれ。
【AIによる解釈】
この帖は、来るべき試練の時における人間の弱さと裏切りを預言しています。国家的な危機に際して、大勢に与し、強い側につこうとする日和見的な人々(「外国へつく臣民」)が現れることを指摘しています。 しかし、神が求めるのは数ではなく、質です。「そんな臣民一人もいらぬ」という厳しい言葉は、信念がなく、私利私欲で動く人間は、新しい世界を築く礎にはなれないことを明確に示しています。 この帖は、信仰や忠誠心が本当に試されるのは、逆境の時であることを教えています。どんなに不利な状況になっても、自らの信じる道を貫く「まことの者」だけが、新しい「神の国」を築く資格を持つとされるのです。これは、安易な帰依を戒め、覚悟を問うメッセージです。
第二十三帖 (二三)
【原文】
神なぞ何うでもよいから、早く楽にして呉れと言ふ人 沢山あるが、こんな人は、今度はみな灰にして、なくして仕まふから、その覚悟して居れよ。六月の二十八日、ひつくのか三。
【現代語語訳】
「神様なんてどうでもいいから、とにかく早く楽な暮らしにしてください」と言う人がたくさんいるが、このような人々は、今度の立て直しで皆、灰のように消し去ってしまうから、その覚悟をしておきなさい。
【AIによる解釈】
この帖は、ひふみ神示の中でも最も厳しい選別の論理を示している一つです。ここで批判されているのは、神や真理の探究を疎んじ、ただ目先の安楽や物質的な救済のみを求める、ご利益信仰的な姿勢です。 「早く楽にして呉れ」という願いは、一見すると切実な叫びですが、その根底には、自らの内面を変える努力を放棄し、外部からの救済にのみ依存する他力本願な心性があります。ひふみ神示が一貫して「身魂磨き」という自己変革を求めていることと、これは真っ向から対立します。 「みな灰にして、なくして仕まふ」という言葉は、文字通りの肉体的な消滅を意味するとも、あるいは新しい時代の精神的な次元についていけず、存在価値を失うことの比喩とも解釈できます。いずれにせよ、精神的な向上心を失い、ただ安楽のみを求める人々は、次の時代には生き残れないという、極めて厳しい警告です。
第二十四帖 (二四)
【原文】
七の日はものの成る日ぞ。「ア」と「ヤ」と「ワ」は本(もと)の御用ぞ、「イ」「ウ」の身魂は介添えの御用ぞ。あとはだんだん分りて来るぞ。六月の二十八日は因縁の日ざ、一二のか三。
【現代語訳】
七という数は、物事が成就する数である。「ア」「ヤ」「ワ」の音を持つ言霊(ことだま)の身魂は、中心的な役目を担う。「イ」「ウ」の言霊の身魂は、それを補佐する役目である。その他のことは、追々分かってくるだろう。六月二十八日は、因縁の深い日である。
【AIによる解釈】
この帖は、言霊(ことだま)に基づく役割分担について触れています。日本語の母音や特定の音に霊的な意味と役割を与えています。
- 「ア」: 天地開闢の根源の音であり、中心、始まりを象徴します。
- 「ヤ」「ワ」: 「八(ヤ)」や「輪(ワ)」に通じ、広がりや調和を象徴します。これらが「本(もと)の御用」、つまり中心的な働きを担うとされます。
- 「イ」「ウ」: 「五(イ)」や「生(ウ)」に通じ、生命力や現実的な働きを象徴します。これらは中心を助ける「介添えの御用」とされます。 これは、新しい世界を創造する働きには、それぞれの魂の特性に応じた役割分担があることを示唆しています。すべての人が同じ役割を担うのではなく、それぞれの個性や使命に応じて、中心となったり、補佐したりすることで、全体の調和が生まれるという思想が根底にあります。具体的な解釈は難しい部分ですが、音の響きが持つ霊的な力(言霊)が、神の計画において重要な要素であることを示しています。
第二十五帖 (二五)
【原文】
一日に十万、人死にだしたら神の世がいよいよ近づいたのざから、よく世界のことを見て皆に知らして呉れよ。この神は世界中のみか天地のことを委(まか)されてゐる神の一柱ざから、小さいこと言ふのではないぞ、小さいことも何でもせなならんが、小さい事と臣民思うてゐると間違ひが起るから、臣民はそれぞれ小さい事もせなならんお役もあるが、よく気をつけて呉れよ。北から来るぞ。神は気もない時から知らして置くから、よくこの神示、心にしめて居れよ。一日一握りの米に泣く時あるぞ、着る物も泣くことあるぞ、いくら買溜めしても神のゆるさんもの一つも身には附かんぞ、着ても着ても、食うても食うても何もならん餓鬼の世ざ。早う神心にかへりて呉れよ。この岩戸開くのは難儀の分らん人には越せんぞ、踏みつけられ踏みつけられている臣民のちからはお手柄さして、とことはに名の残る様になるぞ。元の世に一度戻さなならんから、何もかも元の世に一度は戻すのざから、その積りで居れよ。欲張っていろいろ買溜めしてゐる人、気の毒が出来るぞ、神よく気をつけて置くぞ。この道に縁ある人には、神からそれぞれの神を守りにつけるから、天地の元の・(てん)の大神、くにの大神と共に、よく祀りて呉れよ。六月の三十日、ひつくのか三。
【現代語訳】
一日に十万人もの人が死ぬような事態になったら、神の世がいよいよ近づいた証拠だから、世界の情勢をよく見て、皆に知らせてあげなさい。この神は、世界中はもちろん、天地すべてのことを任されている神の一柱なのだから、小さなことを言っているのではないぞ。もちろん、小さいと思うような日常の務めも何でもしなければならないが、これを小さいことだと侮っていると間違いが起きる。民にはそれぞれ、地道な小さい役目もあるのだから、よく気をつけてくれ。「北から来るぞ」。神はまだ誰も気づいていない時から知らせておくから、この神示をよく心に刻んでおきなさい。一日に一握りの米にもありつけず、泣く時が来るぞ。着る物がなくて泣くこともあるぞ。いくら買い溜めをしても、神が許さないものは一つも身につけることはできない。着ても着ても、食べても食べても満たされない、餓鬼のような世の中になるのだ。早く神の心に立ち返ってくれ。この岩戸開きという大試練は、本当の苦労を知らない人には乗り越えられない。今まで踏みつけられ、虐げられてきた民の力こそが、手柄を立てさせ、永遠にその名が残るようにしてやるぞ。一度、原始の世(元の世)に戻さなければならないから、何もかも一度はそこまでリセットするのだ。そのつもりでいなさい。欲張っていろいろ買い溜めしている人は、気の毒な結果になるぞ。神はよく見ているから、気をつけておくぞ。この道に縁のある人には、神がそれぞれの守護神をつけるから、天地の根源の天の大神、国の大神と共に、よくお祀りしなさい。
【AIによる解釈】
この帖は、来るべき大災厄の具体的な様相を預言しています。「一日に十万、人死にだしたら」という数字は、戦争や災害、パンデミックなどによる未曾有の規模の死を、「一日一握りの米に泣く」は極限的な食糧危機を示唆しています。この混乱の中で、物質的な備え(「買溜め」)は無力であり、神に許されたもの以外は自分のものにならないと断言します。これは、物質主義的な価値観の完全な崩壊を意味します。 そして、この大試練を乗り越える力を持つのは、エリートではなく「踏みつけられ踏みつけられている臣民」であると明言しています。これは、既存の社会で虐げられてきた人々の持つ、純粋さや忍耐力が高く評価される価値観の逆転を再び示しています。 「北から来るぞ」という警告は、地政学的な脅威(ソ連の参戦など)とも、あるいは自然災害とも解釈できる、多義的な預言です。 最後に、「元の世に一度戻す」という言葉は、文明が一度リセットされ、よりシンプルで根源的な状態から再出発することを示唆しています。この大混乱期を乗り越える者には、神からの守護が約束されると結んでいます。
第二十六帖 (二六)
【原文】
「あ」の身魂とは天地のまことの一つの掛替ない身魂ぞ、「や」とはその左の身魂、「わ」とは右の身魂ぞ、「や」には替へ身魂あるぞ、「わ」には替へ身魂あるぞ、「あ」も「や」も「わ」ももも一つのものぞ。みたま引いた神かかる臣民を集めるから急いで呉れるなよ、今に分かるから、それまで見ていて呉れよ。「い」と「う」はその介添の身魂、その魂と組みて「え」と「を」、「ゑ」と「お」が生まれるぞ、いづれは分ることざから、それまで待ちて呉れよ。言ってやりたいなれど、今言っては仕組成就せんから、邪魔はいるから、身魂掃除すれば分かるから、早う身魂洗濯して呉れよ。神祀るとはお祭りばかりでないぞ、神にまつらふことぞ、神にまつらふとは神にまつはりつくことぞ、神に従ふことぞ、神にまつはりつくとは、子が親にまつはることぞ、神に従ふことぞ、神にまつらふには洗濯せなならんぞ、洗濯すれば神かかるぞ、神かかれば何もかも見通しぞ、それで洗濯洗濯と、臣民 耳にたこ出来るほど申してゐるのざ。七月の一日、ひつくのかみの道ひらけあるぞ。
【現代語訳】
「ア」の言霊を持つ魂とは、天地の中心となる、真に一つのかけがえのない魂である。「ヤ」とはその左に仕える魂、「ワ」とは右に仕える魂だ。「ヤ」には代わりの魂がいる、「ワ」にも代わりの魂がいる。しかし、「ア」も「ヤ」も「ワ」も、元は一つのものである。霊的に選ばれ、神がかった民を集めるから、焦ってはいけない。やがて分かるから、それまで静かに見ていなさい。「イ」と「ウ」は、その補佐をする魂だ。その魂と組んで、「エ」と「オ」、「ヱ」と「ヲ」の働きが生まれてくる。いずれ分かることだから、それまで待っていてくれ。教えてやりたいが、今言うと計画が成就しなくなる。邪魔が入るからだ。魂を掃除すれば自然と分かるようになるから、早く魂を洗濯してくれ。神を祀るとは、祭典をすることだけではない。神にまつろうことだ。神にまつろうとは、神にまつわりつくこと、神に従うことだ。神にまつわりつくとは、子が親に甘え、信頼しきるように、神に従うことだ。神にまつろうには、魂の洗濯をしなければならない。洗濯すれば神が降りてくる。神が降りれば、何もかもお見通しになる。だからこそ、民の耳にタコができるほど「洗濯、洗濯」と申しているのだ。七月の一日、ひつくの神の道が開かれるぞ。
【AIによる解釈】
この帖は、再び言霊による役割分担と、神の計画の秘匿性について述べています。第二十四帖をさらに発展させ、「ア」を絶対的な中心、「ヤ」「ワ」を左右の補佐と位置づけています。「ヤ」「ワ」に「替へ身魂」がいるというのは、その役目は固定された個人ではなく、条件を満たした別の魂が担うことも可能であるという、柔軟なシステムを示唆しています。 「イ」「ウ」が補佐役となり、そこから「エ」「オ」「ヱ」「ヲ」という働きが生まれるという記述は、五十音図の構造を霊的な世界の生成発展プロセスになぞらえているようです。 計画の詳細を「今言っては仕組成就せん」と秘匿する理由は、「邪魔はいるから」だと説明されます。これは、悪なる存在が神の計画を妨害しようとしていることを示唆しており、計画の成就には慎重な手順が必要であることを物語っています。 そして、その秘密を理解する唯一の方法が「身魂洗濯」であると結論づけます。「神にまつはりつく」という、子供が親を慕うような絶対的な信頼と帰依の心を持つためには、まず自らを清める必要があると、繰り返し強調しています。
第二十七帖 (二七)
【原文】
何もかも世の元から仕組みてあるから神の申すところへ行けよ。元の仕組は富士(二二)ぞ、次の仕組はウシトラ三十里四里、次の仕組の山に行きて開いて呉れよ、今は分るまいが、やがて結構なことになるのざから、行きて神祀りて開いて呉れよ、細かく知らしてやりたいなれど、それでは臣民の手柄なくなるから、臣民は子ざから、子に手柄さして親から御礼申すぞ。行けば何もかも善くなる様に、昔からの仕組してあるから、何事も物差しで測った様に行くぞ。天地がうなるぞ、上下引繰り返るぞ。悪の仕組にみなの臣民だまされてゐるが、もう直ぐ目さめるぞ、目さめたらたづねてござれ、この神のもとへ来てきけば、何でも分かる様に神示で知らしておくぞ。秋立ちたら淋しくなるぞ、淋しくなりたらたづねてござれ、我(が)を張ってゐると、いつまでも分らずに苦しむばかりぞ。この神示も身魂により何んなにでも、とれるやうに書いておくから、取り違ひせんやうにして呉れ、三柱と七柱揃うたら山に行けよ。七月一日、ひつくのか三。
【現代語訳】
何もかも太古の昔から計画されていることだから、神が申す場所へ行きなさい。最初の計画の要は富士(二二=調和)であった。次の計画は、艮(うしとら)の方角にある、三十里か四十里離れた場所だ。その次の計画の地となる山へ行って、道を開いてくれ。今は分からないだろうが、やがて素晴らしいことになるのだから、行って神を祀り、道を開いてくれ。細かく教えたいが、それでは民の手柄がなくなってしまう。民は神の子だから、子に手柄を立てさせて、親である神からお礼を言いたいのだ。行けば何もかもうまくいくように、昔から計画してあるから、物差しで測ったように正確に物事は進むぞ。やがて天地が唸るほどの大変動が起き、上下がひっくり返るぞ。悪の計画に、民は皆だまされているが、もう直ぐ目が覚める。目が覚めたら訪ねてきなさい。この神の元へ来て聞けば、何でも分かるように、この神示で知らせておくぞ。秋が立てば、世の中は寂しく(厳しく)なるぞ。そうなって心細くなったら訪ねてきなさい。我を張っていると、いつまでも真実が分からずに苦しむばかりだ。この神示も、読む人の魂の状態によって、どのようにでも解釈できるように書いておくから、取り違えをしないようにしてくれ。三柱の神と七柱の神(に相当する人々)が揃ったら、その山へ行きなさい。
【AIによる解釈】
この帖は、神の計画が段階的に、そして地理的な場所と連動して進むことを示しています。「元の仕組は富士」に始まり、「次の仕組はウシトラ三十里四里」の山へと、聖地が移行していくことを示唆しています。「ウシトラ(艮)」は鬼門の方角であり、日本の霊的な中心線に関わる重要な場所とされます。 「臣民の手柄なくなるから」細かく教えない、という言葉は、神が人間に求めている姿勢をよく表しています。それは、ただ指示通りに動くロボットではなく、自らの意志と判断で行動し、困難を乗り越えて「手柄」を立てることです。神は、人間の主体性と成長を望んでいるのです。 「悪の仕組にみなの臣民だまされてゐる」が「もう直ぐ目さめる」という預言は、大衆の覚醒が近いことを示します。その覚醒のきっかけは「秋立ちたら淋しくなるぞ」という、秋以降に本格化する厳しい試練であると示唆されます。 最後に「三柱と七柱揃うたら山に行けよ」と、行動開始の条件を示しています。これは、特定の数の重要な役目を持つ人々が揃うことが、次の段階へ進むための鍵であることを意味しています。
第二十八帖 (二八)
【原文】
世界中まるめて神の一つの詞(王)で治めるのぞ。それが神のやり方ぞ、百姓は百姓、鍛冶は鍛冶と、今度はとことはに定まるのぞ、身魂の因縁によりて今度はハッキリと定まって動かん神の世とするのぞ、茄子の種には瓜はならんぞ、茄子の蔓に瓜をならすのは悪の仕組、今の世はみなそれでないか。これで世が治まったら神はこの世に無いものぞ。神とアクとの力競べぞ。今度はアクの王も神の力には何うしてもかなはんと心から申す所まで、とことんまで行くのざから、アクも改心すれば助けて、よき方に廻してやるぞ。神の国を千切りにして膾(ナマス)にするアクの仕組は分りて居る、アクの神も元の神の仕組を九分九厘までは知ってゐて、天地ひっくり返る大戦となるのぞ。残る一厘は誰も知らぬ所に仕かけてあるが、この仕組、心で取りて呉れよ、神も大切ざが、この世では臣民も大切ぞ。臣民この世の神ぞ、と言ふて鼻高になると、ポキン折れるぞ。七月一日、ひつ九のか三。
【現代語訳】
世界中を丸ごと、唯一の神の言葉(法則)のもとに治めるのだ。それが神のやり方だ。百姓はその天分を、鍛冶はその天分を全うするというように、今度は永遠に変わらない天職が定まるのだ。それぞれの魂が持つ因縁によって、その役割がはっきりと定まり、揺らぐことのない神の世とするのだ。茄子の種からは瓜は実らない。茄子の蔓に無理やり瓜をならせようとするのが悪のやり方であり、今の世は皆そんなことばかりではないか。こんな偽りの状態で世が治まるなら、神などこの世にいないのと同じだ。これは、神と悪との最終的な力比べなのだ。今度は、悪の王でさえも「神の力には到底敵わない」と心から降参するところまで、徹底的にやるのだから、悪も改心さえすれば助けて、善い働きができるようにしてやるぞ。日本の国をズタズタに切り刻んで滅ぼそうという悪の計画は、すべてお見通しだ。悪の神も、根源の神の計画を九分九厘までは知っている。だからこそ、天地がひっくり返るほどの大戦争となるのだ。しかし、残りの一厘の secret は誰も知らない所に仕掛けてある。この最後の計画の真意を、心で読み取ってくれ。神も大切だが、この地上世界では民もまた大切だ。民はこの世における神なのだ。しかし、そう言われて高慢になると、ポキンと鼻を折られるぞ。
【AIによる解釈】
この帖は、新しい世界の秩序と、神と悪の最終決戦の様相を明らかにしています。新しい世界では、各人が自らの魂の因縁(「身魂の因縁」)に合った天職に就き、それが永遠に定まる、いわば「適材適所」が完全に実現した社会が築かれると説きます。個性を無視し、無理やり型にはめようとする現代社会のあり方(「茄子の蔓に瓜をならす」)を「悪の仕組」として厳しく批判しています。 神と悪の戦いは、悪側も神の計画を「九分九厘」まで知っているため、熾烈を極めるとされます。しかし、勝敗を決するのは、誰も知らない「残る一厘」の神の秘策です。この「一厘の仕組」こそが、神の計画の核心であり、それは理屈ではなく「心で取りて呉れ」と、直感的な理解を求めています。 最後に、「臣民この世の神ぞ」という非常に重要な言葉が示されます。これは、人間には神性が内在しており、地上世界を創造していく共同創造主としての役割があることを意味します。しかし、それは同時に大きな責任を伴うため、「鼻高になると、ポキン折れるぞ」と、驕りや慢心を強く戒めています。
第二十九帖 (二九)
【原文】
この世が元の神の世になると云ふことは、何んなかみにも分って居れど、何うしたら元の世になるかといふこと分らんぞ、かみにも分らんこと人にはなほ分らんのに、自分が何でもする様に思ふてゐるが、サッパリ取り違ひぞ。やって見よれ、あちへ外れ こちへ外れ、いよいよ何うもならんことになるぞ、最後のことは この神でないと分らんぞ。いよいよとなりて教へて呉れと申しても間に合はんぞ。七月一日、ひつくのか三。
【現代語訳】
この世が、やがて根源の神が治める本来の世に戻るということは、どんな神々にも分かっている。しかし、具体的にどうすればその世が実現するのかという方法は分からないのだ。神々にも分からないことが、人間に分かるはずがないのに、人間は自分が何でもできるかのように思い上がっているが、それは全くの見当違いだ。やってみるがいい。あちこちで失敗し、いよいよどうにもならないことになるぞ。最後の仕上げは、この根源の神でなければ分からないのだ。土壇場になってから「教えてください」と泣きついても、もう間に合わないぞ。
【AIによる解釈】
この帖は、人間の知恵や計画の限界を改めて強調しています。新しい世界の到来という大筋は、霊界の多くの存在(「何んなかみにも」)が知っているが、その具体的な実現方法(プロセス)は、最高位の神、すなわち「この神(ひつくのかみ)」のみが知っているとされます。 これは、人間の力で未来をコントロールしようとすることの傲慢さと無力さを指摘するものです。「やって見よれ」という突き放したような言葉は、人間が自らの力で試行錯誤し、その結果として完全に行き詰まる(「いよいよ何うもならんことになるぞ」)という経験をすること自体が、神の計画の一部であることを示唆しています。 人間が自らの無力を悟り、完全に神に委ねる(降参する)段階に至らなければ、本当の救いの手は差し伸べられないのです。「いよいよとなりて教へて呉れと申しても間に合はんぞ」という警告は、手遅れになる前に、早くその傲慢さを捨て、神に心を向けるべきであるという、強い促しです。
第三十帖 (三〇)
【原文】
富士を開いたら まだ開くところあるのざ、鳴戸へ行くことあるのざから このこと役員だけ心得て置いて呉れよ。七月一の日、ひつくのか三。
【現代語訳】
富士(内なる神性)を開いたら、まだ開くべき場所がある。次は鳴門へ行くことになるから、このことは役員(中心的な立場の人)だけが心に留めておいてくれ。
【AIによる解釈】
この帖は、神の計画が特定の聖地を巡って段階的に進展していくことを、さらに具体的に示しています。「富士を開く」ことが第一段階であるとすれば、次なる目的地は「鳴戸(なると)」であると明かされています。 「富士」が火(カ)の象徴、火山、精神性の中心であるのに対し、「鳴門」は渦潮で有名な水の象徴、霊的なエネルギーが出入りするゲートウェイと解釈できます。これは、第十六帖で示された「火水(カミ)の結び」、つまり火の力(精神)と水の力(物質・肉体)の統合というテーマと深く関連しています。富士(火)の段階が完了した後、鳴門(水)の段階へ移行することで、陰陽の統合が完成に近づくことを示唆しています。 この情報が「役員だけ心得て」おくべき機密事項とされているのは、計画の核心に触れる重要な情報であり、時が来るまで公にすべきではないという慎重な配慮からでしょう。
第三十一帖 (三一)
【原文】
今度の御用は結構な御用ぞ、いくら金積んでも、因縁ない臣民にはさせんぞ。今に御用させて呉れと金持って来るが、一一神に聞いて始末せよ。汚れた金 御用にならんから、一厘も受取ることならんぞ。汚れた金 邪魔になるから、まことのもの集めるから、何も心配するなよ。心配 気の毒ぞよ。何も神がするから慾出すなよ、あと暫くぞよ、日々に分かりて来るから、素直な臣民うれしうれしで暮らすから。
【現代語訳】
今度の神の御用は、本当に尊い御用なのだ。いくら大金を積んでも、霊的な因縁のない者にはさせない。やがて、「この御用をさせてください」とお金を持って来る者が現れるが、その都度、神に尋ねて判断しなさい。汚れたお金は御用には使えないから、一厘たりとも受け取ってはならない。汚れたお金はかえって邪魔になる。神が真実のものを集めるから、何も心配することはない。心配するのは神に対して失礼(気の毒)なことだ。何もかも神が計らうのだから、欲を出してはいけない。もうしばらくの辛抱だ。日ごとに物事ははっきりしてくるから、素直な心を持つ民は、やがて「うれしうれし」と喜んで暮らせるようになるのだから。
【AIによる解釈】
この帖は、神の御用における「清貧」の思想と、神への絶対的な信頼を説いています。神の御用は、金銭的な力では動かせず、あくまで「因縁」と魂の清浄さが条件であることを改めて強調します。 「汚れた金」を受け取ってはならない、という厳しい戒めは、この活動が金銭によって穢されたり、方向性を誤ったりすることを防ぐためのものです。不浄な動機から提供されたものは、たとえ善意に見えても、霊的な次元で「邪魔になる」とされています。 「心配 気の毒ぞよ」という言葉は、神の全能の計画を信じきれず、人間的な思い煩いをする心そのものが、神への不信の表れであり、神を悲しませる(気の毒)ことだと教えています。物質的な心配や我欲を捨て、すべてを神に委ねる「素直」な心を持つことこそが、やがて来る「うれしうれし」の世を生きるための鍵であると示しています。
第三十二帖 (三二)
【原文】
世の元からヒツグとミツグとあるぞ、ヒツグはの系統ぞ、ミツグはの系統ぞ。ヒツグはまことの神の臣民ぞ、ミツグは外国の民ぞ。とと結びて一二三(ひふみ)となるのざから、外国人も神の子ざから外国人も助けなならんと申してあらうがな。一二三唱へて岩戸あくぞ。神から見た世界の民と、人の見た世界の人とは、さっぱりアベコベであるから、間違はん様にして呉れよ。ひみつの仕組とは一二三の仕組ざ、早う一二三唱へて呉れよ、一二三唱へると岩戸あくぞ。七月の二の日、ひつくのか三。
【現代語訳】
世の初めから、「ヒツグ(日継ぐ)」と「ミツグ(水継ぐ/貢ぐ)」の系統がある。「ヒツグ」は太陽(日)の系統、つまり日本の正統な霊統である。「ミツグ」は月(水)の系統、すなわち外国の民のことだ。「ヒ(日)」と「ミ(水)」が結ばれて、初めて「ひふみ」という調和が生まれるのだから、外国人も同じく神の子であり、助けなければならないと申してあるだろう。ひふみ祝詞を唱えることで、岩戸は開くのだ。神から見た世界の人々と、人間から見た世界の人々(の価値や役割)とは、全くあべこべであるから、間違えないようにしてくれ。「秘密の仕組み」とは、この「ひふみ」の仕組みのことだ。早く「ひふみ」を唱えなさい。「ひふみ」を唱えると岩戸が開くのだ。
【AIによる解釈】
この帖は、「ヒツグ」と「ミツグ」という対の概念を用いて、日本と外国の関係性、そしてその統合について説いています。
- ヒツグ: 「日を継ぐ者」の意。太陽信仰、霊性(縦のつながり)を象徴する日本の霊統。
- ミツグ: 「水を継ぐ者」または「貢ぐ者」の意。月、物質文明(横のつながり)を象徴する外国の民。 神の計画は、この二つの系統が対立するのではなく、「とと結びて一二三(ひふみ)となる」、つまり統合・調和することによって完成すると説きます。これは、単なる日本の優位を説く国粋主義ではなく、日本の霊的な中心性と外国の物質的な力を統合し、より高次の文明を創造するという、壮大なビジョンを示しています。 「神から見た世界の民と、人の見た世界の人とは、さっぱりアベコベである」という言葉は、人間の持つ差別意識や偏見を戒め、霊的な視点からは全ての民が等しく神の子であり、それぞれの役割があることを教えています。そして、その統合を促す具体的な実践として、根源的な宇宙の理を表す「ひふみ」を唱えることが、岩戸を開く鍵であると示されています。
第三十三帖 (三三)
【原文】
神の用意は済んでゐるのざから、民の用意 早うして呉れよ、用意して早う祀りて呉れよ。富士は晴れたり日本晴れと申すこと、だんだん分りて来るぞ。神の名のついた石があるぞ、その石、役員に分けてそれぞれに守護の神つけるぞ、神の石はお山にあるから、お山開いて呉れよ。ひつぐの民、みつぐの民、早う用意して呉れよ、神急けるぞ。七月二日、ひつくのか三。
【現代語訳】
神の側の準備はすべて整っているのだから、民の側の準備を早くしてくれ。準備をして、早く神を祀ってくれ。「富士は晴れたり日本晴れ」と申したことの意味が、だんだんと分かってくるぞ。神の名が刻まれた石がある。その石を役員たちに分け与え、それぞれに守護の神をつけるぞ。その神の石は、例の山にあるから、その山を開いてくれ。「ひつぐの民(日本人)」も「みつぐの民(外国人)」も、早く心の用意をしてくれ。神は急いでいるのだ。
【AIによる解釈】
この帖は、神の計画が最終段階に入り、あとは人間の側の「用意」を待つばかりである、という切迫した状況を伝えています。準備が整えば、「富士は晴れたり日本晴れ」という理想世界の実現が間近であると示唆しています。 「神の名のついた石」とは、物理的な石であると同時に、神から与えられる役目や権能の象徴とも考えられます。それを「役員」に分け与えるということは、新しい世界を築くための具体的な役割分担が始まることを意味します。その石が「お山(第二十七帖で示された山か)」にあるということは、その聖地を開くことが、計画を発動させるための重要な鍵であることを示しています。 最後に、前帖で示された「ひつぐの民」と「みつぐの民」の両方に対して、準備を促している点が重要です。これは、この計画が日本人だけのものではなく、全世界の民を対象としたものであることを改めて強調しています。
第三十四帖 (三四)
【原文】
何事も天地に二度とないことで、やり損ひしてならん多陀用幣流天地(たたよへるくに)の修理固成(かため)の終りの四あけであるから、これが一番大切の役であるから、しくじられんから、神がくどう申してゐるのざ、神々さま、臣民みなきいて呉れよ。一二三(ひふみ)の御用出来たら三四五(みよいつ)の御用にかからなならんから、早う一二三の御用して呉れよ。何も心配ないから神の仕事をして呉れよ、神の仕事して居れば、どこにゐても、いざといふ時には、神がつまみ上げて助けてやるから、御用第一ぞ。一日(ひとひ)に十万の人死ぬ時来たぞ、世界中のことざから、気を大きく持ちてゐて呉れよ。七月の三日、ひつくのか三。
【現代語訳】
これから起こることは、天地開闢以来、二度とない大事業であり、絶対にやり損なってはならない、混沌としたこの世界(漂える国)を修理固成(しゅうりこせい)する、最後の夜明けなのだ。これが一番大切な役目だから、失敗は許されない。だからこそ神はくどくどと申しているのだ。神々も、民も、皆よく聞いてくれ。「ひふみ(一二三)」の御用が済んだら、次は「みよいつ(三四五)」の御用に取り掛からねばならないから、早く「ひふみ」の御用を済ませてくれ。何も心配はいらないから、神の仕事をしなさい。神の仕事さえしていれば、世界のどこにいようとも、いざという時には神がつまみ上げて助けてやる。だから御用が第一だ。一日に十万人の人が死ぬ時が、いよいよ来たぞ。これは世界中のことだから、心を大きく持って、動揺しないようにしてくれ。
【AIによる解釈】
この帖は、今進行している計画が、古事記に記された「天地の修理固成(国造り)」に匹敵する、あるいはそれを完成させるための、宇宙史上最も重要な事業であることを宣言しています。その重大さゆえに、神は「くどう」ほど念入りに警告と指示を与えているのです。 計画の段階が示されており、「ひふみ(一二三)」の段階が完了すれば、次の「みよいつ(三四五)」の段階へ進むとされています。「ひふみ」が個人の魂磨きや準備段階とすれば、「みよいつ(御代いつ)」は新しい御代(みよ)をいつ(五)創るかという、具体的な世界建設の段階を指しているのかもしれません。 そして、第二十五帖の「一日に十万、人死にだしたら」という警告が、「来たぞ」と、まさにその時が到来したことを告げる、極めて緊迫した内容となっています。しかし、そのような大混乱の中にあっても、「神の仕事」をしていれば絶対に助かるという、強い確約(「神がつまみ上げて助けてやる」)が与えられています。これは、物理的な場所や状況よりも、その人の心のあり方(御用第一)こそが、救済の唯一の条件であることを示しています。
第三十五帖 (三五)
【原文】
死んで生きる人と、生きながら死んだ人と出来るぞ。神のまにまに神の御用して呉れよ、殺さなならん臣民、どこまで逃げても殺さなならんし、生かす臣民、どこにゐても生かさなならんぞ。まだまだ悪魔はえらい仕組してゐるぞ、神の国千切りと申してあるが、喩(たと)へではないぞ、いよいよとなりたら神が神力出して上下引っくり返して神代に致すぞ、とはの神代に致すぞ。細かく説いてやりたいなれど、細かく説かねば分らん様では神国(しんこく)の民とは云はれんぞ。外国人には細かく説かねば分らんが、神の臣民には説かいでも分る身魂授けてあるぞ、それで身魂みがいて呉れと申してあるのぞ。それとも外国人並にして欲しいのか、曇りたと申してもあまりぞ。何も心配いらんから、お山開いて呉れよ、江戸が火となるぞ、神急けるぞ。七月の七日、ひつくのか三。
【現代語訳】
これから、一度死んでから生き返る人と、生きているのに死んだも同然になる人が出てくるぞ。神の御心のままに、神の御用をしてくれ。殺さねばならない民は、世界のどこまで逃げても殺さねばならない。逆に、生かすべき民は、どんな場所にいても必ず生かすのだ。悪魔はまだまだ、ものすごい計画を立てているぞ。「神の国を千切りにする」と申してあるが、これは比喩ではないのだ。いよいよという時になったら、神が神力を発揮して、天地をひっくり返して神の世、永遠の神代にするのだ。細かく説いてやりたいが、細かく説かなければ分からないようでは、神の国の民とは言えない。外国人には細かく説かなければ分からないだろうが、日本の民には、説かなくても直感で分かる魂が授けられているのだ。だからこそ、その魂を磨いてくれと言っているのだ。それとも、外国人並みに扱ってほしいのか。魂が曇ったと言っても、あまりにもひどすぎる。何も心配はいらないから、例の山を開いてくれ。江戸(東京)が火の海になるぞ。神は急いでいるのだ。
【AIによる解釈】
この帖は、生死の概念が変容することを示唆しています。「死んで生きる人」とは、古い自我が一度死に、神の生命に生きる者、つまり霊的に生まれ変わる人を指します。一方、「生きながら死んだ人」とは、肉体は生きていても、魂の向上を忘れ、新しい時代の波動についていけなくなった人を指します。選別の基準は、どこにいるかではなく、神の御心に従っているかどうか、ただそれだけです。 「神の国千切り」が比喩ではないという言葉は、日本が物理的に分割、破壊される危機が現実にあることを強調しています。しかし、その最大の危機の瞬間に神力が介入し、すべてが逆転して「神代」が到来するという、劇的なシナリオが再び示されます。 そして、日本人には本来、理屈を超えて真理を直感できる霊性(「説かいでも分る身魂」)が備わっているはずだとし、その能力を発揮できない現状を「曇りたと申してもあまりぞ」と強く叱咤しています。論理的な説明を求めるのではなく、内なる声を聴くために魂を磨くことを強く求めています。最後に「江戸が火となるぞ」と、東京への最終警告ともいえる言葉で締めくくられ、事態の切迫を伝えています。
第三十六帖 (三六)
【原文】
元の神代に返すといふのは、たとへでないぞ。穴の中に住まなならんこと出来るぞ、生(なま)の物食うて暮らさなならんし、臣民 取り違ひばかりしてゐるぞ、何もかも一旦は天地へお引き上げぞ、われの慾ばかり言ってゐると大変が出来るぞ。七月の九日、ひつくのか三。
【現代語訳】
「元の神代に返す」というのは、比喩ではないのだ。本当に、穴を掘ってその中に住まなければならなくなる時が来るぞ。火を使わず、生の物を食べて暮らさなければならなくなる。民は、全く見当違いなことばかりしている。全てのものは、一旦天と地(神)のもとへお返しするのだ。自分の欲望ばかりを主張していると、大変なことになるぞ。
【AIによる解釈】
この帖は、「元の神代に返す」という言葉が、精神的な意味だけでなく、極めて物理的、原始的な生活様式への回帰を意味することを、衝撃的な具体例を挙げて説明しています。
- 「穴の中に住まなならん」: 住居やインフラがすべて破壊され、原始的な住居形態に戻ることを示唆します。
- 「生の物食うて暮らさなならん」: エネルギー供給が途絶え、火を使うことすらできなくなるほどの、文明の完全な崩壊を示唆します。 これは、現代人が当たり前だと思っている文明の利器が、すべて失われる事態を想定せよ、という警告です。「何もかも一旦は天地へお引き上げぞ」という言葉は、人類が築き上げてきた物質文明が、一度完全にリセットされることを意味します。この究極のサバイバル状況の中で、生き残るために本当に必要なものは何か、そして我欲を主張することがいかに無意味であるかを、人々に悟らせるための荒療治であると解釈できます。
第三十七帖 (三七)
【原文】
人の上の人、みな臭い飯食ふこと出来るから、今から知らして置くから気をつけて呉れよ。お宮も一時は無くなる様になるから、その時は、みがけた人が神のお宮ぞ。早う身魂みがいておけよ、お宮まで外国のアクに壊されるやうになるぞ。早くせねば間に合わんことぞ、ひつくのか三。
【現代語訳】
世の指導者的な立場にいる人々は、皆、牢獄で食べるような臭い飯を食うことになるかもしれない。今のうちから知らせておくから、よくよく気をつけておきなさい。神社仏閣も、一時はすべて無くなるようになる。その時こそ、魂が磨かれた人そのものが、生きた神の宮となるのだ。早く魂を磨いておきなさい。神社までが、外国の悪の力によって破壊されるようになるのだぞ。早くしないと、本当に間に合わなくなるぞ。
【AIによる解釈】
この帖は、指導者層の失脚と、有形の宗教施設の崩壊を預言しています。「人の上の人、みな臭い飯食ふ」とは、戦後の戦争犯罪人裁判や公職追放など、指導者たちがその責任を問われ、地位を失うことを生々しく示唆しています。 さらに衝撃的なのは、「お宮も一時は無くなる」という預言です。これは、物理的な社殿の破壊だけでなく、既存の宗教組織や権威がその力を失うことを意味します。しかし、それは宗教の終わりではありません。 「みがけた人が神のお宮ぞ」という言葉は、ひふみ神示の核心的な教えの一つです。これからは、建物や組織といった外面的なものではなく、一人ひとりの人間の内側に神が宿る「生きた宮」の時代が来ることを宣言しています。真の信仰は、個人の磨かれた魂の中にこそ見出されるのです。この内なる宮殿を築くこと、すなわち「身魂みがき」が、何よりも急務であると訴えかけています。
第三十八帖 (三八)
【原文】
残る者の身も一度は死ぬことあるぞ、死んでからまた生き返るぞ、三分の一の臣民になるぞ、これからがいよいよの時ざぞ。日本の臣民同士が食い合ひするぞ、かなわんと云うて外国へ逃げて行く者も出来るぞ。神にシッカリと縋(すが)りて居らんと何も分らんことになるから、早く神に縋りて居れよ、神ほど結構なものはないぞ。神にも善い神と悪い神とあるぞ、雨の日は雨、風の日は風といふこと分らんか、それが天地の心ぞ、天地の心を早う悟りて下されよ。いやならいやで他に代りの身魂があるから神は頼まんぞ、いやならやめて呉れよ。無理に頼まんぞ。神のすること一つも間違ひないのぞ、よく知らせを読んで下されよ。ひつきのか三。
【現代語訳】
生き残る者も、その身は一度死んだようになることがあるぞ。死んでから、また生き返るのだ。最終的に残るのは、民の三分の一になる。これからが、いよいよ正念場だぞ。日本人同士が食料などを奪い合って争うことになる。耐えられないと言って、外国へ逃げていく者も出てくるだろう。神にしっかりと掴まっていなければ、何が何だか分からないパニック状態になるから、早く神に頼りなさい。神ほど素晴らしいものはないのだ。ただし、神にも善い神と悪い神がいるぞ。雨の日には雨が降り、風の日には風が吹く。それが当たり前の自然の摂理であることが分からないか。そのように、厳しいことも優しいことも、すべてが天地の心なのだ。その天地の心を早く悟ってくれ。もしこの御用がいやなら、いやで構わない。代わりの魂は他にいくらでもいるから、神は無理に頼みはしない。いやならやめてくれ。無理強いはしない。神のすることに一つも間違いはないのだ。この知らせをよく読んでくれ。
【AIによる解釈】
この帖は、最終的な選別の厳しさと、その過程で起こる社会の混乱を描写しています。「残る者の身も一度は死ぬ」とは、第三十五帖の「死んで生きる」と同じく、古い自我の死と霊的な再生を意味します。「三分の一の臣民になるぞ」という具体的な数字は、このプロセスがいかに厳しいものであるかを示しています。 「日本の臣民同士が食い合ひする」という預言は、社会秩序が完全に崩壊し、人々が生存をかけて争う、悲惨な状況を指しています。このような極限状況では、理屈や常識は通用せず、唯一の頼りは「神にシッカリと縋る」ことだけだと説きます。 「神にも善い神と悪い神とあるぞ」という警告は、霊的なものに目覚めたとしても、その導きが正しいものかを見極める審神者(さにわ)の必要性を示唆しています。そして、「雨の日、風の日」の比喩は、神の働きには厳しい側面(天災や試練)と優しい側面(恵みや救い)の両方があり、そのすべてを受け入れることが「天地の心を悟る」ことだと教えています。最後に、この道は強制ではないという突き放したような言葉で、個人の自由意志と覚悟を厳しく問うています。
第三十九帖 (三九)
【原文】
地震かみなり火の雨降らして大洗濯するぞ。よほどシッカリせねば生きて行けんぞ。カミカカリが沢山出来て来て、わけの分らんことになるから、早く此の理(みち)をひらいて呉れよ。神界ではもう戦の見通しついてゐるなれど、今はまだ臣民には申されんのぞ。改心すれば分りて来るぞ、改心第一ぞ、早く改心第一ざ。ひつくのか三。
【現代語訳】
地震、雷、そして火の雨(焼夷弾や火山弾か)を降らせて、世の中の大洗濯をするぞ。よほどしっかりと心を定めておかなければ、生きていくことはできないぞ。これから、神懸かりになる者がたくさん出てきて、世の中は訳の分からない混乱状態になる。だから、早くこの真理の道を開いて、人々の指標を示してくれ。神の世界では、もうこの大戦の結末は見通しがついているのだが、今はまだ民には言うことはできない。改心すれば、その結末も自ずと分かってくる。改心が第一だ。何よりもまず、早く改心することが第一なのだ。
【AIによる解釈】
この帖は、大洗濯の具体的な方法として、激しい天変地異(「地震かみなり火の雨」)が起こることを明確に預言しています。これは、物理的な浄化と同時に、人々の心を揺さぶり、覚醒を促すための神の荒療治です。 「カミカカリが沢山出来て来て、わけの分らんことになる」という預言は、霊的な世界への関心が高まる一方で、低級な霊に憑依されたり、偽りの啓示に惑わされたりする人々が続出し、社会が霊的に混乱する危険性を示唆しています。この混乱の中で、本物と偽物を見分けるための正しい指針、すなわち「此の理(みち)」を確立することが急務であると説いています。 「神界ではもう戦の見通しついてゐる」が、それを「まだ臣民には申されん」という部分は、神の計画の秘匿性を再び示していますが、その理由がこれまでとは少し異なります。ここでは、答えを先に教えるのではなく、人々が自ら「改心」することで真実を悟る、というプロセスそのものが重要であると示唆しています。救済は、与えられるものではなく、自らの改心によって勝ち取るものなのです。
第四十帖 (四〇)
【原文】
北も南も東も西もみな敵ぞ、敵の中にも味方あり、味方の中にも敵あるのぞ。きんの国へみなが攻めて来るぞ。神の力をいよいよ現はして、どこまで強いか、神の力を現わして見せてやるから、攻めて来て見よ、臣民の洗濯第一と言って居ること忘れるなよ。一二のか三。
【現代語訳】
北も南も東も西も、すべてが敵となるぞ。しかし、その敵の中にも味方がおり、逆に味方だと思っている者の中にも敵がいるのだ。この神の国(日本)に、世界中が皆で攻めてくるぞ。その時こそ、神の本当の力をいよいよ現して、どれほど強いものかを見せてやる。さあ、攻めてくるなら来てみよ。ただし、忘れてはならない。これは、民を洗濯(浄化)することが第一の目的なのだということを。
【AIによる解釈】
この帖は、日本が全世界から孤立し、四面楚歌の状態に陥ることを預言しています。「北も南も東も西もみな敵ぞ」という言葉は、連合国との戦争が世界のあらゆる国を巻き込む総力戦となることを示唆しています。 しかし、その対立構造は単純な国家間のものではなく、「敵の中にも味方あり、味方の中にも敵ある」と、より複雑な様相を呈することを示します。これは、国籍や立場を超えた、魂レベルでの共鳴や反発があることを意味しており、第十五帖の「顔は日本人でも心は外国魂」という教えと通じます。 「攻めて来て見よ」という挑戦的な言葉は、一見すると好戦的に見えますが、その本質は神の絶対的な力への自信の表れです。この世界的な規模の国難は、実は神が仕組んだものであり、その目的は日本の民を浄化し、鍛え上げるための「洗濯」であると結論づけています。外的な危機は、内的な変革を促すための、神の壮大な装置なのです。
第四十一帖 (四一)
【原文】
人の知らん行かれん所で何してゐるのぞ。神にはよう分って居るから、いよいよといふ時が来たら助けやうもないから、気をつけてあるのにまだ目さめぬか。闇のあとが夜明けばかりと限らんぞ。闇がつづくかも知れんぞ。何もかも捨てる神民、さひはひぞ、捨てるとつかめるぞ。ひつきのか三。
【現代語訳】
人が知らないような、行くこともできないような場所(人々の心の奥底)で、一体何をしているのか。神にはすべてお見通しだ。いよいよという時が来たら、助けようにも助けられなくなる。だから警告しているのに、まだ目が覚めないのか。闇の後が、必ずしも夜明けだとは限らないぞ。さらに深い闇が続くかもしれないのだ。何もかもを捨て去ることができる民は、幸いである。捨ててこそ、本当に大切なものを掴むことができるのだ。
【AIによる解釈】
この帖は、個人の内面の罪や隠し事に対する、鋭い警告から始まります。「人の知らん行かれん所」とは、他者には見えない個人の心の中を指し、そこでの悪想念や不誠実さを神は見抜いていると説きます。 そして、「闇のあとが夜明けばかりと限らんぞ」という、第二帖の「冬の先が春とは限らんぞ」に並ぶ、衝撃的な警告を発しています。これは、試練を乗り越えれば自動的に救われるという安易な希望を打ち砕くものです。改心がなければ、試練の闇はさらに深く、長く続く可能性があるのです。 この厳しい状況を乗り越える唯一の道として、「何もかも捨てる」ことが示されます。これは、財産や地位だけでなく、我欲、執着、固定観念、プライドといった、自分を縛る内面的なものをすべて手放すことを意味します。この「捨てる」という行為(自己の空無化)によって初めて、神の光や真理といった、本当に価値あるものを「つかめる」のだという、逆説的な真理を教えています。
第四十二帖 (四二)
【原文】
初めの御用はこれで済みたから、早うお山開いて呉れよ。お山開いたら、次の世の仕組書かすぞ、一月の間に書いて呉れた神示(ふで)は「上つ巻」として後の世に残して呉れよ、これから一月の間に書かす神示は次の世の、神の世の仕組の神示ざから、それは「下つ巻」として後の世に残さすぞ、その積りで気をつけて呉れよ。御苦労なれども世界の臣民の為ざから、何事も神の申すこと、すなをに聞いて下されよ。七月の九日、ひつくのか三かく。
【現代語訳】
最初の御用は、これで一旦終わりである。だから、早く例の山を開いてくれ。山を開いたら、次の新しい世の計画を書き記させるぞ。この一ヶ月の間に書かせた神示は「上つ巻」として、後世に残してくれ。これから一ヶ月の間に書かせる神示は、次の世、すなわち神の世の具体的な仕組みに関する神示だから、それは「下つ巻」として後世に残させる。そのつもりで、心してくれ。大変な苦労だが、これは世界中の民のためなのだから、何事も神の申すことを、素直に聞いて実行してくれ。
【AIによる解釈】
この帖は、ひふみ神示第一巻「上つ巻」の締めくくりです。「初めの御用はこれで済みた」と、第一段階の啓示が完了したことを宣言しています。 「上つ巻」の役割は、来るべき大峠(大洗濯)の警告と、それに対する心構え(身魂磨き)を説くことにありました。そして、次なる段階として、聖地である「お山」を開くという、具体的な行動を促しています。 その行動が実行されれば、次の啓示として、「次の世の仕組」、つまり新しい神の世の具体的なビジョンが「下つ巻」として降ろされることが予告されています。これは、神の計画が、人間の側の行動や覚悟に応じて、段階的に開示されていくことを示しています。 最後に、この御用が個人のためではなく、「世界の臣民の為」という大きな目的を持つことを改めて述べ、「すなをに聞いて下されよ」と、素直な心で神意に従うことの重要性を説いて、第一巻を締めくくっています。
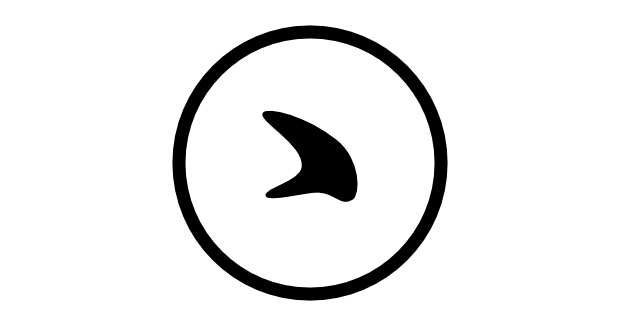





コメント